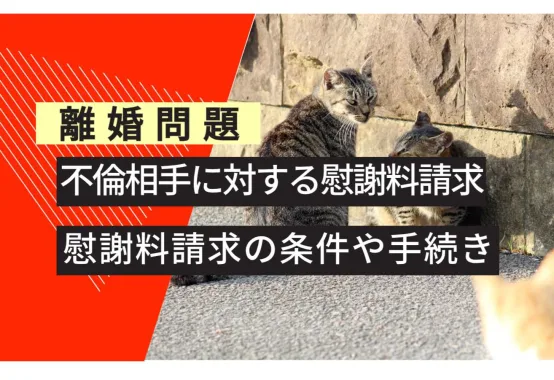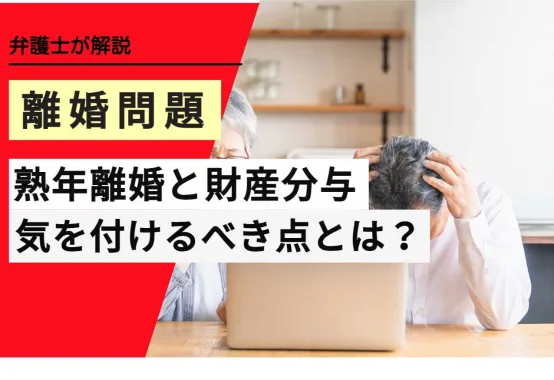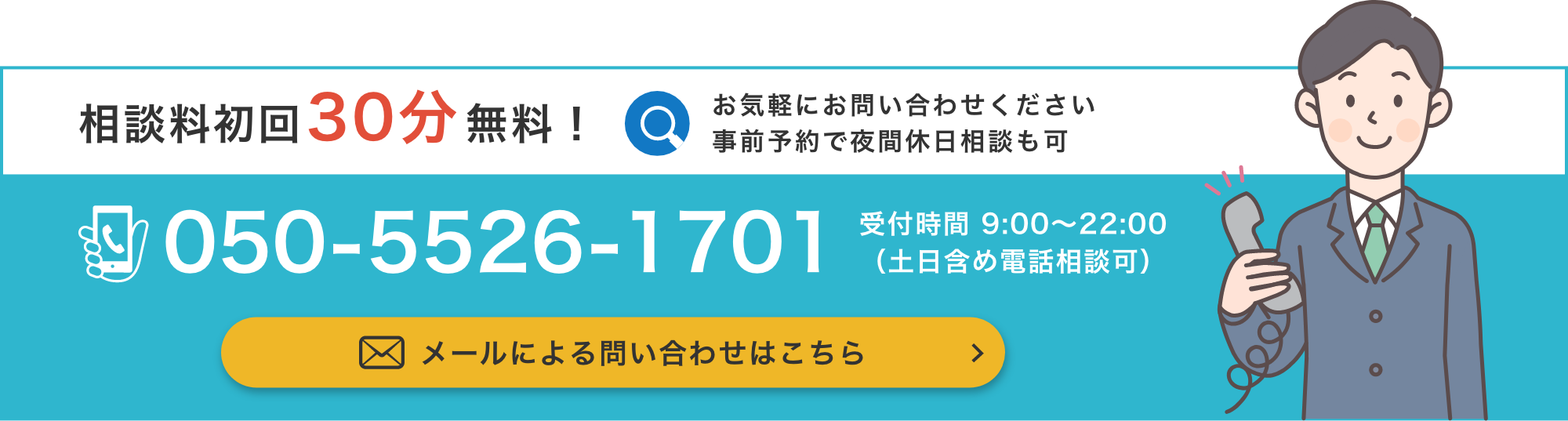離婚時に大きな争点となる問題が財産分与です。
財産分与は、その対象財産が多くなり、時に大きな経済的な負担を伴います。
そして、財産分与の問題は高度に専門的な知識・経験を必要とします。
そのため、弁護士に依頼せずにプロセスを進めることは、必要のない負担が生じ、あるいは、本来得られる財産分与を失うリスクがあります。
本記事を読んで分かること
- 財産分与の対象は?
- 財産分与の対象となる預貯金とは?
- オーバーローンしている場合の財産分与の内容
- 子供名義の預貯金は対象となるのか
初回30分無料で電話相談お受けします
【電話相談受付中】
財産分与の対象となる預貯金
財産分与とは、夫婦が婚姻中経済的に協力して得た財産を清算するものです。
通常、離婚時に財産分与の協議等が行われますが、離婚時に必ず協議して合意しなければならないものではありません。離婚後に財産分与の請求をすることは認められます。
財産分与は、夫婦が協力して獲得した財産を離婚時に清算するものです。そのため、財産分与の対象となる財産は、経済的協力により得られた共有財産となります。
別居時点で有している預貯金は、共有財産であると推定され、財産分与の対象となります。
子ども名義の預貯金
子供名義の預貯金でも、その預金の原資が夫婦の財産であれば、共有財産となります。
例えば、子供の将来の教育資金に充てるために、子供名義の口座に積み立てをしている場合には、その原資は夫婦の共有財産ですから、その預金も共有財産となります。
また、児童手当や育児に関する補助金については、たとえ子供名義の預金口座に入金されていても、夫婦の共有財産として扱われることになります。
他方で、預金の原資がお年玉や入学祝いであって、これらの目的が子供に対する贈与である場合には、財産分与の対象から除外されます。
しかし、この場合でも、夫婦の経済事情、贈与の額、贈与の時期、子の年齢などの諸般の事情から、預金の原資が共有財産ではなく、贈与されたお金であることを証明しなければなりません。


「別居時点」の貯金残高が対象となる
預貯金の財産分与では、別居した時点の残高が対象となります。これを財産分与の基準時といいます。
財産分与は、夫婦の経済的な協力により築いた共有財産を清算する制度です。
そのため、夫婦が別居することで、夫婦の共同生活の実態は失いますので、それ以降は経済的な協力関係もなくなります。
よって、別居時点の預貯金などの財産が共有財産として財産分与の対象となり、別居後に得た預貯金は財産分与の対象から外れることになります。
別居直前に引き出している場合
別居直前に引き出していても、引き出した預貯金額も財産分与の対象となることがあります。
確かに、財産分与の対象は別居時点の残高ですから、別居時点で既に無くなっている預貯金は財産分与の対象からは除外されます。
しかし、常に別居前に引き出した預貯金が財産分与の対象から外れてしまうと、容易に財産分与の金額を減らすことができてしまいます。
そこで、別居直前に大きな金額の預貯金が引き出されていたとしても、この預貯金の使い道が合理的に説明できない場合には、引き出した預貯金は別居時点でも存在しているものと判断されます。

預貯金を財産分与する時の「割合」
財産分与の割合は2分の1となるのが原則です。
財産分与は、夫婦が協力して得た共有財産を清算するものですから、たとえ、夫婦の一方の収入が少なかったり、専業主婦であるため無収入であっても、財産分与の割合は半分となります。
預貯金が特有財産である場合
財産分与は別居日の共有財産を対象とします。
なぜなら、別居をすることによって、夫婦の経済的な協力関係が無くなるからです。
しかし、別居日時点の預金の中に、独身時代から持っている預貯金や相続した預貯金が含まれていることがあります。
結婚前から持っている預貯金や相続・贈与により取得した預金は、夫婦の経済的な協力によって築かれたものではありません。
これらの預貯金は、特有財産として財産分与の対象から除外されます。
特有財産がある場合の計算
具体的には、以下のとおりです。
【特有財産がない場合の計算】
①自宅不動産
評価額 3200万円
住宅ローン 3500万円
差額 −300万円
② その他財産
預貯金 500万円
投資信託 100万円
合計 600万円
③ ①-②(通算説)
300万円
【特有財産がある場合の計算】
預貯金500万円のうち400万円が特有財産の場合、②その他財産の合計は200万円となります。
❷その他の財産
預貯金 100万円(500万円−400万円)
投資信託 100万円
合計 200万円
そのため、③の合計は、−100万円となり、財産分与の対象額はゼロとなります。
特有財産と共有財産が混在している場合
特有財産と共有財産が混在している場合、特有財産の主張が認められない場合があります。
結婚前の預貯金や相続等により得た預貯金が、その他の預貯金の入出金がなく厳格に管理されていれば特有財産と認定される可能性は高いです。
しかし、多くの場合、その預金口座内に給与等の入金が多くあり、また、ライフラインの支払い、子供の学費や習い事の月謝の支払いといった諸々の支払いが継続的になされています。
また、婚姻後の入出金によって、結婚時の残高を下回る時期があった場合には、特有財産であった預貯金は夫婦の生活費に充てられたと考えられることもあります。
このような場合、結婚後の入出金によって、別居時点の預金残高のうち、どの部分が特有財産とされる預金であるかを特定できなくなっています。
そのため、結婚後の預金と混在してしまっている場合には、その別居時点の預金全てあるいは大部分が共有財産として財産分与の対象となることがあります。
借金がある場合の預貯金の財産分与
夫婦が共同生活を送る場合、預貯金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや教育ローンなどのマイナスの負担も負うことがあります。
このような債務を負う場合の財産分与について説明します。
債務自体は分与されない
借金等の債務の半分を相手方に負担させることはできません。
住宅ローンや借金といった債務それ自体は財産分与の対象とはなりません。
借入の半分を相手に負担させたいと考えている人がいますが、これは間違いです。
つまり、住宅ローンが1000万円残っていたとしても、その半分の500万円を相手方に対して支払ってもらうことはできません。
財産分与はあくまでも婚姻期間中に協力して得た財産を清算するものですから、借金等の債務を清算することは予定していないからです。
プラスの財産とは相殺できる
住宅ローンが住宅の評価額よりも上回る場合(いわゆるオーバーローンの状況です。)、オーバーローン部分を相手方に負担させることはできませんが、オーバーローン額とその他のプラスの共有財産と相殺(そうさい)することはできます。
ただし、住宅ローンを負担しながら、その住宅に居住し続ける場合には、オーバーローン部分をその他の財産と相殺できない(非通算説)と考える見解もあります。
オーバーローン時の計算方法
具体的には、以下のとおりです。
①自宅不動産
評価額 2000万円
住宅ローン 3500万円
差額 マイナス1500万円
② その他財産
預貯金 1000万円
投資信託 500万円
合計 1500万円
③ ①-②
0円
このように、オーバーローン額とその他財産とを相殺することで、財産分与の対象額はゼロ円となります。
つまり、ゼロ円となる以上、相手方に対して財産分与として金銭を支払う必要がありません。
逆に、相手方に対して財産分与を請求して共有財産の分与を求めることができます。
相殺してもマイナスの場合
住宅ローンのオーバーローン部分とその他の財産とを相殺しても、未だマイナス部分が残る場合でも、ゼロ円と扱われます。
①自宅不動産
評価額 2000万円
住宅ローン 3500万円
差額 マイナス1500万円
② その他財産
預貯金 500万円
投資信託 500万円
合計 1500万円
③ ①-②
−500万円
この場合でも、-500万円の半分を相手方に負担させることは出来ません。
隠している預貯金の調査方法
別居日時点の相手方の預金残高が少ない場合には、その他の預金口座で管理されている可能性があります。配偶者に知られずに貯蓄をしている、いわゆる「へそくり」の通帳を持っていることはよくあります。
配偶者が預金口座の資料を提示しない場合に、隠し口座を見つける方法を解説します。
同居時に隠し財産の証跡を確保しておく
同居している時に、相手方の財産の資料や情報を得ておくことが非常に大事です。
一旦別居をしてしまうと、生活の本拠を異にしてしまうため、相手方の財産資料に触れる機会を失います。相手方の財産資料を得るためには、同居時点から、相手方の財産情報に関心を持ち、隠し財産を含めた財産情報を得ておくことが肝要です。
資料の開示を求める
まずは、相手方に対して、預金口座の資料を任意に開示するように求めます。
単に、憶測から資料の開示を求めても、相手方から任意の資料開示は期待できません。
請求書、明細書、DM、給与明細などの根拠に基づき、預金口座の存在を主張しながら、任意開示を強く求めていきます。
調査嘱託による収集
調査嘱託という特殊な方法により調査することが考えられます。
調査嘱託とは、裁判所が、当事者の申立てにより、金融機関等に対して、必要な調査を依頼する証拠調べの方法です。
要は、金融機関等に対して、裁判所を通じて、相手方の財産に関する情報を開示してもらう手続です。
ただ、探索的な調査嘱託は認められません。
調査嘱託が裁判所に採用されるためには、申立ての具体的な理由・根拠が必要です。
さらに、預貯金の調査嘱託では、銀行名だけでなく、支店名まで特定しなければなりません。
ただし、ゆうちょ銀行に関しては、支店名の特定は求められません。
また、調査嘱託の場合、別居時点の残高に加えて取引履歴の取り寄せもできます。ただし、別居前の3か月から6か月程の期間に限定されることが多いと考えます。
財産分与の流れ
財産分与を求めるための手続にはいくつかあります。
まずは話合いを試みる
まずは、離婚時又は離婚後、(元)夫婦間で財産分与に関する話し合いを行います。
話合いをした結果、合意に至れば合意書を作成しましょう。合意書等の書面がなければ、夫婦間の合意内容を事後的に証明することができません。
調停の申立てをする
話合いによる解決ができない場合には、離婚調停や財産分与の調停の申立てを家庭裁判所に対して行います。
調停手続では、家庭裁判所の調停委員2人が夫婦を仲裁し、話し合いによる解決を目指します。相手方が銀行口座の開示に応じない場合には、調査嘱託の申立てをするなどして、隠し財産の調査を尽くします。
調停手続の結果、夫婦間で合意できる場合には調停が成立します。
審判により判断が示される
調停手続を経ても合意に至らない場合には、調停は不成立となり審判手続に移行します。
審判手続では、裁判官が、当事者双方の主張と証拠に基づき、事実の認定をした上で、争点に関する判断を下します。そのため、調停手続と比べると、当事者間の話し合いの要素は薄いといえます。
審判が出された後、2週間が経過すれば、審判は確定します。この2週間以内に即時抗告をすれば、高等裁判所にて再度審理を求めることができます。
財産分与の問題は弁護士に相談しよう

預金が特有財産であることの証明は簡単なようで、実はかなり技術的で、難しいことが多いです。
そのほか、財産分与には多くの法律上の論点が複雑に絡み合います。
1人で財産分与の問題に立ち向かうと、精神的な負担を受けるだけでなく、本来得られる利益を失うリスクもあります。
初回相談30分を無料で実施しています。
面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
お気軽にご相談ください。
対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。