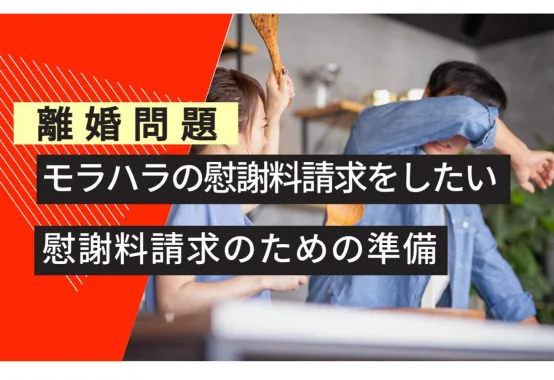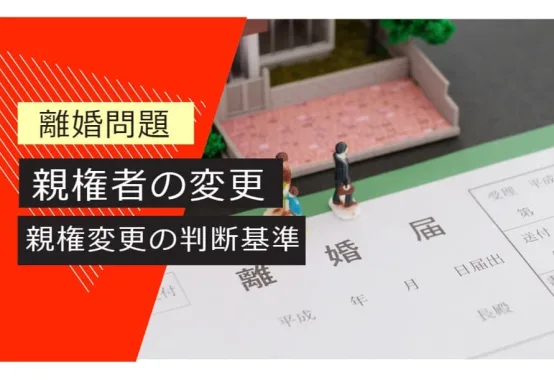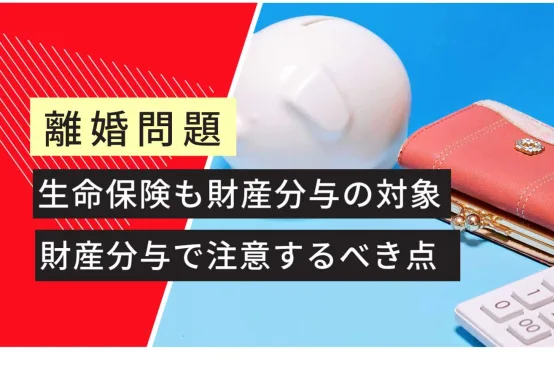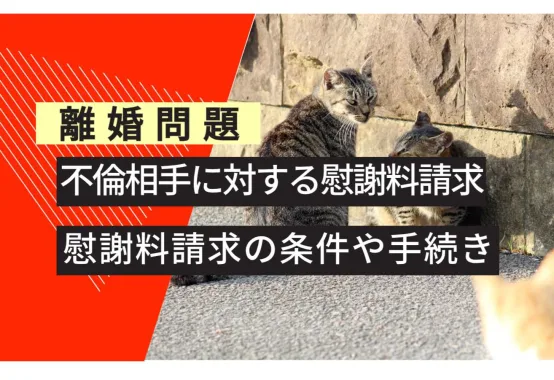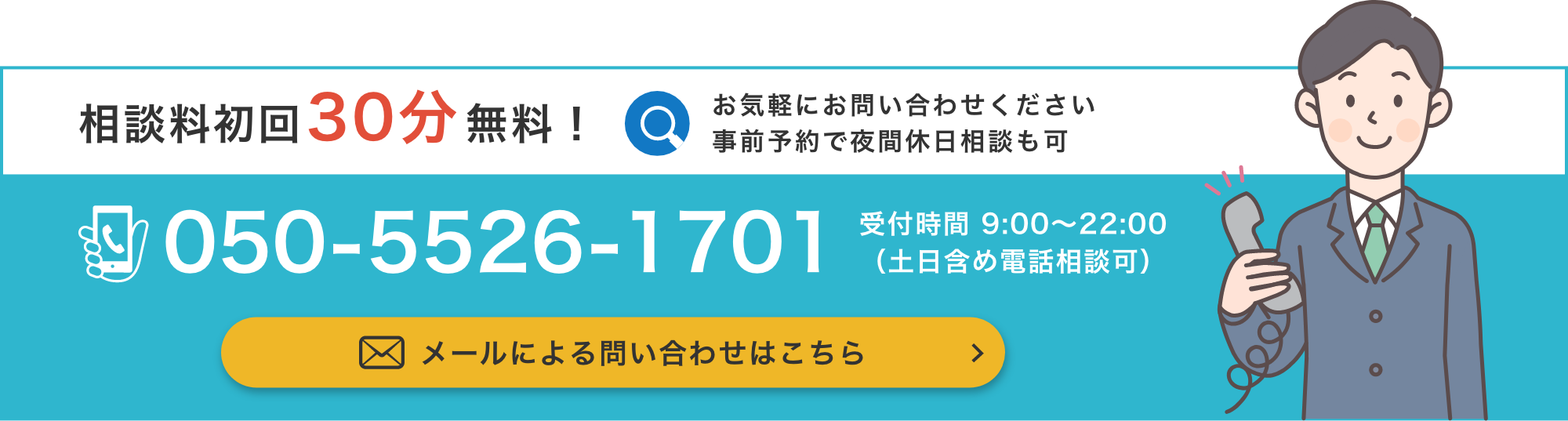離婚時の財産分与の対象に退職金も含まれるのか?という問題ですが、
「含まれます。」
今回のコラムでは、財産分与における退職金の処理を中心に、財産分与の基本的な部分を補足しながら解説していきたいと思います。
初回30分無料で電話相談お受けします
【電話相談受付中】
財産分与とは
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を清算するものです。
そのため、財産分与の対象財産は、婚姻中の夫婦の協力により共同して築いた財産である共有財産となります。
結婚する前から有していた財産、同居中に取得した財産であっても親族から贈与を受けた財産や相続した財産は、夫婦で経済的に協力して築いた財産ではありません。このような財産は特有財産と呼ばれ、財産分与の対象から除外されています。
財産分与はどの時点の財産か?
夫婦が別居を開始させることで夫婦間の経済的な協力関係はなくなります。
そのため、別居後に築いた財産は共有財産とはいえません。
よって、財産分与の対象は別居時点の共有財産となります。
財産分与に関する割合のコラム|財産分与の割合を変えられるのか?弁護士が解説します


退職金が財産分与の対象になる
婚姻期間中に、長年勤務を続けてきた労働者が退職金をもらう場合、その退職金も財産分与の対象財産となります。
退職金は、給与の後払いとしての性格を有しています、つまり、本来給与として受け取るはずのものを退職時にまとめて受け取るものです。
婚姻期間中に受け取る給与やその入金された口座残高は共有財産として財産分与の対象となる以上、退職金も夫婦で協力して築いた財産であると言えます。
財産分与の対象となる退職金の金額
受け取った退職金の全てが共有財産となるわけではありません。
結婚する前から会社に勤めている場合、その結婚前の勤続期間については、夫婦の経済的な協力関係はありません。
また、別居してから離婚前に退職金を受け取っている場合には、その別居から受け取るまでの勤続期間も、夫婦の経済的な協力関係にはありません。
したがって、退職金を共有財産として財産分与の対象とする場合、同居期間に対応する退職金額のみが財産分与の対象金額となります。
同居中に支払われた退職金
夫婦が同居中に、退職をして支給された退職金については、財産分与の対象となります。
その対象財産の計算方法は何種類かあります。
①勤続年数に対する同居期間の割合で計算
1つは、会社の勤続年数の割合で計算する方法です。
計算式
対象額=支給された退職金額×同居期間÷勤続期間
例えば、1990年4月に入社し、2000年4月に結婚し、2020年3月に退職金1500万円を受け取った場合です。この場合、勤続期間は360か月、退職金を受け取るまでの同居期間は240か月ですから、1000万円が財産分与の対象額となります。
1500万円×240÷360=1000万円
②支給率の割合で計算する方法
もう一つは、勤務年数の支給率対する同居期間の支給率の割合で計算する方法です。
計算式
対象金額=支給された退職金額×同居期間の支給率÷勤務期間の支給率
選択される計算方法
①と②のうち、①の計算方法を用いることが一般的です。
ただ、①の方法だと、夫婦間の公平に反するような金額になるような場合には、②の方法を使うこともあるでしょう。
別居時点で退職金の残高が減少している場合
問題になるのが、退職してから別居するまでの間に退職金にあたる預金の全部又は一部が無くなっている場合です。
例えば、退職金が夫のギャンブルや遊興費に充てられたために、その預金残高が無くなっている場合です。たとえ、別居時点で退職金にあたる預金が減少していたとしても、退職金にあたる預金が別居時点でも残っているものと認定される可能性はあります。
他方で、退職金の使途が、教育費や家事費に充てているのであれば、減少した別居時点の預金残高が財産分与の対象となります。なぜなら、夫婦の家事債務を退職金で支払ったことで、その他の共有財産は減らずに済んだといえるからです。つまり、退職金で支払わなくてもそのほかの共有財産で支払えば、結局は共有財産の合計は変わらないといえます。
初回30分無料で電話相談お受けします
【電話相談受付中】
将来支払われる退職金の場合
離婚時点で支払われていない退職金は財産分与の対象となるのでしょうか?
離婚時点で退職金を受け取っていない以上、財産分与の対象から外れるような気もします。
しかし、まだ支給されていないとしても、退職金は給料の後払的性格を持っており、夫婦の経済的協力によって築き上げた財産といえます。
また、支払われていない退職金が財産分与の対象から除外されると、会社を退職するまで離婚を我慢しなければならなくなります。
そこで、離婚時に支払われていない退職金についても財産分与の対象となります。
支払われる蓋然性が高い場合
しかし、あらゆる場合、支払われていない退職金を財産分与の対象とするわけではありません。
会社の経営状況が悪化していたり、退職金の支給された前例がないなど、退職金が払われる可能性が低いような場合にまで、退職金を財産分与してしまうと、夫婦の一方がとても不利になってしまいます。
そこで、退職金の支給を受ける蓋然性(がいぜんせい)が高い場合に財産分与の対象となります。
この支給を受ける蓋然性については、
- 退職金規定の有無やその内容
- 会社の規模
- 会社の経営の安定性
- 勤続年数
- 定年までの期間の長短
- ほかの従業員に対する支給実績
等を踏まえて検討されています。
財産分与の対象額の計算方法
将来支払われる退職金を財産分与の対象とする場合、その対象額の計算方法にはいろいろあります。
まず、①離婚する時に退職金の分与をする方法と②将来の退職金の支払時に分与をする方法があります。
①は離婚時に分与し、②は離婚時ではなく実際に退職する時に分与する点で違いがあります。
①の計算方法
①の計算方法は、離婚する時に、計算された退職金を分与する方法です。
これを前提として、分与するべき退職金の計算方法には2通りあります。
▶離婚時に退職したと仮定した方法
一つ目は、離婚する時に自主退職したものと仮定して、これにより支給される退職金見込額のうち同居期間に対応する金額を対象額とするものです。
例えば、離婚時に退職した場合に支給される退職金見込額が1500万円、入社してから離婚時までの勤続期間が20年、同居期間が15年の場合には、1125万円が対象額となります。
1500万円×15年÷20年=1125万円
なお、実際に離婚時に退職するのではなく、離婚時に退職したと仮定した場合に支払われる退職金の金額を証明する書面を勤務先に発行してもらうことが多いでしょう。
▶将来の退職金を現在に引き直す方法
二つ目は、将来の退職時に支払われる退職金を基準に離婚時の現在価値に引き戻すことで対象額を算出する方法があります。
例えば、6年後に定年退職により退職金の支払いを受けられる場合、6年後の退職金見込額のうち同居期間に対応する金額を計算します。
6年後に受け取る金額から中間利息を控除して離婚時点の価値に引き直しをします。
引き直しの結果、算出される金額が対象額となります。
▶引き直し計算(中間利息の控除)について
民法では法定利息な割合が3%とされています。
実際に銀行預金の利率は3%よりも遥かに少ないですが、法律上は3%で増えていくと仮定されます。
そのため、現在の100万円は一年後に法定利息を加えた103万円、二年後には約106万円、三年後には約109万円、四年後には約112万円といった具合で増えていきます。
逆に四年後の約112万円の現時点の価値は、112万円ではなく、法定利息を差し引いた100万円とされます。
このように、法定利息を考慮すると、数年後の退職時に受け取る金額は、現時点の金額とは同額とは考えません。
法定利息分を差し引いた金額が現在価値となります。
②の計算方法
②の計算方法は、離婚する時に支払うのではなく、将来の退職時に分与する方法です。
この方法においても、2通りの方法があります。
一つ目は、離婚時に退職したと仮定して、離婚時に支払われる退職金を財産分与の対象額とし、これを将来の退職時に分与する方法です。
二つ目は、将来の退職時に払われる退職金のうち同居期間に対応する部分を財産分与の対象額とし、これを実際の退職時に分与するものです。
よく使われる方法
以上の計算方法のうち、実務上よく使われる計算方法は、離婚時に退職したと仮定した場合の退職金見込額を離婚時に分与する方法です。
ただ、退職金の金額はかなり大きな金額となることも多いです。
これを退職前に相手方に分与するだけの資力がないケースもあります。
そのため、退職金については、離婚時ではなく、実際の退職時まで猶予することもあるでしょう。
企業年金は財産分与の対象となる
企業年金に加入している場合、企業年金も財産分与の対象となります。
企業年金は、厚生年金のような公的な年金ではないため、離婚時の年金分割の対象にはなりません。
企業年金も退職金と同様に、既に受け取っている場合と受給前で処理が変わります。
既に受給している場合
企業年金の受取方法として、一括で受け取る場合(一時金方式)と、年金の形態で受け取る場合(年金方式)があります。
一時金方式であれば、既に企業年金は預貯金に形を変えているため、同居期間に対応する企業年金が財産分与の対象となります。
年金方式であれば、将来受給する年金額の合計から中間利息を除いた金額のうち同居期間に対応する部分が財産分与の対象となります。
受給が開始されていない場合
受給が開始されていない場合、年金額の総額から受給開始までの中間利息を控除した上で同居期間に対応する部分が財産分与の対象となります。
退職金の情報を知る方法
財産分与を話し合いで合意する場合には、夫から任意に退職金の金額が分かる資料を提示してもらいます。口頭による説明では、その内容を十分に精査することができません。そのため、勤務先から退職金額証明書の発行を受けるように要請しましょう。
調停や裁判手続きにおいても、夫から退職金の資料の提出を求めます。
しかし、夫が退職金の資料を任意に提示しない場合も想定されます。その場合には、家庭裁判所を通じて、夫の勤務先に対する調査嘱託の申立てを行います。これにより、勤務先が裁判所に対して、夫の退職金に間する情報を開示します。
財産分与の手続
まずは話し合いを
いきなり弁護士に依頼したり、調停の申し立てをするのではなく、まずは当事者間で離婚に関する話し合いを進めましょう。
調停手続や訴訟手続は想像以上に時間を要しますので、早期の解決を目指すのであれば、当事者間による話し合いが良いでしょう。
夫婦間での話し合いが進まない場合には、弁護士を代理人として話し合いを進めることを検討しましょう。
財産分与は離婚の必須条件ではない
ちなみに財産分与は、離婚協議をする時に一緒に話し合われる事項です。
財産分与の内容を調整できないために、離婚それ自体も成立しないことはよくあります。
ただ、離婚をする際に、必ず財産分与の内容を決めなければいけない訳ではありません。
つまり、財産分与を決めずに離婚をしても、離婚してから2年以内であれば、財産分与を求めることはできます。
そのため、長期化を避けるためにも、まずは離婚を成立させてから、財産分与の協議を進めるのも一つの手かもしれません。
調停の申し立てを
夫婦間の協議が難航する場合には、家庭裁判所への離婚調停申立てをすることになります。
離婚調停においては、離婚するのか否かに加えて、財産分与などの離婚条件に関する話し合いも行われます。
調停手続では、家庭裁判所の調停委員二人が当事者双方の言い分を聞き取り、調停委員の仲裁を通じて事案の解決を目指します。
調停手続は、1ヶ月半から2ヶ月に1回の頻度で行われます。
トータルの回数は少なければ3回程ですが、長いケースであれば一年以上調停手続を続けることはあります。
調停手続を経ても解決できない場合には、離婚訴訟を提起することになります。
▶裁判所の財産分与調停の解説はこちら
訴訟を提起する
調停でも離婚条件の話し合いがつかない場合には、離婚訴訟を提起することになります。
離婚訴訟では、調停手続とは異なり、話し合いの要素が少なくなります。
当事者双方が、離婚原因や財産分与に関する主張とこれを裏付ける書証の提出を行います。
専門的な手続となりますので、弁護士に依頼することが多いでしょう。
裁判官による和解の提案
当事者双方の主張と立証が一通り終えると、裁判官による和解案の提案があります。
仮に、訴訟手続を和解せずにそのまま進めると、証人尋問をした上で判決となり、この判決に不服があれば控訴をすることになります。
第一審の手続には一年半から二年ほどの時間を要します。
控訴審も半年から一年の時間を要します。
そうすると、和解をせずに訴訟手続を進めるとかなりの時間を要することがわかります。
そこで、訴訟手続の終盤に近づくと裁判官から、将来の判決を踏まえた和解の提案がなされます。
裁判官による和解の提案を経ても合意ができなければ、夫婦双方の尋問手続をした上で、判決がなされます。
判決内容に不服があれば、判決を受け取った日の翌日から2週間以内に控訴することができます。
仮差押え
夫が退職金を隠したり費消するような場合、妻は十分な財産分与を受けられなくなるリスクがあります。
そのため、そのようなリスクを避けるため、財産分与までにあらかじめ夫の財産を仮差押えをしておくことがあります。
退職前であれば、勤務先に対して、夫に支払う退職金を仮差押えします。これにより、勤務先から夫に対する退職金の支払いが止まります。
退職後であれば、退職金が入金された口座の仮差押えをすることで、口座からの引き出しができなくなります。
財産分与は弁護士に相談しましょう

退職金をはじめとした財産分与の問題は、非常に難しい問題を含んでいます。
当事者間の話し合いの段階から弁護士にアドバイスを受けながら適切に進めていくことが重要です。
弁護士費用を節約したいあまり、ご自身のご判断のみで進めてしまうと、かえって不利な状況になることもあります。
当事務所では初回相談30分を無料で実施しています。
面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
お気軽にご相談ください。
対応地域は、難波、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。