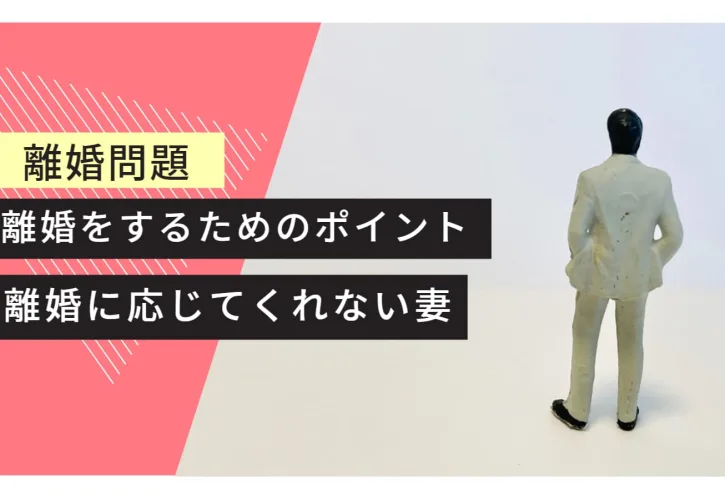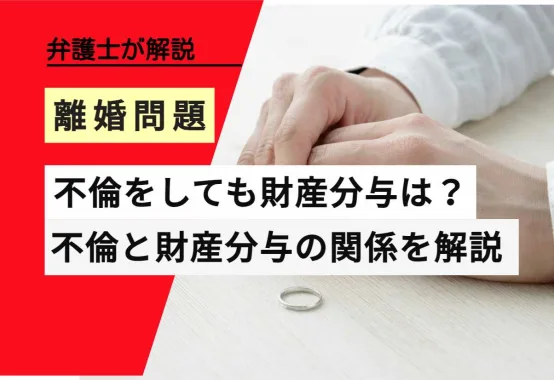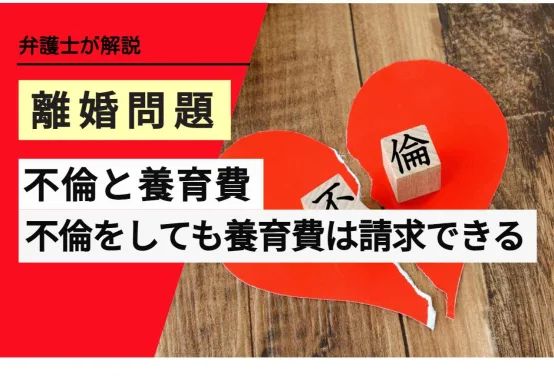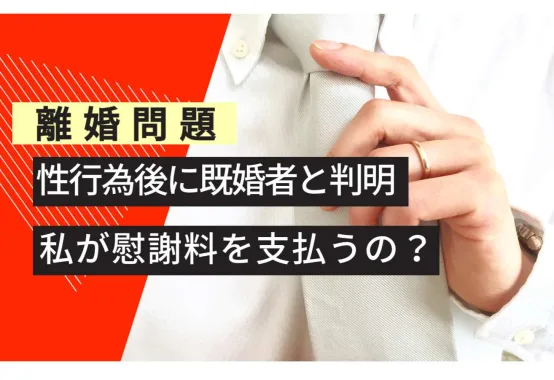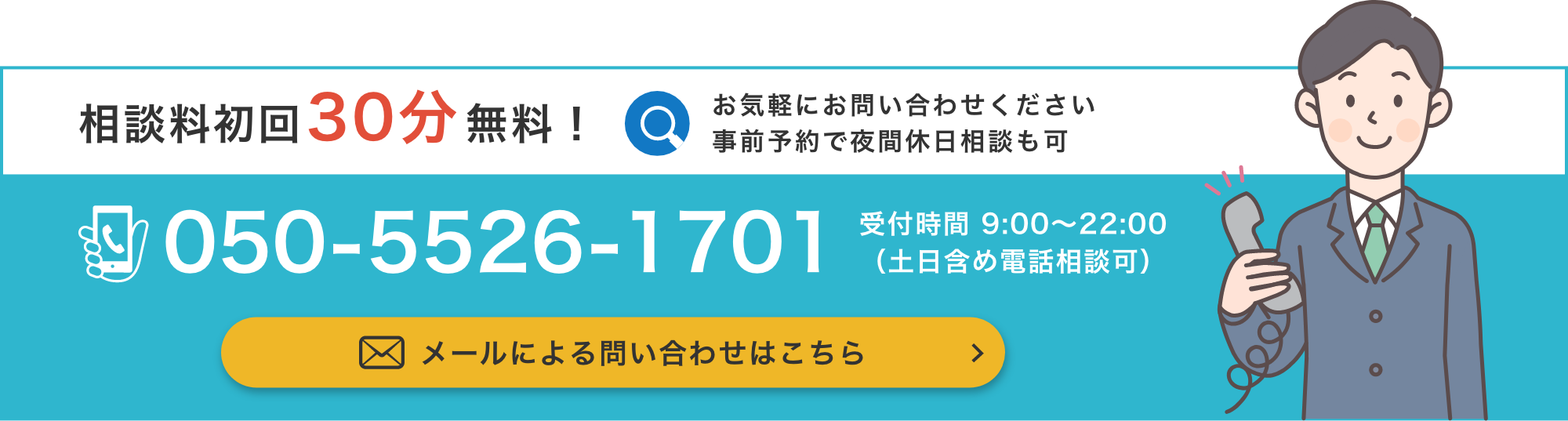別居をしている妻がなかなか離婚に応じないケースはあります。
その理由の一つが、妻側が離婚条件に納得できないというものです。慰謝料や自宅不動産の居住関係、子供の親権、子どもの養育費の額や面会交流などに納得できず、離婚に応じてくれないケースもあります。
婚姻費用を受け取り続けたいと考える人や経済的な不安から離婚を思いとどまってほしいと考える人もいるでしょう。また、夫に対する愛情を持っており、夫婦関係の修復を希望しているケースもあります。
闇雲に離婚届へのサインを求めても進展することはありません。離婚に応じない理由を考察して、応じられない真の理由に応じた進め方が重要になります。
本記事では、離婚したくない妻と離婚する方法・対処法を弁護士が解説していきます。
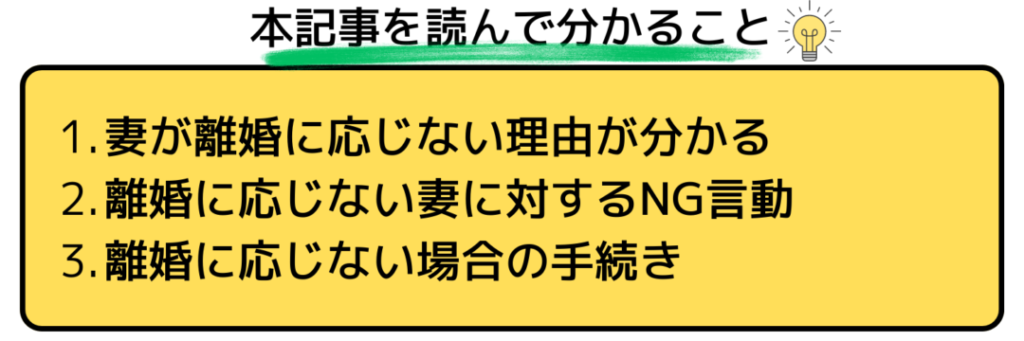
初回30分無料で電話相談お受けします
【電話相談受付中】
離婚に応じれてくれない妻の心理・理由
離婚に応じない妻に離婚を納得してもらうためには、離婚に応じない理由を理解する必要があります。
離婚に応じない理由はさまざまですが、以下のような理由が主として挙げられます。
離婚に応じない理由
- 生活苦になるから
- 有利な離婚条件を引き出したいから
- 財産分与をしたくないから
- 再婚されたくないから
- 子供の養育環境
- 夫に対する愛情
- 世間体を気にしている
生活苦になるから
妻側の経済的自立に時間がかかることや、離婚後の妻の生活が苦しくなることを理由に離婚を拒否するケースがあります。
離婚さえしなければ、妻は、収入の多い夫に対して、別居後、妻とその子供の生活費(いわゆる婚姻費用)を請求し続けることができます。他方で、離婚をすると、妻は夫に対して、この婚姻費用の請求ができなくなり、婚姻費用よりも低い金額養育費だけもらえます。子供がいない場合には、養育費の請求もできません。
そのようなことから経済的な不安を拭い去ることができないと、離婚に応じてくれないことが多いのです。
有利な離婚条件を引き出すため
離婚時の離婚条件を少しでも有利なものとしたいがために、妻が離婚を拒否することはよくあります。
夫婦に、不貞行為やDVといった明確な離婚原因がない場合、夫婦双方が離婚に応じない限り、3~5年は別居しなければなりません。そこで、妻は夫に対して、離婚できる数年間、婚姻費用の請求をし続けることができます。つまり、夫側からすれば、妻の提示する離婚条件で離婚しない限り、向こう3~5年は婚姻費用の負担をしながら別居生活を強いられることになります。
このような夫婦のパワーバランスから、妻は、有利な離婚条件で合意しなければ、離婚せず婚姻費用を弁済することを求めることがあるのです。
財産分与を支払うことになるから
妻が夫に対して財産分与を支払うことを拒否したいために、離婚を拒否することがあります。
特に、住宅ローン付の夫名義の自宅不動産がある場合、妻も住宅ローンの半分を負担しなければならないと誤解し、これを回避したいがために、離婚も拒否するケースもあります。
また、妻が夫よりも多くの資産を有している場合には、妻が夫に対して財産分与をする必要がある可能性があります。
このような経済的な負担を避けるために離婚に応じないことがあります。
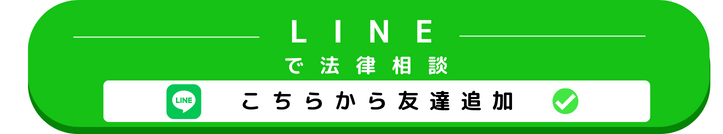
再婚されたくないから
夫が離婚後に再婚することを妨げたいために、離婚に応じないことがあります。
特に、妻が幼い子供を抱えている場合に、夫が再婚した上で、再婚相手が夫の子供を産んだり、連れ子と養子縁組したりすることに強い拒否感を持つことがあります。
また、夫の離婚請求に応じてしまうと、夫の思い通りになることに嫌悪し、離婚に前向きになれないことがあります。特に、妻がモラハラやDVといった被害を受けている場合には、妻側の拒否反応は特に強く出る傾向です。
子供の養育環境が悪くなるから
子供のいる夫婦の場合、特に子供がまだ幼い場合、離婚することによって子供の養育環境が悪化することを恐れて、離婚することに躊躇するパターンはあります。
夫が離婚後に再婚して子供が生まれることで、家族関係が複雑になる、子供に対する愛情が薄くなることも危惧しているパターンもあります。
夫に対する愛情があるから
妻が、夫に対する愛情を持ち続け、夫婦関係の修復を強く求めている場合には、離婚に応じないことがあります。別居しているにもかかわらず、定期的に帰宅したり、旅行に行ったり、中には性行為を行うなど、離婚の意思が妻に対し率直に伝わらず妻が夫婦関係の修復を期待してしまうことがあります。
世間体を気にしている
世間体を気にして離婚に躊躇するパターンもあります。離婚をすれば、家族や友人、職場に報告しなければならないこともあります。周囲の目が気になり離婚に踏み切れないことがあります。離婚することでバツイチになる、シングルマザーになることに不安を覚え、離婚に応じられない妻もいます。


離婚を拒否し続ける妻が提示する離婚条件とは

妻が離婚を拒否する理由の一つに、「有利な離婚条件」を獲得することがあります。
離婚条件には、慰謝料・財産分与・親権・養育費・面会交流が含まれています。
慰謝料
離婚に際して、妻が離婚を求める夫に対して慰謝料を求めることは多いです。
不貞行為であれば、ケースバイケースですが、不貞行為の内容(妊娠や出産の有無)、回数、期間、婚姻期間や未成熟な子供の有無等の事情を勘案して、150万円前後の金額で認定されるケースが実務上多いでしょう。
慰謝料の請求やその金額が原因となって、夫婦双方で互いに譲らない硬直状態が続き、離婚が成立しない状況となることがあります。
財産分与
財産分与とは、夫婦の共有財産を、夫婦の一方から他方に譲渡するものをいいます。
離婚協議において、妻側から、財産分与に関する高額な請求を受けることも多々あります。さらに、妻側が、住宅ローン付きの自宅不動産に居住し続けており、離婚後もその自宅に居住することを希望するなど、離婚後の自宅不動産の利用関係について調整できないことがあります。
このように、財産分与に関する合意ができないために、離婚を成立させることができないがあります。
子供の親権
夫婦に未成年の子がいる場合、離婚時に子供の親権者を決めなければなりません。
親権は、必ず決める必要があります。親であれば誰しも、子供は可愛いことは当たり前です。
そのため、夫婦の両方が子供の親権を強く希望し、双方が譲らないケースがあります。
このように、子供の親権者の決定を巡り離婚協議が紛糾し、離婚が成立しないことがあります。
ただ、母親が子供を連れて、あるいは、父親が母親と子を置いて別居をしているような場合、父親が子の親権を獲得することは非常に難しいのが現状です。
子供の養育費
親は未成熟の子供を扶養する義務を負います。そのため、離婚後、子を養育監護しない親は親権者となる親に対して養育費を負担します。
たとえ成人年齢が18歳に引き上げられたとしても、養育費は20歳まで負担することを要します。
養育費の金額は、父親と母親の収入状況に応じて算出されます。この養育費の金額を巡り、夫婦間で対立を生じさせ、離婚協議を長期化させることがあります。
面会交流について
面会交流とは、離婚後に親権者ではない親が定期的に子供と面会をして、話をしたり遊んだりする親子間の交流をいいます。
夫婦関係が悪化し離婚せざるを得ない夫婦において、子供の親権者となる母親が、子供との面会交流を強く希望する父親に対して、強い拒絶反応を示して、面会交流を一切受け入れないケースがあります。
面会交流の条件が決まらないために、夫婦双方が一歩も譲らず、離婚条件の協議が暗礁に乗り上げることがあります。
妻側の離婚条件の検討方法
離婚に応じてもらうために経済的な不安から離婚条件に納得できないことが原因で妻が離婚に応じない場合は、離婚条件を妻側に譲歩していくことで離婚に応じてもらえる場合もあるでしょう。
しかし、譲歩をするにしても限度があります。およそ法的に認められない法外な慰謝料の支払いを安易に認めるべきではありません。
そこで、譲歩できたとしても、今すぐに離婚した場合の経済的負担と今すぐに離婚しなかった場合の経済的負担を比較して、その差がどの程度であるかを精査するべきです。
離婚に応じない妻と離婚とするための対応6選
離婚してくれない妻を説得して離婚するためには、先ほど解説した離婚を拒否する理由や妻が考える離婚条件を踏まえた上で、納得できる離婚条件を提示することが重要です。
以下では離婚に応じない妻を説得するためのポイントを説明します。
①誠実に冷静に協議する
まずは、冷静になって誠実に協議することです。
別居をする程に夫婦関係が悪化しているため、当事者が直接話し合いをすれば、互い感情的となり、非難合戦を始めてしまうかもしれません。
このような事態は、協議離婚を遠ざけるNG行動です。そこで、たとえ妻側から厳しい言動があったとしても、これに対抗するような言動を抑え、冷静になって、誠実に協議する姿勢が大事です。これまでの婚姻期間中に、間違った言動があった場合には、真摯に謝罪することも検討しましょう。
②経済的な不安要素を払拭させる
妻が抱える不安要素を解消させる離婚条件を提示させることが重要です。
特に、専業主婦であった妻が、離婚後の生活状況に不安を抱えることは当然のことです。
離婚後の生活状況を不安視して、離婚を拒否して婚姻費用を請求し続けることもあります。
そこで、夫としては、想定される別居期間に対応する婚姻費用に匹敵する慰謝料や解決金を提示するなどして、妻の不安要素を解消するよう努めます。
③離婚の誤解を解く
妻が離婚の誤解を持っている場合には、その誤解を解くことが重要です。
例えば、財産分与において、住宅ローンや借入の半分を負担しなければならないと誤解していることがあります。しかし、財産分与では借入の負担を求めることができません。
収入や資産がないと、子供の親権を得られないとの誤解も多いです。しかし、親権の判断において、親の収入や資産はそこまで重要視されません。
夫が妻に対して十分な説明を行い、離婚に対して前向きになるように説得を試みます。
④早期に離婚するメリットを提示する
早期に離婚をするメリットを説得的に説明することで、離婚に納得してもらえる可能性があります。
感情的になって離婚に応じない妻に対して、離婚をした方が諸々の面で有利となることを説明します。
たとえば、子供がいる夫婦の場合、婚姻費用をもらい続けるよりも、離婚をして、児童扶養手当やひとり親の扶助をもらった方が経済的に有利になることがあります。
また、長期間別居をした場合に想定される結果よりも有利な離婚条件を提示し、早期に離婚をする決断をするよう説得します。
さらに、別居期間が長期間続くことで、妻にも心理的なストレスが生じかねません。そこで、早期解決はストレスの軽減につながり、離婚に応じる利点になることも説明しましょう。
⑤証拠を用意して提示する
離婚原因となる不倫やDV、モラハラ等の有責行為に関する証拠を提示します。
不貞行為等の有責行為の証拠を計画的に収集しておくことが重要です。その上で、収集できた証拠を妻いに提示します。仮に、協議離婚に応じなかったとしても、離婚裁判に至れば離婚判決が出される見込みを伝え、早期の協議離婚に応じるように説得します。
⑥別居を提案する
妻に対する説得が奏功せず、協議離婚に応じなければ、別居することを提案します。
離婚に向けて別居期間を重ねることで、夫婦関係は修復できない程に破綻します。婚姻期間にもよりますが、3~4年の別居期間により、婚姻関係を継続し難い重大な事由として離婚が認められます。
離婚を拒否する妻にしてはいけないNG行為

離婚を拒否する妻に対して取るべきではない行為は、次のとおりです。
- 感情的になること
- つきまといをすること
- 妻の条件を頑なに拒否すること
感情的になること
夫が妻に対して、冷静にならず、感情に任せて発言をすれば、離婚を拒否する妻の態度はより一層硬化することが通常です。
当事者同士での話し合いでは、どうしても感情的になり冷静さを保てない場合には、弁護士に依頼することを積極的に検討しましょう。
つきまといをすること
妻が離婚を拒否する態度を変えない場合、痺れを切らした夫が、妻やその親族の自宅や勤務先に乗り込んでしまうことがあります。
妻や親族が望んでいないにもかかわらず、夫が妻の自宅等に無理に乗り込むことは明らかに離婚協議を逆行させます。場合によっては、夫のつきまといを理由に裁判所から接近禁止命令等の「保護命令」、警察からの「警告」や公安委員会に対する「禁止命令」を受けることもあります。
妻の条件を頑なに拒否すること
妻側から提示された離婚条件を頑なに拒否し、歩み寄る姿勢を見せないことです。
妻側に離婚原因がなければ、直ちに離婚することができません。直ちに離婚できないということは、長期間にわたり婚姻費用を負担しなければなりません。
このような状況を踏まえて、妻の離婚条件があまりにも法外な内容でない限り、妻が提示する離婚条件に真摯に向き合い、対案を作成するなどして慎重に話し合いを進めます。
協議離婚できる場合の注意点
離婚に応じていない妻が協議離婚に応じるに至った場合、次の点を注意しましょう。
離婚を強制できない
合意書や公正証書等で離婚に同意したとしても、翻意して離婚に応じなくなることもあります。その場合であっても、法律上離婚を強制執行することは出来ません。この場合には、離婚調停や離婚裁判を進めるしかありません。
離婚を先決させる
配偶者が離婚に応じる場合には、その他の問題は一旦棚上げにして離婚届の提出を先決させることも考えます。離婚に際して、財産分与、離婚慰謝料、養育費、面会交流などの問題が発生します。これら全てを離婚前に合意させようとすると、かなりの労力と時間を要してしまう可能性があります。そのため、これら離婚時の問題を一旦保留にした上で、離婚届の提出を先決させ、離婚を成立させるのも選択肢の一つとなります。
別居後も離婚話が進まない場合、離婚調停の申立てを行う
妻が離婚に一切応じない場合には、しばらく別居生活を送るか、離婚調停等の手続きを進めていくかです。以下では離婚調停等の手続きについて説明していきます。
離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員会が間に入って夫婦間のトラブルの解決を目指して話し合う手続きです。
関連記事|離婚調停とは?離婚調停の流れや時間、調停成立後の流れを弁護士が解説
調停手続き
離婚調停では、夫婦別室で、双方入れ替わりながら調停委員2名に対して、話をすることになるため、妻と顔を合わせることなく話し合いができます。
離婚調停は、1ヶ月半から2ヶ月に一回の頻度で行います。事案によって区々ですが、3回から5回程、調停期日を行います。
離婚調停を通じて双方が条件に合意できれば調停成立となり、調停離婚となります。双方で合意できなければ調停不成立となり、調停手続きは終結します。
離婚調停で成立した合意内容のうち、慰謝料、財産分与、養育費に関する支払条項には法的拘束力がありますから、この内容に従わない場合には、強制執行により実現させることができます。
関連記事|離婚調停とは?離婚調停の流れや時間、調停成立後の流れを弁護士が解説
離婚調停で気を付けるべき注意点
離婚調停も裁判所を通じた話し合いの場です。そのため、離婚条件を全く譲歩しなかったり、相手方やその代理人を誹謗中傷したり、相手方に対する嫌がらせは控えるべきです。
また、調停手続きを有利に進めるためにも、調停委員に対して誠実に対応し、感情的な対応は控えるべきです。裁判所から指示された事項や期限を守ることも重要です。
関連記事|離婚調停中にやってはいけないこととは?離婚調停の不利な発言や注意点
離婚訴訟(離婚裁判)を提起する
離婚調停が不成立となった場合には、離婚訴訟を起こすことができます。
離婚訴訟は、調停手続を先行させなければなりませんので、調停手続を経ずにいきなり離婚訴訟を提起することはできません(調停前置)。
離婚原因があること
妻が離婚に応じない場合、夫において、離婚原因があることを証明しなければなりません。
離婚原因とは、離婚することを正当化させる離婚理由をいい、民法770条1項に5つの離婚原因が定められています。
離婚原因を客観的な証拠により証明することができれば、妻の意思に関係なく判決により裁判離婚することができます。離婚原因を証明することがなければ、離婚できない、または、高額な離婚条件を突き付けられることになります。
離婚原因(民法770条1項)
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の行方不明
- 強度の精神病
- 婚姻を継続し難い重大な事由
離婚裁判の審理
離婚訴訟における審理は、書面によるやりとりが中心になり、主張する離婚原因を裏付ける証拠も提出しなければなりません。
離婚訴訟の審理において、夫と妻双方の主張立証が尽くされれば、証人尋問を行い、その後、判決手続に移行します。
ただ、全ての事案において、必ず証人尋問や判決手続が行われるわけではありません。ほとんどの事案では、書面による主張立証が尽くされた後、証人尋問の実施前に裁判官を通じた和解協議を行います。
和解協議を経てもなお、離婚条件が調わないのであれば、証人尋問を実施した上で判決がなされることになります。判決文を受け取った日の翌日から2週間以内に控訴しなければ、判決は確定します。
関連記事|離婚裁判の期間と流れ|長期化する原因や早期解決のポイント
離婚に応じない場合には別居期間が必要

妻が夫からの離婚請求に一切応じない場合には、長期間の別居をするしかありません。
離婚訴訟において、離婚を認める離婚判決がなされるためには、離婚原因が存在していることが必要です。
つまり、不貞行為や暴力(DV)などの離婚原因が存在し、これを裏付ける客観的な資料があれば、離婚訴訟において十分に主張立証をすれば離婚判決が出ます。
他方で、明確な離婚原因がない場合には、相手方が離婚に応じない限りは離婚は認められません。
このような場合でも、ある程度の別居期間を置くことで、夫婦関係が修復できない程に破綻していると評価され、これにより離婚判決を得ることができます。
別居期間の長短だけでなく、結婚してから別居するまでの同居期間との対比で、婚姻関係が破綻したと言えるほどの別居期間と評価できるかが問題となります。別居生活が3年から4年ほど続けば離婚できると考えます。
関連記事|別居を何年すれば離婚できる?別居期間と離婚の問題を弁護士が解説
有責配偶者による離婚請求
離婚請求をする夫が有責配偶者である場合には、さらに別居期間が長くなることがあります。
夫側が不貞行為をした場合やDVの加害者であるなど有責配偶者の場合、自ら離婚原因を作っておきながら、その離婚請求を容易く認めてしまうと、妻側があまりにも酷となります。
そこで、有責配偶者による離婚請求については、以下の条件を満たすことが必要です。
有責配偶者の離婚が認められるためには
①別居期間が相当の長期間となり
②夫婦の間に未成熟子が存在せず
③妻が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれるなど、離婚により著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められない
①の別居期間は相当程度長期間必要とされ、10年前後は必要と考えられています。
②について、子供が小学校や中学校に在籍している間は、なかなか離婚は認められにくい傾向です。
このような状況で、有責配偶者である夫が短期間で離婚を成立させるためには、妻側から提示される厳しい離婚条件を受けざるを得ません。
離婚に応じれてくれない場合には弁護士に相談を

夫婦関係が修復できなくなっており、夫婦としての実態がなくなっていたとしても、妻側は、離婚後の生活不安から、容易には離婚に応じないことが多いです。
離婚条件は多岐にわたり、複雑な問題を含んでいることが多いです。離婚協議が難航している場合には、ご相談ください。
当事務所では、多くの離婚相談をお受けしています。初回相談30分を無料で実施しています。
対応地域は大阪府内に限らず、和歌山市、和歌山県、奈良県などの他府県からのご相談もお受けしています。お気軽にご相談ください。