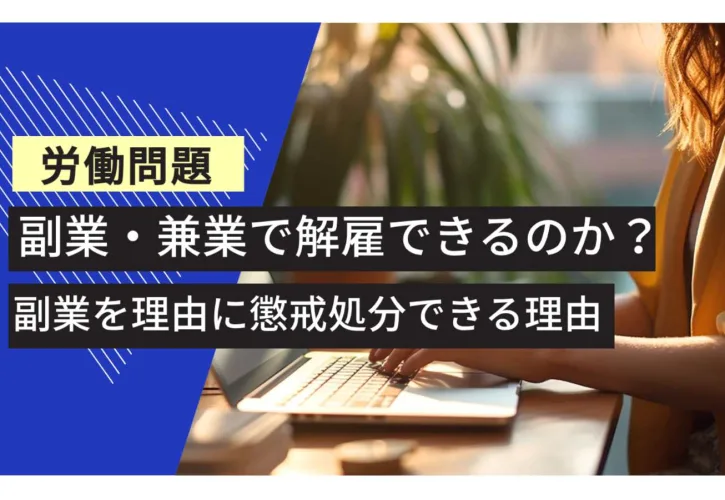-
就業規則で兼業禁止としています。従業員がこの就業規則に反して兼業・副業をしている場合、会社はその従業員を解雇することができるのでしょうか?
-
就業規則で兼業禁止を定めていたとしても、その兼業が本業に重大な影響を及ぼさない限りは、兼業していることをもって解雇することはできません。
副業や兼業を理由とした懲戒処分は難しい
従業員は、使用者と労働契約を結んで、使用者の指揮監督を受けながら仕事をします。その対価として給与や賞与を得ます。しかし、従業員が使用者の指示を受けるのはあくまでも所定労働時間内です。所定労働時間とは、あらかじめ定められた労働する時間です。そのため、所定労働時間以外の時間は、使用者の指揮監督を受けない自由な時間ということができます。
自由な私的時間をどのように使うかは個人の自由です。そこで、本業に悪影響が生じる特段の事情がない限り、副業・兼業は自由というべきです。よって、副業や兼業をしたことを理由に解雇等の懲戒処分を行うことは難しいでしょう。


副業や兼業を理由とした懲戒処分が有効となる場合
副業や兼業を自由に行えるとしても、全くの自由というものではありません。
副業や兼業を行うことで使用者に損失を生じさせる場合には、副業や兼業を制限せざるを得ません。また、副業や兼業を届出制や許可制としているのに、無断で副業兼業をしている場合にも懲戒処分の対象となり得ます。
副業・兼業を理由とする懲戒処分の条件
副業を理由とした懲戒処分が有効となるためには、以下の条件を満たすことを要します。
- 就業規則
- 無断で副業兼業を行ったこと
- 会社に損失を生じさせること
就業規則の定め
懲戒処分を行うためには就業規則に懲戒処分の理由となる懲戒事由や懲戒処分の内容を具体的に定めておくことが必要です。就業規則の定めがないのに、副業や兼業を理由とした懲戒処分をすることはできません。
副業・兼業については、届出制や許可制を採用し、無断で副業・兼業を行うことを懲戒事由として定められていることが必要です。
無断で副業兼業を行ったこと
従業員が、副業兼業の届出や許可の手続きを取らずに、無断で副業兼業を行った場合には、懲戒処分を受ける可能性があります。
しかし、手続違反があったとしても、本業と全く関係のない場合や本業に全く影響を生じさせない場合にまで懲戒処分とするべきではありません。副業や兼業によって本業に具体的な不利益が生じる場合に限り懲戒処分とするべきです。
会社に損失を引き起こす
副業や兼業が会社に損失を招くなどの不利益を生じさせる場合には、懲戒処分を受けます。
副業・兼業が制限される場合
秘密漏洩
競業他社の副業
本業の労働に支障が生じる
本業の信用を害する
秘密漏洩
会社の技術に関する重要な情報や顧客情報等の機密が洩れれば、顧客の喪失や技術の流出を招き会社に損失が生じます。そこで、従業員が、副業や兼業に際して、会社の秘密情報を利用したり、他社に漏洩させることは防がなければなりません。
競合他社の副業
本業の競合会社での副業は、本業の顧客情報や機密情報が漏れてしまうリスクがあります。そのため、競合他社で仕事をしたり、競合する事業の起業をすることは懲戒処分の対象となります。
本業に支障が生じている
副業の影響で、本業に悪影響が出ている場合にも懲戒処分を受ける可能性があります。
副業が深夜帯や休日に行われるため、従業員の心身を酷使してしまい、本業のパフォーマンスが悪くなってしまうことも考えられます。本業のパフォーマンスの低下だけでなく、第三者を巻き込む事故を引き起こすおそれもあります。
そこで、従業員の健康を悪くし、本業に悪い影響を生じさせる場合には、懲戒処分を受けることもあります。
会社の社会的信用や名誉を害している
違法カジノや風俗店の副業を行うことで、会社の社会的な信用や名誉が悪化することがあります。sこで、このような業態における副業を無断で行う場合には、懲戒処分を受ける可能性があります。
TIPS!【厚労省のガイドラインの策定】
厚生労働省において、平成30年1月、副業・兼業についてガイドラインが作成され、令和2年9月にはガイドラインを改定されました。
収入を増加させたい、生活費の不足を補填したい、自分が活躍できる場を広げる、様々な分野の人とつながりができる、時間を有効活用したい等の様々な理由から、副業・兼業を希望する労働者は年々増加しています正社員だけでなく、パート・アルバイト、会社役員、起業による自営業主等さまざまです。他方で、主として中小企業において、人材の定着を図りたい、本業に注力させたい等の理由から、就業規則等で兼業・副業禁止の規定を設けるケースが多いです。
参照|副業・兼業の促進に関するガイドライン
選択する懲戒の程度
無断で兼業副業をしたとしても直ちに解雇処分とするべきではありません。まずは、譴責(けんせき)などの軽微な懲戒処分とするべきでしょう。無断副業などの問題行為を繰り返す場合には、順を追って重い処分を受ける可能性はあります。
ただ、後述するように、副業兼業の内容が本業に与える影響が大きい場合には、懲戒解雇等の重い処分を受ける可能性はあります。
東京地方裁判所令和3年3月4日
週5日1日3時間ほどで深夜に及ばない兼業については、本業に支障が生じる高い可能性がないため、兼業禁止規定にあたらない。
東京地方裁判所平成20年12月5日
大学講師が授業時間外で外語語学校の講師や通訳等として仕事をしていたケースで、本業に支障が生じないことを理由に、無許可兼業に当たらないと判断しました。
副業・兼業で懲戒解雇となる場合
副業や兼業で懲戒解雇できる場合はかなり限られているといえます。
副業兼業は原則として自由です。懲戒処分を行うことができるのは例外的な場面です。懲戒解雇は、雇用契約を一方的に終了させる重大な処分です。そうすると、副業兼業を理由に懲戒解雇という懲戒処分を行うためには、さらに厳格な条件を満たすことが求められます。
副業や兼業を理由に解雇処分とする場合には、解雇できる合理的な理由があり、解雇処分とすることが社会的に相当といえるかを慎重に判断する必要があります。
競業他社の役員に就く(名古屋地判昭47.4.28)
例えば、競合他社の役員に就任した従業員が、本業では部長職として会社の秘密情報にも触れる職位にあった場合には、懲戒解雇も有効となり得ます。
タクシー運転手が非番に副業をする(仙台地裁平成1年2月16日)
十分な休養が取れない副業を行い、乗客の生命を預かる運転業務に携わることは、事故防止というタクシー会社の義務を果たせなくなるとともに、本業の仕事を十分に尽くせないことから、副業を行っていたことは懲戒解雇の事由にあたると判断しました。
競合企業の代表者に就任する東京地裁平成3年4月8日
経理部長である社員が、競合他社の代表者となり、本業に関連する取引をして収益を得ていたことは、重大な義務違反であるとして、懲戒解雇を有効としました。
不当解雇を受けた場合に行うべきこと
使用者から受けた解雇処分に納得できない場合に、従業員が行うべきことを紹介します。
解雇理由を明らかにしてもらう
まず、解雇処分の内容や理由を明らかにしてもらいます。特に解雇理由が明確でなければ、労働者が受けた解雇処分が有効なものかを判断することができません。
そのため、使用者に対して、解雇理由証明書等の発行を依頼します。
関連記事|解雇理由証明書とは?
解雇無効の主張をする
解雇理由が明らかになった後、解雇処分が無効であり、今もなお雇用契約が存続していることを主張します。口頭でも解雇無効の主張はできますが、事後的に説明できるようにするため、内容証明郵便を用いて書面により通知するべきでしょう。
バックペイを請求する
解雇が無効であれば、雇用契約は存在していることになります。そのため、会社に対して、解雇処分を受けた時から解決するまでの賃金を請求することができます。
解雇処分から解決時までの受け取る給与を専門用語で「バックペイ」と呼びます。
解決金を受け取る
不当解雇は無効となり、雇用契約は存続していることになります。そうなると、使用者は、従業員を雇用契約に基づき復職させることが必要となります。
しかし、使用者は、一度解雇をした従業員を再度復職させることに、強い抵抗感を持つことが通常です。そこで、使用者側が従業員に退職してもらうために解決金の支払いを提案する場合があります。
解決金としては、給与半年分から1年分で設定されることが多く、解雇無効の訴訟手続を通じて支払われることが多い印象です。
残業代を請求する
サービス残業をしている場合には、解雇無効の主張と一緒に残業代の請求をするべきです。残業代には時効があります。時間外等割増賃金の消滅時効は、3年とされています。民法改正前、消滅時効は2年とされており、時効期間が伸長されましたが、それでも3年で消えてしまいます。
時効により消滅する前に残業代請求をしておくことが大切です。
兼業・副業のメリット・デメリット
働き方改革の流れから、兼業副業を解禁する動きが活発になっていますが、人的資源の限られている中小企業においては、死活問題といえます。そのため、副業兼業を導入するにあたっては、労働者側・企業側の副業兼業に関するメリット・デメリットをよく知っておく必要があるでしょう。
労働者側のメリット
① 技能の向上
離職せずに別の仕事に就くことで、多様なスキルや経験を得ることができようになり、労働者が主体的にキャリア形成を図ることができます。
②自己実現の機会
本業の所得や経験を活かして、自分がやりたいことに挑戦でき、自己実現の機会を得ることができます。
③ 所得が増加する
就労先が増えることで収入が増えます。収入が増えることで、自己投資や自己実現の機会も増えます。
④ 起業や転職に向けた準備
本業を続けながら、多様な職種に触れることで、将来の起業・転職に向けた準備や試行を行うことができます。
労働者側のデメリット
① 就労時間の長時間化
ダブルワークに伴い、就業時間が長くなる可能性があるため、健康状態を害するリスクがあります。
② 従業員としての義務を怠るリスク
兼業副業に注力するあまり職務専念義務を怠ったり、企業秘密の漏洩による秘密保持義務を怠ったり、競業への就労により競業避止義務を懈怠するおそれがあります。
企業側のメリット
①労働者の技能の向上
労働者が、兼業・副業先の就労により、社内では得られない知識・スキルを獲得することができます。
② 労働者の自主性の向上
労働者が、社外で自主的な副業・兼業を行うことにより、労働者の自律性・自主性が養われます。
③ 人材の定着
労働者の労働の自由を守ることで、本業への定着を促し、優秀な人材の獲得・流出の防止ができ、競争力が向上します。
④事業機会の拡大
兼業・副業を通じて、労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を取り入れることで、事業機会の拡大を促します。
企業側のデメリット
①情報漏えいのリスク
兼業・副業を行う労働者により、会社の機密情報や営業上の秘密等が外部に漏洩するおそれがあります。そのため、会社側としては、競合先への兼業副業を禁止し、企業秘密の漏洩についても、就業規則に明確な規定を設け、副業等をする労働者に対して副業に伴う注意点を指導することが重要です。
②人材流出のリスク
副業は、人材の定着を促し得る一方で、自社に引き留めるだけの魅力がなければ、副業等を契機に、従業員が副業の方へ転職してしまうリスクはあります。
③安全配慮義務
労働契約法第5条では「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」とされています(安全配慮義務)。
全ての使用者がこの労働者に対する安全配慮義務を負っています。
副業等を行う労働者は、長時間労働により健康状態を害するおそれがありますから、本業及び副業の使用者はいずれも労働者の全体としての業務量・時間が重すぎないかを把握し、労働者の健康に支障が生じないよう配慮することが必要です。
副業兼業を理由に懲戒処分を受けた場合には弁護士に相談を
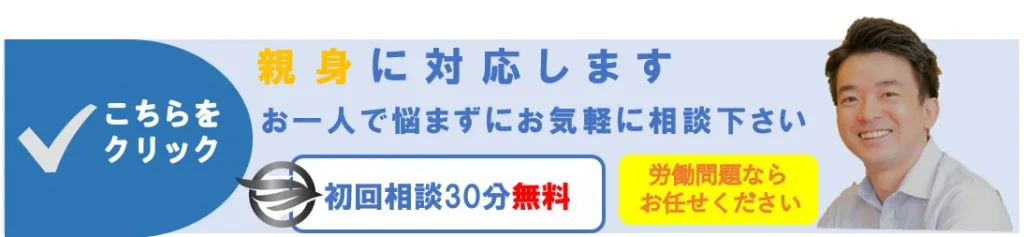
今後も副業・兼業は、コロナ禍の影響も重なり、より一層促進されるものと思われます。上述しましたように、副業・兼業にはメリットもある一方で、抑えておくべき留意点もあります。これらを予め十分に踏まえ、就業規則や雇用契約書に規定しておくなどのルール化をしておくことも重要となります。
当事務所では中小企業への法的アドバイスなどのリーガルサービスに力を入れております。労務管理のお悩みがおありでしたらお気軽にご相談下さい。