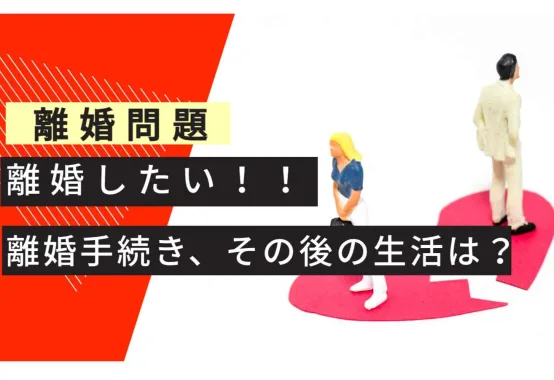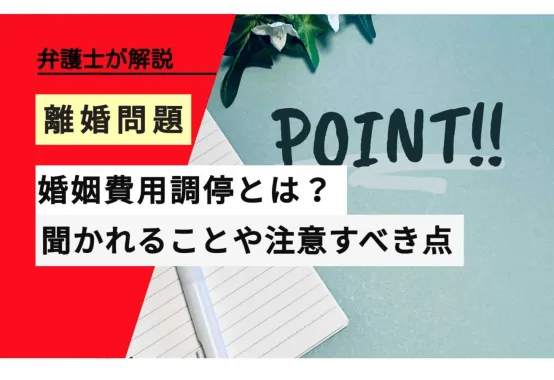夫婦関係が悪化しても、すぐに別居できないケースもよくあります。
例えば、現在の自宅に継続して居住したいと思っているのに、相手方が自宅をなかなか出て行かない場合、選択されるのが「家庭内別居」です。
家庭内別居とは、夫婦関係が破綻に近いほど悪化しても同じ家に住み続け、接触を避けて生活を続けることです。会話を最小限におさえてお互いに顔を合わせないようにしているケースが多数です。
ただし家庭内別居は実際の別居とは異なります。将来離婚するときに「離婚原因」として認められない可能性もあるので注意しましょう。
この記事では家庭内別居が法律上の離婚原因になるのか、日本における家庭内別居の割合やよくある理由、知っておきたい法律知識をお伝えします。夫や妻との関係が悪化して別居に踏み切れない方はぜひ参考にしてみてください。
家庭内別居の状態で離婚はできるのか?
家庭内別居の状態であっても、夫婦が合意するのであれば当然ながら離婚することは出来ます。
他方で、配偶者が離婚を頑なに拒否する場合、離婚を求める配偶者側で「離婚原因」を主張し、証明しなければ離婚請求は認められません。
しかし、「家庭内別居」では離婚原因にはなりにくいのが現実です。そもそも、「家庭内別居」それ自体が、「別居」と認められることが非常に困難です。裁判所では、「家庭内別居」は特段の事情がない限り「別居」」ではなく「同居生活」と捉える傾向が強いです。つまり、家庭内別居状態が続いたとしても、離婚原因としての別居状態として認定されないということです。
ただ、「家庭内別居」とは別に、不貞行為やDVなどの問題行為が存在するのであれば、「離婚原因」は認められます。
以下では、「家庭内別居」とは一体何かを説明した上で、「家庭内別居」に関連する問題を解説していきます。
家庭内別居とは何か?
家庭内別居は、法律上の用語ではなく明確な定義はありません。これをあえて定義すると、家庭内別居とは、夫婦が生活の本拠を同一にしつつ、夫婦としての共同生活の実態を喪失させている状態を言うものと理解しています。
家庭内別居には様々なケースがあり、夫婦間の会話が少ない、性交渉が少ない、寝室を別にする、一緒に外出しないというケースもあれば、衣食住だけでなく家計面も含めて完全に分離している状況まであります。
仮面夫婦との違い
家庭内別居に似た概念として「仮面夫婦」があります。仮面夫婦は、対外的には、良好な夫婦であるかのように振る舞うが、家庭内では夫婦としての実態が乏しいような状況をいいます。家庭内別居と仮面夫婦は重なる点もありますが厳密には異なる用語になります。
家庭内別居の割合と離婚率
家庭内別居は別居と異なり、外観上分かりにくいです。特に、当事者以外の裁判官や調停委員からは、同じ屋根の下で生活している状況で別居している実態があるか否かを確認することは簡単ではありません。
では、このような家庭内別居をしている夫婦の割合はどのくらいになっているのでしょうか?
婚活メディア「e-venz(イベンツ)」を運営するノマドマーケティング株式会社(東京都渋谷区)が、全国の30歳以上の男女100名を対象にとったアンケート結果があります。
●家庭内別居の経験者…44%
●家庭内別居後に離婚になったケース…83%
●家庭内別居後離婚に至るまでの期間…5年以内が22%でもっとも多く、次いで1年以内の17%、3番目は半年以内の15%
母数が小さいので必ずしも正確ではありませんが、30歳以上の夫婦の半数近くが家庭内別居を経験しており、8割以上が離婚に至る可能性があるというデータが出ています。
家庭内別居と復縁
上記アンケート結果によれば、家庭内別居後に離婚に至った割合は83%であり、多くの夫婦が離婚している状況が分かります。つまり、家庭内別居に至れば復縁することは難しいといえます。ただ、家庭内別居にも、大なり小なりがあります。そのため、家庭内別居の中でも深刻な状況に至っていないのであれば、夫婦間の溝を埋める努力を尽くせば、夫婦生活を修復できる可能性はあるでしょう。


家庭内別居のメリットとデメリット

家庭内別居を選ぶ夫婦でよくある理由・メリットは以下のとおりです。
経済的な理由
片方が専業主婦の場合などには、離婚すると生活が苦しくなる可能性が高いでしょう。
「別居したい」と思っても引越しなどの新居の準備に費用がかかりますし、別居後の生活費も二重になってしまいます。
経済的な事情から家庭内別居を選択するパターンがよくあります。
対外的な問題・世間体
実際に別居すると周囲に気づかれて、実家や親戚、勤務先や友人などから事情を尋ねられたり好奇の目で見られたりする可能性があります。
家庭内別居であれば一見普通の夫婦に見えるので、対外的な問題は発生しにくいものです。
外見を気にして家庭内別居を選択される方も少なくありません。
子どもへの影響
夫婦が別居すると、子どもと暮らせるのは一方の親だけとなり、別居親は子どもと自由に会えなくなってしまいます。
特に子どもが小さい場合、影響を懸念してしばらく家庭内別居する例がよくあります。
別居したくてもできない
相手方の不貞行為やDVが理由で別居をしようと決意している事案で、現在の自宅に住み続けたいものの、相手方が自宅から退去しようとしないため、やむなく家庭内別居をしている場合です。
【家庭内別居のデメリット】
①精神的な負担
家庭内別居による一番のデメリットは、精神的な負担を伴う点です。夫婦仲が悪く、夫婦としての生活実態がないにもかかわらず、同居を継続させることには、それ相応の心的ストレスを伴います。中には、精神疾患を招くこともあります。
②子供の成長に悪影響
未成熟の子がいる場合、両親と一緒に生活を送れるメリットがある一方、不仲の両親の下で養育されることで、かえって健全な成長を妨げるリスクもあります。
③離婚協議が進みにくい
同居を継続させることで、ズルズルと夫婦関係が続いてしまい、離婚協議の機会を得にくいデメリットもあります。


家庭内別居は離婚原因になる?

家庭内別居を続けていたとしても、離婚原因にはなりにくいでしょう。
離婚原因が必要なのは訴訟で離婚するケース
協議離婚や調停離婚では、離婚原因は不要です。つまり、離婚原因がなくても、双方が離婚に同意すれば離婚することは可能です。
ここでいう「離婚原因」とは、離婚を正当化させるための離婚理由を指し、民法民法770条で列記された以下のような事情を指します。
・配偶者に不貞な行為があったとき。
・配偶者から悪意で遺棄されたとき。
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
家庭内別居であっても完全な別居であっても明確な離婚原因がなくても、双方で合意ができるのであれば離婚をすることはできます。
一方で、相手方が離婚に応じず離婚裁判にまで発展した場合には「法律上の離婚原因」がなければ離婚できません。
家庭内別居は離婚原因にならない
家庭内別居だけでは離婚原因にならない可能性が高いといえます。
食事を一緒にしない、一緒に寝ない、会話をしない、セックスレスといった事情があったとしても、同居している以上、「夫婦関係が破綻している」と認定されにくいからです。
夫婦関係が悪化しているとしても、同居を継続できている以上、夫婦関係が破綻しているとまではいえないことがほとんどです。
長期にわたって家庭内別居を続けていても、相手方が離婚を受け入れなければ離婚できない可能性が高いでしょう。
そこで、離婚を望む場合には、家庭内別居ではなく別居を開始することも検討するべきでしょう。
TIPS!別居婚とは
別居とは、離婚に向けて生活の本拠を異にする状態をいいます。これと似た用語として別居婚があります。別居婚とは、夫婦が同居をせずに離れて暮らし夫婦生活の形態をいいます。別居婚は離婚に向けた別居とは異なります。
家庭内別居でも離婚原因が認められる場合
家庭内別居でも、以下のような事情があれば離婚原因が認められる可能性があります。
- 相手が不貞行為している
- DVやモラハラの被害を受けている
- 相手が生活費を渡してくれないため、経済的に困窮している
- 婚姻関係を継続し難い重大な事由が存在している
これらの事情が「客観的な資料」により十分に証明できる場合には、たとえ完全に別居せずに家庭内別居に留まっていたとしても離婚することは可能です。
しかし、これらの事情がない場合には、長期にわたり家庭内別居を継続したとしても、夫婦関係を継続し難いとして離婚を求めることは困難です。
ただ、家計が完全に分離されており、食事や洗濯などの共同生活の実態も全くなく、このような状況が長期間にわたり継続している等の事情が客観的に証明できる場合には、例外的に家庭内別居が婚姻を継続し難い事由として離婚原因となる可能性はあるでしょう。
【東京地方裁判所平成15年4月21日】妻が結婚当初から家事を拒否していたため、夫が妻に対して離婚を切り出し、話し合った結果、家庭内別居をし、その後は妻が家を出て別居することとなった事案です。裁判所は、夫婦関係は、妻の家事を拒否する態度という婚姻を継続し難い事由により、家庭内別居を開始させた平成14年1月31日には破綻したものとして、夫からの離婚請求と慰謝料請求を認めました。
長期間の別居は離婚原因になる
長期に渡って別居していると、夫婦関係を修復できない程に破綻したとして、婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとされと認定される場合があります。
だいたい3年~5年程度別居していたら訴訟で離婚が認められるケースが多数です。なお、別居期間については、同居している期間の長短や未成年の子供の有無等の事情を考慮して判断されますから、事案に応じた実質的な判断が必要です。
より確実に相手と離婚したいなら、家庭内別居よりも夫婦の一方が退去する完全な別居をお勧めします。
家庭内別居と財産分与
家庭内別居と実際の別居では、離婚時の財産分与の取り扱いも異なります。
財産分与には「基準時」があります。基準時とは、「いつの財産を基準に計算するか」というタイミングです。
財産分与は「夫婦が共同生活において築いた財産」(共有財産)を対象にするので、別居するとその後の財産の変化は考慮されません。つまり「別居時点の財産」が財産分与の対象財産になります。
一方、家庭内別居の場合には「別居」とはいっても家計が1つです。家庭内別居を開始しても、財産分与の基準時になりません。将来本当に別居するときか、離婚するタイミングを財産分与の基準時として計算します。
証拠を集めやすいメリットも
財産分与を有利に進めるためには相手の財産に関する資料を集めなければなりません。
実際に別居してしまったら、これらの資料集めは難しくなるでしょう。
家庭内別居であれば相手の手持ちの資料にアクセスしやすいので、預金や保険などの財産資料を集めやすくなります。
家庭内別居中の浮気・不倫問題
家庭内別居中に夫や妻が不貞行為したら、慰謝料を請求できることが多いでしょう。
不貞行為で慰謝料が発生するのは、不貞行為によって夫婦関係を破綻させられたためです。
別居してから一定期間が経過すれば夫婦関係が破綻したと考えられることが多いので、別居後に行われた不貞行為が発覚しても慰謝料請求は困難となります。ただ、別居後の不貞行為であっても、別居直後のものであれば、その時期や不貞相手との関係性によっては、別居以前から不貞関係があったと認定される可能性もあります。
一方、家庭内別居の場合、夫婦関係が冷え切っていたとしても、婚姻関係が破綻しているとまでは評価されないため、「不貞行為によって夫婦関係が破綻した」と評価されやすくなります。その場合、配偶者や不貞相手に慰謝料を請求できます。
不貞行為の証拠を集めやすい
同居していると不貞行為の証拠を集めやすいメリットもあります。
相手のスマホやかばんなどの中身を見る機会もありますし、相手の行動パターンも把握しやすいからです。探偵事務所に依頼するときにも「いつどこで尾行すればよいか」などの計画を立てやすくなります。
客観的な資料がなければ不貞行為が行われたことを認定されません。完全別居をしてしまうと、このような資料の収集する機会がかなり乏しくなりますから、同居期間中に十分な資料収集を行うことを推奨します。
家庭内別居中の生活費(婚姻費用)
家庭内別居であっても、夫から生活費が支払われない場合には、生活費の支払いを求めることができます。この生活費のことを法律上婚姻費用と呼びます。
婚姻費用の分担請求
婚姻費用とは、夫婦が家庭生活を営む上で必要となる費用をいいます。婚姻費用は、夫と妻の収入状況と家族構成を踏まえて計算されます。
ただ、婚姻費用は夫婦が別居していることを前提としており、婚姻費用の算定表も、別居していることを前提に作成されています。
家庭内別居でも婚姻費用の請求はできる
完全な別居ではなくても、家庭内別居でも婚姻費用の請求は認められます。
婚姻費用の根拠は、配偶者に対して、自分と同じレベルの生活をさせる義務(生活保持義務)にあります。
この生活保持義務は、別居している夫婦だけでなく、同居している夫婦でも負っています。
そこで、家庭内別居であっても、妻が収入の多い夫よりも低い水準の生活を強いられている場合には婚姻費用の支払いを求めることができます。
婚姻費用の金額を修正する必要
ただ、婚姻費用の計算は、完全な別居を想定しています。つまり、夫婦のそれぞれが別々の住居に住み、それぞれにおいて居住費や医療費などの生活費が発生していることを前提としています。
そのため、家庭内別居における婚姻費用を算定する場合には、完全な別居を想定している婚姻費用の計算式を一部修正する必要があります。
具体的には、算定表や算定式により婚姻費用を算出します。婚姻費用の中には、食費、居住費、水道光熱費といった費用が含まれています。そのため、夫婦が同居していることにより、支払いを免れている生活費があれば、それを婚姻費用の中から控除することで、最終的な婚姻費用額を算出します。
家庭内別居中に離婚を決意したときにすべきこと
家庭内別居中、離婚したいと考えたら以下のように対応しましょう。
資料や証拠を集める
まずは財産に関する預貯金通帳のコピーや不貞行為の証拠など、資料を集めましょう。
いきなり離婚を打診すると、交渉で不利になる可能性があります。離婚を打診すると相手方が防御態勢に入り、これにより資料の収集が困難となることが多いため、離婚を打診する前に、十分な証拠収集を行いましょう。
離婚条件を検討する
次に希望する離婚条件を検討しましょう。
決めておくべき条件は主に以下の6つです。
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
- 親権
- 養育費
- 面会交流
自分の希望する条件を事前にまとめておくと、話し合いをスムーズに進めやすくなります。
相手に離婚を打診する
準備が整ったら相手に離婚を打診しましょう。相手が離婚を受け入れれば条件交渉を行います。相手が離婚を拒否したら、離婚に応じるよう説得しなければなりません。
合意できなければ別居または離婚調停を申し立てる
相手がどうしても離婚に応じない場合や離婚条件で合意できない場合には、協議離婚は難しくなります。
いったん別居して冷却期間を置くか、家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。
家庭内別居の問題は弁護士に相談を

家庭内別居中に離婚する方法は、相手の反応によっても異なります。別居すべき場合も調停を申し立てるべき場合もあり、将来訴訟が予測されるケースも考えられます。
子どもの親権争いが生じるケースも多く、素人判断で対応すると、予想外の不利益を受けてしまうリスクも心配です。
家庭内別居で離婚を考えたら、法律の専門知識をもった弁護士へ相談しましょう。
子どもの問題、お金の問題、離婚後の生活など、あらゆる面から「できるだけ有利になる方法」の提案を受けられて、後悔しない離婚を実現しやすくなります。
当事務所でも離婚に関するご相談を数多くお受けしています。親身になって対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。