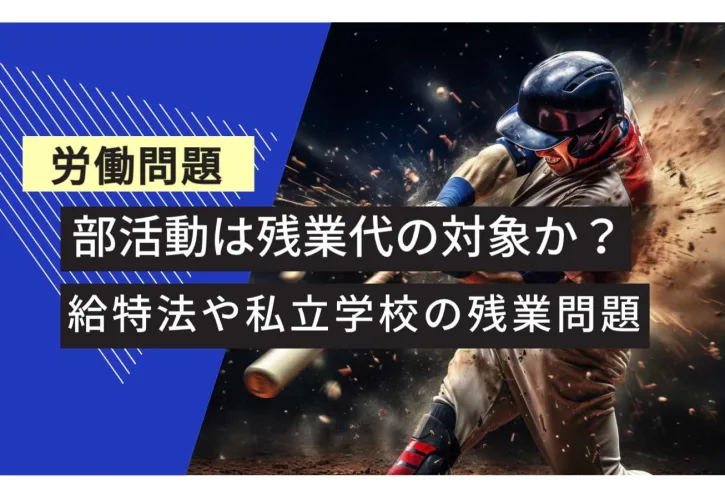学校の先生も、民間の企業の従業員と同じく、労働者です。
他方で、公立学校の教員の場合、地方公務員ですから民間企業の従業員や私立学校の教員とは異なる法令が適用されます。
そのため、公立学校の教師の場合、部活動等に従事したことを理由に残業代等を受け取ることができません。
これに対して、私立学校の教師の場合には、公務員ではないため、民間企業の従業員と同じように部活動を理由とした残業代請求をすることができる可能性があります。
今回のコラムでは、学校の先生が、部活動を理由に残業した場合、その残業代を請求できるのか解説したいと思います。
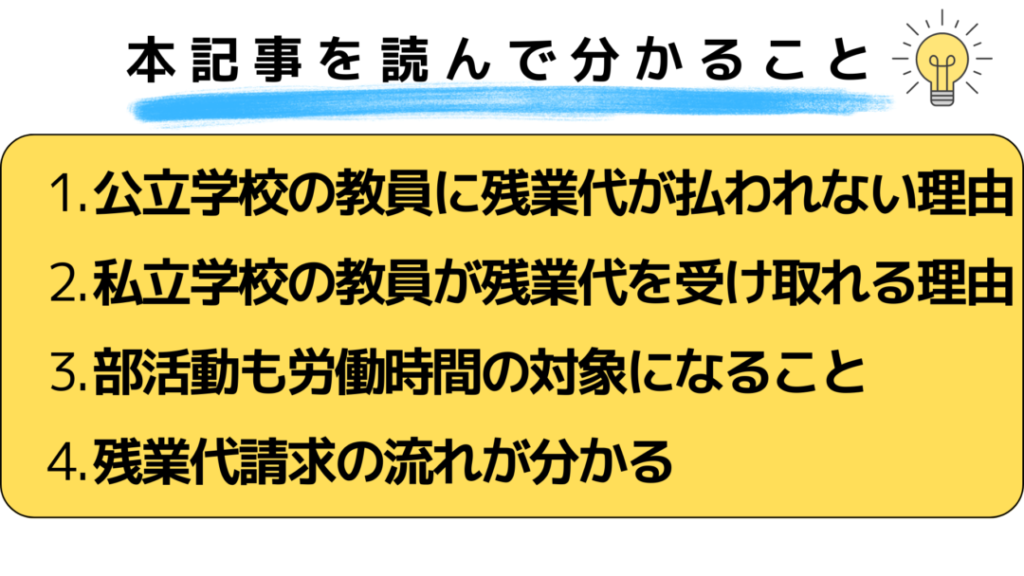
1.公立学校の先生には残業代が払われない
1-1.給特法とは?
公立学校の先生には、『公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(いわゆる給特法)』が適用されます。
この給特法が適用されることで、地方公務員にも適用される労働基準法のルールの一部が除外されることになります。
具体的には、
① 給与月額の4%に相当する金額の教職調整額を支払う
②①の教職調整額が支払われることに伴い、残業代や休日勤務手当が支払われない
③教員に対して、原則として残業を命ずることはできない。残業等を命じることができるのは限定4項目と呼ばれる四つの業務を行う場合のみ
と規定されています。
1-2.限定4項目とは何?
この限定4項目とは、
❶生徒実習に関する業務、
❷学校行事に関する業務、
❸職員会議 に関する業務、
❹非常災害等やむを得ない場合に必要な業務
をいいます。
この限定4項目以外の業務に関しては、 時間外勤務命令が禁止されます。
なお、給得法3条では、教職調整額と時間外等手当について以下のとおり定められています。
給特法3条
1 教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。以下この条において同じ。)には、その者の給料月額の百分の四に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。
2 教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。
2.公務員の部活動は残業代の対象になるのか?

公立中学校や公立高校において、教員がクラブ活動の顧問を担当することはよくあるかと思います。
このクラブ活動への従事が、法定労働時間である8時間を超えて行われている場合に、公立学校の教員に対して残業代が支払われるのでしょうか?
2-1.部活動は限定4項目に当たらない
クラブ活動は、課外活動ではありますが、生徒の自主性、協調性、連帯感を育むことのできる学校教育の一環ということができます。
特に、強豪校であれば、学校を挙げてそのスポーツに熱心に取り組むことはよくあります。
しかし、クラブ活動は、先程紹介しました限定4項目のいずれにも該当しません。
限定4項目の業務に含まないということは、教員に対して部活動指導のための時間外労働を命じることができません。
そこで、限定4項目の業務には該当しないクラブ活動を、教員の自発的行為とみなすことで、時間外・休日勤務手当を支給しないものとしながら、『特殊業務手当』等の名目の手当を支給する場合があります。
| ▼給特法での制定経緯に関する文部科学省の解説はこちら▼ |
3.私立学校の場合の残業代は?

3-1.給特法は適用されない
先程紹介した給特法は、あくまでも公立の教職員のみを対象としています。
つまり、私立学校の教員においては、残業等を命じることのできる業務は限定4項目に限らないし、給与の4%に相当する教職調整額の支払いをする必要はありません。
ただし、公立学校の運用を参考に、給与の4%に相当する手当が支給されているケースもあります。
その代わりに、法定労働時間を超えて労働に従事した場合や休日に出勤した場合には、労働基準法のルールに従い、残業代等を支払う必要が生じます。
3-2.部活動が労働時間にあたるのか
私立学校の教員に対して、給特法が適用されないとしても、直ちに部活動に従事した時間全てが時間外手当等の対象になるわけではありまさん。
残業代等の対象となるためには、部活動に従事した時間が労働時間と評価できることが必要です。


4.労働時間とは?

4-1.労働基準法のルールについて
労働基準法では、1週間あたりの労働時間の上限を40時間とし、1日あたりの労働時間の上限を8時間と定められています(法定労働時間)。
労働時間が6時間を超える場合には、45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与える必要があります。
法定労働時間を超える労働や休日労働等をした場合には、割増賃金を支払わなければなりません。
これらの時間外手当や休日手当の対象となるのは、あくまでも労働時間です。
| 時間外労働した場合 | 25% |
| 1か月の残業時間が60時間を超える場合 | 50% |
| 休日労働した場合 | 35% |
| 深夜労働(午後10時から午前5時まで)した場合 | 25% |
4-2.労働時間とは何か?
部活動が休日や法定労働時間8時間を超えて行われている場合、この部活動に従事する時間が労働時間に当たるのであれば、割増賃金の対象となります。
労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。
この時間に該当するかは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるかを客観的な視点から判断します。
労働契約、就業規則、労働協約等の定めだけで労働時間か否かが判断されるわけではありません。
例えば、契約書内で『部活動は労働時間ではない』と明記されていたとしても、これだけで部活動の時間が労働時間ではないと判断されるわけではありません。
4-3.労働時間か否かを判断する方法
部活動を含め、ある行為が、あらかじめ決められた労働時間(所定労働時間)を超えて行われる場合、その行為が労働時間といえるかを判断するにあたり、
①使用者により義務付けられていること
②場所的拘束性があること
③業務性があること
といった事情が重要な判断要素になります。
①について
勤務先などの使用者から、その行為を行うことを義務付けられている場合には、その行為は労働時間と評価される可能性があります。
義務付けられている場合とは
❶明示的な命令がある場合
❷黙示的な命令がある場合
❸余儀なくされた場合
をいいます。
❶については、わかりやすいと思います。
勤務先から、その行為をするように就業規則、契約書、個別の指示などによって命令されている場合には、その行為を行うことに義務付けられているといえます。
❷については、その行為の内容や時間帯を踏まえて、本来の業務との関連性がある場合には、黙示的な命令があったと評価されます。
❸については、明示又は黙示の命令があるわけではないものの、その行為を行わないことにより受ける不利益や業務上の不都合等を踏まえ、その行為を行わざるを得ない場合には、余儀なくされていると評価されます。
②について
その行為が行われる場所がどこなのかは労働時間にあたるのかを判断する要素となります。
その行為が、勤務先の指定した場所で行うことを求められている場合には、労働時間であると認定される可能性が高まります。
③について
その行為の業務性、つまり、本来の業務との関連性が高ければ高いほど、その行為は労働時間に該当すると判断されます。
通勤時間や出張前後の移動時間は、本来の業務を行うための前提ではあるものの、本来の業務それ自体との関連性があるかといえば、乏しいと言わざるを得ません。
そのため、通勤時間や移動時間は労働時間とは言いにくいでしょう。
朝礼や作業場所までの歩行時間については、業務性はないことはないでしょうが、それ程強くありません。
そのため、その行為が勤務先によって義務付けられているのか等の個別の事情を加味しながら判断していくことになります。
終業後の洗身や入浴については、本来の業務との関連性はそれ程強くなく、これら行為を行うかどうかが労働者の任意に委ねられているのであれば、これら行為は労働時間と評価されない可能性があります。
5.部活動は労働時間にあたるのか?

5-1.部活動とは何か?
部活動は、正規の教育課程ではない課外活動ではあります。
しかし、先ほども解説したように、部活動は、生徒の自主性、協調性といった人格形成に大きな役割を果たすもので、学習指導要領においても、「学校教育の一環として,教育課程との関連が図られるよう留意する」こととされています。
その上、部活動の顧問は、各教員の意思のみで選任されることはありません。
学校長が校務分掌として各教員に対して部活動の顧問等に就くよう要請することで、顧問に就任することがほとんどかと思います。
部活動のこのような性質を踏まえながら、労働時間に該当するのかを検討していくことが必要になると思います。
5-2.①について
明示的な指示はない
上記のとおり各教員は学校長の職務命令等によって部活動の顧問に就任するかと思います。
しかし、部活動の日々の練習や対外試合について、学校長が顧問に対して明示的な指示命令をすることはほとんどないと思います。
万が一学校長が口を出すなら、学校長が代わりに顧問をしてくれ❗️と心の中でツッコミたくなるくらいです。
そのため、明示的な指示は通常考えにくいと思われます。
ただ、野球やサッカーなどの強豪校で、学校が総力を上げてその部活動に注力しているような場合には、もしかすると、学校側が細かい部活動のスケジューリングをしているケースもあるかもしれませんが、非常に珍しい事案かと思います。
黙示的な指示や余儀なくされているといえるのか
教員は、部活動の顧問として、授業終了後に行われる部活動に加えて、就業前の朝練、土日等の休日に行われる練習や対外試合の引率に従事します。
これら行為の一つ一つについて、学校長による明示の指示はないとしても、顧問の先生が学校に対して、スケジュール表の提出、朝練習の届出、日記の提出等をすることによって、学校が顧問によるクラブ活動の具体的な内容を把握した上で、これら部活動の内容に対して何らの異議も出していないのであれば、所定労働時間を超える、あるいは、休日に行うクラブ活動を黙示的に容認していると評価することができると考えます。
そのうえ、顧問という立場が、校長によって校務分掌として任命されるものであることも踏まえると、部活動は学校の黙示的な命令により、あるいは、余儀なくされて行われたと言うことができると考えます。
さいたま地方裁判所判決平成29年4月6日
バレーボール部の活動として、本件学校に朝練習の届け出をしている日や、少なくとも原告作成の本件日記中に、バレーボールの朝練習をした記載がある日については、午前7時30 分以降の原告の早出残業を認める。
日記の記載の有無にかかわらず、週番日誌 にバレーボール部の活動が記録されている場合には、当該部員の下校時刻を原則として終業時刻とする
5-3.②について
部活動は、学校内のグラウンドや体育館、音楽室等の学校施設を利用して行われることが通常です。
仮に、校外の施設を利用する場合でも、その施設利用料を学校が負担したり、学校の名義で使用されているのであれば、学校が指定した場所で部活動を行うことを義務付けられていると言えるでしょう。
5-4.③について
部活動は学校教育の一環であり、生徒の人格形成に大きく貢献するもののいえます。
さらに、部活動の顧問が、校務分掌として任じられるものであり、事実上拒否することが困難な業務命令ということができます。
そうすると、部活動には業務性が認められると考えられます。
5-5.部活動は労働時間にあたる可能性
以上述べたとおり、部活動は教員による自発的な活動ではなく、労働時間に該当すると判断される可能性は十分にあると考えます。
6.固定残業代が払われている場合
残業を伴う部活動に対して、特殊業務手当等の名称の固定残業代が支給されているケースもあります。
しかし、固定残業代の全てが、残業代の支払いとして有効になるわけではありません。
固定残業代が残業代の支払いとして有効となるためには、固定残業代に関する有効な合意があることが必要となります。
・設定されている残業時間が1ヶ月の残業時間の上限である45時間を遥かに超えている
・固定残業代を除いた給与をベースに時給計算すると最低賃金を下回ったり、これを若干上回っている
・設定されている残業時間を超えた残業をした場合に、残業代の精算がなされていない
といった事情がある場合には、固定残業代に関する合意が有効に成立していないと判断されることがあります。
さらには、固定残業代として支払われている手当の名称や内容が不明瞭であるため、その手当内に他の手当が含まれており、固定残業代を明確に区別できない場合にも、残業代の支払いと認められないこともあります。
7.残業代を請求する手続き
労働者が残業代を請求する流れを説明します。
残業代を求める通知をする
労働者は使用者に対して、残業代一切の支払いを求める通知をします。残業代の請求は、口頭でも行えますが、通知内容を明確にするとともに消滅時効の更新(中断)をするために内容証明郵便で送付します。
労働時間の資料を確保する
残業代一切の請求をするとともに、労働時間を証明するための資料を確保します。就業規則や賃金規定に加えて、タイムカード、業務日報、給与明細、パソコンのログ履歴、メールの送受信歴等の資料を開示するように求めます。使用者が資料の開示を拒否する場合には、証拠保全の申立てを検討します。
消滅時効に注意する
残業代にも消滅時効があります。令和2年4月以降の残業代については、3年の時効期間です。令和2年3月以前の残業代については、2年の時効期間となります。時効期間を過ぎた残業代については、使用者は消滅時効の援用をしてきます。そのため、時効期間が過ぎる前に、使用者に対して、残業代の支払いを「催告」します。催告により、6か月間、時効の完成が猶予されます。
6か月の経過するまでに合意ができなければ、速やかに労働審判の申立て又は訴訟提起をします。
使用者と交渉する
使用者側の反応を踏まえて、使用者と交渉を行います。
労使間の交渉の結果、合意に至れば、残業代の金額や支払方法等を記載した合意書を作成します。合意に至らない場合には、労働審判の申立てなどの次のステップに移行します。また、使用者側が全く交渉に応じない場合にも、早期に次の段階に移ります。
労働審判を申立てる
労働審判とは、裁判官と労働審判委員2人で構成する労働審判委員会が労働者と使用者を仲裁して、労使間の紛争を3回の審判期日で解決を目指すプロセスです。
労働審判では、3回の労働審判で解決を図るプロセスです。そのため、後述する訴訟手続きと比べると、かなり早期に紛争解決できる手続といえますが、その反面、十分な審理を行えないため、一定程度の譲歩を求められてしまいます。
3回の期日を経てもなお、話し合いによる解決ができない場合には、裁判所は当事者に対して労働審判を言い渡します。労働審判を受けてから2週間以内に異議申立てをしなければ、労働審判は確定します。
訴訟を提起する
訴訟手続では、原告と被告の当事者双方が、主張・反論を繰り返し行います。当事者の訴訟活動により審理が尽くされた時点で、裁判官が判決を言い渡します。訴訟手続きでは、労働審判とは異なり、当事者双方が主張・立証を繰り返し行い、慎重な審理を行います。そのため、訴訟の期間は1年以上の期間を要します。また、残業代の不払いが悪質であると判断される場合には、残業代と同額の付加金の支払いを命じられることもあります。
TISP!付加金とは?
残業代等を支払わない場合、使用者は、未払い残業代等に加えて、これと同じ金額の支払いをしなければなりません。これを付加金といいます。
関連記事|付加金とは?付加金の支払が認められる場合を弁護士が解説します
残業代の問題は弁護士に相談しよう
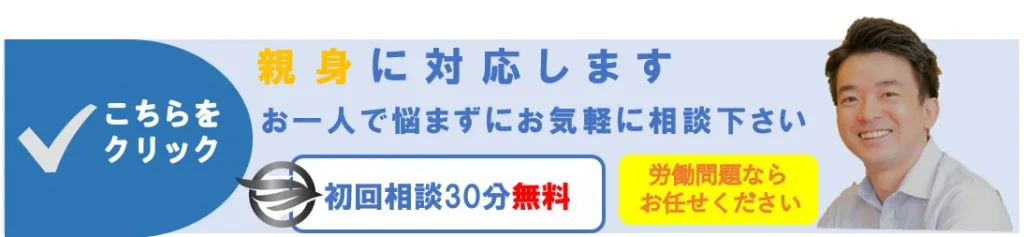
部活動が残業代の対象となる労働時間と評価できるかは、様々な事情を総合的に判断することを要します。
さらに、固定残業代を支払っている場合に、これが残業代の支払いといえるかは、とても難しい法的な判断が必要です。
部活動の残業代を請求を考えている場合、あるいは、残業代の請求を受けている場合、まずは弁護士に相談してみましょう。
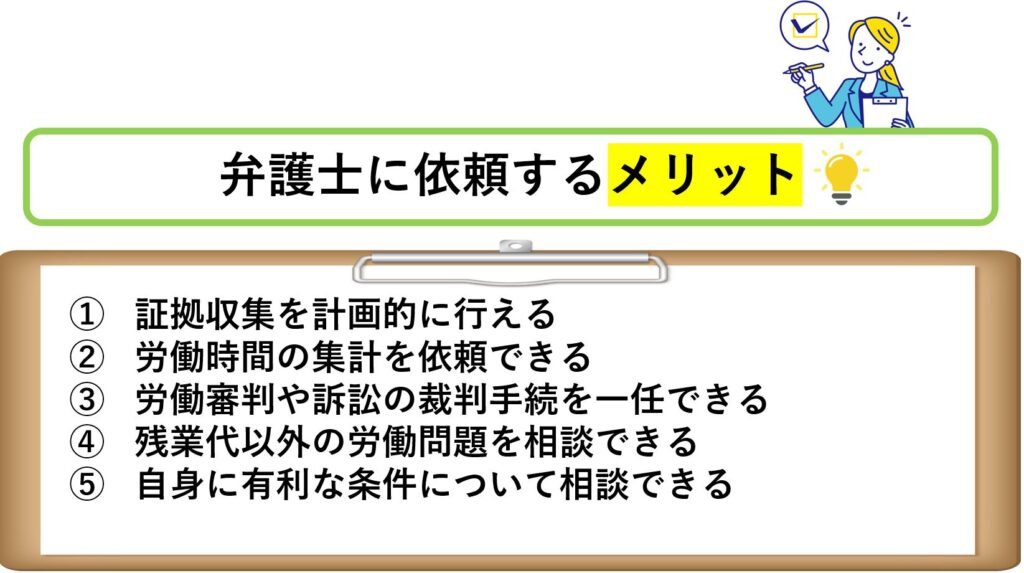
当事務所では初回相談30分を無料で実施しています。
面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
お気軽にご相談ください。
対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。