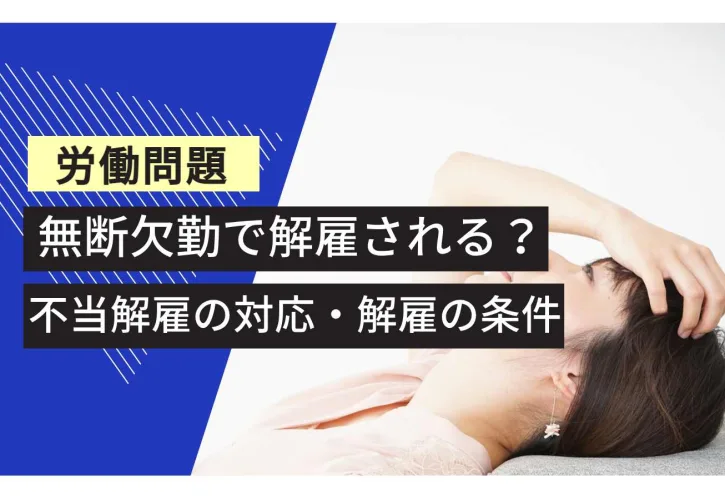無断欠勤が続くと、当然に解雇を受けると思っていませんか?
たしかに、従業員は、決められた時間に出社した上で、仕事をしなければなりません。それにもかかわらず、無断で欠勤すれば、労働契約に違反することになります。
しかし、無断欠勤をすることはよくないことですが、これを理由に即座に解雇処分とすることは重過ぎるでしょう。不当解雇であれば、バックペイ、解決金などの請求が認められる可能性があります。
無断欠勤を理由とする解雇処分が認められる条件を弁護士が解説します。
無断欠勤とは?

従業員は、雇用契約により労務を提供する義務を負っています。欠勤とは、従業員が、出勤するべき日に、この労務を提供する義務を尽くさないことを言います。
従業員は、労務の提供をしたことの対価として給与の支給を受けますから、欠勤をした場合、仕事をしていない以上、その日の給与は支払われません。
欠勤の種類
欠勤には、会社の承認を得た欠勤のほか、会社の承認を得ない無断欠勤があります。
無断欠勤には、①会社に欠勤の届出をしたが、欠勤に合理的な理由のない欠勤と、②届出のない欠勤があります。②が無断欠勤に該当することに争いはありませんが、①については無断欠勤には該当しないとの考え方もあります。就業規則において、①の欠勤も無断欠勤の扱いとされているかを確認しましょう。
無断欠勤をする理由は
無断欠勤する理由にはいろいろあります。やむを得ない理由による欠勤もあれば、理由のない欠勤まであります。
- 急病や事故
- 精神疾患
- 労働災害
- セクハラ・パワハラ・いじめ
- モチベーション・出勤意欲の低下
急病や事故を理由とする欠勤
事故や急病により欠勤届を出せずに欠勤している場合もあります。診断書をもらい、これを提出した上で、休職制度の利用をするようにしましょう。
精神疾患を理由とする欠勤
うつ病などの精神疾患を発症し、会社に欠勤の連絡をすることができないこともあると思います。メールやLINE、配偶者や親族からでも良いので早い時期に欠勤の連絡をするようにします。その上で、休職制度の利用を検討しましょう。
労働災害
精神疾患や怪我の原因が労働災害である場合です。長時間労働やハラスメントが原因で精神疾患を発症しているような場合です。労働災害を理由に休業している場合には、解雇することが制限されます。
セクハラ・パワハラ・いじめによる欠勤
上司や同僚からセクハラ、パワハラ、いじめを受けて欠勤していることもあるでしょう。ハラスメントが理由で出社できていない場合には、会社側に相談し、ハラスメントの改善するように求めましょう。
会社は従業員の職場環境を整える義務を負います。そのため、従業員のハラスメント等の被害状況を改善することなく解雇することはできません。
モチベーションの低下
モチベーションの低下により出社したくない場合もあります。ただ、出社意欲の低下は欠勤の合理的な理由とはいえません。使用者側から懲戒処分が行われるリスクはあるでしょう。


無断欠勤による解雇が有効となる条件
無断欠勤をしても、当然に解雇が有効となるものではありません。
確かに、欠勤は、労働者が労働を提供する義務の不履行です。その上、欠勤を無断ですることは悪質な債務不履行ともいえます。
しかし、解雇処分は、従業員の立場を奪う重大な処分です。そのため、解雇が有効となるためには、非常に厳しい条件を満たすことが必要です。
解雇が有効となるためには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められることを要します。これら事情を満たさない解雇は、解雇権の濫用となり無効となります。
たとえば、1回の無断欠勤、やむを得ない理由による無断欠勤を理由として解雇処分は無効となる可能性が高いといえます。
労働契約法16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
2週間以上連続して無断欠勤している場合
労働基準法20条1項の但書には、『労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては』、解雇予告手当を支給する必要がないと定められています。
厚生労働省の通達では、「労働者の責めに帰すべき事由」の一例として、「原則として2週間(14日)以上にわたり、正当な理由がなく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合には、労働者の責めに帰すべき理由となる」としています(昭和23年11月11日本発1637号、昭和31年3月1日本発111号)。
そのため、従業員が、出勤の要請に応じず2週間以上連続して欠勤すれば懲戒解雇とすることができると考えられます。
連続欠勤でも解雇できないことも
従業員が連続欠勤していても、常に解雇が認められるわけではありません。
ハラスメントが理由
欠勤の理由が上司のハラスメントのように会社側が就労環境の整備を怠っていることが欠勤の原因である場合、たとえ連続欠勤があっても懲戒解雇すると不当解雇になるでしょう。
影響が小さい
また、無断欠勤によって会社側に損失が発生していない場合やその程度が小さい場合には、たとえ連続欠勤が続いていたとしても、懲戒解雇が無効となる可能性があります。
精神疾患
また、連続欠勤の原因が、従業員のメンタルヘルスの不調が疑われる場合にも、治療を勧めた上で休職等の処分をし、その後の経過を見るなどの対応を採ることが必要とされ、連続無断欠勤のみを理由に解雇に付すと無効とされるリスクがあります。
日本ヒューレットパッカード事件・最高裁平成24年4月27日
精神的な不調のために欠勤を続けている労働者に対して諭旨退職の懲戒処分をした事案です。
使用者は、精神科医による健康診断を実施するなどした上で、その診断結果等に応じて、必要な場合は治療を勧めた上で休職等の処分を検討し、その後の経過を見るなどの対応を採るべきである。それにもかかわらず。このような対応を採ることなく、直ちにその欠勤を正当な理由なく無断でされたものとして諭旨退職の懲戒処分の措置を執ることは無効であると判断しました。
無断欠勤を理由とした解雇の裁判例
裁判例においても、欠勤の日数だけでなく、以下のような事情を考慮して解雇の有効性を判断しています。
| ① 欠勤の回数、期間、連続欠勤か否か、正当の理由の有無 ② 会社に対する支障の有無や程度 ③ 使用者からの注意指導、教育状況 ④ 勤務態度、勤務成績、過去の処分歴 ⑤ 他事例の処分との均衡 |
| 事案名 | 欠勤の状況 | その他事情 | 有効性 |
| 東京プレス工業事件・横浜地裁昭和57年2月25日 | 6か月間で24回の遅刻と14日の無断欠勤 | 就労すべき日数の69% | 解雇有効 |
| 日本郵便事件・東京地裁平成25年3月28日 | 26日の欠勤 | 再三にわたって電話による出勤命令にも関わらず無視し続けた、退職届の提出を拒否 | 解雇有効 |
| 開隆堂出版事件東京地裁平成12年10月27日 | 2週間にわたる欠勤 | 事前の届をせず、欠勤の理由や期間、居所を具体的に明確にしない | 解雇有効 |
| 住友重機事件横浜地裁昭和56年6月26日 | 6か月間に32日間の無断欠勤 | 解雇有効 | |
| 栴檀学園事件仙台地裁平成2年9月21日 | 正当な理由のない1ヶ月の無断欠勤 | 業務に大きな支障がなかったこと、それまで使用者が特に注意をしなかった | 解雇無効 |
| 紫苑タクシー事件福岡高判昭和50年5月12日 | 3カ月の無断欠勤 | 無断欠勤が会社代表者による暴行が原因であったこと | 解雇無効 |
| 神田運送事件・東京地判昭和50年9月11日 | 1年間に99回の遅刻早退(出勤日数252日のうち)と27回の欠勤 | 何らかの制裁措置により警告することなく、即解雇した | 解雇無効 |
| 太平洋設備機械事件・昭和37年5月28日 | 無断欠勤が19日 | 会社が厳格に出欠管理をしていなかった | 解雇無効 |
解雇処分の有効性を判断するポイント
これまでの裁判例を踏まえますと、長期間の連続する無断欠勤をしてしまうと、解雇処分が有効となる可能性があります。
他方で、無断欠勤があるものの、日数が少なかったり、連続して行われていない場合には、直ちに行われる解雇処分は不当解雇となる余地があります。
特に、無断欠勤や遅刻・早退に対して、使用者が従業員に対して、適切な注意・教育指導を行い、更生の機会を与えていたかが重要なポイントとなります。
解雇理由を確認する
解雇通知が口頭やメールで行われることもよくあります。
文書で告知されたとしても、解雇理由が判然としないことも多々あります。解雇理由を把握し解雇処分の有効性を判断するため、解雇理由証明書の発行を依頼します。
就業規則を確認する
懲戒解雇を含め懲戒処分を行うためには、懲戒事由に該当する懲戒事由と懲戒処分の内容を就業規則に定めていることが必要です。
無断欠勤を理由に懲戒解雇を受けた場合には、就業規則の内容を確認します。
欠勤の理由を確認する
欠勤を理由に解雇処分を受けた場合、その欠勤の理由が何かを確認します。
欠勤の理由が業務災害やハラスメントである場合には、これを裏付ける客観的な資料を確保しておくことが重要です。精神疾患が原因で欠勤している場合には、医師の診断書等の医療記録を準備しておきます。
面談・注意指導を受けたことがあるか
裁判例の紹介でもあったように、欠勤を繰り返したとしても、面談や注意指導を通じて改善の機会を与えられていない場合には、解雇処分は無効となる可能性があります。
そこで、解雇処分を受けるまでに、面談や注意指導、配置転換の機会を受けていたかを確認します。
懲戒処分を受けたことがあるか
解雇処分を受けるまでに、厳重注意や軽微な懲戒処分を受けたことがあるのかを確認します。
懲戒処分は、戒告・譴責(けんせき)→減給→降格→出勤停止→解雇といった順で重たくなります。
順を追って懲戒処分を受けることなく解雇処分をいきなり受けているのであれば不当解雇になる可能性があります。
弁明の機会を与えられているか
解雇処分は非常に重い処分です。そのため、解雇処分を行うにあたっては、従業員に対して言い分を述べる機会(弁明の機会)を与える必要があります。
また、就業規則において、賞罰委員会の開催を条件として規定している場合にも、就業規則のプロセスに従って解雇処分を行う必要があります。
不当解雇を受けた時の3つの注意点
不当解雇を受けた時の注意点を説明します。軽率な対応をしてしまうと、事後的に不当解雇を争うことができなくなります。
失業給付金の仮給付を受ける
解雇の効力を争う場合、失業給付(失業保険)を仮給付として受け取るようにします。
解雇の効力を争っているにもかかわらず、離職を前提とする失業給付の本給付を受けてしまうと、解雇を受け入れたと判断されてしまう可能性があるからです。
そこで、解雇の効力を争う場合には、「仮給付」という形で、求職の申し込みをせずに失業保険の手当を受給するようにします。
なお、不当解雇を争った結果、合意により退職する場合には、解決時を退職日とすると、受給していた失業給付を返還しなければならなくなります。そのため、退職日を解決時とするのではなく解雇日とするように注意しなければなりません。
解雇予告手当を受け取らない
不当解雇を争う場合には、解雇予告手当を受け取らないようにします。
本来、使用者は労働者を解雇する場合、30日前の解雇予告をしなければなりませんが、30日分の賃金に相当する解雇予告手当を支払えば、労働者を即時解雇することができます。
しかし、不当解雇を争っておきながら、解雇予告手当を請求したり、これを受け取ってしまうと、解雇を受け入れている意思表示になりかねません。
不当解雇を争う場合には、解雇予告手当の受取を控えるようにしましょう。
退職届や退職合意書にサインしない
退職届を提出したり、退職合意書に署名捺印することも控えるべきです。
解雇に際して、使用者から退職届の提出を求められたり、退職合意書へのサインをを求められることがあります。しかし、本来であれば退職する十分な理由がないにもかかわらず、使用者の求めに応じてしまうと、自主的な退職をしたと判断されてしまい、事後的に退職の効力を争いにくくなります。
不当解雇を受けた場合の対応や手順
解雇処分に納得できない場合、社員が使用者に対して行うべき対応を解説します。
解雇理由を明らかにしてもらう
まず、解雇処分の内容や理由を明らかにしてもらうため、解雇理由証明書等の発行を依頼します。
解雇が無効であると主張する
解雇処分が不当解雇である可能性が高い場合、速やかに解雇処分が無効であり、労働契約が継続していることを使用者側に通知します。口頭ではなく、内容証明郵便を用いて通知するのが望ましいでしょう。
バックペイを請求する
解雇処分を受けた時点から解決するまでの期間の賃金を請求します。
解雇が無効であれば雇用契約は存続していることになります。しかし、労働者は、解雇処分を受けたことで出社することができなくなっています。会社側の責任で仕事をして給与を得られなくなっている場合には、労働者は出社をしていなくても、会社に対して給与の支払いを求めることができます。このような給与を専門用語で「バックペイ」といいます。
解決金を受け取る
解雇が無効となれば、使用者は一度解雇をした労働者を復職させなければなりません。しかし、解雇処分を通じて、労使間の関係は悪化していることがほとんどです。そこで、使用者は、雇用契約を合意により終了させるため、従業員に対して解決金を支払うことがあります。
解決金は、訴訟手続きにおいて支払われることが多く、給与の半年分から1年分の金額となることが多いでしょう。
残業代を請求する
残業代を受け取っていない場合には、残業代の請求も忘れずに行います。
残業代には消滅時効があるため、速やかに残業代の請求を通知します。残業代の時効期間は3年ですが、民法改正前の令和2年3月以前の残業代の時効期間は2年です。
時効期間が到来するまでに、内容証明郵便を利用して残業代請求をすることが重要です。
解雇を受けた場合には弁護士に相談を
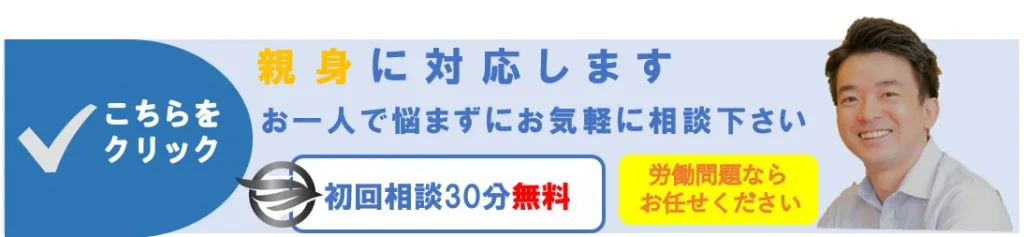
欠勤にも様々な理由があり、無計画に欠勤を理由として解雇等の処分を行うと、これら処分が無効と判断されるリスクがあります。無断欠勤等を行う問題社員の対応には計画性が重要です。
無断欠勤等の問題社員の対応にお困りでしたら、一度弁護士にご相談ください。
無理をせずに早い時期に弁護士に相談することをおすすめします。
初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
お気軽にご相談ください。