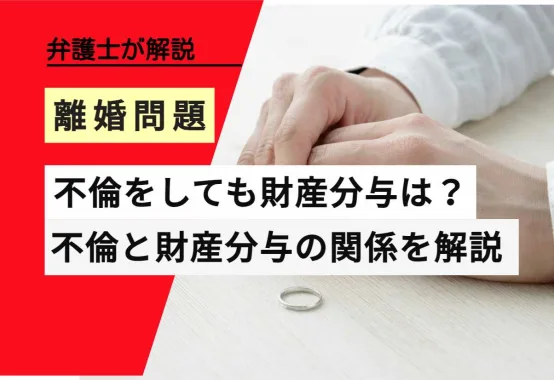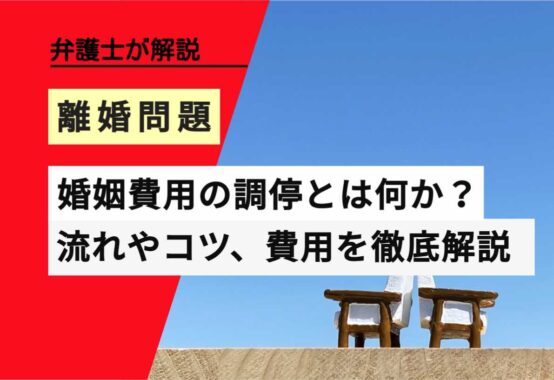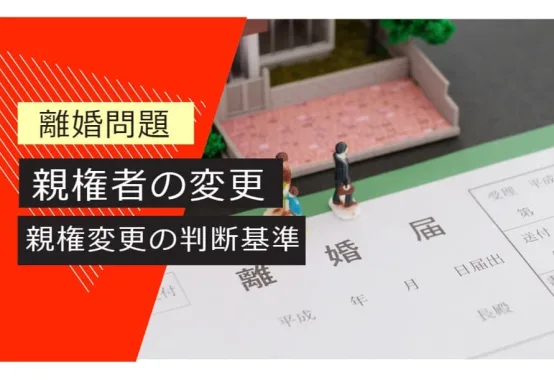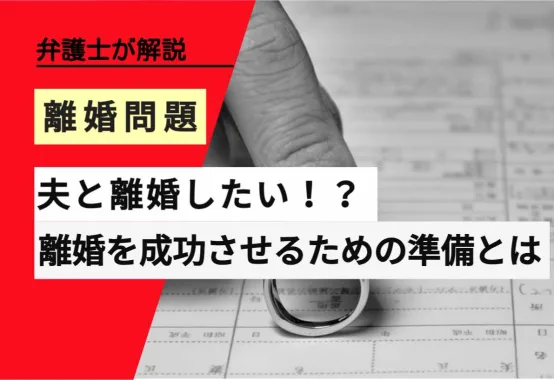熟年離婚に明確な定義はありませんが、中年に差し掛かった夫婦や子育てがひと段落した夫婦、20年以上連れ添った夫婦が離婚することと一般に認知されています。
令和3年の全体の離婚件数184,386件のうち、最も多いのが婚姻期間5年未満(54,510件、29.6%)で、それに次いで多いのが婚姻期間20年以上(38,960件、21.1%)となっています。
本記事では、そんな熟年離婚を検討中の方に向けて、熟年離婚のメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。
熟年離婚とは
熟年離婚とは、長年連れ添った夫婦が離婚することを言いますが、法律上明確に定義されているものではありません。結婚して20年以上が経過しているような、50代以上の夫婦が離婚する場合を熟年離婚と呼ぶことが一般的です。
熟年離婚の件数と離婚率
厚生労働省の統計(「人口動態統計月報年計(概数)の概況」)によれば、離婚件数自体は減少傾向ですが、熟年離婚の件数は、昭和60年では20,434件でしたが、令和3年では38960件まで増加しています。
また、熟年離婚(婚姻期間20年以上)の離婚率は、最も多い婚姻期間5年未満に次ぐ2位であり全体の21.1%を占めています。

熟年離婚の原因・理由と夫婦の特徴
熟年離婚をしたいと思う主要な理由や夫婦の特徴を紹介します。熟年離婚の理由は、各夫婦が置かれている状況によって異なります。
性格の不一致・価値観の相違
男女ともに離婚原因の1位は性格の不一致です。
長年連れ添う中で、子どもの出産や成長、親の介護、夫の定年退職といった数々のイベントを経ていきます。若い頃には経験しなかった出来事を通じて、夫婦間の性格の不一致や価値観の相違を感じることがよくあります。
また、家事や育児への不参加、親族との付き合い方の違い、金銭感覚等のズレなどが長年にわたり積み重なり、夫婦関係が破綻に向かうこともあります。
子どもの成長
子供が成人する、あるいは、結婚するタイミングに合わせて熟年離婚をするケースもあります。子供の健全な成長のために、たとえ性格の不一致、不貞行為、モラハラ等があっても、我慢をして夫婦関係を維持する人もいます。
子供が成人し、自立するタイミングで、自分の道・第2の人生を歩むために離婚を決意するケースはよくあります。
夫の定年退職
夫の定年退職を機に熟年離婚を決意するケースもあります。
現役時代、夫は、日中仕事をしているため、平日の日中自宅に夫がいることは通常なかったことです。それが、定年退職後、夫が、休日だけでなく平日も含め自宅に常に滞在するようになることで、これまでの夫婦の生活状況が大きく変わります。中には、このような状況の変化にストレスを感じてしまい、熟年離婚を決断するケースもあります。
両親の介護
平均寿命が延びたことで、高齢の夫婦が老齢の親を長期間にわたり介護する状況が増加しています。いあゆる「老々介護」という言葉もよく耳にするようになりました。
親の介護は肉体的な負担だけでなく精神的な負担を生じさせます。そのうえ、実親ではなく配偶者の親の介護であれば、通常の介護よりも過酷になりがちです。
それにもかかわらず、配偶者が介護に協力的ではないだけでなく、感謝の気持ちを示すこともないことから、親の介護を通じて夫婦関係を悪化させ、熟年離婚を決意させるケースがあります。
再婚したい
熟年離婚の理由として、再婚があります。
子供たちの成長や両親の看取りなどを経たことなどを理由に、長い結婚生活に終止符を打ち、第二人生として再婚をしたいと考え、熟年離婚を決意するケースもあります。
熟年離婚の5つのメリット
熟年離婚にはいくつかのメリットがあります。
最も大きなメリットは、義理の親や配偶者の介護をすることなく、老後の生活を自分のペースで過ごすことができる点です。
塾年離婚を進めるにあたっては、そのメリットだけでなく、後述するデメリットを十分に理解した上で、熟年離婚をするべきか、熟年離婚をするとして必要となる準備を進めていくことが大切です。
熟年離婚のメリット
①新たな趣味や旅行などの自由な時間の使い方
②自分の収入を自由に使える
③新たなパートナーとの再婚
④相手や相手の親を介護する必要がなくなる
⑤親族関係をリセットできる
新たな趣味や旅行などの自由な時間の使い方
熟年離婚をすることで、残りの人生を、新しい趣味や旅行などの自由な時間に充てることができます。
長い夫婦生活の中で、たくさんの諦めと妥協を経験してきた方は多いのではないでしょうか?また、人生も折り返し地点となり、これからの人生を自分のためだけに生きていきたいと感じることは、決して悪いことではありません。
離婚後は相手の趣味やペースに合わせる必要などありませんし、自由に恋愛しても問題ありません。残りの人生を一人で自由気ままに生きることもできます。
自分の収入を自由に使える
熟年離婚後、自分の得ている収入を自由に使うことができます。お金の使い方を自己決定できる点が熟年離婚のメリットの一つです。
配偶者に収入を管理されることもないし、お金の使い方を気にする必要もありません。自分自身で資金計画を立てながら、その収入を趣味や旅行などに投じることができるのです。
新たなパートナーとの再婚の可能性
熟年離婚後、残された人生を共に送る新たなパートナーと再婚できることもメリットの一つです。
夫婦仲が冷め切った状態で晩年を迎えるよりも、新鮮さを感じられる新たなパートナーとともに幸せな時間を共にしたいと考える人もいるでしょう。熟年離婚により自由に恋愛して独身を謳歌したいと思う人もいるでしょう。
相手や相手の親を介護する必要がなくなる
熟年離婚をすることで、相手や相手の親を介護する必要がなくなります。
特に年齢差のある夫婦の場合、相手が体調を崩したり、認知症になったりしてしまえば、残りの人生の多くの時間を介護に充てることになりかねません。また、自分の親ならまだしも、相手の親を介護することに抵抗がある方はたくさんいらっしゃいます。しかし、熟年離婚をすれば、相手の面倒を見る必要はありませんし、相手の親を介護する必要もなくなります。
こうした介護ストレスからの解放は、まさに熟年離婚のメリットの1つです。
親族関係をリセットできる
熟年離婚をすることで、親族関係をリセットできるメリットがあります。
夫婦生活を送る中で、相手の親族に対してストレスを感じる機会が多かった方もいらっしゃるのではないでしょうか?熟年離婚さえしてしまえば、相手側の親族との関係をまっさらの状態にリセットすることができます。赤の他人なので、交流を持つ必要などありません。
気を遣う必要がなくなるばかりか、顔を合わせる機会もなくなります。


熟年離婚のデメリット(リスク)
熟年離婚の最も大きなデメリット、つまり、熟年離婚を決断するリスクは、離婚後の生活の不安です。特に、専業主婦として長年生活してきた人であれば、離婚後に定職に就くことが難しいこともあります。
その他のデメリットも含めると、熟年離婚のデメリットは以下のとおりです。
熟年離婚のデメリット
①金銭面で困窮する恐れがある
②財産分与で揉めやすい
③子どもと溝ができる可能性がある
④孤独な生活となる
金銭面で困窮する恐れがある
熟年離婚をすることで、金銭面で困窮する恐れがあります。
熟年離婚の場合、子どもはすでに独り立ちしていることが多いですし、相手と離婚して別居するとなれば、その後の生活費等はすべて自身で賄わなければなりません。居住地すら自身で確保しなければならない場合もあります。となれば、収入を得ることは必須です。
もともと仕事や資格を持っている方であれば収入を得る土台はできていますが、定年退職した年齢の方や専業主婦(主夫)だった方が、再就職するのは簡単なことではありません。アルバイトやパートだけでは収入が足りなくなり、離婚前より不自由な生活を送ることになりかねないのです。離婚後、1人きりでの生活が始まるとなれば、金銭面についてはしっかりと考慮しない限り、熟年離婚に踏み切るのは難しい現実があります。
財産分与で揉めやすい
熟年離婚をすることで、財産分与で揉めやすいというデメリットがあります。
夫婦として過ごした年月が長いということは、それだけ築き上げた財産も大きいということ。財産分与は、2分の1ずつが原則ですが、中には不動産や自動車など、簡単には分割できない財産も多く、婚姻歴の浅い夫婦と比較すると、どうしても財産分与で揉めやすいのが問題です。
また、夫が定年退職に際して退職金を受け取っている場合に、その退職金の行方やその残高について争いになりがちです。
夫婦の共有財産のすべてを現金化し、2分の1ずつにできれば話は早いですが、そう単純に済む話ではなく、財産分与トラブルへと発展する可能性が非常に高いです。
関連記事|退職金も財産分与の対象になるのか?弁護士が詳しく解説します
子どもと溝ができる可能性がある
熟年離婚をすることで、子どもと溝ができる可能性があります。
離婚をしたからといって、子どもの立場からすればどちらも親であることに変わりはありません。離婚をすることで、親子が全員そろって交流する機会は確実に減りますし、それが理由で子どもと溝ができてしまう可能性があります。離婚によって相手と離れ、さらに子どもとの関係に溝ができてしまえば、将来孤独な日々を送ることにもなりかねません。頼れる相手がいないというのは、想像以上の不安を抱えることになります。熟年離婚するのであれば心身共に衰えることになる、ご自身の老後の生活を見据えた上で行わなければなりません。
孤独な生活となる
熟年離婚により、夫婦関係だけでなく親族関係をリセットするだけでなく、子どもとの関係も薄まることもあります。一人暮らしとなり、身の回りの世話をしてもらう子供や親族もいなくなり、孤独な生活を強いられる可能性があります。離婚後の孤独感から熟年離婚を後悔する人もいます。
熟年離婚で失敗しないための準備
熟年離婚で失敗しないためには、いかにデメリットを埋めるための準備ができるかにかかっています。特にお金の問題は、必ずクリアしておきたい項目です。
相手も同様に離婚したいならまだしも、この年齢で離婚などしたくないと感じる方も多いため、揉める可能性は必ず視野に入れておかねばなりません。場合によっては、調停や裁判といった法的手続きへと発展する可能性も想定して事前の準備をしておきましょう。
日々の生活費の問題(婚姻費用)
熟年離婚後の金銭面の不安を払拭するためにも、あらかじめ就職活動をしておく、十分な貯蓄を確保しておくといった準備が必要です。
しかし、年齢によっては就職活動が思うように進まなかったり、就職できたとしても低収入となることもよくあります。
そこで、就職活動を行いつつ、相手方の収入の方が多い場合には、婚姻費用の請求を早い時期にしておくべきです。
婚姻費用とは、夫婦が社会生活を送る上で通常必要となる生活費を言い、別居してから離婚するまで請求することができます。
離婚成立時までに一定程度の時間を要することが予想されますので、婚姻費用の請求は必ずしておきましょう。
慰謝料の問題
配偶者の浮気・不倫やDVを理由に熟年離婚する場合、慰謝料の問題が生じます。
慰謝料請求をする場合には、慰謝料の原因となる不貞行為やDVを裏付ける客観的な証拠を収集しておくことが必要です。慰謝料を請求する側で、不倫やDVの証明をしなければいけないからです。
また、熟年離婚の場合、婚姻期間が長期にわたるため、不貞行為やDVの慰謝料額は、一般的な相場よりも高額になる可能性があります。その分、配偶者や不貞相手との交渉が難航するケースもあるため、注意が必要です。
財産分与の問題
適切な財産分与を求めるために、相手方の共有財産をしっかり把握しておきましょう。
財産分与は、結婚してから別居するまでに協力して得てきた共有財産を離婚時に清算するものです。
しかし、相手方が共有財産の情報を自ら開示しない場合には、こちらが相手方の財産の情報を突き止めなければなりません。
そこで、同居期間中に、相手方の財産情報を必要な限りで収集しておくことが求められます。預貯金であれば、金融機関名と支店名まで把握しておくことが必要です。
財産分与は離婚した日の翌日から2年の経過により請求することができなくなりますので注意しましょう。
自宅不動産と住宅ローン
財産分与の中でも問題となりやすいのが自宅不動産と住宅ローンの処理です。
妻が夫名義の自宅に居住し続ける場合、夫が居住し続ける場合、離婚を機に売却する場合など、いろいろなパターンが想定されます。
熟年離婚の場合、住宅ローンの残額がある程度減っていることも多いでしょうが、住宅ローンが残っている場合には、自宅不動産の処理方法によって住宅ローンの扱い方も変わってきます。
退職金と財産分与
退職金も財産分与の対象となります。離婚時に既に退職済であれば、退職金が支給された口座残高が財産分与の対象となります。退職前であっても、別居時点で自主退職した場合に支給される退職金に相当する金額が財産分与の対象となります。
退職金の見落としがないように、財産分与の話し合いを進めていくようにします。
親権と養育費の問題
熟年離婚の場合、子どもは成人していることが多いでしょう。中には、子どもが未成年であったり、成人していても大学等に在学しており未成熟である場合もあります。
このような場合には、熟年離婚に際して、未成年の子供の親権と子供の養育費の問題を合意しておくことが必要です。
毎月の養育費の金額だけでなく、大学の授業料や養育費の終期(大学卒業時か22歳までか)を協議して、決めておくことが重要です。
年金分割の請求
年金分割とは、婚姻期間中(結婚してから離婚するまで)の厚生年金保険の保険料の納付記録を分割する制度です。
年金分割は離婚成立日の翌日から2年以内に年金事務所に対して請求する必要があります。熟年離婚後に生活費の不足が生じないように、年金分割を忘れずに請求しておきましょう。
▶年金分割に関する裁判所の解説はこちら
遺言書を作成しておく
熟年離婚が成立するまでに、万が一、死亡すると、離婚しようとしている配偶者に多くの財産が相続されてしまいます。
熟年離婚は特に離婚手続きの中でも長期化しやすい傾向です。その上、熟年夫婦である以上、離婚手続中に何らかの事情で死亡する可能性も決して低くはありません。
そのため、離婚した配偶者に対して遺産が相続されないようにするため、元気なうちに遺言書を作成しておくことが肝要です。できれば、早い時期から、遺言書の作成に加えて、配偶者以外の親族等に対して生前贈与をしておくことも大切です。
熟年離婚の離婚手続きの進め方
熟年離婚を成立させるための離婚手続きを紹介します。
離婚手続きは、通常、①離婚協議→②離婚調停→③離婚裁判の流れで進んでいきます。
離婚協議の手続き
離婚協議とは、夫婦で話し合いをして進める離婚手続きです。当事者同士で協議できない場合には、代理人弁護士を通じて話合いを進めることもあります。双方で離婚条件が合意できれば、離婚届を提出することで協議離婚が成立します。協議離婚が成立する際には、離婚条件を明確にした協議書や合意書を作成しておくことが大切です。
ただ、熟年離婚の場合、婚姻期間が長い分、財産分与の対象となる財産も比較的多くなること等から、離婚そのものや財産分与で揉めるケースが非常に多く、調停や裁判といった手続きにまで発展することが多くあります。
離婚調停の手続き
離婚協議が奏功しない場合、離婚調停の手続きを通じて離婚手続きを進めていきます。
調停手続きとは、裁判所の調停委員の仲裁を基に、当事者間で話し合いを行うプロセスです。直接、当事者が対面して話し合うことはありませんが、あくまでも「話し合い」であるいことに留意する必要があります。
調停手続きは、1か月半から2か月の頻度で行われるため、離婚調停の手続期間は、1年前後となることが多いです。調停手続きを経て、調停が成立すれば、調停離婚となります。他方で、調停の経ても合意に至らない場合には、調停は不成立となります。
離婚裁判の手続き
調停が不成立となれば、離婚裁判(離婚訴訟)を提起することになります。
離婚裁判では、原告と被告の双方が、主張と立証を繰り返し行い審理を進めていきます。調停手続きのように、話し合いの要素は薄いといえます。
ただ、ある程度の審理が尽くされれば、裁判官から裁判上の和解が勧告されることがほとんどです。裁判官は、当事者双方の主張や証拠を踏まえて形成した心証に基づき、将来の判決を見据えた和解案を提示します。裁判所の和解勧告により和解が成立すれば、裁判離婚となります。
しかし、和解が実らない場合には、当事者尋問を経て判決手続きとなります。判決となれば、控訴審まで移行する可能性もあり、裁判期間は相当長期となります。
熟年離婚は弁護士に相談を

熟年離婚は、残りの人生を自由に過ごせたり、相手や相手の親、そして親族との関係をリセットし、ストレスのない日々を送れたりといった大きなメリットがあります。
しかし、離婚後に1人で生活していけるだけの収入を得る必要があるばかりか、子どもとの関係に溝ができてしまうなどのデメリットも抱えています。また、離婚そのものがどうしても話し合いで解決しない場合、調停や裁判をするしかありません。
そこで、もし、熟年離婚についてお悩みであれば、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、調停や裁判へと発展する前に、協議離婚を成立するためのサポートが可能です。そればかりか、弁護士には有利な条件で離婚するための豊富な知識や経験、交渉力があるため、仮に調停や裁判に発展したとしても安心して任せることができます。