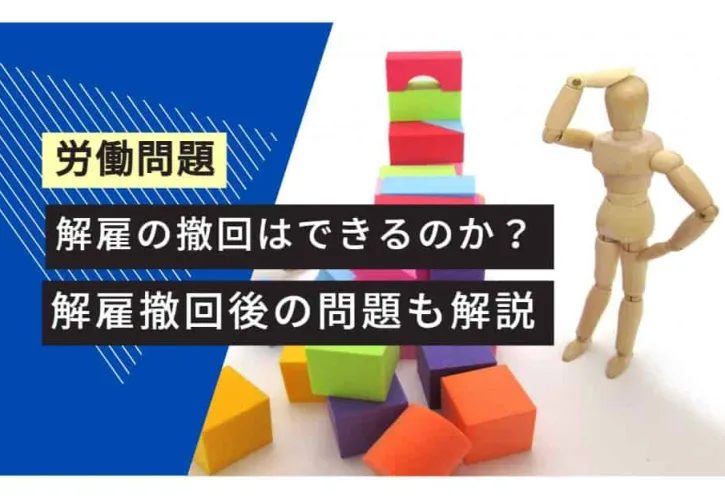従業員の解雇は、雇用契約を一方的に終了させる重たい処分です。
そのため、解雇処分には多くの法律上の問題を引き起こします。その一つが、解雇処分後の解雇の撤回です。
不当解雇には、使用者側に多くの経済的な負担を生じさせます。使用者側が、このような不当解雇に伴う経済的な負担を避けるために、一度行った不当解雇を撤回することがあります。
しかし、不当解雇の撤回はそう簡単にできるものではありません。
本記事では、解雇処分の撤回について弁護士が詳しく解説をしていきます。
解雇を撤回する理由
会社が一度行った解雇処分を撤回する理由は様々です。
主要な理由としては、以下のものが挙げられます。
解雇撤回の理由
①解雇が無効となると悟った
②経済的な負担が大きくなる
③時間的な負担が生じるから
④解雇撤回しても復職できないと考えるから
解雇が無効となると悟った
使用者が労働者を解雇した後、労働者からその解雇の無効を主張し、従業員としての地位にあることの確認を求めることがあります。
解雇処分が有効となるためには、解雇とする合理的な理由があり、解雇とすることが社会通念上相当といえることが必要です。
労働契約法16条(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
解雇処分の有効要件は非常に厳格で、それが有効となるケースは非常に稀です。
従業員から解雇理由証明書の発行を求められたり、解雇無効の主張を受けて、会社が顧問弁護士や社会保険労務士等の専門家に相談したところ、専門家から無効となる見込みを告げられて、解雇処分が無効になるとはじめて気づきます。
このような事情から、会社が解雇処分を撤回することがあります。
経済的な負担が大きくなるから
解雇が無効となると、会社には様々な経済的な負担を招きます。
解雇が無効となる場合、使用者は労働者に対して、解雇処分をしてから解決時までの給料に相当する金額を支払う必要があります。これをバックペイと呼びます。
さらに、解雇が不当解雇となる場合には、労働者との労働契約を合意解約するために、解決金を支払う必要が生じることもあります。労働審判や訴訟手続きで解雇処分が争われる場合には、弁護士費用(着手金・報酬金)の経済的な負担も発生します。
そのほか、退職金や解雇予告手当といった経済的な負担も生じます。
このような諸々の経済的な負担を避けるために、解雇の撤回をする場合があります。
▶労働審判に関する裁判所の解説はこちら
時間的な負担
労働者が解雇の有効性を争う場合、労働審判の申立てや訴訟提起を行い、これら裁判手続きを通じた解決を求めることがほとんどです。
これら手続きは長期に及びます。比較的迅速な手続きである労働審判であっても解雇処分から6か月前後の期間を要します。訴訟手続きであれば1年以上の期間を要します。
このような時間的な負担を考慮して解雇の撤回をすることもあるでしょう。
解雇撤回しても復職をしないと考えたから
労働者は、解雇の無効を主張しますが、大多数の事案では本音では復職を希望しないケースがほとんどです。そのため、使用者側は、バックペイの負担を軽減させるとともに、労働者との交渉を有利に進めたいがために、解雇処分を撤回し復職を認めることがあります。


解雇無効を主張していない場合
解雇処分とは雇用契約を終了させる解除(民法545条)の一種です。
解除処分は、一方的に撤回することはできないとされています。
そのため、使用者は、労働者の承諾がない限り、解雇処分を撤回させることはできないことになります。
したがって、労働者が解雇無効を主張していない場合には、会社は一方的に解雇処分の撤回をすることはできません。
関連記事|解雇と退職の違いとは?会社都合退職・自己都合退職の違いとは?
関連記事|整理解雇とは?整理解雇の要件と実施方法を弁護士が解説
関連記事|問題社員を解雇したいときの注意点
解雇無効を主張している場合
労働者側が使用者に対して、解雇無効を主張している場合、解雇の撤回について黙示的な承諾をしている、あるいは、解雇の撤回を認めないという主張が信義則違反又は権利濫用となる場合があります。
ただ、解雇の撤回に伴う復職が簡単に求められてしまうと、労働者は過酷な環境を強いられてしまいます。
そこで、解雇の撤回が認められたとしても、復職条件が適切に提示されなければ受領拒絶の解消は認められないと考えられます。
受領拒絶の解消(復職条件の提示)
労働条件の引き下げなどの不利益変更は、労働者の自由意志に基づく同意が必要となるため、解雇処分前の労働条件を下回る復職条件を拒否できます(労働契約法8条)。
また、使用者には職場環境を整備する義務がありますから、復職に伴う職場環境の整備するよう求めることができます。
そこで、使用者が、解雇を撤回したうえで復職の申出を受け入れたとしても、その復職に伴う労働条件次第では、使用者による受領拒絶、つまり、労働者からの労務の提供を拒否する状態が解消されていない(方便的解雇撤回といいます。)として、労働者が復職を拒否する可能性があります。
そのため、使用者としては、受領拒絶の状態を実質的にも解消させるためには、以下の条件を満たすことが必要となります。
受領拒絶の解消のための条件
①労働者の不安を解消させるための十分な説明や聴き取り
②合理的な就労開始日、就労場所、職務内容等の復職後の勤務条件の明示
③解雇期間中の未払賃金の支払い
①十分な説明と聴き取り
解雇の撤回が認められるためには、労働者に対して、解雇撤回後の就労場所や就労条件について十分な説明を行います。これに対して、労働者からの質問があれば真摯に回答しなければなりません。労働者からの質問に対して拒否し続けた状況で復職を命じても、それは有効なものとはいえません。
名村造船所事件大阪地方裁判所昭58.12.27
就労場所、就労条件等について、労働者らの疑問に答え、その不安を解消させるため十分の説明を尽くすべきであるから、労働者らの求めを拒み続けたまま本件仮就労命令をしたとしても、これをもって使用者が受領拒絶の態度を改め、労働者らの労務提供を受領するための措置を講じたものということはできない。
②合理的な勤務条件を提示すること
復職後の勤務条件・勤務場所・勤務開始日は、合理的なものでなくてはいけません。
使用者は労働者に対して、就労環境を整備する義務を負っています。解雇処分によって、使用者やその従業員との信頼関係は崩れてしまっています。
そのため、使用者は、自ら解雇処分を行った以上、単純に解雇前の就労条件を提示するだけでは十分ではありません。解雇前の就労条件よりも低い条件では当然ながら不十分といえます。
また、解雇撤回後に復職を即時求めるような復職命令も不適切です。さらに、解雇前に労働者に対するハラスメント(パワハラやセクハラ)が認められる場合には、復職の前提として、これらハラスメントを改善しなければなりません。
アリアス事件東京地方裁判所平成12.8.25
解雇撤回後、職場復帰については、就労開始日、就労場所及び勤務内容の明示を求め、就労の意思を書面により通知し、本件復職命令自体を拒否する意思を表示していたことはない。
他方、使用者は、復職後の原告の職務内容等の明示に全く応じなかったものであり、使用者の責に帰すべき事由に基づき履行不能になったものといえ、原告は被告に対する未払賃金請求権を有すると認められる。
③解雇期間中の賃金の支払い
解雇を撤回する以上、解雇処分以降も雇用契約は存続していることになります。そのため、使用者は復職の前提として、解雇処分後に未払いとなっている賃金を支払う必要があります。
労働者は使用者に対して、労務の提供として就労しなければ、その反対給付である賃金を請求することはできません(民法624条1項、ノーワークノーペイ)。これが原則です。
しかし、不当解雇など使用者の責に帰すべき事由によって労務の提供ができなくなった場合には、労働者は賃金の支払いを求めることができます(民法536条2項本文)。そのため、不当解雇から復職までの賃金を支払う必要が使用者にはあります。
また、長時間労働が常態化していた場合には、残業代等も支払う必要が生じるでしょう。
グリース事件東京地方裁判所平28.11.11
5月26日に解雇の撤回がされてから出社を求める日までの期間が短いこと、労働者は復職の条件を検討中であるのでしばらく待つよう求めていること、解雇撤回までの賃金の支払には争いが残っていたことなどを考慮すると,出社を命じた5月30日に出社しなかったからといって,まだ就労意思はあったと認められる。
他方で、未払賃金があることや使用者と訴訟が係属していることは出社を拒否する理由とはならないこと、本件業務命令により出社を命じた6月17日は、解雇を撤回した5月26日からは相当期間が経過していること,本件業務命令前の復職後の労働条件は通知されていること,解雇撤回後も別の会社において就労し続けていることなどの事情からすると、6月17日以降の就労意思は認められないというべきである。
一心屋事件東京地裁平成30年7月27日判決
労災復職後、使用者が就労場所の変更及び定額残業代の廃止などの労働条件の変更を提示し、労働者がこれに応じず復職しなかった場合、その期間中の未払賃金を請求した事案。
使用者の提案は、人事権行使の裁量の範囲に留まらない賃金減額を含むものと言わざるを得ない。労働者が使用者事業所に赴いた際には、労働者のタイムカードは準備されておらず、労働者に対して同意書に署名して提出をしてもらいたいとの意向を使用者が有している旨を伝えているのみである。
よって、その当時使用者において労働者の就労を受け入れる体制にあたことを認めるに足りる適切な証拠はなく、使用者には責めに帰すべき事由があるといえ、この間、休職前の賃金の支払を請求することができる。
解雇撤回後の問題
解雇の撤回の上、復職条件を整備されれば、労働者は労働契約に基づき仕事をする義務を負うことになります。しかし、復職条件が提示されたといえども、解雇前のように就労することは事実上難しいことが多いでしょう。解雇撤回後には、以下の点に留意する必要があります。
撤回後の賃金請求ができなくなる
民法624条1項による賃金請求が認められるためには、労働者が労務の提供をする就労意思を有している状況にあることが必要であるというとなります。
そのため、使用者が受領拒絶の状態を解消したにも関わらず、労働者が復職に応じない場合等には、就労の意思が認められず、民法536条2項による賃金の請求はできなくなると考えられます。
二次解雇になるリスク
解雇撤回後、適切な労働条件を提示しているにもかかわらず、労働者が合理的な理由なく復職に応じない場合、無断欠勤となりますので、それを理由とした解雇処分がなされる可能性があります。
ただし、普通解雇にしろ懲戒解雇にしろ、解雇処分は労働者の地位を奪う重大な処分ですから、慎重な対応が必要です。解雇を回避するための代替措置の検討やその実施をしたか否か(解雇回避努力)、労働者からの弁明の機会の付与等が必要になります。場合によっては、解雇処分とするのではなく退職勧奨をして、退職届の提出を促すことも検討するべきでしょう。
二次解雇を回避するための対応
復職せざるを得ない場合、労働者は会社に対して労働を提供しなければなりません。欠勤し続けると、これを理由に解雇されるリスクがあります。ただ、一度解雇をした使用者との関係性を修復することは困難となるのが実際かと思います。
そこで、二次解雇を避けるために取りうる方策は以下のものが考えられます。
有給を利用する
復職するための条件が整備されたといえども、出社することは容易ではないことが多いでしょう。その場合に、未消化の年次有給休暇が残っている場合には、有給休暇を取得することが考えられます。
休職制度を利用する
会社内に休職制度がある場合には休職することを検討します。
精神疾患を患い就労できない場合には、休職をすることが考えます。ただし、休職期間の満了時に復職できなければ、解雇や自然退職となる場合があります。
他方で、精神疾患の原因が、会社による解雇や会社の業務によるものであれば、私傷病ではなく業務災害となります。業務災害による休業中は解雇することができません。
退職勧奨を受け入れる
会社においても、一度解雇をした以上、社員を復職させずに離職させたいと考えるのが自然です。そのため、社員は会社から退職届を出すように促されることが多いでしょう(退職勧奨)。社員においても、関係性の悪化した職場に在籍し続けることは、心身の負担を招きます。
そのため、退職条件を十分に精査し、有利な条件であれば退職勧奨に応じることも検討しましょう。
解雇の撤回の問題は弁護士に相談を
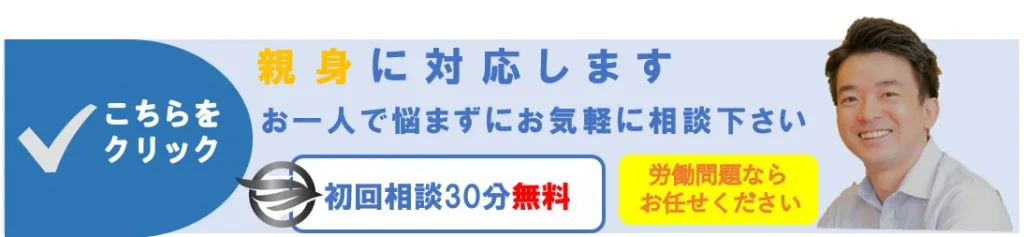
解雇の撤回には様々な問題を引き起こします。解雇処分を受けたことで大きな精神的な負担を生じさせます。その上で、会社の都合により一方的に解雇を撤回されると、さらなる負担を招きます。
一人で悩まずにご相談ください。当事務所では初回相談30分を無料で実施しています。対応地域は、大阪府全域、和歌山市、和歌山県、奈良県、その他関西エリアお気軽にご相談ください。