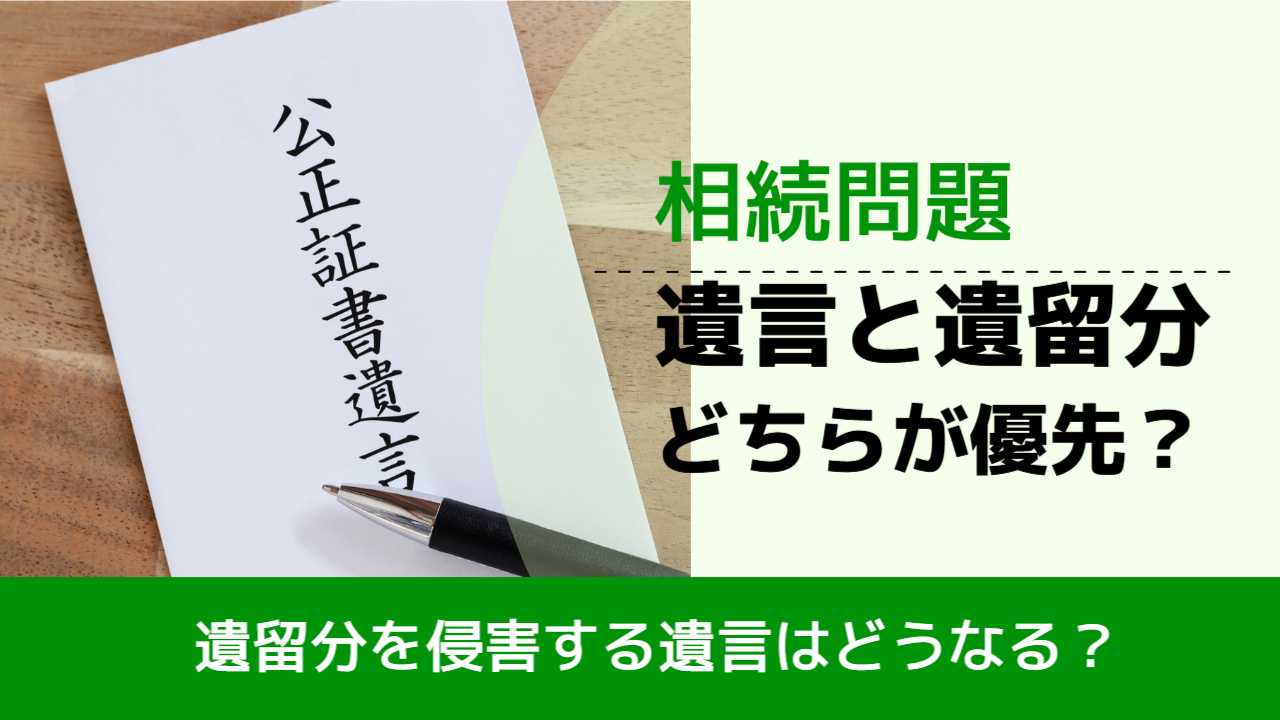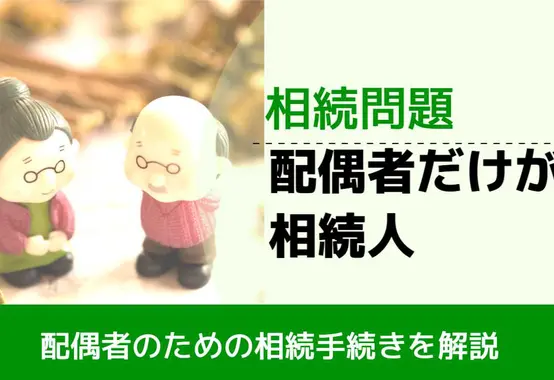遺言は、故人が財産を誰にどの程度分けるのかという意思を示す重要な手段ですが、日本の法律では「遺留分」という一定の相続人が最低限受け取ることが保障される権利が存在します。
たとえ、遺言書を作ったとしても、遺留分の権利は遺言に優先します。つまり、遺言があったとしても、遺留分侵害額請求を行使することが認められており、遺言書が公正証書遺言であっても同様です。
ただし、常に遺留分請求が認められるものではありません。例えば、そもそも相続人が遺留分の権利を持たない兄弟姉妹である場合や遺留分の消滅時効が経過しているような場合です。
しかし、遺留分の請求が制限されるような事案でなければ、遺留分の義務者は、遺留分請求に応じなければならず、双方共に多くの負担を招くことになります。
そこで、できる限り、遺言書を作成する以上、遺留分の問題が生じないように遺留分の対策を講じておくことが、残された家族のメリットになります。
本記事では、遺言と遺留分の基礎知識を解説するとともに、遺留分と遺言の優先順位や、それらを考慮した適切な遺言の作成方法について詳しくご紹介します。
遺留分と遺言の基本概念
遺留分と遺言は、相続手続きにおける重要な概念です。以下では、これらの基本的な概念を説明します。
遺の定義と役割
遺言は、個人が自身の死後に財産をどのように分配するかを表明する手段です。その主な役割は、遺産相続における被相続人の意思を明確にし、法定相続分とは異なる財産分配を可能にすることです。遺言には、自筆証書遺言や公正証書遺言などの形式があり、法律で定められた要件を満たす必要があります。
被相続人は、遺言を作成することで、法定相続人以外の者に財産を残したり、特定の相続人に多くの財産を与えたりすることができます。また、遺言は遺産分割の紛争を防ぐ役割も果たし、相続人間の争いを未然に防ぐことができます。
ただし、遺言の効力には遺留分制度との関係で一定の制限があります。そのため、遺言者は、法定相続人の遺留分を侵害しない範囲で財産処分を行うように配慮することが必要です。このバランスを取ることが、遺言作成の鍵となります。
遺留分制度の目的と意義
遺留分は、法律により特定の相続人(兄弟姉妹以外の相続人)に最低限保障された遺産の割合を指します。
遺留分制度は、被相続人の財産処分の自由と相続人の最低限の相続権を調整する重要な役割を果たしています。この制度の主な目的は、一部の相続人が不当に相続から排除されることを防ぎ、相続人の生活保障を確保することにあります。
そのため、被相続人が遺言で財産を自由に処分できる一方で、法定相続人の一定割合の相続権を保護することで、バランスの取れた相続を実現します。


遺留分を侵害する遺言の効力
遺留分を侵害する遺言は相続においてしばしば問題となります。遺留分を侵害する遺言の効力について解説していきます。
遺留分を侵害する遺言の内容
遺留分を侵害する遺言は、相続人間での紛争の原因となります。
たとえば、遺言に全ての財産を一人の相続人に引き継がせる内容が記載されている場合です。他の相続人は一切遺産を取得することができません。生前に一定程度の贈与を受けていれば別ですが、そうでなければ遺言内容に納得できず、遺留分請求をすることは珍しくありません。
さらに、全ての財産ではなく、一部の財産を遺す遺言であっても、引き継ぐ財産の金額が遺留分額に達しない場合には、遺留分を侵害することになります。
また、遺言の内容自体は、各相続人に公平に遺産を分配する内容であっても、特定の相続人が多額の生前贈与を受けている場合には、遺留分を侵害する可能性はあります。
遺留分を侵害する遺言は無効にはならない
遺言の内容が遺留分を侵害していたとしても、遺言そのものが法的に無効となるわけではありません。
なぜなら、遺言は被相続人の意思を尊重するものであるため、遺留分侵害額が保障されれば、遺言それ自体を無効とする必要がないからです。
遺言は、遺留分を侵害しても無効にはなりませんが、遺留分が遺言に優先するため、遺言により遺留分を侵害された権利者は遺留分侵害額請求をすることができます。
どの遺言であっても遺留分を請求できる
遺留分を持つ相続人は、遺言の種類にかかわらず、その権利を請求することが可能です。
つまり、自筆証書遺言だけでなく公正証書遺言や秘密証書遺言であっても、その内容が遺留分を侵害すれば、遺留分の請求をすることができます。
そのため、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成したからといって、遺言が遺留分に優先するわけではないことに注意をしましょう。
遺留分侵害額請求できない場合
遺留分は相続人に保障された最低限の権利ですが、全ての相続人が請求できるわけではありません。ここでは、遺留分を請求できない特定の状況について詳しく解説します。
遺留分の権利を持っていない
遺留分の権利は、相続人であれば有しているわけではありません。遺留分は、直系卑属(子供や孫)、直系尊属(両親や祖父母)、配偶者が対象となり、兄弟姉妹には遺留分の権利を与えられていません。そのため、法定相続人が兄弟姉妹である場合、一部の兄弟姉妹に遺産を一切相続させない遺言を作成したとしても、遺留分侵害は生じないことになります。
また、兄弟姉妹が先に死亡している場合、兄弟姉妹の子供、つまり、被相続人から見れば甥や姪が代襲相続人となりますが、甥や姪も同様に遺留分の権利を持ちません。
さらに、被相続人の配偶者や子供、両親であっても、相続放棄をした場合には、はじめから相続人ではないことになります。そのため、相続放棄をすれば、遺留分の権利も無くなることになります。
生前贈与を受けているため遺留分の侵害がない
生前贈与を受けていると、遺留分が侵害されない場合があります。
遺留分は、遺留分侵害額を計算するにあたって、遺留分額から生前贈与を受けた金額を控除します。そのため、生前贈与された財産が遺留分の権利を満たしている場合、遺留分の侵害がなく遺留分請求をすることができません。仮に、生前贈与の金額が遺留分額を満たさない場合には、遺留分侵害額の金額は減ることになります。
遺留分の時効が到来している
遺留分の請求権には法律で定められた時効が存在し、これを過ぎると遺留分請求ができなくなります。
この時効は法律関係の安定を確保することや、紛争を長期間にわたらせないために設けられています。
具体的には、遺留分侵害額請求権の時効は被相続人の死亡を知った日から1年、または相続の開始日から10年となります。遺留分権利者が遺言の内容を知ってるにも関わらず、1年以上遺留分請求をしなければ時効により遺留分請求は消滅します。
ただし、時効期間が過ぎれば当然に権利が消えるわけではありません。時効による効果が生じるためには、時効の援用が必要です。時効の援用とは、時効の完成を主張する意思表示です。
時効期間が経過しているかの確認は非常に重要ですので、弁護士にあらかじめ相談することを推奨します。
遺言で遺留分が侵害されている時の具体的な対応
遺言により遺留分の侵害を受けている可能性がある場合、適切な対応を行うことが重要です。以下では、その具体的な手順と考慮すべきポイントについて解説します。
遺言の無効を主張できるか検討する
遺言が無効とされる可能性を検討します。
具体的には、遺言書に必要とされる方式や、遺言者の意思能力が満たされているかが重要なポイントとなります。例えば、自筆証書遺言が無効とされるケースには、署名や日付が適切に記載されていない場合や全文が自筆で書かれていない場合が挙げられます。
また、遺言者が遺言の作成当時、重度な認知症を患っていたり、成年後見を受けている場合には、
十分な判断能力を持たないために遺言が無効となることがあります。
そのため、以上のような事情がある場合には、遺言の無効を主張するべきか検討しましょう。ただし、公正証書遺言の場合には、公証人によるチェックを経ているため、遺言の無効が認められる可能性はそれ程高くありません。
遺留分侵害額請求の内容証明を送付する
遺留分侵害額請求を行う際には、その意思を明確に伝えることが重要です。そこで内容証明郵便を使って遺留分侵害額請求をする方法があります。内容証明郵便は、送付した書面の内容とその送付日時を記録として残せるため、いつ、どのような通知をしたかを証明することができます。
特に、遺留分の場合には、遺留分侵害を知った日から1年の時効期間があるため、時効が経過する前に遺留分請求したことを事後的に確実に証明できることが重要になります。
適切な形式で内容証明郵便を作成し、迅速に送付することが、遺留分侵害額請求を進める上での重要なステップとなります。
遺産や生前贈与を調査して遺留分侵害額を算出する
遺留分の侵害額を算出するためには、まず遺産全体の内容と被相続人が生前に行った贈与について詳しく調査を行うことが不可欠です。
遺留分の侵害額を計算する計算式は以下のとおりです。
| ①遺留分を算定するための財産の価額 =相続開始時における被相続人の積極財産の額 +相続人に対する生前贈与の額(原則10年以内) +第三者に対する生前贈与の額(原則1年以内) −被相続人の債務の額 ②遺留分額 =①遺留分を算定するための財産の価額×(総体的遺留分の割合)×(法定相続分の割合) ③遺留分侵害額 =②遺留分額 −遺留分権利者が受けた特別受益の額 −遺産分割の対象財産がある場合において遺留分権利者の具体 的相続分に相当する額 +遺留分権利者が負担する債務(遺留分権利者承継債務) |
遺留分の基礎財産には、相続開始時の遺産だけでなく生前贈与も含まれます。ただし、遺留分の義務者に対する生前贈与については、期間制限が設けられています。相続人に対する生前贈与は相続開始前10年間、相続人以外の人に対する生前贈与は1年間に限定されています。
相続時の遺産や生前贈与を調査した上で、これらの財産を適切に評価することで、遺留分侵害額を算出することができます。一方、遺留分を請求する側にも生前贈与があった場合には、遺留分権利者が受けた特別受益の額として遺留分額から控除されることになります。この権利者側の生前贈与については上述したような期間制限は規定されていないため、注意が必要となります。
遺言作成時の遺留分への配慮
遺言を作成する際には、遺留分の問題を避けるために、遺留分に配慮した適切な対策をすることが重要です。
遺言者が意図する財産の承継を実現しつつ相続の公平さを保つ方法として、いくつかの遺留分対策を取り入れることができます。本記事では、それらの具体的な方法を詳しく解説していきます。
一部の遺産を相続させる
特定の相続人に一切相続させないという極端な遺言内容とするのではなく、一部の遺産を特定の相続人に相続させることで、相続人の遺留分の権利を侵害しないように配慮することが可能です。
仮に、特定の相続人に相続させる遺産額が完全に遺留分額と一致していなかったとしても、その差額がそれほど大きくないのであれば、遺留分侵害額があったとしても、遺留分請求を受けない可能性はあります。なぜなら、わずかな遺留分侵害額を回収するために、弁護士費用や時間・労力を費やそうと考えないことが多いからです。
逆に、遺言作成後の財産状況の変動により、特定の相続人が承継する遺産額が想定以上に多額となってしまう場合には、生前贈与や生命保険金の活用により調整を図ることも検討しましょう。
付言事項を用いる
遺留分を侵害する遺言を作成する場合、付言事項を用いることで、遺言者の意図をより具体的かつ明確に相続人に伝えることができ、相続人間の紛争を防ぐことができます。
付言事項とは、遺言書でどの財産を誰に残すのかといった遺言事項以外の部分で、遺言者自身の気持ちを記した部分を言います。
付言事項には、権利義務の変動という法的効果はなく、その内容に法的拘束力はありませんが、遺言者の考え方や気持ちを相続人に伝えるために非常に役立つ要素です。なぜ、このような遺言を作成したのかを伝えることで、遺言の拝啓に存在する遺言者の想いを相続人が理解しやすくなり、相続に関する誤解を減らし、円満な解決が期待できます。さらに、家族間の感情的な軋轢を和らげ、紛争の回避に繋がる可能性が高まります。
このように、付言事項は相続問題を感情面から調整する有効な手段として活用することができます。
生前贈与の内容を遺言で触れておく
遺言書に生前贈与の詳細を明記することが、相続トラブルを防ぐ一つの実効的な方法です。例えば、遺言に『生前贈与として令和2年に長男に不動産Aを譲渡した』との記載があれば、遺留分侵害額の計算において、この生前贈与を考慮することができます。
上述したとおり、遺留分権利者が受けた生前贈与は遺留分侵害額の計算において考慮されます。時に、生前贈与を受けた当事者しか、その事実を知らず、その他の相続人には知れ渡っていないことも珍しくありません。
そこで、遺言書において、生前贈与の詳細を明記して、相続人に生前贈与の事実を知らせることで、遺留分の問題を予防できるかも知れません。ただし、遺言書の記載だけで生前贈与の事実を認定することはあまりありません。これを裏付ける客観的な証拠と合わせることで生前贈与の認定ができるものと考えます。
このように、生前贈与の詳細を遺言に触れておくことは、遺留分の問題を予防することが期待できます。
遺留分の放棄をしてもらう
相続におけるトラブルを未然に防ぐ有効手段のひとつとして、遺留分の放棄を依頼する方法があります。
遺留分の放棄には、生前にする方法と死後にする方法があります。
生前に遺留分の放棄をするためには、遺留分権利者本人が家庭裁判所に遺留分放棄の許可申立てを家庭裁判所に対して行った上で、家庭裁判所から遺留分放棄の許可を得て行う必要があります。遺留分を請求できなくなるという不利益を受ける遺留分権利者本人が申立てをしなければならないことから、実際にはなかなか利用されることはありません。
次に相続開始後の遺留分放棄ですが、遺留分権利者が遺留分義務者に対して、遺留分侵害額請求を行使しないと意思表示をすれば足ります。
遺留分対策としての生前贈与の活用
生前贈与は、遺留分対策として効果的な方法の一つです。遺言者が生前に財産を贈与することで、相続財産を減少させ、遺留分の計算基礎を小さくすることができます。ただし、相続開始前の一定期間内に行われた贈与は、遺留分の算定基礎に加算されるため、贈与の時期や方法に注意が必要です。
特に有効な方法として、年間110万円以内の贈与を継続的に行うことが挙げられます。この金額は贈与税の基礎控除内であり、贈与税の課税を受けることなく生前贈与できます。また、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与制度を活用することも考えられます。
なお、生前贈与を行う際は、贈与の意思を明確にするため書面で残すことが重要です。また、贈与税の申告が必要な場合は適切に手続きを行うことが求められます。
遺留分対策としての生命保険の活用
生命保険も遺留分対策に活用できます。死亡保険金は受取人固有の財産となり、遺留分の算定基礎に含まれないからです。ただし、死亡保険金の総額が遺産総額に比して大きくなると、遺留分の算定基礎に含まれる可能性があるため注意が必要です。
家族間の話し合いによる遺留分問題を回避する
家族間で事前に十分な話し合いを行い、家族間で合意を図ることは、遺留分問題を回避する方法の一つです。相続人全員が納得できる財産分配の方針を生前に決めておくことで、将来的な紛争リスクを軽減できます。
具体的には、家族会議を開催し、被相続人の意向を尊重しつつ、各相続人の事情や希望を確認します。その上で、相続人間の公平と実情に即した分配案を検討し、相続人間の納得を得るようにします。
この過程で、遺留分権利者の理解と同意を得ることが重要です。遺留分を超える財産移転に関しても、その必要性や妥当性について説明し、納得を得られれば、将来の遺留分侵害額請求のリスクを低減できます。その上で、協議内容を公正証書遺言として文書化することで、より確実な効力を持たせることができます。
ただし、この方法は、相続人間で生前に遺産の分配について話し合いができるだけの関係性があることが大前提となります。相続人間の関係性が良好ではない場合、生前に話合いをすることで、かえって相続問題を勃発させてしまうリスクもあります。
遺留分の問題は難波みなみ法律事務所に

遺留分と遺言の関係について理解し、どのような場合に遺留分請求ができるのか、遺留分の問題を防ぐためにできる対策を説明しました。
遺言は、遺言者の相続に関する思いを実現させるだけでなく、親族間の紛争を未然に防ぐために利用されるものです。しかし、遺言を作ったばかりに、かえって「遺留分」という親族間の紛争を作り出してしまうのも非常に残念です。そのため、遺言を作るからには、遺留分の対策もしっかり講じて、家族間の対立を可能な限り予防することが重要です。かといって、生前から遺留分対策を十分に行うことも簡単ではありません。
そこで、遺言を作成する際には、弁護士に相談した上で、遺留分対策を踏まえた適切な遺言書を作成するようにしましょう。