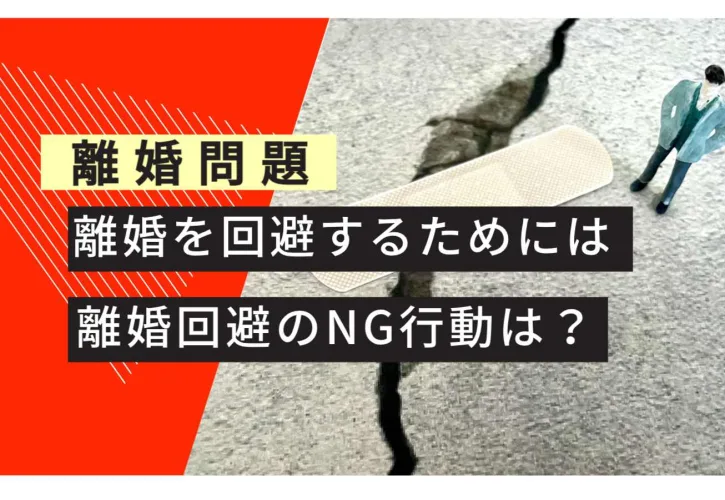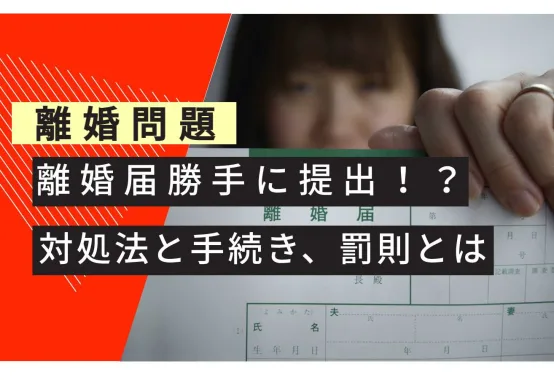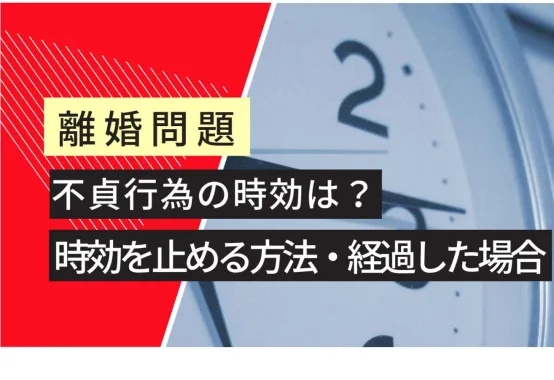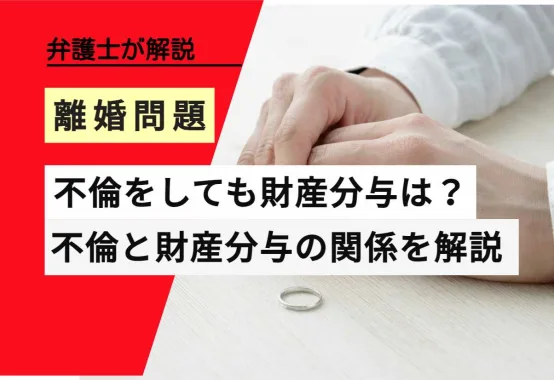離婚をする夫婦は少なくありません。
ただ、実際に離婚する夫婦の多くは円満離婚ではなく、不満を残しながら離婚します。
つまり、夫・妻のどちらかが離婚を告げ、もう一方は「離婚したくない」というケースが多いということです。
『離婚したくない』には、離婚それ自体を拒否するだけでなく、離婚すること自体は反対しないが、離婚に関する各条件が納得できない場合も含まれています。
一体、なぜこのようなすれ違いが起きてしまうのでしょうか。ここでは、「離婚をしたくない理由」と「離婚をしたい理由」、それぞれの心理について解説します。
この理由を知ることによって、夫婦の関係改善や離婚の回避などに役立つ可能性があるでしょう。
本記事では、離婚を求める配偶者に対する対処法を解説します。
本記事を読んで分かること
- 離婚をしたい理由・したくない理由が分かる
- 離婚原因の内容が分かる
- 離婚を回避するためにとるべき行動が分かる
離婚したくない場合には離婚は強制されない
離婚を切り出されても、「離婚したくない!」と思うのであれば離婚に応じる必要はありません。
離婚は、夫婦の話し合いにより離婚届を市町村役場に提出することで成立するのが原則です。
そのため、離婚を求めれても、あなたが離婚に応じない限り、すぐに離婚を成立させることはできません。たとえ、不貞行為やDVなどの離婚原因があったとしても、離婚を求められても、すぐに応じる必要はありません。
離婚原因があれば離婚裁判を通じて、将来的に離婚判決が出される可能性はありますが、離婚を認める判決が確定するまでの期間は、1年以上の期間を要します。
離婚をしたくないのはなぜか?
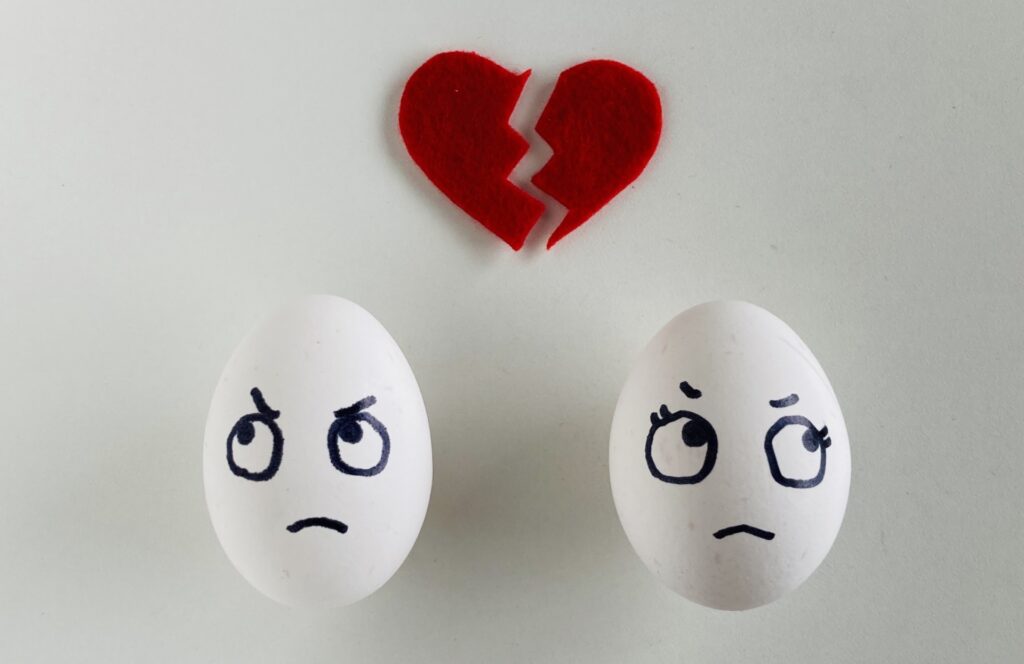
離婚をしたくない理由には、様々あります。
その理由を整理することで、離婚を求める配偶者の心理を理解できるようになり、離婚を回避できるかもしれません。
まず、「離婚したくない理由」から紹介します。
離婚したくない主な理由には、以下の5つが挙げられます。
未練や好意
1つ目は最も多いとされる「相手に未練や好意がある」という理由です。
関係がこじれてしまっていても、本来は愛し合って結婚した二人です。
意地を張っていただけのつもりが、いつしか溝が深まり、相手に離婚を言い渡されてしまったというケースも少なくありません。
相手に対して未練や好意がある場合は、離婚をしたくないと考えるのは当然といえるでしょう。
子供と離れたくない
2つ目は「子供と離れたくない」という理由です。
経験上最も多い理由であると考えます。
お互いに離婚自体には納得できていても、子どもの存在を考えると離婚したくないという気持ちになる人も多くみられます。
離婚後に子供と会えなくなることは耐えられない、両親がそろっていないと子供に不自由をさせてしまい養育環境が悪くなってしまうなどと考えた末に離婚を踏みとどまる夫婦も多いようです。
経済面の不安
3つ目は「経済面に不安がある」理由が挙げられます。
これは特に専業主婦やパート従業員であることの多い妻側に多い理由です。
離婚後の生活を考えると、離婚に踏み切れない人も多くいます。
我慢して結婚生活を続ければ相手の収入で安定して暮らせるなど、金銭面につながりを感じるケースも多いようです。子供がいる場合はなおさら不安を感じ、離婚したくないと考えるでしょう。
孤独に耐えられない
4つ目は「一人になることに耐えられない」という理由です。
今まで一緒にいたパートナーがいなくなると、当然ほとんどの人は寂しさや心細さを感じるでしょう。この孤独感に耐えられない人は、離婚を避けることがあります。
世間体
5つ目は「世間体が気になる」ことです。現代では離婚はさほど珍しくなくなりました。
とはいえ、日本にはまだ離婚に対する偏見を持つ人もいます。
そのため、社会的にマイナス評価を与えられることをおそれたり、知り合いへの体裁が気になったりする人は、離婚をしたくないと考える傾向にあるのです。
離婚したくない理由
- 未練や好意がある
- 子供と離れたくない
- 経済面に不安がある
- 1人になることに耐えられない
- 世間体が気になる


離婚をしたいのはなぜか?
離婚をしたくない理由に加えて、離婚を求める配偶者が離婚を求める理由も理解しておくことが離婚の回避につながります。
離婚をしたい理由にはどのようなものがあるのでしょうか。
今回は、平成30年度の司法統計を参考に、男女別の離婚原因をランキング形式で解説します。特に多い5位までは、あわせて詳細も説明します。
夫の離婚原因
| 男性の離婚原因 | |
| 1位 | 性格の不一致 |
| 2位 | 精神的に虐待 |
| 3位 | 異性関係(不貞) |
性格の不一致
まずは、男性の離婚原因を見ていきましょう。1位は「性格が合わない」ことです。
結婚後、妻と性格が合わないと感じる男性も多いようです。すると、次第に家で一緒に過ごすことが苦痛になり、離婚を決意するケースも多いといわれています。
精神的な虐待(モラハラ)
2位は「精神的に虐待する」というものです。
妻からの虐待やモラルハラスメントに悩む男性も少なくありません。長期間にわたり心ない言葉を浴びせられると、心身のバランスが崩れる原因につながります。
男性の場合は周りに虐待の相談をしにくく、離婚までに時間がかかりやすい傾向にあります。
異性関係
3位は「異性関係」です。妻の不貞行為等が引き金となり、離婚を決意する男性もいます。
反対に、男性が妻以外の女性に興味を持ち、離婚後に不倫相手と一緒になろうと考えるケースもあるようです。
家族・親族の折り合いが悪い等
4位は「家族親族との折り合いが悪い」という理由です。
配偶者が親族との付き合いを断ったり、配偶者の家族との折り合いが悪かったりする場合に、離婚を切り出すケースがあります。
5位は「性的不調和」です。性行為を長期間配偶者に拒否される、いわゆるセックスレスが原因で離婚となる夫婦も多くいます。
以下、6位は「浪費する」、7位は「同居に応じない」という理由です。浪費については、配偶者がパチンコやギャンブル等の浪費に明け暮れて生活費を渡さないということが多いです。
8位は「暴力を振るう」、9位は「家庭を捨てて省みない」、10位は「生活費を渡さない」という理由となっています。
妻の離婚原因
次に、女性の離婚原因を見ていきましょう。
| 女性の離婚原因 | |
| 1位 | 性格の不一致 |
| 2位 | 生活費を渡さない |
| 3位 | 精神的な虐待 |
性格の不一致
1位は男性と同様に「性格が合わない」という理由です。
性格とひとまとめにしているものの、その言葉が指す範囲は広く、夫婦によっても異なります。
たとえば、夫との趣味が合わないため離婚したいケースもあれば、生活習慣が合わず離婚したいケースもあるようです。
生活費を渡さない
2位は「生活費を渡さない」ことです。夫が生活費を渡してくれず、生活上必要なものが購入できないケースがこれに該当します。
お金が足りないことを夫に伝えると、管理が悪いと攻撃されるケースもあるようです。
精神的な虐待
3位は「精神的に虐待する」ことです。
直接的な暴力がなくても夫から心ない言葉で攻撃されたり怒られたりするなど、モラルハラスメント(モラハラ)や精神的DVなどが含まれます。
精神的な虐待は肉体的な虐待と比べると発覚しにくく、長期化しやすいことが問題視されています。
夫に怒られる自分が悪いと思い込み、離婚まで時間がかかる女性も少なくありません。
暴力や異性関係
4位は「暴力を振るう」という理由です。
夫からの暴力に耐えられなくなり、離婚を決める女性もいます。肉体的なDVがこれに該当し、暴力の内容や証拠の有無によって離婚までにかかる時間や慰謝料の額などが変動します。
5位は「異性関係」です。
夫の不倫が原因で離婚を決めた場合、証拠や不倫相手との交渉などが必要になります。
そのため、なかなか離婚の話が進まずに時間が経ってしまうケースも少なくないようです。
不倫が原因で離婚をする場合は、事前準備が非常に重要になるでしょう。
そのほかに、6位は「浪費する」、7位は「家庭を捨てて省みない」という理由が挙げられます。8位は「性的不調和」、9位は「家族親族と折り合いが悪い」、10位は「酒を飲み過ぎる」という理由です。
なお、司法統計に出ている結果は、あくまでも離婚調停などの申し立てを家庭裁判所に行ったケースのみが対象となっています。
関連記事|離婚原因とは何か?離婚手続きを弁護士が分かりやすく解説


性格の不一致は離婚原因とならない
これまで見てきたように、男女共に性格の不一致が離婚原因の一位となっていました。
しかし、性格の不一致は、直ちには離婚原因にはなりません。法的に性格の不一致が法律上の離婚原因とならない理由を説明します。
離婚原因とは何か?
離婚原因とは、裁判所が離婚をしたくない夫婦の一方に対して、離婚を命じることを正当化する理由を言います。
民法770条1項に、5つの離婚原因が規定されています。
民法第770条【裁判上の離婚】
①夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
離婚原因の1号から4号には該当しない
性格の不一致は、770条一項の1号から4号には当てはまりません。
1号から4号は具体的な離婚原因が規定されていますが、いずれも性格の不一致とは言えません。
婚姻を継続し難い重大な事由
では、5号の『その他婚姻を継難い重大な事由』といえるか。
この婚姻関係を継続し難い重大な事由とは、不貞行為や悪意の遺棄に匹敵するような重大な事由であることが必要です。
離婚原因の有無については、相手方が認めている場合は別ですが、そうではない場合には、その離婚原因があることを主張する側で証明しなければなりません。
しかし、性格の不一致は、夫婦間の主観的な事情であり、不貞行為や悪意の遺棄のように外形的に分かるような事情ではありません。
つまり、性格が合う合わないを判断するための一般的な基準が存在しないため、第三者である裁判官が夫婦間の性格が合わないかどうかを判断することは非常に難しいのが現実です。
そのため、相手方が離婚に反対する立場の場合には、性格の不一致が離婚原因となることは非常に困難と言うほかありません。
不貞やDV等の離婚原因がないことが重要
離婚を回避するためには、不貞行為やDVなどの離婚原因が存在していないことがポイントです。
不貞行為や度重なる暴力は、夫婦関係を修復できない程に破壊する問題行為です。離婚を切り出された際に、いくら適切な対応ができたとしても、既に婚姻関係が破たんしているのであれば、離婚の回避は困難となります。
離婚を切り出された時の対応方法5つ

突然夫もしくは妻から離婚を切り出されたとき、離婚をしたくない場合はどのように行動したら良いのでしょうか。
行動次第では離婚を回避できる可能性もあるため、あらかじめ取るべき行動や避けるべき行動を把握しておくことが大切です。
離婚を求められたとしても、感情的にならずに冷静な対応が大切です。
まず「離婚を回避したい場合に取るべき行動」です。要点は以下の5つが挙げられます。
離婚を回避するための行動・ポイント
- 冷静になること
- 相手方の主張に耳を傾けること
- 率直な気持ちを伝える
- 離婚届の不受理申出をしておくこと
- 子供との交流を続ける
冷静になること
1つ目は「冷静になること」です。突然離婚を突きつけられると、どうしても焦ってしまうものです。しかし、感情的になってしまうと、和解が遠のいてしまいます。感情的にならないよう注意し、冷静に相手の話に耳を傾けるようにしましょう。
傾聴(耳を傾ける)
2つ目は「相手方の主張に耳を傾けること」です。離婚を求める配偶者に対して、持論をぶつけて議論をしても離婚は回避できません。相手方の主張に耳を傾け、離婚したい原因を探り、その原因を解消できるように最大限努力することが重要です。
気持ちを伝える
3つ目は、「率直な気持ちを伝えること」です。婚姻期間が長くなれば、夫婦関係がマンネリ化してしまい、相手方に対して抱いている愛情や感情を素直に伝える機会が少なくなりがちです。あなたの率直な気持ちが分からず、不安に感じ、離婚をしたいと感じてしまっていることもあるかもしれません。あなたの素直な気持ちを相手方に対して伝えることも大切です。気持ちの押し付けにならないよう、自筆の手紙を作成して、これを手渡す方法も有効です。
離婚届けの不受理届を出しておく
4つ目「離婚届不受理申出をしておく」ことです。これは相手の一存で離婚届が提出された場合に、受理されないようにするための申出です。申出は市区町村役場で行えます。申出を済ませておくことにより「知らないうちに離婚となった」というトラブルを避けられます。
離婚届は、夫婦2人の署名捺印と証人の署名捺印が必要です。
そのため、離婚を希望しない配偶者が署名捺印しない限り離婚届が受理されることはありません。
ただ、離婚を希望する配偶者が、反対する相手方の署名捺印を無断で行なって、これを提出するということが考えられます。
この場合でも、離婚届は市役所にて受理されますから、予め離婚届の不受理届をしておくことが必要になります。
なお、相手方が無断で離婚届を提出した場合、市役所において、離婚に反対する配偶者の本人確認をすることができないことから、この場合には市役所から本人確認のできなかった配偶者宛に離婚届の受理通知が送付されます。
離婚に反対する配偶者は、この受理通知の受領により離婚届の提出を知ることになります。
この場合には、離婚無効確認の調停や訴訟などの手続を進めることになります。
子供との交流を続ける
夫婦に子供がいる場合には、子供とのやりとりや交流を継続させ、子供との信頼関係を維持しておくことが重要です。「子はかすがい」ということわざがあるように、子供と親の関係が夫婦関係を繋ぎ止めることもあります。ただ、子供や子の監護者の意思に反して、無理やり子供に面会したり、執拗に面会を強く求めると、かえって逆効果となるため、注意が必要です。
離婚回避のために取ってはいけない行動
離婚を切り出されると、気が動転してしまい、感情に任せた無計画な言動を行いがちですが、控えるべきです。
次に、「離婚を回避するために取ってはいけない行動」をチェックしていきましょう。要点には、以下の3つが挙げられます。
離婚回避のために取ってはいけないの行動
- 相手にすがりつくこと
- 別居すること
- 相手を無理に説得すること
相手に依存する
1つ目は「相手にすがりつく」ことです。離婚の決意が固まっている相手にすがりついても、重荷となるだけです。
やみくもにすがる行為は避け、冷静に解決策を探るよう努めましょう。冷静になれない場合は、話し合いを延期することも一つの方法です。
勢いで別居する
2つ目は「別居する」ことです。
冷却期間として、別居という選択をする夫婦もいます。ところが、別居期間が長くなると離婚が認められる可能性があるため注意が必要です。
できる限り長期間の別居は避け、じっくり二人で話し合う機会を設けましょう。
無理に説得する
3つ目は「相手を無理に説得する」ことです。弱みを指摘するなどして、離婚を諦めるよう相手を説得する人も少なくありません。
しかし、これは火に油を注ぐ行為といえます。
ののしり合ったり、無理に詰め寄ったりすることは避け、冷静に話し合いを行いましょう。
離婚を回避するための関係修復の方法
夫婦関係を修復したいために離婚したくないとひたすら言い続けても、関係の修復は難しいでしょう。夫婦関係を修復したいのであれば、積極的に関係修復に向けた対応を講じる必要があります。
コミュニケーションの質を高める
夫婦関係が悪化している場合、多くの夫婦が夫婦間のコミュニケーションを疎かにしています。
夫婦関係の修復を図るためには、夫婦間のコミュニケーションの機会を増やし、その上で、コミュニケーションの質を高めることが重要です。ついつい、夫婦間のコミュニケーションでは感情的な対応になり、すぐに口論になりがちです。しかし、このような対応を続けては、夫婦間の溝は一層深まっていきます。
できる限り、相手方の気持ちや意見に耳を傾け、否定ばかりするのではなく、誠実に向き合い、改善できる点を改善できるように努めることが必要です。そして、日常的な些細な出来事から会話の機会を増やしていくように努力してみましょう。
感謝の気持ちを率直に伝える
ついつい配偶者に対する感謝の気持ちを伝えることを忘れがちです。
関係が悪くなると、パートナーの良い部分を見落としがちになります。意識して「ありがとう」の気持ちを伝えることが重要です。たとえば、食事の準備をしてくれた、ゴミを出していたなどの日常の行為に感謝を伝えましょう。感謝の言葉や励ましのメッセージをメモに書いて、見えるところに留めておくことで、関係に温かさを加えられます。
夫婦のスキンシップを増やす
夫婦間のスキンシップを意識的に増やすことも関係修復の対応策となります。
夫婦関係が悪化しているときほど、スキンシップが不足していることが多いです。例えば、手をつなぐ
、抱きしめるなどの小さなスキンシップを積極的に取り組むことが挙げられます。
また、小恥ずかしいかもしれませんが、ハグやキスなどのスキンシップを行い、配偶者に対する愛情を伝えることも必要になるかもしれません。ただ、このようなスキンシップをする場合でも、相手方の心情や心身の状況に向き合いながら、利己的にならず、リラックスした時間帯を選ぶことがポイントです。
カップルとしての「時間」を作る
夫婦になると、結婚前のカップルであった時の時間・機会を忘れがちです。
夫婦だけでデートをする機会を作ってみましょう。映画や食事、散歩など、二人で楽しめる時間を計画してみましょう。また、共通の趣味を持つようにして、新鮮な関係を築くことを試してみましょう。
離婚調停で離婚を回避するためには
夫婦間の協議の末、夫婦関係が修復できれば幸いですが、説得の甲斐なく修復できない場合、離婚調停を申し立てられる可能性があります。
離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員(男女・2人)の仲介を経て離婚問題の解決を目指す手続きです。そのため、離婚調停も離婚協議と同様、夫婦の話し合いの場であることに変わりはなく、離婚を強制されることはありません。
しかし、離婚調停の申立てを受けてもなお、夫婦関係の修復を目指したいのであれば次の点に注意しなければなりません。
婚姻費用はしっかりと支払うこと
離婚調停中、婚姻費用を滞納せず、約定とおりに支払うように心がけます。
婚姻費用とは、別居中の配偶者や子の生活費をいいます。離婚を求める配偶者との信頼関係を構築するためにも、配偶者やその子供の日常生活に支障があってはなりません。婚姻費用の請求のある・なしにかかわらず、婚姻費用については前向きな姿勢が重要です。婚姻費用の滞納があると、配偶者の信頼を失墜させる原因になりかねません。
調停を欠席しない
離婚調停を欠席することは避けなければなりません。特に、離婚調停を無断で欠席するようなことがあると、配偶者の信頼を大きく損ねる原因となります。万一、出席ができない場合には、代理人弁護士を就けるなどして適切に対応するようにします。
調停委員との関係を良好にする
調停手続では、当事者は直接対面することはありません。調停委員を介して意見を述べたり、質問を受けます。そのため、自分自身の意思は、主張書面や調停委員を通じて伝達されますから、調停委員との関係性も良好に保つことは非常に重要です。調停委員が自身に対して抱いている印象・好感度いかんによって、配偶者に対する伝わり方も変わってくる可能性があります。少なくとも調停委員を敵に回すことなく、できるだけ味方でいてもらえるよう誠実に態度を示すことが大切です。
関連記事|離婚調停中にやってはいけないこととは?離婚調停の不利な発言や注意点
陳述書を提出する
調停手続きにおいても、口頭による説明だけでなく主張書面を提出することもあります。さらに、よりストレートに「離婚したくない」強い思いを伝えるために「陳述書」を作成することがあります。
離婚調停における「陳述書」は、離婚調停に至る原因、別居に至る原因、これらに対する思い、改善点・反省点等を記載した文書です。しかし、ツラツラと心情を記載してもまとまりのない文書となり、調停委員や配偶者に思いは伝わりません。読み手の立場に立ち、要点を絞りながら作成することが重要です。
関連記事|離婚調停の陳述書の書き方とは?陳述書の目的・注意点や文例
円満調停を申し立てる
当事者の話し合いによっても、夫婦関係の修復ができないのであれば、第三者に仲裁を求めることを検討します。
そこで、離婚をしたくない配偶者は、夫婦関係の修復を図るために、家庭裁判所に対して円満調停の申立てを行うようにします。
円満調停とは
離婚したくない配偶者が離婚を回避するための裁判手続きの一つとして、「夫婦関係円満調整調停」が挙げられます。
夫婦関係調整調停とは、その名のとおり裁判所の調停制度を利用するものです。
裁判所の調停委員が夫婦の間に入り、夫婦関係を維持・改善するためのアドバイスを行います。これにより、夫婦間で生じている対立を話合いにより解決させ、夫婦関係の修復を図るものです。
数回の調停期日を経ても、結論が出ない場合には、調停は不成立となります。
円満調停のメリット
円満調停は、裁判所の調停委員が仲裁的役割を果たすことで夫婦関係の修復を目指すものです。
調停手続は、直接相手方と面会することはなく、全て調停委員を通じて話をしていきます。
当事者間が直接対峙する必要がありませんので、感情的な対立を回避することができ、冷静な話し合いが期待できます。
また、夫婦関係に関する知識や経験のある調停委員が、当事者から事案や双方の言い分を聞き取った上で、中立的な立場から事案解決に向けたアドバイスをすることがあります。
これにより、当事者間の協議では気が付かなかった視点から事案に向き合えるようになることがあり、夫婦の関係修復に役立つかもしれません。
円満調停のデメリット
円満調停といっても、家庭裁判所の調停委員が夫婦を仲裁して話し合いを促す手続きです。そのため、円満調停には強制力がありません。夫婦間で話し合いによる調整ができなければ、夫婦関係の修復は期待できません。また、調停手続きは多くの人にとって初めての経験となります。初めての経験であるため、かえって話し合いが硬直的になるリスクもあります。
離婚を回避するためには、弁護士に相談を

離婚したくない配偶者が取るべき行動やこれに関する解説をさせていただきました。
離婚を回避するためには、要約すると、離婚を求める配偶者と真摯に向き合い、その配偶者に傾聴した上で、問題点や課題を解決していこうという誠実な態度・努力が求められると思います。
本コラムを参考に、何とか離婚を回避するため、夫婦の信頼関係を再構築するよう努めてください。
弁護士に依頼するメリット
- 離婚回避のために取るべき行動を知ることができる
- 交渉や調停手続等の不慣れな手続を一任でき、負担を軽減できる
- 有利な条件についてアドバイスを受けることができる
当事務所では離婚問題に注力しており、数多くの離婚相談をお受けしています。
初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話、メールによる方法でお受けしています。
早めの対応が肝心ですので、お気軽にお問合せの上ご相談ください。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。
宜しくお願いします。