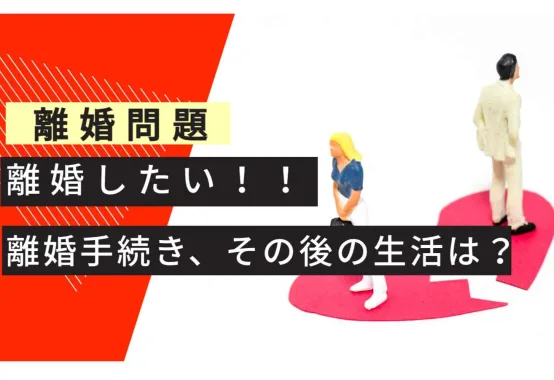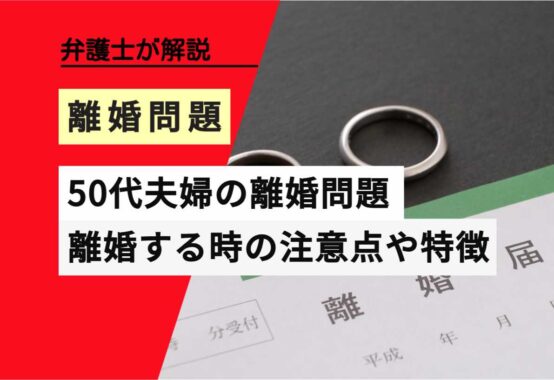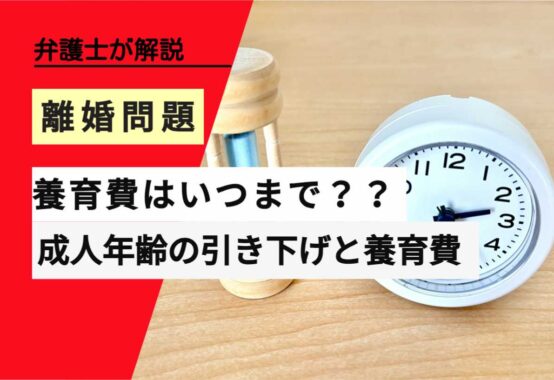離婚を検討している夫婦であれば、聞いたことがあると思う、離婚原因というワード。
男女ともに離婚したい理由の1位は「性格の不一致」です。しかし、性格の不一致では、法律上の離婚原因として不十分と考えられています。
民法では5つの離婚原因が列記されていますが、列記された離婚原因に該当するのか判断を悩ませる事案も多くあります。どのような離婚理由が離婚原因となるのかを本記事を通じて解説していきます。
離婚原因のランキング
夫婦が離婚したいと考える離婚理由は様々です。
離婚したい理由のランキング(参照|婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別 全家庭裁判所)をみると、裁判離婚できる離婚原因に該当する理由もあれば、離婚原因にはなりにくい理由もあります。
ただし、夫婦が離婚に同意するのであれば、離婚したいと思う理由が法律上の離婚原因に当たらなくても、離婚することは可能です。
夫側と妻側が離婚したい離婚理由のランキングをそれぞれ見ていきます。
夫が離婚したい理由のランキング

司法統計によれば、夫が離婚したい理由の1位は「性格の不一致」で、59.6%を占めています。2位の「精神的な虐待」は、モラハラの一種です。3位は、配偶者の不貞行為なども含む「異性関係」です。
上位3位のうち全てが法定の離婚原因に該当するというわけではありません。
また、性格の不一致や性行為に至らない異性関係は離婚原因には該当しにくいです。
精神的な虐待についても、悪質性の高い人格非難であれば、夫婦関係を維持させることのできない離婚原因に該当する可能性はあります。
しかし、これに至らない暴言やモラハラのすべてが法定の離婚原因に当たるものではありません。
妻が離婚したい理由のランキング

妻が離婚したいと思う理由の1位は、夫と同じく、「性格の不一致」でした。2位は「生活費を支払わない」、3位は「精神的な虐待」、4位が「暴力を振るう」、5位が「異性関係」でした。
男性とは異なり、夫による暴力やDVがランキングに入っています。


離婚原因ランキングの具体的な内容
夫婦が離婚したいと考える離婚原因の上位について、その具体的な内容を解説します。
性格の不一致
夫婦の性格の不一致は、夫婦ともに離婚したいと考える離婚理由の1位です。ただ、性格の不一致は、法律上の「離婚原因」にはなりません。
なぜなら、夫婦の性格の不一致は、第三者である裁判官には分かりにくい主観的な事情です。不貞行為やDVといった離婚原因は、写真や資料といった客観的な証拠により証明できますが、性格の不一致は客観的な証拠から説明することが非常に難しいものです。
離婚したいと考える多くの夫婦が「性格の不一致」を抱えていますが、離婚判決を命じることのできる離婚原因にはなりにくいといえます。
精神的な虐待
「精神的な虐待」は夫の離婚理由2位、妻の離婚理由3位となっています。精神的な虐待とは、暴力等の物理的な虐待ではなく、人格非難などの行き過ぎた暴言やモラハラを指します。その他にも、無視をしたり、外出させないといった態度もモラハラの一種になります。
モラハラや言葉の暴力といった精神的虐待についても、そのような被害を受けていたことを事後的に証明することが難しいことも多く、いかにモラハラ等の被害状況を証拠化できるかがポイントになります。
異性関係
夫の離婚したい理由ランキングの3位は、「異性関係」です。妻の離婚したい理由5位にも入っています。配偶者以外の異性と性行為を行う不貞行為が主たる要因ですが、性行為に至らない異性関係も離婚したいと思う理由になっています。異性とデートをしたり、親密なやりとりをするなどです。
不貞行為が離婚原因として規定されていますが、これに至らない異性関係も、夫婦関係を維持できない事情として離婚原因になることもあります。
暴力を振るう
妻の離婚したい理由の4位は、夫の妻に対する暴力です。暴力等のDVは、夫婦関係を継続できない重大な事由として離婚原因となります。
ただ、揉み合いになって転倒するなど、暴力が故意ではない場合や暴力を誘発させるような言動があるような場合など、暴力にも様々な種類があります。全ての暴力が法定の離婚原因となるかというと、そうではありません。
生活費の不払い
妻の離婚したい理由の2位は、「生活費の不払い」です。生活費の不払いが継続的に行われる場合、経済的な虐待として離婚原因になる可能性があります。また、別居後も生活費の支払いをしない場合には、「悪意の遺棄」に該当することもあります。
家族との折り合いが悪い
夫の離婚したい理由4位が「家族との不和」です。
配偶者の親やきょうだいとの折り合いが悪いために、夫婦関係が悪化し離婚に至るケースも多くあります。
しかし、家族との関係が悪いことだけで法定の離婚原因になることは少ないでしょう。なぜなら、あくまでも離婚の問題は夫婦の問題と考えるからです。ただ、家族との不仲が発端になり、夫婦関係が悪くなり、別居したり、DVやモラハラなどを招く場合には、法定の離婚原因を満たすといえるでしょう。
浪費する
夫の離婚したい理由の5位が妻の浪費です。
浪費により経済的に困窮し離婚したいと思うことも多くあります。
しかし、浪費それだけで法定の離婚原因となるわけではありません。浪費や借金により生活を送ることが困難になり、夫婦関係を継続できなくなれば、離婚原因に該当する可能性はあります。
裁判離婚で認められる離婚原因
民法で規定された法定の離婚原因とは、民法770条1項に列記された夫婦関係を破綻させる理由を言います。民法770条1項に定められた離婚原因は次のとおりです。
- 1号 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
- 4号 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき。
- 5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
配偶者が離婚に応じる場合、法定の離婚原因がある必要はありません。そうではなく、離婚に応じない場合には、法定の離婚原因があることが必要となります。先ほど紹介した離婚原因ランキングの中には、法定の離婚原因に当てはまるものもあれば、これに該当しないものもあります。
以下では法定の離婚原因を細かく見ていきます。
1号:不貞行為はどのような行為か
離婚原因の一つ目は、配偶者に不貞な行為があったときです。つまり、不貞行為(浮気・不倫)を離婚原因として定めています。不貞行為とは、自分の意思により、配偶者以外の人と性交を行う行為です。
さらに、性交を行わなかったとしても、これに準じる行為、口腔性交(オーラルセックス)や肛門性交(アナルセックス)も不貞行為に当たると判断される場合があります。仮にこれら性交類似行為が不貞行為に当たらないと判断されたとしても、婚姻を継続し難い重大な事由と判断される可能性はあります。
他方で、キスをしたり、女性の胸を触る行為といった不適切な行為については、不貞行為には当たりません。ただ、これら不適切な行為も、婚姻を継続し難い重大な事由とされる可能性があります。
関連記事|不貞行為とは何か?どこからが不貞行為かを弁護士が解説します
2号:悪意の遺棄とは何か
悪意の遺棄とは、正当な理由もなく、夫婦の同居・協力・扶助義務を果たさないことをいいます。
悪意の遺棄における悪意とは、夫婦関係を破壊しようと意図したり、これを認容するような態度をいいます。
夫婦は相互に、同居し、協力・扶助をする義務を負っています。それにもかかわらず、この同居・協力・扶助義務に違反してこれらを果たさないような状況が続いていることを遺棄といいます。
正当な理由がないこと
上記の遺棄に当たる行為があっても、それに正当な理由がある場合には、悪意の遺棄には当たりません。例えば、単身赴任のように仕事の関係で同居できない場合には、遺棄には該当しません。
ただ、正当な理由があり同居できないとしても、協力扶助義務を負いますから、生活費を送らなければ、悪意の遺棄に該当する可能性があります。
3号:配偶者の生死が3年以上不明であるとき
『3年以上生死不明』は、実務上あまり離婚原因として問題になるケースはありませんので、簡単に解説します。
生死不明とは、生存も死亡も証明できない状態です。配偶者の所在不明が長期間が続いている場合には、生死不明であると推認されます。他方で、連絡が取れないだけで、SNSの更新などがされている場合には、生死不明とは言えません。
4号:回復の見込みがない強度の精神病
強度の精神病とは、夫婦が負っている協力義務を十分に果たされない程の精神障害をいいます。
成年後見を利用しなければならない程度に達している必要はありません。また、身体障害は精神障害ではありませんので、この離婚原因には該当しません。回復の見込みがないとは回復の見込みがないとは、夫婦間の協力義務を果たせる程に回復できる可能性がない場合をいいます。
5号:婚姻関係を継続し難い重大な事由
離婚原因を具体的に定めた1号から4号に該当しないものの、その他の事情により婚姻関係が回復できない程に破綻している場合には、離婚原因となります。
この事情を「婚姻を継続し難い重大な事由」と呼びます。婚姻関係を継続できない重大な事由としては次のものが挙げられます。
- DV(暴力)
- モラハラ
- セックスレス
- 配偶者の犯罪行為や服役
ただ、全ての事由が離婚原因に当てはまるわけではありません。その内容や程度、期間等の具体的な事情に応じて判断されます。
離婚手続きの流れ
離婚手続きは、夫婦の話し合いにより進めていくのが基本です。離婚を成立させる方法や流れを説明します。
離婚協議(話し合い)
まずは、夫婦間で話し合いをします。別居前に話し合いをするのか、別居後に話し合いをするのかはケースバイケースです。円満離婚を目指すのであれば、同居中から離婚協議を進めるのが理想です。しかし、DVやモラハラの気質のある配偶者であれば、速やかに別居をした上で、離婚協議をする方が良いかもしれません。
当事者間での話し合いが進展せず、折り合いが付かない場合には、弁護士に委任をした上で、弁護士を代理人として離婚協議を進めることを検討しましょう。
離婚協議の結果、夫婦間で合意できれば、合意書を作成した上で、離婚届けを提出します。
離婚調停の申立をする
離婚協議が進まない場合には、離婚調停の申立てをします。調停手続きは、裁判所が仲裁をして、夫婦間の話し合いを行い、離婚の成立を目指すプロセスです。
調停期日では、当事者双方が入れ替わりで調停室に入室し、調停委員から聞き取りを受けます。入れ替わりで入室するため、相手方と顔を合わせることは原則としてありません。
調停手続きは、平均して3回から5回程実施されます。調停手続の結果、離婚条件について合意ができれば調停が成立します。
関連記事|離婚調停中にやってはいけないこととは?離婚調停の不利な発言や注意点
訴訟提起をする(離婚裁判)
調停が不成立となれば、家庭裁判所に対して離婚訴訟を提起することになります。訴訟手続きでは、双方が、準備書面と証拠を提出することで、審理を進めていきます。当事者による主張・立証が尽くされれば、証人尋問(当事者尋問)を行い、最終的な判断(判決)が出されます。
ただ、証人尋問を行う前に裁判官から和解の提案がなされるのが大半です。和解により夫婦が合意できれば、裁判上の和解により離婚が成立します。判決が出される場合には、2週間以内に控訴しなければ判決が確定しますので、離婚が成立します。
関連記事|離婚裁判の期間と流れ|長期化する原因や早期解決のポイント
離婚問題は弁護士に相談しよう

離婚原因は様々なものがあります。主観的に離婚原因であると思っても、裁判上離婚原因とならないことはよくあります。また、離婚原因になったとしても、これを裏付ける客観的な証拠がなければ意味がありません。そのため、離婚原因を主張するとしても、計画的にその証拠を収集する必要があります。
離婚原因についてお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。お気軽にご相談ください。
対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。