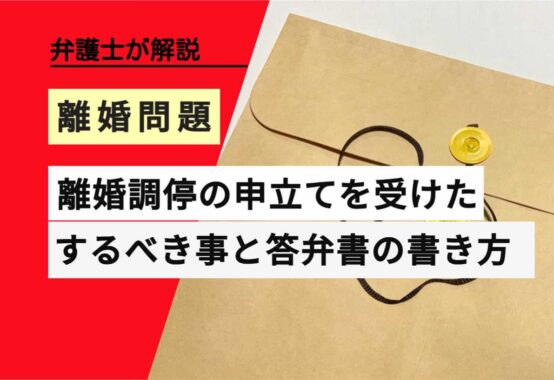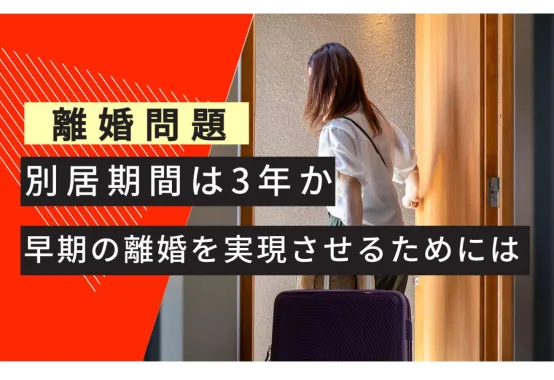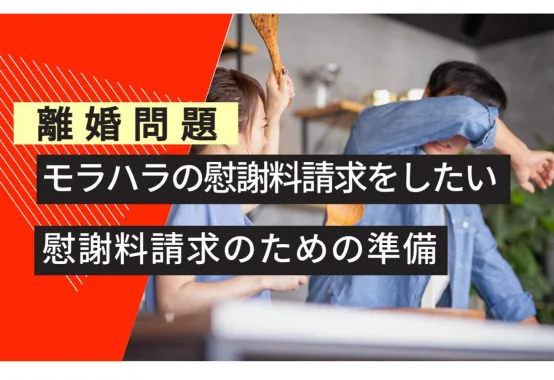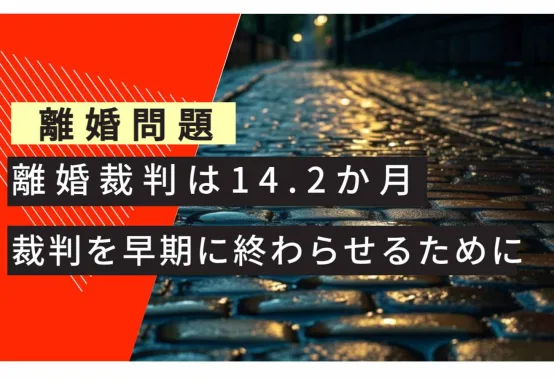離婚調停の期間は、最短で申立てをしてから半年、平均的には1年前後の時間は必要となります。
調停期日を1回や2回ほど実施して半年以内で調停離婚が成立するケースもありますが、協議するべき事項が多ければ、半年を超えて調停手続きを行うことも非常に多いです。長期化する事案では、2年を超えて調停手続を行うこともあります。
離婚調停を速やかに終結させるために、自身の利益を確保しつつ譲るべき事項は譲ることが大事です。
ただ、最短で離婚調停を成立させることを優先するあまり、離婚条件を必要以上に譲歩することはおすすめしません。離婚調停には強制力があり、一度合意すると基本的に撤回できないからです。
今回のコラムでは、離婚調停の成立するまでの期間と離婚調停の流れについて解説していきます。
離婚調停の日数は6か月から1年
離婚協議が難航した場合に行う手続きが離婚調停です。司法統計によれば離婚調停を含めた婚姻関係の調停手続き(審判含む)は、6か月から1年が平均的です。

調停手続きの回数
手続きが行われる回数については、1回~3回で解決する割合は50.84%、4回~10回で解決する割合は39.49%、11回~20回で解決する割合は2%、21回以上の割合は1%を下回ります。
離婚調停がなぜ長期化するのか
離婚調停が長期化する大きな原因は、夫婦間での対立が強く、互いに離婚条件を一歩も譲らない強硬な姿勢を固持することにあります。
離婚調停が成立するまでに1年以上の期間を要することは全体の30%ほどになっています。1回から3回で終結している中には調停離婚が成立せずに不成立となりケースも多く含まれていると思われます。そのため、全体のうち離婚調停が成立するまでに1年以上の長期間を要する割合はさらに多くなると推測されます。
離婚調停が長期化する理由は様々考えられますが、次の理由が挙げられます。
| TIPS!調停が長期化する理由 ✓ 離婚条件で強く対立し、一切譲歩しようとしない ✓ 細かい条件面にまで強く拘る ✓ 調停手続きの進行が遅い |
離婚条件の強い対立
特に離婚条件の対立が強い場合には、互いに条件面の歩み寄りをしようとしなかったり、微細な条件にまで拘る傾向が強いです。そこで、対立する離婚条件の種類やその理由を以下で解説します。
離婚原因で対立する
長期化する理由の一つで、離婚原因の有無です。離婚原因のある・なしで対立したり、離婚原因がないために相手方が離婚に応じない場合です。離婚原因がないために、相手方との離婚条件の協議がなかなか進展せずに長期化することがあります。特に、離婚を求める配偶者が不倫やDV等の有責行為を行っている場合(有責配偶者)には、離婚条件の交渉はかなりハードになります。
慰謝料で対立する
配偶者が不貞行為やDV、モラハラといった有責行為に及んでいる場合、慰謝料請求を調停手続きで行うことがあります。しかし、この有責行為の「ある・なし」や慰謝料額について対立が生じ、調停手続きが進展しないことがあります。
財産分与で対立する
財産分与が対立することも非常に多いです。特に互いの共有財産の「ある・なし」、特有財産の「ある・なし」、自宅不動産の評価額について激しく対立することもよくあります。
関連記事|贈与や遺産は財産分与の対象となるのか?財産分与の対象財産を弁護士が解説します
親権や面会交流で対立する
子供のいる夫婦の場合、子の親権や養育費、面会交流を理由に激しく対立することがあります。親権問題や面会交流の問題が調停手続きで争われる場合、家庭裁判所の調査官による調査や裁判所内の試行面会を行われることもあります。この場合には、通常よりも時間を要してしまいます。
細かい条件に固執する
細かい条件に執拗にこだわり、一向に譲らない場合にも調停手続きを長期化させます。
心情的な対立が強い場合には、離婚条件そのものとの関連性の薄い、細かい事情で対立が生じてしまいがちです。
調停手続きが遅い

調停手続きそのものが、ゆっくり進むプロセスであるため、長期化してしまいます。
そもそも、調停の申立てをしてから、第1回目の調停期日まで1か月半から2か月程の期間を要します。第2回目の調停期日以降も、2か月前後に一度のペースで進行します。その上、調停期日当日の時間にも限りがあるため、申立人と相手方に割かれる時間は1時間もありません。
このように調停手続きの進行具合が迅速とまでは言えないことが長期化となる理由となっています。
大阪家庭裁判所の調停時間
午前の部 10:00~11:20
午後の部① 13:20~14:40
午後の部② 15:00~16:20

離婚調停を最短で解決するためには
離婚調停を最短で解決するためには、離婚条件の譲歩・資料の迅速な収集・主張書面の早期の提出が必要となります。
✓ 離婚条件の譲歩
✓ 資料の迅速な収集と提出
✓ 主張書面を早期に提出する
離婚条件を譲歩する
離婚調停を早期に成立させるためには、離婚条件の一定程度の譲歩が必須です。
調停手続きは、当事者の双方が調停委員を介して話し合いを進めて合意をするプロセスです。そのため、当事者双方に譲歩をすることが調停成立の前提となっています。
調停手続きを早期に解決したいがために、重要な条件についてまで大幅に譲歩しすぎることは控えるべきです。重要となる条件については強く主張しつつ、訴訟手続きに移行した場合の見通しや調停不成立となった場合の不利益の程度を十分に踏まえながら、離婚条件の譲歩をするようにします。
資料の迅速な収集と提出
必要となる資料を速やかに確保して早めに裁判所に提出します。
調停手続きにおいて、必要となる資料は様々です。財産分与であれば財産関係の資料(通帳、保険証券、登記簿謄本等)、婚姻費用や養育費であれば収入資料(給与明細、源泉徴収票、申告書)、慰謝料請求をしている場合には、不貞行為やDV等の裏付け資料などが挙げられます。
これらをできるだけ速やかに収集し、必要な限りで裁判所に提出するようにします。
主張書面を早期に提出する
主張書面を期限に後れることなく速やかに提出します。
調停期日当日の時間は限られています。そのため、離婚条件や離婚原因に関する言い分を述べる十分な時間を確保できません。また、口頭だけでは言い分を的確に伝えることができません。
そこで、調停委員から主張書面の提出を指示されることがあります。そのため、指定される提出期限までに、漏れの無いように主張を整理した上で主張書面を作成し、これを提出することが重要です。


離婚調停の申立てから成立までの流れ
離婚協議により離婚が成立しない場合には、離婚調停の申立てをせざるを得ません。早期に解決するために知っておくべき調停手続きの基礎を解説します。
申立ての準備
申立てにあたり、様々な必要な書類がありますから、以下の資料を収集、作成していきます。
申立書、事情説明書、進行連絡メモ等については、申立てをする裁判所のWebサイトに書式が掲載されていますので、こちらを利用して必要事項を記入します。
なお、申立てをする裁判所によって書式や提出書類の種類が異なりますので注意が必要です。
申立時に準備する資料
- 申立書2通と控え1通
- 事情説明書1通
- 送達場所の届出書
- 進行連絡メモ
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)1通(3ヶ月以内に発行されたもの)
- 収入印紙 1200円分
- 郵便切手 1130円分(140円×1,84円×5,50円×5,20円×10,10円×10,1円×20)
- 年金分割のための情報通知書(発行日から 1 年以内のもの)
申立てをする裁判所
離婚調停の申立てをする裁判所は、申立てをする人の住所や本籍地ではなく、相手方の住所を管轄する家庭裁判所になります。
そのため、申立てをする人が大阪市、相手方が東京都であれば、大阪家庭裁判所ではなく東京の家庭裁判所となるので、注意が必要です。
申立てを行う
先程紹介しました書類の準備ができたら、管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
その際には、郵便切手や印紙も同封します。不足書類があれば、家庭裁判所から不足書類の追完を依頼されます。
一回目の日程調整
申立てを行い、不足書類がなければ、家庭裁判所の裁判所書記官から申立てをした人に対して連絡が入り、第一回目の調停を行う実施期日(調停期日)の調整を行います。
通常は申立てをした日から1か月半から2ヶ月前後の日程で調整されます。
相手方に書類が送付される
一回目の調停期日が決まれば、申立時に提出した申立書が家庭裁判所から相手方に送達されます。その際に、一回目の調停期日の案内も相手方に対して行われます。


第1回目の調停期日当日の流れ
受付をしてから終了するまでの第1回目の調停期日の具体的な流れを説明します。
受付をする
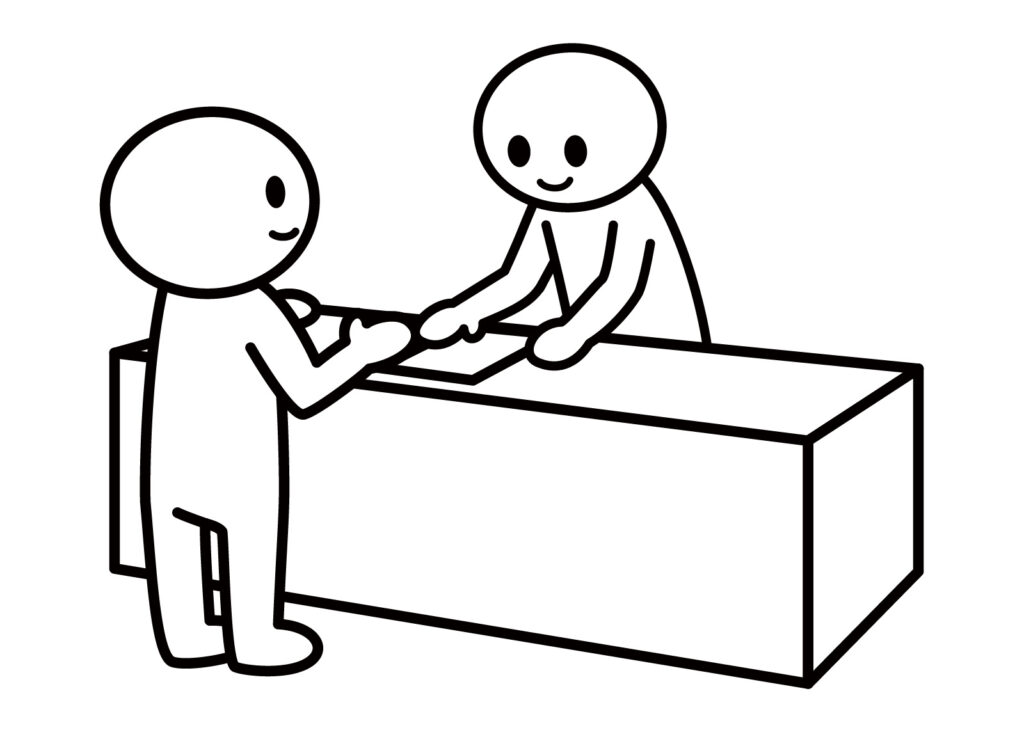
申立人は、家庭裁判所と調整した第一回目の調停期日に、家庭裁判所に出向きます。
家庭裁判所の調停係の窓口にて、調停事件が係属している裁判所の部や係、調停事件の事件番号を伝えます。
係属部や係、事件番号は、家庭裁判所から返送された申立書の控えに記載されています。あるいは、初回期日の日程調整の際に、書記官から口頭で伝えられます。
なお、相手方は、当事者の鉢合わせを防ぐため、申立人の指定時間よりも20分から30分ほど先の時間を指定されています。
待合室に行く
受付を終えると、窓口の職員から、待合室が書かれた用紙あるいはカードが交付されます。これを受けて指定された待合室に向かいます。
待合室は、申立人あるいは相手方専用の待合室になりますので、相手方と同じ部屋になることはありません。
調停室に向かう
待合室で待機していると、調停委員が待合室まで来て、申立人の氏名あるいはその番号で呼びますので、これを受けて、調停室に向かいます。
調停室に入室する
調停室には、調停委員2名(男女)が在室します。相手方が調停室において同室することは、ありません。
ただし、調停が成立する場合には、相手方が同室します。
本人確認と手続の説明
申立人は調停委員から、運転免許証等の身分証明の提示を求められ、本人確認を行います。本人確認ができれば、調停委員から調停手続の概要の説明を受けます。
なお、裁判所内では、写真撮影や録音・録画は禁止されていますので、これら行為は控えましょう。
申立ての経緯等の聴き取り

調停委員から、申立てをするに至った経緯や申立人が考えている離婚やその離婚条件に関する主張を聴き取りされます。時間としては、10分から30分程になります。
聴き取りが概ね終われば、調停室から退室し、待合室に戻ります。
相手方の入室
相手方も、申立人と同様に受付をした上で、申立人の聴き取りが終えて、申立人が待合室に戻ったことの確認ができ次第、調停室に入室し、同様の流れで聴き取り等を行います。
相手方においても、時間としては10分から30分程になります。
申立人の再入室
相手方の聴き取りが終われば、調停委員による声掛けを受けて、申立人が再度調停室に入室します。この時に、相手方の離婚に関する考えや申立人の主張に対する見解の概要を伝えられます。
これを受けて、申立人は、相手方の言い分に対する考えを述べます。
相手方の再入室
申立人の退室後、相手方に再度入室してもらいます。同様に、申立人の言い分を伝えた上で、時間の許す限りで、相手方から言い分を聞き取ります。
時間が無くなれば、次回期日までに何らかの主張反論をしてもらうことになります。
次回期日に向けた宿題と期日調整
調停委員は、申立人と相手方からの聴き取りを通じて、争点となる問題を把握します。その上で、争点に関する事項について、次回期日に向けて、必要な書類や主張書面の準備をそれぞれに対して指示します。
これと一緒に、次回期日の調整が行われます。申立人・相手方・調停委員2名・裁判所のスケジュールを踏まえて次回期日が調整されます。
そのため、次回期日は、通常1ヶ月半から2ヶ月先の日程で指定されます。ただ、お盆休みや年末年始といった長期休暇が間に挟まると、次回期日は2ヶ月半から3ヶ月先に指定されることもあります。
第2回目の期日までに指示された準備を行う
書類や主張書面の提出は、指定された調停期日の10日前から1週間ほど前までに提出するよう求められます。
そのため、できるだけ早い時期から、書類の収集や書面の作成を着手するようにします。
第2回目期日当日
初回期日と同様、指定された時間に裁判所内で受付を行います。初回期日と同じ要領で調停室に入室します。
相手方から書類や主張書面が提出されている場合には、調停委員から提出書類に対するコメントを求められます。
必要であれば、次回期日までに反論書面や証拠の提出が求められます。初回期日と同じ要領で双方が入れ替わりで言い分を述べていきます。
調停期日を通じて把握された新たな争点や絞られた争点に関して、調停委員から当事者の一方あるいは双方に対して、次回期日に向けた準備を指示されます。その上で、次回期日の調整が行われます。
第3回期日以降
これまで同様に、次回期日までに証拠や主張書面を準備し、調停期日当日に、提出された書類等を踏まえた、双方からの聴き取りを行います。
調停条項案の作成
複数回の調停期日を通じて、争点となっている問題が解消されると、調停の成立に向けて、調停条項案を作成します。
調停条項とは、双方で合意できた事項を列記した、調停手続における和解内容のことです。
家庭裁判所において、調停条項の大枠を提示されることはありますが、細かい文言や特殊な条件については、これらを希望する当事者から明確に提示することが必要となります。
調停の成立

調停条項案の話し合いを行い、双方がその内容に異存なければ、調停を成立させます。
調停を成立させる場合、調停室に、調停委員2名、裁判官、裁判所書記官に加えて、申立人と相手方が同室します。
この場合には、当事者が対面しますので注意が必要です。
そして、裁判官が合意できた調停条項の内容を全て読み上げることで調停が成立します。
例外的に当事者の同室が難しい場合には、申立人と相手方の入れ替わりで調停条項の読み上げを実施してもらえることはあります。
調停不成立と離婚訴訟
調停期日を経ても、離婚条件について折り合えない場合には、調停は不成立となります。この場合、自動的に訴訟手続に移行することはありません。
別途で離婚を求める当事者が離婚訴訟を提起することが必要です。
なお、離婚訴訟の場合、調停手続と異なり、相手方の住所だけでなく訴訟を提起する原告の住所地を管轄する家庭裁判所も管轄裁判所となります。
▶離婚調停に関する裁判所の解説はこちら
調停離婚成立後の手続き
離婚調停が成立すると、法律上夫婦は離婚となります。しかし、調停離婚が成立しても、直ちに戸籍に離婚の事実が反映されるわけではありません。戸籍に離婚の事実を記載するために、夫の戸籍に入籍している妻が、離婚届と調停調書を市役所に提出する必要があります。本籍地では市役所に提出する場合には、戸籍謄本も必要となるため注意が必要です。
10日以内に届け出る必要がある
調停離婚の成立した日から10日以内に離婚届と調停調書を市役所に届け出る必要があり、10日を過ぎると、3万円以下の過料を科される可能性があります。土日も含めての「10日」の期間制限です。その上、調停調書が家庭裁判所から送達されるまでに、3日前後の期間を要します。そのため、かなりタイトなスケジュールの下で離婚届を提出することが必要となります。
なお、離婚届には、相手方の署名捺印は要しません。一人で市役所に出向き離婚届と調停調書を提出されば足ります。
離婚調停の問題は弁護士に相談しよう

離婚調停には、解説しましたように1年以上の期間を要することが多いです。
その期間、代理人を就けなければ、お一人で調停手続に向き合い続けなければならず、精神的な負担が大きくなることも多いです。離婚調停をされる際には一度弁護士に相談されることをおすすめします。
まずはお気軽にご相談ください。
初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。お気軽にご相談ください。
対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。