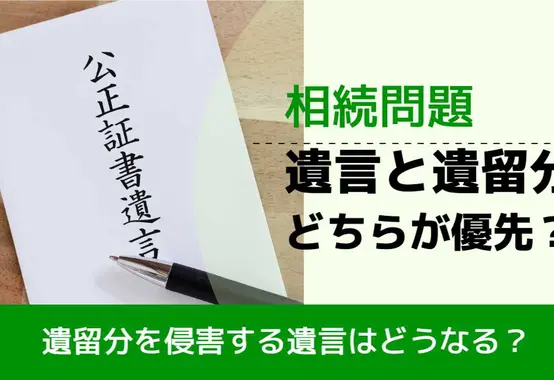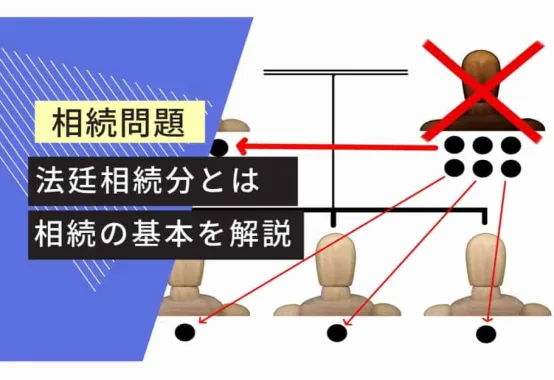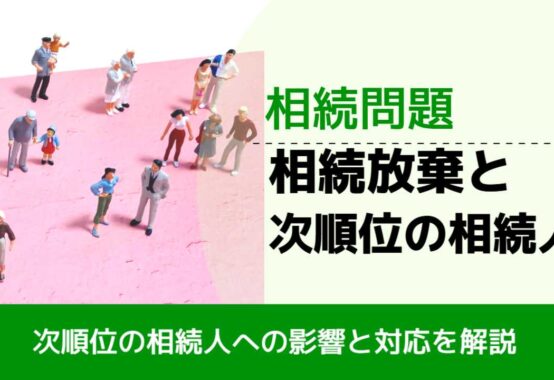遺産相続が発生した際、相続人全員で遺産分割について話し合う必要があります。その結果をまとめたものが遺産分割協議書です。「遺産分割協議書」は、相続手続きを進める上で非常に重要な書類ですが、相続人全員の合意のもと作成する必要があり、不備があると手続きが滞ってしまうことも珍しくありません。
そこで、この記事では、遺産分割協議書の作成方法から、ひな形、そして円満に協議を進めるためのポイントまで、わかりやすく解説していきます。
一人が遺産を全て相続する場合でも遺産分割協議書は必要?
複数の相続人がおり、そのうちの一人が全ての遺産を相続する場合でも、原則として遺産分割協議書が必要です。
以下では、相続人の一人が全部を相続する場合でも遺産分割協議書が必要な理由を説明します。
理由1:不動産の名義変更や預金解約などの手続きに必須
不動産を相続する際には、法務局での名義変更(相続登記)手続きが必須です。この手続きには、相続人全員の合意を証明する書類である「遺産分割協議書」の提出が不可欠となります。特に、法定相続分とは異なる割合で遺産を分ける場合、例えば、特定の相続人一人が不動産をすべて取得するようなケースでも、その合意内容を第三者に客観的に示すため、遺産分割協議書が必須となります。
また、預貯金の解約や名義変更を行う際にも、金融機関から遺産分割協議書の提出を求められるのが一般的です。相続人全員の合意内容が書面で明確に示されていない場合、金融機関における相続手続きを進めることができません。
このように、遺産分割協議書は、不動産や預貯金といった主要な相続財産に関する手続きを円滑に進める上で、事実上欠かせない書類となります。
理由2:相続人全員の合意を証明し、将来のトラブルを防ぐため
遺産相続は時に「争族」とも呼ばれるほど、親族間でトラブルに発展しやすいものです。口約束で遺産分割の合意がなされても、後になって「言った・言わない」の水掛け論に発展したり、感情的な理由から合意内容を覆そうとされたりするリスクは、決して低くありません。
このような不必要な紛争を避けるためには、遺産分割協議書の作成が不可欠です。この書面は、相続人全員が遺産分割について合意したことを示す、法的な効力を持つ文書です。全ての相続人が署名し、実印を押すことで、その合意は確定的なものとして客観的に証明され、後々のトラブルを未然に防ぐ強力な証拠となります。
一度作成された遺産分割協議書の内容は、原則として撤回できません。たとえ後から新たな財産が見つかったり、他の相続人の経済状況に変化が生じたりした場合でも、安易に合意をやり直すことは認められません。そのため、安心して手続きを進めることが可能です。これにより、将来的な不安を軽減し、円満な相続を実現できます。


遺産を一人が全て相続するための5つのステップ
一人が全ての遺産を相続する際も、適切に手順を踏む必要があります。
遺産分割に必要となるステップを順番に、そして正確に行うことが、後々のトラブルを防ぎ、円満な相続を実現する鍵となるでしょう。
STEP1:誰が相続人になるのかを確定させる(相続人調査)
遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要があります。もし一人でも欠けた状態で協議を進めてしまうと、その協議は法的に無効となり、後々の大きなトラブルにつながる可能性があります。そのため、遺産分割の手続きにおいて、最初に相続人が誰であるかを正確に確定させる「相続人調査」は、最も重要なステップの一つです。
相続人調査を具体的に進めるには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)を取得する必要があります。また、相続人の現在戸籍も取り付けします。
これらの戸籍謄本は、被相続人や相続人の本籍地の市区町村役場で取得できるほか、遠方の場合は郵送で取り寄せることも可能です。
| 順位 | 相続人の種類 | 備考 |
| 常に相続人 | 配偶者 | 血族相続人と常に一緒に相続します。 |
| 第1順位 | 子 | 子が亡くなっている場合は孫などの直系卑属が代襲相続します。 |
| 第2順位 | 直系尊属 | 父母、祖父母など。子がいない場合に相続人となります。 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 子も直系尊属もいない場合に相続人となります。 |
STEP2:相続する財産の内容をすべて洗い出す(遺産調査)
相続人調査の次は、被相続人の財産を正確に把握する「遺産調査」が非常に重要です。この調査を怠ると、遺産分割協議が適切に進まないだけでなく、相続税の申告漏れや、相続人同士の新たなトラブルにつながる可能性があります。すべての遺産を正確に把握することが、円満な相続手続きの基礎となります。
調査対象となる財産は、不動産や預貯金、株式などの「プラスの財産」だけではありません。借金や住宅ローン、未払金といった「マイナスの財産(相続債務)」も含まれます。これらのすべてを洗い出すことで、相続財産の全体像を正確に把握できます。
調査によって判明したプラスとマイナスの財産は、すべて「遺産目録」として一覧にまとめましょう。遺産目録を作成することで、相続人全員が遺産の全体像を容易に共有できるようになり、透明性の高い遺産分割協議につながります。
STEP3:相続人全員で話し合い、合意を得る(遺産分割協議)
相続人調査と財産調査が完了したら、いよいよ「遺産分割協議」へ進みます。この協議には、法定相続人全員が参加し、遺産の分け方について話し合い、全員の合意を得ることが必須です。相続人のうち一人でも欠けた状態で協議を進めた場合、その合意は法的に無効となる恐れがあります。
特に、一人が全ての遺産を相続するケースでは、他の相続人への丁寧な説明と理解を促すことが不可欠です。特定の相続人が全遺産を相続する理由や背景を具体的に伝え、納得を得るプロセスは重要です。遺産相続は、時に「争族」と表現されるほどトラブルに発展しやすいものです。感情的にならず、各相続人の主張を冷静に聞き入れ、円滑な解決を目指しましょう。
遺産分割協議の話し合い方法には、いくつか選択肢があります。全員が一同に会して話し合う方法もありますが、この対面の方法に限られません。電話、メール、書面でのやり取りにより合意形成する方法も認められます。
全員の合意が形成されたら、その合意内容を法的に有効な書面として残すべく、次のステップである「遺産分割協議書の作成」へと進みます。
STEP4:合意内容をもとに遺産分割協議書を作成する
STEP3で相続人全員が「一人が全ての遺産を相続する」という合意に至った場合、その内容を法的に有効な「遺産分割協議書」として書面にまとめます。
口頭による合意でも有効とされることがありますが、不動産の名義変更や預貯金の解約といった相続手続きを行う際には、必ず遺産分割協議書の提出が求められます。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を明確に証明する重要な書類です。作成にあたっては、相続人全員の署名と実印による押印に加えて、各自の印鑑証明書の添付をすることが必要です。
STEP5:作成した協議書を使って名義変更などの手続きを行う
遺産分割協議書が完成したら、いよいよ各財産の名義変更や解約といった具体的な「相続手続き」に進みます。この最終ステップでは、作成した遺産分割協議書が、それぞれの財産を相続人へ承継させるための重要な書類となります。
不動産を相続する場合は、法務局で相続登記(名義変更)の手続きを行います。2024年4月1日からは相続登記が義務化されており、3年以内に登記をしないと10万円以下の過料が科される可能性があるため、速やかな手続きが求められます。
預貯金の場合は、各金融機関で口座の解約や名義変更の手続きを行います。こちらも、遺産分割協議書に加え、金融機関所定の書類など、複数の提出書類が必要です。
これらの手続きは提出先によって必要書類が異なる場合があります。そのため、事前に各機関へ確認することが大切です。
また、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内という相続税の申告期限も意識し、余裕を持って手続きを進めるようにしましょう。
【テンプレートあり】一人が全て相続する遺産分割協議書の書き方
以下では、一人が全ての遺産を相続する際の遺産分割協議書について、その具体的な作成方法を詳しく解説します。
遺産分割協議書に記載すべき9つの項目
遺産分割協議書に法的な書式は定められていませんが、法的な効力を持ち、その後の手続きを円滑に進めるためには、9つの必須項目を記載する必要があります。これらの項目に不備があると、不動産の名義変更や預貯金の解約などの手続きが滞る原因となる可能性があります。
遺産分割協議書に記載すべき項目は、以下の通りです。
1. 被相続人の情報: 氏名、最後の住所、死亡年月日を正確に記載します。
2. 相続人全員の表示: 全相続人の氏名、住所、生年月日、被相続人との続柄を明記します。
3. 協議で合意した旨の文言: 遺産分割協議が成立したことを示す文言を記載します。
4. 誰がどの財産を相続するかの記載: 例えば、「相続人〇〇が被相続人の全ての遺産を取得する」といった具体的な内容を明確に記載します。財産は特定し、漏れがないようにしましょう。
5. 財産リストにない財産の扱い: 後日、新たな財産が発見された場合の取り扱いについても明記しておくことが重要です。例えば、「本協議書に記載のない財産が後日判明したときも、全て相続人〇〇が相続する」といった文言を記載すると良いでしょう。
6. 清算条項: 相続人間に金銭の精算がある場合に、その内容を記載します。
7. 協議成立年月日: 遺産分割協議が成立した日付を記入します。
8. 相続人全員の署名: 相続人全員が自筆で署名します。
9. 実印の押印: 相続人全員が実印を押印します。実印と印鑑証明書が揃わなければ協議書が無効となるため、この項目は特に重要です。
これらの項目を適切に記載することで、遺産分割協議書は法的に有効な書類として機能します。
遺産分割協議書(*パターン①)
(被相続人の表示)
被相続人 甲山 太郎
生年月日 昭和12年3月4日生
本 籍 大阪府大阪市中央区○○町○○番地
相続開始日 令和●年○○月○○日
上記被相続人(以下「被相続人」という。)の相続人である甲山次郎(昭和○○年●月●日生、以下「甲」という。)及び甲山三郎(昭和○○年●月●日生、以下「乙」という。)は、被相続人の遺産につき、遺産分割協議を行い、本日、次のとおり合意した。
第1条 甲は、別紙遺産目録記載の被相続人の遺産全てを取得する。
第2条 別紙遺産目録記載の相続財産以外に、新たな相続財産が発見された場合には、甲が全ての相続財産を相続する。
第3条 甲及び乙は、本協議書に定めるほか、何ら債権債務の存しないことを相互に確認する。
以上の遺産分割協議の合意を証するため、本書2通を作成し、各自1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
甲(住 所)
(氏 名) ㊞
乙(住 所)
(氏 名) ㊞
遺産分割協議書(パターン②)
(被相続人の表示)
被相続人 甲山 太郎
生年月日 昭和12年3月4日生
本 籍 大阪府大阪市中央区○○町○○番地
相続開始日 令和●年○○月○○日
上記被相続人(以下「被相続人」という。)の相続人である甲山次郎(昭和○○年●月●日生、以下「甲」という。)及び甲山三郎(昭和○○年●月●日生、以下「乙」という。)は、被相続人の遺産につき、遺産分割協議を行い、本日、次のとおり合意した。
第1条 甲は、下記の相続財産を相続する。
1 不動産
⑴ 土地
所在:大阪府○○市○○区〇丁目
地番:○○番○○
地目:宅地
地籍:○○㎡
⑵ 建物
所在:大阪府○○市○○区〇丁目
家屋番号:○番○
種類:居宅
構造:
床面積:
2 預貯金
⑴ 〇〇銀行通常貯金
記号番号〇〇〇〇〇―〇〇〇〇〇〇〇
⑵ 〇〇銀行〇〇支店普通預金
口座番号〇〇〇〇〇〇〇
3 その他の財産
本条1項及び2項記載の相続財産以外の一切の財産
第2条 甲及び乙は、本協議書に定めるほか、何ら債権債務の存しないことを相互に確認する。
以上の遺産分割協議の合意を証するため、本書2通を作成し、各自1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
甲(住 所)
(氏 名) ㊞
乙(住 所)
(氏 名) ㊞
財産(不動産・預貯金など)の正しい記載方法
遺産分割協議書に財産を記載する際は、法務局や金融機関といった第三者が客観的にその財産を特定できるよう、正確に記述することが非常に重要です。曖昧な表現や記載漏れがあると、手続きが滞ったり、無効と判断されたりする可能性があります。
例えば不動産(土地・建物)の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている通りに、正確に転記する必要があります。土地であれば「所在」「地番」「地目」「地積」を、建物であれば「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などを漏れなく記載しましょう。
(記載例:所在 横浜市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇、家屋番号 〇〇番〇〇)
預貯金については、「金融機関名」「支店名」「種別」「口座番号」を正確に記載します。
(記載例:〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇〇 )
株式や自動車などのその他の財産も同様に、それらを特定するための情報を詳細に記載してください。株式であれば「証券会社名」「銘柄」「株数」、自動車であれば「登録番号」「車台番号」などを記載します。これらの情報を正確に記すことで、後々の手続きをスムーズに進められます。
| 財産の種類 | 記載すべき主な特定情報 |
| 不動産 | 登記事項証明書に記載の所在、地番、地目、地積など |
| 預貯金 | 金融機関名、支店名、預金種別、口座番号 |
| 株式 | 証券会社名、銘柄、株数 |
| 自動車 | 登録番号、車台番号 |
作成はパソコン?手書き?作成時のポイントと注意点
遺産分割協議書の作成方法について、パソコンと手書きそれぞれの特徴や注意点をまとめました。
本文をパソコンで作成した場合でも手書きで作成した場合でも、相続人全員の署名は必ず自筆で行う必要があります。これは、本人が内容に同意したことを示す重要な要素です。また、捺印についても、実印を使用し、各自の印鑑登録証明書を添付します。ただし、内容の誤読や誤記を防ぐためにも遺産分割協議書は手書きではなくパソコンのワード文書により作成するようにしましょう。
作成した遺産分割協議書は、相続人の人数分用意し、全員が同じものを1通ずつ保管することが重要です。これにより、後で内容を確認したり照合したりする際もスムーズに進みます。
円満な相続のために知っておきたい注意点
相続人間の感情的な対立を招かないための配慮、相続税など、様々な視点から注意点を理解しておくことが不可欠です。これから解説する4つの具体的な注意点を事前に把握し、適切に対応することで、遺産相続を円満に解決し、長期的な家族関係を良好に保つことにつながります。
他の相続人への配慮を忘れずに
一人の相続人が全ての遺産を相続することになった場合、他の相続人が自身の法定相続分を放棄するに等しいため、話し合いを進める際には一定程度の配慮が必要なこともあるでしょう。まずは、なぜ自分が全ての遺産を相続したいのか、その具体的な理由を説明し、他の相続人の理解と納得を得ることが重要です。
この際、他の相続人の協力に対する感謝の気持ちを伝え、高圧的な態度を取らないよう心がけることが大切です。感情的なしこりを残してしまうと、遺産分割協議がまとまらないだけでなく、その後の親族関係が悪化するリスクも生じます。
「相続放棄」と「遺産分割協議」の違いを理解しておく
特定の相続人だけが遺産をすべて相続し、他の相続人が自身の相続分を不要とする場合、その方法として「相続放棄」と「遺産分割協議で相続分をゼロにする」という二つの選択肢があります。これらは法的意味合いや効果が大きく異なるため、その違いを正確に理解しておくことが極めて重要です。
「相続放棄」とは、家庭裁判所へ申述し、承認されることで、プラスの財産(不動産や預金など)もマイナスの財産(借金など)も一切承継せず、初めから相続人ではなかったものとみなされる手続きです。相続放棄の申述は、自身が相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ行う必要があります。相続放棄の場合、相続放棄により同順位の相続人がいなくなると、次順位の相続人が相続人となるため、話し合いが困難になることもあります。
一方、「遺産分割協議で一人の相続人が全てを相続する」合意は、相続人としての地位は維持したまま、話し合いによって遺産を取得しないと合意することです。この場合、相続放棄とは異なり相続人としての地位は残るため、被相続人に借金があった場合には、債権者からは、法定相続分に応じた支払いを請求される可能性があります。遺産分割協議における債務の負担に関する合意は、あくまで相続人内部での取り決めに過ぎません。
遺産分割が難しいと感じたら専門家への相談も検討しよう
遺産分割協議は、複雑な法律や手続きが関わるだけでなく、相続人同士の感情的な問題も絡みやすいものです。自分たちだけで解決が難しいと感じた場合は、早めに弁護士へ相談することを検討しましょう。
相続人同士の関係が悪く、協議がまとまらない場合
感情的な対立が激しく、話し合いが困難な場合は、交渉代理が可能な弁護士に依頼することで、客観的な視点から問題解決を促し、相続争いを収束できる可能性が高まります。
相続人に行方不明者、未成年者、認知症の人が含まれる場合
これらの相続人がいる場合、遺産分割協議を行うためには、不在者財産管理人、特別代理人の選任、成年後見人専任の申立てなど、家庭裁判所での特別な手続きが必要です。これらの手続きは複雑なため、司法書士や弁護士のサポートが不可欠です。
相続財産が複雑な場合
多数の不動産や非上場株式など、評価や名義変更手続きが複雑な財産が含まれるケースでは、正確な処理が求められます。専門知識を持つ弁護士に依頼することで、適切な評価と手続きの実施が期待できます。
手続きに不安がある、あるいは多忙で時間が取れない場合
相続手続きには多大な時間と手間がかかります。専門家に依頼することで、書類の収集や作成といった煩雑な作業を任せられ、時間的・精神的な負担を軽減できるでしょう。
遺産分割の問題は難波みなみ法律事務所へ

複数の相続人がいる状況で一人が全ての遺産を取得する場合でも、遺産分割協議書の作成は、相続手続きを円滑に進め、将来的なトラブルを避ける上で不可欠な書類です。
一見シンプルな単独相続に見えても、その手続きには「相続人調査」から「財産調査」、「遺産分割協議」、「協議書の作成」、そして「名義変更などの手続き」に至るまで、法的に定められた複数のステップがあります。これらの手順を一つずつ正確に踏むことが、後々の複雑な問題を防ぎ、円満な相続を実現する鍵となります。
遺産分割協議書の作成、相続人との合意形成、あるいは各種手続きに不安や困難を感じる場合は、一人で抱え込まずに弁護士への相談を検討してください。弁護士に相談することで、法的に有効な書類を正確に作成し、煩雑な手続きをスムーズに進められます。
初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。