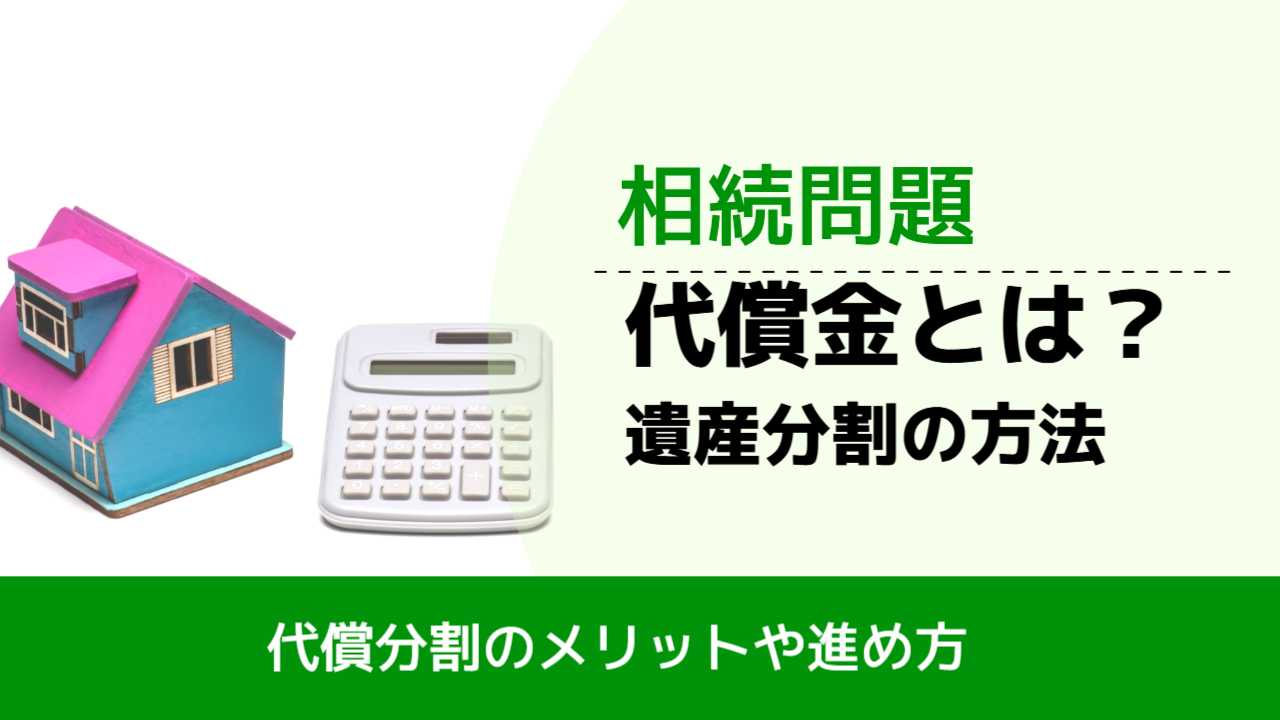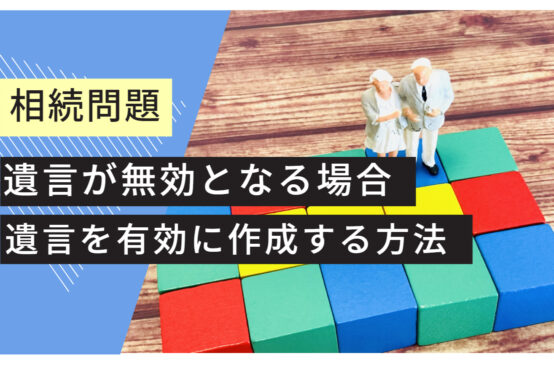遺産分割の方法として「代償分割」という選択肢があります。これは、特定の相続人が不動産や株式などの遺産を現物で取得する代わりに、他の相続人に対して金銭を支払う方法です。
しかし、代償金を受け取ったり、支払ったりする場合には、税金がかかるのか、金額はどのように決めるのかなど、様々な疑問が生じるかと思います。
この記事では、相続における代償金について、その基本的な意味から、金額の決め方、手続きの流れ、そして税金の取り扱いまで、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
そもそも相続における「代償金」とは?
遺産分割に際して選択されることのある代償分割。以下の項目では代償分割や代償金の基本について解説します。
不動産などを分けずに公平な遺産分割を実現する「代償分割」
代償分割は、相続財産の中に、不動産や自社株などの資産が含まれる場合に特に有効な方法です。特定の相続人がこれらの財産を単独で取得する代わりに、その価値に見合う金銭(代償金)を自己資金から他の相続人へ支払います。これにより、相続人全員が公平に遺産を受け取れるよう、円滑な遺産分割を実現できます。
例えば、代償分割が有効なケースとしては、以下のような状況が挙げられます。
- 家業を継ぐ相続人が、事業用不動産や同族会社の自社株を維持したい場合
- 被相続人の自宅を売却せず、特定の相続人が住み続けたいと希望する場合
こうした状況において、特定の遺産をそのままの形で残しつつ、他の相続人にもその価値に見合う分配を行う上で、代償分割は有効な手段となります。
この仕組みを利用することで、大切な不動産などを手放さずに済むだけでなく、相続人全員が納得して遺産分割を完結できるという大きなメリットがあります。
他の遺産分割方法(現物分割・換価分割)との違い
代償分割のほかに、各相続人が遺産をそのまま直接取得する「現物分割」があります。この方法のメリットは、相続人それぞれが具体的な財産をそのまま取得できるため、各自の持ち分が明確になり、評価額の細かな違いに神経質にならずに済む点です。手続きも比較的シンプルに進められるでしょう。一方でデメリットとしては、不動産と現金のように財産評価額に大きな差がある場合、公平な分割が困難となり、相続人間で不公平感が生まれやすい点が挙げられます。
もう一つの方法は、相続財産の売却により現金化し、その金銭を相続人全員で分配する「換価分割」です。最大のメリットは、遺産を現金化できるため、細かく分割し、相続人全員に平等な分配が実現できる点です。しかし、大切な不動産などを手放す必要があること、売却には仲介手数料などの手間と費用がかかることがデメリットとなります。また、売却価格が当初の評価額よりも低くなることで、手取り額が減る可能性も考えられます。
これら三つの遺産分割方法の特徴、メリット、デメリットをまとめると、次のようになります。遺産分割方法ごとの特徴、メリット、デメリット、向いているケースを以下の表にまとめました。
| 遺産分割方法 | 特徴 | メリット | デメリット | 向いているケース |
| 現物分割 | 遺産をそのままの形で分ける | 手続きが簡単、具体的な財産をそのまま取得できる | 公平な分割が難しい、不公平感が生じやすい。共有関係が生じ権利関係が複雑になることも。 | 遺産の種類が少ない、評価額に差がない場合 |
| 換価分割 | 遺産を売却して現金で分ける | 公平な分配が可能 | 不動産などを手放す、売却に手間・費用がかかる、手取り額が減る可能性 | 公平性を最重視したい、遺産を現金で分けたい場合 |
| 代償分割 | 特定の相続人が現物を取得し、他の相続人に代償金を支払う | 不動産などを残し公平に分割できる | 代償金を支払う側にまとまった資金が必要、評価で対立することも | 不動産などを残したい、特定の財産を引き継ぎたい場合 |


代償分割で遺産相続するメリットと知っておきたい注意点
代償分割は、不動産など物理的に分割が難しい遺産を、相続人全員で公平に分ける際に有効な方法です。他方で、代償分割をする際に知っておくべき注意点があることも忘れてはいけません。
以下では、代償分割のメリットと注意点について、具体的に詳しく解説します。
【メリット】実家などを売却せずに相続できる
代償分割を選択するメリットは、相続財産に含まれる不動産や特定の事業用資産を売却したり、分散させることなく、特定の相続人がそのまま引き継げる点です。この方法では、不動産などを取得した相続人が、自身の法定相続分を超える部分に対し、他の相続人へ金銭(代償金)を支払うことで調整します。
代償分割の主なメリットは以下の通りです。
- 不動産や特定の事業用資産を売却せずに引き継げます。
- 相続財産が物理的に分割しにくい場合でも、大切な資産を維持できます。
- 売却に伴う手間や費用、価格が想定より低くなるリスクを回避できます。
- 相続人全員の納得が得られやすく、円満な遺産分割に繋がりやすいです。
【メリット】相続人同士で公平に分けやすい
代償分割は、不動産など物理的に分割が難しい相続財産がある場合でも、相続人同士で公平な分割を実現できる大きな利点があります。
例えば、相続財産が不動産だけの場合や不動産に比べて預貯金やその他の金融資産が少ない場合には、代償分割することを検討します。つまり、代償分割による調整を行うことで、特定の相続人が思い入れのある実家などの財産を承継しつつも、他の相続人が不公平感なく、納得のいく形で遺産を受け取ることが可能になります。
【注意点】代償金を支払う側にまとまった資金が必要になる
代償分割では、不動産などの高額な遺産を取得する代わりに、他の相続人に対して法定相続分に見合う現金を支払うため、まとまった自己資金が必要となる点が大きな注意点です。遺産分割協議で代償金の支払いに合意しても、実際に支払いができなければ、後々相続人間でトラブルの原因となりかねません。そのため、事前に自身の支払い能力を十分に確認しておくことが不可欠です。
自己資金だけでは代償金の支払いが難しい場合、金融機関の不動産担保ローンなどを活用することも選択肢の一つとなります。
資金調達が現実的でない場合は、無理に代償分割を進めるのではなく、換価分割など別の遺産分割方法を検討し直すことも視野に入れるべきでしょう。
【注意点】相続財産の評価方法で意見が対立することも
代償分割を進める際、特に注意が必要なのは、相続財産の評価方法を巡る意見の対立です。不動産には一見して分かる定価がなく、「路線価」「固定資産税評価額」「実勢価格(時価)」など、複数の評価基準があります。どの基準を採用するかによって評価額は大きく変動するため、相続人間で意見の対立が生じやすくなります。
このような状況において、代償金を支払う側の相続人は、支払額を抑えるため、固定資産税評価額や相続税路線価といった低めの評価額を主張する傾向があります。一方、代償金を受け取る側の相続人は、より多くの金銭を得たいと考え、実勢価格(時価)での評価を求めることが一般的です。このようにして、双方の利害の対立が生じやすくなります。
もし話し合いで合意に至らない場合は、不動産鑑定士に鑑定を依頼することも有効な解決策の一つです。不動産鑑定士への依頼費用は一般的に20万円から100万円程と幅が大きく、物件の種類や利用目的によっては高額な鑑定費用が生じることも珍しくありません。ただ、客観的な評価を得ることで、円滑な遺産分割に繋がる可能性は高まります。
代償金の金額はいくらが妥当?決め方の基本ルール
代償金の正確な金額を算出するためには、不動産などの相続財産を適正に評価することが不可欠です。不動産には複数の評価方法が存在するため、どの基準を用いるかによって代償金の額が大きく変動する可能性があります。具体的な評価方法については、以下で詳しく解説します。
相続人全員の話し合いによる合意が原則
代償金の金額について、法律に明確な計算式は定められていません。そのため、相続人全員の話し合いにより、その金額を自由に決定するのが基本的な原則です。
遺産分割協議は、相続権を持つ全員が参加し、合意に至って初めて法的に有効となります。一部の相続人だけで代償金の金額を決定しても、法的な効力は持たず、後々のトラブルにつながる可能性があります。
円満な遺産分割を実現するには、なぜその金額になったのか、客観的な根拠に基づき冷静に話し合うことが重要です。例えば、不動産の評価額などを根拠に、納得できる理由を提示しながら話し合いを進めることで、全員の理解を得やすくなります。
もし話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所での手続きに移行する可能性があります。主な手続きは以下の通りです。
- 遺産分割調停:裁判所の調停委員が間に入り、相続人同士の合意形成を促します。
- 遺産分割審判:調停で合意に至らない場合、裁判官が遺産分割の方法を決定します。
長期化する相続争いを避けるためにも、冷静な話し合いを通じて円満な合意形成を目指しましょう。
基準となる不動産の評価方法とは?
代償金の金額を決定する上で、その基礎となる不動産の評価額をどのように算出するかは、非常に重要なポイントです。法律上で明確に定められた評価方法は存在しないため、相続人全員がどの評価方法を採用するか合意する必要があります。
一般的に用いられる不動産の主な評価方法は、以下の4つが挙げられます。
・実勢価格(時価)
・公示価格
・相続税評価額(路線価)
・固定資産税評価額
不動産の評価方法とその特徴を以下にまとめました。これらの評価方法のいずれを採用しても、法律上の問題は生じません。しかし、代償金を支払う側は、代償金の負担を抑えるために低めの評価額(相続税評価額や固定資産税評価額)を主張しがちです。
一方、代償金を受け取る側は、より多くの金銭を得るため実勢価格のような高めの評価を主張する傾向があります。円満な遺産分割を実現するためには、相続人全員が納得できる評価基準について十分に話し合い、合意することが肝要です。
| 評価方法 | 特徴 | 時価に対する目安 |
| 実勢価格(時価) | 実際に市場で取引されると想定される価格。売り手と買い手の需要と供給によって決まるため、客観性が高く、最も公平な評価基準とされます。 | 100% |
| 公示価格 | 国土交通省が毎年公表する土地の標準的な価格。公共事業の用地買収などで利用され、土地取引の目安にもなります。 | 概ね100% |
| 相続税評価額(路線価) | 相続税や贈与税を計算する際に用いられる価格。実勢価格よりも低く評価される傾向があります。 | 概ね80% |
| 固定資産税評価額 | 固定資産税や都市計画税、不動産取得税などを計算する際に用いられる価格。こちらも実勢価格よりも低い傾向があります。 | 概ね70% |
【具体例】法定相続分を基にした代償金の計算シミュレーション
代償金の具体的な金額をイメージしやすいよう、法定相続分を基にした計算シミュレーションをご紹介します。
シミュレーションの前提条件は以下のとおりです。
- 被相続人:父(他界)
- 相続人:母、長男、次男の3人
- 相続財産:評価額5,000万円の実家のみ
- 遺産分割の方針:長男が実家を単独で相続し、他の相続人に代償金を支払う
まず、法定相続分に基づき、各相続人が本来受け取るべき遺産の価額を算出しましょう。
- 母の法定相続分:5,000万円 × 1/2 = 2,500万円
- 長男の法定相続分:5,000万円 × 1/4 = 1,250万円
- 次男の法定相続分:5,000万円 × 1/4 = 1,250万円
次に、実家を単独で取得する長男が、他の相続人へ支払う代償金の金額を計算します。長男は評価額5,000万円の実家を単独で取得しますが、自身の法定相続分は1,250万円です。そのため、長男は自身の法定相続分を超える3,000万円を、母と次男に支払うことになります。
- 母へ支払う代償金:2,500万円
- 次男へ支払う代償金:1,250万円
- 長男が支払う代償金合計:3,750万円
このように、各相続人の最終的な取得分が法定相続分と等しくなり、評価額5,000万円の実家を売却することなく公平な遺産分割が実現できます。
【一番知りたい】代償金を受け取ると税金はどうなる?
代償分割を検討する際、多くの方が気になるのは「税金」の問題でしょう。
代償金の授受には、主に以下の3種類の税金が関連する可能性があります。以下では、代償金とそれぞれの税金との関係について、具体的な計算方法や注意点を含め、詳しく解説します。
相続税の計算方法|代償金の扱いは?
相続税は、各相続人が最終的に取得した財産の価額に基づいて計算されるのが基本原則です。代償分割が行われた場合も、最終的に各自が受け取った財産や代償金の合計額に対して相続税が課されます。
代償金を支払った側の課税価格
代償金を支払って不動産などの現物財産を相続した相続人の課税価格は、取得した現物財産の価額から支払った代償金の額を差し引いて計算します。例えば、相続人Aが相続税評価額5,000万円の土地を相続し、相続人Bに代償金2,500万円を支払った場合、Aの相続税の課税価格は5,000万円から2,500万円を差し引いた2,500万円となります。
代償金を受け取った側の課税価格
一方、代償金を受け取った相続人については、受け取った代償金に対して相続税が課税されます。上記の例で、相続人乙が甲から代償金2,000万円を受け取ったとします。この場合、乙の相続税の課税価格は、受け取った代償金2,000万円がそのまま課税価格となります。
贈与税はかからない?遺産分割協議書への記載が必須
代償分割によって支払われる代償金は、遺産分割の一環として扱われるため、原則として贈与税の課税対象にはなりません。
しかし、代償財産の時価を超える金額を支払う場合には、相続人間で相続財産を超える財産の受け渡しがあったことになるため、時価を超える部分については贈与税の負担が生じる可能性があります。
所得税が課税される特殊なケース
代償金は、遺産分割の一環として行われる相続財産の移転とみなされるため、原則として代償金を受け取った側にも、支払った側にも所得税の税負担は生じません。
しかし、例外的に所得税(譲渡所得税)が課税される特殊なケースがあります。
これは、代償金を支払う側の相続人が、自身の固有財産を他の相続人に直接渡して代償金とした場合です。これは「代物弁済」と呼ばれます。代物弁済が行われた場合、代物弁済をした相続人は、その時の時価により資産を譲渡したこととなるため、その資産の譲渡益に対して譲渡所得税が課税されます。
他方、代償分割により遺産を取得した人がその遺産を売却した場合にも譲渡所得税の負担が生じることになります。この場合、支払った代償金を取得費として控除することはできないのが原則です。
代償分割の手続きと流れを4ステップで解説
代償分割の手続きは、専門的な知識が必要なため、複雑に感じられるかもしれません。しかし、適切な手順を踏めば円滑に進められます。以下の項目では、代償分割をスムーズに進めるための具体的な手順を、初心者の方にも分かりやすく4つのステップに分けて解説します。
ステップ1:相続人の特定と遺産の調査
まず、遺産分割を進めるにあたって必要なことは、相続人の特定と遺産の調査です。
相続人の特定をするためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の現在戸籍を取り付けます。相続人の特定ができれば、相続関係図を作成して相続人の情報を見える化します。
また、並行して被相続人の遺産を調査します。預貯金については、相続開始時の残高証明や数年分の口座履歴を、不動産については、登記簿謄本や評価証明を取り寄せます。その他に株式や投資信託などの資産があれば、信託会社等の金融機関に資料の取付けをします。遺産調査を終えれば、遺産目録を作成します。
ステップ2:相続人全員で代償分割に合意する
代償分割の手続きを進める上で、次のステップは、相続人全員が参加する「遺産分割協議」を通じて合意を成立させる点です。
遺産分割は、相続権を持つ全員の同意がなければ法的に成立しません。そのため、相続人nのうち反対する相続人がいる場合、代償分割を進めることはできません。この段階で相続人全員の理解と納得を得ることが極めて重要です。
この協議では、特定の相続人が実家などの不動産や、分割が難しい事業用資産を単独で取得したいと希望する場合に、他の相続人との公平性を保つために代償分割を提案します。その際、代償分割を選択する理由や具体的なメリットを明確に説明し、相続人全員でその内容を確認することが肝要です。
ステップ3:代償金の金額を決定する
代償分割における代償金の金額決定は、相続財産、特に不動産の評価額を正確に算出することから始まります。どの評価方法を採用するかによって代償金の額は大きく変動するため、相続人全員で十分に話し合い、合意を形成することが不可欠です。
決定した評価額を基に、各相続人の法定相続分などを参考に具体的な代償金額を計算し、相続人全員が納得できる金額を決定します。もし当事者間の話し合いで金額がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停や審判に移行し、最終的な金額が決定されることもあります。円満な解決を目指すため、慎重な協議が求められます。
ステップ4:遺産分割協議書を作成・締結する
相続人の全員が代償分割を含む遺産分割協議の内容に合意した後、その合意内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。この遺産分割協議書は法的な効力を持つ重要な書類であり、誰がどの財産を相続するのか、代償金の金額はいくらで、いつまでにどのような方法で支払われるのかといった詳細を明確に記載しなければなりません。
遺産分割協議書には、以下の主な項目を記載します。
- 被相続人の氏名、死亡日、最後の住所
- 相続人全員の氏名
- 合意に至った遺産分割の方法と割合
- 代償金の金額、支払期日、振込先
作成された協議書の内容に間違いがないことを確認した上で、相続人全員が自署し、各自の実印を押印することが必要です。
トラブル回避の鍵!遺産分割協議書の書き方と注意点
代償分割において、遺産分割協議書を正確に作成することは遺産分割後のトラブルを回避するために非常に重要です。以下では、遺産分割協議書の書き方とその注意点を解説します。
「代償分割であること」を明確に記載する
遺産分割協議書に「代償分割であること」を明確に記載することは、税務上のトラブルを避ける上で非常に重要です。この記載がない場合、税務署から単なる個人間の「贈与」と見なされ、代償金を受け取った側に高額な贈与税が課されるリスクがあります。遺産分割の一環として代償金が支払われたことを客観的に示すためにも、正確な記述が不可欠です。
具体的には、遺産分割協議書に以下の内容を明確に盛り込む必要があります。
| 記載事項 | 内容 |
| 代償の対象(代償財産) | どの財産を誰が相続する代償か |
| 支払当事者 | 誰が誰に対して代償金を支払うのか |
| 代償金額 | いくらの代償金を支払うのか |
| 支払期限 | いつまでに支払いを完了するのか |
特に「遺産を取得する代償として」といった文言を入れることで、その金銭の授受が遺産分割の調整であることを明確に示せます。
【ひな形】代償分割の条項を盛り込んだ遺産分割協議書の記載例
代償分割を行う際の遺産分割協議書には、合意内容を明確にし、具体的な記載が不可欠です。ここでは、父が亡くなり、長男が実家である不動産を単独で相続し、その代償として次男に金銭を支払うケースを想定したひな形をご紹介します。
第〇条 長男太郎は、下記の不動産を相続する。
記
(不動産の表示は登記簿謄本に記載されている通りに正確に記載してください。)
第〇条 長男太郎は、前条記載の不動産を相続する代償として、次男次郎に対し、金〇〇〇万円(〇〇万円)を支払う。
第〇条 長男太郎は次男二郎に対し、前条の金員を令和7年〇月末日までに、次男二郎の指定する銀行預金口座宛に振り込む方法により支払う。振込手数料は長男太郎の負担とする。
この記載例のように、「誰がどの財産を取得するのか」「誰が誰に、いくらの代償金を、いつまでに、どう支払うのか」を明確に盛り込むことが重要です。「遺産を取得する代償として」という文言は、代償金が贈与とみなされないために不可欠な一文です。
相続の代償金に関するよくある質問(Q&A)
実際の相続では「代償金が支払われなかったらどうなるのか」「分割で支払うことは可能なのか」といった、さらに具体的な疑問や不安を感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
そこで以下の項目では、代償分割を進める上で抱きがちな「よくある質問」について、Q&A形式で分かりやすくご紹介します。
| 対処法 | 概要 | 強制力 | 主な前提/準備 |
| 内容証明郵便 | 支払いを催促する書面 | なし | 内容証明の作成と送付 |
| 履行勧告 | 裁判所による履行の促し | なし | 遺産分割調停・審判の決定 |
| 強制執行 | 相手の財産を差し押さえる法的措置 | あり | 債務名義(裁判所の決定等) |
Q.代償金が支払われなかったら、どうすればいい?
代償分割の合意にもかかわらず、代償金が期日までに支払われない場合、状況に応じた段階的な対処法を検討する必要があります。
以下に、代償金が支払われない場合の段階的な対処法をまとめました。
まず第一歩として、内容証明郵便を利用して支払いを催促することが有効です。電話やメールでは相手が対応しない可能性もありますが、内容証明郵便は支払いを促す心理的な効果が期待できます。さらに、後の法的手続きにおいて客観的な証拠としても役立ちます。
もし、遺産分割調停や審判によって代償分割が決定していた場合は、家庭裁判所に「履行勧告」を申し立てることが可能です。これは、家庭裁判所が相手に対し、支払いを促す制度ですが、法的な強制力はありません。
最も強力な手段は、相手の財産を差し押さえる「強制執行」です。しかし、強制執行を行うには「債務名義」と呼ばれる法的な文書が不可欠です。具体的には、以下のようなものが債務名義に該当します。
- 確定判決
- 和解調書
- 調停調書
- 審判書
- 執行認諾文言付きの公正証書
もし遺産分割協議書を公正証書で作成していない場合は、まず「代償金支払請求訴訟」を提起し、勝訴判決を得る必要があります。この勝訴判決が債務名義となり、強制執行が可能になります。
Q.代償金を分割で支払ってもらうことは可能?
代償金の支払いに関しては、相続人全員が承諾すれば分割払いを設定できます。しかし、口約束で済ませてしまうと、後にトラブルへ発展する可能性があるため、必ず遺産分割協議書に具体的に明記することが重要です。
協議書には、分割払いの回数、各回の支払額、それぞれの支払期日、具体的な支払方法(銀行振込など)、期限の利益の喪失を詳細に記載してください。これにより、支払いに関する認識のずれを防ぎ、双方にとって明確な取り決めとなります。
将来的な支払い遅延などのトラブルを未然に防ぐためには、遺産分割協議書に遅延損害金に関する取り決めを加えておくことをおすすめします。例えば、「支払いを遅滞したときは、未払い金に対し年〇%の遅延損害金を付加して支払う」といった条項を盛り込むと良いでしょう。
さらに、遺産分割協議書を公正証書として作成することも非常に有効な手段です。公正証書を作成しておくことで、代償金の不払い時に訴訟手続を経ることなく直ちに強制執行を行うことができます。これにより、代償金を受け取る側の権利をより確実に保護できます。
Q.弁護士への相談はどのタイミングですべき?
相続の専門家への相談は、相続が発生した直後、特に遺産分割協議を始める前の早い段階で行うことが、後のトラブルを未然に防ぐ上で最も効果的です。相続に関する問題は多岐にわたり、放置すると複雑化する傾向があるためです。
具体的な相談タイミングとしては、以下のケースが挙げられます。
- 相続人同士で意見が対立しそうなとき:遺産分割の方針や代償金の金額などで意見の食い違いが生じる可能性がある場合。
- 不動産など財産の評価方法で揉めそうなとき:不動産の適正な評価額について、相続人間で認識のずれがある場合。
もし、すでに相続人間で話し合いがまとまらないなど、深刻なトラブルが発生している場合は、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士は、法的観点から解決策を提示し、交渉や調停、裁判を通じて円満な解決へ導いてくれるでしょう。早い段階での専門家への相談が、深刻なトラブルを回避し、円滑な相続実現の鍵となります。
代償金の問題は難波みなみ法律事務所へ

これまで、相続における代償金の基本的な意味、代償分割のメリットや注意点、代償金の決め方、税金の取り扱い、そして具体的な手続きの流れについて詳しく解説してきました。
相続時のトラブルを未然に防ぎ、スムーズで円満な相続を実現するためには、まず相続人全員が代償分割の内容について十分に話し合い、合意を形成することが何よりも重要です。そして、その合意内容を遺産分割協議書へ正確かつ具体的に記載し、相続人全員が署名・実印を押印することが求められます。
相続人同士の意見対立など、少しでも不安な点や疑問が生じた際は、相続に詳しい弁護士へ早めに相談することをおすすめします。弁護士は、個別の状況に応じた適切なアドバイスを提供し、円満な解決へと導いてくれるでしょう。代償分割を正しく理解し、適切な手続きを踏むことで、皆様にとってより良い相続の実現を目指しましょう。
初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。