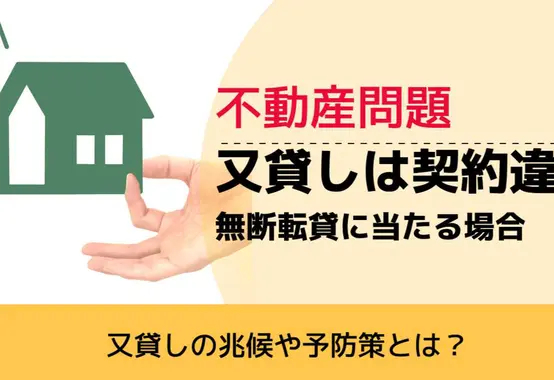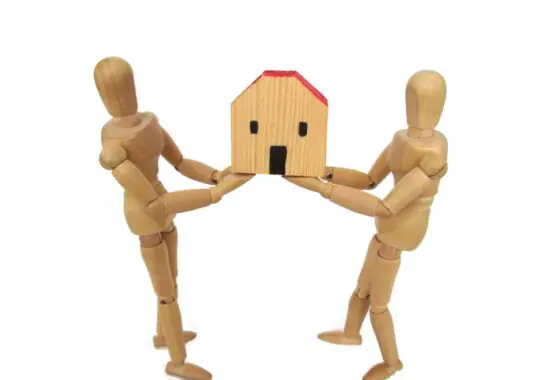不動産投資におけるサブリース契約は、空室リスクを回避し、安定した収入を得るための選択肢となります。しかし、その一方で、契約内容を十分に理解せずに安易に契約してしまうと、後々後悔するデメリットも潜んでいます。
本記事では、サブリース契約の デメリット に焦点を当て、契約前に知っておくべき重要な注意点やリスクを詳しく解説します。「家賃保証」という言葉の裏に隠された落とし穴や、契約解除の難しさ、オーナーとしての権利制限など、サブリース契約がもたらす可能性のある問題を具体的に提示します。サブリース契約を検討する前に、ぜひ本記事を参考に、慎重な判断をしてください。
まずは基本から|サブリース契約の仕組みとメリット
サブリース契約のデメリットを解説するにあたり、まずはサブリース契約の基本を理解しておくことが大切です。
以下では、サブリース契約とは何か?という基本的な事項、契約の仕組みやメリットを解説します。
サブリースとは?一括借り上げの仕組みをわかりやすく解説
サブリースとは、不動産会社(サブリース会社)がオーナーから建物を一括で借り上げ、それを入居者に転貸する契約形態です。オーナーとサブリース会社の間で賃貸借契約(マスターリース)が結ばれ、サブリース会社と実際の入居者の間では、これとは別の賃貸借契約(転貸借契約)が結ばれるという、三者間の構造になっています。
サブリース会社が行う一括借り上げとは、オーナーが所有するアパートやマンションといった物件を部屋単位ではなく、建物全体としてまるごと借り上げることを指します。これにより、オーナーは個々の入居者と直接契約したり、煩雑な入居者対応に追われたりする必要がなくなります。
サブリース契約の最も大きな特徴は、この一括借り上げに基づいた保証賃料の仕組みです。これは、たとえ物件に空室があったり入居者が家賃を滞納したりした場合でも、サブリース会社からオーナーに対して、契約で定められた一定の保証賃料が毎月支払われるというものです。これにより、オーナーは安定した家賃収入を確保できると考えられています。
オーナーが享受できる主なメリット
サブリース契約において、オーナーが享受できる主なメリットは複数あります。
サブリース契約におけるオーナーの主なメリットは以下の通りです。
- 安定した家賃収入が得られる(空室や滞納のリスク軽減)
- 煩雑な賃貸管理業務を任せられる
- 家賃収入の管理がシンプルになる
まず、最も大きいのは空室リスクや家賃滞納リスクを気にせず、安定した家賃収入を得られる点です。サブリース会社が物件を一括で借り上げるため、たとえ個別の部屋に空室が発生したり、入居者が家賃を滞納したりした場合でも、オーナーはサブリース会社から毎月一定の保証賃料を受け取ることができます。この保証賃料は、満室時の家賃収入に対して80%から90%程度が相場とされています。これにより、将来の収入を予測しやすくなり、資金計画も立てやすくなるでしょう。
次に、煩雑な賃貸管理業務をサブリース会社に一任できる点も大きなメリットです。具体的には、入居者の募集や審査、日々の家賃集金、入居者からの設備に関する問い合わせや近隣トラブルといったクレーム対応、さらには退去時の立ち会いや原状回復の手配など、多岐にわたる業務のほとんどを任せられます。これにより、オーナー自身が管理業務に追われることなく、時間や手間を大幅に削減できます。特に、本業が忙しい方や、遠方に物件を所有している方にとっては、管理の負担が軽減されることは大きな魅力となります。
また、家賃収入の管理もシンプルになります。個別の入居者からではなく、サブリース会社からまとめて保証賃料が振り込まれるため、入金管理が容易です。入居者が複数いる場合でも、振込元が一つになるため、通帳の記帳や収支の確認が楽になり、確定申告の際の手間も軽減されることが期待できます。これらのメリットは、不動産経営の専門知識がなくても、比較的容易に経営を開始・継続できる環境を提供します。


【契約前に要確認】サブリースで注意すべき7つのデメリット
サブリース契約は、空室リスクの軽減や管理業務の負担削減といったメリットがある一方で、見過ごせないデメリットも存在します。これらのデメリットを契約前に十分に把握しておかないと、「こんなはずではなかった」と想定外の事態に直面し、後々の後悔につながる可能性があります。
以下では、サブリース契約を検討するにあたり、特に押さえておくべき7つの具体的なデメリットについて、それぞれの内容と注意点を詳しく解説していきます。契約判断の材料として、ぜひ参考にしてください。
①保証家賃は永続ではない!減額されるリスクがある
サブリース契約の最大の魅力の一つとして、「家賃保証」を挙げる方が多いでしょう。しかし、この保証家賃が契約期間中ずっと同じ金額で固定されるわけではないという点は、必ず理解しておくべき重要な点です。契約書には通常、2年ごとなど一定期間ごとに、保証する家賃の見直しを行う旨の条項が含まれています。
この見直しにより、サブリース会社からオーナーに対し、家賃の減額が求められるケースが少なくありません。減額の理由としては、周辺の家賃相場の下落、建物の経年劣化による資産価値の低下、あるいは空室が増加したことによる入居率の低下などが挙げられます。特に賃料減額請求は、サブリース会社に法的に認められている権利であり、過去の裁判でも減額が認められた事例が多く存在します。
そのため、「30年一括借り上げ」といった長期の契約期間を謳う広告を目にしても、それが30年間同じ家賃で保証されるという意味ではないことを認識しておく必要があります。サブリース契約における保証家賃は、あくまで変動するリスクがあることを前提に、契約内容を慎重に確認することが不可欠です。契約書の見直しに関する条項をしっかりと確認し、将来的な減額リスクも考慮した上で判断することが大切です。
②管理手数料がかかるため手取り収入は低くなる
サブリース契約では、サブリース会社に物件を一括で借り上げてもらうとともに、空室保証で物件の管理をしてもらうため、管理料を支払う場合があります。この管理料の一般的な相場は、月額賃料の10%〜20%程度が目安とされています。つまり、仮に家賃収入が月額100万円だった場合、そのうち10万円から20万円程度が手数料として差し引かれることになります。
そのため、物件が満室稼働した場合の想定家賃収入と比較すると、オーナーがサブリース会社から受け取る保証賃料は必然的に少なくなり、手取り収入が低くなる傾向があります。これは、オーナーが直接入居者と契約し、管理業務だけを不動産会社に委託する一般的な管理委託契約と比較した場合に顕著です。一般的な管理委託契約における管理手数料は、家賃総額の5%程度が相場とされています。
サブリース契約におけるこの管理手数料は、サブリース会社が空室や家賃滞納が発生した場合でもオーナーに代わってリスクを負い、一定の家賃収入を保証するための費用です。安定した収入を得られるメリットがある反面、その分コストが発生するという側面があることを理解しておくことが重要です。
③契約開始直後は収入ゼロ?「免責期間」に注意
サブリース契約を結んだからといって、契約開始直後からすぐに家賃収入が入るとは限りません。多くのサブリース契約には「免責期間」が設定されています。これは、サブリース会社が新たな入居者を募集し、賃貸活動を行うための準備期間として設けられるものです。この免責期間中は、オーナーに対して家賃保証が行われないため、家賃収入が一切発生しません。
免責期間は、一般的に1ヶ月から3ヶ月程度で設定されますが、物件の状況や契約内容によってはそれ以上の期間となるケースもあります。
また、最初の契約時だけでなく、入居者が退去するたびに新たな免責期間(再免責期間)が設けられることもあります。
この免責期間中は家賃収入がゼロまたは減額されることになるため、住宅ローンや維持費の支払いなど、オーナー側の資金計画に大きな影響を与える可能性があります。
契約前に、免責期間の有無、その期間、そして再免責期間の規定についても、契約書で必ず確認することが非常に重要です。不当に長い免責期間が設定されていないか、複数のサブリース会社を比較検討する際の重要なチェックポイントとなるでしょう。
④オーナーからの解約は原則として難しい
サブリース契約は、オーナーとサブリース会社の間で締結される賃貸借契約に該当します。この契約には借地借家法が適用されるため、貸主であるオーナーからの一方的な解約は原則として認められません。法律上、借主であるサブリース会社の権利が厚く保護されており、オーナーが契約を解除するためには、借地借家法第28条に定められる「正当事由」が必要となります。
この正当事由は非常に厳格に判断され、「収益性が低いから」「自分で管理したいから」といったオーナー側の都合だけでは、正当事由を充足させることは難しいのです。仮に契約書にオーナーからの解約に関する条項があったとしても、正当事由を十分に説明できなければ、高額な立ち退き料や違約金の支払いを求められます。
このように、サブリース契約においては、一度契約を結ぶとオーナーからの解約は非常に困難となる可能性が高い点を理解しておく必要があります。
⑤高額な修繕費用を請求されるケースも
サブリース契約において、建物の維持管理はサブリース会社の業務範囲に含まれますが、修繕にかかる費用負担の区分については注意が必要です。特に大規模修繕や、入居者退去時の原状回復にかかる費用は、原則としてオーナー負担となるケースが多く見られます。契約書でこの費用負担の範囲が明確でない場合、想定外の高額な修繕費用を請求されるリスクがあります。
また、修繕工事はサブリース会社が指定する業者で行われることも珍しくありません。この場合、オーナー自身が複数の業者から相見積もりを取る機会が制限されるため、結果として工事費用が相場よりも割高になる可能性も否定できません。さらに、契約内容によっては、修繕の必要性や工事内容、業者選定についてオーナーの意向が反映されにくく、知らない間に不要な工事が進められ、その費用だけを請求されるといったトラブルにつながる可能性もゼロではありません。
このようなリスクを避けるためには、契約を締結する前に、契約書に記載された修繕費用の負担区分を詳細に確認することが極めて重要です。
⑥入居者を選ぶ権利がない
サブリース契約では、オーナーと入居者の間にサブリース会社が入るため、入居者との賃貸借契約の貸主はサブリース会社になります。その結果、物件の所有者であるオーナーは、実際に入居する人を選ぶための入居審査に直接関与できません。つまり、入居者を決定する権利がオーナー様にはありません。
サブリース会社は、空室期間を短縮し、早期に入居者を確保することを優先する傾向にあります。そのため、自主管理や管理委託契約でオーナー自身が審査する場合と比べて、入居審査の基準が緩やかになる可能性があります。その結果、家賃の支払いが滞りがちな入居者や、騒音、ゴミ出しといった共同生活のマナーを守らないなど、後々のトラブルにつながりやすい入居者が入居してしまうリスクが高まることがあります。
⑦サブリース会社の倒産で家賃収入が途絶えるリスク
サブリース契約における深刻なリスクの一つに、サブリース会社の倒産が挙げられます。もしサブリース会社が経営破綻した場合、オーナーへの保証家賃の支払いは完全に停止します。これは、空室リスクを負わないというサブリースの最大のメリットが失われ、オーナーの収入が途絶えることを意味します。
さらに、サブリース会社が倒産すれば、サブリース会社は賃料を滞納することになりますから、オーナーはサブリース会社との賃貸借契約を解除することになります。サブリース会社との契約を解除した場合、これをベースとする転貸借契約も当然に効力を失い、入居者は物件から退去しなければなりません。
ただ、オーナーとしては、賃料収入が途絶えないようにするために入居者と直接賃貸借契約を締結することを希望することも多くあります。しかし、サブリース会社の倒産に伴い、誰に賃料を支払うべきか、預けている敷金をどうするのかなどの混乱を招いてしまい、入居者との賃貸借契約をスムーズに結べないことも珍しくありません。
また、サブリース会社の突然の倒産は、新たな管理会社探しや自主管理への切り替えといった急な対応を迫られることになり、その間の空室リスクや管理業務の負担がオーナーに直接のしかかることになります。
契約書で必ずチェックすべき5つの重要項目
サブリース契約は長期にわたり、オーナー様の権利や収益に大きく影響するため、契約書の内容を詳細に確認することが極めて重要です。
以下では、サブリース契約で必ずチェックすべき、トラブルになりやすい5つの重要項目について、具体的な確認ポイントを解説します。
保証賃料の額と見直しのタイミング
サブリース契約書を確認する上で特に重要な点の一つは、契約書に明記されている「保証賃料」の具体的な金額です。この金額が、周辺の家賃相場(市場賃料)から見て妥当な水準であるかを事前に確認することが重要です。高すぎる保証賃料が提示されている場合、後々減額されるリスクが高い可能性も考えられます。
また、この保証賃料が何年ごとに見直されるのかという頻度やタイミング、そしてどのような条件や理由に基づいて見直しが行われるのかといった具体的な条項が、契約書にどのように記載されているかを詳細にチェックする必要があります。
さらに、賃料改定のプロセスが「協議の上で決定する」となっているのか、あるいは、サブリース会社からの「通知をもって効力を生じる」といった一方的なものかなど、変更手続きに関する規定も不可欠な確認ポイントです。これらの項目を事前にしっかりと把握しておくことで、将来的な賃料減額リスクに備えることができます。
免責期間の有無と期間の長さ
サブリース契約を結んだからといって、契約開始直後からすぐに家賃収入が得られるわけではありません。多くのサブリース契約には、「免責期間」と呼ばれる期間が設定されていることが一般的です。
契約書を確認する際は、まずこの免責期間に関する条項の有無を必ず確認しましょう。口頭での説明だけでなく、契約書にその期間が明確に記載されているかを確認することが非常に重要です。免責期間の長さが「〇ヶ月」あるいは「〇日間」と具体的に明記されているかを確認します。一般的な免責期間は1ヶ月から3ヶ月程度が目安とされています。ご自身の契約に設定されている期間が、この一般的な期間と比較して妥当であるかを判断することが大切です。
契約書で確認すべき免責期間に関する主な項目は以下の通りです。
- 免責期間に関する条項の有無
- 契約書に期間が具体的に記載されているか(〇ヶ月、〇日間など)
- 設定されている期間の長さ(一般的な目安と比較して妥当か)
- 再免責期間の有無や期間
原状回復や修繕費用の負担区分
サブリース契約において、建物の維持管理にかかる費用負担の範囲は非常に重要な確認ポイントです。これらの項目が曖昧なまま契約してしまうと、後から予期しない高額な費用を請求され、トラブルに発展するケースが少なくありません。
そのため、契約書の「原状回復」や「費用負担」に関する具体的な条項を細部まで確認し、オーナーがどこまで費用を負担するのかを明確に理解しておくことが大切です。また、修繕工事に際して、サブリース会社の指定する業者に必ず発注しないといけないのか、オーナー側で自由に発注できるのかなども確認しておくことが大切です。
中途解約の条件と違約金の有無
貸主であるオーナーからの中途解約は原則として認められにくく、法的に定められた「正当事由」が必要となります。
契約書で、オーナーからの解約が認められるのか、認められるとして、どのような場合に可能となるのかを確認しておくことが重要です。
また、オーナー側からの都合で中途解約する場合に、違約金が発生するかの有無、およびその金額や計算方法についても契約書で確認が必要です。想定外の費用を請求されるリスクを避けるためにも、事前に明確に把握しておくことが不可欠です。
契約更新の条件
サブリース契約は長期にわたるため、契約期間満了時の更新条件は非常に重要です。
契約更新時に、サブリース会社から保証家賃の引き下げや免責期間の追加など、オーナーにとって不利な条件変更を提示されることも少なくありません。
そのため、契約更新に際して確認すべき主な事項は以下の通りです。
- サブリース会社からの条件変更の可能性と内容(保証家賃、免責期間など)
- オーナーからの更新拒絶の可否および条件
- 更新拒絶の申し入れ期間(契約満了の〇〇ヶ月前など)
- 契約更新料の有無、金額、負担者
これらの事項について、事前に契約書をしっかりと確認し、不明な点はサブリース会社に問い合わせて明確にしておくことが、後々のトラブルを防ぐ上で不可欠です。
信頼できるサブリース会社の選び方
サブリース契約には様々なメリットがありますが、家賃の減額リスクや中途解約の難しさなど、事前に知っておくべき多くのデメリットやトラブルの要因も潜んでいます。これらのリスクを可能な限り回避し、安定した不動産経営を実現するためには、契約を結ぶ相手となるサブリース会社をいかに慎重に見極めるかが極めて重要になります。
会社の経営基盤と実績を調べる
サブリース契約は一般的に長期にわたるため、契約するサブリース会社の経営基盤の安定性を確認することは極めて重要です。
前述したように、サブリース会社が倒産した場合、オーナーへの保証家賃支払いが停止するなど、不動産経営にとって深刻な問題となるリスクがあるためです。
複数の会社から見積もりを取り比較検討する
サブリース会社を選ぶ際には、たった1社の提案だけで契約を決めるのは避けるべきです。必ず2〜3社以上の会社から見積もりを取り、比較検討することが非常に重要となります。複数の会社から提案を受けることで、それぞれの会社の特徴やサービス内容、費用体系の違いが明らかになり、より客観的に判断できるようになります。
デメリットも正直に話してくれる担当者か見極める
信頼できるサブリース会社を選ぶ上で、担当者の誠実さは非常に重要な判断材料です。メリットばかりを強調し、サブリース契約に潜む潜在的なデメリットやリスクについて十分な説明をしない担当者には注意が必要です。
将来的なトラブルを避けるためにも、サブリース契約のデメリットについて、こちらから尋ねる前に正直かつ丁寧に説明してくれるかどうか。これが、誠実さを見極める第一歩となります。
サブリースだけが選択肢ではない?他の管理方法との比較
サブリース契約は賃貸経営における管理方法の一つですが、これが唯一の選択肢ではなく、管理委託や自主管理という別の方法も存在しています。
以下では、「管理委託契約」と「自主管理」について、それぞれのメリット・デメリットを含め、さらに詳しく解説していきますので参考にしてください。
管理業務だけを委託する「管理委託契約」
管理委託契約とは、物件の所有者であるオーナーが、不動産会社(管理会社)と賃貸管理業務に関する委任契約を結ぶ形態です。
この契約では、入居者の募集、賃貸借契約の締結・更新手続き、賃料等の集金、入居者からのクレーム対応や建物・設備の維持管理といった、賃貸経営に必要となる業務を管理会社に委託します。
サブリース契約との最大の違いは、家賃収入の仕組みと空室リスクを誰が負うかにあります。管理委託契約の場合、オーナーが入居者と直接契約を締結し、入居者から直接賃料を収受することになります。管理会社に支払うのは、委託した管理業務に対する手数料であり、一般的に家賃収入の3%~5%程度が相場とされています。そのため、物件が満室で稼働した場合の手取り家賃収入は、サブリース契約で保証賃料を受け取るよりも高くなる傾向があります。
一方で、空室リスクはオーナー自身が負うことになります。しかし、サブリース契約と比べて、入居者の募集条件の設定や入居者を選定する際の基準にオーナーの意向を反映させやすいメリットがあります。また、管理会社との契約期間も比較的短く設定されることが多く、必要に応じて管理会社を変更したり、契約を解除したりしやすいという柔軟性も持ち合わせています。
収益性を最大化できる「自主管理」
自主管理とは、物件のオーナー自身が入居者の募集、賃料の集金、設備の修繕対応、入居者からの問い合わせ対応、さらには退去時の手続きといった賃貸経営に関わる全ての業務を自ら行う管理形態です。サブリース契約における手数料や、管理委託契約における管理費用がかからないため、家賃収入がそのままオーナーの手取り収入となるため、他の管理方法と比較して収益性を最も高められる可能性があります。
しかし、自主管理は全ての業務を自分で行うため、多大な時間と労力がかかります。入居者募集に失敗してしまい空室期間が長くなり、期待した利益を実現できないリスクがあります。また、家賃滞納が発生した場合の督促や、入居者からの突発的なクレーム対応、設備故障への対応など、精神的・時間的な負担も大きくなります。不動産経営や法律に関する専門知識も必要となるため、安易な選択は危険と言えます。
サブリース契約の問題は難波みなみ法律事務所へ

本記事では、サブリース契約の仕組みとメリット、そして注意すべき具体的なデメリットについて詳しく解説してきました。
サブリース契約は、空室リスクや家賃滞納のリスクを気にすることなく、煩雑な賃貸管理業務をサブリース会社に任せられるという大きなメリットがあります。
その一方で、契約内容を十分に理解せずに安易に契約してしまうと、予期せぬデメリットに直面するリスクにも配慮する必要があります。
不動産投資の目的やライフスタイル、不動産経営に対する知識や経験、そしてどの程度リスクを許容できるのかを十分に考慮し、様々な管理方法と比較検討することが重要です。