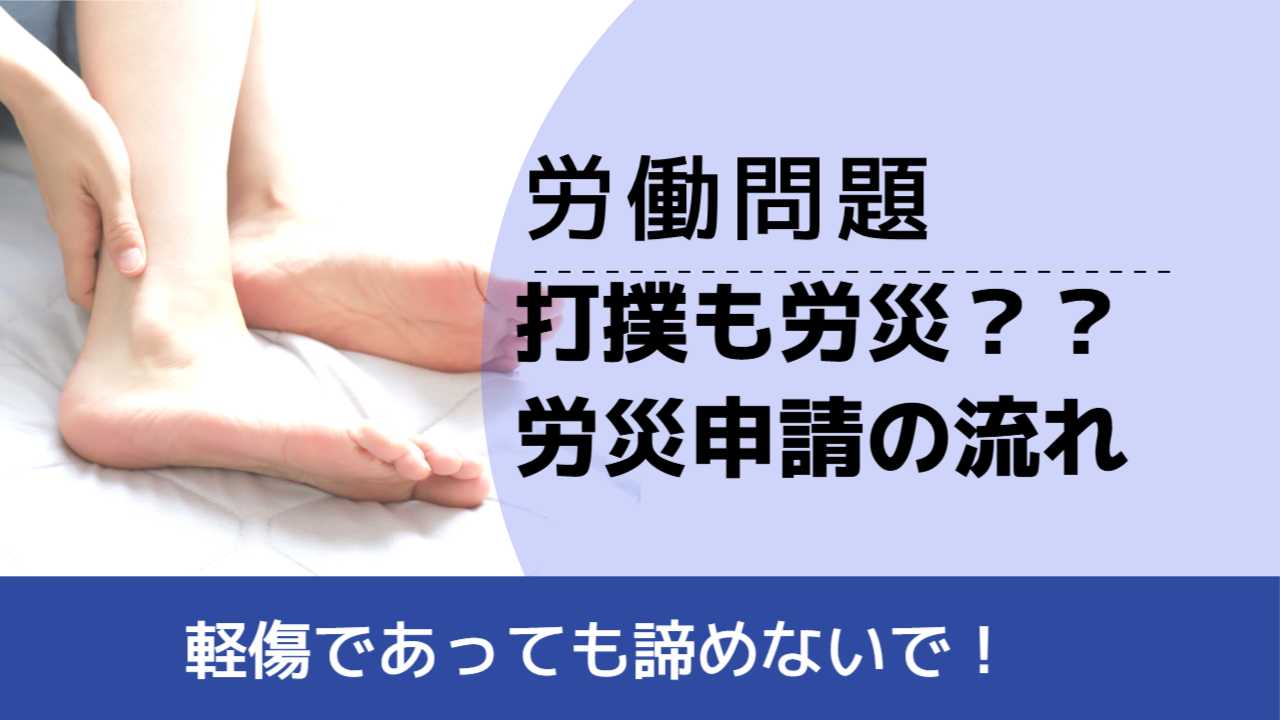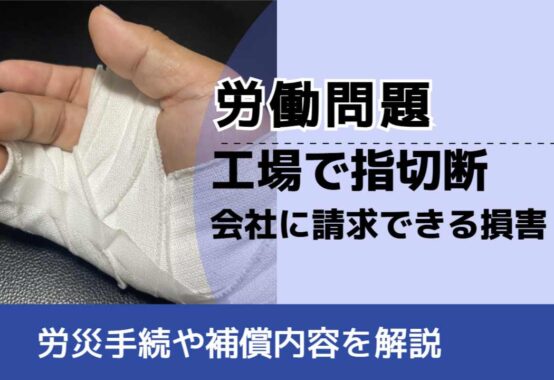仕事中の不慮の事故による打撲、もしかして労災が使えるかも?そう思っても、手続きが面倒そう、あるいは「これくらいの軽い怪我で申請しても良いのだろうか…」と、ためらってしまう方もいるかもしれません。
しかし、業務中のケガであれば、たとえ軽い打撲でも労災保険の給付対象となる可能性があります。泣き寝入りせずに、きちんと補償を受けることが大切です。
この記事では、労災申請の手続きから、気になる補償内容まで、わかりやすく徹底解説します。安心して療養に専念できるよう、ぜひ参考にしてください。
仕事中の打撲、「これくらいなら…」と我慢していませんか?
たとえ軽度な打撲だと自己判断しても、後から症状が悪化したり、実は骨折やひびが入っていたりするリスクも考えられます。勤務中や通勤中に負った怪我であれば、打撲のような軽傷であっても、労災保険給付の対象となる可能性があります。
打撲でも労災保険は使える
労災保険は、業務が原因で発生した負傷に対し給付を行う公的制度です。この制度は、怪我の程度が、軽い打撲や切り傷といった軽度なものから、骨折のような重傷に至るまで、業務上の災害であれば適用対象となります。たとえ「机の角に体をぶつけた」や「倉庫で荷物に足をぶつけた」といった、日常的に起こりうる軽微な打撲であっても、業務中に発生したものであれば、労災保険の適用を受けることができます。
「これくらいの怪我で労災を使うのは申し訳ない」と感じる方もいるかもしれませんが、軽い打撲と自己判断して放置することは、以下のようなリスクにつながることがあります。
| ・実は骨にひびが入っている可能性がある ・適切な治療の機会を逃し、症状悪化につながる |
早めに医療機関で診察を受けることで、適切な治療を受け、症状の悪化を防ぐことにつながります。労働災害による負傷で労災保険を申請することは、労働者に認められた正当な権利です。会社に遠慮することなく、ご自身の健康と安全のために、迷わず申請を検討してください。
労災を使わない(労災隠し)ことで生じるリスク
業務中の打撲を「これくらいなら」と自己判断し、労災として申請しないという選択は、労働者と会社双方にとって大きなリスクを伴います。まず、労働者側から見ると、本来労災保険で賄われるべき治療費や薬代などを、労働者自身が負担することになります。業務災害の場合、健康保険の適用は原則として認められていません。もし誤って健康保険を利用した場合、後日その費用を返還するよう求められる可能性があります。さらに、軽い打撲だと思っていた症状が、時間の経過とともに悪化したり、実は骨折や重篤な損傷が隠れていたりした場合には、治療費や休業補償の面でより大きな負担が生じる可能性があります。
一方、会社側が労働災害の発生を認識しながら報告しない「労災隠し」は、労働安全衛生法違反にあたる犯罪行為です。この行為が発覚した場合、事業主には労働安全衛生法第120条第5号に基づき、50万円以下の罰金が科せられます。罰金刑は刑事罰であり、企業の社会的信用を大きく損なうことにもつながりかねません。
このように、労災を使わないという選択は、労働者と会社双方にとって不利益をもたらします。そのため、たとえ軽度の打撲であっても、業務中に発生した怪我は速やかに会社に報告し、適切な労災申請を行うことが重要です。


労災保険の対象となる怪我の条件とは?
労災保険が適用されるのは、単に仕事中に怪我をしたというだけではありません。その怪我が「業務」または「通勤」が原因で発生したものであることが、労災認定を受けるための大前提です。業務が原因で発生した事故を「業務災害」、通勤途上で発生した事故を「通勤災害」といいます。
以下では、業務災害や通勤災害がどのようなケースを指すのか、具体的に解説していきましょう。
| 災害の種類 | 定義 |
| 業務災害 | 労働者が事業主の支配下にある状況で、業務遂行中に業務が原因で発生した災害 |
| 通勤災害 | 就業のため住居と職場との間を合理的な経路および方法で移動中に発生した災害(業務の性質を有するものを除く) |
仕事が原因で発生した「業務災害」
業務災害とは、労働者が事業主の支配下にある状態で、仕事が原因となって発生した負傷や疾病を指すものです。労災保険が適用される業務災害と認定されるためには、以下の2つの要件を満たすことが必要です。
- 業務遂行性:労働者が労働契約に基づき、事業主の支配・管理下にある状態で災害が発生したこと。
- 業務起因性(業務との因果関係があるか):業務と怪我や病気の間に因果関係があることが求められます。
これら2つの要件が認められて初めて、業務災害として労災保険の対象となります。
具体的には、作業中に機械に体をぶつけて打撲を負った場合や社内を移動中に床で滑って転倒し打撲した場合には業務災害といえます。また、休憩時間中であっても事業場の不備や欠陥により打撲した場合には業務災害となります。
これらの例のように、業務中に起きた怪我は、その多くが業務災害として扱われる可能性があります。自己判断せずに、適切な手続きを行うことが大切です。
通勤・退勤中に発生した「通勤災害」
通勤災害とは、労働者が就業のために住居と就業場所の間を、合理的な経路および方法で移動中に負傷したり、疾病にかかったりすることを指します。ここでいう「通勤」は、単に住居と職場を往復する移動だけでなく、他の就業場所への移動などが含まれます。
通勤災害に該当する具体的な事例としては、以下のようなケースが挙げられます。
- 駅の階段で転倒し、打撲を負った場合
- 会社の最寄り駅から職場へ向かう途中で自転車に衝突され、怪我をした場合
- 自転車通勤中に転倒し、負傷した場合
しかし、通勤経路を逸脱したり、移動を中断したりした場合は、原則として通勤災害とは認められません。ただし、日用品の購入、病院への通院、職業訓練の受講、親族の介護といった日常生活上必要な行為を、やむを得ない事情により、かつ最小限度の範囲で行った場合は、例外として認められます。この場合、逸脱・中断している間は通勤災害とはなりませんが、元の経路に復帰すれば再び通勤災害の対象となります。コンビニで買い物を終え、通常の通勤経路に戻った後に負傷した場合なども通勤災害と判断される可能性があります。
打撲で労災を申請する3つのメリット
「この程度の打撲で労災を申請するのは大げさではないか」「会社に迷惑をかけるのでは」と、申請をためらう方は少なくありません。しかし、業務中や通勤中に発生した打撲であれば、労災保険の申請は労働者の正当な権利であり、労災申請にはいくつかのメリットがあります。
以下では労災申請のメリットについて詳しく解説していきます。
メリット1:治療費の自己負担がゼロになる
労災保険が適用される大きなメリットの一つは、治療にかかる費用の自己負担がゼロになる点です。業務中や通勤中に生じた怪我や疾病に対し、労災保険が適用されると、診察料、検査費用、手術費用、薬代、入院費など、治療に関わる費用が療養(補償)給付として補償の対象となります。これにより、被災した労働者は金銭的な心配なく治療に専念できるという大きな安心感を得られるでしょう。
一般的な健康保険を利用した場合、通常3割の自己負担が発生しますが、労災保険ではこの自己負担が発生しない点が大きな違いです。特に打撲の治療が長引いたり、万が一、精密検査や高額な治療が必要になったりした場合でも、費用に悩まされることなく、安心して療養に集中できます。
ただし、入院時の上級部屋や個室を希望した場合の差額ベッド代や市販薬の購入費など、労災保険の適用外となる費用もあります。また、労災指定病院以外で治療を受けた場合は、一度全額を立て替える必要がありますが、後日、所定の手続きを行うことで労働基準監督署から返金を受けられます。
メリット2:仕事を休んでも収入が補償される
仕事中に負った打撲の治療のため、どうしても仕事を休まざるを得ない場合でも、労災保険の「休業(補償)給付」によって収入が補償されるという大きなメリットがあります。これは、治療に専念したい気持ちと生活費への不安の板挟みになる心配を軽減し、安心して治療に臨めるよう支える重要な制度です。
具体的には、療養のために仕事ができない状態が続く場合、休業4日目から「休業(補償)給付」と「休業特別支給金」が支給されます。この合計額は、原則として給付基礎日額の約8割に相当します(内訳は休業(補償)給付6割と休業特別支給金2割)。
・休業(補償)給付=給付基礎日額の60%×休業日数
・休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数
なお、休業開始から最初の3日間は「待期期間」と呼ばれ、この期間中は労災保険からの給付は行われません。業務災害の場合、この3日間については、事業主が労働者に対し平均賃金の6割以上の休業補償を行う義務があります。
メリット3:万が一の際に適切な補償が受けられる
軽い打撲と自己判断した場合でも、実際には骨折や神経症状といったより重い症状が後から判明したり、予期せぬ後遺症が残ったりするケースも少なくありません。例えば、治療後に手足のしびれが残る、あるいは関節の可動域が制限されるといった、日常生活や仕事に影響を及ぼす症状が現れる可能性も考えられます。
万が一、治療を続けても症状が改善せず「症状固定」と判断された時に、一定の後遺症が残ってしまった場合、労災保険から「障害(補償)給付」が支給されます。この給付は、後遺障害の程度に応じて定められた第1級から第14級までの「障害等級」に基づき決定されるものです。具体的には、第1級から第7級までは年金、第8級から第14級までは一時金として支給されます。
将来の生活や医療費の不安を軽減するためにも、業務中や通勤中の打撲であっても、万が一に備えて労災申請を行うことは、極めて重要な選択肢と言えるでしょう。
【5ステップ】打撲で労災を申請する具体的な手続きの流れ
仕事中の打撲で労災保険を申請したいと考えていても、「手続きが複雑で難しそう」「何をすれば良いのかわからない」といった不安を感じる方も少なくないでしょう。しかし、労災申請は正しい手順を踏まえれば、意外とスムーズに進められます。
以下では、打撲で労災を申請する際の具体的な手続きを、5つのステップに分けて分かりやすく解説します。
ステップ1:会社へ怪我の発生を報告する
仕事中に打撲を負ってしまった場合、たとえ軽傷だと感じても、労災申請の第一歩として、まずは会社へその発生を報告することが必須です。怪我の程度にかかわらず、直属の上司、職場の責任者、または人事・総務の担当者など、社内で定められた適切な窓口に速やかに連絡してください。この報告は、労災保険の適用を受ける上で非常に重要な手続きです。
報告する際には、以下の点をできるだけ正確かつ具体的に伝えることが大切です。
- いつ
- どこで
- 何をしている時に
- どのように怪我をしたのか
例えば、「〇月〇日の午前中に、製造ラインで作業中、機械のレバーに右足をぶつけて打撲した」といったように、状況を詳細に伝えることで、業務との因果関係が明確になり、その後の手続きがスムーズに進められます。
報告が遅れると、事故と業務との因果関係の証明が困難になる可能性があり、労災認定に支障が生じる恐れがあります。事業主には労働災害の発生を労働基準監督署に報告する義務があるため、早期の報告は会社にとっても必要な対応となります。ご自身の安全と権利を守るためにも、怪我をした際は迷わず、速やかに会社へ報告してください。
ステップ2:労災指定病院で診察を受ける【健康保険証は使わない】
会社への報告が済んだら、次に医療機関を受診しましょう。その際、原則として「労災指定病院」で診察を受けるようにします。
労災指定病院とは、労災保険の治療を行う指定を受けた医療機関のことで、労災指定病院で受診すれば、窓口での治療費支払いは不要となります。これにより、金銭的な立替をすることなく治療に専念できるでしょう。
注意すべき点は、健康保険証を使用しないことです。業務中や通勤中に発生した怪我(業務災害・通勤災害)の治療には、健康保険は適用されません。労災保険と健康保険は併用できないため、万一、健康保険を誤って使用すると、後日、医療費の返還を求められるなど、複雑な手続きが必要となる可能性があります。
お住まいの地域や診療科目から、最寄りの労災指定病院を探し、適切な医療機関で受診するようにしましょう。
ステップ3:病院へ提出する書類を準備する(様式第5号など)
労災指定病院で診察を受けたら、次に「療養の給付請求書」を準備します。この書類は、治療にかかった費用を労災保険から医療機関へ直接支払ってもらうための重要なものです。業務中に怪我をした「業務災害」の場合は「様式第5号」を、通勤中に怪我をした「通勤災害」の場合は「様式第16号の3」を使用します。災害の種類によって使用する様式が異なるため、間違えないよう十分に注意しましょう。
これらの書類は、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできるほか、会社の担当部署や最寄りの労働基準監督署でも入手できます。書類には、以下に示す項目などを正確に記入します。書類の作成にあたっては、会社の担当者が事故状況を録取した上で作成することも多くあります。
主な記入項目
- 労働保険番号
- 負傷または発病年月日・時刻
- 労働者の氏名、職種
- 災害の原因および発生状況
特に災害の発生状況は、どのような状況で何が原因となり怪我をしたのかを具体的に記載することが重要です。また、事業主による証明欄の記入も必要となるため、会社に依頼してください。
作成した書類は、診察を受けた労災指定病院の窓口へ提出します。この書類を提出すると、治療費の窓口負担がゼロとなり、金銭的な心配なく治療に専念できる仕組みです。必ず忘れずに提出し、スムーズな治療を進めましょう。
ステップ4:休業する場合は追加の書類を準備する(様式第8号など)
打撲などによる怪我で仕事を4日以上休む必要がある場合、治療費を補償する療養(補償)給付とは別に、休業中の収入を補償する「休業(補償)給付」を申請する必要があります。この給付を請求するには、追加の書類を準備する必要があります。
必要な書類は、災害の種類によって異なります。
- 業務中に怪我をした「業務災害」の場合:休業補償給付支給請求書(様式第8号)
- 通勤中に怪我をした「通勤災害」の場合:休業給付支給請求書(様式第16号の6)
これらの書類は、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできるほか、会社の担当部署や最寄りの労働基準監督署でも入手できます。
休業補償給付の請求は、様式第8号「休業補償給付支給申請書」の所定事項に記入し、事業主及び診療担当医師の証明を受けて所轄労働基準監督署長に提出します。
ステップ5:作成した書類を労働基準監督署へ提出する
これまで準備した各種請求書(様式第5号や様式第8号など)は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。例えば、療養の給付請求書は、労災指定病院を経由して労基署に提出します。他方で、休業補償給付請求書は、会社を通じて、あるいは、直接、労基署に提出します。
書類が提出されると、労働基準監督署は災害の発生状況や業務との因果関係などについて調査を行います。この調査に基づいて労災として認定されるかどうかが決定され、その結果は申請者へ通知されます。適切な補償を確実に受けるためにも、この最終ステップまで着実に行うことが重要です。
打撲の労災申請に関するQ&A
打撲による労災申請手続きや補償内容について理解を深めた上で、実際に申請する際に生じやすい具体的な疑問や不安を解消していきましょう。ここでは、多くの方が抱える疑問をQ&A形式で解説します。
Q.会社に「労災は使わないで」と言われたら?
会社から「労災保険は使わないでほしい」と依頼された場合でも、その依頼に応じる義務はありません。業務中や通勤中に負った怪我に対して労災保険を申請することは、労働者の正当な権利であり、会社の許可や同意は必要ありません。
労災保険の適用を判断するのは会社ではなく、労働基準監督署です。もし会社が労災申請を妨害する行為に出た場合、それは「労災隠し」と呼ばれる労働安全衛生法違反に該当する可能性があります。労災隠しが発覚した場合、事業主には50万円以下の罰金が科せられるなど、企業にとって大きなリスクとなります。
会社が非協力的な姿勢を示した場合でも、労働者自身が直接、会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ労災申請手続きを進めることができます。対応に困った場合や、会社との間でトラブルになった際には、弁護士に相談することも検討してください。
Q.間違えて健康保険を使ってしまった場合は?
仕事中の打撲で医療機関を受診する際に、誤って健康保険証を使用してしまっても、後から労災保険への切り替えが可能です。まずは、治療を受けた医療機関の窓口に、今回の負傷が労働災害であること、そして健康保険証を誤って使用したことを速やかに申し出てください。
その後、医療機関側を通じて「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を提出します。この際、業務災害の場合は様式第5号、通勤災害の場合は様式第16号の3を使用します。
ただし、月をまたぐなど、医療機関側での切り替えが難しいケースもあります。その場合には、健康保険に対して治療費の10割分を返還した上で、労災保険に治療費の請求をします。または、窓口負担部分は被災労働者に、健康保険負担部分は健康保険に支払うように請求することもあるようです。
いずれの場合も、速やかに適切な手続きを行うことが重要です。以下に、労災保険への切り替え手続きのパターンと提出書類をまとめます。
Q.パートやアルバイトでも労災は使えますか?
結論から申し上げますと、パート、アルバイト、派遣社員といった雇用形態に関わらず、すべての労働者は労災保険の適用対象となります。業務中や通勤中の怪我であれば、正社員と同様に補償を受けられますのでご安心ください。
労災保険は、労働基準法上の「労働者」を対象としており、雇用形態によって区別されることはありません。そのため、正社員とパート・アルバイトの間で、労災保険の適用条件や給付内容に違いが生じることはありません。
たとえ週1日の勤務や短時間勤務であっても、会社に雇われ、賃金を受け取って働く「労働者」である限り、業務中はもちろん、通勤中の怪我も労災保険で補償されます。例えば、アルバイトのシフト中に機械に足をぶつけて打撲した場合や、パートとして通勤途中に転倒して負傷した場合でも、労災保険の給付を受けることが可能です。ご自身の雇用形態を理由に申請をためらう必要はありません。
Q.申請に期限はありますか?
労災保険の給付には、種類ごとに「消滅時効」と呼ばれる期限が設けられています。この時効期間を過ぎてしまうと、原則として給付を請求する権利が失われるため注意が必要です。給付の種類によって、時効期間と、いつから時効期間を数え始めるかを示す「起算点」が異なります。
多くの給付には2年または5年の時効が設定されています。例えば、療養(補償)給付の場合、治療費を立て替えてから2年が経過すると請求できなくなります。また、休業(補償)給付は、賃金を受けなかった日の翌日から2年の時効期間となります。他方で、障害補償給付は、症状固定日の翌日から5年となります。
このような時効の期限を過ぎてしまわないためにも、仕事中に打撲などの怪我を負った際は、たとえ症状が軽くても速やかに会社へ報告し、労働基準監督署への申請手続きを始めることが非常に重要です。
| 給付の種類 | 時効期間 | 起算点 |
| 療養(補償)給付 | 2年 | 療養の費用を支払った日の翌日 |
| 休業(補償)給付 | 2年 | 賃金を受けなかった日ごとにその翌日 |
| 障害(補償)給付 | 5年 | 傷病が「症状固定」した日の翌日 |
労災事故の問題は難波みなみ法律事務所へ
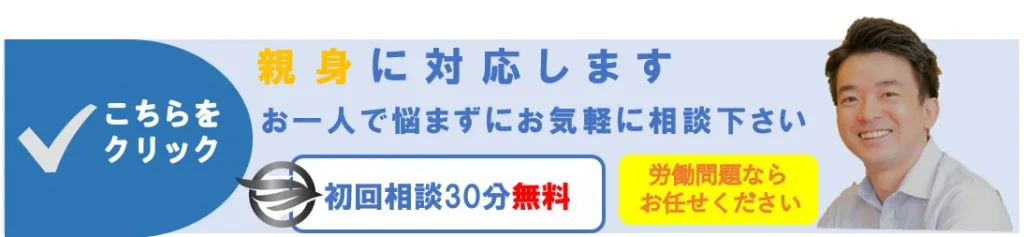
仕事中に負った打撲は、「これくらいなら大したことはない」と自己判断してしまいがちです。しかし、業務中や通勤中に発生した怪我であれば、たとえ軽傷の打撲であっても、労災保険の給付対象となる可能性があります。労災保険を適切に利用することは、被災した労働者の権利です。治療費の自己負担がなくなるだけでなく、休業期間中の収入補償や、万が一後遺症が残った場合の障害補償など、多くのメリットを享受できる重要な制度です。
万が一、会社が労災申請に非協力的な姿勢を示す場合や、手続きに不安を感じる場合は、一人で悩まずに弁護士へ相談することが解決への近道です。
初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。