通勤中や業務中に災害が起きて治療が必要となった場合、労災保険から治療費や休業損害について給付があります。このように、労災保険の給付は労働者の権利ですが、なかには「会社に迷惑をかけるかもしれない」などといった理由で、申請せず全額負担してしまうケースもあるでしょう。
たしかに、労災の発生はとくに会社にとって不都合なことですが、被災労働者が保険の給付を受けない(労災の報告をしない)ことによるデメリットは非常に大きいといわざるを得ません。ごく軽い症状であっても、ここで紹介することを踏まえて、遠慮なく保険を利用しましょう。
労働者側が負う労災申請のデメリット
通勤中または業務中に怪我を負った人(労働者)が労災の申請で不安に思うのは、申請手続きが面倒であることや、勤め先の会社との関係が悪くなることです。
具体的には、次のようにいえます。
申請手続きや書類準備が負担になる
労災保険の給付を受けるときは、被災した労働者自身で所定の請求書を作成し、労働基準監督署や医療機関へ提出する手続きが必要です。給付の種類によって、提出する書類の様式は異なります。
労災を申請するための書類は、治療を始めるときに1通出せば済むというものではありません。休業補償としての給付や、後遺障害が残ったときの給付など、必要な補償の種類ごとに事業主の証明を受けて申請書類を出す必要があります。
労災保険の給付を受けるための申請や、そのための書類の準備は、労働者側の負担、すなわちデメリットのひとつとして感じられることが多いでしょう。
会社と気まずい関係になるかもしれない
労働災害が起きてしまうと、働く人の多くは「会社に迷惑をかけてしまった」と考えがちです。雇用する事業主の視点では、実際に
- 労働基準監督署が行う調査の対応が必要になる
- 労災保険率または労災保険料額が上がる
といったデメリットが発生するため、労災の発生はなるべく避けたいと考える場合もあります。
こうした背景から、労働者が申請を躊躇したり、会社からのプレッシャーを感じやすくなったりするのは事実です。
とはいえ「労災=事業主にとってデメリットとなる事象」が発生したからといって、被災した労働者を不当に扱うことは、法律で禁止されています。
少なくとも療養期間とその後の30日間は解雇できず、労災を理由とする不利益な取扱いは権利濫用にあたると考えられるのです(労働基準法19条)。
通勤中または業務中に事故に遭ったときの労働者の権利は、基本的な労働法や保険制度によって守られています。気後れせず、自分の生活を考えて最善の方法を選びましょう。


使用者(事業主)が負う労災申請のデメリット
働く人が懸念するように、労災の発生は使用者(事業主)のデメリットにつながります。具体的には、保険料率が増加する可能性のほか、取引への影響が挙げられます。
労災保険料の負担が増加する場合がある
労災発生により事業主が負う可能性があるデメリットは、労災保険料率または労災保険料額の上昇です。
事業場の過去3年間における労働災害の発生状況、具体的には労災保険の給付額と保険料の比率(収支率)に応じて、労災保険料率は一定の範囲内で増減します。これをメリット制といいます。下記の条件のいずれかに当てはまる事業には、メリット制が適用されます。
メリット制の適用される条件
常時100人以上の労働者を使用している
常時20人以上100人未満であって、災害度係数が0.4以上である
メリット制が適用される事業場では、労働災害が多発し保険給付額が増えると、労災保険料率が最大40%割増しされる可能性があります。
公共工事の入札参加資格などに影響が出ることがある
労働災害が発生すると、企業の安全管理体制に問題点があると判断され、取引で不都合が生じる可能性があります。
建設業界を中心によくあるのは、重大な労災事故を理由に「指名停止処分」を受けて、公共工事の入札に参加できなくなる問題です。
法的責任を問われ損害賠償請求に発展するケースがある
労災発生について事業主に落ち度(安全配慮義務違反など)があり、労災保険の給付条件である「労災認定」があると、保険給付とは別に損害賠償請求される可能性が大きくなります。
損害賠償請求に応じなければならないのは、損害額のうち保険給付では賄えない部分のみです。とはいえ、多くは高額になります。支払義務を負うのは、労働者の精神的苦痛に関する損害(慰謝料)の全額や、重度後遺障害による損害などとなるためです。
なお、厳密には、労災認定の有無が損害賠償義務の大きさに繋がるわけではなく、労働災害であるという認定が損害賠償義務の有無についてのひとつの証拠となります。
企業の社会的評判が低下するリスクがある
労働災害が発生すると、企業は「従業員の安全を軽視している」「ブラック企業ではないか」といったネガティブなイメージを持たれかねません。とくに、SNSでの情報拡散やメディア報道により、企業のブランド価値が大きく損なわれるケースも少なくありません。
このような評判の低下は、企業の採用活動にも深刻な影響を及ぼします。求職者は企業の評判をインターネットで入念に調べるため、労災に関する情報が拡散されると、応募者の減少や優秀な人材の確保が困難になる可能性があります。
また、安全管理体制への信頼が揺らぐことは、取引先や金融機関からの信用失墜にもつながります。コンプライアンスを重視する企業が増える中、労災発生によって安全体制に問題があると判断されれば、既存の取引が停止されたり、新規の契約が結べなくなったりする恐れもあります。
働く人(労働者)が労災保険を利用するメリット
労災保険を利用して給付を受けるメリットは、経済的な面で非常に大きいといえます。給付額についても、基本的には規定の額となり、労働者に過失があったとしても減額されません。
メリット1:治療費・治療中の損害・後遺障害を負った場合について補償がある
労働災害で負った怪我の治療費について、労災保険から療養(補償)給付や、療養の費用の給付を受けることができれば、自己負担ゼロで治療を受けられます。
労災保険で補償されるのは、治療費だけではありません。治療のため仕事を休むことによる給与の減少分(休業補償)や、後遺障害を負ったときの補償(障害補償)など、それぞれ手厚い保障があります。
下の表にあるのは、労災保険の給付内容です。
| 療養(補償)等給付 | 必要な療養費の全額 |
| 休業(補償)等給付 | 休業4日目移行、1日につき給付基礎日額の60% |
| 障害(補償)等給付 | 障害の程度に応じた一時金または年金一時金:給付基礎日額の101日分〜503日分年金:給付基礎日額131日分〜313日分+特別支給金、特別年金 |
| 遺族(補償)等給付 | 遺族の数に応じた一時金または年金一時金:給付基礎日額の1,000日分年金:給付基礎日額の153日分〜245日分+特別支給金、特別年金 |
| 葬祭料・葬祭給付 | 原則として315,0001円に給付基礎日額の30日分を加えた額 |
メリット2:本人に過失があっても補償は減額されない
労災保険が持つ大きな特徴の一つに「無過失責任」があります。これは、災害の原因が労働者本人の不注意(過失)によるものであって、会社側に過失がなくても、原則として労災保険からの補償額が減額されないという考え方です。
たとえば、
l 業務中に急いでいて足下を確認せず、転倒した
l 慣れた作業だと思い、安全確認を怠ったせいで怪我をした
といったケースでも、業務が原因で発生した災害であれば、保険給付は全額行われます。
もっとも、労働者が自ら災害を発生させようとした場合(自傷行為など)や、極めて重大な過失があった場合には、給付が制限される可能性もあります。とはいえ、発生した労災についてこのような認定がされることは非常に少なく、基本的には安心して保障を受けられます。
労災隠しをしたときのデメリット
働く人が労災保険の申請をしない場合、多額の経済的損失だけでなく、復帰した後の生活にも悪影響を及ぼすかもしれません。会社側は「労災隠し」を法律で禁止されており、違反すると罰則があります。
会社との関係や労災発生の状況がどうであれ、ここで解説するデメリットを踏まえて、双方きちんと災害への対応を心がけましょう。
治療費が全額自己負担になる
業務中や通勤中に発生した怪我や病気には、健康保険は適用されません。健康保険も労災保険も利用しなかった場合、治療費の自己負担率は100%です。
労災発生後の治療において、手違いで健康保険を適用できたとしても、後日、加入している健康保険組合から給付分の返還請求がなされ、結果として全額自己負担となってしまう可能性があります。
有給休暇の残日数を消費してしまう
本来、労災保険を利用すれば、労災保険から休業補償を受けることができますが、労災保険を使用しなければ、休業期間中の補償を受けることができません。そのような状況を避けるために有給休暇を取得することがあります。そのため、労災保険を利用しない場合、本来消化する必要のない有給休暇を消化しなければならない状況に陥る可能性があります。
また、有休を取得した日は休業補償給付を受けられません。そのため、後で労災保険の給付申請をしたとしても、消費した有休が戻ってくるわけでも、二重に給与を受けられるわけでもありません。
時効で保障されなくなるリスクがある
労災保険の給付申請は後からでも可能ですが、一定期間が経つと時効により申請できなくなります。
労災保険の給付のなかでも、治療費や休業損害を対象とする給付は、2年で請求時効を迎えます。給付の種類により請求時効が長くなることもありますが、最大で5年です。
| 給付の種類 | 時効期間 | 起算日 |
| 療養(補償)給付 | 2年 | 療養に要する費用の支出が具体的に確定した日の翌日 |
| 休業(補償)給付 | 2年 | 休業日の翌日 |
| 障害(補償)給付 | 5年 | 傷病が治ゆ(症状固定)した日の翌日 |
| 遺族(補償)給付 | 5年 | 労働者が死亡した日の翌日 |
| 葬祭料・葬祭給付 | 2年 | 労働者が死亡した日の翌日 |
| 介護(補償)等給付 | 2年 | 支給事由が生じた月の翌月の初日 |
「労災隠し」と判断されれば会社が罰則を受ける
労災隠しとは、労働者が労災などによって死亡または休業したとき、事業主が労働基準監督署長への提出が義務付けられている「労働者死傷病報告書」を故意に提出しなかったり、虚偽の内容で報告したりする行為を指します。
労働者死傷病報告書を適切に提出しない場合、その事業主には50万円以下の罰金が科されます(労働安全衛生法第120条第5号)。
労災申請で迷ったら?手続きの流れと困ったときの相談先
労災の申請を検討されている方の中には、「具体的に何から始めればよいのか」「会社が協力してくれない場合はどうすればいいのか」といった不安から、手続きになかなか踏み出せない方も少なくありません。特に、労災申請は被災された方やご遺族自身で行う必要がある場合もあり、その手続きの複雑さに戸惑うこともあるでしょう。
以下の項目では、労災申請の基本的な流れ、会社が協力してくれない場合の具体的な対処法を解説します。
労災に遭ったときの対応のポイント
労災に遭ったときの対応では、その後の保険給付の手続きなどのため、押さえておきたいポイントがあります。ここでは、働く人(労働者)の側から「とっさの対応で何をすればいいのか」を押さえましょう。
労働者の初期対応のポイントとして、労災で怪我などを負った人が意識したいのは、
1. すぐに会社に報告すること
2. 労災保険指定医療機関を受診すること
の2点です。
会社への報告のタイミングは「労災発生後すぐ」です。時間が経つと、発生当時の状況がわからなくなり、労働災害かどうか証明するのも難しくなります。報告は「いつ・どこで・どのような状況で」とのように詳しく伝えることで、後の手続きがスムーズになります。
次に重要なのは、治療費の立替えを避けるため、労災保険指定医療機関を受診することです。指定医療機関でない病院を受診するケースでは、いったん治療費を全額自己負担し、後に給付金を受け取ることになります。指定医療機関では、医療機関に直接治療費の給付が行われるため、手持ち金がない場合でも安心です。
会社が労災の申請手続きに協力してくれない場合の対処法
労災申請は労働者自身の権利であり、上司や承認は必須ではありません。仮に会社が事業主証明などを拒否した場合でも、被災された労働者本人が、自分で勤務先を管轄する労働基準監督署に請求書を提出できます。
労災保険の請求書は、事業主証明欄が空欄のままでも受理されます。このとき、あらかじめ会社に事業主証明を拒否した理由を問い合わせ、その理由を明記した「証明拒否理由書」を請求書に添付すると、手続きがより円滑に進みます。
労働基準監督署に相談する
労災申請に関して疑問や不安がある場合は、労働基準監督署に相談することを検討します。
ご自身の勤務する場所を管轄する労基署(検索するときはこちら)に相談すると良いでしょう。
会社に労働組合があるのなら、組合の窓口で相談することで、労災保険の申請について手続きの支援を受けられることがあります。
弁護士に相談する
弁護士は、被災した労働者の代理人として、その利益を最大化するために活動します。弁護士が会社との交渉を代行し、労災事故の損害賠償請求のプロセスを全面的にサポートします。
とくに、労災保険の給付だけではまかなえない損害を会社側に請求するときは、弁護士の支援が不可欠です。会社に損害賠償の支払いを求める場合には、調停や訴訟に発展する可能性を踏まえた対処が必要となるためです。
まとめ|労災保険の給付は労働者の権利!会社のためにも遠慮なく申請しよう
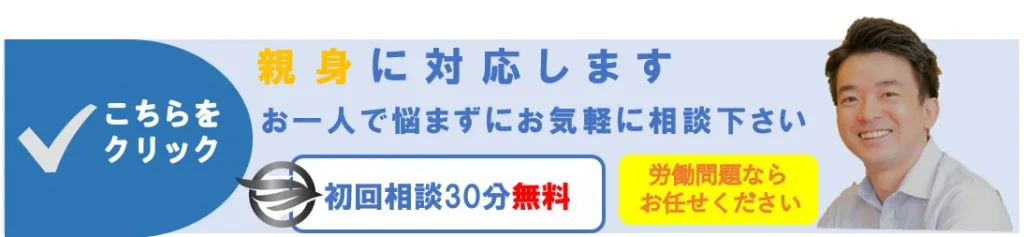
労災保険の給付は手厚く、治療費だけでなく、休業中の給与や後遺障害を負った場合の補償も対象となります。保険の申請は労働者の権利ですので、十分な補償を受けるためにも積極的に利用するべきです。
万が一、協力してくれないのであれば、労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。とくに、治療がある程度長引くような怪我である場合は、弁護士の支援があると安心です。



























































































