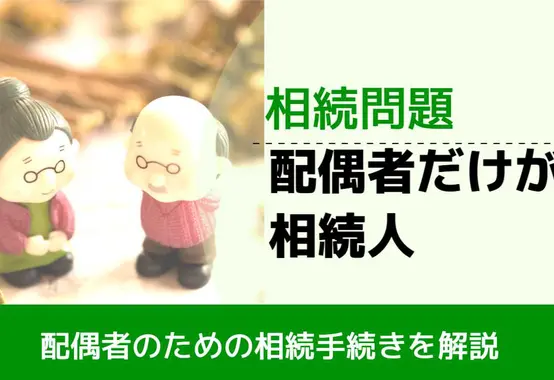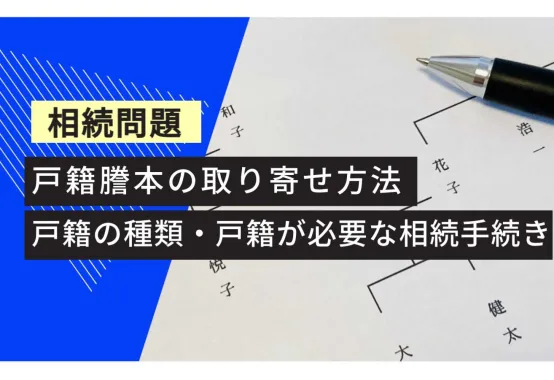大切な人を失った悲しみの中で、遺産相続の手続きに直面することは想像以上に大変なことです。特に、妻が先に他界した場合、夫として何をすべきか、どのような手続きが必要なのか、不安や戸惑いを感じる方も多いでしょう。
そこで、この記事では、弁護士の視点から妻の遺産相続における夫の相続手続きと注意点について詳しく解説します。この記事を読むことで、妻の相続手続きの全体像を把握し、必要な準備や手順を理解することができます。
妻が他界した場合の相続人と相続分
妻が他界した場合、法定相続人と法定相続分は民法に基づいて決定されます。以下において詳細に解説していきます。
子供がいる場合
子供がいる場合、配偶者である夫と子供が相続人となり、夫が2分の1、子供が残りの2分の1を相続します。複数の子供がいる場合は、その2分の1を人数で均等に分けることになります。また、子供には、夫の子供だけでなく、前夫の子供など、夫以外の男性との子供や血縁関係のない養子も含まれます。
ただし、これはあくまで法定相続分は一つの基準であり、遺言書や相続人間の話し合いによって具体的な相続分を変更することが可能です。
子供が他界しているが孫がいる場合
子供が先に他界しているものの、その子供の子供、つまり、孫がいる場合、代襲相続が適用されます。
代襲相続は、相続人であった子供に代わって、その子供(被相続人の孫)が相続権を引き継ぐ制度です。代襲相続により、孫は親が受け取るはずだった相続分を受け取ることができます。
例えば、妻に子供が2人いたが、1人が先に他界し、その子供(孫)が2人いる場合、相続分は以下のようになります。夫が2分の1、生存している子供が4分の1、そして先に他界した子供の2人の子供(孫)がそれぞれ8分の1ずつ相続することになります。
子はいないが、両親が存命である場合
子供がいない場合でも、妻の両親が存命である場合、妻の両親と夫が共同相続人となります。この場合、法定相続分は夫が3分の2、妻の両親が3分の1となります。ただし、妻の両親の相続分は父母で均等に分けられるため、それぞれが6分の1ずつ相続することになります。
子・両親ともにいないが、兄弟姉妹がいる場合
妻に子供や両親がいない場合、妻の兄弟姉妹も法定相続人となります。この場合、兄弟姉妹が均等に相続することになります。また、兄弟姉妹の中に既に他界している人がいる場合、その子供(妻の甥や姪)が代襲相続人となります。ただ、代襲相続は兄弟姉妹の子供までに限定されており、孫以降には適用されません。
法定相続分は、夫が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となり、兄弟姉妹が複数人いる場合には、4分の1の相続分を人数に沿って割り振られます。
内縁の夫は相続人とはならない
内縁関係にある夫婦は法律上の夫婦ではないため、内縁の夫は妻の法定相続人とはなりません。事実上の夫婦生活を長期間にわたって営んでいたとしても、法律婚でなければ相続権は発生しません。
ただし、内縁の夫が妻の財産を相続できる可能性が全くないわけではありません。妻が生前に遺言書を作成し、内縁の夫を受遺者として指定していれば、遺贈という形で財産を受け取ることができます。また、妻に法定相続人がいない場合、特別縁故者として家庭裁判所に相続財産の分与を申し立てることも可能です。


夫が妻の遺産を全て相続するためには
夫が妻の遺産を全て相続するためには、いくつかの方法があります。
夫のみが相続人である場合
夫のみが相続人である場合、妻の遺産は全て夫に相続されることになります。子供や他の親族がいない場合、夫は単独相続人として妻の財産を全て相続することができます。
遺言書を作成する
遺言書は、妻が夫に対して、全財産を相続させるための方法の一つです。
遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
妻が遺言書を作成することで、夫は他の相続人と遺産分割協議をしなくても済むようになるだけでなく、遺産の全てを受け取ることができます。
ただし、他の相続人が妻の子供や両親である場合には、他の相続人の遺留分を考慮する必要があり、完全に他の相続人の権利を奪うことはできません。一方で、他の相続人が妻の兄弟姉妹や甥・姪である場合には、兄弟姉妹らには遺留分は認められていないため、遺言を作成することで夫に全遺産を承継させることができます。
相続人間の話し合いによる遺産分割協議をする
夫以外に相続人がいて、遺言書も作成していない場合、夫が妻の遺産全てを受け取るためには、相続人との話し合いをする他ありません。
他の相続人が、全遺産を夫が取得することに異論がなければ、夫は全遺産を受け取ることができます。しかし、他の相続人全員が同意しない場合には、他の相続人にも遺産を分配しなければなりません。
ただし、話し合いが難航する場合もあります。その際は、弁護士や専門家の助言を求めたり、家庭裁判所での調停や審判を検討することも選択肢となります。
二次相続に注意しておく
夫が妻の遺産のすべてを受け取る場合には、二次相続に注意しなければなりません。
二次相続は、夫が妻の遺産を相続した後、夫が亡くなった際に発生する相続のことを指します。
夫が妻の遺産を取得する場合、配偶者の税額軽減があるため、夫の税負担は大幅に軽減されます。
しかし、夫がその後亡くなった際には、配偶者控除のような制度がないため、夫の相続人に生じる税負担がかなり大きくなることがあります。そのため、妻の相続に際しては、二次相続時の税負担を踏まえながら、夫が全ての遺産を取得するべきかを検討する必要があります。
夫が妻の遺産を相続する時の手続き
妻が他界した場合、夫が遺産を相続するためには様々な手続きを進めていく必要があります。
必要となる手続きを適切に行うことで、夫は妻の遺産を円滑に相続することができます。
戸籍謄本を取り寄せて相続人を確定する
妻が亡くなった後の相続手続きにおいて、戸籍謄本の取り寄せは非常に重要な最初のステップです。
戸籍謄本は、相続人を確定するための公的な文書として機能します。まず、妻の出生から死亡までの戸籍謄本の取り寄せをします。その上で、夫以外の相続人の現在戸籍を取り付けます。代襲相続が発生する場合には、死亡した相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せます。
これらの戸籍謄本を漏れなく取り付けることで、法定相続人全員を正確に把握することができます。相続人を見落としたり、誤って相続人でない人を含めたりすると、後々トラブルの原因となる可能性があるため、弁護士のアドバイスを受けながら進めることが賢明です。
遺言の有無を確認する
妻が遺言書を作成している場合には、遺言執行により遺産を承継することができるため、夫は他の相続人と遺産分割協議をする必要がなくなります。
そのため、妻の遺言書を確認する必要があります。自筆証書遺言であれば、自宅内や貸金庫、法務局などで保管されている可能性があります。また、公正証書遺言についても、自宅内で正本や副本が保管されている可能性もありますし、原本は公証役場にて保管されています。
遺言が作成された痕跡がある場合には、心当たりのある場所を探してみましょう。
妻の遺産を調査する
妻の遺産を調査した上で、遺産目録を作成することが重要です。遺産目録には預貯金、不動産、有価証券、債務など、妻が所有していたすべての資産を含める必要があります。預貯金については、妻名義の口座を確認し、金融機関に残高証明書の発行を依頼します。
不動産は登記簿謄本を取得し、固定資産税評価証明書も入手します。
株式や投資信託なとの金融資産は証券会社に問い合わせ、残高証明や取引履歴を取り寄せします。
負債についても調査が必要で、住宅ローンや個人的な借入金などを確認します。これらの調査を通じて、正確な遺産の全体像を把握することができ、公平な相続手続きの基礎となります。
相続人間の遺産分割協議をする
相続人間での遺産分割協議は、妻の遺産相続において重要なステップです。
この協議では、相続人全員が合意のもと、遺産の分配方法を決定します。
まず、相続人全員の連絡先を確認した上で、遺産分割の意向を確認します。遺産分割協議は、相続人全員が一堂に会する必要まではありません。個別に意向を確認していき、合意形成を図ることも認められます。また、感情的な対立を避けるため、中立的な立場の弁護士や専門家を交えることも有効です。
遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、全員が署名・押印します。この書類は法的効力を持ち、相続登記などの手続きに必要となります。将来のトラブル防止のため、決定事項を詳細に記載しておくことが重要です。
話合いが難航すれば遺産分割調停を申し立てる
遺産分割協議が難航し、相続人間で合意に至らない場合、遺産分割調停を申し立てることが解決策となります。
遺産分割調停は家庭裁判所で行われ、中立的な調停委員が相続人間の話し合いを仲介します。
調停手続では、各相続人の事情や希望を考慮しながら、公平な遺産分割案を模索します。調停で合意が成立すれば、それは裁判所の調停調書として法的効力を持ちます。合意に至らない場合は、遺産分割審判へ移行することになります。
遺産分割調停は、話し合いによる解決が難しい場合の有効な手段ですが、弁護士のサポートを受けながら進めることが望ましいでしょう。
相続税申告をする(申告期限)
相続税申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
相続税の申告期限は厳格に定められており、この申告期限に遅れると加算税や延滞税が課される可能性があるため注意が必要です。
仮に、申告期限までに遺産分割協議ができない場合には、法定相続分で相続したものとして相続税の申告と納税をします。これを未分割申告といいます。その後に遺産分割が成立した場合に改めて相続税申告をすることになります。
妻の相続で夫の相続税はかかるのか?
妻の遺産を相続する際、夫に相続税がかかるかどうかは遺産額や相続人の人数によって異なります。以下では、妻の相続時における相続税の税負担について解説します。
基礎控除額以下なら申告義務はない
相続税の申告義務は相続財産の総額によって決まります。遺産額の総額が基礎控除額以下の場合、夫は相続税の申告をする必要がありません。
基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。例えば、法定相続人が夫と子供2人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。相続財産がこの金額を下回れば、相続税の申告は不要です。
また、相続税の申告義務がなくても、遺産を受け取るための相続手続きは必要です。戸籍謄本の取得や遺産分割協議など、他の相続手続きは滞りなく進めることが重要です。
配偶者の税額軽減制度
配偶者の税額軽減制度は、夫婦の一方が亡くなった際に、残された配偶者の生活の安定を図るために設けられた制度です。
により、配偶者が実際に取得する財産が、法定相続分に相当する金額または1億6000万円のいずれか大きい額までは、相続税が課税されません。
ただし、この制度を利用するためには、配偶者が相続税の申告期限内に遺産分割を終え、実際に財産を取得している必要があります。つまり、未分割申告の場合には利用できません。
ただし、相続開始後3年以内に遺産分割を終えた場合には、税額軽減の対象とすることができます。
子供がいない夫婦の相続でよくある問題
子供がいない夫婦の場合、相続に関して特有の問題が発生することがあります。
相続トラブルを避けるためには、夫婦間で事前に遺言書を作成しておくことが有効です。遺言書があれば、夫の意思を尊重した相続が可能となり、トラブルを未然に防ぐことができます。
以下でよくある問題について解説します。
疎遠になっている妻の兄弟姉妹との話し合いが難航する
妻の兄弟姉妹との関係が疎遠になっている場合、遺産分割の話し合いが難航することがあります。夫婦に子供がおらず、妻の両親も他界している場合には、妻の兄弟姉妹が相続人となります。
特に疎遠となっている妻の兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹が相続権を強く主張し、夫の希望する遺産分割案に頑なに拒否することで、感情的な対立を招き、話し合いが平行線をたどることもあります。
話し合いが難航し、合意形成が困難な場合は、家庭裁判所による遺産分割調停を申し立てることもできますが、調停でも解決ができないことも珍しくありません。
最終的に調停でも解決しない場合は、遺産分割審判に移行することになりますが、妻の相続手続の解決までに、多くの手間と時間を必要とすることになります。
兄弟姉妹の人数が多く話し合いが停滞する
妻の兄弟姉妹の人数が多い場合、遺産分割協議が複雑化し、話し合いが停滞するケースが少なくありません。多数の相続人が関わることで、意見の調整や合意形成が困難になりやすいためです。
相続人が多数に上る場合、意見をまとめる代表者を選任してもらい、効率的に話し合いを進めることが重要です。また、関心度の高くない相続人から順に相続分の譲渡を受けるなどして、相続手続きを進めていくことも有用です。
所在不明な兄弟姉妹がいる
妻の遺産相続において、所在不明な兄弟姉妹がいる場合は、相続手続きが複雑化する可能性があります。
このような状況では、まず不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。選任された管理人が所在不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加することで、手続きを進めることができます。
また、相続人の所在が長期間不明の場合は、失踪宣告の申立てを検討することも一案です。失踪宣告が認められれば、その相続人は死亡したものとみなされ、相続手続きを簡略化できる可能性があります。
さらには、遺産分割審判において、公示送達という特殊な送達手続を利用することで、相続手続を、進めることも可能となります。
妻の相続手続は難波みなみ法律事務所へ

妻の遺産をスムーズに受け取るためには、遺言の作成が非常に重要です。遺言がなければ、相続人との遺産分割協議が必要となり、多くの手間と時間を要することがあります。特に相続人が兄弟姉妹の場合には、手続きが複雑化することは珍しくありません。
相続に関する問題は複雑であり、弁護士のアドバイスを受けることで、円滑な相続手続きを進めることができるでしょう。
初回相談30分を無料で実施しています。
面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
お気軽にご相談ください。
対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。