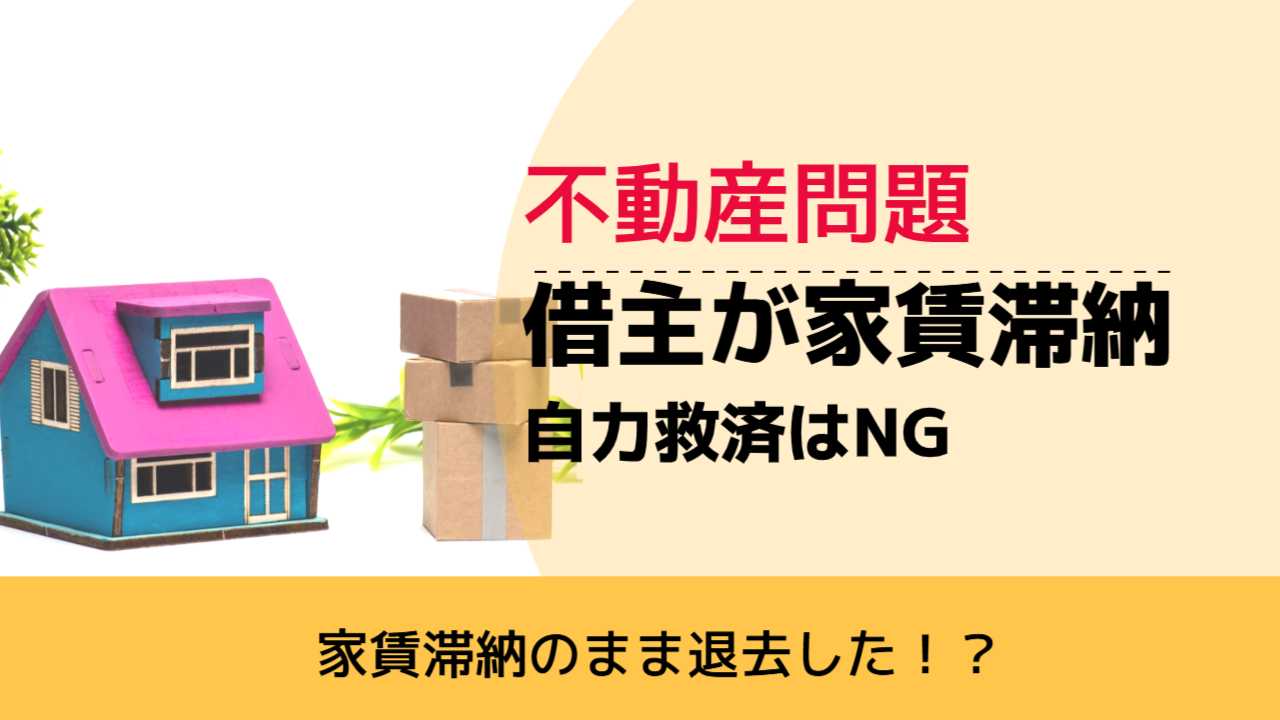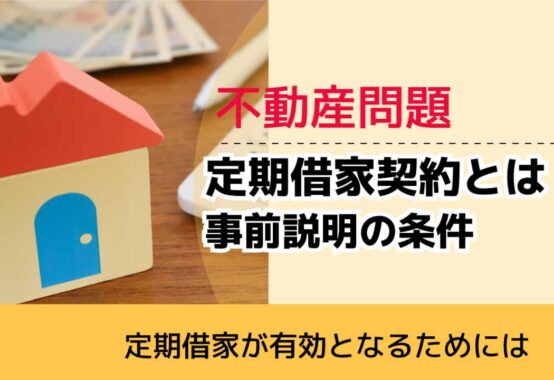賃貸経営において、入居者の家賃滞納は大きな悩みの種です。さらに、家賃の滞納をしたまま退去されてしまうと、オーナーに大きな負担が生じます。
「泣き寝入りするしかないのか…」と諦める前に、まずはオーナーとしてどのような法的措置を講じることができるのかを知っておきましょう。
本記事では、家賃を滞納した入居者が退去してしまった場合に、オーナーが取るべき具体的な対応と、未払い家賃を回収するための手順を解説します。ぜひご参考にしてください。
入居者が家賃を滞納したままいなくなったら?まずやるべきこと

賃料の入金がなく、入居者と連絡が取れない状況で、焦って無断で部屋に立ち入ったり、残された私物を勝手に処分したりすることは絶対に避けるべきです。これらの「自力救済」行為は法律で固く禁じられており、オーナー側が不法行為として逆に訴えられてしまうリスクがあるためです。
まずは冷静に、法的な手順に沿って対応を進めることが重要です。以下の項目では、このような状況に直面した際に最初に行うべき事項について詳しく解説します。
無断退去でも賃貸契約は継続している
入居者が一方的に連絡を絶ち、部屋を空けた状態であっても、賃貸借契約は自動的に終了することはありません。法的には、貸主と借主双方の合意による「解約手続き」が行われるか、または貸主からの有効な「契約解除通知」に加え、借主による「物件の明け渡し」が完了することが必要です。
契約が継続している間、オーナーは滞納している家賃を請求し続ける権利を有しますが、同時にその部屋を新たな入居者に貸し出すことはできません。これは、現在の賃貸借契約が存続している限り、借主はその物件を使用収益する権利を有しているためです。したがって、未払い家賃の回収や室内に残された残置物の処理といった次のステップに進むためには、まず法的な手順を踏んで現在の契約を解除することが不可欠となります。
室内の無断立ち入りと残置物の勝手な処分はNG
入居者が不在の場合でも、賃貸借契約が続いている限り、部屋の使用収益権は入居者にあります。そのため、オーナーが合鍵を使い、無断で室内に立ち入る行為は、刑法130条の「住居侵入罪」に当たる可能性があります。
さらに、室内に残されている入居者の私物、いわゆる「残置物」の所有権は、依然として元入居者に帰属します。オーナーがこれを勝手に廃棄したり、売却したりする行為は、「自力救済の禁止」という法原則に反する違法行為です。無断で残置物を処分した場合、「器物損壊罪」や「窃盗罪」に問われるだけでなく、後から元入居者から損害賠償を請求される可能性もあります。
これらの行為は、かえってオーナーが法的なトラブルに巻き込まれる原因となりますので、絶対に行わないよう注意が必要です。
連帯保証人・家賃保証会社に連絡し状況を伝える
入居者と連絡が取れない場合、次に連絡すべき相手は、賃貸借契約書に記載されている連帯保証人、または入居者が加入している家賃保証会社です。これらの関係者への連絡は、滞納家賃の回収に向けた重要な第一歩となります。
連帯保証人や保証会社に対して滞納家賃の支払いを請求します。連帯保証人は、2020年の民法改正により「極度額」の定めが必要となりましたが、その範囲内で元金に加えて利息や遅延損害金、違約金など、入居者と同等の支払い義務を負うものです。一方、家賃保証会社は、入居者との保証委託契約に基づき、滞納家賃をオーナーへ代位弁済する義務があります。


滞納家賃を回収するための具体的なステップ
入居者と連絡が取れない、または滞納家賃の支払いに応じない場合、オーナーは法的な手続きを通じて滞納家賃の回収と物件の明渡手続を進めていく必要があります。
自力での解決(自力救済)は法的に認められておらず、かえってトラブルを招く可能性もあるため、適切な手順を踏むことが重要です。
以下では、それぞれのステップについて、具体的な進め方や注意点を詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
内容証明郵便で支払いと契約解除の通知
家賃滞納が続く場合、法的な回収手続きの第一段階として内容証明郵便を送付します。内容証明郵便とは、「いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が公的に証明してくれるサービスです。内容証明郵便は、後の訴訟において重要な証拠となるほか、入居者に対して支払いを促す強力な心理的プレッシャーを与え、支払いを促す効果も期待できます。本格的な法的措置へ移行する前の最終通告としての役割も果たします。
内容証明郵便で送る通知書には、以下の項目を明確に記載してください。
- 滞納家賃の総額と具体的な内訳
- 滞納家賃の支払い期限(一般的には1週間程度の「相当な期間」を設定)
- 期限内に支払いが確認できない場合、賃貸借契約を解除する旨の明確な意思表示
通知書の文面に不備があると法的な効力が損なわれるおそれがあるため、弁護士などの専門家に作成を依頼することが、より確実で安心です。
訴訟提起し、家賃回収と部屋の明け渡しを求める
内容証明郵便による督促にも応じない場合、最終的な法的手段として「建物明渡請求訴訟」を提起することになります。
この訴訟の主な目的は、滞納された家賃の支払いを法的に命じる判決を得ることに加えて、同時に物件の明け渡しを強制的に実現することです。これにより、賃貸人と賃借人との信頼関係が破壊されたと裁判所に認められれば、賃貸人の請求が認められる判決が下されます。
また、入居者が行方不明で連絡が取れない場合であっても、訴訟手続きを進めるための「公示送達」という制度があります。これは、裁判所の掲示板に訴状の内容を一定期間掲示することで、借主に書類が送達されたとみなす手続きです。
建物明渡請求訴訟は、専門的な法律知識と複雑な手続きが伴うため、弁護士などの専門家に依頼することが一般的で、確実な解決に繋がります。
判決後に強制執行により財産を差し押える
裁判で勝訴したにもかかわらず、入居者が滞納家賃を支払わない場合や任意に明け渡しに応じない場合には、最終手段として「強制執行」を裁判所に申し立てることができます。強制執行とは、確定判決などの「債務名義」に基づき、強制的に判決の内容を実現させる法的手続きです。この手続きは、地方裁判所や執行官に申し立てを行い、手続きを進めます。
滞納家賃の回収のため、債務者である借主の財産を差し押さえます。差し押さえの対象となる財産は多岐にわたります。
- 給与債権(原則として手取り額の4分の1まで)
- 預貯金
- 動産(車、貴金属など)
- 不動産(土地、建物など)
しかし、差し押さえるべき財産が見つからない場合、債権回収が困難になるリスクもあります。費用倒れにならないよう、事前の財産調査が重要です。
夜逃げ後の残置物(私物)を合法的に片付けるには
入居者が夜逃げし、部屋に家財道具などの「残置物」が残されていたとしても、その所有権は依然として元入居者にあります。この残置物を合法的に片付けるには、建物明渡請求訴訟を経て「強制執行」の手続きを取る必要があります。後々大きな法的トラブルに発展するリスクがあるため、必ず法律に基づいた適切な手続きを踏むことが重要です。
残置物の所有権は元入居者にあることを理解する
入居者が夜逃げのように退去し、室内に家財道具などの私物(残置物)が残されていたとしても、その所有権は元入居者にあります。これは法の大原則であり、たとえオーナーがそれらを「ゴミ」や「価値のないもの」と判断した場合でも、勝手に処分することは認められません。
無断で残置物を廃棄・処分する行為は、元入居者の所有権を侵害するだけでなく、器物損壊罪に問われたり、損害賠償を請求されたりするといった法的リスクを招くおそれがあります。
これらの法的リスクを確実に回避し、残置物を合法的に片付けるためには、次の項目で詳しく解説する強制執行という正式な法的手続きを踏むことをご理解ください。
強制執行の手続きを経て法的に処分する
残置物を法的に処分するには、まず裁判所で「建物明渡請求」の判決を取得する必要があります。これらの判決は、強制執行を進める上で必要となる「債務名義」となります。
判決が確定した後、オーナーは地方裁判所の執行官へ「建物明渡しの強制執行」を申し立てます。これらの手続きは、以下の段階を経て進められます。
- 申立て
- 明渡しの催告
- 断行
強制執行の申立後に2週間を目処に執行官が現地に赴き明渡しの催告を行います。催告後1か月を目処に断行します。断行に際して、執行業者が残置物の搬出を行います。状況に応じて、残置物を他の保管場所に運搬して保管します。1ヶ月程の一定期間の経過後、借主が残置物の引き取りをしなければ、動産執行の方法に従って売却しますが、買受希望者がいなければ、貸主自身が買受けることになります。
ただ、建物明渡しの強制執行の申立てと同時に動産差押えの申立てをしておくことで、断行日において、差押動産を売却することができます。貸主自身が買い受けることで、保管替えをすることなく明渡しを実現させることができます。
家賃滞納トラブルの再発を防ぐための効果的な対策

トラブル発生後の対応はもちろん重要ですが、同様の問題を未然に防ぐ「予防策」こそが、長期的に安定した賃貸経営の鍵を握ります。再発を防ぐための対策を講じることで、将来的な不安を軽減し、より健全な経営体制を築くことができるでしょう。
以下では、家賃滞納トラブルの再発を防止するための効果的な予防策を解説していきます。
| 対策の軸 | 目的・効果 |
| 入居審査のプロセスと基準を強化する | 質の高い入居者を選定し、滞納リスクを低減します。 |
| 家賃保証会社の利用を必須条件にする | 万が一の家賃滞納に備え、金銭的リスクを軽減します。 |
| 信頼できる賃貸管理会社と連携する | 専門的な知見に基づき、適切な管理を行います。 |
入居審査のプロセスと審査基準を強化する
家賃滞納トラブルを未然に防ぐためには、入居審査の質を高めることが非常に重要です。
まず、入居希望者が提出する書類の提出を求めます。特に、源泉徴収票や給与明細書といった収入資料や身分証明書を精査することが重要です。虚偽の書類を発行する「アリバイ会社」も存在するため、提出された情報に虚偽がないか、慎重に見極めることが大切です。また、支払い能力を客観的に判断するため、収入額に比して賃料額が高過ぎないかをチェックすることも重要です。
最後に、申込者との面談を実施し、人柄やコミュニケーション能力を見極めることも有効な手段です。書類だけでは判断できない信頼性を確認し、トラブルを未然に防ぐ一助とすることが重要となります。
家賃保証会社の利用を必須条件にする
家賃滞納トラブルへの対策として、家賃保証会社の利用を必須条件とすることは、非常に有効な手段です。
家賃保証会社は、入居者が家賃を滞納した場合に、入居者に代わって滞納家賃を立て替えて支払う役割を担います。これにより、オーナーは家賃回収にかかる手間や精神的負担を大幅に軽減できます。
家賃保証会社の利用は、セーフティーネットとして機能するだけでなく、入居者の質を担保する効果も期待できます。保証会社は独自の審査基準を設け、入居希望者の支払い能力や過去の履歴などを厳しくチェックするため、悪質な滞納者を排除するフィルターとしても機能します。
信頼できる賃貸管理会社と連携する
家賃滞納トラブルの再発防止には、信頼できる賃貸管理会社との連携がきわめて効果的です。
管理会社に委託することで、家賃滞納が発生した際も、適切な初期対応によって問題の長期化を防ぎ、早期解決につなげます。ただ、管理会社が執拗な督促業務を行うことは、非弁行為に該当し弁護士法に抵触する可能性があります。そのため、問題が深刻化する場合には、弁護士へ相談することを検討することになります。
家賃滞納トラブルの解決が困難な場合は弁護士へ相談を

これまでに説明してきた家賃滞納への対応、賃貸物件の明け渡し、残置物の処理といった一連の手続きには、専門的な法律知識が求められ、個人で対応するには多大な時間と労力を要するのが現状です。
もし家賃滞納の問題が長期化し、ご自身での解決が困難だと感じた際には、速やかに弁護士へ相談することが問題解決への最も確実な道筋となります。以下では、弁護士に依頼するメリットや、その際に必要となる費用について詳しく解説していきます。
弁護士に相談するメリットとタイミング
家賃滞納問題において弁護士に相談する最大のメリットは、家賃滞納の督促や交渉、さらには複雑な法的手続きに至るまで、すべての業務を一任できる点です。これにより、オーナーご自身の時間的・精神的負担を大幅に軽減できるでしょう。法律の専門家である弁護士は、個別の状況に応じた最適な解決策を提示することができます。
弁護士への相談を検討すべきタイミングはいくつかあります。まず、滞納者への督促に応じてもらえない、あるいは連帯保証人と連絡が取れないなど、当事者間での交渉が難航した時点が挙げられます。また、内容証明郵便の送付や訴訟提起といった具体的な法的措置を検討し始めた段階では、手続きを誤らないためにも、事前に弁護士へ相談することが不可欠です。
滞納家賃の回収にかかる費用の目安
家賃滞納問題の解決を弁護士に依頼する場合、その費用は複数の項目に分かれます。まず、相談料としては、30分あたり5,500円程度が一般的です。
次に、事件に着手する段階で発生する着手金があります。これは回収できる家賃の金額や物件の種類によって異なりますが、滞納家賃の回収だけでなく物件の明渡しまで請求する場合には、滞納家賃額や物件の評価額に応じて着手金が計算されます。
また、事件が解決した場合には、着手金とは別に弁護士報酬が別途発生します。弁護士報酬は回収した家賃の金額に応じて計算されますが、同時に物件の明渡しも成功した場合には、報酬額が加算されることになります。
さらには、弁護士費用に加え、訴訟や強制執行といった法的手続きを進める際には実費も必要です。これには、裁判所に納める印紙代や郵券(切手)代、強制執行の際に執行官に支払う予納金などが含まれます。
| 費用の種類 | 概要 | 目安となる金額 |
| 相談料 | 弁護士への相談時に発生 | 30分あたり5,500円程度(初回相談を無料で受け付けている事務所も多い) |
| 着手金 | 事件に着手する際に発生 | 請求額や物件の評価額により異なる |
| 成功報酬 | 事件解決の成功に応じて発生 | 回収額の10%から20%程度+物件の評価額に対する一定割合 |
| 実費 | 訴訟や強制執行にかかる費用 | |
| – 印紙代・郵券代 | 裁判所に納める費用など | |
| – 予納金 | 強制執行の際に執行官に支払う費用 | |
| – 執行業者費用 | 強制執行を依頼する業者に支払う費用 | 物件の広さや私物の量・種類に応じて(搬出費用は30万~60万円程) |