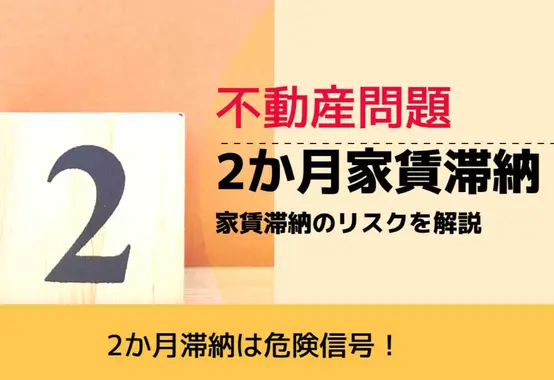賃貸経営において、家賃の1ヶ月滞納は決して珍しいことではありません。しかし、放置すれば法的トラブルに発展する可能性もはらんでいます。
この記事では、オーナーが家賃滞納に適切に対処するための具体的な方法を解説します。督促の流れから、法的手段に踏み切る際の注意点、さらには未然に滞納を防ぐための対策まで、幅広くカバーしていきます。
1ヶ月の家賃滞納で契約解除できるか?
1ヶ月の家賃滞納だけでは賃貸借契約を解除することは原則としてできません。
なぜなら、賃貸借契約は、貸主と借主の信頼関係をベースとする継続的な契約だからです。例えば、売買契約であれば、一回きりの契約ですが、賃貸借契約であれば、長期間にわたって、不動産の貸し借りを継続させるため、貸主と借主の信頼関係が重要な要素となります。
しかし、支払い期限を失念していたり、その他にやむを得ない事情により1ヶ月分の家賃を滞納させてしまうこともあります。このような場合であれば、貸主と借主の信頼関係は修復することができるといえます。そのため、1ヶ月の家賃滞納であれば、当事者間の信頼関係は破壊されたとまでいえないため、賃貸借契約を解除することができません。
ただ、例外的に、これまでも幾度にもわたって家賃の滞納を繰り返している上、借主が反省の態度を見せずに不誠実な態度に終始しているような特段の事情がある場合には、信頼関係が回復できない程度に破壊されたとして、賃貸借契約を解除できる余地があります。
家賃1ヶ月の滞納を「まだ大丈夫」と軽視してはいけない理由

家賃の1ヶ月滞納は、多くの場合、入居者の「うっかり忘れ」や一時的な残高不足など、比較的軽微な原因で生じる場合があります。
しかし、「すぐに払ってくれるだろう」「来月まとめて支払ってくれるはず」と安易に期待し、初期対応を怠ることは非常に危険です。
家賃滞納は1日でも早く対応することが、トラブルを最小限に抑える鍵となるでしょう。
1ヶ月の滞納で強制退去はできないが初動が重要
家賃を1ヶ月滞納したからといって、ただちに賃貸借契約を解除して強制退去を求めることは困難です。
先ほど解説したように、賃貸借契約の解除や強制退去を認めるには、貸主と借主間の「信頼関係の破壊」が必要とされています。過去の判例や裁判例から見ても、一般的に3ヶ月以上の家賃滞納がこの「信頼関係の破壊」の目安となることが多いのが実情です。したがって、1ヶ月程度の滞納では、法的に強制退去の手続きを進めることは原則難しいと理解しておく必要があります。
しかし、強制退去ができないからこそ、この段階での「初動」が極めて重要になります。家賃の滞納に適切に対応することで、入居者が単なる「うっかり忘れ」なのか、あるいは経済的な問題によって支払いが困難なのかを早期に把握できるでしょう。
初動対応によって期待できる効果は以下の通りです。
初動が大事な理由
- 入居者の滞納理由(うっかり忘れ、経済的問題など)を早期に把握できます。
- 最初の1ヶ月の時点で「滞納は見過ごされない」という明確なメッセージを伝え、今後の滞納を抑制する効果が期待できます。
- 万が一、滞納が長期化し、最終的に法的手続きが必要になった場合でも、初期で実施された督促の履歴は、その後の手続きを円滑に進める上で重要な証拠となります。
滞納の長期化が引き起こす経営リスクとは
家賃滞納が長期化すると、賃貸経営に深刻な悪影響を及ぼし、様々な経営リスクを引き起こします。
まず、家賃収入が途絶えることでキャッシュフローが大きく悪化します。ローンを組んでいる場合、その返済が滞るリスクが生じ、最終的に物件が強制競売にかけられる可能性も出てきます。また、管理費や修繕費といった固定支出の支払いに支障をきたし、健全な賃貸経営そのものが困難になる事態も考えられます。
さらに、滞納期間が長引くほど、督促にかかる追加コストが増大します。具体的には、以下のような費用が発生します。
貸主に生じる費用
- 内容証明郵便の郵送費用
- 弁護士費用
- 強制執行費用(予納金、執行補助者の費用、解錠業者の費用等)
これらの費用は、滞納家賃額を上回るケースも存在するため、オーナーにとって見過ごせない大きな負担となります。
また、最も避けたいリスクの一つが、新たな入居者を募集できないことによる機会損失の拡大です。滞納者が退去しない限り、その部屋は事実上の「空室」となり、新たな家賃収入を得る機会を失い続けます。
このように、借主の家賃滞納を放置していると、大きな経営上の損失を招くことすらあるため、適切な対応が肝心です。


【時系列で解説】家賃滞納が発生した際の具体的な対応ステップ
家賃滞納が発生した場合、感情的にならず、法的なルールに基づいた冷静かつ段階的な対応が重要です。
以下で解説する各ステップを順序立てて行うことで、入居者との不必要なトラブルを避け、円滑な問題解決を目指すことができます。以下の項目では、各段階で取るべき具体的な対応と、その際の注意点を時系列に沿って詳しく解説していきます。
【初動】電話・SMSによる入金状況の確認
家賃の滞納から1週間以内であれば、入居者が支払いをうっかり忘れている可能性や、一時的な残高不足といった軽微な理由が考えられます。この段階では、高圧的な督促をするのではなく、あくまで入金状況の確認を目的とした穏やかなコミュニケーションを心がけることが重要です。早期かつ丁寧な対応は、入居者との信頼関係を維持し、その後のスムーズな問題解決につながるでしょう。
連絡には電話またはショートメール、ラインメッセージが効果的です。 いずれの連絡方法についても、できる限り詳細な記録を残すようにしてください。この記録は、後に督促状の送付や、万が一の法的手続きに移行する際に、履歴として重要な証拠となります。記録しておくべき項目は以下の通りです。
【1週間〜1ヶ月】督促状の郵送と連帯保証人への連絡開始
貸主の連絡に借主の反応がない場合や、滞納状況が解消されない場合は、次の段階として書面による督促状を郵送します。督促状の郵送と並行して、連帯保証人に対する請求も検討します。
連帯保証人は賃貸借契約において、主たる債務者である借主が債務を履行しない場合、借主の支払意思や支払能力に関わらず、履行をする責任を負います。そのため、貸主は最初から連帯保証人に支払いを求めることが可能です。
【1ヶ月経過後】保証会社を利用している場合の手続き
家賃の滞納が1ヶ月を超え、連帯保証人への連絡でも進展が見られない場合や連帯保証人がいない場合、賃貸保証会社を利用しているオーナーは、保証会社への「事故報告(滞納報告)」を行う必要があります。滞納発生から80日以内の事後報告がない場合、保証会社が保証債務を負わない(免責)ケースもあるため、速やかな手続きが肝要です。
【2ヶ月経過後】内容証明郵便の送付と契約の解除通知
借主が一向に家賃の滞納を解消しない場合には、内容証明郵便により滞納家賃の督促を求めることを検討します。内容証明郵便とは、郵便局が「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰あてに差し出したか」を証明する制度をいいます。
それでもなお、借主の家賃滞納が3か月以上重なる場合には、最終通告として滞納家賃の催告をした上で、指定期限内に支払いがない場合には賃貸借契約を解除する通知を送付します。
法的なトラブルを回避するために!オーナーが絶対にしてはいけない督促行為

家賃滞納が発生した場合でも、オーナーが法的手続きを経ずに、自らの実力で権利を回復しようとする「自力救済」は、法律で禁止されています。自立救済は、犯罪行為になる可能性があるだけでなく、民事上の損害賠償請求を受ける可能性もあります。
法的なトラブルを避けるためにも、冷静かつ適正な手続きを踏むことが重要です。
無断での入室や鍵の交換
家賃滞納があったとしても、貸主が法的手続きを経ずに自らの力で権利を回復する「自力救済」は禁止されています。
例えば、強制執行によらずに無断で立ち入ったり、室内の家財道具を無断で処分したり運び出したりする行為は、住居侵入罪、窃盗罪、器物損壊罪に該当する可能性があります。
これらの行為によって入居者が精神的苦痛や物理的な損害を被った場合、入居者から損害賠償を請求される民事上のリスクも生じます。
感情的な行動は避け、必ず適切な法的手続きに則って対応を進めるようにしてください。
早朝深夜の訪問や過剰な電話連絡
家賃滞納の督促において、早朝や深夜の訪問、あるいは過剰な電話連絡は、入居者に対する「違法な取り立て」と見なされるリスクがあります。
例えば、早朝や深夜の時間帯の訪問や連絡、1日に何度も電話をかける、連続して留守番電話メッセージを残すなど、常識の範囲を超えた頻度での連絡は、悪質な取り立て行為といえます。たとえ滞納家賃の督促であっても、社会通念を逸脱する取り立てを行うと入居者から損害賠償請求を受けたり、場合によっては刑事罰の対象となったりする可能性も否定できません。
常に冷静さを保ち、適切な時間帯と頻度で連絡を心がけることが重要です。
勤務先への連絡や玄関への張り紙
家賃滞納の事実を勤務先に連絡することは、入居者のプライバシーを侵害し、名誉毀損やプライバシー侵害に該当する可能性があります。
同様に、玄関ドアや集合ポスト、共有スペースに家賃滞納の事実を記載した張り紙を掲示する行為も厳禁です。このような行為は、他の入居者や来訪者など第三者に滞納の事実を公にするものであり、名誉毀損やプライバシー侵害になり得ます。
これらの過剰な督促行為は、入居者との信頼関係を完全に破壊し、その後の交渉を極めて困難にします。さらに、入居者から損害賠償請求訴訟を提起されるリスクも生じるため、オーナー自身が法的責任を問われる事態を避けるためにも、法で認められた範囲での督促に留めることが重要です。
滞納を未然に防ぐための予防策と入居者管理のポイント
家賃滞納が発生した際の迅速かつ適切な対応はもちろん重要ですが、賃貸経営を安定させるためには、そもそも滞納を発生させない予防策を講じることが最も効果的です。
以下では、家賃滞納を未然に防ぐための具体的な予防策を詳しく解説していきます。
入居審査時に確認すべき項目
家賃滞納のリスクを低減するには、入居希望者の審査を十分に行うことです。以下の項目から家賃滞納のリスクを踏まえて賃貸借契約を締結するべきか検討をしましょう。
- 安定した収入と支払い能力
- 人柄や信頼性
- 連帯保証人の有無と能力
- 賃貸保証会社の審査結果
契約時に滞納リスクを減らす特約
家賃滞納を未然に防ぐには、賃貸借契約書に適切な特約を盛り込むのが有効です。これにより、滞納の抑止力となり、万一の際の対応も円滑に進められるでしょう。
家賃滞納リスク軽減に役立つ特約の主な例は以下の通りです。
| 特約の種類 | 主な内容 | 効果・留意点 |
| 遅延損害金 | 滞納額に対し年14.6%を上限とした利率で請求 | 支払意識の向上、滞納抑制効果 |
| 契約解除条項 | 一定期間(例:2〜3ヶ月)滞納で解除催告手続き開始 | 早期解決を促す(ただし別途法的手続きが必要) |
具体的な特約の一つとして、「遅延損害金」に関する定めがあります。家賃滞納時には、その金額に対して遅延損害金を請求する旨を明記することが重要です。遅延損害金の割合を明記しなければ、滞納家賃の遅延損害金の割合は年3%に留まりま すが、消費者契約法で定められている上限の年14.6%を上限とした利率が設定することで、その割合の遅延損害金を請求することができます。この特約により、支払い遅延に対する意識を高め、滞納の抑制に効果が期待できます。
また、滞納が一定期間(例えば2〜3ヶ月)に達した場合に、契約解除をできる旨を定めることも有効です。ただし、この特約がある場合でも、借主が任意に明渡に応じない場合には、別途裁判手続きがある点に留意が必要です。
支払い忘れを防ぐための支払い方法の工夫
家賃滞納を未然に防ぐには、支払い方法の工夫が非常に有効です。入居者の「うっかり忘れ」や手間を原因とする滞納を根本的に解消するためには、支払い方法の自動化が鍵となるでしょう。
標準的な支払い方法として推奨されるのは、口座振替(自動引き落とし)です。入居者は入金の手間が省け、支払い忘れを防ぐことができます。オーナーにとっても家賃回収業務を自動化でき、未収金の削減につながります。支払い忘れによる滞納を抑制し、安定した家賃回収が期待できるでしょう。
次に、クレジットカード決済の導入も有効です。これにより支払い忘れが防止され、滞納リスクの低減につながります。オーナー側も、カード会社を介して毎月確実に家賃が入金されるため、未払いを防ぐ効果が期待できます。
さらに、管理会社等の集金代行サービスの活用も検討に値します。このサービスを利用すれば、口座振替やクレジットカード決済など多様な支払い方法に対応できるだけでなく、集金業務自体を管理会社に任せられます。オーナーは煩雑な集金管理業務から解放され、家賃回収の手間を大幅に削減できるでしょう。
以下の表に、各支払い方法の主なメリットをまとめました。
| 支払い方法 | 入居者の主なメリット | オーナーの主なメリット |
| 口座振替(自動引き落とし) | 入金の手間削減、支払い忘れ防止 | 家賃回収業務の自動化、未収金削減、安定した回収 |
| クレジットカード決済 | ポイントやマイルの獲得、支出の一元管理、支払い忘れ防止 | 確実な家賃入金、未払い防止 |
| 集金代行サービス | 多様な支払い方法からの選択が可能 | 煩雑な集金管理業務からの解放、家賃回収の手間大幅削減 |
家賃滞納の対応に困ったら弁護士への相談も検討しよう

家賃滞納への対応は、これまで説明してきた手順を踏むことで、解決に導けるケースが多くあります。しかし、中には問題が長期化し、複雑になるケースも少なくありません。オーナーご自身で問題を抱え込み、疲弊してしまう前に、専門的な知識を持つ弁護士へ相談することも有効な選択肢です。
弁護士への相談は、家賃滞納問題が法的な局面を迎えた際や、当事者間での解決が困難になった際に特に重要です。例えば、滞納期間が長期化している場合、入居者本人と連絡が取れない、または当事者間での交渉が決裂した場合、連帯保証人との間でトラブルが発生した場合には弁護士への相談や委任を積極的に検討するべきです。
滞納期間が長期化している場合
第一に、滞納期間が長期化し、契約解除や建物明け渡し請求訴訟といった法的措置を具体的に検討し始める段階です。
一般的に、家賃滞納が3ヶ月以上に及ぶと、賃貸借契約における「信頼関係の破壊」が法的に認められやすくなります。明け渡し請求訴訟から強制執行までの一連の手続きは、訴状の作成や裁判の進行など専門的な知識を要し、個人で全てに対応するのは極めて困難です。
入居者との話し合いができない場合
第二に、入居者本人と全く連絡が取れない、あるいは話し合いをしても支払いの意思が見られず、当事者間での交渉が完全に決裂してしまった場合です。音信不通であったり、言い訳ばかりで改善が見られない状況では、第三者である弁護士が介入することで、交渉が進展する可能性があります。
当事務所では初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。お気軽にご相談ください。
対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。