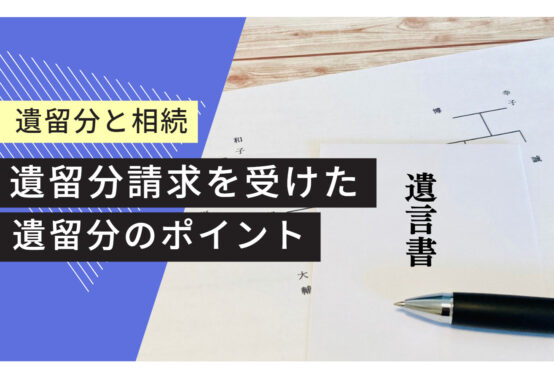相続が発生した際、まず行うべきことの一つが財産調査です。しかし、何から手を付けていいのかわからず、途方に暮れてしまう方も少なくありません。
この記事では、相続財産の調査をスムーズに進めるための第一歩として、自分で財産を調べる方法から、弁護士への依頼を検討するタイミングまで、具体的に解説します。預貯金や不動産といった基本的な情報から、見落としがちな財産まで、網羅的にご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
相続財産調査とは?相続手続きに欠かせない3つの理由
相続財産調査とは、亡くなった方(被相続人)が所有していたすべての財産を洗い出し、その遺産の全容を明らかにする手続きです。
この調査は、その後の相続手続きにおいて、非常に重要な最初のステップとなります。では、なぜ財産調査が不可欠なのでしょうか。その理由は主に3つあります。これらの理由について、以下で詳しく解説していきます。
1.円満な遺産分割協議を行うため
相続財産の調査は、円満な遺産分割協議を進める上で非常に重要なプロセスです。故人(被相続人)の財産が不明確なまま話し合いを始めると、相続人の間で不公平感や疑念が生じやすくなり、不要なトラブルに発展する可能性が高まります。特に、一部の財産が隠されていたり、遺産目録の内容が不正確であったりする場合に、この傾向は顕著です。
すべての相続人が「どのような財産が、どれだけあるのか」を正確に把握している状態が、公平で円満な話し合いのスタートラインとなります。もし遺産分割協議を終えた後に新たな財産が見つかった場合、原則として協議のやり直しが必要となり、それが新たな火種となるリスクも考えられます。遺産分割協議書を作成した後にこのような事態が発覚すると、相続人間にさらなる不信感が生まれる原因にもなりかねません。
このような事態を避けるためにも、まずは預貯金や不動産などのプラスの財産から、借金といったマイナスの財産まで、すべての財産を洗い出して一覧化する「遺産目録」の作成が不可欠です。この財産目録こそが、遺産分割を円滑に進めるための大切な第一歩となるでしょう。
2.相続放棄や限定承認を判断するため
相続では、故人(被相続人)が遺した預貯金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金やローンなどの「マイナスの財産」も引き継ぎます。もし、相続財産全体を調査した結果、マイナスの財産がプラスの財産を明らかに上回る場合、相続人は多額の負債を抱えるリスクが生じます。このような事態を避けるため、相続放棄や限定承認といった選択肢が検討されます。
相続放棄や限定承認は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。被相続人の財産の多寡に関わらず、相続放棄をするのであれば別ですが、相続放棄をするべきかを悩んでいる場合には、この3ヶ月という限られた期間内で、被相続人の財産状況を正確に把握する財産調査が必要です。
3.正確な相続税の申告・納税のため
相続税は、故人(被相続人)が遺したすべての財産、すなわち預貯金や不動産などの「プラスの財産」と、借金や未払金などの「マイナスの財産」を基に計算されます。この遺産額が正確に把握できていなければ、正確な相続税額を算出することはできません。
財産調査が不十分で申告漏れが生じると、税務署による税務調査の対象となるリスクがあります。万一、申告漏れが指摘された場合、本来支払うべき税額に加えて、「過少申告加算税」や「延滞税」といったペナルティ(追徴課税)が課せられます。このようなリスクを回避し、正しく納税を完了させるためにも、相続の初期段階で正確な財産調査を行うことが極めて重要です。


相続財産調査のタイムリミットは?手続き全体の流れと期限
相続財産の調査自体には、法律で定められた明確な期限はありません。しかし、その後の相続手続きには厳格な期限が設けられているため、それらに間に合わせるには、遺産調査をできるだけ速やかに開始する必要があります。
相続放棄・限定承認の期限(3ヶ月以内)
相続では、亡くなった方(被相続人)の財産をすべて受け継ぐ「単純承認」の他に、「相続放棄」や「限定承認」といった選択肢があります。相続放棄は、財産をすべて放棄すること、限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことです。このうち、相続放棄と限定承認を選択する場合には、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述の手続きをする必要があります。
この期限を過ぎると、原則として「単純承認」とみなされ、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて相続することになります。想定外の負債を抱えるリスクを避けるためにも、相続放棄や限定承認をご検討の場合は、早期に財産調査に着手し、期限内に必要な手続きを進めることが重要です。
| 選択肢 | 特徴 | 期限 |
| 単純承認 | 被相続人のプラスの財産とマイナスの財産をすべて引き継ぎます。 | 期限はありませんが、熟慮期間を過ぎると原則として単純承認とみなされます。 |
| 相続放棄 | 被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄し、初めから相続人ではなかったことになります。 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内 |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぎます。負債が資産を上回る場合でも、自身の固有財産で弁済する義務はありません。 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内 |
相続税の申告・納付期限(10ヶ月以内)
相続税の申告と納税には、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内という厳格な期限が設けられています。この期限までに、すべての相続財産を正確に把握し、遺産の総額を確定させなければなりません。これには、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も漏れなく調査し、評価額を算出する作業が含まれます。正確な遺産調査が終えていなければ、正しい相続税額を算出することはできません。
余計な税負担を避け、スムーズな相続手続きを進めるためにも、期限を意識した上で早期に財産調査に取り組み、正確な申告と納税を目指すことが重要です。
自分で調査?専門家に依頼?判断のポイントとメリット・デメリット
相続財産の調査を進める際、相続人ご自身で調査を行う方法と、弁護士といった専門家に依頼する方法の二つの選択肢があります。どちらの方法が最適かは、故人(被相続人)の財産の状況や、相続人ご自身の状況によって大きく異なります。
以下の項目では、ご自身で調査を進めても問題ないケースと、弁護士への依頼を検討すべきケースについて、それぞれの判断ポイントとメリット・デメリットを詳しく解説していきます。
自分で調査を進めても問題ないケース
以下の条件を満たしている場合は、自分で手続きを進めることも一つの選択肢となるでしょう。
これらの条件に該当する場合は、ご自身で相続財産調査を進めることもご検討ください。
| 自分で調査を進めやすい条件 | 詳細 |
| 財産がシンプルで把握しやすい | 遺産の種類が比較的少なく、預貯金やご自宅の不動産など、その内容がシンプルで全体像を把握しやすいケースです。 |
| 相続人が少数で関係性が良好 | 相続人が少数で、かつ相続人同士の関係性が良好であり、協力して調査を進めることができる場合です。 |
| マイナスの財産がないと確信できる | 故人の生前の生活状況から、借金や保証債務といったマイナスの財産が一切ない、またはその可能性が極めて低いと確信できる場合です。 |
| 手続きを行う時間的な余裕がある | 平日の日中に役所や金融機関を訪問し、必要な書類の取得や各種手続きを行うための時間的な余裕を十分に確保できる方です。 |
専門家への依頼をおすすめするケース
相続財産調査は、ご自身で進めるのが難しいケースも少なくありません。特に、以下のような状況では、専門家への依頼を検討することで、安全かつスムーズに手続きを進めることができます。
| 状況 | 具体的な課題 | 専門家に依頼するメリット |
| 財産の種類が多く、複雑な場合 | 遺産が多岐にわたり、専門知識や手間が必要となります。相続放棄や限定承認の3ヶ月という期限を考慮すると、迅速かつ正確な調査が不可欠です。 | 専門知識に基づいた迅速かつ正確な調査により、負債の把握や見落としがちな財産の発見が可能です。相続放棄や限定承認の期限内に対応できるよう、スムーズな手続きをサポートします。 |
| 相続人同士の関係が複雑な場合 | 相続人の人数が多い、または関係性が良好でない場合、財産調査を巡って意見の対立が生じがちです。これにより、手続きが滞る可能性があります。 | 専門家が間に入ることで、客観的な財産調査が可能となり、後の遺産分割協議でのトラブルを未然に防ぎます。相続人間の感情的な対立を避けることができます。 |
| 調査に時間的な余裕がない場合 | 戸籍謄本の収集、金融機関や役所での手続きなど、遺産調査は平日の日中に行う必要。仕事や育児で忙しい場合、ご自身で時間を確保するのは困難です。 | 専門家に依頼することで、調査を効率的に進めることができ、相続人の方の負担を軽減します。時間の制約がある場合でも、迅速な手続きが実現し、期限内の対応が可能になります。 |
【比較】自分で行う場合と専門家に頼む場合の違い
相続財産調査を自分で行うか、専門家に依頼するかは、それぞれメリットとデメリットがあります。費用、時間・手間、調査の正確性、精神的負担の4つの観点から両者を比較し、ご自身の状況に合った選択ができるよう、以下の表で解説します。
相続財産の調査は多岐にわたるため、ご自身で行う場合は多くの時間と労力がかかります。例えば、交通費や書類取得費は実費で済みますが、 時間を捻出すること自体が大きな負担となることもあります。
一方、専門家に依頼した場合、遺産額に応じた一定程度の報酬額が発生しますが、相続手続のプロが迅速かつ正確に財産を洗い出してくれます。これにより、時間的・精神的負担を軽減し、相続税の申告漏れや負債の見落としといったリスクを低減できるメリットがあります。
最終的にどちらを選ぶかは、費用負担を最優先したいか、あるいは確実性や時間、精神的な負担の軽減を重視したいかによって判断が分かれます。ご自身の状況に合わせて、最適な方法をご検討ください。
【財産の種類別】相続財産の具体的な調べ方と必要書類
相続財産の調査では、預貯金、不動産、有価証券といった「プラスの財産」だけでなく、借金や未払金といった「マイナスの財産」も、すべて網羅的に洗い出す必要があります。財産別の遺産調査の調査方法を紹介します。
預貯金・現金の調査方法
故人の預貯金・現金を調査する際は、まず手がかりを見つけることが最初のステップです。
取引のある金融機関が特定できたら、「残高証明書」と「取引履歴」の発行を請求します。残高証明書は、相続開示時の預貯金残高を証明する重要な書類であり、相続税計算や遺産分割協議に不可欠です。
残高証明書の請求により口座は凍結されます。公共料金などの引き落としができなくなるため、口座変更手続きを進めましょう。葬儀費用など当面の資金が必要な場合は、「相続預貯金の仮払い制度」の利用も検討できます。
また、自宅内のタンス、金庫、貸金庫なども念入りに探し、発見された現金は日付と金額を記録し、相続財産として正確に計上する必要があります。
不動産(土地・家)の調査方法
亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産を調査する際は、まずご自宅から「固定資産税の納税通知書」や「権利証(登記識別情報)」といった重要書類を探すことから始めます。これらの書類には、不動産の所在地や地番、家屋番号などの情報が記載されており、その後の調査を進める上で欠かせない手がかりとなります。特に、納税通知書は毎年送付されるため、最新の情報を得るのに役立ちます。
次に、被相続人が所有していた不動産の全体像を把握するため、市区町村役場で「名寄帳(なよせちょう)」を取得します。名寄帳は、同一市区町村内で被相続人が所有していた不動産(土地や家屋など)の一覧が記載された書類です。固定資産税の納税通知書には記載されていない、私道や共有名義の不動産なども名寄帳で確認できることがあります。
名寄帳で把握した不動産については、法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得し、詳細な情報を確認します。登記事項証明書には、不動産の正確な所有者情報や、抵当権などの権利関係が明記されています。この情報が、遺産分割協議や相続税の申告において重要な根拠となります。
また、遺産分割や相続税の申告にあたり、不動産の価値を把握することも必要です。そのための方法として、市区町村役場で「固定資産税評価証明書」を取得する、あるいは国税庁が公開する「路線価」を確認するといった手段があります。より正確な市場価値を知りたい場合は、不動産会社に査定を依頼するのも一つの手段です。
| 調査ステップ | 取得書類 / 確認事項 | 取得場所・確認場所 | 目的 |
| 1. 自宅での初期確認 | 固定資産税の納税通知書、権利証(登記識別情報) | 自宅 | 不動産の所在地、地番、家屋番号などの初期情報の把握 |
| 2. 不動産全体像の把握 | 名寄帳 | 市区町村役場(税務課など) | 被相続人が所有する不動産全体の一覧確認 |
| 3. 詳細な権利関係の確認 | 登記事項証明書(登記簿謄本) | 法務局 | 正確な所有者情報、抵当権などの権利関係の確認 |
株式・投資信託など有価証券の調査方法
故人(被相続人)が保有していた株式や投資信託などの有価証券を調査する際は、まずご自宅の遺品や郵便物を丁寧に確認することが重要です。証券会社からは定期的に以下のような書類が郵送されてくることが一般的です。
手掛かりとなる書類
・年間取引報告書
・取引残高報告書
・保有有価証券残高報告書
・配当金計算書
・株主総会招集通知
これらは、取引している証券会社を特定する手がかりになります。ネット証券を利用していた場合は、故人のパソコンのブックマーク履歴やスマートフォンのアプリなども確認すると良いでしょう。
取引のある証券会社が判明したら、その証券会社へ連絡し、残高証明書の発行を依頼します。この際、一般的に以下の書類の提出が求められます。もし、どの証券会社と取引があったか全く不明な場合には、「証券保管振替機構(通称:ほふり)」に対して情報開示請求を行うと、故人が口座を開設していた証券会社を一覧で確認できます。この手続きを通じて、見落としていた有価証券を発見できる可能性が高まるでしょう。
上場していない株式(非公開株)は証券会社では管理されていないため、被相続人の勤務先や関連会社に直接問い合わせ、株主名簿を確認する必要があります。
生命保険金の調査方法
故人(被相続人)が加入していた生命保険や受け取るべき死亡退職金を調査する際は、まずご自宅の遺品を詳しく確認することが重要です。確認すべき手がかりは以下の通りです。
- 保険証券
- 保険会社から送付された保険料控除証明書や契約内容のお知らせ
- 預貯金通帳の引き落とし履歴
これらの情報から、取引のある保険会社を特定できる可能性があります。
故人が勤務先で加入していた団体保険や、死亡退職金については、勤務先へ問い合わせて確認します。これらの有無や金額、受取人に関する情報は、企業が把握しているのが一般的です。
もし、故人がどの保険会社と契約していたか全く不明な場合は、一般社団法人生命保険協会に照会します。これにより、個人が加入していた生命保険会社の情報が開示されます。
生命保険金や死亡退職金は、受取人固有の財産として扱われますが、相続税法上は「みなし相続財産」となり、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠を超える場合には、課税対象となります。
借金・ローンなどマイナスの財産の調査方法
借金の有無やその総額を網羅的に調べる最も確実な方法は、信用情報機関への情報開示請求です。主に以下の3つの信用情報機関に照会することで、故人(被相続人)が過去に利用していたローン契約、クレジットカードの残債、保証債務などの信用情報を確認できます。
| 機関名 | 主な登録情報 | 開示方法/備考 |
| 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | クレジット会社や消費者金融などからの借入情報、ローン契約内容、支払い状況、残高、申込み記録など | 開示手数料500円。インターネット(一時休止中)または郵送で請求可能。 |
| 株式会社日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融やクレジットカード会社の情報 | スマートフォンアプリや郵送で開示請求可能。 |
| 全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 主に銀行からの借入情報 | 詳しい開示方法は各機関のウェブサイトでご確認ください。 |
これらの機関に情報開示請求を行うことで、故人の金融状況を広範囲にわたって把握できるでしょう。
また、故人の自宅にある遺品や書類も重要な手がかりとなります。以下のものが残されていないか、丁寧に確認しましょう。
- 金銭消費貸借契約書
- ローン返済予定表
- クレジットカードの明細
- 督促状
- 裁判所からの通知
預貯金通帳の取引履歴もチェックし、毎月の定期的な引き落としや、不審な入金・出金がないかを確認することも有効です。消費者金融からの借入やローン返済の形跡が見つかる可能性があります。
自動車・貴金属・骨董品などの調査方法
自動車、貴金属、骨董品といった動産の調査は、まず故人(被相続人)のご自宅や貸金庫などを丁寧に捜索し、現物や関連書類を見つけることから始まります。これらの財産は客観的な価値評価が難しい場合が多く、専門家による査定が不可欠です。
動産調査の主な確認書類は以下の通りです。
- 自動車: 車検証、自動車税の納税通知書、損害保険の保険証券
- 貴金属・骨董品: 購入時の保証書、鑑定書
- その他(ゴルフ会員権など): 各種証明書、契約書
相続財産調査を自分で行う際の3つのポイント
いざご自身で調査を進めるとなると、多岐にわたる作業に戸惑われることもあるかもしれません。
そこで、以下では、ご自身で相続財産調査を行う際に特に役立つ3つのポイントをご紹介します。
故人の遺品や郵便物を手がかりにする
相続財産調査の最初の重要な一歩は、故人(被相続人)のご自宅や身の回りの遺品を丁寧に整理することから始まります。遺品整理を進める中で、相続財産の有無やその詳細を示す重要な手がかりが多数見つかることがあります。 特に、故人宛の郵便物は重要な手がかりとなります。例えば、金融機関からの取引明細、固定資産税の納税通知書、証券会社からの取引報告書、保険会社からの契約内容のお知らせなどが挙げられます。また、以下の重要書類が保管されていないか確認してください。
- 預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード
- 保険証券
- 不動産の権利証(登記識別情報通知書)
- 株券
これらの書類は、財産の所在や種類を特定する上で非常に重要な情報源です。さらに、手帳のメモ、カレンダーの書き込み、故人が使用していたパソコンやスマートフォンの履歴(オンラインバンクのブックマーク、取引に関するメールなど)にも、見落としがちな貴重な情報が隠されていることがあります。
調査に必要な書類(戸籍謄本など)を早めに取得する
多くの財産調査手続きにおいて、被相続人と相続人の関係を公的に証明する書類は不可欠です。金融機関での残高照会や不動産の名寄帳取得など、さまざまな場面で戸籍謄本などの提出が求められるため、これらの書類がなければ調査を進めることができません。
相続放棄や相続税申告には期限があるため、手続きの遅延を防ぐためにも、戸籍謄本の収集は最も早く着手すべき作業と言えるでしょう。
調査結果を「遺産目録」として一覧にまとめる
故人(被相続人)の財産調査で判明した内容は、「遺産目録」として一覧にまとめることが重要です。この遺産目録は、相続人全員が相続財産の全体像を共有し、円満な遺産分割協議を進める上での土台となります。また、相続放棄や限定承認を判断する際の客観的な材料にもなり、その後の相続税申告書や遺産分割協議書の基礎資料としても不可欠です。
裁判所のウェブサイトでも遺産目録のひな形が提供されており、これらを活用すると効率的に作成できるでしょう。正確な遺産目録を作成することが、その後の相続手続き全般をスムーズに進める上で非常に重要です。
遺産調査は難波みなみ法律事務所へ

本記事では、相続財産調査の重要性から具体的な調査方法、そして専門家への依頼について解説しました。相続財産調査は、円満な遺産分割協議を進め、相続放棄や限定承認といった重要な判断を下し、さらには正確な相続税の申告・納税を行うための根幹となる非常に重要なステップです。
この調査には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という相続放棄・限定承認の期限、そして「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」という相続税申告・納付の期限が設けられています。
ご自身で調査を進められるケースもありますが、故人(被相続人)の財産の全体像が不明確な場合、財産の種類が多岐にわたり複雑な場合、あるいは相続人同士の関係が良好でない場合など、少しでも不安を感じるようであれば、早期に弁護士へ相談することが最善の解決策となるでしょう。
弁護士と連携することで、複雑で時間のかかる相続手続きの負担を軽減し、将来的なトラブルを未然に防ぎ、安心して手続きを完了できます。相続財産の全体像が不明で何から手をつけて良いかお困りの際は、まずはご自身の状況に合った専門家への相談を検討することをおすすめします。
初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。