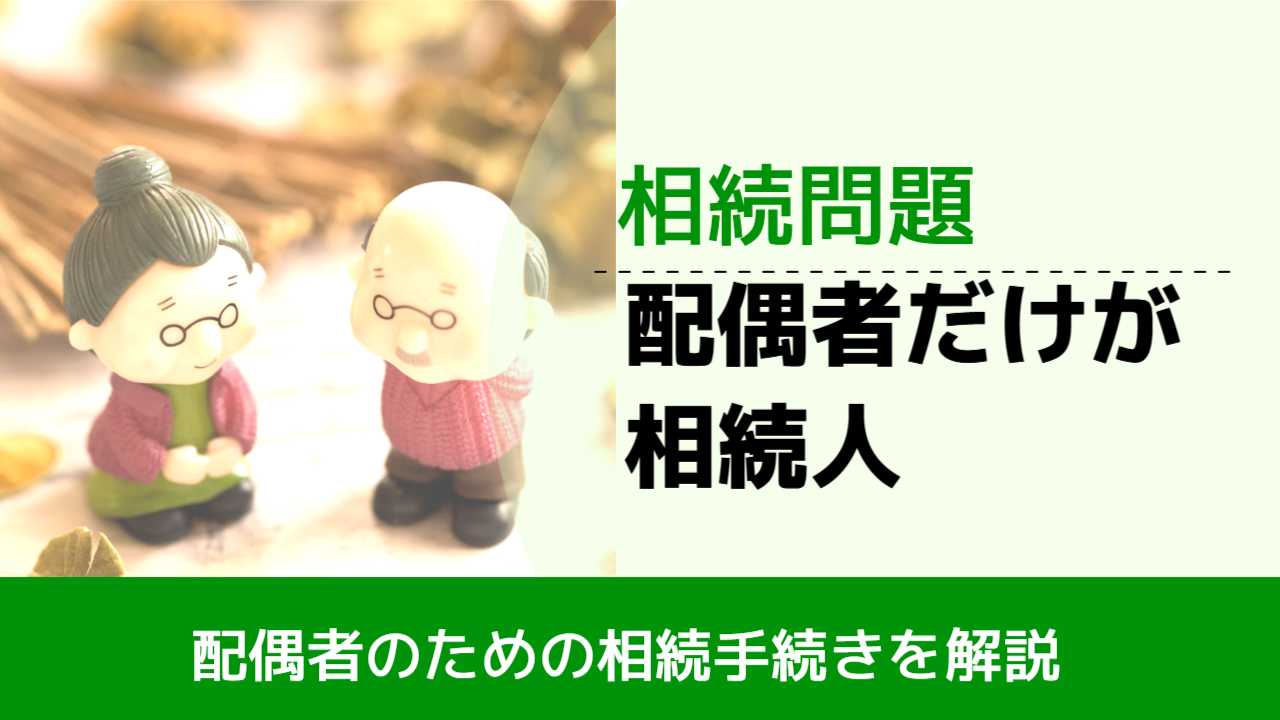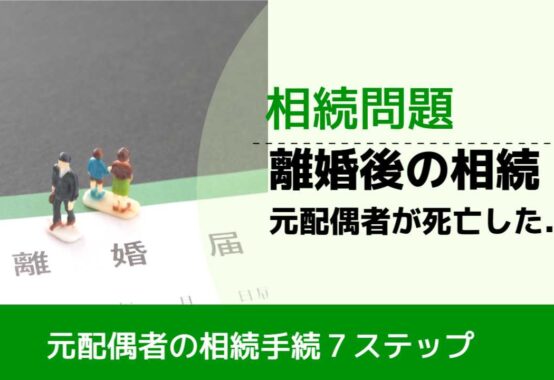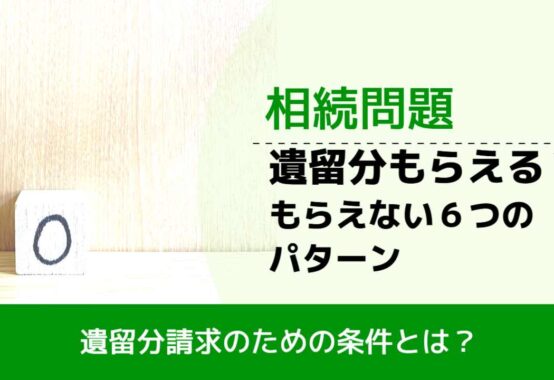大切な方を亡くされた深い悲しみの中、本サイトを見ていただきありがとうございます。
この記事では、相続人が配偶者のみとなるケースに焦点を当て、必要な手続きをわかりやすく解説します。
「相続」と聞くと、どうしても難しい法律や税金の知識が必要になると思いがちです。
特に、相続人が配偶者のみの場合、どのような相続手続になるのか、何から始めたら良いのか不安に感じる方も少なくありません。
この記事が、そのような不安を解消し、手続きをスムーズに進めるための一助となれば幸いです。
まず確認!法律で決まっている相続人の範囲と順位
相続手続きを進める上で、まず知っておきたいのが「誰が遺産を相続する権利を持つのか」という点です。
相続人になれるのは誰?法定相続人の基本ルール
遺産を相続する権利を持つ人は、法律上「法定相続人」と定められています。亡くなった方(被相続人)の配偶者は、常に法定相続人となります。その地位は、他の相続人の有無にかかわらず変わりません。
配偶者以外の相続人には、以下の通り相続する順位が定められています。
| 順位 | 相続人の範囲 |
| 常に | 配偶者 |
| 第一順位 | 子(子が既に亡くなっている場合は孫などの直系卑属) |
| 第二順位 | 父母(父母が既に亡くなっている場合は祖父母などの直系尊属) |
| 第三順位 | 兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は甥や姪) |
この優先順位のルールは非常に重要です。上位の法定相続人が一人でもいる場合、下位の順位の人は相続人にはなれません。例えば、亡くなった方に子がいる場合、父母や兄弟姉妹は相続人にはなりません。この基本ルールを把握することが、相続手続きを進める上での最初の重要なステップとなります。
あなたの場合は誰が相続人?ケース別の法定相続人
前述の法定相続人の基本ルールを踏まえ、具体的な家族構成に当てはめてご自身の相続人が誰になるかを確認しましょう。ここでは、よくある3つのケースを例に挙げます。
| ケース | 相続人 | 法定相続分 |
| 1. 子がいる場合 | 配偶者と子 | 配偶者:1/2、子:1/2(複数いる場合は均等割) |
| 2. 子がおらず、父母がいる場合 | 配偶者と父母 | 配偶者:2/3、父母:1/3(両親ともいれば均等割) |
| 3. 子も父母もおらず、兄弟姉妹がいる場合 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4(複数いる場合は均等割) |
ケース1:亡くなった方に子がいる場合
このケースの相続人は、配偶者と子です。遺産の法定相続分は、配偶者が2分の1、子が残りの2分の1となります。子が複数いる場合は、残りの2分の1を子全員で均等に分けます。
ケース2:亡くなった方に子がいないが、父母(直系尊属)が存命の場合
このケースの相続人は、配偶者と父母です。法定相続分は、配偶者が遺産の3分の2、父母が残りの3分の1を相続します。父母がともに存命であれば、その3分の1を均等に分けます。
ケース3:亡くなった方に子も父母もいないが、兄弟姉妹が存命の場合
このケースの相続人は、配偶者と兄弟姉妹です。法定相続分は、配偶者が遺産の4分の3、兄弟姉妹が残りの4分の1となります。兄弟姉妹が複数いる場合は、その4分の1を全員で均等に分けます。


配偶者だけが遺産を相続できる4つのパターン
これまでの説明で、法定相続人の範囲や順位、それぞれの法定相続分について理解が深まったことと思います。以下では、配偶者だけが遺産を相続するパターンを紹介します。
パターン1:子供・親・兄弟もいない場合
被相続人に子供や孫、両親、兄弟や甥・姪がいない場合には、相続人は配偶者だけです。子供がいなくても、孫がいる場合にはその孫が代襲相続人になります。また、兄弟姉妹がいなくても、甥や姪がいれば、甥や姪が代襲相続人となります。
そのため、代襲相続人すらいない場合には、配偶者のみが相続人となるため、配偶者だけが遺産を相続することになります。
パターン2:遺産分割協議で合意した場合
遺産分割協議とは、亡くなった方の財産について、法定相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意のもとで遺産を分割する手続きです。
将来のトラブルを避け、不動産登記などの手続きを円滑に進めるためにも、その内容を遺産分割協議書として残すことが重要です。
配偶者以外にお子様、ご両親、ご兄弟といった法定相続人がいる場合でも、その全員が「全財産を配偶者一人に相続させる」ことに同意すれば、配偶者が全ての遺産を相続できます。
遺産分割協議書には、以下の内容を明確に記載し、相続人全員が署名および実印で押印します。また、各相続人の印鑑証明書も添付が必要です。
- 誰がどの財産をどれだけ取得するか
- 相続人全員の署名
- 相続人全員の実印
- 各相続人の印鑑証明書(添付)
パターン3:他の相続人が相続放棄をした場合
相続放棄とは、亡くなった方のプラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も一切相続しない旨を家庭裁判所に申し立てる手続きです。配偶者以外の子、親、兄弟姉妹といった他の相続人全員がこの相続放棄の手続きを行うと、結果として配偶者が全ての遺産を単独で相続することになります。
相続放棄は、自己のために相続が開始されたことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められなくなるため注意が必要です。一度、相続放棄が受理されると、原則としてその決定を撤回することはできません。そのため、慎重な検討と迅速な手続きが求められます。
パターン4:「全財産を配偶者に」という内容の遺言書があった場合
亡くなった方が生前に有効な遺言書を作成しており、その内容に「全財産を配偶者に相続させる」旨が記されていれば、原則として配偶者がすべての遺産を単独で相続できます。遺言書は法定相続のルールに優先して効力を持つため、たとえ他に相続人がいても、遺言の内容が尊重されるのです。
ただし、遺言書があっても、配偶者以外の特定の相続人には「遺留分」という最低限の遺産を受け取る権利が法律で保障されています。遺留分が認められる相続人と認められない相続人は以下の通りです。
もし遺留分を侵害された相続人から「遺留分侵害額請求」があった場合、基本的には金銭で支払うことで解決を図ります。複雑な交渉や計算が伴うため、このようなケースでは弁護士などの専門家へ相談し、トラブルを未然に防ぐことを強くおすすめします。
相続税はいくらかかる?知っておきたい配偶者のための税金特例
遺産を相続するにあたり、相続税がいくらかかるのか不安に感じる方は少なくありません。
以下の項目では、相続税の基礎控除の仕組みと、配偶者に適用される税額軽減の特例について詳しく解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら、ぜひ参考にしてください。
そもそも相続税は必ずかかる?基礎控除の仕組み
相続税は、亡くなった方の遺産総額が一定の金額を超えない限りは課税されない税金です。相続税に不安を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際には全体の約92%の方が相続税の申告を必要としません。そのため、過度な心配は不要なケースも多いでしょう。
相続税がかかるかどうかの基準となるのが「基礎控除額」です。遺産総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税の申告も納税も一切必要ありません。まずご自身の遺産総額が基礎控除額を超えるかどうかを確認することが大切です。
基礎控除額は、以下の計算式で算出されます。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
この計算式に、ご自身のケースでの法定相続人の数を当てはめて計算してみましょう。法定相続人の数に応じた基礎控除額の具体的な計算例は以下の通りです。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額の計算式 | 基礎控除額 |
| 1人 | 3,000万円 +(600万円 × 1人) | 3,600万円 |
| 2人 | 3,000万円 +(600万円 × 2人) | 4,200万円 |
| 3人 | 3,000万円 +(600万円 × 3人) | 4,800万円 |
このように、法定相続人の数によって基礎控除額は異なります。まずはご自身のケースに当てはめて、おおよその目安を把握しておくことが重要です。
配偶者なら安心「配偶者の税額軽減」とは
配偶者の税額軽減とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者が相続する遺産について、一定額までは相続税がかからないという特例です。具体的には、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分に相当する金額」のどちらか多い金額までは、相続税が課税されません。この特例があるため、多くの場合、配偶者が相続税を支払う必要がなくなります。
例えば、遺産総額が1億円で、配偶者がすべての財産を相続した場合でも、この特例を適用すれば相続税額は0円になります。これは、1億6,000万円という非課税枠が遺産総額の1億円を上回るためです。
この「配偶者の税額軽減」を適用するには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 法律上の配偶者であること:戸籍上で婚姻関係にある配偶者のみが対象であり、内縁関係の配偶者は含まれません。
- 相続税の申告書を提出すること:税額が0円になる場合でも、必ず相続税の申告書を税務署に提出する必要があります。
- 遺産分割が確定していること:申告期限までに、誰がどの財産を相続するのか遺産分割協議がまとまっている必要があります。
税額0円でも申告は必要?注意すべきポイント
「配偶者の税額軽減」を適用した結果、相続税が0円になったとしても、税務署への相続税申告は原則として必要です。この特例は「相続税の申告書を提出すること」が適用要件の一つであるためです。申告が不要となるのは、遺産総額が基礎控除額以下の場合のみです。申告書を提出しなければ、特例は適用されず、本来の相続税を支払う義務が生じてしまいます。
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。納税額が0円の場合でも、この期限内に申告書を提出しないと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが発生する可能性があるため、注意が必要です。
【やることリスト】相続発生から手続き完了までの全ステップ
大切な方を亡くされ、深い悲しみの中で、様々な相続手続きに直面されている方もいらっしゃるでしょう。
以下では、相続発生から完了までの具体的な流れを、時系列に沿った「やることリスト」として分かりやすく解説します。一つずつ確認しながら、着実に手続きを進めていきましょう。
ステップ1:死亡届の提出と遺言書の確認
ご主人様が亡くなられたら、まず最初に行うべき手続きは「死亡届の提出」です。死亡の事実を知った日から7日以内(戸籍法第八十六条に規定)に、市区町村役場に提出します。この際、医師が作成した死亡診断書(または死体検案書)を添付し、通常、火葬許可申請も同時に行います。提出が遅れると、過料が科せられたり、火葬許可が得られずに葬儀に影響が出たりする可能性があるため、速やかに手続きを進めることが重要です。
死亡届の提出と並行して、遺言書の有無を確認することも非常に重要です。遺言書があるかどうかで、その後の相続手続きが大きく変わるためです。
ご自宅や貸金庫のほか、公証役場で公正証書遺言を作成している場合は、公証役場で遺言書の有無を検索できます。特に、法務局で保管されていない自筆証書遺言は、勝手に開封してはいけません。必ず家庭裁判所で検認という手続きを行い、遺言書の内容を相続人全員に確認してもらう必要があります。
| 遺言書の種類 | 主な保管場所・作成方法 | 開封・手続きの要否 |
| 公正証書遺言 | 公証役場で作成・保管 | 検認手続きは不要 |
| 自筆証書遺言 | 自宅などで保管(法務局での保管制度もあり) | 法務局での保管制度を利用していない場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要 |
ステップ2:相続人の調査と確定(戸籍謄本の収集)
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。この協議を法的に有効に進めるには、まず誰が相続人であるかを正確に確定することが不可欠です。ご自身の知らない相続人がいる可能性もゼロではないため、後のトラブルを避けるためにも、相続人調査は必ず実施しましょう。
相続人調査では、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集める必要があります。これには現在の戸籍謄本だけでなく、除籍謄本や改製原戸籍謄本も含まれます。これらの戸籍を遡って確認することで、亡くなった方の離婚・再婚歴や養子縁組の有無など、現在の戸籍だけではわからない情報を把握し、すべての法定相続人を漏れなく特定できます。
もしご自身での手続きが難しいと感じる場合は、弁護士などの専門家への依頼も検討してみましょう。
ステップ3:相続財産の調査と評価
遺産分割や相続税申告の手続きを進めるには、まずすべての相続財産を正確にリストアップした「遺産目録」を作成することが不可欠です。
遺産目録には、預貯金や不動産、有価証券といった「プラスの財産」だけでなく、借金や住宅ローンなどの「マイナスの財産」もすべて記載します。
財産調査の第一歩として、被相続人の通帳、キャッシュカード、証券会社からの郵便物などを探します。取引の可能性のある金融機関の窓口に照会することで、その銀行の別支店にある口座も含め、預貯金の有無や残高を確認できます。借金がないか不安な場合は、全国銀行個人信用情報センター、CIC、JICCといった信用情報センターに問い合わせて確認できるでしょう。
ステップ4:遺産分割協議と協議書の作成
相続人が複数いる場合、誰がどの遺産をどれだけ相続するかを話し合う「遺産分割協議」が必要です。これは、相続発生後のトラブルを未然に防ぎ、その後の手続きを円滑に進めるために不可欠です。
相続人間の話し合いで合意した内容は、必ず「遺産分割協議書」として書面に残しましょう。この書類は、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約・名義変更といった、さまざまな相続手続きで提出が求められる重要なものです。
なお、法定相続人が配偶者のみの場合や、他の相続人全員が相続放棄をした場合は、遺産分割協議自体が不要となります。
| 項目 | 内容 |
| 被相続人の情報 | 亡くなった方の氏名、生年月日、死亡年月日、本籍地、最後の住所などを正確に記載します。 |
| 相続財産の内容 | 誰がどの財産をどれだけ相続するかを具体的に明記します。 |
| 協議日・署名日 | 遺産分割協議が成立した日付、または相続人全員が最後に署名した日付を記載します。 |
| 署名・押印 | 相続人全員が自ら署名し、実印を押印します。 |
| 添付書類 | 相続人全員の印鑑証明書を添付します。 |
ステップ5:預貯金の解約や不動産の名義変更
遺産分割協議がまとまり、どの財産を誰が相続するのか確定したら、次に実際の財産の解約や名義変更の手続きを進めます。預貯金や不動産は、それぞれ異なる方法で相続手続を進める必要があります。
不動産の名義変更は、「相続登記」として法務局で行います。この相続登記は、2024年4月1日から義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請が必要となり、これに違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続手続きは複雑なため、弁護士などの専門家へ依頼することも検討すると安心です。
ステップ6:相続税の申告・納税(10ヶ月以内)
相続手続きの最終段階として、相続税の申告と納税が必要です。原則として、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、これらの手続きを完了させなければなりません。この期限を過ぎるとペナルティが課される可能性があるため、計画的に手続きを進めることが重要です。
期限厳守を強く意識し、不明な点があれば税理士へ相談することをおすすめします。
相続手続きで失敗しないための注意点
被相続人が残した財産を円滑に、そして確実に引き継ぐためには、いくつかの注意点を押さえておくことが重要です。後悔しないためにも事前に知っておきたいポイントを解説します。
亡くなった夫に借金が見つかった場合の対処法
亡くなった配偶者に借金などのマイナスの財産があった場合、預貯金や不動産といったプラスの財産と同様に、それらも相続の対象となります。もし多額の借金が判明し、その返済義務を負いたくないと考えるのであれば、「相続放棄」または「限定承認」という二つの手続きを検討することが可能です。
「相続放棄」を選択すれば、借金返済の義務はなくなりますが、同時に預貯金や自宅なども受け取れなくなります。
一方、「限定承認」は、相続したプラスの財産の範囲内でのみ借金を返済し、もしプラスの財産が残ればそれを受け取れる手続きです。限定承認には相続人全員の同意が必要で、手続きは複雑で手間がかかります。
遺産の分け方で揉めてしまったらどうする?
遺産の分け方について相続人同士の意見がまとまらず、話し合いでの解決が難しい場合には、家庭裁判所での手続きを検討する必要があります。まず、「遺産分割調停」を家庭裁判所に申し立てます。これは、裁判所の調停委員が中立の立場で間に入り、相続人それぞれの意見を聞きながら、話し合いによる合意形成を目指す手続きです。
もし調停でも合意に至らなかった場合は、「遺産分割審判」へと移行します。審判では、これまでの主張や提出された証拠に基づき、最終的に裁判官が客観的な視点から遺産の分割方法を決定します。
対立が深刻化する前に、相続トラブルの解決を専門とする弁護士へ相談することも有効な手段です。弁護士のアドバイスを受けることで、法的な観点から冷静に状況を整理し、円満な解決へ導くことが可能となるでしょう。
次の相続(二次相続)で子どもに負担をかけないために
亡くなられた方の財産を配偶者のみが相続する場合、次に起こる「二次相続」(今回遺産を相続した配偶者が亡くなった際の相続)において、お子様の相続税負担が重くなる可能性があります。一次相続では配偶者の税額軽減特例があるため相続税が抑えられることが多いですが、二次相続ではこの特例が適用されません。
さらに、法定相続人の数が減少すると、相続税の基礎控除額も少なくなります。
これらの要因により、二次相続では結果的に家族全体で支払う相続税の総額が高くなるケースが見られます。
将来のお子様の負担を軽減するためには、一次相続の時点で対策を講じることも可能です。具体的な対策としては、以下のような方法が挙げられます。
- お子様にも一部財産を相続させ、家族全体で支払う相続税の総額を抑える。
- 生前贈与を活用する。
- 生命保険を活用する。
次の相続で遺産分割のトラブルが生じないよう、ご自身が相続した財産について「誰に何を遺すか」を明確にした遺言書を作成しておくことも重要です。
相続人同士のトラブルは「弁護士」に相談
遺産相続は、時に感情的な対立を引き起こし、相続人同士のトラブルに発展するケースも少なくありません。遺産の分け方で意見がまとまらない、あるいは他の相続人と連絡が取れないといった状況では、当事者間での解決は非常に困難になります。そのような時に頼りになるのが弁護士です。
弁護士は、相続人の代理人として、以下の手続きを進められる唯一の専門家です。
- 他の相続人との交渉代理
- 家庭裁判所で行われる遺産分割調停や審判の手続きの代理
複雑な法律問題が絡む相続トラブルにおいて、法的な観点から冷静な解決策を導き出し、ご自身にとって有利な結果を目指して尽力します。
感情的な対立が深まりやすい相続の場面では、弁護士が介入することで、状況が客観的に整理され、円滑な話し合いにつながることも期待できるでしょう。将来にわたる人間関係への影響を最小限に抑えつつ、適切な解決を目指せます。
1人で悩まずに難波みなみ法律事務所に相談を

この記事では、配偶者の方が遺産を相続するケースを中心に、法定相続人の範囲から、配偶者のみが遺産を相続できるパターン、そして配偶者に適用される相続税の特例までを解説いたしました。慣れない手続きの多さや、複雑な専門用語に、不安や戸惑いを感じることもあるかもしれません。もし、手続きを進める中で「自分一人では難しい」と感じたり、「これはどうしたら良いのだろう」と不安になったりした場合は、決して一人で抱え込まず、弁護士へ相談することも有効な選択肢です。
当事務所では初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。お気軽にご相談ください。
対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。