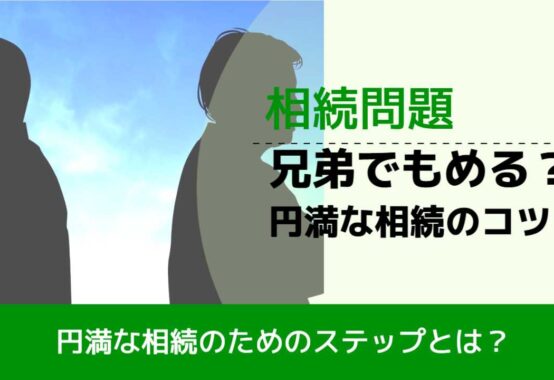相続が発生した際、故人が受け取るはずだった年金、いわゆる「未支給年金」が発生する場合があります。しかし、相続放棄を検討している場合、この未支給年金がどう扱われるのか、受け取ると相続放棄に影響があるのかなど、疑問や不安を感じる方もいるのではないでしょうか。
本記事では、未支給年金の制度について、相続放棄との関係、具体的な手続き方法、そして注意すべき点などをわかりやすく解説します。「相続放棄」を考えている方にとって、未支給年金の扱いは重要なポイントです。
【結論】相続放棄をしても未支給年金は受け取り可能
故人が亡くなった際にまだ受け取れていない年金(未支給年金)は、遺族が相続放棄をした場合でも受け取ることができます。
以下では、未支給年金を受け取っても相続放棄できる理由や受け取れる人の範囲を解説します。
未支給年金が相続財産に含まれない理由
未支給年金は故人の相続財産には含まれないと解されています。
未支給年金が相続財産に含まれないのは、その受給権が年金法によって、民法上の相続とは別の立場から所定の遺族を受給権者と規定した上で、未支給年金の受給を認めています。そのため、未支給年金に関する権利は、遺族自身の「固有の権利」として位置づけられているといえ、相続財産には当たらないと解されています。
そのため、仮に故人に負債があり、相続放棄を選択して故人の財産を一切引き継がない場合でも、この遺族固有の権利である未支給年金は受け取ることが可能です。
未支給年金を受け取れる人の範囲と優先順位
未支給年金を受け取れるのは、故人と死亡時点で生計を同じくしていた遺族に限られます。この「生計を同じくしていた」という点が重要な要件であり、単に相続人であるかどうかにかかわらず適用されます。遺族の範囲と優先順位は法律で明確に定められており、優先順位が高い人がいる場合、下位の人は請求できません。
この順位に基づき、例えば故人に配偶者がいる場合、子がいても配偶者が最優先の請求権者となります。また、同じ順位の人が複数いる場合、例えば子が2人いるケースでは、その中の代表者1人が請求手続きを行い、受け取った年金は全員分とみなされます。
| 順位 | 対象者 |
| 第1順位 | 配偶者 |
| 第2順位 | 子 |
| 第3順位 | 父母 |
| 第4順位 | 孫 |
| 第5順位 | 祖父母 |
| 第6順位 | 兄弟姉妹 |
| 第7順位 | その他三親等内の親族 |


未支給年金を請求するための具体的な手続きの流れ
故人が亡くなり、本来受け取るはずだった年金がまだ支払われていない「未支給年金」が発生した場合、遺族は、日本年金機構に対し請求手続きを行う必要があります。
この手続きは、大きく分けて以下の2つのステップで完了します。
- 必要書類の準備
- 年金事務所または年金相談センターへの提出
以下の項目ではこれらの具体的なステップについて、必要となる書類や提出方法を含めて詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
ステップ1:必要書類の準備と入手方法
未支給年金の請求手続きを進めるにあたり、まず最初に行う重要なステップは、必要書類を正確に準備することです。まず、請求に必須となる「未支給年金・給付請求書」と「受給権者死亡届」を入手してください。これらの書類は、お近くの年金事務所や街角の年金相談センターで受け取れるほか、日本年金機構のウェブサイトからもダウンロードが可能です。
これらの書類以外に、一般的に必要となる主な書類は以下の通りです。
- 故人の年金証書
- 住民票除票、除籍謄本、死亡診断書
- 請求者の戸籍謄本
- 請求者の世帯全員の住民票の写し
- 受け取りを希望する金融機関の通帳または口座情報のわかるもの
なお、故人と請求者の住所が異なるなど、住民票上生計が同一であることが確認できない場合は、「生計同一関係に関する申立書」の提出が追求められます。書類の準備に関して不明な点があれば、事前に年金事務所へ問い合わせて確認することで、手続きをスムーズに進めることができます。
ステップ2:年金事務所または年金相談センターへの提出
準備された書類は、故人の最終住所地を管轄する年金事務所または街角の年金相談センターへ提出します。提出方法には、窓口への持参と郵送の2通りがあります。
手続き前に確認!未支給年金を受け取る際の注意点
未支給年金は相続財産とは異なり、相続放棄後でも遺族固有の権利として受け取れるため、大きな安心材料といえるでしょう。しかし、実際に請求手続きを進める前には、いくつかの重要な注意点があります。以下の項目からは、特に押さえておきたい具体的な注意点について詳しく解説していきます。
請求期限は5年!時効に注意
未支給年金の請求には、厳格な期限が設けられています。年金受給者が亡くなられた場合、未支給年金の請求権には時効があることにご留意ください。具体的には、年金の支払日翌月の初日から起算して5年が経過すると、時効により請求する権利が消滅します。この期間を過ぎてしまうと、原則として未支給年金を受け取ることができなくなるため、十分に注意が必要です。
未支給年金の請求権を失わないよう、他の相続関連の手続きと並行して、できる限り速やかに未支給年金の手続きを進めることが重要です。
受け取った年金は「一時所得」として確定申告が必要な場合も
未支給年金は、相続財産ではなく、請求者自身の「固有の権利」として受け取れるため、相続税の課税対象にはなりません。しかし、所得税法上は「一時所得」として扱われ、所得税・住民税の課税対象となる点には注意が必要です。
未支給年金を受け取る場合、年金保険料は故人が支払っており、請求者には通常、収入を得るための経費が発生しません。そのため、総収入額から特別控除額50万円を差し引いた金額が一時所得として扱われます。
企業年金や個人年金は原則受け取れない
公的年金である未支給年金とは異なり、企業年金や個人年金の取り扱いは異なりますので注意が必要です。これらは原則として故人の「相続財産」と見なされることが多いため、もし相続放棄を選択すると、受け取ることが難しくなる可能性があります。これは、故人の財産を一切引き継がないという相続放棄の性質によるものです。
ただし、個人年金の年金支払期間中に被保険者が死亡した場合には、未払いの年金(未払年金現価)が保険金受取人に支払われることがあります。この未払年金現価は、相続財産に属さず受取人固有の財産と考えられるため、これを相続放棄した相続人が受け取れる余地があります。
故人の口座に振り込まれた年金は引き出さない
未支給年金そのものは遺族固有の権利として相続財産には含まれません。しかし、故人が死亡することで銀行口座は凍結されるため、振り込まれた未支給年金を引き出すことができません。
ただ、未支給年金が故人の口座に振り込まれたとしても、固有の財産として取り戻すことができます。相続人は未支給年金の受給権者に未支給年金を返還する義務を負います。相続人が全員相続放棄した場合には、相続財産清算人から未支給年金の返還を受けることになります。
【一覧】相続放棄で受け取れるお金・受け取れないお金
相続放棄を検討する際、「故人の財産は一切受け取れない」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし実際には、相続放棄をしても受け取れるお金と、受け取ると相続放棄ができなくなる可能性のあるお金が存在します。
以下の項目では、相続放棄をしても問題なく受け取れるお金と、受け取ると相続放棄ができなくなるお金を、以下の表にまとめました。
相続放棄後も受給できるお金(遺族年金・生命保険金など)
相続放棄を検討している方の中には、故人に関するあらゆる金銭を受け取れないと誤解されているケースも少なくありません。しかし、未支給年金と同様に、相続放棄をしても受け取れるお金は確かに存在します。
具体的な例としては、まず遺族年金が挙げられます。遺族年金は、故人が亡くなった後の遺族の生活保障を目的としたものであり、年金法に基づき受給者自身の固有の権利として発生します。
次に、受取人が指定された生命保険金も相続財産には含まれません。保険契約で特定の受取人が指定されている場合、その保険金は受取人固有の財産とみなされ、故人の相続財産には含まれないことが最高裁判所の判例でも示されています。
また、社内規定により受給者が受取人と定められている死亡退職金も同様に、相続放棄後も受け取りが可能です。
ただし、注意点もあります。例えば、生命保険金の受取人が故人本人とされていたり、あるいは死亡退職金を定めた社内規定がない場合は、これらが相続財産となり、受け取ってしまうと相続放棄ができなくなる可能性があるため、必ず事前に確認することが重要です。
受け取ると相続放棄できなくなるお金(預貯金・不動産など)
相続放棄を検討されている方が特に注意すべきは、故人のプラスの財産を受け取ったり、処分したりする行為です。これらの行為は、民法で定められている「法定単純承認」に該当し、原則として相続放棄ができなくなる可能性があります。法定単純承認が成立すると、故人のすべての財産だけでなく、借金などの負債もすべて引き継ぐことになってしまうため、この点は非常に重要です。
これらの行為は、故人の借金を含むすべての債務を承継することを意味します。そのため、相続放棄を考えている場合は、故人の預貯金や不動産といったプラスの財産には、安易に手を付けないよう、十分にご注意ください。誤って法定単純承認とみなされないためにも、専門家への相談も検討されることをお勧めします。
| 相続財産の種類 | 法定単純承認とみなされうる主な行為 |
| 預貯金 | 故人の銀行口座からの引き出しや消費 |
| 不動産 | 故人名義の土地や建物の売却、賃貸、名義変更 |
| 株式 | 故人名義の株式の売却や名義変更 |
| 自動車 | 故人名義の自動車の売却、廃車、名義変更 |
| 生命保険金・死亡退職金 | 受取人が故人本人と指定されている場合の受領 |
相続放棄の問題は難波みなみ法律事務所へ

本記事では、故人が他界した際に未払いだった年金、いわゆる未支給年金が、相続放棄をした場合でも遺族が受け取れる「固有の権利」であることを解説しました。
つまり、故人に負債があり相続放棄を選択した場合でも、この遺族固有の権利である未支給年金は、影響を受けることなく請求できます。決して「負債があるから年金も受け取れない」と諦める必要はありません。
また、相続放棄についても、相続開始したことに加えて、自身が相続人となることを知った日から3か月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります。
不慣れな手続きをご自身で全て行うことは大きな負担を招きますし、場合によっては期限内に手続きを完了できない事態も招きます。
そこで、相続放棄や未支給年金の各種手続きでお悩みがあれば速やかに弁護士に相談することをおすすめします。