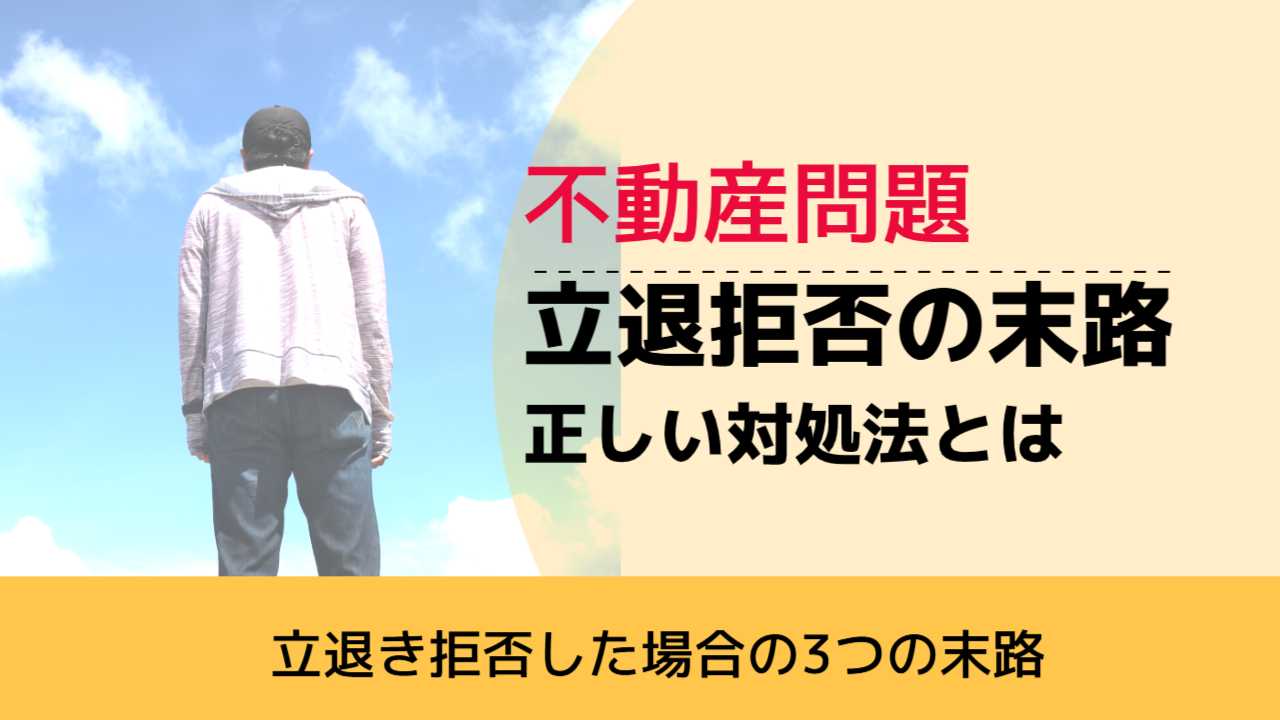立ち退きを求められた時、さまざまな理由から「どうしても立ち退きたくない」と考える方は少なくありません。しかし、立ち退き拒否を続けた末路には、予期せぬリスクが潜んでいることも。
本記事では、貸主からの立ち退きを拒否した場合に起こりうる事態を、弁護士が法的な側面から詳しく解説します。
まず知っておきたい大前提!立ち退き要求は拒否できるのが基本
大家さんから立ち退きを求められたとしても、その要求にすぐに応じる必要はありません。実は、借主は「借地借家法」という法律によって手厚く保護されており、大家さんからの一方的な立ち退き要求は、正当な事由がない限り拒否することができます。
借主は「借地借家法」という法律で手厚く保護されている
賃貸物件に住む借主は、借地借家法という法律によって手厚く保護されています。この法律は、経済的・社会的に弱い立場に置かれがちな借主が住居等を確保できるよう、その権利を守ることを目的に制定されました。貸主からの突然の立ち退き要求により、住み慣れた家を安易に失うことのないよう、借主の居住の安定を保障するものです。
そこで、借地借家法では、貸主が賃貸借契約の更新を拒絶したり、解約を申し入れたりするためには、「正当事由」がなければならないと明確に定めています(借地借家法第28条)。「正当事由」とは、立ち退きを求める合理的な理由を指します。この正当事由がなければ、貸主の都合だけで一方的に立ち退きを強制することはできません。
この「正当事由」が認められるための賃貸人側のハードルは非常に高く、容易には認められません。例えば、単に賃貸人の個人的な都合だけでは不十分とされています。
賃貸人からの一方的な立ち退き要求は認められない
貸主が立ち退きを要求しても、借主がその要求に合意しない限り、賃貸借契約が一方的に解除されることは原則としてありません。これは、借地借家法によって借主の居住権が手厚く保護されているためです。この法律では、賃貸人が賃貸借契約の更新を拒絶したり、解約を申し入れたりする際には、「正当事由」が不可欠であると定められています(借地借家法第28条)。
この「正当事由」は、単に貸主側の都合や、物件を売却したいといった個人的な理由だけでは、簡単に認められるものではありません。裁判所でもその必要性は厳格に判断され、非常にハードルの高い要件とされています。そのため、立ち退き要求を受けたとしても、借主は賃貸人の一方的な要求を鵜呑みにせず、まずはその内容を慎重に確認することが重要です。


要注意!立ち退き拒否が認められない「正当事由」があるケース
借地借家法によって借主の権利は一定程度保護されていますが、貸主側に「正当事由」が認められる場合には、立ち退き要求を拒否しきれない例外が存在します。以下の項目は、具体的にどのような場合に正当事由が認められやすいのか、代表的なケースを詳しく解説します。
建物が老朽化し、倒壊などの危険性が高い場合
貸主が立ち退きを求める「正当事由」の事情として、建物の老朽化が挙げられる場合があります。しかし、単に築年数が古いというだけで、正当事由として認められることは困難でしょう。重要なのは、建物が客観的に見て、地震や台風といった自然災害時に倒壊の危険性があるなど、安全に住み続けることが困難な状況である必要があります。例えば、耐震基準を大幅に満たしておらず、耐震補強工事が多額である場合、建物の中枢部分に腐食や白アリ被害があり老朽化が顕著である場合などが挙げられます。他方で、耐震性不足があったとしても、安価で容易に耐震補強工事できる場合には正当事由が否定される可能性があります。
ただ、建物の老朽化という一事だけでなく、建物の老朽化を契機に建物を取り壊した上で新たな建物を建築するという有効活用の計画が具体的に作られているのかもポイントになります。
貸主自身が建物を使わなければならない高度な必要性がある場合
貸主自身がその物件を使用する高い必要性がある場合、立ち退きの「正当事由」を基礎付ける事情となります。これは「自己使用の必要性」と称され、貸主と借主双方の建物使用の必要性を比較検討し、総合的に判断されます。
例えば、高齢の親の介護のため、実家である当該物件に戻り同居する必要がある場合、失業や病気により経済的に困窮し、現在住んでいる物件の家賃が支払えず、自己所有の当該物件に住むしかなくなった場合などが挙げられます。
一方で、単に「そこに住みたい」という理由や、他に物件を所有しているにもかかわらず自己使用を主張するだけでは、正当事由として十分とはいえません。あくまで、貸主側の自己使用の必要性が「高い」と判断される場合に限られます。そして、立ち退き料の支払いやその金額も、正当事由を補完する重要な要素となります。
家賃滞納など、借主側に契約違反がある場合
借主側の契約違反は、大家さんからの立ち退き要求における「正当事由」の最も典型的な例です。例えば、3ヶ月以上の家賃滞納がある場合には、当事者間の信頼関係を破壊させる契約違反として賃貸借契約を解除させることができます。
他方で、賃料不払いなどの契約違反はあるものの、信頼関係を破壊させるほどの重大な違反ではない場合には、一方的な解除は認められませんが、正当事由の判断要素の一つになります。家賃滞納の他にも、以下のような契約違反が立ち退きの正当事由となることがあります。
十分な額の立ち退き料の申し出がある場合
貸主側からの立ち退き料の申し出は、建物の老朽化や自己使用の必要性といった他の正当事由を補強し、立ち退き要求が認められる可能性を高める重要な要素となります。立ち退き料はあくまで正当事由を『補完する』ものであり、立退料単独で立ち退きを強制できる理由にはなりません。しかし、裁判所が正当事由の有無を判断する際に、貸主側が提示する立退料の金額が、正当事由の判断を左右させます。
『十分な額』とされる立ち退き料は、借主が現在の物件から新しい住居へ移転する際に発生する経済的な損失を補償するものです。具体的には、以下の費用が考慮されます。
| ・引っ越し費用 ・新居の仲介手数料(新居の賃料1ヶ月分など) ・礼金相当額 ・現在の家賃と新居の家賃の差額分 |
【本題】立ち退きを拒否し続けた場合に起こり得る3つの末路

立ち退き要求を拒否し続けることは、自身の権利を守る上で重要な場合もあります。しかし、それが必ずしも借主にとって良い結果だけをもたらすとは限りません。特に、貸主との対話を避け、一方的に居住を続けた場合には、状況が段階的に悪化する可能性があります。
このセクションでは、話し合いに応じない姿勢を取り続けた場合に起こり得る、3つの典型的な「末路」について具体的に解説します。
末路①:貸主との関係が悪化し精神的に疲弊する
立ち退き要求を拒否し続けると、貸主との関係は著しく悪化し、日常生活で精神的な疲弊を感じやすくなります。交渉が平行線をたどると、感情的な対立に発展するケースも少なくありません。
賃貸人と賃借人の関係が険悪になり、安らげるはずの自宅が、常にプレッシャーを感じるストレス空間へと変わってしまうこともあります。
長期にわたるストレスは、うつ病などの心身の不調を引き起こす可能性もあります。
末路②:裁判に発展し、多くの時間と費用を消耗する
貸主との交渉が決裂し、話し合いでの解決が見込めない場合、貸主側が「建物明渡請求訴訟」という裁判を起こす可能性があります。これは、貸主が借主に対し、建物の明け渡しを法的に求める手続きです。裁判に発展すると、精神的な負担に加え、多大な時間と費用を要することになります。
訴訟手続の期間は1年前後、ケースによって1年以上を要することも珍しくありません。この間、裁判への対応に追われ続けるため、日常生活への影響は避けられないでしょう。
また、裁判を有利に進めるには、弁護士への依頼が不可欠です。弁護士費用に加え、訴訟の実費も発生します。もし裁判で敗訴すれば、立ち退き料が一切支払われない可能性もあります。
末路③:敗訴して「強制執行」により無理やり退去させられる
貸主との裁判で貸主側の「正当事由」が認められ、借主が敗訴した場合、最終的に「強制執行」によって強制的に退去させられることになります。強制執行とは、裁判所の執行官が自宅を訪れ、借主の意思に関わらず家財道具を運び出し、鍵を交換することで、強制的に建物の明け渡しを行う手続きです。これは、住み慣れた家から文字通り「追い出される」ことを意味します。
その上、強制執行にかかる費用の請求も受けることになりますので、重い経済的な負担を負うことになります。強制執行にかかる費用の主な内訳は以下の通りです。
- 執行官の費用(6万円前後)
- 執行業者の費用(30万円から60万円程)
- 動産執行の予納金(家財道具の撤去や保管にかかる費用として、3万円から5万円程度)
最悪の事態を回避するために!立ち退きを要求された時の正しい対処法
貸主から立ち退きを要求されても、焦ってその場で即答することは避け、冷静に対応することが肝心です。以下の項目では、貸主から立ち退きを求められた際に、借主として取るべき対応を解説します。
その場で即決せず、通知書の内容を詳しく確認する
貸主から口頭や電話で立ち退きを求められたとしても、その場で安易に承諾することは避けるべきです。まずは冷静に、書面による正式な通知を送ってもらうよう依頼することが第一歩となります。書面でやり取りすることで、後々のトラブルを防ぎ、交渉の記録を残すことができます。
正式な通知書が届いたら、その内容を詳細に確認することが極めて重要です。特に、以下の点を確認しましょう。
- 立ち退きを求める具体的な理由
- 立ち退き期限
- 立ち退き料に関する記載の有無と金額
感情的にならず、交渉のテーブルにつく姿勢を見せる
突然の立ち退き要求に直面すると、怒りや不安を感じるのは自然なことです。しかし、その感情のまま貸主に対し、頭ごなしに拒絶する、一方的に連絡を無視するといった態度は控えるべきです。
このような感情的な言動は、貸主側の態度を硬化させ、その後の交渉を著しく不利にするリスクがあります。冷静さを欠いた対応は、トラブルの原因となり、最終的な解決を遠ざけることにもつながりかねません。
円満な解決と、ご自身にとって有利な条件を引き出すためには、「話し合いに応じる」という冷静な姿勢を示すことが第一歩です。貸主側の事情に耳を傾け、交渉の場につくことで、まずは相手が立ち退きを求める「正当事由」の有無やその詳細を正確に把握する機会が生まれます。
立ち退き料が生活再建に十分な額か検討する
立ち退き料は、単なる迷惑料としてではなく、現在の生活状況や水準を維持したまま新しい生活を始めるための重要な「補償」として捉える必要があります。これは、転居に伴う経済的な損失を適切に補填する目的で支払われるものです。
貸主から提示された立退料の金額を安易に受け入れるのではなく、ご自身で立ち退きに伴い生じる負担を具体的に算出することが重要です。不動産会社や引っ越し業者から実際に見積もりを取り、生活再建に必要な正確な金額を把握しましょう。算出した具体的な金額を根拠として、提示された立ち退き料が十分な額であるかを冷静に判断し、交渉に臨むことが賢明です。
これをやれば有利に?納得できる立ち退き料を引き出す交渉のコツ
立ち退きを求められた場合、単に要求を拒否し続けるだけでは、状況を悪化させてしまう恐れがあります。納得できる条件で円満な立ち退きを実現するためには、適切な交渉術が不可欠です。
以下では、具体的な交渉のコツについて詳しく解説していきます。
立ち退き料の一般的な相場と内訳とは
立ち退き料は、法的に一律の金額が定められているわけではありません。居住用建物の場合には、引越し費用等の移転費用に加えて転居後の賃料と現賃料との差額を加算して立退料を算出することが一般的ですが、賃料の6か月分から1年分や借家権割合を基準に立退料を簡易的に計算することもあります。
ただし、これはあくまで一般的な目安であり、物件の状況や大家さんの都合など、個別の事情によってその金額は大きく変動します。
この立ち退き料の金額は、貸主側の建物使用の必要性の強弱によって大きく左右される傾向があります。貸主側の事情が弱いほど、より高額な立ち退き料が認められる可能性が高まります。
引っ越し費用や次の家の家賃差額など、具体的な金額を提示する
立ち退き料の交渉において、単に「困る」と主張するだけでは、交渉を有利に進めることは難しいでしょう。ご自身の生活再建に具体的にいくら必要なのか、その根拠を明確に提示することが極めて重要です。
具体的に提示すべき費用の内訳は多岐にわたります。主なものとしては、以下の費用が挙げられます。
- 新居の契約初期費用
- 引っ越し業者に支払う費用
- 転居先の賃料差額
- インターネット回線や電話の移設費用、火災保険・地震保険の移転費用
交渉の経過は必ず書面や録音で記録しておく
賃貸人との立ち退き交渉を進めるにあたり、後々の水掛け論を防ぐためにも、交渉の経過を正確に記録しておくことが極めて重要です。この記録は、万が一のトラブル発生時に客観的な証拠として大きな力を発揮します。
最も確実な方法としては、交渉日時、参加者、協議内容、合意事項などを記した議事録等を作成し、双方で内容を確認した上で署名・捺印し、保管することが挙げられます。書面でのやり取りが難しい場合や、口頭での交渉が主体となる場合は、ICレコーダーやスマートフォンの録音機能を利用して会話を記録することも有効な手段です。
弁護士に相談するメリットと依頼すべきタイミング
立ち退き問題において、弁護士に相談する最大のメリットは、貸主の立ち退き要求に「正当事由」があるかを客観的に判断できる点です。法律の専門家である弁護士は、借地借家法に基づき、その正当事由の強弱を的確に見極めます。そして、法的な根拠に基づいた適切な反論を行うことで、借主の権利が不当に侵害されることを防ぎます。
また、交渉の代理人となってもらうことで、貸主と直接やり取りする精神的負担や時間的コストを大幅に軽減できる点も大きな利点です。弁護士は法的根拠や客観的な事実に基づき交渉を進めるため、感情的な対立を避け、より建設的な話し合いが期待できます。立ち退き料の増額交渉においても、過去の判例や法的な根拠に基づいた有利な条件を引き出しやすくなるでしょう。万が一、建物明渡請求訴訟に発展した場合でも、弁護士がスムーズに対応を代行するため、精神的・金銭的負担を軽減し、早期解決を目指せるでしょう。
弁護士に相談・依頼すべきタイミングは以下の通りです。
- 貸主から立ち退き通知書が届いた初期段階
- 当事者同士の交渉が行き詰まった際
- 裁判所から訴状が届いた際
これらのタイミングで速やかに弁護士に相談することで、最悪の事態を回避し、最善の解決策を見つけることにつながります。
立ち退き問題は難波みなみ法律事務所へ

本記事では、貸主からの立ち退き請求を拒否し続けた場合に起こり得る事態、そして取るべき対処法について解説しました。建物の老朽化や借主の契約違反など「正当事由」が認められるケースでは、立ち退き要求に応じざるを得ない場合もあります。また、たとえ正当事由が認められなかったとしても、感情的に拒否し続けることはかえって不利な状況に陥ることもあります。
貸主との交渉に行き詰まったり、今後の対応に不安を感じたりした場合は、一人で抱え込まず、弁護士に相談することを強くおすすめします。弁護士は、借地借家法に基づいた客観的な視点から状況を分析し、法的な根拠に基づいた冷静な交渉を進めることができます。これにより、大家さんとの感情的な対立を避け、ご自身にとってより有利な条件を引き出す可能性が高まるでしょう。