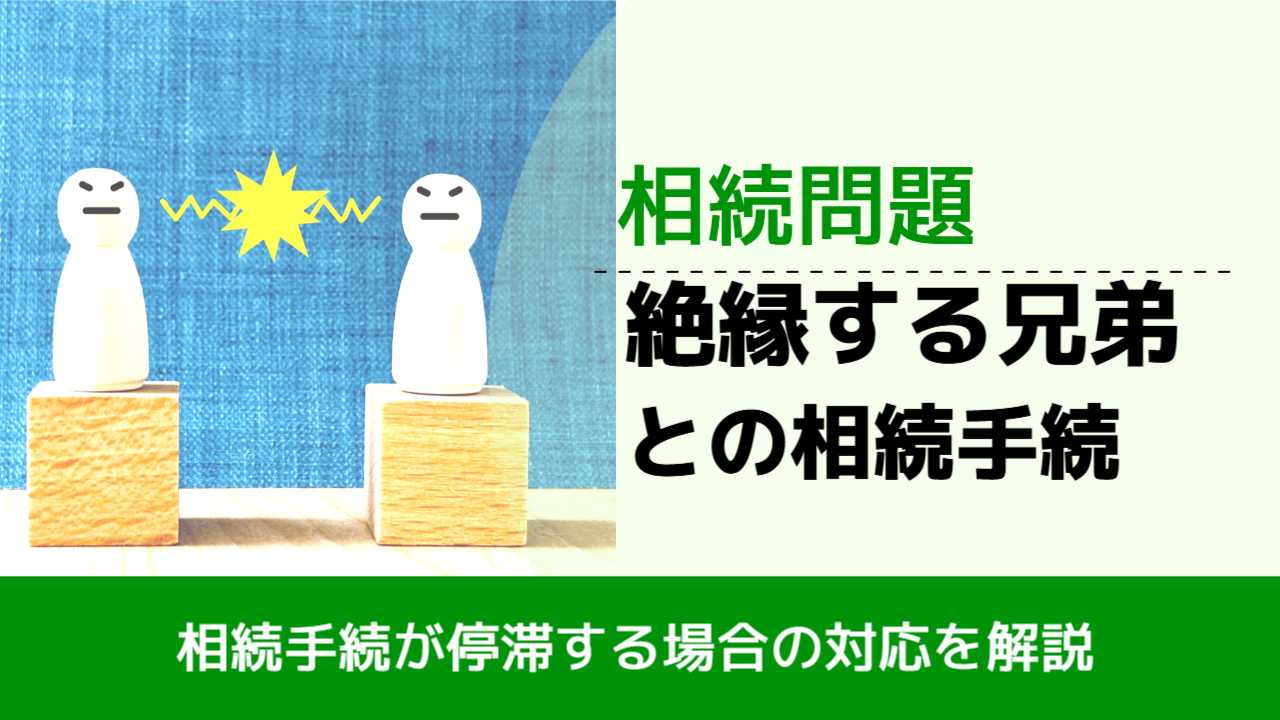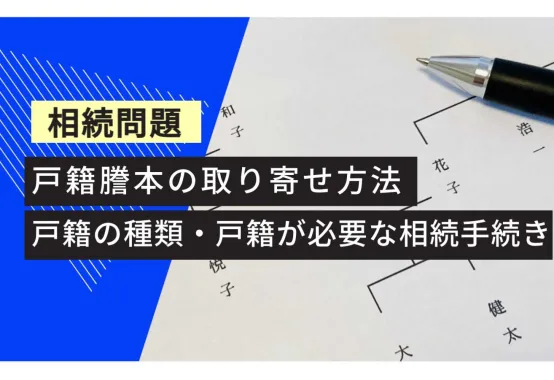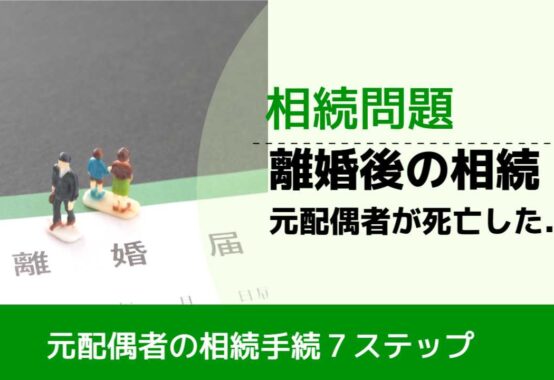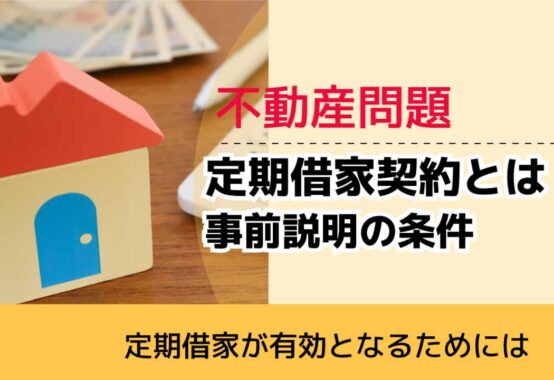絶縁状態にある兄弟がいる場合、相続の手続きは、さらに複雑さを増します。感情的な対立がある人との遺産分割協議は、精神的な負担も大きくなりがちです。
「顔を合わせたくない」
「連絡を取りたくない」
そう思われる方も少なくないでしょう。しかし、相続権は法律で定められた権利であり、適切に相続手続きを進める必要があります。
本記事では、絶縁した兄弟がいる状況でも、できる限り顔を合わせずに相続手続きを進めるための具体的な方法と、相続手続きにおけるトラブルを回避するための対策について解説します。
まず知っておきたい大原則:兄弟と絶縁しても相続権はなくならない

たとえ長年にわたり絶縁状態であったり、何年も顔を合わせていなかったりといった個人的な感情や関係が、法律上の相続権に影響を及ぼすことは一切ありません。以下では、絶縁する兄弟がいる場合の相続手続きを解説します。
遺産を分けるには相続人全員の合意(遺産分割協議)が必須
遺産を分割するには、法定相続人全員が参加し、遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」が必要となります。この協議は、民法上の大原則として、以下の要件を満たさなければなりません。
遺産分割協議の成立要件は以下の通りです。
- 法定相続人全員が参加すること。
- 遺産の分け方について、参加者全員が合意すること。
これらの要件のうち一つでも欠けている場合や、内容に合意しない相続人がいる場合は、協議は成立しません。万が一、一部の相続人だけで協議を進めても、その手続きは法的に無効となる可能性があります。
したがって、たとえ何十年も音信不通で、個人的な感情から絶縁状態にある兄弟姉妹であっても、法的な相続人である限り、遺産分割協議には必ず連絡を取り、参加を促さなければなりません。全員が合意した内容は、遺産分割協議書として書面にまとめ、相続人全員が署名・押印し、印鑑証明書を添付することで、法的な効力を持つ文書となります。
相手を無視して手続きを進めると無効になるリスクも
絶縁した兄弟を除外して行われた遺産分割協議は、法的に無効となるため注意が必要です。遺産分割協議は、相続人全員の合意が大前提です。そのため、たとえ一部の相続人が除外されたり、連絡が取れないまま手続きが進められたりした場合でも、作成された協議書は法的な効力を持ちません。
このような無効な遺産分割協議書では、不動産の相続登記はもちろん、預貯金の解約や名義変更といった重要な手続きが、法務局や金融機関で受理されません。結果として、相続手続き全体が滞り、財産を適切に管理・処分できなくなる可能性があります。
円滑な相続のためにも、法定相続人全員が関与する形で手続きを進めることが不可欠です。


絶縁した兄弟がいる場合の相続手続きの進め方
絶縁状態の兄弟がいる場合の相続手続きは、感情的な対立が生じやすく、非常にデリケートな問題です。しかし、個人的な関係が途絶えていても、法に則って冷静かつ事務的に進めることが、円滑な解決への鍵となります。感情に流されず、事実に基づいた対応を心がけましょう。
ここでは、絶縁した兄弟がいる状況でも、適切な相続手続きを進めるための具体的なステップを解説します。
ステップ1:まずは相続財産と相続人を正確に調査する
絶縁した兄弟との相続を進める上で、まず最初に行うべきは、相続財産と相続人を正確に把握することです。これは遺産分割協議の大前提となる重要なステップであり、この調査が不十分なまま手続きを進めると、後から新たな相続財産や相続人が判明し、遺産分割協議それ自体が無効になるリスクを伴います。
相続財産の調査では、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も網羅的に洗い出す必要があります。具体的な調査方法を以下にまとめました。
次に、法定相続人を確定させるために、被相続人(亡くなった親)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を市区町村役場で取得する必要があります。この手続きによって、自身が把握していない認知した子など、思いがけない相続人がいる可能性がないかを確認できます。
これらの調査結果を終えれば、遺産目録と相続関係図を作成します。
ステップ2:手紙やメールで連絡を取る
絶縁状態にある兄弟との相続手続きにおいては、感情的な衝突を避けることが肝要です。そのため、まずは電話や直接の訪問は極力避け、手紙やメールなど、記録が残る形式で連絡を取ることをお勧めします。
手紙やメールには、遺産分割協議を進める上で不可欠な情報を記載します。具体的には、以下の内容を含めるようにしましょう。
- 故人の氏名、死亡日
- 相手方が相続人であること
- 判明している相続財産の概要
- 遺産分割協議を行いたい旨の提案
- 返信期限
- ご自身の連絡先(氏名、住所、電話番号等)
特に重要な書面を送る際は、郵便局の「配達証明付き内容証明郵便」を利用することをお勧めします。相手方が「受け取っていない」と主張する事態を防ぐ上で非常に効果的な手段です。
文面を作成する際は、感情的な表現は避け、あくまで法的な手続きを進めるための連絡として、冷静かつ丁寧な言葉遣いを心がけてください。これにより、無用な摩擦を避け、円滑な協議への道筋をつけられることが期待されます。
ステップ3:連絡先が分からない場合は戸籍の附票で現住所を調べる
絶縁した兄弟の連絡先が不明で、手紙やメールでの連絡も難しい場合、現住所を特定する有効な手段として「戸籍の附票」があります。
兄弟が住所を転々と変えている場合でも、この戸籍の附票を取り付けることで、過去から現在までの住所の移り変わりを把握し、現住所を特定できる可能性が高まります。
ご自身でこれらの手続きを進めることが難しい場合は、弁護士への依頼を検討すると良いでしょう。弁護士は、職務上請求を利用することで、よりスムーズに戸籍の附票を取得できることがあります。
行方不明の場合は「不在者財産管理人」の選任を検討
戸籍の附票を辿っても絶縁した兄弟の現住所が特定できず、長期間にわたり音信不通で「行方不明」の状態であると判断される場合、遺産分割協議を進める最終手段として、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法があります。
不在者財産管理人とは、行方不明の相続人に代わってその財産を管理し、遺産分割協議に参加する代理人のことです。多くの場合、弁護士や司法書士といった法律の専門家が選任されます。選任された管理人は、行方不明の相続人の権利を守りながら、他の相続人との間で遺産分割協議を進め、合意を形成する役割を担います。
また、7年を超えて行方不明である場合には、行方不明の相続人について失踪宣告の申立てを行うことで、行方不明の相続人が死亡したものとみなして、遺産分割協議をすることができます。ただし、死亡したとみなすことにより、かえって相続関係が複雑になることもあるため、取るべき選択肢は慎重に検討する必要があります。
絶縁兄弟との相続でよくあるトラブルと法的対処法

絶縁状態にある兄弟との相続においては、感情的な対立が法的なトラブルに発展しやすい傾向にあります。
以下の項目では、絶縁状態にある兄弟との間で起こりやすい代表的なトラブル事例を以下の通りご紹介し田中上で、各トラブルに対し、家庭裁判所の調停や審判といった法的な手続きを含め、どのように対処すべきかを解説します。
相手が連絡を無視する場合
絶縁状態にある兄弟が遺産分割協議に応じない、あるいは連絡を無視するといった状況では、まずは「内容証明郵便」を送付し、遺産分割協議を求める意思を伝えることが重要です。内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書が、誰から誰へ差し出されたかを郵便局が証明する制度です。これにより、相手方に対して心理的なプレッシャーを与え、話し合いに応じるきっかけとなる可能性があります。また、後に法的手続きへ移行した場合でも、遺産分割協議を求める意思があったことの客観的な証拠として活用できます。
内容証明郵便を送付しても話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てるのが次のステップです。調停では、裁判官と調停委員が、中立的な立場から当事者双方の意見を聞き、解決策を提示することで、話し合いが円滑に進むよう調整します。当事者同士が直接顔を合わせる必要がないため、感情的な対立を避け、冷静に協議を進められるでしょう。
調停が不成立に終わってしまった場合、自動的に「遺産分割審判」へと移行します。審判では、裁判官が一切の事情を考慮した上で遺産分割方法を決定します。このため、相手方の合意が得られなくても、裁判所の判断によって遺産分割を法的に確定させることが可能です。
感情的な対立で協議がまったく進まない場合
絶縁状態にある兄弟との遺産分割協議では、これまでの経緯や過去の出来事に対する不満、感情が噴出しやすく、冷静な話し合いが困難となるケースが少なくありません。当事者同士での直接的な解決は、かえって対立を深めることにつながりかねません。
感情的な対立で協議ができなければ、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。もし調停でも話し合いがまとまらず、合意に至らなかった場合は、審判手続で解決を目指します。
遺産の使い込みや財産隠しが疑われる場合
被相続人が存命中に、一部の相続人が遺産を使い込んだり隠したりした疑いが生じた場合、まず相続財産の徹底的な調査が求められます。特に、金融機関に対して被相続人名義の取引履歴開示を請求し、不自然な出金がないかを確認することが重要です。被相続人の生前に多額の引き出しや使途不明金が発覚した場合、それは他の相続人に無断で行われた不当利得や不法行為に該当する可能性があります。
このような行為が認められれば、まずは、調査で得られた証拠に基づき、使い込まれた財産を遺産に含めて遺産分割協議を行うよう相手方に求めるのが一般的です。もし相手方が話し合いに応じなかったり、事実を認めなかったりする場合は、家庭裁判所での遺産分割調停や、最終的には訴訟を通じて解決を図る必要があります。
「もう関わりたくない」あなたが選べる2つの選択肢
絶縁した兄弟との相続手続きは、法的な問題解決に加え、精神的な負担も伴います。
そこで、相続手続に伴う負担を最小限に抑えながら、相続問題を解決するための有効な手段を解説します。
選択肢①:プラスもマイナスも財産を一切引き継がない「相続放棄」
相続放棄とは、被相続人の預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて、一切の遺産を相続する権利を放棄する法的な手続きです。この選択肢の最大のメリットは、家庭裁判所での手続きが完了すれば、絶縁している兄弟と遺産分割協議で顔を合わせたり、連絡を取り合ったりする必要が一切なくなる点にあります。精神的な負担から完全に解放されるため、「もう関わりたくない」という思いをお持ちの方にとっては、非常に有効な解決策となるでしょう。
ただし、一度相続放棄をすると原則として撤回できない点には注意が必要です。たとえ後から価値のある財産が見つかったとしても、その財産を相続する権利を失うため、慎重な判断が求められます。また、相続放棄を行うためには、ご自身が相続人であることを知った時から3ヶ月以内、この期間を「熟慮期間」と呼びますが、この期間内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
選択肢②:交渉や手続きをすべて任せる「弁護士への依頼」
絶縁した兄弟との相続において、「もう関わりたくない」と強く感じている場合、弁護士に依頼することは非常に有効な選択肢です。弁護士が代理人となることで、絶縁した兄弟と直接連絡を取り合ったり、顔を合わせたりする精神的な負担を大幅に軽減できる点が最大のメリットと言えます。また、相続に関する交渉窓口を一本化し、感情的な対立を避け、冷静かつ法的な視点から手続きを進めることが可能です。
弁護士は、相手方との遺産分割協議の交渉はもちろん、遺産分割協議書の作成や預貯金の解約など、相続に関するほぼすべての手続きを代行できます。これにより、複雑な手続きに煩わされることなく、相続を円滑に進められるでしょう。
「どうしても顔を合わせたくない」「手続きが複雑で手に負えない」「法的なトラブルに発展しそうだ」といった状況に直面している方に、特に有効な解決策と言えるでしょう。
将来のトラブルを防ぐために遺言書を作成しておく
絶縁した兄弟との相続トラブルは、親がご存命のうちに適切な対策を講じておくことで、未然に防ぎ、あるいはその影響を大きく軽減できる可能性があります。以下の項目からは、これらの具体的な対策について詳しく見ていきましょう。
最も有効な対策は「遺言書」の作成
遺言書を作成すれば、原則として相続人全員による遺産分割協議が不要となり、絶縁した兄弟と直接顔を合わせたり、連絡を取り合ったりする精神的な負担を大幅に軽減できます。親が「誰にどの財産を相続させるか」を明確に指定することで、相続人間の無用な争いを未然に防ぐ効果も期待できるでしょう。
特に、公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」は、法的な不備によって無効になるリスクが極めて低く、将来のトラブル防止に最も効果的な手段です。
遺言書でも侵害できない最低限の権利「遺留分」とは
遺言書の内容よりも優先される、法定相続人に保障された最低限の遺産取得分を「遺留分」といいます。もし遺言書などで遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は、遺産を多く受け取った相手に対し、侵害された分の金銭の支払いを請求する「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
そのため、絶縁した兄弟とのトラブルを回避するために遺言書を作成したにもかかわらず、その遺言書のせいで、絶縁した兄弟との遺留分をめぐるトラブルに発展するおそれがあります。
そこで、遺言書を作成する場合には、他の相続人の遺留分にも一定程度配慮することで、将来の遺留分トラブルを予防することが大切です。
絶縁した兄弟との相続トラブルは難波みなみ法律事務所へ

絶縁状態にある兄弟との相続問題は、感情的な対立を伴い、法的な手続きも複雑なため、一人で抱え込むと心身に大きな負担がかかることがあります。しかし、適切な知識と弁護士のサポートを得ることで、円滑な解決を目指すことは十分に可能です。
兄弟との相続トラブルは、放置すると関係がさらに悪化し、長期化する恐れがあります。そのため、一人で悩まず、できるだけ早い段階で弁護士へ相談することが、法的に正しく、かつ円満に問題を解決するための最も確実な近道と言えます。
初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。