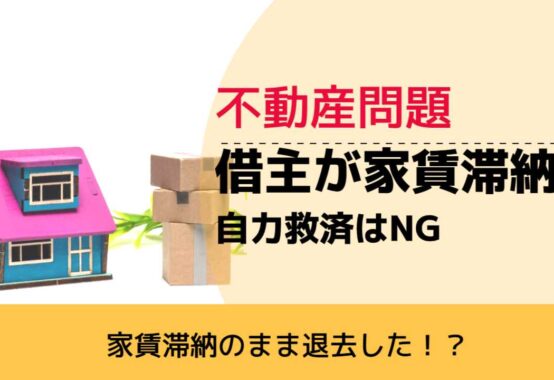不動産賃貸経営において、経済状況の変化や租税公課の負担増に伴い賃料増額を検討することは珍しくありません。
しかし、借主に対して賃料増額請求をしても、借主がこれを素直に受け入れられるとは限らず、賃料増額が思うように実現しないことは珍しくありません。そのため、賃借人から賃料増額請求を拒否されたとき、多くの貸主は次にどう対応すべきか悩んでしまいます。
そこで、この記事では、賃料増額請求を拒否された場合の貸主側の具体的な対応策や法的手続きについて詳しく解説します。この情報を参考にすることで、賃借人との無用なトラブルを避けながら、適切に賃料増額を実現するための道筋が見えてくるでしょう。
また、交渉から調停、訴訟に至るまでの各段階での注意点を理解することで、賃貸経営における収益性を適正に維持することができます。
賃料増額請求の基本知識
賃料の増額は賃貸経営を維持する上で重要ですが、借主との間でトラブルになりやすい問題でもあります。
賃料増額請求を行う場合、まず知っておくべきことを解説します。
賃料増額請求ができる法的根拠
賃料増額請求の法的根拠は、借地借家法第32条に明確に規定されています。
借地借家法32条1項
土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。
このように、貸主は借主に対して、不相当になった現行賃料を増額することが認められています。ただし、貸主は自由に賃料の増額を求められるわけではなく、借地借家法32条に定められた事情を理由に現在の賃料が不相当になっていることが必要です。
賃料増額請求のタイミングは?
賃料増額請求のタイミングは、貸主にとって重要な検討事項です。
一般的に、賃料増額請求は契約更新時に行うのが最も自然なタイミングとされています。更新を機に賃料増額を求める場合には、借主に検討する時間を与えるために、更新月の1〜3ヶ月前に通知するのが望ましいです。
ただ、契約更新時に限らず、契約締結してから数年が経過し、不動産価格の高騰や租税公課の負担増がある場合には、賃貸期間中であっても賃料増額請求をすることは珍しくありません。特に長期間にわたって、賃料改定をしていない物件では、適正賃料との乖離が大きくなっている可能性があります。


借主は賃料増額請求を拒否できるのか?
賃貸借契約において、貸主が賃料増額請求をしても、借主はこれを無条件に受け入れる義務はありません。以下では、拒否できる根拠や拒否する理由を解説します。
借主は賃料増額を拒否できる
借主が、貸主の賃料増額請求に対して拒否することは認められています。つまり、貸主が賃料増額を通知しても、借主はそれに無条件に従う義務はなく、賃料増額に同意しないことも認められています。そのため、借主は、賃料増額請求を受けても、現行賃料を支払い続けることも認められています。
ただし、貸主の賃料増額請求に正当な理由がある場合には、賃料増額請求をした時点から賃料は増額されるため、借主は現行賃料との差額と年10%の利息を支払う義務を負います。他方で、貸主は、現行賃料しか払っていないことを理由に、賃貸借契約を解除することはできません。
借地借家法32条2項
建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
参照:e-gov借地借家法
賃借人が拒否する一般的な理由
賃借人が賃料増額請求を拒否する理由は多岐にわたります。
経済的負担増
最も一般的なのは「経済的な負担増加」を懸念するケースです。特に収入が変わらない中での支出増加は家計を圧迫するため、借主にとって受け入れ難いものとなります。
賃料相場との比較
次に多いのが「相場と比較して高すぎる」という主張です。借主は近隣の類似物件の賃料情報を集め、提示された増額賃料が不当に高いと判断することがあります。
建物の老朽化
「建物の老朽化」も拒否理由となります。築年数の経過とともに物件の価値が下がっているにもかかわらず賃料が上がることに納得できないという主張です。
契約時の説明不足
「契約時の説明不足」も重要な要因です。契約締結時に将来的な賃料増額について十分な説明がなかった場合、借主は不意打ちと感じて反発することがあります。
賃料改定の経緯
また「過去の賃料改定」も影響します。短期間に複数回の増額があった場合や、前回の増額から間もない時期の再度の増額請求は、借主の抵抗感を強めます。
賃借人から拒否された場合の貸主の選択肢
賃借人から賃料増額請求を拒否された場合、貸主には複数の選択肢があります。
どの選択肢を選ぶにしても、増額賃料の正当性を示す客観的な資料を準備しておくことが重要です。
協議による解決を試みる
賃料増額請求が拒否された場合、まずは協議による解決を試みることが重要です。
借主との関係性を維持しながら問題解決を図るためには、一方的な主張ではなく、借主が拒否する理由にも耳を傾けるなど、当事者間の話し合いが効果的です。
具体的な協議の進め方としては、まず増額の必要性や具体的な根拠を明確に説明することから始めましょう。周辺相場の資料や固定資産税の増加額、管理費の上昇など、客観的なデータを示しながら丁寧に説明することで、借主の理解を得やすくなります。
協議の結果、当事者間で合意に至った場合は合意書などの書面を作成することをお勧めします。これにより後のトラブルを防止できます。
協議による解決は、調停や訴訟といった法的手続きに比べて時間や費用を抑えられるだけでなく、借主との関係を維持できるメリットがあります。
賃料増額請求の調停手続き(調停前置)
賃料増額請求が借主に拒否された場合、貸主は賃料増額の民事調停を申し立てることができます。民事調停手続を経ることなく、賃料増額に関する訴訟を提起することはできません。これを「調停前置主義」といいます。賃貸借契約が当事者間の信頼関係をベースとする継続的な契約ですので、賃料の改訂についても可能な限り当事者双方の話し合いによって解決されることが望ましいことが調停前置主義の理由です。
民事調停の手続や流れ
調停委員会は通常、裁判官1名と調停委員2名で構成され、調停委員が当事者双方の主張を聞きながら合意形成を目指します。
調停の進行は一般的に、申立人(貸主)と相手方(借主)が別々の部屋で待機し、双方が入れ替わって調停委員の聞き取りに応じます。当事者同士が直接対面することは少なく、感情的な対立を避けられる利点があります。
貸主は、増額賃料が正しいことを裏付けるために、不動産業者の査定書や不動鑑定士の鑑定書を証拠として提出します。ただ、不動産鑑定士の費用負担も考慮して、調停手続では比較的安価である査定書の提出に留めることもあります。
調停が成立すれば、その内容は裁判上の和解と同じ効力を持ちます。一方、調停が不成立となった場合には、訴訟手続を進めることになります。
調停手続は訴訟と比較して費用や時間の負担が少なく、当事者間の関係を必要以上に悪化させないというメリットがあります。また、裁判所という公的機関が関与することで、借主に対して増額の必要性を理解してもらいやすくなる効果も期待できます。
賃料増額請求の訴訟手続き
賃料増額請求が借主に拒否され、調停でも合意に至らなかった場合、最終的な解決手段として訴訟手続があります。賃料増額に関する訴訟は、調停前置主義に基づき、調停不成立後に提起することになります。
訴訟手続では、賃料増額の正当性を証明するための証拠提出が重要です。周辺相場資料、公租公課の増加を示す資料、物価指数の変動データなどを用意しましょう。特に不動産鑑定士による鑑定意見書は、専門的な見地から適正賃料を示す強力な証拠となります。
訴訟手続においても、当事者間の和解が成立しない場合には、公的鑑定を実施するのが通常です。公的鑑定とは、裁判所が指定する不動産鑑定士による鑑定手続です。鑑定内容に不合理な点がなければ、裁判所は、鑑定意見の内容を判断の決め手とすることがほとんどです。
訴訟には一般的に1年程度の期間を要し、弁護士費用や印紙代などの費用負担も発生します。特に、不動産鑑定士の費用については、私的鑑定に加えて公的鑑定の費用負担も生じるため大きくなりがちです。
賃料増額が認められるための条件と証拠
賃料増額請求が法的に認められるためには、賃料の合意時から事情の変更があることが必要です。賃料を増額できる事情の変更とは何を指すのかを解説します。
周辺相場と比較して不相当であること
賃料増額請求が認められるためには、現在の賃料が周辺相場と比較して著しく不相当であることを証明する必要があります。
ただ、賃料の合意時点で既に合意賃料額が相場賃料よりも低く、その後の事情変更もない場合には、いくら賃料額が相場賃料よりも安価であったとしても賃料増額請求の要件を満たしません。
経済事情の変動
賃料増額請求の正当性を示す重要な要素の一つが経済事情の変動です。借地借家法では、経済事情の変動が賃料増額請求の根拠として明確に規定されています。経済事情の変動という事情は、平成3年の法改正に際して新しく追加されたもので、建物価格や租税公課以外の経済的な状況の変動を指します。想定される経済事情の変動としては、消費者物価指数、通貨供給量、賃金指数などの指標が考えられます。
土地や建物の価格が上がっていること
土地や建物の価格の変動も賃料増額請求の理由となります。
そもそも、家賃は、土地や建物の価格に期待利回りを掛けた金額に必要諸経費を加算して計算されます。そのため、家賃のベースとなる土地や建物の価格が上昇すれば、これに応じて賃料も変動させる必要があります。
税負担等が大きくなっていること
固定資産税や都市計画税などの不動産関連税の増加は、賃料増額請求の正当な理由の一つとなります。先ほど解説したように、賃料は、土地・建物の価値に対する期待利回りに必要諸経費を加算して算出しますが、この必要諸経費には、租税公課やその他負担が含まれています。
具体的に必要経費としては、建物にかかる減価償却費、維持修繕費、固定資産税・都市計画税および損害保険料、土地にかかる固定資産税、都市計画税賃貸借、不動産そのものにかかる管理費などが挙げられます。
租税公課やその他負担が大きくなっている場合には、賃料増額を求める事情変動の一つといえます。
賃料増額請求が拒否された場合の注意点
賃料増額請求を拒否された場合、貸主として冷静な対応が求められます。特に、初期の対応を誤ってしまうと、紛争を長期化させてしまうおそれがあります。
冷静に交渉をする
賃料増額請求を拒否されたとしても、強硬に対応するのではなく、冷静に話し合いをすることが大切です。
まず重要なのは、感情的にならず事実に基づいた冷静な対話を心がけることです。増額の必要性を客観的なデータで示し、周辺相場の調査結果や固定資産税の増加など具体的な根拠を提示しましょう。
交渉の場では一方的に通告するだけではなく、賃借人の意見にも耳を傾ける姿勢が重要です。賃借人が拒否する理由を丁寧に聞き出し、その懸念に対応する提案を複数用意することで合意の可能性が高まります。交渉が難航する場合は、第三者である弁護士を介することも検討しましょう。
適正賃料の査定書や意見書を取得する
賃料増額請求を拒否された場合、貸主側の主張に客観的な根拠を持たせるために適正賃料の査定書や鑑定意見書を取得することが効果的です。
不動産鑑定士による鑑定書は、現在の市場相場や物件の価値を専門的見地から評価した専門的な証拠となります。特に調停や訴訟に進む可能性がある場合、このような不動産鑑定士による客観的な評価資料は、自身の主張の説得力を大きく高めます。ただ、不動産鑑定士の報酬は、50万円から100万円程を要するのが一般的です。
また、不動産業者の査定書も賃料増額の証拠となります。ただ、不動産業者の査定書は、不動産鑑定士の鑑定意見書と比べると専門性や信用性は大きく劣ります。
交渉や調停の段階では、安価で済む査定書のみを手配しておき、訴訟手続に移行したタイミングで高額な費用を要する不動産鑑定士の鑑定書を準備することも戦略的です。
弁護士への相談とタイミング
賃料増額請求が拒否された場合、弁護士への相談は問題解決の大きな助けとなります。
相談のタイミングとしては、借主から明確な拒否の意思表示があった直後が最適です。特に書面で拒否回答を受け取った場合や数回の交渉を経ても進展が見られない段階では、早めに弁護士の意見を求めるべきでしょう。
専門家選びでは、賃貸借契約や賃料増額に精通した弁護士が最適な選択肢となります。不動産関連の案件を多く扱う弁護士事務所を選ぶことで、より的確なアドバイスが期待できます。
費用面では、弁護士の初回相談料は5,000円〜10,000円程度が目安となります。本格的な法的手続きに進む場合は、着手金や成功報酬も含めた費用計画を立てておくことが賢明です。
強硬な立ち退きは控える
安易に立退きを求めるなどの強硬手段は避けるべきです。
賃料増額請求を拒否されたことを受けて、その対抗手段として立退きを求めることはあります。しかし、賃料増額の拒否に対する嫌がらせとして、正当な理由もない立退交渉は、当事者間の信頼関係を破壊させてしまい、賃料増額だけでなく立退き交渉も困難にさせてしまいます。
仮に、賃料増額に加えて立退きを求めるとしても、立退きを求める理由を丁寧に説明し、場合によっては賃借人が納得できるような立退きの条件を提示するように努めることが大切です。
賃料増額請求は難波みなみ法律事務所へ

賃料増額請求が拒否された場合、貸主は複数の選択肢と対応策を検討する必要があります。まず、借主との対話を重視し、増額の必要性や根拠を丁寧に説明することが重要です。それでも合意に至らない場合は、調停や訴訟といった法的手続きに進むことになりますが、これらの手続きでは周辺相場との比較や経済事情の変動などの客観的証拠が求められます。
賃貸経営においては、定期的な賃料見直しを契約時に説明した上で、特約として組み込むことが、将来的な賃料交渉をスムーズにする鍵となります。最終的には、貸主と借主の良好な関係維持と適正な収益確保のバランスを考慮した対応が求められるでしょう。
初回相談30分を無料で実施しています。
面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。