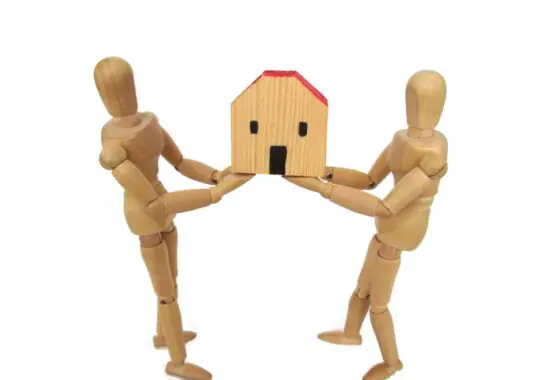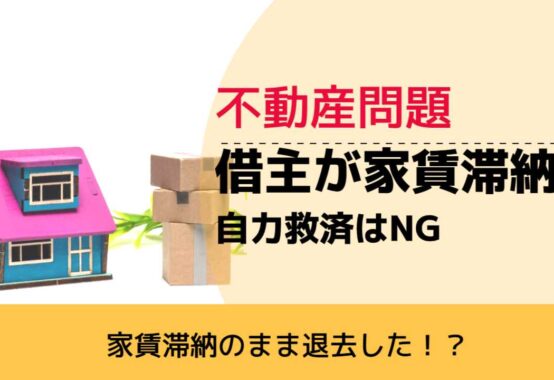不動産経営において賃料の適正化は重要な課題です。賃貸借契約締結時から何十年も賃料の改定をすることなく放置していることも珍しくありません。
一方で、賃料相場の上昇や物件価値の高騰の中、現行の賃料が適正賃料よりも低いと感じている家主やオーナーの方も多いのではないでしょうか。しかし、賃料増額は闇雲に行えば済む問題ではありません。賃料増額請求には十分な法的知識が必要で、進め方を誤ると借主との関係悪化や適切な賃料増額が認められないリスクもあります。
そこで、この記事では、賃料増額請求を弁護士に依頼する際の費用相場やメリットについて詳しく解説します。
賃料増額請求とは?基本的な理解
弁護士への依頼の必要性やメリットを解説する前に、賃料増額請求の基本的な解説を簡単に行います。
賃料増額請求とは
賃料増額請求は、不動産オーナーが借主に対して現在の賃料を引き上げるよう求める権利です。
賃料増額請求をした場合、現行賃料を適正賃料まで引き上げることができますが、当然に相場賃料まで引き上げることができるわけではありません。適正賃料は、利回り法、スライド法、差額配分法、賃貸事例比較法などの計算方法を組み合わせて算出します。
賃料増額請求の法的根拠(借地借家法)
賃料増額請求は借地借家法第11条(借地)および第32条(借家)を法的な根拠として認められています。
第11条(地代等増減請求権)
1.地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
第32条(借賃増減請求権)
1.建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
借地借家法に定められているとおり、賃料増額請求を行う際には、以下の要件を満たす必要があります。たとえ、最終合意時から期間が経過していたとしても、以下の事情の変動がなければ、賃料増額は認められません。
- 土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減
- 建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動
- 近隣の同種の賃料と比較して現行賃料が不相当になった場合
賃料増額請求の流れと期間
まずオーナー側から借主へ賃料増額請求の通知を書面で行います。請求した日を明確にするために、賃料増額請求の通知は内容証明郵便にて行うことが望ましいでしょう。
通知後、借主との協議を行います。この段階で合意に至れば、新たな賃料で契約を継続できますが、借主が増額に応じない場合は調停や訴訟へと進むことになります。
調停の場合、申立てから解決まで通常6か月から1年程かかります。調停で合意できなければ、訴訟手続に移行させることになり、この場合は訴訟提起から判決や和解まで1年から1年半の期間を要します。


賃料増額請求における弁護士費用の相場
賃料増額請求を弁護士に依頼したくても、弁護士費用がどのくらいかかるのか見当も付かない人も少なくないでしょう。以下では、弁護士費用の仕組みや計算方法を紹介します。
弁護士費用の基本
弁護士が代理人として活動する場合の弁護士費用は、着手金と報酬金によって構成されるのが一般的です。
着手金は、依頼時に発生する弁護士費用です。報酬金は案件の終結時に発生する弁護士費用です。着手金は、請求額に対応する経済的利益に所定の割合を掛けることで計算されます。報酬金は、依頼者に帰属する「経済的利益」に所定の割合を掛けることで計算されます。
この所定の割合は、経済的利益の大きさに応じて変動するのが一般的です。具体的には、以下のとおりです。
着手金の相場と計算方法(請求額と現行賃料の差額の7年分:旧日弁連報酬基準)
賃料増額請求における弁護士への着手金は、旧日弁連報酬基準に基づいて計算されることがよくあります。この基準では、請求額と現行賃料の差額の7年分を経済的利益とした上で、差額賃料額の7年分が300万円未満の場合は8%、300万円以上3000万円未満の場合は5%に9万円を加えた金額が着手金額となります。
例えば、月額賃料10万円から12万円への増額請求を考えてみましょう。この場合、月額の差額は2万円となり、7年分に換算すると2万円×12ヶ月×7年=168万円となります。この金額は300万円未満ですので、着手金の目安は168万円×8%=13万4400円となります。
ただし、当事務所も含め法律事務所によっては、最低着手金(20万円、30万円等)を設定していることもあります。また、旧日弁連報酬基準はあくまで目安であり、各弁護士事務所によって独自の料金体系を設けていることもあります。
報酬金の一般的な計算方法
賃料増額請求における報酬金は、増額された賃料と現行賃料との差額の7年分を経済的利益として所定の割合を乗じて計算されることがよくあります。
報酬の料率は、増額分の総額によって段階的に設定されることが多く、差額賃料額7年分が300万円以下の場合は16%、300万円を超え3000万円以下の場合は10%+18万円という料率が適用されるケースが一般的です。この料率体系は旧日弁連報酬基準を参考にしている法律事務所が多いためです。
具体的な計算例を挙げると、月額賃料が20万円から24万円に増額された場合、月々の差額は4万円となります。この差額の7年分は4万円×12ヶ月×7年=336万円となり、300万円を超えるため10%+18万円の料率が適用され、成功報酬は51.6万円となります。着手金と同様に最低報酬金を設定していることもよくあるため注意が必要です。
実費(印紙代・郵便代など)の目安
賃料増額請求を弁護士に依頼する場合、着手金や成功報酬とは別に実費が発生します。これらの実費は依頼者が負担する必要があるため、あらかじめ予算に含めておきましょう。。
賃料増額請求で一般的に発生する実費としては、まず裁判所に提出する書類の印紙代があります。調停申立ての場合は請求額に応じて数千円から数万円程度、訴訟に移行した場合はより高額になります。
また、相手方への書類送達に必要な郵便代も実費として計上されます。その他、不動産鑑定が必要になった場合の鑑定費用(20万円~100万円程)、登記簿謄本や固定資産評価証明書などの各種証明書取得費用、交通費が発生することがあります。
弁護士に依頼するメリット
賃料増額請求を弁護士に依頼することで、家主やオーナーは多くのメリットを得ることができます。
交渉や裁判手続を一任できる
まず、不動産取引に精通した弁護士が、専門的な知識と経験に基づいて、立証資料の収集や相手方との交渉、裁判手続の対応を行います。これにより、最大限の増額を実現できる可能性が高まります。また、増額請求が調停や訴訟に発展した場合、法的手続きの知識と経験を持つ弁護士の存在は不可欠です。書類作成や法廷での主張立証など、専門的なスキルが求められる場面で、適切な対応が可能になります。
借主との感情的な対立を回避できる
貸主と借主が、賃料増額請求に関する協議を直接行うことで、感情的な対立を深めてしまい冷静な対応を困難にさせてしまうおそれがあります。これにより、賃料増額の交渉を難航させるだけでなく、心理的な負担も大きくさせてしまいます。
一方で、弁護士が代理人に就任した上で相手方との協議を行うことで、相手方との感情的な対立を避け、客観的な立場から交渉を進められます。
時間と労力の節減
時間と労力の節約も重要なメリットです。賃料増額請求の手続きは複雑で時間がかかりますが、弁護士に依頼することで、家主やオーナーは本業や他の物件管理に集中できます。これにより賃料増額に求められる時間や労力を節約することができます。長期的に見れば、適切な増額を実現することによる収益増加は、弁護士費用を大きく上回ることが多いでしょう。
他方で、自力で行う場合、書類作成や交渉に多くの時間を費やすことになり、本来の事業や他の物件管理に充てるべき時間が削られます。また、賃借人との関係悪化や訴訟に発展した場合、結果的に大きな機会損失や精神的負担を被ることもあります。さらには、自分で手続きを進めてしまったことで、法的知識の不足や交渉の難しさから思うような結果が得られないリスクがあります。
賃料増額請求を弁護士に依頼する際のポイント
賃料増額請求を弁護士に依頼する際は、いくつかの重要なポイントを押さえておくことが成功への鍵となります。
弁護士選びで重視すべき点
賃料増額請求を弁護士に依頼する際は、適切な専門家を選ぶことが成功の鍵となります。まず重視すべきは不動産賃貸借、特に賃料増額請求の実績と専門性です。この分野に精通した弁護士は賃料増額に係る法的知識や交渉のノウハウを持ち、依頼者の求める結果の成功率が高まります。
次に、依頼者とのコミュニケーション方針や方法も確認すべきポイントです。進捗状況を定期的に報告してくれるか、質問への対応が迅速か、連絡方法は何があるか(電話、メール、LINE、ChatWork)などを踏まえて、信頼関係を築ける弁護士を選びましょう。
費用体系の透明性も重要です。着手金、成功報酬、実費などの内訳が明確で、追加費用の発生条件が明確であるかを確認することが大切です。
弁護士との相性も重要な要素です。長期的な関係になる可能性もあるため、初回相談で話しやすさや方針の一致を感じられるかを判断しましょう。
最後に、弁護士の戦略・アプローチも確認しましょう。交渉重視か訴訟重視か、あなたの希望する方針と合致しているかを事前に話し合うことで、信頼関係を構築できます。
賃料増額請求に関するよくある質問(FAQ)
賃料増額請求に関してよくある疑問にお答えします。
弁護士費用は経費として計上できる?
賃料増額請求に関連して支払った弁護士費用は、不動産所得の必要経費として計上することが可能です。確定申告の際に、弁護士から受け取った領収書や契約書を保管しておくことが大切です。ただし、個々のケースによって取扱いが異なる場合もありますので、詳細は税理士にご相談するようにしてください。
増額請求が認められなかった場合の費用は?
増額請求が認められなかった場合でも、契約で定められた最低報酬額のお支払いをいただく必要があります。また、着手金を返還することもできません。この点については、法律事務所によって区々ですので、契約締結時に費用体系について明確に確認しておくことが重要です。
依頼から解決までの平均期間
賃料増額請求の解決までの期間は、案件の複雑さや交渉状況によって変動しますが、交渉で合意に至る場合で約3〜6ヶ月、調停に移行した場合は6ヶ月〜1年程度、訴訟に発展した場合は1〜2年かかることもあります。これらはあくまでも目安です。
弁護士に依頼する際は、初回相談時に予想される解決期間について具体的に質問し、スケジュール感を共有しておくことが重要です。
賃料増額請求は難波みなみ法律事務所へ

賃料増額請求を弁護士に依頼する際の費用相場と手続きについて解説してきました。
賃料増額請求は適切に行えば、不動産経営の収益性を高める有効な手段となります。弁護士費用を節約したいあまり、誤った賃料増額請求をしてしまうケースも散見されます。弁護士に依頼することで得られるメリットを十分に踏まえた上で、弁護士に依頼するのか、ご自身で対応するのかを検討することが重要です。
初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。