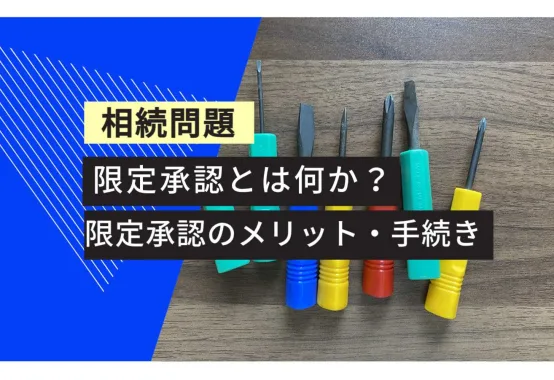遺産分割の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることを検討することになります。
しかし、いざ調停を申し立てようとしても、どこに申し立てれば良いのか迷ってしまう方もいるのではないでしょうか。
この記事では、遺産分割調停の申立先となる裁判所はどこになるのか、といった管轄のルールについて、わかりやすく解説します。また、裁判所が遠方の場合の対処法についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
まずは知っておこう!遺産分割調停とはどんな手続き?
まずは、遺産分割調停とはどのようなプロセスとなるのかを解説します。
遺産分割調停は、相続人間での話し合い(遺産分割協議)では合意に至らない場合に利用される法的な手続きです。
この調停は、裁判官が強制的に判断を下す「審判」とは異なり、あくまで当事者間の話し合いを促進し、双方納得の上での合意形成を目指す手続きです。
遺産分割調停は、相続人間で感情的な対立がある場合や、遺産の評価、寄与分、特別受益などで意見が一致しない場合など、様々なケースで活用されています。
遺産分割調停を申し立てる裁判所はどこ?管轄の基本ルール
遺産分割調停を申し立てる際には、「管轄」というルールに従って、申立てを行う家庭裁判所を決める必要があります。
遺産分割調停の申立てを行う前に、これから解説する管轄のルールを確認し、適切な裁判所を選択しましょう。
原則は「相手方」の住所地を管轄する家庭裁判所
遺産分割を求める相手方(申立人以外の相続人)のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、遺産分割調停の申立てを行います。これは、家事事件手続法で定められたルールです。申立てをする際は、相続人全員に対して行う必要がありますが、管轄を決める基準となる住所は、相手方の中の誰か一人を選べばよいとされています。
ここでいう「住所地」とは、相手方が現に住んでいる住所をいいます。住民票上の住所と現住所が異なる場合には、相手方が実際に住んでいる居所が住所地となります。管轄を間違えると調停手続きが進まない可能性があるため、申立て前に相手方の住所地を確認し、管轄の家庭裁判所を正しく把握しておくことが重要です。
相手が複数いる場合、誰の住所地を選べばいい?
遺産分割調停の相手方(申立人以外の相続人)が複数いる場合、申立人は、その相手方のうちの誰か一人を選び、その人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行うことができます。
どの相手方の住所地を基準にするかについては、申立人が自由に選択できます。選択するにあたっては、申立人自身の居住地からの距離や交通の便、他の相続人の居住地、遺産が所在する場所などを考慮して、手続きを進めやすい家庭裁判所を選ぶと良いでしょう。


管轄の例外はある?知っておきたい特別なケース
遺産分割調停の申立先となる管轄の家庭裁判所は、原則として相手方の住所地を管轄する裁判所ですが、例外的に別の裁判所が管轄を持つ場合もあります。例外的な管轄のケースとしては、主に当事者間の合意によるものや、裁判所の判断によるものなどがあります。ご自身のケースで例外的な管轄が認められる可能性があるかどうかも確認してみると良いでしょう。
相続人全員の合意で決める「合意管轄」
例外の一つに、「合意管轄」があります。これは、相続人全員が特定の家庭裁判所を管轄とすることに合意した場合に認められるものです。原則である相手方の住所地を管轄する家庭裁判所以外の裁判所でも、相続人全員が書面で同意すれば、その裁判所に申立てを行うことができます。
合意管轄の最大のメリットは、当事者全員にとって都合の良い場所にある裁判所を選べる点です。例えば、相続財産の所在地に近い裁判所や、相続人のうち多くの人が居住している地域にある裁判所、あるいは申立人にとって最もアクセスしやすい裁判所などを選ぶことで、手続きの負担を軽減できる可能性があります。
合意管轄を利用するためには、相続人全員の同意を示す「管轄合意書」という書面を作成し、申立て時に家庭裁判所へ提出する必要があります。この書面には、遺産分割調停に関する管轄裁判所を特定の家庭裁判所とすることについて、当事者全員が合意した旨を明記します。
申立人の事情を考慮する「自庁処理」とは?
本来、裁判所は管轄を有さない場合には、管轄違いを理由に管轄のある裁判所に移送する処理をします。ただし、事案によっては、管轄権を持たない家庭裁判所で調停手続きを行う法が適切な場合など、事案を処理するために特に必要があると認めるときには、自ら処理することがあります。これを「自庁処理」といいます。
自庁処理が認められる具体例としては、既にその裁判所に相続に関連する他の調停事件が係属している場合や、申立人の住所地に多くの遺産が存在しており、かつ、その住所地が相続人の最後の住所地である場合などです。ただし、自庁処理は裁判所の裁量による判断であり、申立てさえすれば必ず認められるものではありません。自庁処理を希望する場合は、申立書の中でその必要性や理由を具体的に説明することが重要になります。
例外的な管轄を選ぶ際の注意点
合意管轄や自庁処理といった例外的な管轄を選択する際には、いくつかの注意点があります。まず、合意管轄を選択する場合、相続人全員の合意が必要不可欠です。一人でも同意しない場合は、合意管轄による申立てはできません。全員の合意を得るためには、他の相続人との交渉や調整に手間や時間がかかる可能性があり、最終的に合意が得られないリスクも考慮する必要があります。
一方、自庁処理は裁判所の裁量に委ねられているため、申し立てたからといって必ず認められるわけではありません。裁判所が「特に必要があると認めるとき」という要件を満たさないと判断した場合、本来の管轄裁判所に移送されてしまいます。自庁処理を求める場合は、なぜその裁判所で処理する必要があるのかを具体的に説明する必要があり、手続きが複雑化する可能性もあります。
このように、例外的な管轄の選択は法的な判断を伴い、手続きも複雑になることがあるため、慎重な検討が必要です。迷った場合は、弁護士に相談し、自身の状況に合った最適な申立先や手続きについてアドバイスを受けることを強く推奨します。
裁判所が遠い時の対応方法
遺産分割調停の管轄裁判所が、申立人の居住地や他の相続人の居住地から遠方になってしまうケースは少なくありません。毎回遠方の裁判所へ出頭するのは、時間的にも経済的にも大きな負担となるでしょう。
このような場合でも、出頭による負担を軽減し、調停手続きに参加するためのいくつかの方法が認められています。
電話やウェブ会議システムで参加できる?
裁判所の手続きにおいても、電話会議システムやウェブ会議システム(ビデオ通話など)を利用して、遠隔地から調停期日に参加することが可能になっています。これにより、管轄裁判所から遠方に居住している相続人も、裁判所に直接出向くことなく調停に参加できる機会が広がっています。
これらのシステムを利用することで、交通費や移動にかかる時間を大幅に削減できるという大きなメリットがあります。
ただ、対面でのコミュニケーションとは異なり、ニュアンスが伝わりにくいことも考慮しておく必要があります。
なお、電話会議システムやウェブ会議システムの利用を希望する場合は、事前に管轄家庭裁判所に、これらシステムを利用したい意向を伝えておくことが必要です。
弁護士に代理で出席してもらう方法
遺産分割調停において、弁護士に依頼して代理人として手続きを進めてもらうことも有効な手段です。弁護士に依頼すれば、専門的な知識に基づいた適切な主張をしてもらえるだけでなく、相手方や調停委員との交渉も安心して任せることができます。これにより、ご自身の精神的・時間的な負担を大幅に軽減できます。
さらに、管轄裁判所が遠方にある場合、管轄裁判所で活動する弁護士に代理を依頼することで、遠距離の移動負担を解消できるメリットは大きいでしょう。その上、体調が優れない場合や、調停期日に都合がつかない場合でも、弁護士が代理人として出廷することができます。
弁護士費用としては、相談料、着手金、報酬金などが発生しますが、事案の内容や依頼する弁護士によって金額は異なります。費用対効果を十分に考慮し、自身の状況に合った弁護士を選ぶことが重要です。
遺産分割調停の申立て手続きと必要書類について
遺産分割調停の管轄裁判所が把握できたところで、申立てに向けた具体的な手続きについて見ていきましょう。
遺産分割調停の申立てにあたっては、申立書に加えて、これ以外にもさまざまな書類の提出が必要です。一般的に必要となるのは、申立書、遺産の内容を記載した遺産目録、事情説明書などが挙げられます。
これらに加えて、相続関係を証明するための戸籍謄本類一式や相続財産に関係する資料が必要です。
申立てにかかる費用としては、まず収入印紙代があります。これは被相続人1人につき1,200円が基本となります。また、裁判所との連絡のために使用される郵便切手も必要となり、その金額は申立てを行う家庭裁判所によって異なります。
遺産分割調停の管轄に関するよくある疑問
遺産分割調停の管轄に関するよくある質問とそれに対する回答わ紹介します。
Q.相手方の住所がわからない場合は?
遺産分割調停を申し立てるには、原則として相手方の正確な住所地を特定し、その住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行う必要があります。しかし、疎遠になっているなどの理由で相手方の正確な現住所が分からないというケースもあるでしょう。
まずは、戸籍の附票を取得して住所の異動を確認する方法を検討しましょう。戸籍の附票には、戸籍が作成されてからの住所の移り変わりが記録されています。これにより、手がかりを得られる可能性があります。調査を尽くしても住所が分からない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は職務上必要な範囲で調査を行うことができます。
それでもなお、相続人の住所が判明しない場合には、不在者財産管理人の選任を申立てる必要があります。その上で、不在者財産管理人を相手方として調停申立てをすることになります。
Q.調停で話がまとまらない場合、審判の管轄はどこになる?
遺産分割調停で話し合いがつかず、合意に至らなかった場合、調停は不成立となります。調停が不成立となった場合、申立ては自動的に遺産分割審判手続に移行します。この審判手続きでは、最終的に裁判官が当事者の主張や提出された証拠に基づいて、遺産の分割方法を終局的に決定することになります。
遺産分割審判は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属します。ただ、調停が不成立になったことで審判手続に移行した場合には、実務上、調停を行っていた家庭裁判所がそのまま引き続き審判を行うことになります。
遺産分割調停は難波みなみ法律事務所へ

遺産分割協議がまとまらない場合には、相続手続きを進めるためには、遺産分割調停を申立てる必要があります。
遺産分割調停は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てることになりますが、家庭裁判所が遠方である場合には、無理をして遠方の裁判所まで出頭せずに電話やウェブなどのシステムを利用して効率よく調停期日に参加することも検討しましょう。
初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。