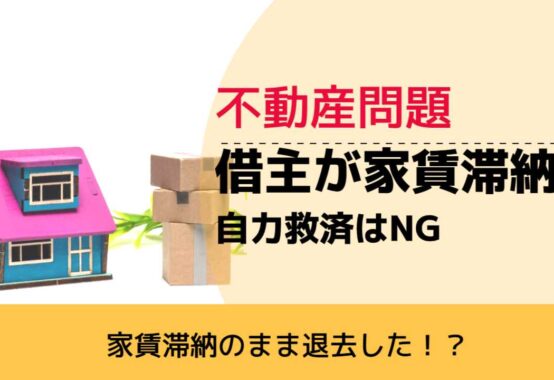立ち退きを検討されている貸主にとって、合意書の作成は非常に重要なプロセスです。借主が立ち退きに応じるに至ったにもかかわらず、合意内容を書面化しなければ、立ち退き後に新たな紛争を再燃させてしまうおそれがあります。
しかし、不慣れな場合は、何から始めれば良いのか迷ってしまうこともあるでしょう。
本記事では、立ち退き合意書の作成において必要な記載事項から、立ち退きに関するトラブルを未然に防ぐための注意点まで、わかりやすく解説します。
さらに、すぐに使えるテンプレートもご用意しました。ぜひ、この記事を参考に、円滑な立ち退きを実現してください。弁護士に依頼するメリットについても触れていきます。
立ち退き合意書とは?円満な明け渡しに不可欠な理由
立ち退きの合意書は不可欠な文書であり、抜け漏れがないように適切に作成することが求められます。以下では、立ち退き合意書の意義を解説します。
立ち退き合意書が持つ法的な効力
立ち退き合意書は、貸主と借主との間で取り交わされた賃貸借契約の合意解約に関する内容(明け渡し期日、立ち退き料の金額、支払い条件など)を法的に確定させ、当事者を拘束する効力を持ちます。
合意書に記載された内容は、両者の正式な約束事を証明する強力な証拠となります。これにより、後日、一方の当事者が合意した内容に反する主張や行動を取った場合でも、合意書を根拠として対抗し、反論することが可能です。
さらに、もし借主が合意した期日までに物件を明け渡さないなど、合意内容が適切に履行されない事態が発生した場合、立ち退き合意書は、明け渡し請求訴訟などの法的手続きを進める上で極めて重要な証拠資料となります。
口約束ではなく書面で残す重要性
立ち退きに関する合意は、口約束でも法的に成立し得ますが、後々のトラブルに繋がりやすいという大きなリスクが伴います。最も起こりやすいのが、「言った、言わない」の水掛け論です。立ち退き料の金額や支払い時期、明け渡し期日、原状回復の範囲など、重要な取り決めについて、お互いの記憶や解釈が異なり、後になって主張が食い違うケースが少なくありません。このような状況は、円滑な解決を著しく困難にし、紛争に発展する可能性を高めます。
また、借主にとっても、立ち退き料の金額や支払い条件、明け渡し期日などが書面で保証されることは、退去に向けた準備を進める上での大きな安心感につながります。このように、立ち退き合意書を作成することは、貸主だけでなく借主にとってメリットが大きく、円満な契約終了のために極めて重要なプロセスと言えるでしょう。


【テンプレート付き】立ち退き合意書に必ず盛り込むべき8つの項
立ち退き合意書を法的に有効なものとし、貸主・借主双方が納得して契約を終了させるためには、必ず記載すべき主要な項目があります。これらの項目を漏れなく記載することで、賃貸借契約の合意解約、物件の明け渡し、立ち退き料などに関する両者の権利や義務が明確になり、後々のトラブルのリスクを減らすことができます。
賃貸借契約の合意解約に関する条項
立ち退き合意書では、まずこの合意書が、賃貸借契約を貸主・借主双方の合意に基づいて終了させるものであるという意思表示を明確にすべきです。この点を明確に記載することで、後々「立ち退き合意書は交わしたが、賃貸借契約自体はまだ続いているのではないか」といった誤解を防ぐことができます。
この条項には、どの賃貸借契約を指しているのかを特定するため、対象となる物件の情報を正確に記載します。具体的には、物件の所在地、建物名、部屋番号など、賃貸借契約書や登記情報を参照しながら不動産の情報を漏れなく盛り込むことが重要です。
さらに重要な点として、本合意書によって賃貸借契約が「いつ」終了するのか、つまり合意解約の効力発生日(契約終了日)を明確に定める必要があります。この日付を当事者間で共有し、書面に残すことで、契約関係の終了時期に関する認識の齟齬を防ぎ、その後の手続きを円滑に進めることが可能になります。
なお、合意解除により借主は対象物件を占有する権限を失います。そのため、合意解除してから明渡期限まで、一定期間がある場合には、解除してから明渡期限まで明渡しを猶予することを記載することもあります。
第〇条(合意解約)
賃貸人(以下、「甲」という。)と賃借人(以下、「乙」という。)は、本日付にて別紙物件目録記載の建物(以下、「本件建物」という。)の賃貸借契約(以下「本件契約」という。)を合意解約し、甲は乙に対し、本件建物の明渡しを令和〇年〇月〇日まで猶予する。
物件の明け渡し期日
立ち退き合意書における最も重要な項目の一つに、物件の明け渡し期日があります。この期日については、「〇年〇月〇日」のように、具体的な年月日を明確に記載する必要があります。曖昧な表現である「〇ヶ月以内」などでは、正確な明け渡し日が特定できず、後に認識のずれやトラブルの原因となる可能性があります。
明渡期限については、無茶な期限を指定すると、借主からの反発を招いたり、明渡義務の履行を困難にさせます。そこで、明渡期限を設定する際には、借主が新居を探し、引っ越しの準備をするための期間を考慮した上で明渡期限を設定することが必要です。
以上のように、合意書内に明渡期限を具体的に明記することで、借主は明記された期日までに物件を明け渡す法的義務を負います。したがって、合意書に正確な日付を記載することは極めて重要と言えるでしょう。
第〇条(明渡し)
1.乙は甲に対し、令和〇年〇月末日限り、第〇条で定める立退料の支払を受けるのと引き換えに、「本件建物」を明け渡す。
2.乙は甲に対し、本件建物の鍵一切を交付する方法により前項で定める本件建物の明渡しを行う。
立ち退き料の金額と支払い条件
貸主が借主に対して立退料を支払う場合には、立ち退き合意書に、合意された立ち退き料の金額を「金〇〇円」のように具体的な数字で明記することが不可欠です。金額を曖昧にせず、明確に記載することで、後日の金額に関する認識の齟齬を防ぐことができます。
また、支払い条件や期限についても具体的に記載する必要があります。支払い時期については、原則として物件の明け渡し完了を確認した後の具体的な期日(例えば、明け渡し完了日から〇営業日以内)を定めます。場合によっては、明渡しと同じ日に立退料を支払う場合や、明渡し前に立退料の一部を支払う場合もあります。
支払い方法についても、振込先となる借主の銀行口座情報や、振込手数料をどちらが負担するのかといった点まで明記することで、支払いの際のトラブルを防ぐことができます。
第〇条(立退料)
甲は乙に対し、第〇条の明渡期日限り、本件建物の明渡しを受けるのと引き換えに、立退料として金〇〇円を支払う。
第〇条(立退料)
1.甲は乙に対し、立退料として金〇〇円を支払う。
2.甲は乙に対し、前項の立退料の内〇〇円を令和〇年〇月末日限り、乙の指定する銀行口座宛に、残金〇〇円を第〇条で定める明渡期日限り、本件建物の明渡しを受けるのと引き換えに、それぞれ支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
明け渡し遅延時の賃料相当損害金
立ち退き合意書において、定められた明け渡し期日までに借主が物件を明け渡さない場合の賃料相当損害金に関する条項を設けることが有用です。これは、明け渡しが遅れることによって貸主が被る損害、例えば新しい入居者の受け入れが遅れることによる機会損失などを補填したり、賃料相当損害金を負担させることで、明渡義務の履行を心理的に強制させることを目的としています。
賃料相当損害金の金額は、月額賃料をベースにすることが一般的ですが、ケースによっては月額賃料よりも高めの金額(例えば月額賃料の1.5倍)で合意するケースもあります。あまりに高額すぎる損害金は、消費者契約法により無効とされる可能性もあるため注意が必要です。
第〇条(賃料相当損害金)
乙が、第〇条の明渡期日に本件建物の明渡しをしない場合、甲に対し、本件建物の明渡しに至るまで、賃料相当損害金として、1か月金〇〇円の割合による金員を毎月末日限り支払う。
敷金の精算・返還について
立ち退きに関する合意書を作成する際には、敷金・保証金の取り扱いについて明確に定めておくことが重要です。
敷金とは、賃貸借契約が終了し、借主が物件を明け渡した後、未払い賃料や原状回復費用などを差し引いて、借主に返還されるお金です。立ち退きによる合意解約の場合も、この基本的な考え方に変わりはありません。
合意書に、敷金から差し引く金額(未払賃料や原状回復費用)を具体的に記載し、貸主が借主に返還する敷金の金額を明記することで、後々のトラブル防止につながります。特に、原状回復義務の範囲については、借主と十分に話し合い、合意した内容を反映させることが重要です。ただ、借主が明渡期限に明渡しを履行しない場合には、賃料相当損害金が発生するため、合意時点で相殺後の敷金の残額を特定できないこともあります。その場合には、単に、敷金〇〇円を本件建物明渡し後〇日以内に賃借人の賃貸人に対する債務を精算し、その残額があれば返還すると記載するに留めます。
第〇条(敷金の返還)
1.甲は乙に対し、乙が本件契約締結時に預託した敷金金〇〇円から乙の甲に対する債務額を差し引いた後の残額を返還する。
2.甲は乙に対し、前項の敷金の残額を、本件建物の明渡期日から1か月以内に、乙の指定する銀行預金口座宛に振り込む方法で支払う。振込手数料は甲の負担とする。
原状回復義務の範囲
立ち退き合意書において、借主が退去時にどこまで原状回復を行うかという範囲を明確に定めることは、トラブル防止のために極めて重要です。
原状回復とは、借主が借りた当時の状態に戻すことを指しますが、その範囲には明確なルールがあります。基本的な考え方として、通常の住生活による損耗や時間の経過に伴う劣化(通常損耗・経年劣化)については、原則として貸主の負担となります。例えば、壁クロスの自然な変色や家具の設置による床のへこみなどはこれに該当します。一方、借主の故意や不注意(過失)、または通常の利用方法に反する使用によって生じた建物の損傷や汚れ(例:タバコのヤニ汚れ、物を落下させたことによる床の傷など)については、特別損耗として、借主が原状回復の義務を負います。
この一般的な基準については、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が参考になります。
合意書の作成時点で、物件内の状況を確認した上で原状回復するべき範囲やその金額を特定できる場合には、合意書内に原状回復の金額やその支払方法を記載するようにします。ただ、立退きのケースであれば、建物を取り壊す予定であることも多いため、原状回復は免除することも多くあります。
第〇条(原状回復)
甲は乙に対し、第〇条の明渡義務を履行することを条件として、本件建物の原状回復義務を免除する。
残置物(残された私物)の所有権放棄
物件の明け渡し時に、借主が家財道具などの私物を室内に残したままにしてしまうケースが見られます。これらは「残置物」と呼ばれ、その取り扱いを巡って貸主と借主の間でトラブルに発展する可能性があります。法律上、残置物の所有権は原則として借主に帰属するため、貸主が借主の同意なく勝手に処分すると、後に損害賠償請求を受けるリスクも考慮しなければなりません。
このようなトラブルを未然に防ぐためには、立ち退き合意書に「残置物の所有権放棄」に関する条項を明確に記載することが非常に重要です。これにより、明け渡し時に物件内に残された借主の動産類について、その所有権を借主が放棄し、貸主が任意に処分できる旨を合意によって定めることができます。具体的な記載例としては、「乙(借主)は、本物件の明け渡し時に本物件内に残置した一切の動産類の所有権を放棄し、甲(貸主)がこれを任意に処分することに同意する。」といった文言が有効です。
さらに、この残置物の撤去や処分にかかる費用をどちらが負担するのかについても、合意書で定めておくことが望ましいでしょう。所有権を放棄した借主が処分費用も負担するケースが多く見られますが、立退のケースでは、貸主側の費用負担で処分するとの内容も珍しくありません。
第〇条(残置動産の所有権放棄)
乙が甲に対して本件建物を明け渡した後、本件建物に家財類及びその他動産類一切が残置されていた場合、乙はその所有権を放棄し、甲において任意に処分しても何らの異議を述べない。なお、その場合の処分費用は乙の負担とする。
清算条項(これ以上の請求をしない旨)
「清算条項」とは、立ち退き合意書の作成をもって、合意書に定める事項のほか、貸主・借主間の賃貸借契約に関連する全ての権利義務関係を最終的に清算し、それ以外に「何らの債権債務も存在しないこと」を相互に確認する旨を定める条項です。この条項を盛り込む最大の目的は、物件の明け渡し完了後に、当初想定していなかった金銭的なトラブルが発生してもお互い何らの請求もしないようにすることで、事案を終局的に解決させる点にあります。
具体的には、合意書で定めた敷金精算や原状回復費用、立ち退き料の金額以外に、後から借主が別の名目で費用請求を行ったり、損害賠償を求めたりする可能性が考えられます。清算条項を明記することで、「本合意書に記載された内容以外については、互いに請求を行わない」という両者の意思を明確に示せます。
もし、この清算条項がない場合、たとえ立ち退き料の支払いなどが完了していても、後日になって予期せぬ請求を受けるリスクが残ります。これにより、既に解決したはずの問題が蒸し返され、再度交渉が必要になったり、最悪の場合、紛争に発展したりする可能性も否定できません。清算条項は、貸主・借主双方にとって、契約終了後の権利義務関係を確定させ、将来の不安要素を取り除くために極めて重要な意味を持つ条項と言えるでしょう。
第〇条(清算条項)
甲と乙は、本合意書に定めるもののほか、何らの債権債務関係の存在しないことを相互に確認する。
法的効力を高める!立ち退き合意書作成時の注意点
円滑な立ち退きを実現するため、また万が一トラブルが発生した際の対応を確実にするためには、作成プロセスにおいてもいくつかの重要な注意点があります。
以下では、合意書の作成における4つの注意点について詳しく解説します。
必ず書面で2部作成し、署名・捺印をもらう
立ち退き合意書を作成する際は、貸主と借主のそれぞれが保管できるよう、必ず同じ内容の書面を2部作成しましょう。これは、双方が合意内容をいつでも確認できるようにするためであり、後日トラブルになった際に、各自が所持する合意書を証拠として提示するために不可欠です。作成した2部の合意書には、貸主と借主の双方が自筆で署名し、実印または認印で捺印することが重要です。
署名・捺印することで、合意書の内容に間違いがなく、その内容で合意したことの明確な意思表示となります。また、合意書が複数ページにわたる場合は、各ページの綴じ目に契印を押すことや、作成された2部の合意書の間に割印を捺印しておくことも望ましいと言えます。これにより、書面の改ざんを防ぎ、2部の合意書が同一のものであることを証明できます。
収入印紙が必要になるケースとは?
立ち退き合意書は、賃貸借契約の合意解約を証明する文書であるため、印紙税法上の課税文書には該当しません。したがって、収入印紙の貼付は不要です。しかし、合意書の内容によっては例外的に印紙税が必要となるケースがあります。
具体的には、損害金や違約金として5万円以上の金額が明記されている場合には、印紙税の課税対象となり、その金額に応じた収入印紙が必要となることがあります。収入印紙の貼付を怠った場合、本来納めるべき印紙税額のほかに、その2倍に相当する金額との合計額である過怠税が課されるリスクがあるため、注意が必要です。
立ち退き料は「明け渡し完了後」の支払いが原則
立ち退きに関する合意において、立ち退き料の支払いタイミングは重要なポイントです。
原則として、立ち退き料は物件の明け渡しが完了した後、借主が退去したことを確認してから支払うのが基本です。これは、貸主側のリスクを回避するためです。もし、明け渡しよりも先に立ち退き料を支払ってしまうと、借主が立ち退き料を受け取ったにもかかわらず、約束通りに物件を明け渡さないといった不測の事態が発生する可能性があります。このような場合、貸主は立ち退き料を支払ったうえに、改めて明け渡しを求めるための手続きが必要となり、二重の手間や費用が発生するリスクを負うことになります。
一方で、借主によっては引っ越し費用や新居の契約金などの準備のために、立ち退き前に一部の支払い(前払い)を求めてくるケースも考えられます。借主からこのような要望があった場合は、交渉によって対応を検討することになりますが、貸主としてはリスクを踏まえた上で慎重に判断する必要があります。例えば、立ち退き料の一部を前払いとし、残金は明け渡し完了後に支払う、といった条件で合意することも考えられます。この場合には、明渡期限までに明渡しをしなければ立退料を返還する旨を定めておくことが必要です。
いずれの支払い方法を採用する場合でも、立ち退き合意書には、立ち退き料の具体的な金額に加え、支払い時期や支払い方法を明確に記載することが極めて重要です。これにより、支払いに関する両者の認識のずれを防ぎ、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
合意書締結を円滑に進めるための交渉術
立ち退き交渉は、貸主・借主の双方にとってデリケートなプロセスであり、単に法的な要件を満たし、条件を提示すれば済むものではありません。借主の状況や感情にも配慮した、丁寧かつ粘り強い交渉が求められます。
以下では、立ち退き合意書をスムーズに締結するために役立つ、具体的な交渉のポイントや効果的な心構えについて詳しく解説します。
「正当事由」を丁寧に説明する
貸主側がなぜ物件の明け渡しを求める必要があるのか、その「正当事由」を借主の方に丁寧に説明することが、立ち退き交渉における最初のステップとして極めて重要です。
借地借家法では、貸主からの賃貸借契約の解約や更新拒絶にあたっては「正当の事由」が必要と定められています。この正当事由があるかどうかが、立ち退きが認められるかどうかを判断する上で非常に重要な基準となります。借主側がこの正当事由について納得できるよう、具体的に伝えることが、円満な合意形成に向けた第一歩となります。
正当事由の具体例としては、以下のようなケースが挙げられます。
- 建物の老朽化が進み、建て替えが不可欠であるケース
- 貸主自身またはその家族が物件を自己使用する必要が生じたケース
これらの理由を説明する際は、単に「建物が古いから」「自分で使いたいから」と伝えるのではなく、なぜ立ち退きが必要なのか、その背景にある状況を客観的に具体的に説明することが大切です。立退料を多く払えば正当事由が満たされるわけではないため、注意が必要です。
説明の際には、極力、感情的にならず、常に真摯な態度で臨むことが不可欠です。借主の方の立場や抱える不安に耳を傾けて、誠実に対話を試みる姿勢を示すことで、信頼関係の構築につながり、その後の交渉を円滑に進めることが期待できます。
立ち退き料の相場と算定根拠を把握しておく
立ち退き料については、法律上の明確な算定基準は定められていません。そのため、個別の状況や交渉によって金額が大きく変動し、一律の相場があるわけではない点を理解しておくことが重要です。一般的に立ち退き料は、借主が物件を明け渡すことによって被る経済的な損失を補償する目的で支払われます。具体的には、以下のような費用が含まれることが一般的です。
- 引っ越し費用
- 新しい賃貸借契約にかかる初期費用(敷金、礼金、仲介手数料など)
- 現在の物件よりも家賃が高い場合の差額(通常1年~2年分程度)
- 事業開始に伴う初期投資
- 休業による損失
- 営業減収
明け渡しまでの猶予期間を提案する
立ち退き交渉において、物件の明け渡し期日は、借主の方が次の住まいを見つけ、引っ越し準備を整えるために必要な期間を十分に考慮して設定すべきです。この期間が不十分な場合、借主の方に過度な負担を強いることになり、合意形成が難航する要因となり得ます。
一般的に、立ち退き交渉における明け渡しの猶予期間は1ヶ月から3ヶ月程度が一つの目安となりますが、借主の方の個別の状況によって必要な期間は異なります。
交渉の初期段階で、貸主側からある程度の猶予期間を提示することは、借主の方の不安を和らげ、その後の話し合いを円滑に進める上で有効な手段となり得ます。提示する猶予期間の長さは、立ち退き料の金額とも関連付けて交渉が可能です。例えば、貸主側の都合で短い期間での明け渡しを希望する場合、立ち退き料を増額するなど、柔軟に検討することで借主の方の理解を得やすくなるでしょう。
立ち退きの問題は難波みなみ法律事務所へ

本記事では、立ち退き合意書がいかに重要であるか、そしてトラブルを未然に防ぐために合意書に必ず記載すべき事項や作成時の注意点について詳しく解説いたしました。立ち退き合意書は、貸主と借主が合意した内容を明確にし、合意後の紛争を防ぐための極めて重要なツールです。物件の明け渡し期日、立ち退き料の金額と支払い条件、敷金の精算、原状回復義務の範囲など、主要な項目を漏れなく具体的に記載することが、合意内容の確実な履行につながります。
借主との間で丁寧に交渉を進めた上で、合意書を適切に作成することは、貸主と借主の双方にとって、不要なトラブルを避け、円満な形で賃貸借契約を終了させることにつながります。しかし、個別の状況によっては交渉が難航する場合や、法的な手続きに不安を感じることもあるかもしれません。そのような場合には、弁護士へ相談することが有効な手段です。不動産問題に精通する弁護士の知識や交渉経験を借りることで、複雑な状況でも適切な対応が可能となり、問題の早期解決が期待できます。
初回相談30分を無料で実施しています。
面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
お気軽にご相談ください。
対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。