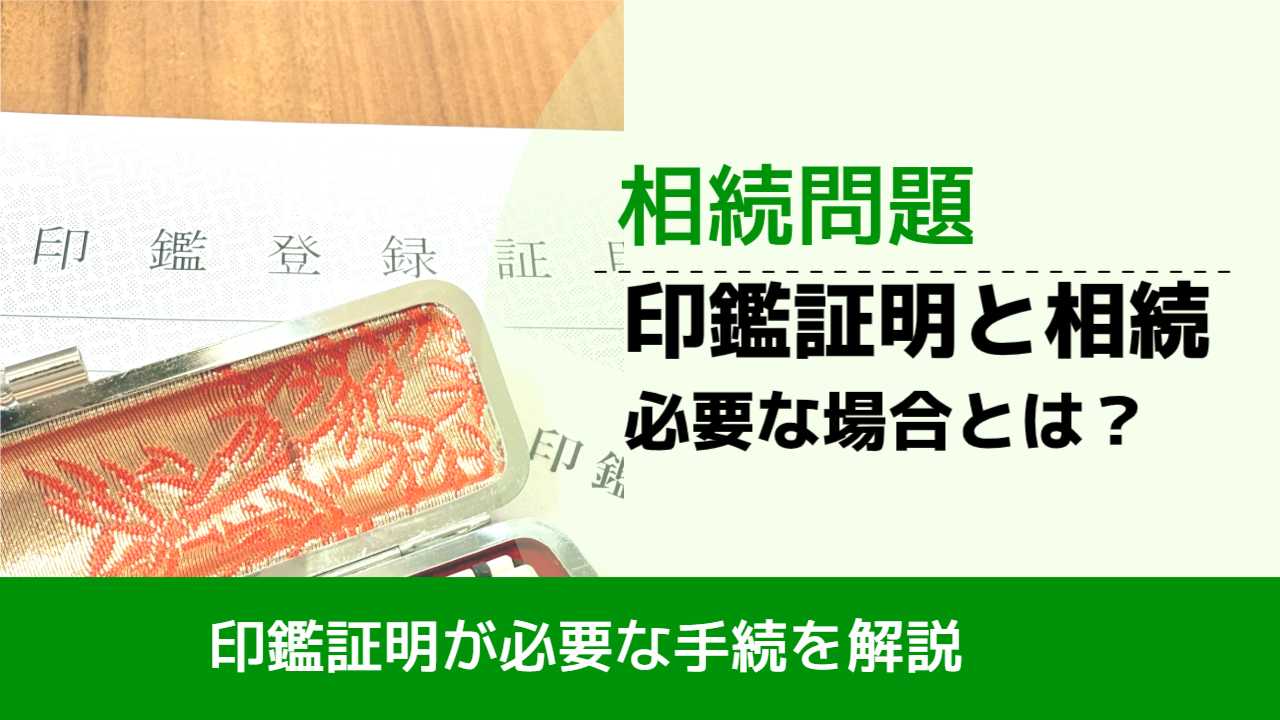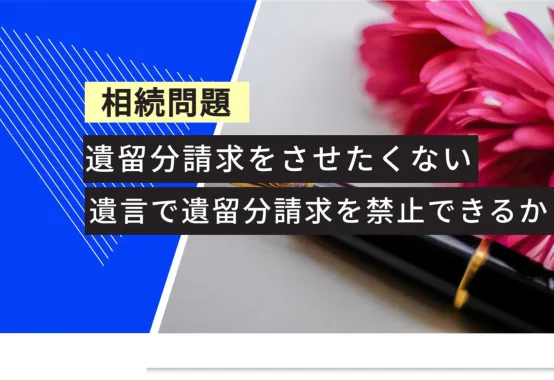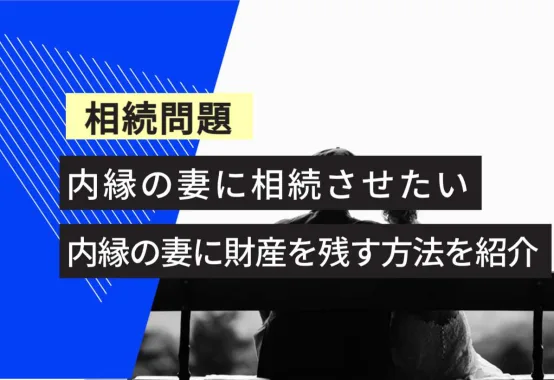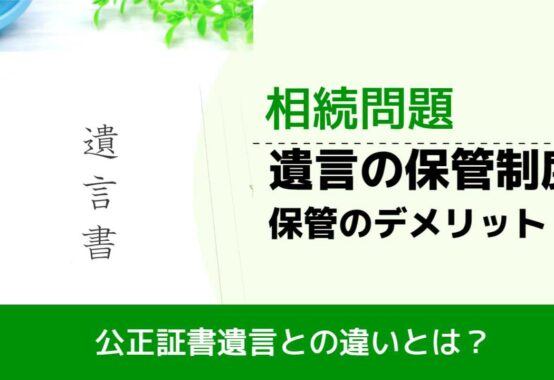相続の手続きを進めるにあたり、印鑑証明が必要になる場面は多々あります。しかし、具体的にどのような時に、なぜ必要になるのか、いまいちピンとこない方もいるのではないでしょうか。
本記事では、印鑑証明が相続においてどのような役割を果たすのか、取得方法から注意点まで、わかりやすく解説します。必要な場面を把握し、スムーズに手続きを進めるためにも、ぜひ参考にしてください。この記事が、皆様の相続手続きの一助となれば幸いです。
相続手続きで「印鑑証明」が重要な理由とは?
相続手続きは、故人(被相続人)の財産を法定相続人へ正確に引き継ぐという、非常に重要な法的手続きを伴います。そのため、金融機関等の関係各所では、手続きを行う人物が「正当な相続人本人であること」を厳格に確認する必要があります。この本人確認において、印鑑証明書が極めて重要な役割を果たします。
印鑑登録証明書とは、市区町村に届け出て登録された「実印」の印影が、間違いなく本人のものであることを公的に証明する書類です。実印の捺印に印鑑証明を添付することで、その個人の意思表示が個人の真意であることを強く示すことができる点が最大の特徴です。このため、金融機関や法務局など、さまざまな提出先において、印鑑証明書は高い信頼性を持つ書類として位置づけられています。
印鑑証明書の主な役割は以下の通りです。
- 相続人本人であることの確認
- 実印の印影が本人のものであることの公的証明
- 個人の意思表示の正当性の担保
- 書類の信頼性向上と法的効力の担保
- 後々のトラブルやなりすましによる不正の防止
例えば、遺産分割協議によって相続財産の分け方を決めた場合、その内容を記した「遺産分割協議書」には、相続人全員の実印押印が捺印されます。この実印と印鑑証明書をセットで提出することで、遺産分割協議書に記された内容が、各相続人本人の明確な意思に基づいて作成されたものであることが公的に証明されます。これにより、書類の信頼性が高まり、法的な効力が担保されるため、後々のトラブルやなりすましによる不正を未然に防ぐことが可能となります。
このように、印鑑証明書は相続手続きにおける書類の信頼性を保証し、円滑かつ安全に遺産を承継するために不可欠な役割を担う書類と言えるでしょう。相続手続きを滞りなく進める上では、その重要性を理解し、必要なタイミングで適切に準備することが求められます。


印鑑証明が必要になる相続手続きの6つのケース

相続手続きを進める上で、故人の財産を承継するにあたっては、様々な公的機関で相続人ご自身の印鑑証明書が求められる場面が多くあります。
以下では相続手続きにおいて特に印鑑証明書が求められる代表的な5つのケースについて、それぞれ詳しく解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら、ご確認ください。
ケース1:遺産分割協議書を作成するとき
相続手続きにおいて、まず重要となるのが遺産分割協議書です。これは、故人の遺産を法定相続人全員がどのように分割するかについて合意した内容を記した書類を指します。具体的には、「誰がどの財産をどれだけ取得するか」といった内容を明確に記載するものです。遺産分割協議書は、相続登記や相続預金の解約などの相続手続きを行うにあたって提出を求められる書類です。
この遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、各自の実印を押印することが求められます。実印の押印と同時に、その印影が間違いなく本人のものであることを公的に証明する印鑑証明書も必要となります。
遺産分割協議書と印鑑証明書は、その後の不動産の相続登記や預貯金の解約、株式・有価証券の名義書き換えなど、多岐にわたる相続手続きの基礎となる、極めて重要な書類です。
ケース2:不動産の名義変更(相続登記)を行うとき
故人名義の不動産を相続人の名義へ変更する「相続登記」を行う際も、印鑑証明書は欠かせない書類です。相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局に申請しますが、この手続きにおいては、相続人の意思確認を厳密に行うため、印鑑証明書の提出が求められます。
特に、遺産分割協議によって不動産の分け方を決定した場合、その合意内容を記した「遺産分割協議書」を添付して相続登記を申請します。この遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印することが求められており、その実印が本人のものであることを公的に証明するために、相続人全員の印鑑証明書を法務局へ提出する必要があります。
ケース3:預貯金の解約や名義変更をするとき
被相続人名義の預貯金を解約し払い戻したり、相続人名義へ変更したりする際も、金融機関から印鑑証明書の提出を求められます。
これは、金融機関が相続手続きの正当性を確保し、相続人間の不要なトラブルを防ぐため、相続人全員の明確な意思を確認する必要があるからです。
預貯金の解約や名義変更を行う際は、以下の点に注意してください。
- 金融機関は、口座名義人が亡くなったことを知ると、被相続人の口座を凍結します。
- 凍結された預貯金を引き出すためには、適切な相続手続きを行う必要があります。
- 必要書類や手続き方法は各金融機関が独自の書式やルールを定めている場合が多いため、手続きを開始する前に必ず該当の金融機関に問い合わせ、必要な書類や手順を事前に確認することが非常に重要です。
ケース4:株式・有価証券の名義を書き換えるとき
被相続人名義の株式や投資信託などの有価証券を相続する場合も、名義変更の手続きが必要です。これらの手続きは、証券会社や信託銀行などの金融機関で行います。
名義書換の手続きでは、遺言書や遺産分割協議書がない場合には、金融機関が用意する「相続手続依頼書」や「株式名義書換請求書」といった書類に相続人が実印で押印し、印鑑証明書を添付することが求められます。
ただ、金融機関によって必要となる書類が異なることもあるため、手続きを開始する前に、必ず該当の金融機関へ問い合わせ、必要書類や手続きの詳細を事前に確認するようにしましょう。
ケース5:相続税の申告手続きをするとき
相続税の申告は、被相続人の遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数で算出)を超える場合に必要となる手続きです。この相続税申告書を税務署に提出する際、相続人全員の印鑑証明書が求められます。
ただし、遺言書がある場合や相続人が1人である場合には、印鑑証明の提出は求められません。
ケース6:相続分の譲渡をするとき
相続人が相続分の譲渡をする際には、印鑑証明を添付する必要があります。
相続分譲渡とは、相続人の1人が特定の相続人や第三者に対して、自分の相続分を譲渡することをいいます。
相続分譲渡をする際には、相続分譲渡証書を作成することを要しますが、相続分譲渡の意思表示が真正なものであることを示すため、相続分譲渡証書には印鑑証明書を添付することを要します。
印鑑証明書の取得方法

相続手続きで必要となる印鑑証明書は、所定の手順を踏むことでスムーズに取得が可能です。
以下では、いくつかの印鑑証明の取得方法について詳しく解説します。
まずは印鑑登録(実印の登録)を済ませる
印鑑証明書は、市区町村に登録された実印を公的に証明する書類です。そのため、印鑑証明書を取得するには、事前の印鑑登録が不可欠です。印鑑登録は、お住まいの市区町村の役場窓口で手続きができます。
手続きに必要なものは、次の通りです。
- 登録する印鑑(実印)
- 運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの本人確認書類
登録できる印鑑には規定があります。例えば、印影のサイズが8ミリメートル四方より小さいものや、25ミリメートル四方を超えるような大きすぎる印鑑は登録できません。また、ゴム印やシャチハタなど、印影が変形しやすい材質のもの、氏名以外の情報が刻印されている印鑑も登録できません。
印鑑登録の手続きが完了すると、「印鑑登録証(カード)」が交付されます。このカードは、印鑑証明書を発行する際に必要となるため、大切に保管してください。
印鑑証明書を発行してもらう
印鑑登録が完了しましたら、次に印鑑証明書の発行手続きを行います。最も一般的な方法は、お住まいの市区町村の役所の窓口で申請することです。
窓口で印鑑証明書を発行してもらう際に必要なものは、印鑑登録証(印鑑登録カード)と手数料が必要となります。印鑑登録カードを持参していれば、実印そのものは必要ありません。
コンビニ交付サービスを利用する方法
市区町村の窓口が開いている時間帯に役所へ行くのが難しい方でも、コンビニエンスストアのキオスク端末(マルチコピー機)を利用して印鑑証明書を取得できる便利なサービスがあります。
この「コンビニ交付サービス」は、土日祝日や早朝・深夜でも印鑑証明書を発行できるため、忙しい方にとって非常に利便性の高い方法です。
このサービスを利用するには、顔写真付きの「マイナンバーカード」が必須です。また、お住まいの自治体がコンビニ交付サービスに対応している必要もあります。対応状況は、お住まいの市区町村のウェブサイトなどで事前に確認しておくと良いでしょう。
代理人が取得する場合の手順と必要なもの
ご本人が病気や仕事の都合で役所に行けない場合でも、代理人が印鑑証明書を取得できます。代理人が窓口で申請する際の手順は、以下の通りです。
まず、役所の窓口に備え付けの交付申請書に記入した上で、本人の印鑑登録証を提示することで印鑑証明の交付を受けることができます。印鑑登録証の交付により本人の委任の意思が確認できるため、別途委任状は不要とされています。提出した書類と手数料が確認された後、印鑑証明書が交付されます。
相続手続きで押さえておきたい印鑑証明のポイント
ここまで、相続手続きにおける印鑑証明書の必要場面と具体的な取得方法について解説しました。以下では、スムーズに相続手続きを進めるためには、いくつかの実務的なポイントを押さえておくことが重要です。
注意点1:有効期限は提出先によって違う
印鑑証明書そのものに法律上の有効期限は定められていません。しかし、金融機関や法務局など、提出先によっては独自の有効期限を設定している点が重要な注意点です。
相続登記や相続税申告において提出する印鑑証明書には期限はありません。一方、金融機関に関係する相続手続を進めるにあたっては、取得日から3か月以内の印鑑証明を求められることがあります。
このように、提出先によって求められる期限は異なります。そのため、手続きを行う直前に印鑑証明書を取得するのが最も確実です。
注意点2:必要枚数は?少し多めに準備すると安心
相続手続きでは、不動産の名義変更(法務局)、預貯金の解約(金融機関ごと)、有価証券の名義変更(証券会社ごと)など、提出先ごとに印鑑証明書の原本の提出が求められます。そのため、まずはご自身の相続財産の種類と数を把握し、各提出先に必要な枚数を合計して、最低限の必要枚数を用意しておくことが大切です。
注意点3:提出するのは必ず「原本」
相続手続きでは、印鑑証明書を提出する際、コピーではなく必ず原本が必要です。これは、印鑑証明書が個人の意思表示や取引の正当性を公的に証明する重要な書類であり、偽造や不正を未然に防ぐためです。
不動産の相続登記、預貯金の解約、株式の名義変更、相続税の申告など、多くの相続手続きにおいて、それぞれ提出先で印鑑証明書の原本が求められます。そのため、必要な手続きを事前に洗い出し、あらかじめ必要枚数分の原本を取得しておくことが重要です。
一部の手続きでは、印鑑証明の原本が還付されることもあります。例えば、相続登記や相続税申告の際には、申請時に原本還付を請求すれば、提出した印鑑証明書の原本を返却してもらうことができます。還付された原本は、他の手続きで再利用することも可能です。しかし、全ての提出先で原本が返却されるわけではありません。
こんな時どうする?印鑑証明にまつわるQ&A
相続手続きを進める中で、印鑑証明書に関する疑問や想定外の事態に直面することは少なくありません。
こうした「こんな時どうする?」といった具体的なお悩みに対し、以下ではQ&A形式で分かりやすく解説します。
Q.実印を紛失してしまった場合は?
実印を紛失した場合は、速やかに市区町村の役所での手続きが必要です。第三者による不正利用やなりすましを防ぐためにも、まずは印鑑登録を行った役所に「紛失届」を提出し、印鑑登録の使用をストップしてください。これにより、印鑑証明書の交付が速やかに停止されます。
紛失届の手続きと同時に、新しい印鑑を用意して再度「印鑑登録」を行うと、新しい実印の印鑑証明書を発行できるようになります。
これらの手続きが完了すれば、新しい実印とその印鑑証明書を用いて、滞りなく相続手続きを進められます。実印の紛失は不安に感じるかもしれませんが、適切な手順を踏めば問題なく対応できますのでご安心ください。
Q.相続人が海外に住んでいるときは?
海外に居住し、日本国内に住民票がない相続人は、印鑑登録ができないため、通常の印鑑証明書を取得できません。
このような場合でも、相続手続きを進める代替手段として、居住地の在外公館(大使館・領事館)で発行される署名証明書(いわゆるサイン証明書)を利用します。
署名証明とは、在外公館の領事の面前で本人が書類に署名したことを証明する公文書です。この証明により、その署名が間違いなく本人の意思に基づくものであることが公的に認められ、日本における実印と印鑑証明書の代わりとして法的効力を持ちます。遺産分割協議書など、実印の押印と印鑑証明書の添付が求められる相続手続きの場面で特に活用されます。
Q.相続人に未成年者がいる場合はどうすればいい?
未成年者が相続人に含まれる場合の主なポイントを以下にまとめます。
未成年者が相続人となる遺産分割協議では、未成年者本人が直接参加して法律行為を行うことはできません。そのため、未成年者の代わりに、法定代理人である父母が遺産分割協議に参加して署名捺印と印鑑証明を添付します。
ただ、法定代理人の父母も同様に相続人となる場合、父母と未成年者との間で利益相反が生じるため父母は未成年者の代理人として遺産分割に参加できません。その場合には、未成年者の意思を代理する「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。選任された特別代理人は、遺産分割協議書に実印を押印し、その印鑑証明書を添付することになります。
Q.他の相続人が協力してくれないときは?
遺産分割協議は、相続人全員の合意と、それぞれの実印押印、印鑑証明書の添付がなければ成立しません。このため、一人でも協力しない相続人がいる場合、相続手続きは完全に滞ってしまいます。このような事態に直面した際は、まず相手が非協力的な理由を丁寧にヒアリングし、冷静に話し合うことから始めましょう。感情的な対立を避け、手続きが滞ることで全員に生じるデメリットを具体的に伝えることが重要です。
当事者間での解決が困難な場合は、弁護士への相談を検討してください。弁護士が代理人として交渉に介入することで、法的な観点から円滑な説得を促し、解決へと導く可能性があります。
それでも進展が見られない場合の最終手段としては、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる方法が挙げられます。調停では、裁判所の調停委員が間に入り、相続人同士の話し合いを調整します。もし調停が不成立に終わった場合でも、その後「審判」に移行し、最終的には裁判所が遺産の分割方法を決定するため、手続きを完了させることが可能です。
相続手続は難波みなみ法律事務所へ

本記事では、相続手続きにおいて印鑑証明書がなぜ重要なのか、そしてどのような場面で必要になるのかについて詳しく解説しました。印鑑証明書は、遺産分割協議書への押印をはじめ、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金や株式といった金融資産の解約・名義変更、さらには相続税の申告まで、多岐にわたる重要な手続きで提出する書類の法的な有効性を証明するために不可欠な公的書類です。
相続手続きは専門的な知識を要する場面が多く、複雑に感じたり、相続人間で意見の相違やトラブルが発生したりする可能性もゼロではありません。もし手続きに不安を感じる場合や、スムーズな進行が難しいと感じるような状況であれば、一人で抱え込まずに、弁護士へ相談することも有効な手段です。専門家のサポートを得ることで、複雑な手続きを円滑に進め、安心して相続を完了させることができるでしょう。
初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。