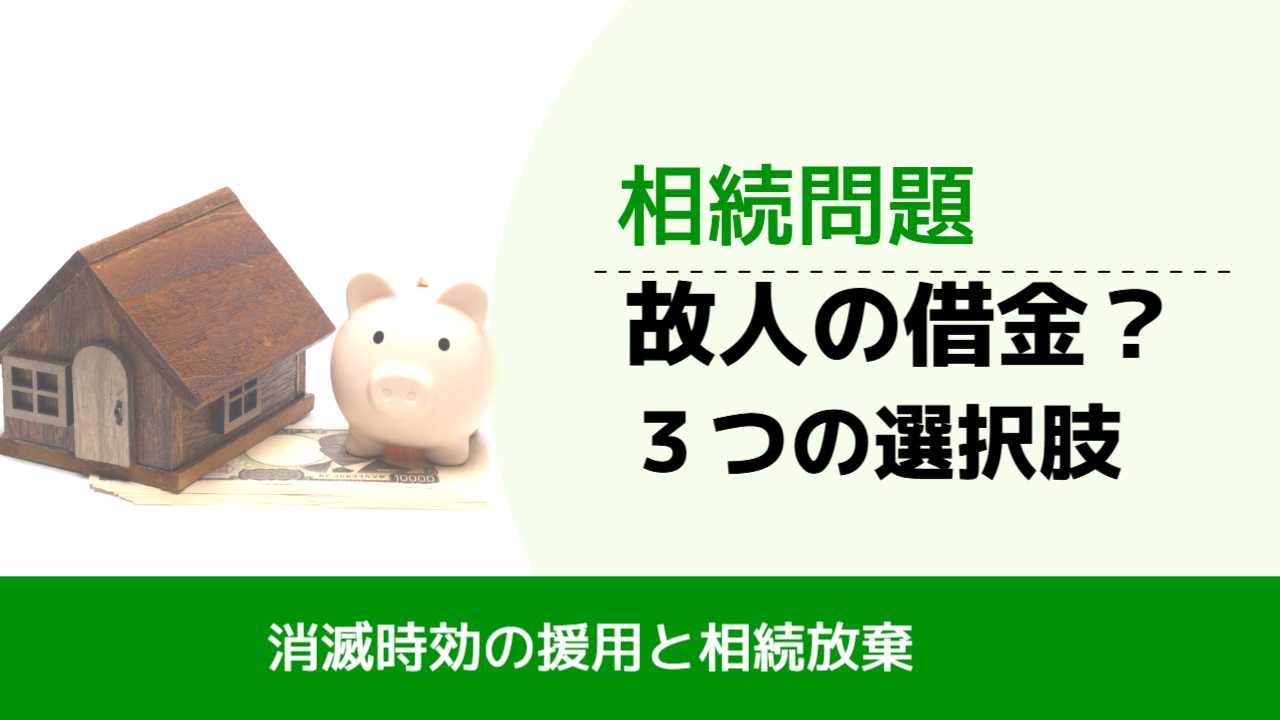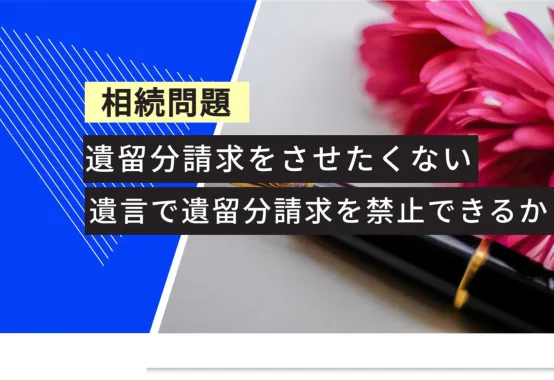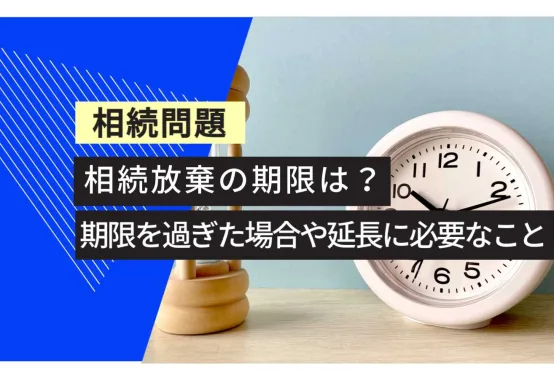亡くなられた方の借金は、一定期間が経過すると時効によって消滅する可能性があります。しかし、相続においては、借金も財産の一部として扱われるため、何もしなければ相続人が返済義務を引き継ぐことになります。
「もしかしたら、亡くなった人の借金も時効で消せるかもしれない」そう思ってこの記事にたどり着いた方もいるのではないでしょうか。
本記事では、相続が発生した場合に、借金を負わないための3つの対処法を解説します。相続放棄、限定承認、そして時効の援用について、わかりやすくご紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
【まず結論】故人の借金は「時効の援用」か「相続放棄」で対応できる
故人の借金が判明し、ご自身がその返済義務を負うのではないかと不安に感じている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、必ずしもご自身が返済の責任を負う必要はありません。故人の借金問題には、主に二つの対処法が考えられます。
以下では、故人の借金に関する対応方法の詳細や手続きの流れ、またご自身の状況に合った選択肢を見つけるためのポイントを分かりやすく解説します。
時効を過ぎても自動的には消えない?「時効の援用」手続きが必要
故人の借金に関して、消滅時効期間が経過しても、その返済義務が自動的に消滅するわけではありません。つまり、時効とは、ある一定期間が経過することにより、権利が消滅する制度ですが、期間経過だけで当然に権利の消滅が確定するわけではありません。
借金の返済義務を法的に消滅させるには、債務者が債権者に対し、「時効の援用」という意思表示をすることが必要です。民法第145条に「時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」と定められている通り、この意思表示をしない限り、時効が完成したとしても借金が消滅することはありません。つまり、時効の援用が債権者に到達した時点で初めて時効の効果が確定し、法的に返済義務が消滅します。
借金問題の解決策は時効だけじゃない!相続放棄・限定承認という選択肢
故人の借金問題に対する対処法は、時効の援用だけではありません。相続においては、「相続放棄」や「限定承認」といった法的手続きも有効な選択肢です。
「相続放棄」とは、亡くなった方のプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も一切引き継がないことを家庭裁判所に意思表示する制度です。これにより、相続人は故人の借金に対する返済義務を負うことがなくなります。
一方、「限定承認」とは、相続で得たプラスの財産の範囲内でのみ故人の借金を返済する手続きです。相続財産を上回る借金があったとしても、ご自身の財産を守りつつ借金を整理できる方法です。ただ、限定承認をするためには相続人全員で手続を進める必要があります。


亡くなった人の借金の時効はいつ成立する?知っておきたい期間と条件
亡くなった人の借金も、一定の期間を経過することで「消滅時効」が成立し、返済義務が消滅する可能性があります。以下では、亡くなった方の借金に関する時効期間や時効援用手続きの進め方について詳しく解説します。
時効成立までの期間は最後の返済から原則5年
亡くなった方の借金における消滅時効の成立期間は、原則として最後の返済日、あるいは返済期日から5年と定められています。この5年のカウントが始まる日、すなわち時効の起算点は、相続人が借金の存在を知った日ではなく、故人が最後に返済や新たな借り入れなどの取引を行った日を基準とします。
民法は2020年4月1日に改正され、時効期間のルールも変更されました。改正後の時効期間は、「債権者が権利を行使できると知った時から5年」、または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方とされています。消費者金融やクレジット会社からの借金については、民法の改正前後を問わず時効期間は5年となります。一方で、事業者ではない個人からの借入については、民法改正前の借入であれば10年、改正後の借入であれば5年となります。
例えば、故人が2018年5月1日に金融機関に対して最後の返済を行った場合、時効の起算日はその翌日である5月2日となり、時効が成立するのは2023年5月1日の経過後です。
【要注意】時効がリセットされてしまう3つのケース
故人の借金について、たとえ時効期間が経過していても、特定の行動をとることで時効が「更新(リセット)」され、それまでの期間がゼロに戻って再カウントされるため注意が必要です。民法改正により、旧民法での「時効の中断」は「時効の更新」に名称が変わっています。時効が更新される主なケースは、以下の3つです。
- 債務の承認
- 裁判上の請求
- 差押え
ケース① 債務の承認
債務の承認とは、債務者である相続人が借金の存在を認める行為を指します。例えば、借金の一部を返済したり、債権者に対し「支払いを待ってほしい」と支払いの猶予を求めたり、借金の減額交渉をしたりする行為がこれに該当します。こうした行為は、時効期間をゼロに戻し、新たに時効期間のカウントを始めることになります。時効がすでに完成している場合であっても、債務を承認すると時効の援用ができなくなるため、特に注意が必要です。
ケース② 裁判上の請求
債権者から訴訟や支払督促といった裁判上の請求を起こされた場合も、時効は更新されます。訴えの提起によって訴訟が終了するまで時効の完成は猶予され、その後の確定判決や和解によって権利が確定すると、時効期間がリセットされる仕組みです。判決の確定等があると、時効期間は10年に伸長されます。そのため、裁判所から通知が届いた際は、速やかに対応を検討する必要があります。
ケース③ 差押えや仮差押え
債権者が、差押えなどの強制執行を行った場合も、時効が更新される事由となります。一方で、仮差押えをした場合には、時効の更新はされず時効の完成が猶予されるに留まります。
時効の援用手続きの具体的な進め方
時効を援用する際には、債権者へ「時効援用通知書」を送付します。この通知書は、内容証明郵便で送ることが一般的です。
時効援用通知書に記載すべき主な項目は以下の通りです。これらの情報を記載することで、時効援用が法的に有効である旨を債権者へ明確に伝えることができます。
| 項目 | 具体的な内容 |
| 差出人情報 | 氏名、住所、連絡先 |
| 債権者情報 | 会社名、契約番号など、債権者を特定できる情報 |
| 時効完成の事実 | 消滅時効が完成している旨 |
| 援用意思の表示 | 消滅時効を援用するという明確な意思 |
内容証明郵便を利用する主な理由は、郵便局が「いつ、誰が、どのような内容の文書を送ったか」を公的に証明してくれるため、将来的なトラブルを防ぎ、法的な証拠として残せる点にあります。一方、普通郵便の場合、相手が受け取っていないと主張すると、その証明が難しくなります。
時効援用通知書はご自身で作成することも可能で、インターネット上にはテンプレートも存在します。しかし、記載内容に不備があったり、債権者とのやり取りで意図せず債務を承認してしまい、時効が更新(リセット)されるリスクも考えられます。正確かつ確実に手続きを進めるためには、弁護士などの専門家へ依頼することを検討すると良いでしょう。
時効が使えない場合に検討したい「相続放棄」と「限定承認」
故人の借金に関して、時効の援用が常に利用できるとは限りません。例えば、時効期間がまだ経過していない場合や、前述した「時効の更新(リセット)」により時効期間が振り出しに戻ってしまったケースでは、時効の援用は選択できません。しかし、そのような状況でも、相続人が故人の借金を負わないための法的な手続きは存在します。それが「相続放棄」と「限定承認」です。
以下の項目からは、それぞれの制度について詳しく解説し、ご自身の状況に合った選択肢を見つけるための判断基準をご紹介します。
選択肢①:相続放棄|プラスの財産もマイナスの財産もすべて手放す
相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てることで、亡くなった方のプラスの財産(預貯金、不動産など)とマイナスの財産(借金、保証債務など)のすべてを一切受け継がないようにする法的な手続きです。この手続きが認められると、申述した相続人は「初めから相続人ではなかった」とみなされます。
相続放棄には、以下のような特徴があります。
| 【メリット】 ・亡くなった方の借金に対する返済義務が無くなります。これにより、ご自身の財産を保全し、借金の負担から解放されるでしょう。 【注意点】 ・一度相続放棄をすると、原則撤回できません。たとえ後から亡くなった方に多額のプラスの財産があったと判明しても、それを相続することはできなくなります。 ・自身が相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人へと移ります。例えば、子が放棄すれば親に、親が放棄すれば兄弟姉妹へと相続権が移動するため、他の親族に予期せぬ影響が及ぶ可能性があります。 |
相続放棄を検討する際は、これらの点を十分に理解した上で、慎重に判断することが重要です。
選択肢②:限定承認|相続財産の範囲内でのみ借金を返済する
限定承認とは、相続によって得た預貯金や不動産などのプラスの財産を上限として、故人の借金を負担する制度です。この方法を選ぶと、もし借金がプラスの財産を超過しても、相続人はご自身の固有の財産から返済する義務を負いません。借金を返済した後にプラスの財産が残った場合、その財産を相続できます。これが大きなメリットです。
限定承認が特に有効なケースは、以下の通りです。
- 故人の借金の正確な金額が不明な場合
- 先祖代々受け継いできた実家など、どうしても手放したくない大切な財産がある場合
しかし、限定承認の手続きは複雑であり、迅速な対応が求められます。
【比較表】あなたに合うのはどれ?時効援用・相続放棄・限定承認の選び方
故人の借金問題に直面した場合、「時効の援用」「相続放棄」「限定承認」という3つの対処法が考えられます。これらはそれぞれ異なる特徴を持つため、ご自身の状況に最適な選択肢を見極めることが重要です。
故人の借金問題に対する3つの対処法(時効の援用、相続放棄、限定承認)の主な特徴を以下の表にまとめました。
| 選択肢 | 時効の援用 | 相続放棄 | 限定承認 |
| 概要 | 時効期間の経過で借金消滅 | 財産・借金すべて放棄 | プラスの財産の範囲内で借金返済 |
| メリット | 借金の負担が消滅 | 借金返済義務なし | 自身の財産を守れる |
| デメリット | 誤って承認して時効更新 | 全ての遺産放棄、撤回不可、次順位影響 | 手続き複雑、費用、全員申述要 |
| 条件 | 最終返済から原則5年経過 | 相続開始を知り3ヶ月以内 | 相続開始を知り3ヶ月以内、全員 |
| 期限 | なし | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
| おすすめ | 時効完成の可能性が高い人 | 財産が借金以下、全て手放したい人 | 借金不明でも財産を残したい人 |
プラスの財産が不要で、借金から完全に解放されたい場合は相続放棄が、時効の条件を満たしている場合は時効援用が、そして借金や財産の全容が不明でも大切な財産は残したい場合は限定承認が有効な選択肢となるでしょう。選択肢の中には期限が設けられている場合がありますので、早めに検討し、必要に応じて弁護士へ相談することをおすすめします。
故人の借金が発覚したら…まず取るべき3つのステップ

故人の借金が突然発覚すると、大きな動揺や不安を感じるのは当然です。
問題を適切に解決するには、感情的にならず、順序立てて行動することが何よりも重要です。これからご紹介する3つのステップを踏むことで、状況を正確に把握し、ご自身にとって最適な解決策を選択できるようになるでしょう。
Step1: 故人の財産と借金の全体像を把握する「財産調査」
故人の借金が発覚した場合、まず「財産調査」を行い、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)の全体像を把握しましょう。この把握が、今後の対策を講じる上で最も重要となります。
遺品の中から、借金の契約書や督促状、預貯金通帳、不動産の権利証、生命保険証券といった財産に関する手がかりを探します。不動産については、固定資産税の納税通知書や市区町村役場で取得できる「名寄帳」により所有状況を確認できます。
借金の正確な借入状況は、信用情報機関への情報開示請求を行うことで確認できます。以下の3機関すべてに情報開示を請求しましょう。
- CIC
- JICC
- KSC(全国銀行個人信用情報センター)
これらの調査結果に基づき「遺産目録」を作成し、資産と負債のどちらが多いかを客観的に判断することが、次のステップに進むための重要な準備となります。
Step2:財産状況をもとに対応方針を決定する
Step1で故人の財産状況、具体的にはプラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)の全体像を把握した後、その情報に基づき、今後どのように対応するかの方針を決定する重要なステップへと進みます。この方針決定は、その後の手続きや結果に大きく影響するため、慎重な検討が求められます。
検討すべき主な選択肢は、以下の4つです。
- 時効の援用
- 相続放棄
- 限定承認
- 単純承認(そのまま相続して返済)
それぞれの状況に合わせた判断基準は以下の通りです。特に、相続放棄や限定承認には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という厳格な期限が設けられています。この期間を過ぎると、原則として自動的に「単純承認」とみなされ、相続分に応じて故人の借金も相続することになるため、迅速に方針を決定し、行動に移すことが重要です。
| 対応方針 | 判断基準 |
| 相続放棄 | 借金がプラスの財産を明らかに上回る、または借金しかない場合 |
| 限定承認 | プラスの財産もあるが借金の正確な額が不明、または借金がプラスの財産を超える可能性がある場合 |
| 時効の援用 | 時効の成立条件を満たしている場合 |
| 単純承認(そのまま相続) | プラスの財産が借金を大きく上回り、返済に問題がない場合 |
Step3: 方針決定後、速やかに手続きを実行する
方針が固まったら、速やかに手続きを実行することが非常に重要です。どの方法を選ぶべきか判断に迷う場合や手続きに不安がある際は、この段階で弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。弁護士のアドバイスを受けることで、適切な選択肢を判断し、複雑な手続きを円滑に進められるでしょう。
故人の借金問題でよくある質問
故人の借金問題は、予期せぬ形で発覚することも多く、その対応には多くの疑問や不安が伴うものです。
以下では、実際に多くの方から寄せられる相談内容を、Q&A形式でご紹介します。
督促状が届いたのですが、どうすればいいですか?
故人の借金に関する督促状が届いた場合でも、決して慌てて債権者(貸主)に連絡したり、安易に一部でも返済したりしないよう注意が必要です。こうした行為は、借金の存在を認める「債務の承認」とみなされる可能性があります。一度債務を承認すると、時効の援用ができなくなるだけでなく、「単純承認」と判断され、後からの相続放棄が認められなくなるおそれがあるため、注意が必要です。
まずは、督促状に記載されている内容を冷静に確認することが重要です。具体的には、時効が成立しているか、あるいは相続放棄を検討すべきかを判断する上で、以下の情報が重要な手がかりとなります。
- 債権者名
- 借入日
- 最終返済日
- 借金額
督促状を受け取った際は、決してご自身で対応しようとせず、速やかに弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。弁護士は、督促状の内容を精査し、法的に最も適切な対応を判断します。また、債権者との交渉や書類作成、家庭裁判所への相続放棄の申述といった複雑な手続きについても、代理人として進めてくれるため、安心して問題解決へと進めることができます。
相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎてから借金が発覚した場合は?
相続放棄は原則として「自己のために相続の開始があったと知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間は「熟慮期間」と呼ばれており、この期限を過ぎると相続放棄はできなくなります。ただ、この期間を過ぎたからといって、必ずしも相続放棄ができなくなるわけではありません。相続人が「相続財産が全くないと信じ、かつ、そのように信じたことに合理的な理由がある」状況で、後に借金の存在を知った場合、その借金の存在を知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる可能性があります。
ただし、期限を経過してからの相続放棄の手続きは、一般的な相続放棄に比べて専門的な判断が求められるため、簡単ではありません。そのため、このような状況に直面した際は、諦めずに速やかに弁護士へ相談することが非常に重要です。
借金の調査方法がよく分かりません
故人の借金を正確に把握するには、遺品からの情報収集と信用情報機関への情報開示請求が有効な手段です。
まず、故人の自宅にある遺品の中から、借金の手がかりとなる書類を探しましょう。例えば、貸金業者との契約書、督促状、返済明細書、預金通帳の取引履歴などが挙げられます。
より確実な方法として、信用情報機関への情報開示請求があります。日本には「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」「株式会社日本信用情報機構(JICC)」「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」の3つの信用情報機関が存在します。これらすべてに開示請求を行うことで、故人の金融機関や貸金業者からの借入状況を網羅的に把握することが可能です。
ただし、信用情報機関で把握できるのは、あくまで加盟している金融機関からの借入情報に限られます。個人間の借金や、税金・社会保険料などの滞納状況は調査対象外となりますので、この点にご注意ください。
一人で悩まないで!借金問題は専門家への相談が解決の近道
故人の借金問題は、時効の援用、相続放棄、限定承認といった、専門知識を要する複雑な手続きが伴います。ご自身で対応しようとすると、法的な判断ミスを犯したり、煩雑な手続きに多くの時間を要したりするリスクがあります。このような状況で弁護士に相談すれば、次のような多くのメリットが得られます。
状況に応じた最適な解決策の提案
弁護士は被相続人の借金状況や相続財産の内容を分析し、時効の援用、相続放棄、限定承認の中から、個々の状況に最も適した解決策を法的観点から導き出してくれます。
専門的で煩雑な手続きの正確な代行
時効援用の内容証明郵便作成・送付や、家庭裁判所への相続放棄・限定承認の申立てなど、専門知識が不可欠な手続きを一任できます。
特に弁護士であれば、個別の債権額に制限なく対応し、依頼者に代わって裁判対応も行うことが可能です。
精神的負担の軽減(債権者対応の窓口)
債権者からの督促や連絡の窓口になってもらえるため、直接債権者とやり取りをする必要がなくなり、精神的な負担を大幅に軽減し、問題解決に集中しやすくなるでしょう。
亡くなった人の借金問題は難波みなみ法律事務所へ

亡くなった方の借金問題に直面した際、本記事では「時効の援用」「相続放棄」「限定承認」という3つの主要な対処法があることを紹介しています。これらの選択肢は、故人の借金の状況や残された財産、そして相続人の意向によって、どれが最適であるかが異なります。
どの手続きを選ぶべきか、またご自身の状況で時効が成立しているのかといった判断には、専門的な知識が求められます。安易な自己判断は、思わぬ不利益を招く可能性も考えられます。複雑な法的手続きを正確に進め、ご自身にとって最善の解決策を見つけるためには、弁護士へ速やかに相談することが、問題解決への最も確実な近道です。
一人で悩まず、まずは弁護士の意見を聞いてみることをおすすめします。早期に相談することで、心の負担を軽減し、適切な対応へと確実に進めることができるでしょう。