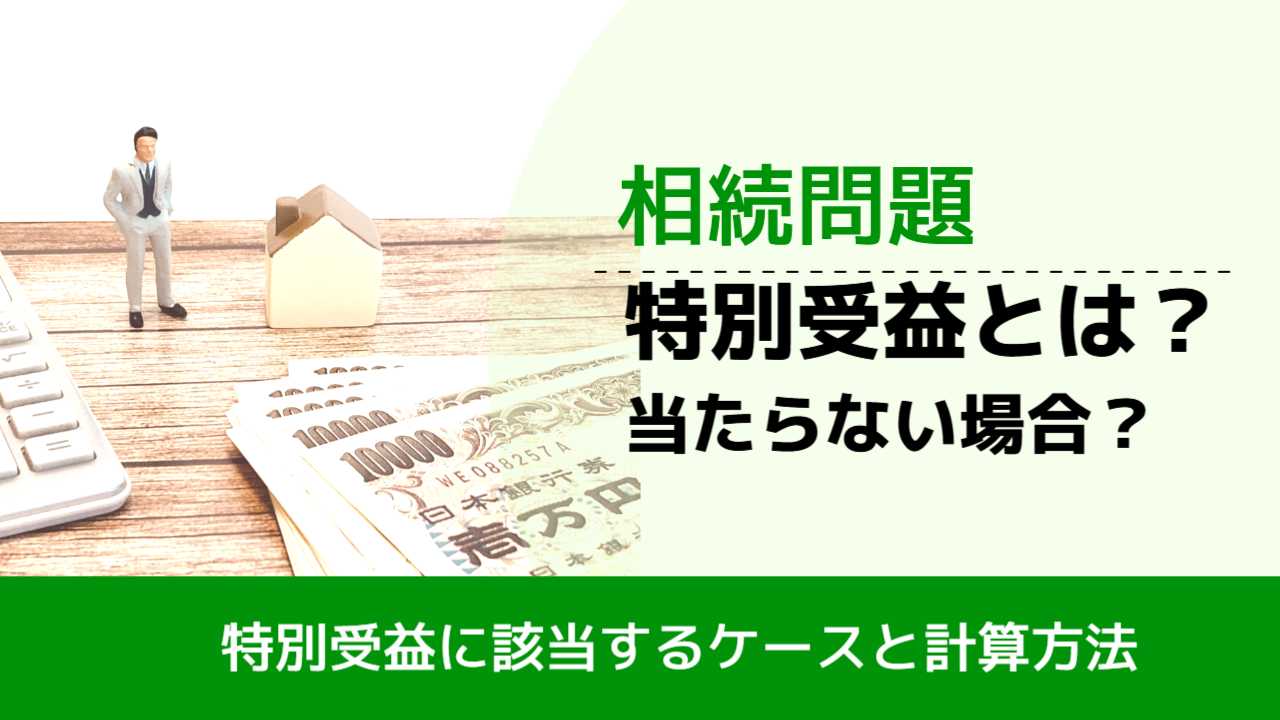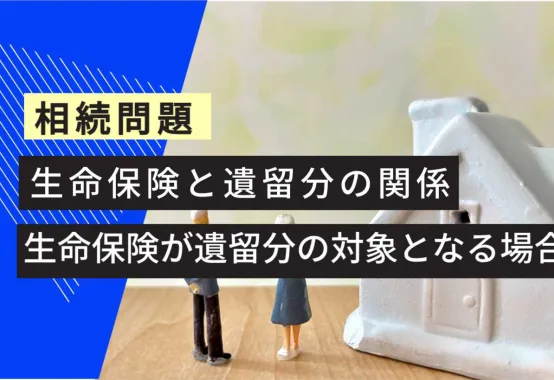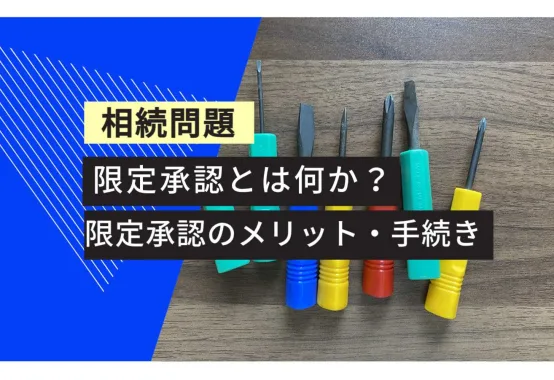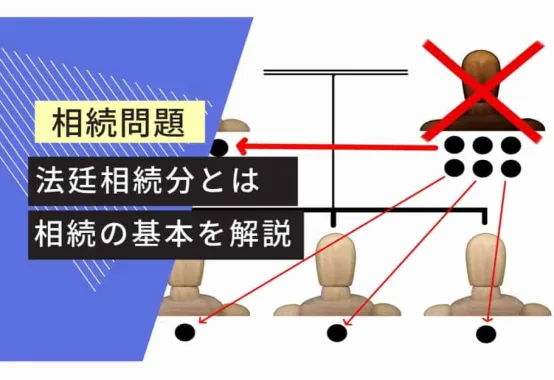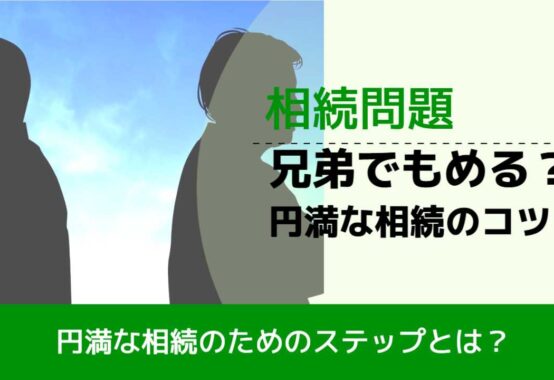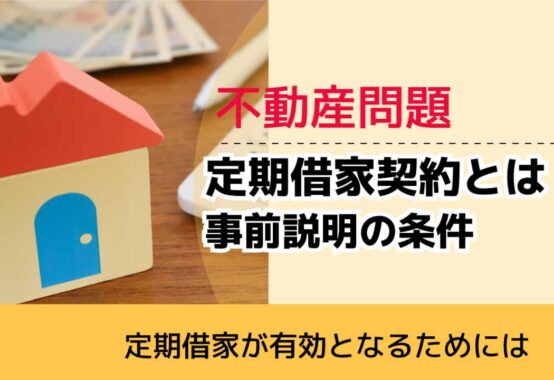相続対策として注目される生前贈与ですが、場合によっては「特別受益」とみなされ、相続時に贈与を受けた人が有利になりすぎないよう調整されることがあります。しかし、すべての生前贈与が特別受益になるわけではありません。
そこで本記事では、どのような贈与が特別受益とみなされないのか、具体的なケースを交えながら解説します。親族間で争いが起こらないように、特別受益にあたらない生前贈与について正しく理解し、適切な対策を講じることが大切です。相続に関する不安を解消し、円満な相続を実現するための一助となれば幸いです。
「あの人だけズルい…」は間違い?生前贈与と特別受益の基本的な考え方
親から兄弟姉妹の誰か一人だけが、住宅購入資金、独立開業のための資金、あるいは留学費用といったまとまった援助を受けていたと聞けば、「あの人だけ有利だ」「不公平だ」と感じるのは無理もありません。
そこで、民法では「特別受益」という制度により、相続人間の公平を実現させるため具体的な相続分が調整されます。ただし、すべての生前贈与が特別受益にあたるわけではなく、その判断は個別の状況によって異なります。
そもそも「特別受益」とは?相続人間の公平性を保つための制度
特別受益とは、民法第903条に規定された制度で、被相続人(亡くなった方)から特定の相続人が生前に受け取った、遺産の前渡しといえる特別な利益を指します。具体的には、以下のようなものがこれに該当する可能性があります。
特別受益の目的は、相続人間の実質的な公平性を確保することにあります。もし特別受益の制度がなければ、被相続人から生前に多額の財産を受け取った相続人と、そうでない相続人との間で不公平が生じる可能性があります。民法は、このような相続人間の不均衡を是正し、相続人が公平な相続を受けられるよう調整する役割を果たします。
特別受益が認められた場合、その利益の価額を相続財産に加算し、各相続人の具体的な相続分を計算し直します。この特別受益の加算は「持ち戻し」と呼ばれます。


【ケース別】これは特別受益にあたる?あたらない?具体例でチェック
生前の贈与が、全て特別受益として扱われるわけではありません。特別受益に該当するかどうかの判断は、個々のケースにおける様々な事情を考慮して行われます。
そこで、以下の項目からは、ご自身のケースをイメージしやすいよう、これから見ていく具体例を紹介しながら詳しく解説します。
遺贈
まず、被相続人が遺言によって特定の相続人に財産を譲る「遺贈」は、原則として特別受益に該当します。これは、遺産の一部を前もって受け取ったものとみなされるためです。
一般的な生活費や教育費の援助
生活資金の贈与は生計の資本としての贈与には当たりますが、その金額が少額である場合には、親の扶養義務の範囲内であるとして、特別受益とされません。金額が10万円以下の場合には、扶養義務の範囲内と判断されることが多いです。
ただ、金額が10万円以下であっても、被相続人の収入状況や資産状況から、扶養義務の範囲を超えると判断できるケースもあります。他方で、10万円を超えていたとしても、相続人が持病により就労できないために生活支援している場合には、扶養義務の範疇であるとして、特別受益にあたらない可能性があります。
例えば、生活支援の送金額が20万円である場合、10万円を超える部分のみが特別受益となるのではなく、20万円全体が特別受益となります。また、多数回にわたる送金があるものの、送金額が10万円を超えるものもあれば、超えないものもある場合には、月額10万円を超える生活支援のみが特別受益に該当すると判断した事例もあります(東京家審平成21年1月30日)。
お祝い金
結婚祝い、結納、出産祝い、お年玉など、社会通念上妥当な範囲内のお祝い金も、通常は特別受益とはみなされません。また、挙式費用についても、同様に常識的な範囲であれば特別受益には当たりません。
大学の学費
大学の進学率が上昇している現代において、大学の学費は原則として特別受益には当たりません。
たとえ、兄弟のうち1人だけが大学に進学していたとしても、扶養義務の範囲内であるとして、特別受益にはならないのが原則です。
ただし、親の当時の収入状況や資産状況から、かなり無理をして大学の学費を負担している場合には、例外的に大学の学費負担が特別受益にあたる可能性もあります。また、私立大学の医学部の入学金等については、他の学部の学費と比べてかなり高額となるため、特別受益になります。ただ、実家の家業を承継するために私大医学部に進学したケースでは、特別受益には当たらないと判断した裁判例があります(京都地判平成10年9月11日)。
住宅購入資金
子どもがマイホームを購入するために、親から購入資金の支援を受けることは珍しくありません。このような住宅購入資金の贈与は、生計の資本としての贈与にあたるため、特別受益に該当します。
被相続人からの借入
相続人が被相続人から借入をしていても、相続人は被相続人に借入金を返済する義務を負うため、特別受益にはなりません。この場合、被相続人の相続人に対する貸金債権が相続財産となり、遺産分割されることになります。
仮に、消滅時効期間が経過して借入債務が消滅したとしても、特別受益には該当しないと考えられます。
相続人の配偶者や子供に対する贈与
被相続人が相続人ではなく相続人の配偶者や子に対して贈与をした場合、相続人ではない以上、特別受益には該当しません。
例外的に、配偶者や子供の名義を借用しただけで、実質的には相続人に対する贈与と言える場合には、特別受益に該当する可能性があります。
生命保険金
特定の相続人が受け取る生命保険金ですが、原則として、生命保険金は受取人固有の財産であり、相続財産には含まれないため、特別受益にはあたりません。
しかし、保険金額が遺産総額に対して著しく大きいなど、保険金受取人と他の共同相続人との間に生じる不公平が到底容認できないほど著しい特段の事情がある場合に限り、例外的に特別受益に準じて持ち戻しの対象となると判断されています。
以下に、生命保険金が特別受益と判断された、または判断が否定された主な事例をまとめます。
| 判決裁判所・日付 | 遺産総額に対する保険金の割合 | 判断結果 |
| 東京高等裁判所 平成17年10月27日 | 約99% | 特別受益と判断 |
| 大阪家裁堺支部 平成18年3月22日 | 約6% | 特別受益を否定 |
| 名古屋高等裁判所 平成18年3月27日 | 約61% | 特別受益と判断 |
| 広島高等裁判所 令和4年2月25日 | 約272%(2.72倍) | 特別受益を否定→夫から妻への保険金で生活保障が目的 |
このように、具体的な割合や状況によって判断が分かれるため、生命保険金が特別受益に該当するかどうかの判断は複雑です。
特別受益があると相続分はどうなる?「持ち戻し計算」の仕組み
相続人間の不公平を是正し、相続人間で公平な遺産分割を実現するために、特別受益は持ち戻された上で、相続人の具体的相続分が計算されます。この計算において、相続開始時の遺産総額に特別受益の価額を加えたものを「みなし相続財産」と呼びます。この「みなし相続財産」を基準に、まず各相続人の法定相続分を計算します。
以下では、持ち戻し計算の手順を解説します。
「みなし相続財産」を計算する
遺産分割の公平性を保つ目的で、特別受益があった場合の相続分の計算では「みなし相続財産」を計算します。この「みなし相続財産」は、被相続人が亡くなった時点での本来の相続財産に、特別受益と判断された生前贈与や遺贈の価額を加算したものです。具体的には、「みなし相続財産 = 相続開始時の財産 + 特別受益の価額」という計算式で求められます。
その上で、みなし相続財産に法定相続分の割合を掛けて、特別受益を受けた特定の相続人の相続分から特別受益の金額を控除することで調整します。
兄弟の1人が住宅資金援助を受けていた場合の計算例
| 【ケース設定】 被相続人:父 相続人:母、兄、弟の3名 父の遺産総額:7000万円 兄が生前に受けた特別受益:住宅購入資金として2000万円 |
上記のケースにおける持ち戻し計算は、以下の3つのステップで進められます。
相続開始時の遺産に特別受益額を加算し、「みなし相続財産」を算出します。
| 7000万円(遺産)+ 2000万円(兄への住宅資金贈与)= 9000万円(みなし相続財産) |
計算したみなし相続財産を法定相続分で分けます。このケースでの法定相続分は、母が2分の1、兄と弟がそれぞれ4分の1ずつです。
| 母:9000万円 × 1/2 = 4500万円 兄:9000万円 × 1/4 = 2250万円 弟:9000万円 × 1/4 = 2250万円 |
特別受益を受けた兄の相続分から、生前贈与額を差し引きます。
| 母:4500万円 兄:2250万円 - 2000万円(住宅資金贈与)= 250万円 弟:2250万円 |
この結果、最終的に各相続人が取得する額は以下の通りです。この計算により、生前贈与を受けた兄も、他の相続人との公平性が保たれた形で遺産を受け取れる仕組みです。
親の意思で贈与分を考慮しないことも可能?「持ち戻しの免除」とは
被相続人が「持ち戻しをしない」という意思表示をすることで、この計算を免除できる制度があります。これを「持ち戻しの免除の意思表示」と呼びます。持ち戻し免除が認められる場合を以下紹介します。
明示的な持ち戻し免除
被相続人が、特定の相続人に対する生前贈与を特別受益として扱わないという意思を明確に示している場合には、特別受益の持ち戻し免除が認められます。
明示的な免除を行う最も確実で一般的な方法は、遺言書にその意思を明確に記載することです。これにより、亡くなった後に遺族が故人の真意を巡って争うリスクを大幅に軽減できます。
ただし、持ち戻し免除の意思表示をしたとしても、他の相続人が持つ「遺留分」を侵害することはできません。仮に、持ち戻しの免除によって他の相続人の遺留分が侵害される場合、侵害された部分については遺留分侵害額請求の対象となる可能性があるため、注意が必要です。
黙示的な免除の場合
被相続人(親など)が遺言書などで明確に意思表示をしていなくても、その生前の言動、贈与が行われた背景、その後の状況など、様々な事情を総合的に考慮した結果、「持ち戻しを免除する意思があった」と推定されるケースがあります。例えば、以下のようなケースでは黙示の免除が認められる可能性があります。
- 家業の承継のために生前贈与をする必要があった場合
- 被相続人が生前贈与に対する見返りとして生活支援を受けている場合
- 病気等の理由により生活保障のために生前贈与をする必要があった場合
- 相続人全員に生前贈与している場合
この黙示の意思表示は客観的な証明が非常に難しく、相続人間の解釈の違いから紛争に発展しやすい側面があります。
特別受益の問題は難波みなみ法律事務所へ

特別受益に該当するかどうかの判断は、贈与の金額や目的、被相続人の収入や資産、他の相続人との公平さなど、多岐にわたる要因が絡み合うため、そう簡単に判断することができません。
個別の事情によって特別受益の判断は大きく変わるため、ご自身のケースで不安な点がある場合や、相続人間で意見が割れそうな場合は、早期に弁護士へ相談することが最善の解決策と言えます。弁護士は、客観的な証拠収集を支援し、法的根拠に基づいた有利な主張を行うことができます。専門家である弁護士の知見を借りることで、複雑な問題もスムーズに解決へと導けるため、一人で抱え込まず、積極的に相談を検討されることをお勧めします。
初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。