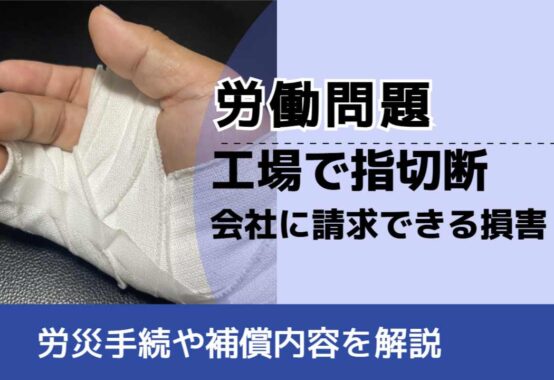この記事では、通勤途中の事故が労災として認定されるケースについて解説します。毎日の通勤で予期せぬ事態に遭遇し、怪我をしてしまった場合、労災保険が適用される可能性があります。しかし、どのような状況であれば労災と認められるのか、具体的な条件や申請方法が分からず、お困りの方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、通勤災害と認められるための条件や、労災申請に必要な手続きについて、わかりやすく解説します。万が一の事態に備え、ぜひ参考にしてください。
通勤中の事故は「通勤災害」として労災保険が適用される
会社への通勤中や退勤中に発生した事故は、原則として「通勤災害」として労災保険の給付対象となる可能性があります。
労災保険法における「通勤災害」とは、労働者が通勤中に被った負傷、疾病、障害、または死亡といった事態を指します。具体的には、自宅と会社の往復経路や、就業場所から他の就業場所への移動中に発生した事故などが、通勤災害の対象となり得ます。
仕事中に発生する事故を指す「業務災害」と同様に、通勤災害もまた労働者を保護するための制度として設けられています。業務災害が職務遂行中に発生する被災事故を対象とするのに対し、通勤災害は「通勤」という特定の移動過程におけるリスクに対応します。これらはいずれも、労働者の安全と健康を守る社会保険制度の一つであり、労働者が安心して働ける環境を支える重要な役割を担っています。
しかし、通勤中に発生したすべての事故が自動的に通勤災害として認定されるわけではありません。労災保険が適用されるには、いくつかの「通勤」の条件を満たす必要があります。例えば、移動経路が「合理的な経路」であったか、途中で「逸脱」や「中断」がなかったかなど、具体的な状況によって判断が分かれるケースも存在します。
そもそも「通勤災害」とは?労災認定の基本的な考え方
通勤災害として認定されるには、単に通勤中に事故に遭えば良いというわけではありません。労災保険法に定められた「通勤」の要件を厳密に満たす必要があります。
以下の項目では、労災保険における「通勤」の具体的な定義や、通勤災害と認定されるための「合理的な経路・方法」といった重要なポイントを詳しく解説します。
労災における「通勤」の3つの定義
労災保険法では、通勤災害が適用される「通勤」を、労働者が「就業に関し、合理的な経路および方法で往復すること」と定義しており、具体的には次の3つのパターンが定められています。
- 住居と就業の場所との間の往復
- 就業の場所から他の就業の場所への移動
- 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
それぞれの定義について詳しく見ていきましょう。
住居と就業の場所との間の往復
1つ目は、最も一般的な「住居と就業の場所との間の往復」です。これは、自宅から勤務先へ向かう移動や、勤務を終えて自宅へ帰る移動を指します。「住居」とは、労働者が日常生活のために利用している家屋等の場所で、就業のための拠点となる所を指します。長時間の残業、早出出勤、交通事情、自然現象などにより通常の住居以外の場所に宿泊しているような場合には、その宿泊先は住居ということができます。
就業の場所から他の就業の場所への移動
2つ目は、「厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動」です。
具体的には、同一企業内で本社から支社へ移動するケースや、副業・兼業で複数の勤務先を持つ方が勤務先Aから勤務先Bへ直接移動するケースなどがこれに該当します。
住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
3つ目は、「住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動」です。これは、単身赴任などで家族と離れて暮らす方が、赴任先の住居と帰省先の住居(家族が住む家など)との間を移動する場合を指します。週末に家族のもとへ帰る際の移動も、この定義に含まれることがあります。
「合理的な経路・方法」であることが重要
通勤災害と認定されるためには、通勤に利用する「経路」と「方法」が「合理的」であることが求められます。この「合理性」は、労災保険の給付を判断する上で不可欠な要素となります。
まず、「合理的な経路」とは、労働者が通勤のために通常利用する経路を指します。利用できる経路が複数あったとしても、社会通念上通常利用する経路であれば、必ずしも最短距離の経路でなくとも合理的な経路となります。他方で、合理的な理由もなく著しく遠回りとなるような経路を採る場合には合理的な経路とは認められません。
次に、「合理的な方法」とは、電車やバス、会社が許可しているマイカー、自転車、徒歩など、社会通念上、相当と認められる移動手段を指します。ただ、マイカー通勤が禁止されていたとしても、通勤方法として当然に合理性を欠くものではなく、許可を得ていないことをもって「合理的な方法」ではないとすることはありません。他方で、無免許運転や飲酒運転といった法令に違反する移動方法は、合理的な方法とはみなされません。
このような合理性が失われた状態を、通勤経路からの「逸脱」や「中断」と呼びます。原則として、逸脱や中断があった場合は通勤災害とは認定されません。
アパートの階段における転倒事故について、アパートの階段は住居と通勤経路との境界でるため、通勤の経路と認められるとして通勤災害に該当する(昭49.4.9基収第314号)。
「マイカー通勤の労働者が、同一方向にある妻の勤務先を経由する経路上における災害」について、勤務先が同一方向にあり、それほど離れておらず、妻の勤務先を経由することは、通常行われることであるため、合理的な経路であるとして通勤災害を肯定(昭49.3.4基収第289号)。
他方で、勤務場所を通り越して約450mほど走行した場所の妻の勤務場所で妻を下車させた後、自分の勤務先に向かう道中の事故については、逸脱中の事故であるとして通勤災害とはいえない(昭49.8.28基収第2169号)。
通勤が就業に関するものであること
通勤災害であるためには、通勤が就業に関して住居と就業の場所との間を往復する行為であることが必要です。
この「就業に関し」とは、通勤や退勤が業務に就くため、あるいは、業務を終えたことにより行われるものであることが必要です。例えば、業務終了後、事業場施設内で長時間にわたりサークル活動を行った後、帰宅する途中で被災した場合には、就業と帰宅との関連性を失わせることを理由に、通勤に該当しない可能性があります。
業務終了後、事業場施設内で2時間以上サークル活動を行い帰宅する途中の事故は通勤災害にあたらない(昭49.9.26基収2023号)


こんな場合はどうなる?通勤災害と認められる・認められない具体例
通勤災害と認められるかどうかは、個々の状況によって判断が分かれる複雑な問題です。
以下の項目では、通勤災害がどのような場合に認定され、またどのような場合に認定されないのかを、具体的な事例を挙げてわかりやすく解説します。
通勤災害と認められるケース
通勤災害と認められる具体的なケースは多岐にわたります。最も基本的なのは、自宅と会社の間の「合理的な経路」を「合理的な方法」で移動中に事故に遭うケースです。例えば、普段利用している通勤電車内での転倒、駅の階段での事故、マイカー通勤中の交通事故などが挙げられます。これらの事故は通勤の範囲を逸脱していないため、通勤災害として認定される可能性が高いでしょう。
また、常に同じ経路でなければならないわけではありません。交通渋滞や道路工事、自然災害による通行止めなどを避けるため、やむを得ず普段とは異なる経路を利用した場合でも、それが「合理的な迂回ルート」であれば通勤災害と認められます。
通勤災害と認められないケース(通勤の「逸脱」と「中断」)
通勤災害が認められない主なケースとして、通勤の「逸脱」と「中断」が挙げられます。これらの行為は、通勤の途中で本来の目的から外れる行為、あるいは通勤とは関係のない行動をとることを指し、原則として労災保険の対象外となります。
まず「逸脱」とは、通勤の合理的な経路から外れて、通勤とは無関係な目的で他の場所へ立ち寄る行為です。例えば、仕事帰りにテーマパークへ行ったり、通勤経路から大きく外れた飲食店に立ち寄ったりするケースがこれに該当します。
一方、「中断」とは、通勤経路の途中で、通勤とは関係のない行為を一定時間行うことを指します。具体的には、通勤経路上の映画館で映画を観る、バーで飲酒する、あるいは麻雀を行うことなどが挙げられます。
これらの逸脱または中断があった場合、その行為を行っている間はもちろんのこと、その後、合理的な通勤経路に戻ってからの移動も、原則として通勤とは認められません(労災保険法第7条第3項)。ただし、次に見出しで詳しく解説するように、日常生活上必要な特定の行為がやむを得ない事由で行われた場合は、例外的に認められることもあります。
| 区分 | 定義 | 具体例 |
| 逸脱 | 合理的な通勤経路から外れ、通勤と無関係な目的で他の場所へ立ち寄る行為 | 仕事帰りにテーマパークへ行く、通勤経路から大きく外れた飲食店に立ち寄る |
| 中断 | 通勤経路の途中で、通勤と関係のない行為を一定時間行うこと | 通勤経路上の映画館で映画を観る、バーで飲酒する、麻雀を行う |
「退勤途中、経路上の喫茶店でコーヒーを飲んだ後の災害」について、通勤災害にはあたらない(昭49.11.15基収第1867号)。
「退勤途中、書店及び交通事故写真展示会場に立ち寄り、再び通勤経路に復した後の災害」について、日常生活に必要な行為ではないため、通勤災害に当たらない(昭49.11.27基収第3051号)
「逸脱・中断」でも例外的に認められる日常的な行為
通勤経路からの逸脱や中断は、原則として通勤災害の対象外ですが、例外的に通勤とみなされるケースも存在します。
これは、日常生活を送る上でやむを得ない行為であり、かつその行為が最小限度であると認められる場合に限られます。逸脱や中断後、合理的な通勤経路に戻ってからであれば、再び通勤として扱われます。
具体的には、厚生労働省令で定められている以下の行為が例外として挙げられます。
- 日用品の購入など
- 病院での診察や治療
- 選挙の投票
- 要介護状態にある家族の介護や通院の付き添い
- クリーニング店や理髪店への立ち寄り
ただし、これらの行為が「日常生活上必要な行為」であると判断されたとしても、逸脱や中断が許容されるのは経路に戻った後からです。行為を行っている最中や、その行為のために立ち寄った場所にいる間に発生した事故は、通勤災害の対象外となるため、注意が必要です。例えば、飲食店での飲食中や、病院での診察中に怪我をした場合は、通勤災害とは認められない可能性があります。
もしも通勤中に事故に遭ってしまったら?発生直後からの対応フロー
通勤中に万が一事故に遭ってしまった場合、適切な対応を知っておくことは非常に重要です。予期せぬ事態に慌てることなく冷静に対処できるよう、事故発生直後からの手順を時系列に沿って解説します。
以下の項目では、事故発生直後から労災保険の申請手続きに至るまでの一連の流れを、重要な4つのステップに分けて具体的にご紹介します。
ステップ1:会社への報告
警察への連絡や負傷者の救護が落ち着いた後は、速やかに会社へ連絡することが重要です。労災保険の申請手続きを進めるには、会社の協力が不可欠です。
事業主には、労災事故が発生した際に労働基準監督署へ「死傷病報告」を行う義務があります。これを怠ると「労災隠し」とみなされる可能性があります。会社に正確な情報を伝えることで、その後の手続きを円滑に進めることができるでしょう。
報告は、直属の上司や人事・総務担当者など、労務管理に関わる部署へ行いましょう。会社へ伝えるべき内容は、具体的に以下の点を含めることが望ましいでしょう。
- 事故が発生した日時と場所
- 事故の具体的な状況(どのようにして事故が起こったか)
- 怪我の有無や程度、現在の状態
- 警察への連絡状況
まずは電話で第一報を入れるのが基本です。事故の衝撃で詳細を話すことが難しい場合でも、「通勤中に事故に遭った」という事実だけでも伝えることが大切です。その後の詳細な報告は、落ち着いてから改めて行うようにしてください。
ステップ2:病院で診察を受ける
事故による怪我の診察は、できるだけ労災保険指定医療機関を受診することをおすすめします。労災保険指定医療機関であれば、治療費を窓口で自己負担することなく、スムーズに手続きを進められます。厚生労働省のウェブサイトなどから、お住まいの地域や職場から最寄りの労災保険指定医療機関を検索できます。
以下に、受診する医療機関の種類による手続きの違いをまとめました。
| 医療機関の種類 | 治療費の窓口負担 | その他の手続きのポイント |
| 労災保険指定医療機関 | なし | スムーズに手続きを進められる |
| それ以外の医療機関 | 全額自己負担(一時的) | 後日、労働基準監督署へ請求し払い戻し |
病院の受付では、以下の点を明確に伝えましょう。
- 通勤中の事故による怪我であること
- 労災保険を利用したい旨
もしこの旨を伝えずに健康保険証を提出すると、健康保険での受診扱いとなり、後から労災保険への切り替え手続きが必要になるため、注意が必要です。
もし労災保険指定医療機関以外を受診した場合は、原則として、一度治療費の全額を自己負担し、その後、労働基準監督署に「療養の費用請求」を行うことで、かかった費用が払い戻されます。
労災保険が適用される場合、原則として健康保険は利用できません。仮に誤って健康保険を使ってしまったとしても、後から労災保険への切り替えは可能ですが、手続きに手間がかかります。そのため、診察時には必ず労災保険の利用を申し出ることが重要です。適切な補償を受けるためにも、これらの点に留意して病院を受診しましょう。
ステップ3:労災保険の申請手続きを行う
通勤災害が発生し、警察への報告や会社への連絡、病院での診察を終えたら、労災保険の申請手続きに進みます。労災保険の申請は原則として被災した労働者本人が行いますが、実際には多くの会社がこの手続きをサポートしてくれるでしょう。申請書類の提出先は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署です。
申請に必要な書類(請求書)は、受け取る補償の種類によって異なります。
| 補償の種類 | 請求書の名称(様式番号) |
| 治療費 | 【労災指定病院】療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3) 【労災指定外病院】療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5) |
| 休業中の補償 | 休業給付支給請求書(様式第16号の6) |
これらの書類は、労働基準監督署や厚生労働省のウェブサイトから入手できます。
請求書には、災害の発生状況を詳細に記載する項目や、事業主による証明印が必要な箇所があります。そのため、会社の人事や総務担当者と連携しながら、正確な情報に基づいて書類を作成することが重要です。
知っておきたい労災保険の主な補償内容
通勤災害が労災として認定された場合、被災した労働者は労災保険からさまざまな給付を受けられます。これらの給付は、事故によって生じる経済的負担を軽減し、療養や生活を支援するためのものです。以下の見出しでは、特に利用する可能性が高い補償内容について、具体的な給付内容や申請のポイントを詳しく解説していきます。
治療費に関する補償(療養給付)
通勤災害と認定された場合に受けられる補償のうち、特に重要なのが、治療にかかる費用を補填する「療養給付」です。これは、通勤災害による怪我や病気の治療に必要な費用を労災保険から給付する制度であり、これにより、被災した労働者は安心して医療を受けられます。病気や怪我が治癒するまで、療養に必要な期間、給付が継続されるのが特徴です。
診察料、薬剤費、手術費、入院費用といった費用のほか、一定の要件を満たせば通院交通費も対象となります。なお、指定医療機関以外で支払った費用については、その支払日の翌日から2年以内が請求期限となります。
仕事を休んだ際の所得補償(休業給付)
通勤災害による怪我や病気で、仕事を休まざるを得なくなった場合、その間の生活を支える所得補償として「休業給付」が設けられています。これは、労働者が療養のために働くことができず、賃金を得られない場合に支給される重要な制度です。
休業開始から最初の3日間は「待期期間」とされ、この期間は休業(補償)給付の支給対象外です。給付は休業開始から4日目以降に開始されます。通勤災害の場合には、事業主から待期期間の休業補償を受けることはできません。
支給額は以下の内訳で構成されます。
この給付により、療養中の経済的な不安が軽減され、治療に専念できる環境が整えられます。
| 支給内容 | 割合(給付基礎日額に対して) | 備考 |
| 休業(補償)給付 | 60% | 労災保険から支給 |
| 特別支給金 | 20% | 上乗せ支給 |
| 合計 | 80% | 給与の約8割に相当 |
自動車保険(自賠責保険)との違いと利用のポイント
通勤中の交通事故では、労災保険だけでなく自動車保険(自賠責保険)も適用されます。これら二つの保険は、補償の目的や仕組みに違いがあるため、それぞれの特徴を理解し、適切に利用することが重要です。
原則として、どちらの保険を先に利用するかは被災した労働者が選択できます。しかし、自動車保険の場合、保険会社から一方的に治療費の支払いを打ち切られることがありますが、労災保険の場合には被災者保護のために比較的長期の治療を期待できる点で労災保険にはメリットがあります。
ただし、同一の損害項目に対して、重複して補償を受けることはできません。例えば、治療費を労災保険から受け取った場合、その分の治療費を自賠責保険から再度受け取ることはできません。しかし、異なる損害項目であれば、両方の保険から給付を受けられます。治療費は労災保険、労災保険ではカバーされない慰謝料は自賠責保険から請求するといった併用が可能です。
通勤災害に関するよくある質問
以下の項目では、通勤災害に関する具体的な疑問に対し、Q&A形式で分かりやすく解説します。通勤手段の違い、雇用形態による適用範囲、さらには会社との間でトラブルが生じた際の対処法など、読者の皆様が特に知りたいであろうポイントに焦点を当てて説明します。
マイカーや自転車での通勤中も対象になりますか?
通勤手段がマイカーや自転車、徒歩などであっても、原則として通勤災害として労災保険の対象となり得ます。労災保険法で定められている「合理的な方法」であれば、通常の交通手段として広く認められており、通勤方法自体が問題となるケースは少ないでしょう。
ただし、いくつかの注意点があります。会社に届け出た通勤経路や方法と異なっていても、「合理的な経路・方法」であると認められれば、通勤災害として扱われる可能性があります。また、マイカーやバイク通勤が禁止されていたり、届出がなかったとしても、その経路や方法が合理的であれば通勤災害となります。しかし、無免許運転や飲酒運転は合理的な方法ではないと判断されます。
パートやアルバイトでも労災は使えますか?
パートやアルバイトの方も、正社員と同様に労災保険の適用対象となります。労災保険は、雇用形態に関わらず、事業主に雇用されて賃金を得ているすべての「労働者」を保護する制度です。そのため、以下のような幅広い立場の労働者が、通勤災害や業務災害の給付を受けることができます。
- パートタイム労働者
- アルバイト
- 派遣社員
- 契約社員
- 日雇い労働者
労災保険は労働基準法上の労働者を対象としており、会社に雇用関係がある方であれば適用されます。労働者を一人でも雇用している事業主には、労災保険への加入が法律で義務付けられています。
したがって、会社の規模や独自の判断によって、特定の雇用形態の労働者が労災保険の対象外となることはありません。万が一の通勤災害や業務災害に遭遇した際には、ご自身の雇用形態にかかわらず、労災保険の申請を検討しましょう。
会社が労災申請を認めてくれない場合はどうすればいいですか?
会社が労災申請に非協力的な姿勢を示した場合でも、労働者自身で手続きを進めることは可能です。労災保険の申請は労働者の正当な権利であり、会社の許可や承認がなくとも実施できることを覚えておきましょう。
もし会社が申請手続きに協力してくれない場合は、労働者自身が直接、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に申請書類を提出できます。労災保険の請求書には「事業主証明欄」がありますが、会社から証明が得られない場合であっても、労働基準監督署は申請を受理し、審査を進めます。
ご自身での手続きが難しいと感じる場合や、会社との間でトラブルに発展する可能性がある場合は、迷わず労働基準監督署や弁護士などの専門機関に相談することをおすすめします。適切なサポートを受けながら、安心して労災申請を進めていきましょう。
通勤災害の問題は難波みなみ法律事務所へ
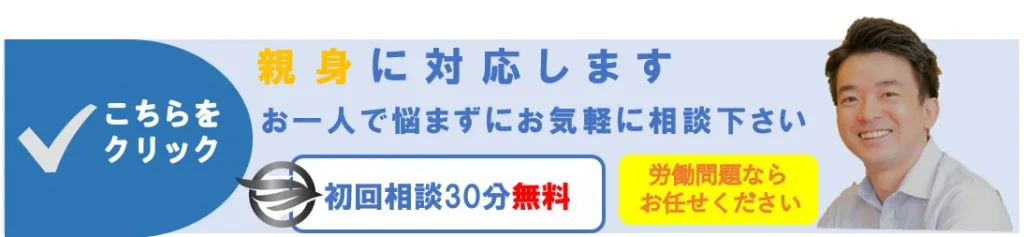
もしもの事態に備え、通勤災害に関する正しい知識を身につけておくことは、自身の生活を守る上で非常に重要です。
本記事では、通勤災害として認められるケースと認められないケースの具体例を解説しました。どのような状況が対象となるのかを把握しておくことで、いざという時に適切な判断ができるでしょう。特に、通勤経路からの逸脱や中断は通勤災害の認定に大きく影響するため、日常生活上やむを得ない行為の例外についても、理解を深めておくことが重要です。
万が一、通勤中に事故に遭ってしまった場合は、慌てずに適切な対応を取ることが重要です。会社が労災申請に非協力的な場合でも、労働者自身で労働基準監督署に直接申請できることや、弁護士などの専門家に相談できることも覚えておくと良いでしょう。
通勤災害の知識を正しく理解し、万が一の事態に備えることは、ご自身とご家族の安心につながります。本記事で解説した内容を参考に、通勤災害に関する備えを整えましょう。