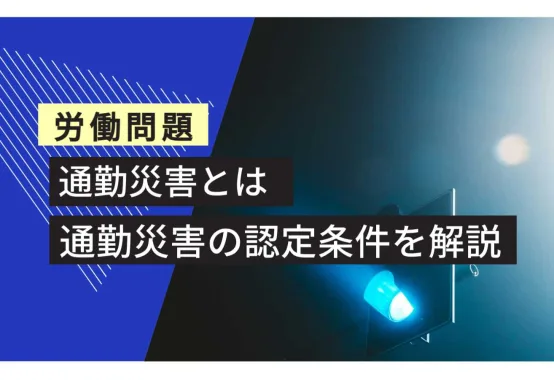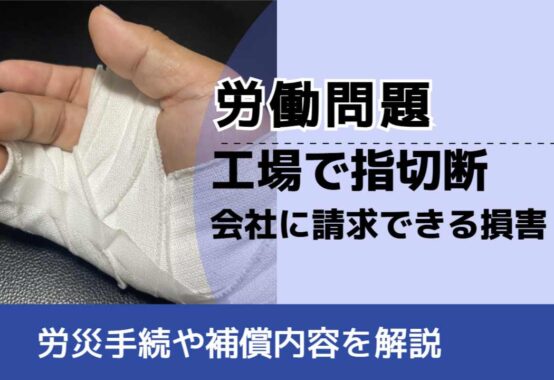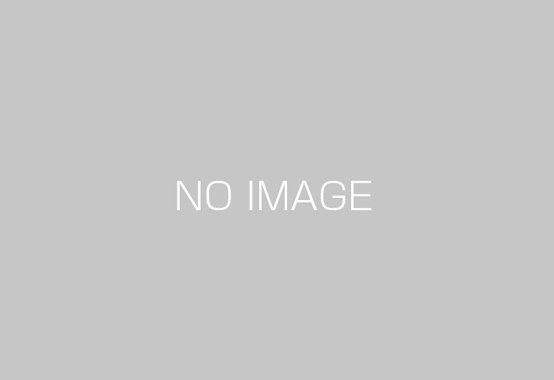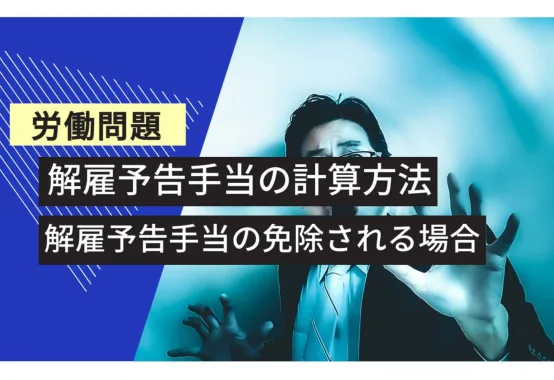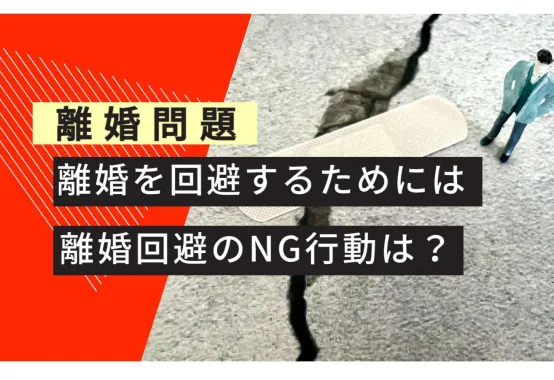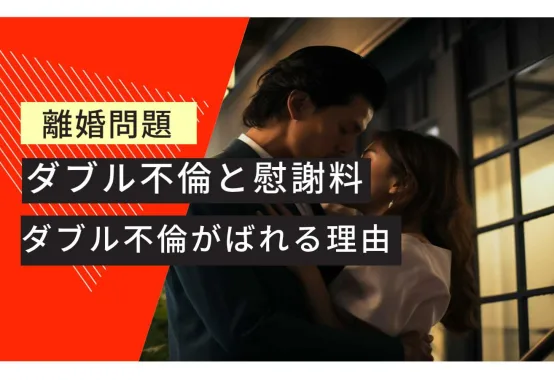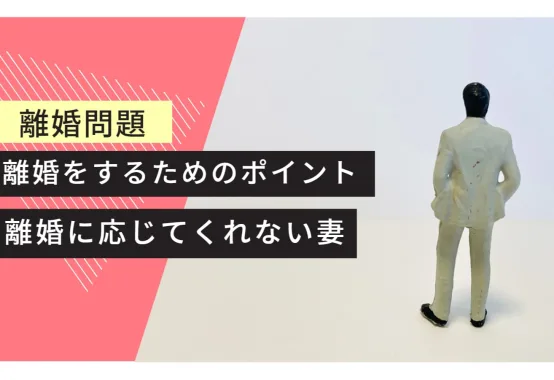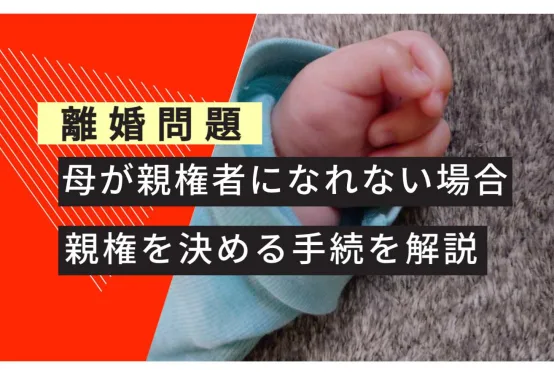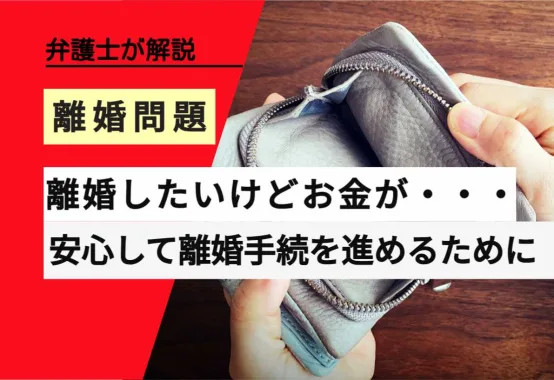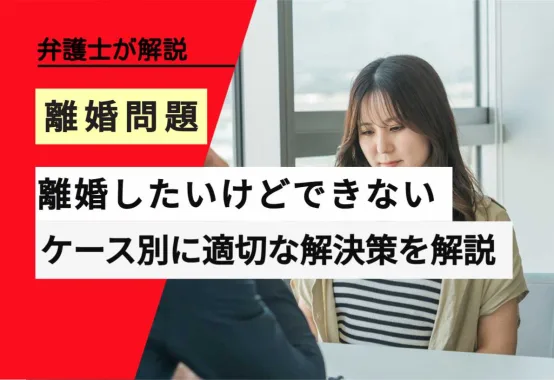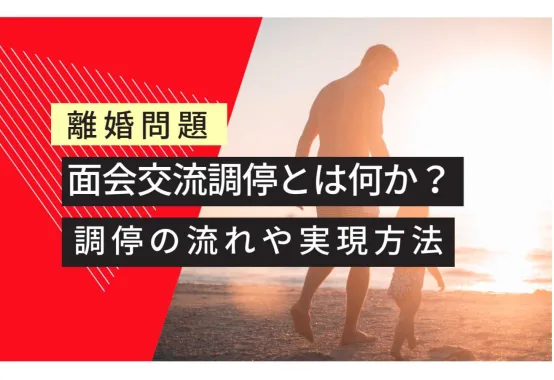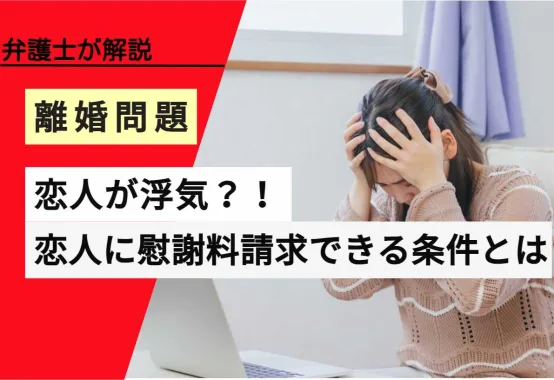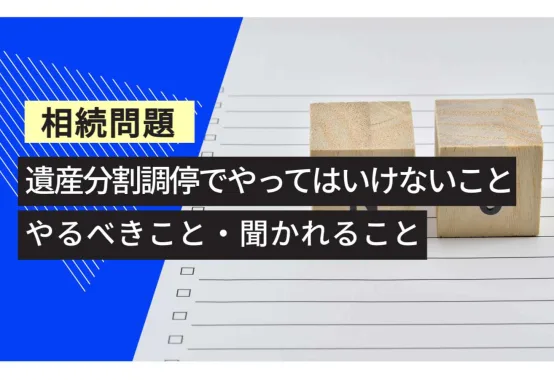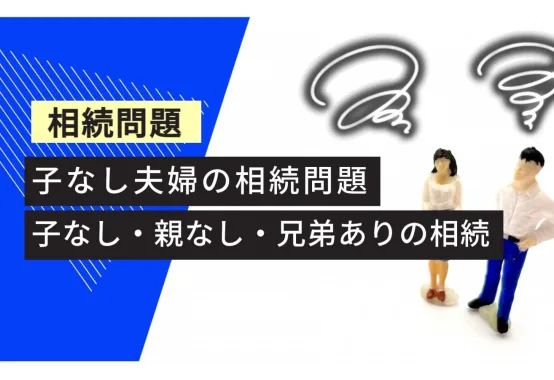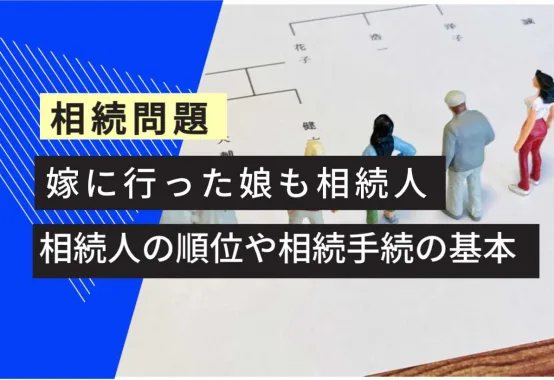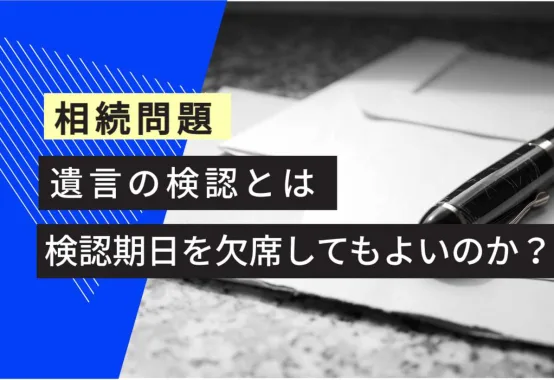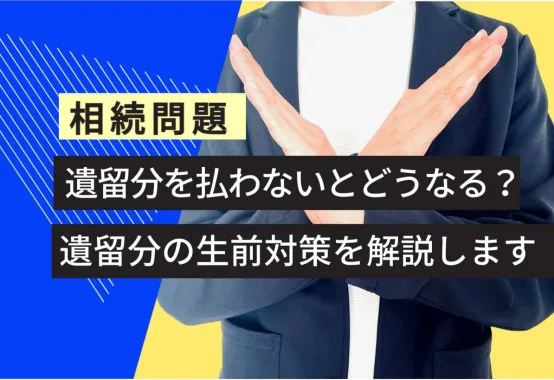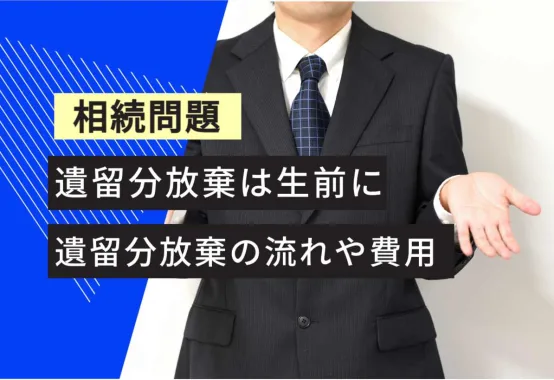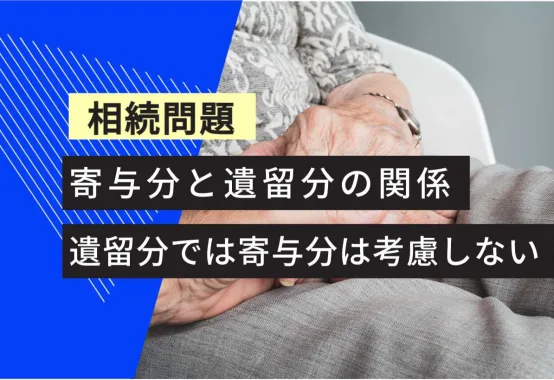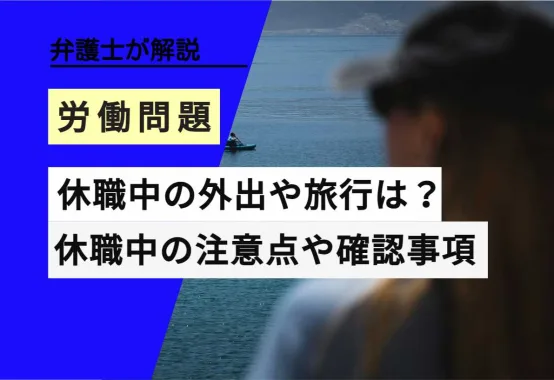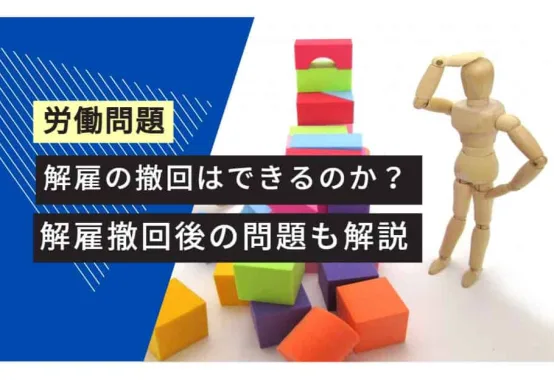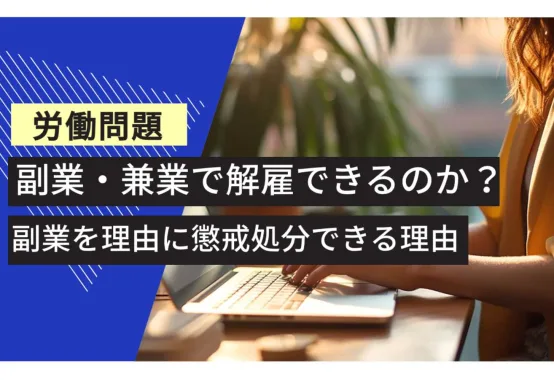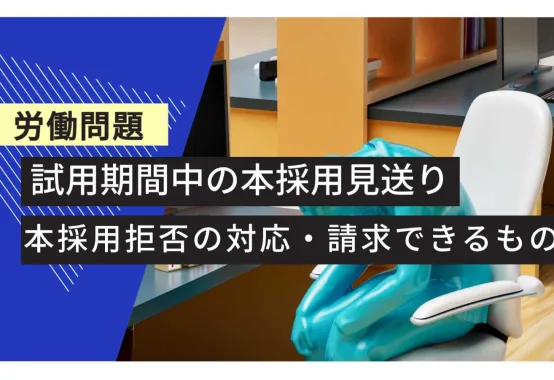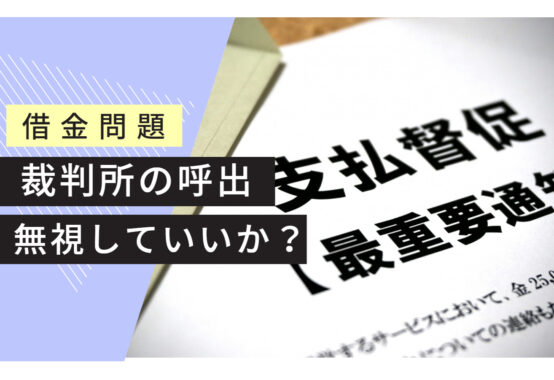退職時に支払われることのある退職金。
しかし、退職金をいざ受け取ってみると、仕事上のミス等を理由に、退職金の金額が減額されていることがあります。
退職金の全部または一部を不支給とすることができる場合とは、長年の功労を抹消できるような重大な事情がなければ認められません。
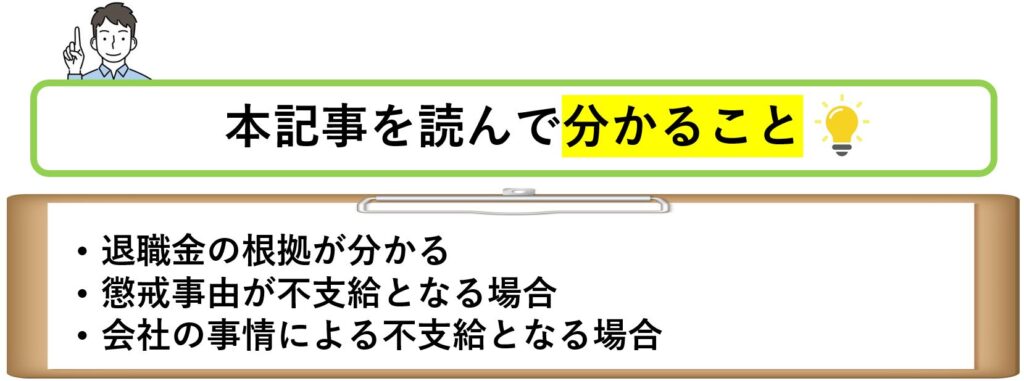
1.退職金の請求根拠
労働基準法上、退職金制度を設けることは会社の義務とされていません。
そのため、労働者は会社に対して、当然に退職金の支払いを求めることはできません。
会社が労働者に対して退職金の支払義務を負うためには、退職金の支払が雇用契約の内容となっていることが必要です。
1-1.退職金規定(就業規則)
具体的には、退職金規定等の就業規則にて退職金の支払条件について詳しく定められている場合です。
ただ、退職金規定があれば「それでOK」というわけではありません。
退職金の規定が具体的な計算方法が定められていることが必要です。
具体的な計算方法が明記されておらず、会社の業績等に応じて算出するような場合には、退職金の根拠としては不十分といえるでしょう。
1-2.雇用契約で規定
就業規則等に退職金の規定がないとしても、会社と労働者との間で個別に退職金の合意をすれば、退職金の支給は雇用契約の内容となります。
1-3.労使慣行がある場合
就業規則もなければ、雇用契約書にもその定めがない場合には、会社は従業員に対して退職金を支払う義務を負いません。
しかし、これらの規定がなくても、会社が一定の退職金の算定基準に基づいて退職金を支給する取扱いが繰り返されている場合には、その取扱いが労使慣行として雇用契約の内容となることがあります。


2.退職金を減額できるのか?
退職金が契約内容となっている場合、会社は、様々な理由で退職金を減額したり、不支給とすることはできるのでしょうか。
2-1.懲戒解雇を理由とする場合
退職金には、会社への功労に報いる役割もあります。
そのため、懲戒事由が存在し、それが会社への功労を無にするような事情である場合には、退職金の全部又は一部を不支給とすることも認められます。
2-1-1.不支給の規定があること
しかし、退職金には、賃金の後払いとしての役割もあります。
そのため、懲戒事由等の非違行為が少しでもあれば、退職金の全部又は一部を不支給とすることができるとなれば、従業員の受ける不利益は大き過ぎます。
そこで、退職金の不支給とするためには、まずは退職金を不支給とする規定が存在することが必要です。
ただし、退職金不支給の定めがなかったとしても、懲戒事由の重大さ等を踏まえて退職金の全部または一部の不支給が認められるケースもあります。
2-1-2.不支給の適用は限定的
退職金は、「賃金の後払いとしての役割」と「会社に対する功労に報いる機能」を果たしています。
そのため、懲戒事由があれば、ただちに退職金を不支給とすることは認められません。
退職金の不支給が認められるためには、これまでの勤続の功労を抹消したり、これを減少させるような著しい背信行為がある場合に限りで、退職金の全部または一部の不支給が認められると解されています。
このように、退職金の不支給の場面はかなり限定されており、懲戒解雇が有効であるからといって、常に退職金を不支給とできる訳ではありません。
2-1-3.懲戒事由を理由に一部不支給が認められたケース
小田急電鉄事件(東京高判平15.12.11)
- 私生活上の痴漢であり会社の社会的評価は毀損されていない
- 20年余りの勤務態度が非常に真面目であったこと
- 退職金の3割
ヤマト運輸 事件(東京地判平19.8.27)
- 帰宅途中の酒気帯び運転
- 退職金の3分の1
日本郵便株式会社事件(東京高判平25.7.18)
- 私生活上の酒気帯び運転
- 退職金の約3割
2-2退職後に懲戒事由が判明した場合
在職中に分からなかった懲戒事由が退職後に分かった場合、これを理由に退職金の全部又は一部を不支給とすることはできるのでしょうか。
2-2-1.懲戒解雇を要件としている場合
退職金の不支給に関する規定が、『懲戒解雇した場合には、退職金の全部または一部を支給しない。』といった内容である場合、懲戒解雇せずに退職している場合には、懲戒解雇による離職ではない以上、退職後に発覚した懲戒事由を理由とした退職金の不支給はできない可能性があります。
2-2-2.懲戒解雇を要件としていない場合
退職金の不支給の規定が、『懲戒解雇に相当する事由がある場合には、退職金の全部または一部を支給しない。』といった内容である場合には、退職後に判明した懲戒事由を理由に退職金の不支給とすることができます。
既に退職金の支払いが済んでいる場合には、その返還を求めることも可能です。
ただ、この場合も同様に、懲戒事由があれば当然に減額できるわけではありません。
これまでの功労を無いものとできるだけの著しい背信行為と言える事情であることが必要です。
2-3.会社側の経営不振による減額
まだ退職しておらず、退職金が現に発生していない段階で、会社が就業規則を変更したり、従業員と個別に合意して、退職金を減額することがあります。
2-3-1.個別の同意による変更
個別の同意について、口頭や同意書等を作成すれば、簡単に退職金の減額ができるわけではありません。
退職金は賃金の後払いとしての機能を果たします。
賃金の減額を伴う不利益変更となる以上、たとえ合意書等による同意があったとしても、その同意が従業員の自由な意思に基づくものであることが必要となります。
自由な意思かどうかは、
- 退職金の減額の程度
- 退職金の減額に至った経緯
- 会社から従業員への説明の有無や程度
を考慮して判断されます。
2-3-2.就業規則の変更が必要となることも
個別の同意を得ても、就業規則に退職金の定めがあり、個別の同意内容が就業規則の内容を下回る場合には、個別の同意は無効となります。
そのため、この場合には、就業規則の変更が必要となります。
2-3-3.就業規則の変更
退職金の内容を定めた就業規則を変更して、退職金を減額させる場合も、簡単ではありません。
退職金などの重要な権利に変更をもたらす以上、退職金の減額による不利益を従業員が受け入れることを許容できるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容であることが必要とされています。
たとえば、会社の存続自体が危ぶまれたり、経営危機による雇用調整が予想される状況にあり、会社の倒産や整理解雇による失職を回避するために退職金の減額をするような場合、高度の必要性が認められる可能性があります。
3.自己都合か会社都合か?
自己都合による離職か会社都合による離職かによって、退職金の金額や計算割合を変えていることがあります。
通常は、退職金の金額は、自己都合による離職よりも会社都合による離職の方が大きくなります。
3-1.会社都合の離職とは
会社都合の離職は、解雇(重責解雇を除く)、雇止め、会社の退職勧奨を受けた退職が該当します。
3-2.自己都合の離職とは
自己都合による離職とは、自発的な退職届の提出をした場合、雇用期間の満了により契約が終了したような場合です。
3-3.判断基準
自己都合か会社都合かは、形式に判断しません。
つまり、従業員が退職届を提出していれば必ず自己都合による離職になるわけではありません。
- 勤務を継続することに支障があったか
- その支障が会社によって生じたものか
- 退職の理由が会社側の原因によるものか
などを考慮して具体的に判断する必要があります。
| 労働審判に関する裁判所の解説はこちら |
4.弁護士に相談しよう
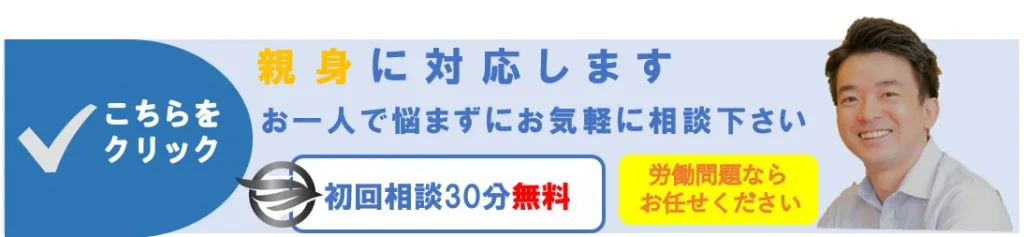
退職金は、退職後の生活を支える重要なお金です。
安易に退職金の金額を減額されてしまうと、従業員やその家族の退職後の生活が脅かされます。
そのため、会社は、退職金を減額するに値する事情があるのかを慎重に判断しなければなりません。
適切に弁護士に相談することが重要です。
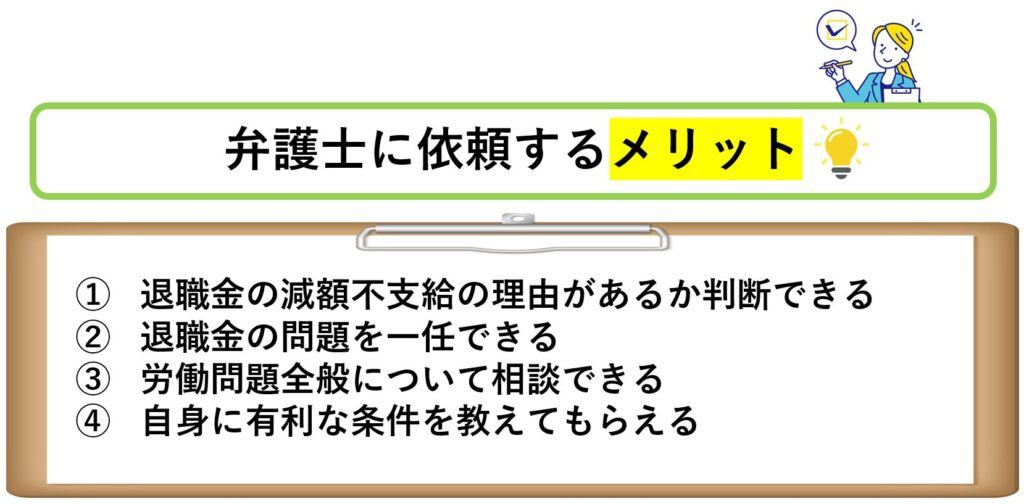
初回相談30分を無料で実施しています。
面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
お気軽にご相談ください。
対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。