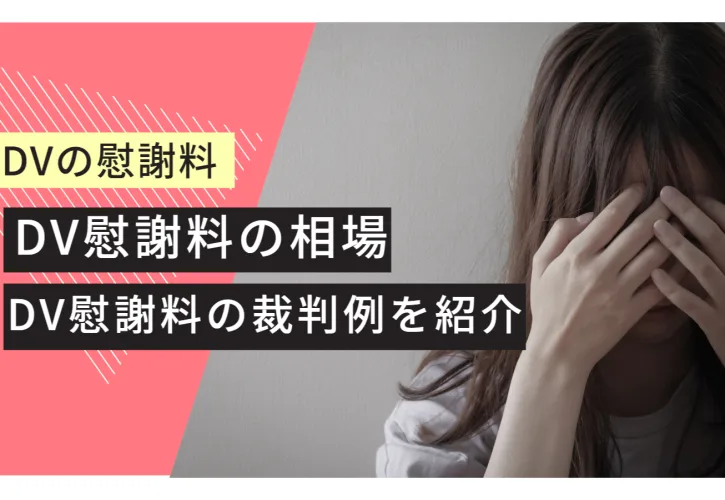DVによる離婚は年々増えています。
女性の離婚原因は、不倫・浮気等の不貞行為よりも暴力を振るうDVの方が多くなっています。
DVを理由とした慰謝料を請求する場合に認められる慰謝料額やDVの証明方法について解説します。
本記事を読んで分かること
- DVの基礎知識
- DV慰謝料額の相場
- DV慰謝料の証明方法
DVの慰謝料額の相場
DVの慰謝料額の相場は、50万円から300万円といわれています。平均額は、123万円といわれています。
DVはドメスティックバイオレンスの略称です。
DVとは、配偶者、もしくは、恋人など親密な関係にある人からの暴力をいいます。
2001年には、DV防止法が制定されました。
DV防止法では、DVを、殴る蹴る等の身体的な暴力だけでなく、無視をする、暴言を吐き続ける等の精神的な暴力、避妊に協力しない、無理矢理性行為を行うといった性的な暴力も含めて定義しています。過激なモラハラもDVと判断される場合があります。
・身体的な暴力
・精神的な暴力
・性的な暴力
DVによって、夫婦関係が破綻し離婚せざるを得なくなった場合には、DVを理由とした離婚慰謝料を請求できます。
また、DVにより怪我をした場合には、通院に伴う治療費や慰謝料を請求できます。
後遺障害の対象となれば後遺症に伴う損害についても請求することはできます。
TIPS!経済的DVとは
経済的DVとは、夫が収入のすべてを管理し、妻に生活費をほとんど与えないような形態のDVをいいます。近年では、この形態のDVも増回傾向となっています。
関連記事|経済的DVとは?経済的DVの対策や離婚への影響を弁護士が解説します

DVの慰謝料額の増額となる事情
離婚慰謝料のうち、主な慰謝料の原因がDV等の暴力の場合、慰謝料の平均額は123万円程度のようです(ケース研究322号神野泰一「離婚訴訟における離婚慰謝料の動向」参照)。
DV慰謝料に関する裁判例を見ていくと、50万円とするケースもあれば、500万円とするケースもあります。
DV慰謝料の金額を考える上では、以下のさまざまな事情を考慮することが多いです。高額の慰謝料額を認容するケースでは、DVが身体的な暴力を伴い、骨折等の重症を負うなど、暴力の程度がかなり苛烈で、単発ではなく長期間に渡って執拗に行われているような事案が多いです。
DVによる怪我の程度・結果
DVにより骨折等の傷害を受けたり、入院を余儀なくされる傷害を受けた場合には、その傷害の結果は、慰謝料の増額事情となります。また、受傷の結果、後遺障害の残存した場合には、それに相応する慰謝料が発生します。
また、傷害を受けていなかったとしても、深刻な精神疾患を罹患したり、自殺未遂を図ったような場合でも、慰謝料の増額事由になり得るでしょう。
DVの態様
DVの態様が、口頭による暴言よりも、殴る蹴るといった有形力を行使する暴力の方が、慰謝料の増額事情になります。
また、配偶者だけでなく、その子どもに対しても暴力を振るったり、妊娠中の妻を殴る蹴るという悪質な態様についても、増額理由となります。
婚姻期間の長さ
夫婦の婚姻期間が長い場合にも、慰謝料の増額理由となります。
DVの責任割合
DVをするに至る経緯に、被害者の配偶者側にも落ち度がある場合には、慰謝料の減額理由となり得ます。
例えば、被害者側が加害者側に対して挑発するような言動、暴言を吐くような場合です。
また、被害者側も暴力を振るったり、暴力に対して応戦するような場合も、減額理由になる可能性があります。
DVの頻度・回数・期間
DVの回数が多い、頻度が高い場合にも、DV慰謝料の増額理由になります。
また、DVの期間が単発ではなく、長期間にわたり継続されている場合には、慰謝料の増額事由となります。
保護命令の有無や逮捕の有無
DV加害者に対して、保護命令が出されていることがあります。
保護命令とは、配偶者からの身体に対する暴力を防ぐために、裁判所が加害者に対して、被害者へのつきまとい等をしてはならないこと等を命ずるものをいいます。保護命令に反する場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
保護命令を受けていることや保護命令に違反していることは慰謝料の増額理由となります。
さらに、保護命令に違反して逮捕された場合にも、さらに慰謝料の増額事由となります。
関連記事|DV防止法とは?保護命令やDV防止法を分かりやすく弁護士が解説します
モラハラがDVとなる場合の慰謝料は?
モラハラが精神的なDVといえる場合には、慰謝料請求することができます。
モラハラは、モラルハラスメントの略称で、倫理や道徳に反する精神的な嫌がらせをいいます。
モラハラが単なる精神的な嫌がらせを超えて、精神的な暴力といえる程に過激なもので、慢性的に行われている場合には、モラハラもDVと言えるでしょう。
ただ、肉体的な暴力とは異なり、言葉による暴力は、形に残りにくく事後的に証明することが困難な場合が多いです。
そのため、DVとも言えるモラハラを理由に慰謝料請求する場合には、録音・録画、日記の作成、カウンセリングや心療内科の通院といった証拠の計画的な収集が大事となります。
DV慰謝料の裁判例
DVを理由とする慰謝料に関する裁判例を紹介します。過去の先例を参照することで、慰謝料額の増減理由となる事情を整理することができます。また、DV慰謝料のために必要となる資料も理解することができます。
100万円以下の事例
【東京地裁平成16年8月25日判決】
| 金額 | 100万円 |
| 事案 |
|
| 判断 | 双方が相手に対する思いやりを欠いたことを指摘し得るものの、夫の暴力等の行為によることが大きいことは否定し得ないとして、慰謝料は100万円が相当である。 |
100万円を超え200万円以下
【東京地裁平成15年2月3日判決】
| 金額 | 150万円 |
| 事案 |
|
| 判断 | 夫の行為等を総合勘案すると、妻の受けた苦痛を慰謝するには、150万円が相当である。 |
【東京地裁平成19年4月11日判決】
| 金額 | 150万円 |
| 事案 |
|
| 判断 | 婚姻関係の破綻が夫の側に一方的な責任があったということはできないこと、ある程度頻繁に暴力を振るうことがあったと推認できるものの、傷害の結果を与える程度の暴力を頻繁に振るっていたという事実を認めることはできないとして、慰謝料150万円の限度で認容した。 |
【神戸地裁平成6年2月22日判決】
| 金額 | 200万円 |
| 事案 |
|
| 判断 | 婚姻期間、夫の暴行の態様,妻の受傷の程度等に鑑みると、本件慰謝料の額は金200万円と認めるのが相当である。 |
200万円を超え300万円以下
【東京地裁平成15年7月10日判決】
| 金額 | 300万円 |
| 事案 |
|
| 判断 | 婚姻関係は、夫の妻に対する暴力行為や妻らに対する執拗な脅迫行為の反復により完全に破綻していること、これら一連の行為により妻が著しい精神的苦痛を受けていること等から、慰謝料として300万円を認定。 |
300万円を超えるケース
【東京地裁平成15年6月11日判決】
| 金額 | 500万円 |
| 事案 |
|
| 判断 | 婚姻関係は、夫の妻に対する暴力行為や妻らに対する執拗な脅迫行為の反復により完全に破綻していること、これら一連の行為により妻が著しい精神的苦痛を受けていること等から、慰謝料として300万円を認定。 |
DVを証明できる証拠を確保する
DVを理由とした慰謝料請求をするためには、DVの存在を客観的な証拠により証明することが重要です。
客観的な証拠により、DVの存在だけでなく、その怪我の程度やDVが行われた期間を証明することができる場合があります。
DV被害の泣き寝入りをしないように、証拠集めを計画的に行いましょう。
DVの証明する証拠
- 傷跡の写真
- 医療記録
- DVの動画や写真
- 日記
- メールやライン
- 警察等への相談記録
- 陳述書
傷痕の写真
配偶者から身体的な暴力を受けた場合には、その受傷した部位を写真や動画の撮影を行うようにします。
傷痕の写真によって、暴力を受けたことやその暴力の程度を証明することが可能です。
診断書等の医療記録
医療機関の通院履歴や受傷内容を裏付ける資料として、診断書や診療録があります。
医療記録には、被害者が訴える症状や怪我をするに至った経緯が詳しく記載されていることがあります。
また、受傷内容や程度(骨折、全治○○週間等)も確認することができます。
DVの動画や写真
DVを行なっている時の動画、録音もDVの証明方法として有効です。
DVが行わられる場合、人格非難するような暴言を吐いたり、物を撒き散らすことがよくあります。
DVの様子を動画や録音することができれば、DVの内容を具体的に証明することが可能となります。
日記の作成
DVの詳細を記載した日記もDVの証明方法になります。
ただ、日記の内容はできる限り具体的に記載し事実を記載するようにします。
また、過去の分をまとめて記載することは控えます。
できる限り記憶が新鮮なうちに、DVを受けた都度日記に記載するようにします。
メールやライン
DVの被害を受けている場合、家族や友人に相談していることがあります。
家族等への相談をメールやラインでしている場合には、そのメールやラインメッセージを証拠として提出することでDVを証明できる場合があります。
また、家族や友人に相談していない場合でも、自治体の運営するDVの相談窓口に相談していることもあります。
この相談窓口への相談履歴がDVの裏付けとなる場合があります。
警察等への相談記録
配偶者からの暴力が収まらず、身の危険を感じた場合、警察に通報することもあるでしょう。
また、警察に、配偶者のDV被害を相談することもあるでしょう。
この警察への通報記録や相談記録は、情報公開手続や弁護士会照会等の手続を利用することで開示してもらうことができます。
陳述書の活用
DVの客観的資料を十分に確保しておくことは容易ではありません。
しかし、これら客観的な資料が十分になくても諦める必要はありません。
被害者本人が記憶に基づいて具体的なエピソードを記載した陳述書を提出することで、DVを証明できる可能性があります。
いつ、どこで、どのような経緯で、どのような暴力を、どの程度受け、その結果どのような怪我を負ったのかを具体的にエピソードを多く挙げて丁寧に陳述してください。
陳述書の内容と当事者尋問の供述内容が真に迫るもので、先後に矛盾のない整合されたものであれば、DVの事実を認定される可能性は十分にあります。
関連記事|離婚調停の陳述書の書き方とは?陳述書の目的・注意点や文例
✓裁判所のDVに関する解説はこちら
証拠の確保は難しい
DVの被害を受けている状況下で、DVの証拠を冷静になって計画的に収集しておくことは簡単ではありません。
先ほど解説したように、DVの証拠としては、傷跡の写真や診断書、暴力の内容を綴った日記、暴力や暴言を受けている際の動画や録音です。
DVを受けている当時から、将来の裁判を予期して、計画的にDVの証拠を保全することは可能かもしれません。
しかし、暴力を受けている当時、自らが裁判沙汰に巻き込まれるとは思いもしません。
また、DVを受けている被害者は、加害者によって精神的なコントロールをされていることも多く、証拠を確保しようと考える余裕・気力が生まれないこともあります。
その上、配偶者による暴力は、前触れなく突然起こることがほとんどです。
突然のことのため、咄嗟に記録する余裕がないこともあります。
また、DVにより骨折等の通院を必要とする怪我をすれば別ですが、これまでに至らない怪我であれば、通院を控えることもよくあります。
このような理由から、事前にDVに関する証拠を収集することができないため、DVの証明も難しくなる場合がよくあります。
証拠保全のポイント
証拠を収集しておいても油断は禁物です。
何らかの拍子で、その証拠の存在を配偶者に知られてしまうと、配偶者によって証拠を破壊されたり隠されたりすることがあります。
せっかく確保した証拠が台無しとなってしまいます。
そこで、証拠を廃棄されないように、親族や友人に預けたり、証拠のデータをクラウドサーバーやUSBメモリー等で保管するようにしましょう。
DV慰謝料を請求する流れ
DVの慰謝料請求をする場合、被害者と加害者の夫婦関係は破綻していることがほとんどです。
そのため、DVの慰謝料請求は離婚時に行われることが多いです。そこで、DVの慰謝料請求は、①離婚協議、②離婚調停、③離婚裁判の各手続きを通じて、行われることになります。しかし、いろいろな理由から離婚手続きを先行させた上で、離婚成立後にDV慰謝料のみを調停や訴訟を通じて行うこともあります。
離婚協議
離婚協議は難航することが多いでしょう。
離婚協議とは、加害者と被害者の夫婦間で、DV慰謝料も含めた離婚条件を協議し、離婚の話し合いを進めていくプロセスです。
しかし、DV加害者は、自身の行為がDVであるとの自覚を持たないことも多く、被害者に対して責任転嫁することも多々あります。そのため、当事者間の離婚協議は困難を極めることが多いです。
また、被害者本人の直接の協議は、DV被害を深めるリスクもあります。
そのため、DV慰謝料も含めた離婚協議を行う場合には、まず確実に別居を行い退避します。子供のいる夫婦であれば必ず子供を連れて別居するようにします。相手方のつきまといが激しい場合には、保護命令の申立ても行います。
また、被害者本人による協議は回避し、できる限り弁護士等の第三者を通じた交渉を行うことで自身に有利な条件で協議を進めるようにします。
離婚調停
離婚調停は、裁判所の仲裁による話し合いですから、DV慰謝料も含めた離婚条件の合意を見込めます。
離婚調停とは、家庭裁判所の裁判官と調停委員2人で構成される調停委員が夫婦を仲裁して、離婚の成立を実現させる手続きです。
離婚調停では、調停委員が当事者双方から、その言い分を聞き取りますが、当事者双方が入れ替わりで調停室に入室しますから、当事者が顔を合わせることは基本的にはありません。
調停手続を経て、慰謝料や財産分与等の離婚条件が調整できれば離婚調停が成立します。
しかし、調停手続きを経ても、合意に至らない場合には、調停は不成立となります。
なお、離婚調停に際しては、婚姻費用を請求し忘れないように注意します。
離婚裁判
離婚裁判は、離婚を求める当事者が家庭裁判所に対して、訴訟を提起することで開始されます。
離婚裁判では、当事者双方が、主張・反論とこれを裏付ける証拠の提出を繰り返しますので、調停手続きのような話し合いの要素はそれほど強くありません。
当事者双方の主張反論を経た上で、当事者双方の当事者尋問の結果を踏まえ、裁判官は判決を下します。
ただ、離婚裁判においても、当事者双方が主張反論を尽くした段階で、裁判官による和解勧告が行われます。和解勧告の結果、裁判上の和解が成立するケースも多くあります。
TIPS!DVは離婚原因になる
民法には、次の5つの離婚原因が定められています。
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④回復の見込みのない強度の精神病
⑤婚姻を継続しがたい重大な事由
これらのうちDVは、最後の⑤に該当する可能性がある離婚理由となります。
DV慰謝料が支払われない時の対応
調停手続きや訴訟手続きを通じて、DV慰謝料の支払義務が確定したとしても、相手方がその支払いに応じないことは往々にしてあります。
この場合には、相手方の財産を差押えたり、差押えを行うための財産開示や第三者からの情報取得手続きを活用します。
差押えを行う
調停調書や確定判決がある場合には、これを根拠に、DV慰謝料の支払義務者の財産を差し押さえることができます。調停調書や確定判決を「債務名義」といいます。これらのほかにも、強制執行認諾文言付の公正証書も債務名義となります。
差し押さえるできる相手方の財産は、預貯金、不動産、生命保険の解約返戻金といった相手方名義の財産一切です。これに加えて、相手方が勤務先に有している給与債権も差押えの対象となります。
ただし、給与債権の差押えは、給与の手取収入額の4分の1に制限されます。
相手方の財産状況を把握する
義務者の財産状況を把握し、差押えの実効性を確保するために、財産開示・第三者からの情報取得・弁護士会照会といった各制度を利用します。
DV加害者の財産を差し押さえるためには、DV加害者の財産の具体的な情報が必要となります。
特に、預貯金の口座を差し押さえるためには、金融機関名だけでなく支店名の特定まで必要となります。
時間や労力をかけてDV慰謝料の債務名義を取得したにもかかわらず、その内容を実現できなければ、その債務名義は絵に描いた餅となります。
そこで、判決や調停の内容を実現するため、裁判所を通じた手続きである財産開示と第三者からの情報取得の各手続きを利用します。また、弁護士会を通じて、金融機関から、口座の有無や残高に関する情報を収集します。
DV慰謝料の消滅時効に気を付ける
DVの慰謝料請求にも「時効」があります。いつまでも請求できるわけではありません。放置をすると、消滅時効により請求できなくなるリスクがあります。
慰謝料は離婚時から3年
DVを理由に離婚した場合、被害配偶者は加害配偶者に対して離婚慰謝料を請求することができます。
DVを原因とする離婚慰謝料は、離婚時から「3年」の消滅時効となります。あくまでも離婚慰謝料の請求ですから、DVを原因とする治療費や後遺障害に関する損害賠償については、扱いを異にします。
DVの損害賠償は3年または5年
DVのうち身体的暴力による場合、身体を侵害する不法行為ですから不法行為の時から「5年」の時効となります。他方で、身体的暴力ではないDVの場合や身体を侵害しない場合には、3年の時効となります。
離婚時から6か月は完成猶予される
婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、夫婦の一方から他方に対する権利の時効は完成しません。そのため、離婚成立まで、DVの損害賠償請求権が時効により消滅することはありません。
DVの慰謝料の問題は弁護士に相談しよう

DVを根拠とする慰謝料請求をするためには、計画的に証拠を収集することが重要です。
その上で、この証拠を基に、DVが如何に深刻なもの、被害者の心に深い傷を負わせたかを説得的に説明していくことが非常に大事です。
DVで悩んでいる場合、1人で抱えがちです。
しかし、抱えれば抱えれる程、事案は深刻化し、証拠を収集する機会も失います。
ご自身で頑張り過ぎずに、適切に弁護士に相談することが重要です。
弁護士に依頼するメリット
DVの証拠を計画的に収集できる
DV被害の対処法を相談できる
DVの証拠を基に精神的苦痛の重大さを説明できる
慰謝料請求の手続を一任できる
離婚手続全般について相談できる
初回相談30分を無料で実施しています。
面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
お気軽にご相談ください。
対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。