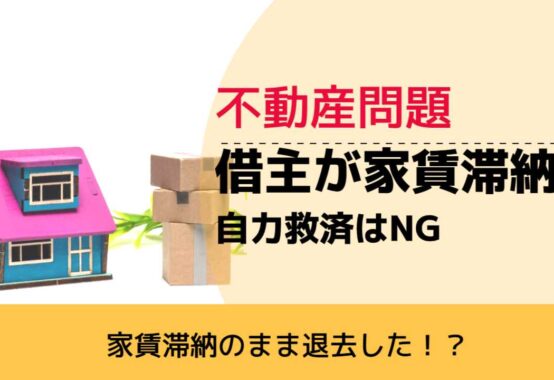サブリース契約は、安定した賃料収入を見込めるというメリットがある一方で、家賃保証額の減額やサブリース業者からの解約による空室リスクなど、オーナーにとって不利益が生じるケースも少なくありません。
「サブリース契約を結んだけど、どうも話が違う…」
「解約したいけど、本当に解約できないのだろうか?」
このようなお悩みを抱えていませんか?
サブリース契約であっても、普通の賃貸借契約と同様に解約が難しいのも事実です。しかし、諦めるのはまだ早いです。本記事では、サブリース契約の解約が難しい理由から、具体的な解約手順、そして注意点までを徹底的に解説します。
なぜ?サブリース契約の解約が難しいと言われる2つの大きな理由
サブリース契約は、「空室が出ても家賃収入が得られる(空室保証)」や「入居者管理の手間がかからない」といった利点から、多くの不動産オーナー様にとって魅力的に映る選択肢です。しかし、その手軽さの裏側には、オーナー側から契約を解除することが難しいという側面もあります。想定外の家賃減額やトラブルが発生した場合でも、なぜ容易に契約を解消できないのでしょうか。
理由1:「借地借家法」でサブリース会社が法的に守られているため
サブリース契約において、不動産オーナーは「貸主」、サブリース会社は「借主」という立場になります。このサブリース契約にも借地借家法が適用されます。サブリース契約の場合、賃借人は事業者であるサブリース業者となりますが、最高裁の判例によればサブリース契約であっても借地借家法の適用対象となります。
これにより、サブリース会社の権利が法律によって強く保護されることになります。すなわち、借地借家法第28条では、貸主から賃貸借契約の解約を申し入れる場合や更新拒絶をする場合、「正当の事由」がなければならないと定められています。つまり、オーナーがご自身の都合だけでサブリース契約を一方的に解約しようとしても、法的に認められるためには、この正当事由が必要となります。たとえ賃貸借契約がサブリース契約であっても、その一事のみで容易に正当事由が認められるものではありません。その上で、オーナーがやむを得ず解約を申し出る場合、サブリース業者から、高額な違約金の支払いを求められることも少なくありません。これが、サブリース契約の解約が難しいと言われる大きな理由の一つです。
理由2:契約書にオーナーにとって不利な解約条項が盛り込まれているため
サブリース契約の解約を困難にしているもう一つの大きな要因は、契約書そのものに潜んでいます。多くのサブリース契約書には、オーナー側からの中途解約を原則として認めない条項を設ける、あるいは、そもそも中途解約の規定を設けていない場合があります。
さらに、契約期間が10年を超えるような場合で、かつ、中途解約の条項がない場合には、サブリース業者の債務不履行がない限り、中途解約すらできない事態となります。中には、契約期間を30年とする長期のサブリース契約もあります。
これらの不利な条項は、契約時に十分な説明がなされないままサインに至るケースもあります。そのため、サブリース契約を締結する際は、契約書の内容を安易に信用せず、隅々まで確認することが非常に重要です。


「こんなはずでは…」サブリース契約でよくあるトラブル事例
サブリース契約は、「家賃保証」「空室リスクなし」といったメリットが強調され、魅力的な選択肢のように提示されることもあります。しかし、その言葉の裏には、オーナーにとって想定外のトラブルが潜んでいるケースも少なくありません。以下では、多くのオーナーが実際に経験した代表的なトラブル事例を具体的にご紹介し、注意すべき点を詳しく解説していきます。
一方的な家賃の減額を要求される
サブリース契約の魅力として「家賃保証」が挙げられますが、多くの契約において、この保証は永続的なものではありません。
契約書には通常、「経済情勢や近隣の家賃相場の変動に応じて、賃料を見直すことができる」といった条項が含まれています。
特に、契約から数年が経過し、契約更新のタイミングなどで、サブリース会社から周辺家賃の下落や空室率の上昇といった理由で、一方的な保証賃料の減額を求められるといったトラブルが最も多く発生しています。
オーナーが賃料減額請求に応じない場合、サブリース会社は借地借家法第32条に基づく「借賃増減請求権」を根拠に、減額の正当性を主張してきます。交渉でも合意に至らなければ、調停や訴訟といった法的手続きに打って出てくることもあります。さらには、賃料減額に応じない場合には賃貸借契約の解約申入れを示唆されるなど、オーナー側が交渉において不利な立場に立たされやすく、結果として不本意な条件を受け入れざるを得なくなる状況が見られます。
高額な修繕費用を請求される
サブリース契約では、物件の維持管理にかかる費用負担を巡るトラブルも多く報告されています。例えば、転借人の退去時における原状回復工事やリフォーム工事に際して、これを賃貸人であるオーナー負担とした上で、サブリース業者が工事業者を指定するといった契約内容となっていることも少なくありません。
そのため、オーナーが他の工事業者からの相見積もりを取ることすら認めず、市場価格よりも著しく割高な工事費用の負担を強いられるといったトラブルも発生しています。
サブリース会社の倒産で賃料が途絶える
万が一サブリース会社が倒産した場合、それまで約束されていた家賃の支払いが途絶えてしまうという深刻な事態に直面する可能性があります。
オーナーと入居者との間には直接の賃貸借契約がないため、サブリース会社が倒産しても、オーナーがすぐに入居者から直接家賃を回収することは困難になります。さらに、入居者様がサブリース会社の倒産を知らず、これまで通り倒産した会社の口座に家賃を振り込み続けてしまう可能性もあります。
諦めるのはまだ早い!サブリース解約が認められやすくなる「正当事由」とは
前述の通り、サブリース契約においてサブリース会社は借地借家法により借主として保護されており、オーナーからの一方的な解約は原則として認められません。
しかし、法律で定められた「正当事由」があると裁判所に判断された場合に限り、オーナーからの解約が認められる可能性があります。
以下では、正当事由として認められやすい具体的なケースや、過去の判例について詳しく解説します。
正当事由とは何か?
賃貸人による更新拒絶や解約の申入れには、正当事由が具備されていなければ認められません(借地借家28条)。
正当事由の判断基準として、借地借家法28条は以下の事情を掲げています。
- 賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情
- 建物の賃貸借に関する従前の経過
- 建物の利用状況及び建物の現況
- 賃借人に対する財産上の給付
正当事由の判断においては、当事者双方の建物使用を必要とする事情が基本的要素となり、その他の事情は付随的な要素となります。そのため、貸主側の建物使用の必要性がない、または、非常に低い場合には、たとえ高額の立退料を提示したとしても、正当事由は認められないことになります。
正当事由として認められる可能性のあるケース
サブリース契約の解約に必要となる「正当事由」は、オーナーとサブリース会社双方の事情を総合的に比較考慮して判断されます。
サブリース契約では、共同事業としての側面があるため、契約締結に至る経緯や履行状況、当事者双方における投資と収益の均衡、双方当事者の契約存続に対する期待及び保護の必要性、サブリース業者の実績などを踏まえながら、各要素を判断するケースもありますが、サブリース契約であることを重要な要素と捉えないケースもあります。例えば、サブリース契約には、建設受注・管理一体型、販売・管理一体型、借上管理型がありますが、前二者の形態では、サブリース業者は賃料収入だけでなく、建設や販売によって収益を得ており、他方で、借上管理型では、サブリース業者の収益は賃料差益のみです。そのため、正当事由を判断するにあたっては、サブリース業者の収益の大きさやオーナーの収益との均衡を踏まえて判断することもあります。
サブリース契約における貸主側の自己使用の必要性については、保証賃料が低下し投下資本を回収するために別のサブリース業者を選定する必要がある場合や自宅の修繕費を確保するためにサブリース物件を売却する必要がある場合などが挙げられます。
また、正当事由を判断する上で、転借人の利益も考慮する必要があるため、サブリース契約において、サブリース業者との契約が終了しても、転借人との賃貸借契約をオーナーが承継した上で、引き続き転借人が使用を継続できるような合意をしている場合には、通常よりも正当事由が認められやすくなるのではないかと考えます。
これらの事情だけでは正当事由を充足するに十分でない場合には、オーナーからサブリース会社への一定額の立退料提供が、正当事由を補完する要素となり得ます。
しかし、単に保証賃料が低いといった事情だけでは、賃貸人側の自己使用の必要性が低いと捉えられ、正当事由が否定されるケースも多くあります。
裁判例から見るサブリース契約の正当事由
サブリース契約の解約において、オーナー様の事情だけでは「正当事由」として認められないケースも少なくありません。
実際の裁判例においても、このようなオーナーの主張が退けられた事例が見られます。
以下で紹介する裁判例からもわかる通り、裁判所は様々な事情を総合的に考慮するため、サブリース契約の解約は容易ではないと言えます。
札幌地方裁判所平成21年4月22日
サブリース契約であること自体が、正当事由を認める方向での独立の考慮要素となるものではないとした上で、サブリース業者がオーナーに支払う賃料をはるかに上回る収益をテナントから得ていても、サブリース契約において想定される範囲内のことであることから、これを正当事由の根拠とすることはできないとして、正当事由を否定しました。
東京地方裁判所平成24年1月20日
オーナーがサブリース業者に対して期間満了に伴い更新拒絶をしましたが、オーナー側に正当事由がないと判断した事例です。
まず、オーナー側はサブリース契約を終了させて、より高額の賃料を得たいというものであるところ、これは賃料増額請求権の行使等を通じて将来に向かって増額させることも可能である上、サブリース業者において本件建物の使用に関して支障を生ずるなどの特段の事情があったとはいえず、オーナーはサブリース業者から月々の約定の賃料を得られている以上、建物使用の必要性は低いとしました。
他方、サブリース事業によるサブリース業者の固有の利益に加えて、転借人の建物使用の必要性も踏まえると、サブリース業者の建物使用の必要性があるとして、オーナーの正当事由を否定しました。
東京高等裁判所判決平成14年3月5日
オーナーの正当事由を肯定した事例です。
この事案では、サブリース契約に、オーナーとサブリース業者との賃貸借が終了する場合でも、転貸借契約をオーナーが承継し、転借人が使用を継続できる合意を含んでいました。
そのため、転借人の承継に関する合意があるため、転借人の保護が図られているので、オーナーがサブリース業者に対して解約申入れることの正当事由が肯定されると判断しました。
東京地方裁判所平成23年6月9日
オーナー側がサブリース業者の債務不履行などを理由として更新拒絶について、裁判所は正当事由を否定しました。
まず、オーナー自らが管理する必要があるとの主張については、自己使用の必要性と評価できないとし、サブリース業者が高収入を得ていることも正当事由にはならないとした上で、オーナーの主張する債務不履行の事実について違法不当ではないなどと判断しました。
他方で、サブリース業者は、本件建物の5階を自ら使用し、かつ1階から4階部分をテナントに転貸してサブリース事業の収入を得ており、サブリース業者にとって建物の使用を継続する必要性は相当大きいとし、更新拒絶につき正当事由の存在を否定しました。
東京地方裁判所平成25年3月21日
オーナーが、契約の期間満了に伴い更新拒絶をし、その正当事由が認められた事案です。
裁判所は、本契約が、投資家であるオーナーとサブリース業者との間の共同収益事業という複合契約的な側面があることから、正当事由を判断する上で、契約締結に至る経緯、契約の履行状況、当事者双方における投資と収益の均衡、双方当事者の契約存続に対する期待及びその要保護性の程度、サブリース業者の実績などを評価し、契約実態に即応した形で、自己使用の必要性、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況、補完要素としての立退料等の提供といった要素を考察するのが相当であると判断しました。
その上で、保証賃料が下がる中で投下資本の回収のため自らの希望するサブリース業者を改めて選定をしたいという原告の自己使用の必要性があること、反面、サブリース業者においては契約更新を繰り返し、3回の更新を経るなど回数を重ね、収益を上げることで自己使用の必要性が相対的に低くなったということはできること、転借人の居住権には影響が出ないことなどを踏まえて、更新拒絶には正当事由があるたしました。
東京地方裁判所平成27年8月5日
オーナーが、老後のためのまとまった資金を得るため本件建物を空室の状態で第三者に売却する必要があるとして、期間満了又は解除を理由に建物の明渡し等を求めた事案です。
オーナーの居住する自宅は築60年を超える老朽化した木造草ぶき平家建の建物であり、その補修改築のためにまとまった資金を必要としていること、その資金を確保するために、本件建物を可能な限り高額で売却するために、賃借人、転借人のいない空き家の状態で本件建物を売却する必要があること、他方、被告は、本件建物を賃貸(転貸)して賃料を得ているにすぎず、業者側にとっても本件建物を使用する強い必要性があるわけではないことから、相当額の立退料を支払わせることで、正当事由を補完することができるとしました。
サブリース解約を進めるための具体的な5つのステップ
これまで、サブリース契約の解約がなぜ難しいのか、また、解約を認められる可能性のある「正当事由」について解説してきました。
以下では、実際にサブリース契約の解約を進めるにあたり、オーナーが取るべき具体的な行動を、時系列に沿って5つのステップに分けて詳しく解説します。具体的には、以下の順で見ていきます。
- ステップ1:サブリース契約書の内容を再確認する
- ステップ2:内容証明郵便で解約通知書を送付する
- ステップ3:サブリース会社との交渉に臨む
- ステップ4:交渉が難航する場合は専門家へ相談する
- ステップ5 : 調停申立や訴訟提起を進める
ステップ1:サブリース契約書の内容を再確認する
サブリース契約の解約に向けた第一歩は、お手元にある契約書の内容を正確に理解することです。これは、サブリース会社との交渉を進める上で最も基本的な土台となります。
感情的に要求を伝えるのではなく、法的な根拠に基づき、契約書の内容を正確に理解した上で、計画的に行動することが重要です。
特に重要なのは、「中途解約に関する条項」です。オーナーからの解約申し入れが可能であるのか、いつから可能なのかといった規定が定められているかを確認します。また、解約に伴う違約金の有無やその算出方法についても、詳細に確認しておく必要があります。
中途解約条項だけでなく、今後の交渉で論点となる可能性のある項目も漏れなくチェックしましょう。確認すべき項目は以下の通りです。
- 契約期間と自動更新の有無
- 家賃の改定(減額)に関する具体的な条件
- 原状回復や大規模修繕における費用負担の割合
これらの条項は、トラブル事例でもご紹介した家賃減額や修繕費用の請求に関わる重要な部分です。契約内容を正確に把握することが、次のステップへ進むための鍵となります。
ステップ2:内容証明郵便で解約通知書を送付する
サブリース会社との交渉に臨む前に、まずは解約申入れや更新拒絶の意思を正式に伝える必要があります。この際、普通郵便ではなく、内容証明郵便を利用することが極めて重要です。内容証明郵便は、「いつ、誰が、どのような内容の文書を誰に送ったか」という事実を郵便局が公的に証明してくれる制度です。これにより、「通知を受け取っていない」といったサブリース会社からの言い逃れを防ぎ、法的な証拠を残すことができます。
通知書には、契約を終了させる意思を明確に示すとともに、以下の項目を具体的に記載しましょう。
- 物件の所在地や名称など、特定の情報
- 契約当事者であるオーナー様とサブリース会社の氏名または名称、住所
- サブリース契約を解約する、または、更新拒絶する旨の明確な意思表示
- 解約や更新拒絶の正当事由の内容
内容証明を送付する際には、相手が通知書を受け取った事実を証明できる「配達証明」を併せて利用することを強く推奨します。これにより、解約通知が相手に到達したことの確実な証拠が得られます。
ステップ3:サブリース会社との交渉に臨む
内容証明郵便で解約通知書を送付した後、多くの場合、サブリース会社から連絡があり、直接交渉の場を持つことになります。
この段階は、契約解除を実現するための山場と言えるでしょう。交渉に臨むにあたっては、感情的にならず、冷静かつ論理的に進めることが非常に重要です。事前に準備した「正当事由」を改めて整理し、正当事由に関する具体的な証拠を手元に用意しておきましょう。
交渉の場では、これらの証拠を提示しながら、サブリース契約を継続することが困難である理由や、オーナーにとって不利益が大きい状況を具体的に説明します。ただし、一方的な主張を繰り返すのではなく、サブリース会社側の言い分にも耳を傾ける姿勢を見せることも大切です。
交渉が長期化したり、双方の主張に大きな隔たりがあったりする場合には、解決金(立ち退き料や違約金の一部相当額など)の支払いを条件に、早期の合意を目指すことも選択肢の一つです。
ステップ4:交渉が難航する場合は専門家へ相談する
サブリース会社との直接交渉が進展しない、あるいは交渉に応じてもらえない場合は、次の段階として弁護士への相談を検討しましょう。
弁護士に相談・依頼する主なメリットは以下の通りです。
- 正確な法的知識に基づいた的確なアドバイス
- 代理交渉による冷静な話し合いと精神的・時間的な負担軽減
- 過去の事例を踏まえた戦略的な交渉
弁護士は借地借家法をはじめとする関連法規に基づいた正確な知識を持っているため、オーナーが主張できる正当事由や、契約書に盛り込まれた不利な条項の有効性などについて、法的な観点から的確なアドバイスを得ることができます。
また、弁護士であれば、オーナーの代理人としてサブリース会社と交渉できるため、感情的な対立を避けて冷静に話し合いを進めることができます。これにより、精神的・時間的な負担が大幅に軽減されます。さらに、過去の事例や判例も踏まえ、より有利な条件での解約を目指して戦略的に交渉を進めてもらうことも期待できます。
弁護士への相談や委任は、単なるアドバイスにとどまらず、必要に応じて調停や訴訟といった法的措置も視野に入れた具体的なアクションへの準備となります。交渉が難航したと感じたら、一人で抱え込まず、早期に弁護士の助言を仰ぐことが、問題解決への近道となるでしょう。
ステップ5:調停申立てや訴訟提起をする
サブリース会社との交渉が進展しない場合には、次のステップとして、調停申立てや訴訟提起をすることを検討します。
調停手続きは、簡易裁判所の調停委員が当事者双方を仲裁することで話し合いによる解決を目指すプロセスです。あくまでも話し合いの場となるため、裁判所による最終的な判断が示されることはありません。
他方で、訴訟手続きは、当事者双方が主張と立証をそれぞれ繰り返すことで審理を深めていき、最終的に裁判所が終局的な判断を示すプロセスとなります。
サブリース業者との交渉状況を踏まえて、話し合いによる解決の余地があれば、調停の申立てをすることを検討します。一方で、十分な正当事由がある場合や交渉の余地がない場合には、訴訟提起を進めることもあるでしょう。
解約前に必ず確認!知っておきたい3つのリスクと注意点
サブリース契約の解約を目指す際は、単に手続きを進めるだけでなく、いくつかの重要なリスクや注意点を事前に認識しておく必要があります。
以下では、サブリース契約の解約前に必ず確認しておきたい、具体的な3つのリスクと注意点について詳細に解説します。
高額な違約金や立退料を請求される可能性がある
サブリース契約書には、オーナーが契約を解約する際に、高額な違約金に関する定めが盛り込まれているケースが多く見られます。
この違約金は、サブリース会社が契約期間中に本来得られたはずの利益(逸失利益)を補填することを目的としています。また、正当事由が不十分である場合には、サブリース会社から高額な立退料を求められるケースも少なくありません。
不当な請求には安易に応じず、必ず弁護士へ相談し、アドバイスを求めることが重要です。
交渉が長期化し、精神的・時間的負担がかかる
サブリース契約の解約交渉は、数ヶ月から1年以上と長期に及ぶケースも少なくありません。特にサブリース会社が解約や条件変更に消極的な場合、話し合いが平行線をたどりやすく、解決が見えない状況が続きがちです。
このような長期化は、オーナー側にとって大きな精神的な負担となります。いつ解決するのか分からない不安や、不動産のプロであるサブリース会社を相手に、専門知識のない立場で交渉を進めることによる心理的なプレッシャーは、計り知れないものがあるでしょう。
また、交渉のためには、サブリース会社との打ち合わせに加え、さまざまな準備に時間を割く必要があります。これらを本業や日常生活の傍らで行うことは、想像以上の時間的な負担となります。特に遠方の物件の場合、移動時間も加わり、さらに負担が増大することもあります。
解約交渉を進める際は、このような時間的・精神的な負担も考慮に入れておく必要があります。
入居者との直接契約に切り替える手間が発生する
サブリース契約に、オーナーが転貸借関係を承継する旨の合意がある場合、サブリース契約を解約すると、オーナーはこれまでサブリース会社が行っていた業務、特に転借人の契約管理を引き継ぐ必要が生じます。
これは単に窓口が変わるだけでなく、煩雑な手続きを伴う可能性があります。まず、現在入居中の各入居者(賃借人)に対し、貸主がサブリース会社からオーナーへ変更になった旨を通知し、今後の家賃の振込先などの変更事項を伝える必要があります。
サブリース会社が入居者から預かっていた敷金についても、オーナーが適切に引き継ぎ、将来の退去時に精算する義務が発生します。サブリース会社からの入居者情報や契約書類の引き渡しがスムーズに行われなかったり、敷金の精算や引き継ぎを巡ってトラブルに発展したりするリスクも考慮に入れておく必要があります。これらの手続きは、ご自身の時間と労力を大きく費やすことになります。
サブリース解約の問題は難波みなみ法律事務所へ

サブリース契約の解約は、借地借家法や複雑な契約内容が絡む専門性の高い問題です。オーナーご自身だけで適切な対応を進めるのは、非常に困難を伴う場合があります。サブリース会社との交渉や法的な手続きには専門知識が不可欠であり、一人で抱え込むと精神的な負担も大きくなりかねません。
このような状況で有効なのが、弁護士への相談です。弁護士に依頼することで、オーナー様の代理人としてサブリース会社との交渉窓口を一本化できます。複雑なやり取りを全て任せられるため、オーナーの精神的・時間的な負担を大きく軽減できます。また、内容証明郵便の作成や送付、さらには交渉が決裂した場合の調停や訴訟といった法的手続きも代行してもらえます。特に、法廷での代理人活動は弁護士にしか認められていません。
初回相談30分を無料で実施しています。
面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
お気軽にご相談ください。
対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。