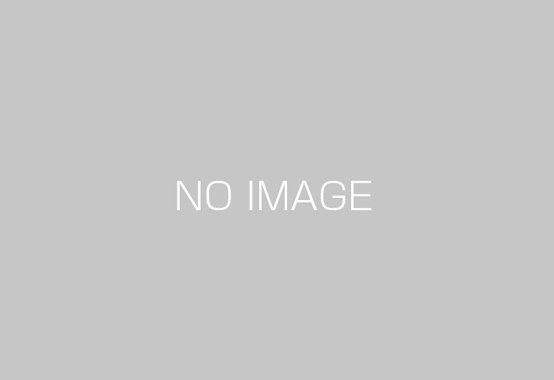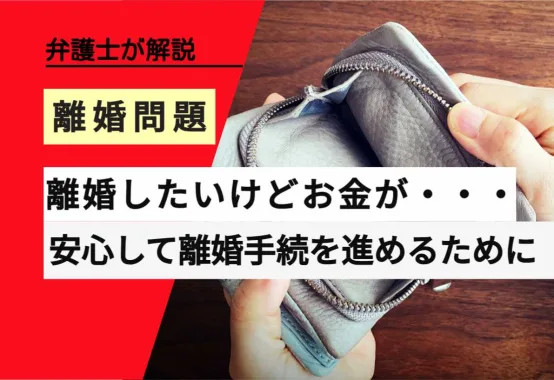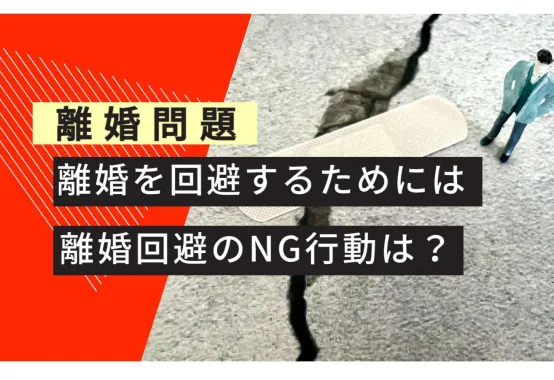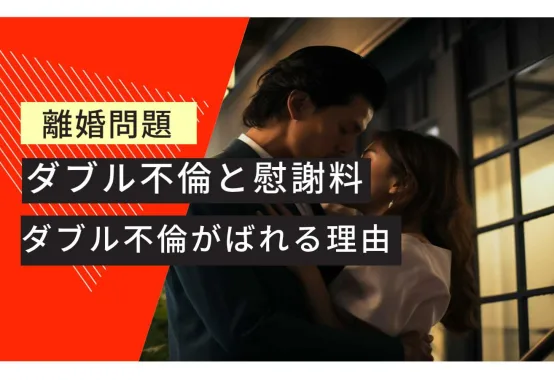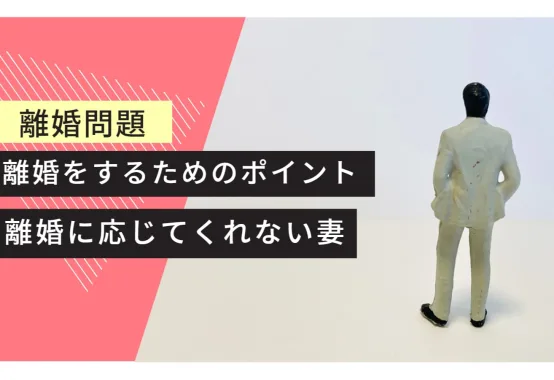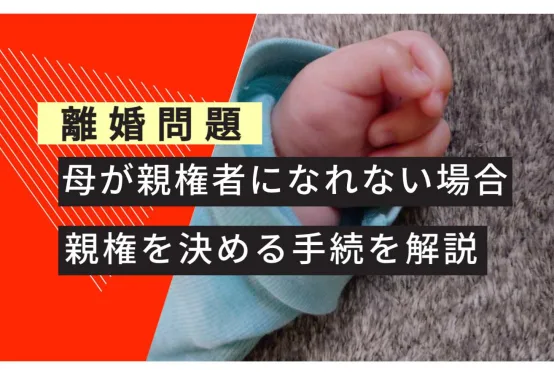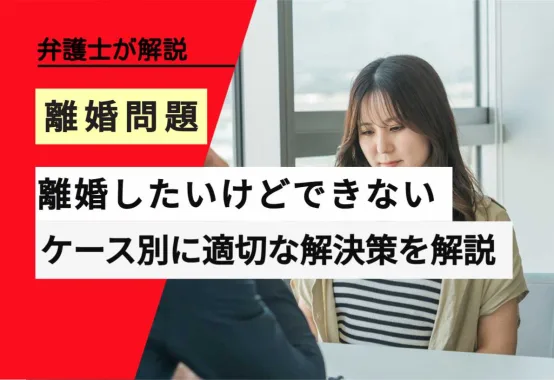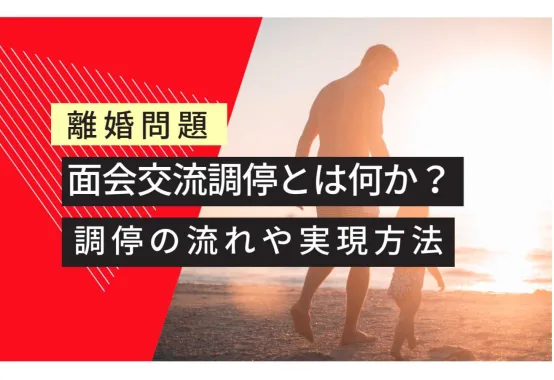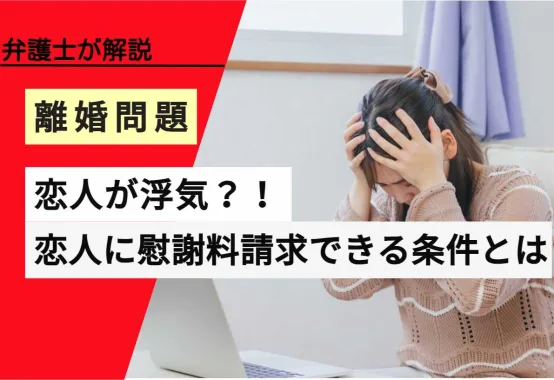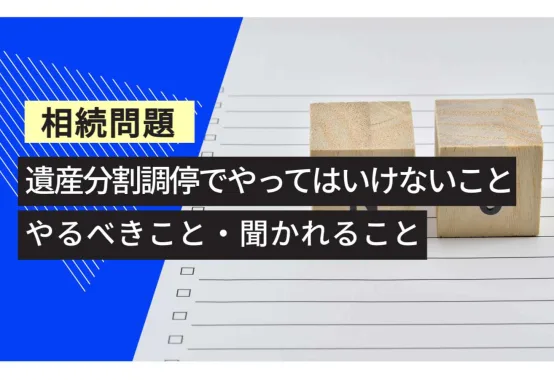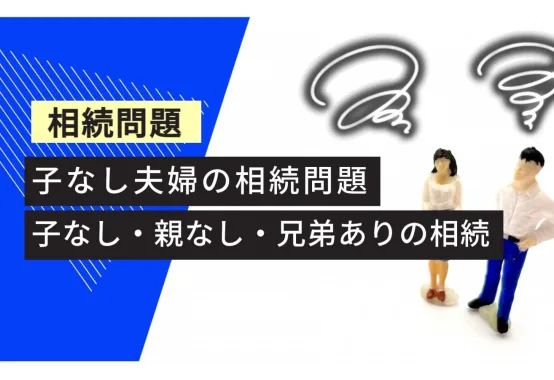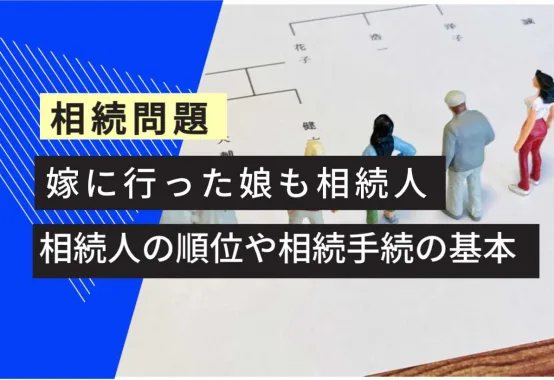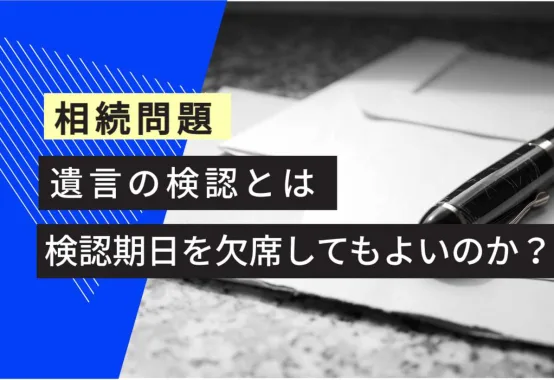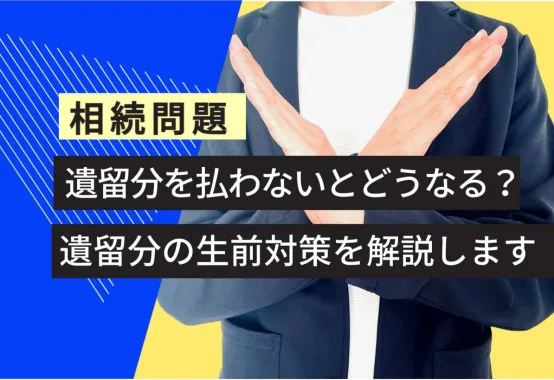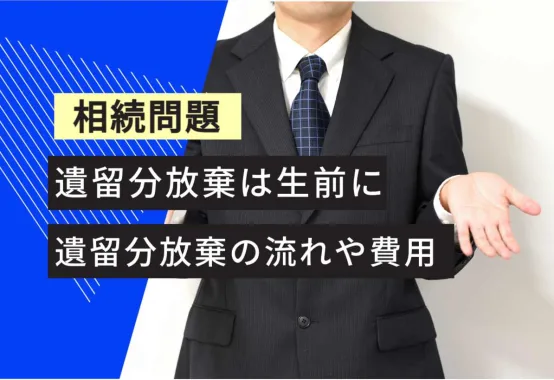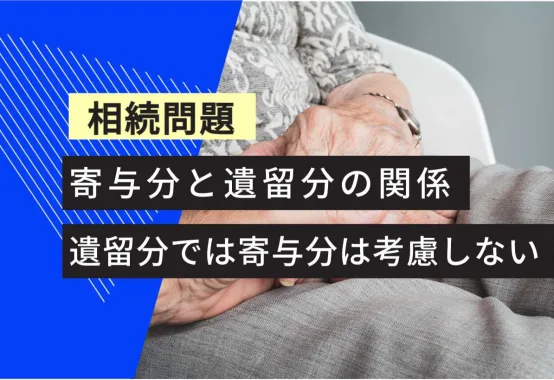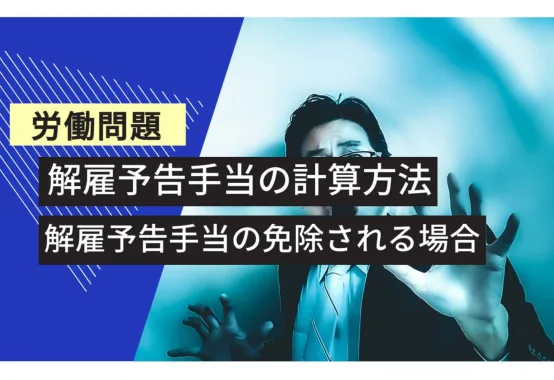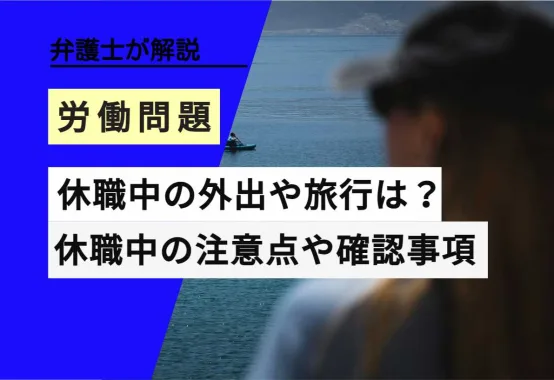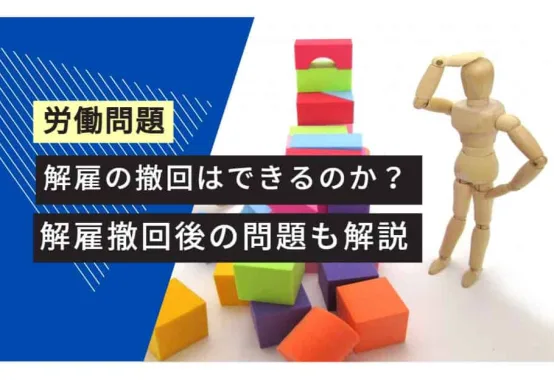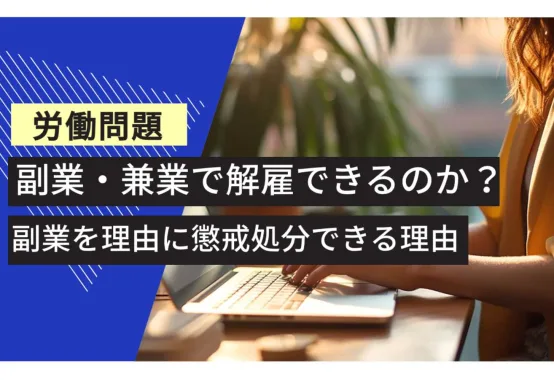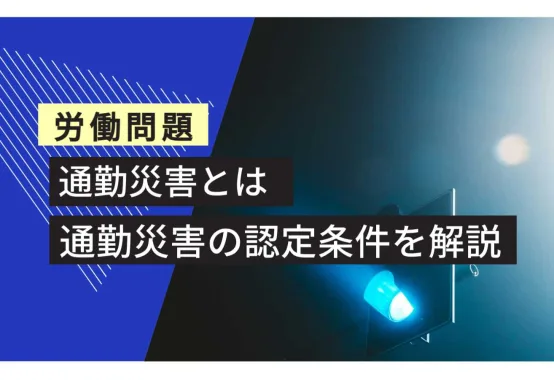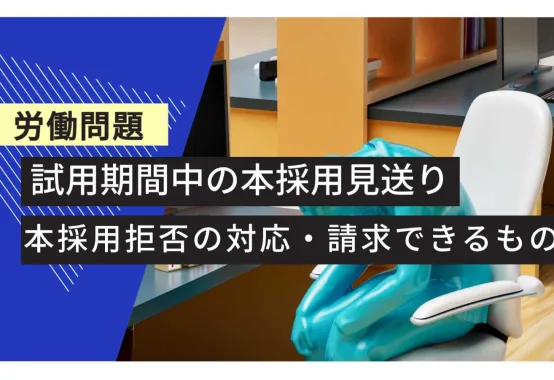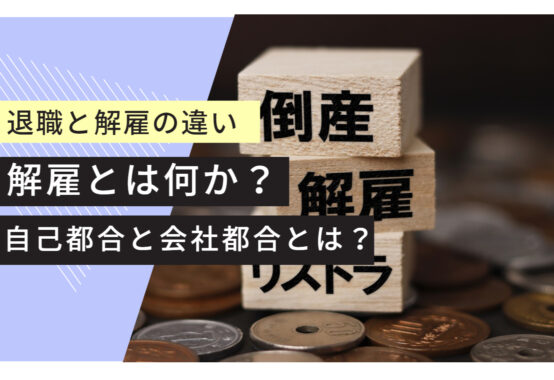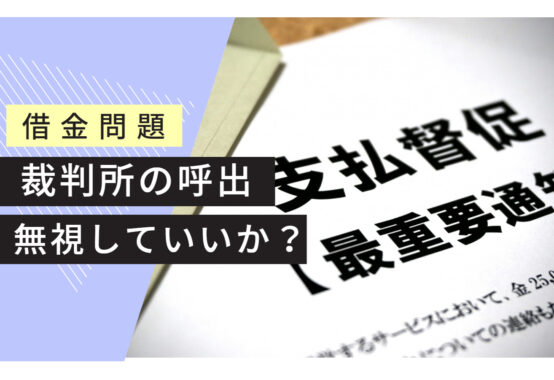子供のいる夫婦の離婚問題では、子供の親権問題が必ず生じると言っても過言ではありません。
しかし、多くの事案で、母親が子供の親権者となっている現実があります。母親が離婚時に親権者となれないケースは多くはありません。
その中でも、母親が親権を獲得できず、親権者が父親となるケースが一定数あります。
母親が親権を取れない理由としては、別居後に父親が監護していたり、育児放棄や虐待といった問題のある監護状況等が挙げられます。
今回は、母親が親権問題で負けるケースを解説したいと思います。
1. 親権とは

親権とは、未成年の子供に関して親が持っている権利のことです。
親権には、未成年の子どもを養育監護する権利(監護権)に加えて、子どもの有する財産を管理する権利が含まれています。
父母が婚姻している間は、父と母が共同して親権者となります。これを共同親権と呼びます。
他方で、父母が離婚すると、父母のうちどちらかのみが子供に対する親権を持つことになります。
これを単独親権と呼びます。
単独親権となるのは、離婚をして父母が別々の生活をするにもかかわらず、父母の両方が親権者となると、未成年の子の福祉を害すると考えられているからです。
離婚に際して、財産分与、慰謝料、年金分割、養育費については、棚上げにして事後的に協議することはできますが、親権については、離婚時に誰を親権者とするのかを決めなければ離婚自体ができません。
なお、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことによって、子どもの親権は子供が18歳になるまでとなりました。
ただ、成人年齢の引き下げがなされても、養育費の支払は、20歳までとされていますので、注意が必要です。
父親が親権を取得するための必要な事項については、こちらのコラムを参照ください。
2. 親権の決め方
後述するように、親権の判断においては、母親が圧倒的に有利な状況にあることがほとんどです。
父親が親権を取得できるケースというのは非常に限られた場合と言っても言い過ぎではないです。
このような状況で、母親が親権を取得できない限られた場合とは、どのようなケースを指すのでしょうか。検討していきます。
まずは、親権者の適格性の判断基準から解説していきます。
2-1.親権の判断基準
単独親権の日本では、離婚時に必ず親権者を決めなければなりません。
親権者の決定について、夫婦間で対立する場合には、家庭裁判所により、夫婦のうちいずれが親権者として適格な者であるかを判断されることになります。
親権者の決定においては、父母のいずれが親権者となることで、子の健全な成長が実現できるのかといった基準で判断されます。
この判断における基準としては、母性優先、継続性、子の意思、きょうだい不分離、面会交流な実施状況が採用されています。
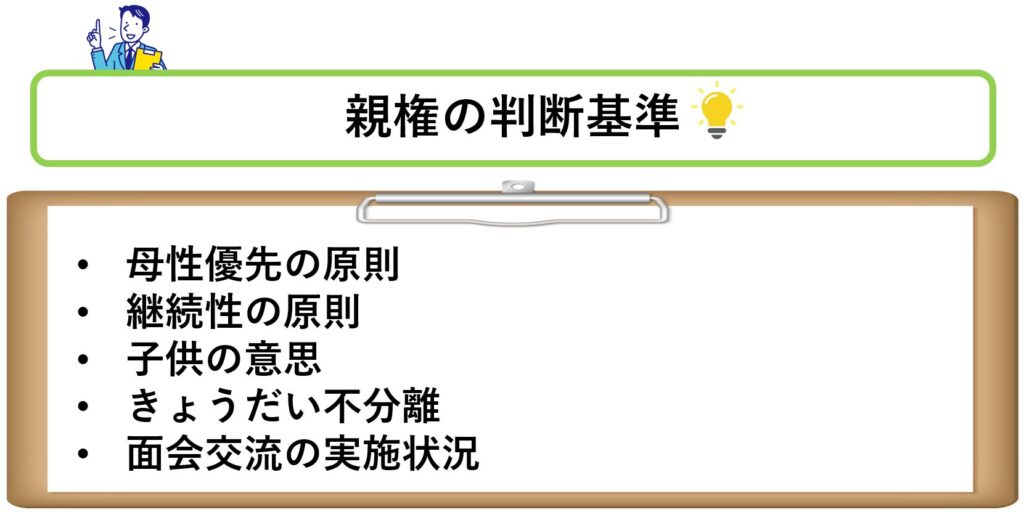
2-1-1.母性優先の原則
母性優先の原則とは、子供、特に乳幼児の養育監護は、特別の事情のない限り、母親に委ねることが子供の福祉に適うという考え方です。
この考え方は、乳幼児期の子供の発達段階において、母親の存在が子供の人格形成にとって重要な役割を果たすと考えられていることが根底にあります。
親権者の判断において、この母性優先の考え方が重視される関係で、母親が親権者に指定されることが多いです。
しかし、昨今では、単に生物学上の母親であることを重視する必要はなく、母性的な役割を果たしている監護者との関係を重視するべきとされています。
そのため、父親やその他監護者が主たる監護者としての役割を果たしているのであれば、その監護状況に応じた親権者の認定がなされています。
監護養育の考え方が多様化している現代においても、乳幼児期の主たる監護は母親が担っていることが多く、子供との心理的身体的な結びつきが強いです。
そのようなことから、母親の監護養育に特段の問題点がないのであれば、母親が親権者となることが多いのが実情です。
2-1-2.継続性の原則(現状維持の原則)
監護者と子供の精神的結びつきを監護者の変更に伴って断絶させてしまうと、子供に対して過度な心理的な負担を強いてしまいます。
そこで、現状の監護者の監護養育が安定しており、これを変える必要がない場合には、現状の監護状況を重視するべきという考え方が継続性の原則といいます。
乳幼児期であれば、監護をしてきた親との心理的な結びつきが子供の成長に重要な役割を果たしているため、出生から現在までの監護状況が重視されます。
そのため、母親が子供を連れて別居し、離婚までの期間子供の養育監護を継続させている場合には、先程の母性優先の原則に加えて、出生から離婚時まで継続する監護状況を重視して、母親が親権者に指定されることが多いです。
他方で、小学校3〜4年生以降の子供であれば、小学校や友人との繋がりが強くなっているため、監護する親との結びつきに加えて、これまでの生活環境との結びつきも重視されます。
そのため、母親が子供を連れて別居した上で、離婚までの期間、子供の別居前の生活環境を変えることなく、子供の養育監護を継続させている場合には母親が親権者に指定されることが多いです。
仮に、別居に伴い、子供の生活環境が変わってしまったとしても、母親が引き続き子どもを監護しており、別居から離婚時までの新たな生活環境に特段の問題が見受けられないのであれば、別居以降の安定した生活環境を守るため、母親が親権者となることが多いでしょう。
2-1-3. 子の意志の尊重
子の親権者の指定にあたっては、子供の意思を把握するように努め、子供の年齢や発達の程度に応じて、子供の意思を尊重しなければならないとされています。
ただ、全ての子供の意思を尊重しなければならないわけではありません。
例えば、小学校低学年以下の幼い子の場合、同居する監護親の影響を特に受けやすい傾向にあり、子供自身の真意を把握することが困難なことが多いでしょう。
そこで、子供が意思を表明できる年齢としては、10歳以上と考えられています。
ただ、10歳以上といえども、精神的に未成熟であることに変わりはないため、子供の発言それ自体を額面通りに受け取るのではなく、その発言が真意によるものなのかを、発言時の態度や行動等を観察する必要はあります。
そのため、乳幼児に関しては、親権者に関する意志の確認自体をしないか、仮に意思確認をしたとしても、親権者の指定における判断材料として重視しないことがほとんどです。
小学校の中学年頃までは、母親や監護者の監護状況を優先し、子の意思は補充的要素に留まります。
小学校の高学年頃から中学校3年生までは、子の意思を尊重しつつ、これまでの監護状況を踏まえながら決定します。
家事事件手続法では、子どもが15歳以上の場合は子どもの意見を聞くことが義務付けられており、15歳以上の子供の意思は重要視されます。
2-1-4. きょうだい不分離

子どもが複数人いる場合、長男の親権者は父親、次男の親権者は母親といったように父母それぞれに分離することなく、兄弟姉妹は同一の親の下で養育監護するのが望ましいとされます。
これを「きょうだい不分離の原則」といいます。
この考え方の理由は、これまで一緒に暮らしてきたきょうだいが離婚に伴って引き離されることによって、二重の心理的な負担を負わせることにかること、きょうだいが一緒に生活し、これを通じて様々な体験を得ることで人格形成に資することにあります。
ただ、別居後、きょうだいが分離して生活しており、その期間が相当長期間になっている場合には、きょうだいが分離して親権者の指定がなされることはあります。
2-1-5. 面会交流の実施状況
面会交流とは、子どもと離れて暮らしている父母のうち一方が、定期的に、子どもと会って話をしたり一緒に遊んだりすることを言います。
子供の年齢によっては、直接面会する方法ではなく、電話や手紙による面会を行うこともあります。
これを間接交流と言います。
面会交流の目的は、離婚や別居によって、一方の親と離れ離れになった子供が、離れて生活する一方の親と定期的な交流を行うことで、親子関係を良好なものとし、子供の健全な人格形成を実現させることにあります。
親権者の判断をするにあたって、別居中の面会交流が適切に行われている場合には、監護する親に有利な事情として扱われます。
ただ、面会交流の実施状況が思わしくなかったとしても、この事情のみをもって親権者の判断が変わることはないでしょう。
2-1-6. 子の奪取
継続性の原則とも関係してくる事情ですが、たとえ子供の監護実績が長期間に及んでいたとしても、子供の監護が違法な奪取行為により開始されている場合には、親権者の判断においてはマイナスの事情として考慮されます。
例えば、別居開始後、子供が母親の監護の下で生活していたところ、父親が子供の通う幼稚園に出向き許可なく子供を幼稚園から連れ去り、その後監護を継続したような場合です。
この場合、未成年者略取誘拐に該当し得る行為ですから、先ほどの例の父親が子供を監護し続けたとしても、父親による監護実績は重視されない可能性が高いでしょう。
このような場合には、監護していた母親は速やかに監護者指定及びこの引き渡しの審判前の仮処分を一日でも早く申立てをするようにします。
他方で、別居に伴って一方の親が他方の親の意思に反して子供を連れて別居したような場合です。
例えば、母親が、父親の意に反して、子供を連れて別居した場合、確かに、父親の意向に反していたとしても、これをもって直ちに違法と評価することはできない、あるいは、違法であるとしても違法性の程度は低いとされ、別居後の監護養育の継続性を尊重して、監護する親を親権者とされることが多いでしょう。
また、母親が子供を残して別居し、別居後に父親が一定期間子供を養育監護し、その監護状況が安定している場合には、父親が親権者と指定されることもあります。
Tips!最高裁平成17年12月6日判決【事案】子供が、共同親権者の1人である母親の実家 において母親及びその両親に監護養育されて平穏に生活していた。 子の通う保育園へ迎えに来た祖母が自動車に子を乗せる準備をしているすきをついて、父親が、子に向かって駆け寄り、背後から自らの両手を両わきに入れて子を持ち上げ、抱きかかえて 、あらかじめドアロックをせず、エンジンも作動させたまま停車させていた父親 の自動車まで全力で疾走し、子を抱えたまま運転席に乗り込み、ドアをロックして から、子を助手席に座らせ、祖母が、同車の運転席の外側に立ち、運転席のドアノブ をつかんで開けようとしたり、窓ガラスを手でたたいて制止するのも意に介さず、 自車を発進させて走り去ったというものである。 【判示】 祖母に伴われて保育園から帰宅する途中に前記態様で有形力を用いて連れ去り、保護されている環境から引き離して自分の事実的支配下に置いたのであるから、その行為が未成年者略取罪の構成要件に該当することは明らかである。 本件において、父親は、離婚係争中の他方親権者である母親の下から子を奪取して自分の手元に置こうとしたものであって、そのような行動に出ることにつき、子の監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情は認められないから、その行為は、親権者によるものであるとしても、正当なものということはできない。 また、本件の行為態様が粗暴で強引なものであること、子が自分の生活環境についての判断・選択の能力が備わっていない2歳の幼児であること、その年齢上常時監護養育が必要とされるのに、略取後の監護養育について確たる見通しがあったとも認め難いことなどに徴すると、家族間における行為として社会通念上許容され得る枠内にとどまるものと評することもできない。 以上によれば、本件行為につき、違法性が阻却されるべき事情は認められないのであり、未成年者略取罪の成立を認めた原判断は、正当である。 |
3. 母親が親権者に指定されない場合とは
母親が親権者に指定されない場合は、限られたケースになります。
例えば、以下のようなケースが想定されます。
母親が親権者に指定されない事案
- 別居後の監護者が父親
- 別居前の主たる監護者が母親以外の者
- 子供に対する虐待
- 母親が重度の精神疾患を患っている
- 子供の意思
3-2. 別居前の主たる監護者が母親以外
先程解説したように、母性優先の原則とは、母親であるだけで親権者の指定にとって有利となる考えではありません。
子供の養育監護を主として行い、子供との情緒的な結びつきが強い親が、母性的な役割を果たすことから、そのような親が親権者として指定されることがあります。
そのため、別居前に、父親が子育てに積極的に関与し、子供の養育監護の大部分を担っている場合には、父親が親権者に指定される可能性があるでしょう。
父親と母親が、子供の養育監護をそれぞれ分担しており、負担割合として半々であれば、別居後の監護状況や子供の年齢に応じた意思を踏まえて親権者の適性を判断します。
また、子供の主たる監護者が母親であったとしても、その監護状況に不適切な点がある場合、例えば、育児放棄、わいせつ行為、暴力・暴言があるような場合には、母親が親権者としての適格を欠くと判断されることがあります。
3-3.子どもに対する虐待
児童虐待の事実は、親権者の適格を否定する重大な事情になります。
かつては「法は家庭に入らず。」と言われ、親の子供に対する虐待については、家庭内で解決するべきと言われていた時代がありました。
しかし、現代では、民法に加えて、児童虐待防止法や児童福祉法といった子供の権利と安全を守るための法制度が整備されています。
児童虐待には、身体的虐待だけでなく、性的な虐待、心理的虐待、育児放置(ネグレクト)があります。子への虐待には、子どもに対する直接的な攻撃だけでなく、配偶者に対して、子どもの面前で暴力等のDVが行われる心理的な虐待も含まれています。
いずれの虐待であっても、子どもの福祉に反することは明らかであり、親権の喪失や親権の一時停止の理由にもなります。
そのため、母親による児童虐待の事実は、親権者としての適格を否定する大きな事情の一つとなります。
▶虐待の証明は難しい
ただ、虐待の事実を明らかにすることは簡単ではありません。
虐待をする親は、虐待の事実を認めないだけでなく、そもそも虐待の認識を持っていないこともあります。
また、「親に嫌われたくない」「これ以上虐待を受けたくない」という思いから、虐待被害を受けている子供自身が、虐待の事実を認めず、親をかばうこともあります。
そのため、調停や訴訟等の審理において、母親の虐待の実態が明るみにならないこともあります。
虐待の事実を裏付ける客観的な証拠がなければ、虐待の事実は認定されない可能性が高いでしょう。
3-4.重度の精神疾患
母親が重度の精神疾患を患っており、子どもの監護能力に問題がある場合には、子どもの福祉のため、母親に親権が認められないことがあります。
単に、母親が精神疾患に罹患しているだけでは足りません。精神疾患の程度が重篤であり、回復の見込みが低く、長期入院による治療を要するような場合には、母親が十分な監護能力を有さないと判断されることがあります。
3-5.子供の意思
子供が母親との生活を希望しない意思を表明する場合には、母親が親権者とならない可能性があります。子供が満15歳以上の場合、家庭裁判所は必ず子供の陳述を聴取しなければなりません。そのため、15歳以上の子供が明確に母親との生活を希望しない旨を述べた場合には、母親の親権が認められない可能性があります。
子供が15歳未満であっても、小学校高学年以上であれば、子どもの意思を尊重する傾向は強いでしょう。
4.親権の判断要素として重視されない事情
逆に、以下で述べる事情は親権者になれない事情と勘違いされていることが多いです。しかし、実務上、親権者の判断において決定的な判断要素とはされていません。
①不貞行為
②低収入・無職
③監護補助者がいない
4-1.収入額が少ない・無職であること
父親から、以下のような主張が出ることが多いです。
母親は収入が少なく、十分な養育環境を維持できないため、親権者として不適格である、という主張です。
妻は夫よりも収入が低いことが多く、特に、仕事をしていない専業主婦である場合や子供が乳幼児であるため十分に就労できない場合には、夫婦間の収入格差は顕著となることが多いでしょう。
しかし、母親の低収入が理由で親権者としての適格が否定されることはほとんどありません。母親の経済面の不安は、父親から支払われる適正な養育費(離婚前であれば婚姻費用)、児童手当や児童扶養手当などの公的支援によって、生活費の不足を解消できます。
しかも、経済的な余裕・経済力だけが子供の健全な成長に資する訳ではないからです。
4-2. 不貞行為(不倫・浮気)をしたこと
母親が不貞行為をした場合に、これを理由に親権者の適性を欠くという主張が夫からされることも多いです。
確かに、妻が不貞行為を行い、これが引き金となり離婚するに至っている場合、夫からすれば不貞行為により夫婦関係が破壊されただけでなく、仮に母親が親権者と指定されれば、子供とも引き離されることとなり、「踏んだり蹴ったり」の結果となるため、母親が親権者として不適格であると主張したくなる心情も理解できます。
しかし、不貞行為は配偶者が負うべき貞操義務に反する裏切りではあるものの、あくまでも夫婦間の問題であって、これによって直ちに子供の親権者としての適格性を否定するものではありません。
ただ、不貞行為によって、子供の養育監護がなおざりにされ、育児放棄と呼べる状況になっていたり、浮気相手と子供を頻繁に面会させるなどして、子の養育環境を複雑なものとしている場合には、親権者として不適格と判断されることはあるでしょう。
4-3.監護補助者がいない
子どもの養育監護をサポートする親の親族(祖父母や叔父・叔母)が身近にいることも、親権者の適格性を支える事情になります。
しかし、監護補助者となるべき親族が身近にいなかったとしても、それだけで親権者としての適格が否定されるわけではありません。
監護補助者となるべき親族がいなかったとしても、地域のコミュニティ、学校関係、友人関係によっても、子どもの養育監護を補完することは可能です。
| ✓裁判所による子供に関する調停の解説はこちら |
5. 父親側に親権を取られないためのポイント・注意点

多くの事案では、母親がこの出生から別居までの期間、主たる監護者として子の養育監護を担っています。
そのため、別居前の監護状況を理由に、親権が父親に帰属することはあまりありません。
父親が親権者に指定される大部分の事案では、別居に際して、母親が子供を置いて別居を開始したり、父親が子供を連れて別居を開始した上で、別居から親権者(あるいは監護権者)の指定を受けるまでにある程度の期間を経過させてしまっていることが多いです。
そのため、母親が親権を希望するのであれば、子供を連れて別居を開始するべきです。
母親が子供を置いて別居を開始させてしまうと、母親側が不利な状況に陥ります。絶対に子供を置いて別居を開始させることは避けるべきでしょう。
5-1.父親が子供を連れて別居した場合の対処法
万一、父親が子供を連れて別居を開始するようなことがあれば、直ちに子の引き渡しと監護権者を指定する審判前の保全処分という手続をしなければなりません。
子供を監護する父親と悠長に話し合いを重ねてしまったことで、いつの間にか長い期間が経過している状況は回避しなければなりません。
時間との勝負という側面もありますから、あまり悠長にはしていられません。
5-2.面会交流に協力する
母親の親権が認められるために、子どもと父親との面会交流には積極的に応じるようにしましょう。
別居後においても、子供が母親との生活を継続させているのであれば、余程の極端な事案でない限り、母親が親権者と指定されるでしょう。
ただ、様々な事情が重なって、母親が親権を取れない可能性も生じます。
母親が確実に親権者となるためには、父親に対して面会交流を積極的に提案した上で、これを実行するようにします。
別居から離婚までの間、父親と子供との面会交流が適切に実施できている場合には、裁判所としても、離婚後も面会交流を通じて子供と父親の良好な親子関係は構築できると期待できるため、母親を親権者と指定しやすくなります。
5-3.離婚のために親権を譲歩しない
DVやモラハラをする夫から一日も早く離れたい思いから、離婚成立を優先するため、親権にこだわる夫に親権を譲り、離婚成立後に親権者の変更をすればよい、と考えてしまう人がいます。
しかし、子どもの親権者が安易に変更されてしまうと、子どもの生活環境が不安定なものになってしまいます。そのため、親権の変更は、子供の生活環境を安定させるため、非常に厳しい条件を満たす必要があります。
そうすると、「離婚後に変更すればよい。」という安易な考えで、子の親権を父に譲ることは絶対に避けなければなりません。子どもと一緒に別居を開始させ、暴力的な夫とのやり取りは、弁護士等の代理人を通じて行うようにしましょう。
6. 親権者または監護権者の指定の手続
子供のいる夫婦が離婚する場合、子どもの親権者を決めなければ離婚することができません。
子供の親権者を決まる手続きには、夫婦の話し合いによる協議のほか、離婚調停や離婚訴訟といった裁判手続きがあります。
また、離婚前の監護者指定についても、監護者指定と子の引渡しの調停や審判、審判前の保全処分の手続きがあります。
6-1.協議離婚
まずは、夫婦間で、親権者の指定に関して協議を行います。
夫婦間で協議ができる場合には、親権者を指定して協議離婚します。
6-2.裁判手続
しかし、夫婦間の協議が調わない場合には、裁判手続を通じて決めるほかありません。
離婚調停や離婚裁判において、裁判所が子供の親権者を指定する場合、父母のうちどちらが親権者として適格であるかを審理します。
また、離婚前の時点において、一方の親が子供の監護権者の指定の申立てをすることがあります。
この場合には、監護者指定と子の引き渡しの調停、審判あるいは審判の保全処分の申立てを行います。
緊急性が高い場合には、この保全処分の申立てをします。
調停手続は、裁判官と調停委員2名で構成される調停委員会が当事者の仲裁を行い、話し合いにより解決を図る手続です。
監護権とは、子供と一緒に生活をして日常の養育監護を行う権利のことで、親権の中に含まれているものです。
離婚前であれば、親権は父母の両方がこれを行使する共同親権となります。
ただ、別居中の夫婦の場合、父母のうちどちらかが事実上子供の養育監護をしていますから、離婚前に父母のどちらが監護者として適格かを決めることがあります。
裁判手続を通じて子の監護権者の指定を受けた場合、離婚するまでの間、その監護者である親による養育監護に特段の問題がないのであれば、監護権者である親が親権者として指定されることがほとんどです。
6-3. 審理の内容・流れ
父母のうちいずれかが、裁判所に対して、調停や審判の申し立てを行うことで、審理が開始されます。
裁判手続における審理において、父母の両方から、子供の出生から現在までの養育監護状況に関する主張を出してもらいます。
その上で、家庭裁判所の調査官によって、子供の監護状況の調査を行います。
調査にあたっては、父母だけでなく、監護補助者となる祖父母や親族からも聴き取りを行います。
さらに、子ども本人にも聞き取りを行い、子どもの意思や健康状態を確認します。
また、子供が住む自宅に訪問し、自宅の間取りを確認し、子供の養育環境として適切かを調査します。
保育園や小学校の教員に対しても聞き取り調査を行い、子供の養育状況を確認します。そのため、予め保育園や学校の担任や責任者と、日頃から連絡を取り合うなどして連携を取っておくことが重要です。
さらに、父母と子供に裁判所に来庁してもらい、裁判所の施設内で一方の親と子供に面会してもらい、その交流場面を観察されることがあります。
これらの調査手続を経た上で、調査官において、調査報告書が作成され、裁判所に提出されます。
調査報告書には、子供の養育監護状況に関する記載に加えて、親権者あるいは監護権者指定に関する調査官の意見が付されています。
親権や監護権に関する判断を行う裁判官においても、ある程度調査報告書の内容を踏まえた判断をすることが多いでしょう。
親権者の変更をするためには
離婚後に親権者を変更することは簡単ではありません。
簡単に親権者の変更ができてしまうと、子どもの生活の安定が害されてしまいます。そのため、親権者の変更は、子の利益のために親権者を変更するべき重大な事情があることが必要です。親権者を変更するべき事情として、次の事情が挙げられます。
- 子どもに対して暴力を振るう
- 育児放棄をしている
- 親権者の監護状況や監護能力に問題がある
- 親権者が死亡した
- 子どもの意思
- 面会交流を拒否している場合
民法819条6項(親権の変更)
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
親権の問題は弁護士に相談を
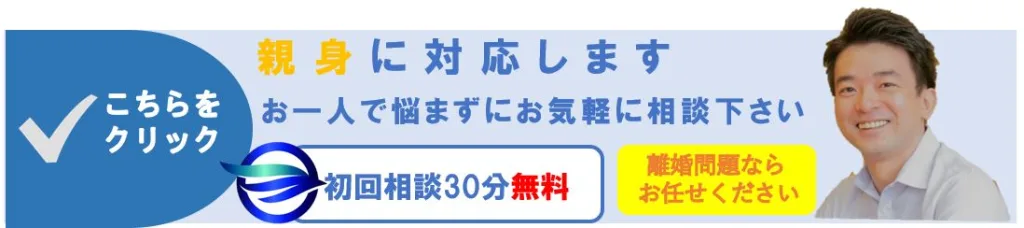
親であれば、誰しもが子供に対して、強い愛情を持っています。
子に対する強い愛情があるからこそ、子どもの親権問題が生じます。
しかし、子の親権者の判断は、子の福祉を考えながら様々な事情を考慮した慎重な判断が必要です。
事案の中には、速やかな対応を要するものもあります。
本来親権や監護権を得ることができたにもかかわらず、時期を逸したことで、親権や監護権を諦めざるを得ないものもあります。
別居後ではなく、別居前の早い段階でご相談していただくことが大切です。
弁護士に依頼するメリット
親権を得られるよう計画的に進められる
子の引渡し等の裁判手続を一任できる
離婚問題全般を相談できる
自身に有利な条件で解決を図れる
当事務所では初回相談30分を無料で実施しています。
対応地域は、大阪府全域、和歌山市、和歌山県、奈良県、その他関西エリアとなります。
お気軽にご相談ください。