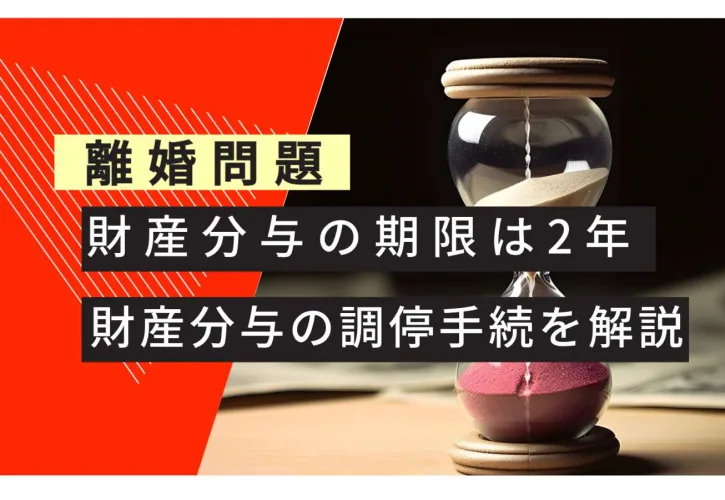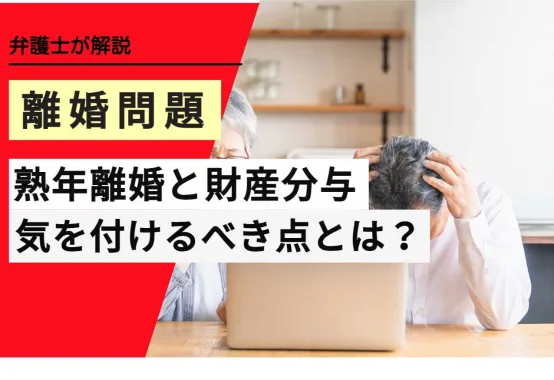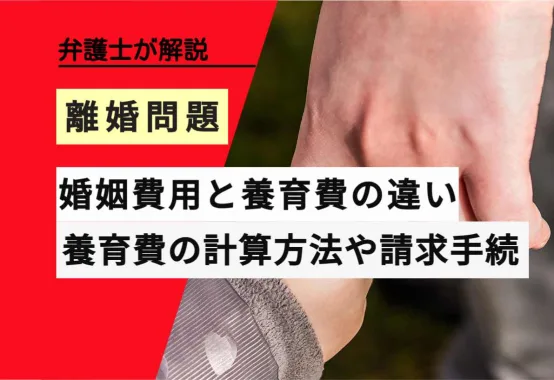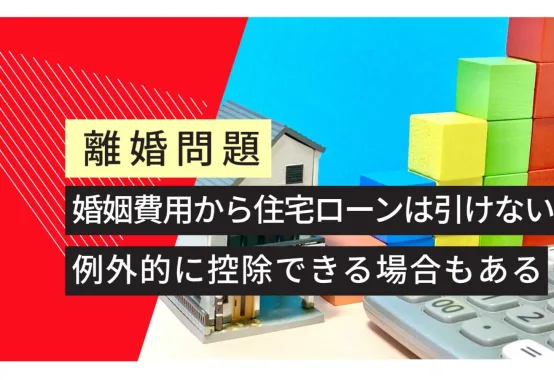離婚時に問題なるのが財産分与です。
財産分与とは、離婚に際して、夫婦の共有財産を清算することをいいます。通常、離婚をする際に、財産分与についても協議されることが多く、離婚後に財産分与を請求することはそれほどありません。ただ、とりあえず離婚の成立を先行させた後、残っている財産分与や離婚慰謝料の問題を解決させることもあります。
しかし、離婚時の財産分与も、離婚をしてからいつまで経っても請求できるわけではありません。財産分与は離婚時から2年の経過で消滅します。
本記事では、財産分与の請求期限や2年経過後に財産分与を請求できるかを弁護士が解説します。
財産分与とは何か?
財産分与とは、婚姻中に築いた夫婦の共有財産を離婚に際して分配する制度です。結婚前の財産や親からもらった財産は、「特有財産」として財産分与の対象から除外されます。財産分与による分与割合は、夫婦間の公平から2分の1(50:50)とされるのが原則です。
関連記事|財産分与の対象にならないものとは?共有財産と特有財産について弁護士が解説します
関連記事|財産分与と割合とは?離婚問題に精通する弁護士が解説します
財産分与の期限・時効は離婚時から2年

離婚の際に必ず財産分与の合意をしなければならないと誤解されていることがあります。
しかし、離婚に際して、財産分与を合意しなければならないことはありません。つまり、離婚後に財産分与を請求することは可能です。ただ、この離婚の財産分与には、期限が定められています。
財産分与は「離婚をした日」から2年以内
財産分与は離婚の時から2年以内に調停の申立てや審判の申立てをしなければ、財産分与の請求はできなくなります。財産分与は調停等の手続をしなくても当事者間の話し合いで行うことができます。
しかし、相手方に対する財産分与の意思表示や当事者間の話し合いだけでは、この2年の期限は止まりません。そのため、当事者間の話し合いが進展しない場合には、離婚時から2年が経過するまでに、家庭裁判所に対して調停や審判の申立てをしなければなりません。
ただし、2年を経過していたとしても、相手方が任意で財産分与に応じる場合には、当事者の合意により財産分与の請求をすることは認められます。
「離婚をした日」とはいつか?
離婚をした日とは、離婚の形態によって意味が変わりますので、注意が必要です。
「離婚をした日」とは
協議離婚であれば離婚届けを提出した日
調停離婚であれば調停成立日
裁判離婚であれば判決確定日
戸籍謄本には離婚の種類と離婚成立日が記載しています。戸籍謄本を取得し、離婚をした日の正確な日をチェックしておきましょう。
「別居時」から2年ではないため注意
財産分与の期間は、「離婚時」から2年です。「別居時」ではありません。
財産分与の期間を「別居時」から2年であると勘違いしてしまい、期間を徒過させないために、焦って財産分与の合意をしてしまうケースも中にはあります。財産分与における「別居時」はあくまでも共有財産の基準時であって、財産分与の期間の起点ではありません。


「2年」の期間制限の法的な性質|消滅時効との違い
2年の期限は、厳密に言うと「消滅時効」ではなく除斥期間(じょせききかん)となります。
消滅時効と除斥期間は、権利が消える点では共通しますが、異なる点もたくさんあります。除斥期間というワードは聞きなれないワードかと思います。
除斥期間と似たものとして、消滅時効があります。一定期間の経過により、ある権利が無くなってしまう点では共通しています
しかし、消滅時効と除斥期間には援用の有無・更新(中断)の有無の点で違いがあります。
時効援用が要らない
消滅時効は、一定の期間が到来すれば、時効によって消滅した意思表示(時効の援用)をする必要があります。つまり、権利者は相手方に対して、「消滅時効の援用をします。」という意思表示をしなければ、消滅時効の効果が生じません。
しかし、除斥期間は、一定の期間が到来すれば当然に権利が消滅しますので、別途で意思表示をする必要がありません。
時効の更新(中断)がない
時効の場合、時効期間中に支払の猶予を求めたり、権利の存在を認める等をすることで時効期間がリセットされます(時効の更新)。また、義務者に支払いを催告することで時効の完成が6か月間猶予されます(時効の完成猶予)。
除斥期間の場合には、時効の更新や時効の完成猶予といったものがありません。そのため、離婚してから2年以内に、財産分与の合意をするか、合意ができない場合には、調停等の申立てをしなければなりません。2年の期限については、延長はないため、くれぐれも注意をしなければなりません。
調停の申立てを離婚時から2年以内にする
2年以内に財産分与の合意ができない場合には、2年の経過時までに家庭裁判所に財産分与の調停を申立てなければなりません。
いくら、裁判外で相手方に対して、財産分与を求める意思表示をしていたとしても、2年以内に合意ができなければ、2年の経過により財産分与を求めることはできなくなります。
2年の期間までに財産分与に関する合意が成立しそうになければ、早い段階で財産分与の調停申立ての準備をするようにしましょう。
相手方の住所地の裁判所に申し立てる
調停を申し立てる家庭裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立人の住所地の裁判所ではないので注意です。例えば、申立人が大阪市、相手方が東京都に居住している場合、調停の申立ては、大阪家庭裁判所ではなく、東京都内の家庭裁判所になります。
ただし、当事者間で相手方の住所地の家庭裁判所以外の家庭裁判所で調停を行う合意がある場合には、合意した家庭裁判所にて、調停手続を進めることができます。
☑財産分与の調停申立てに関する裁判所の解説はこちら


確定した財産分与の時効は5年又は10年間
確定した財産分与請求権の時効は5年又は10年となります。財産分与を解決するプロセスによって確定した財産分与の時効期間が異なります。
協議により財産分与の合意をした場合
当事者間の話し合いにより財産分与の合意が成立する場合には、合意した財産分与の権利は、合意時から5年の消滅時効となります。当事者間で合意した財産分与に関する権利も、他の債権と同様に5年の消滅時効の適用を受けるからです。
調停や審判で財産分与が確定した場合
調停、審判及び訴訟といった裁判手続きを通じて確定した権利については、消滅時効が10年とされています。
2年の期限内に財産分与の調停申立てを行った上で、調停、審判等を通じて、財産分与の内容が確定した場合には、その財産分与の権利は、10年の消滅時効により消滅します。
裁判手続きを通じて財産分与の内容が確定しても、義務者が任意に支払わない場合があります。その場合に、強制執行をすることなく、漫然と放置すると、10年の時効期間の経過により、確定した財産分与の権利は消滅します。
ただ、この場合の時効は除斥期間ではなく消滅時効となりますので、義務者による時効の援用を受けて、初めて時効により消滅します。
(判決で確定した権利の消滅時効)
第169条
1.確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
財産分与の求めるための手続き

財産分与を求める場合には、相手方に対して財産分与の請求を行い、当事者間で協議することがあります。しかし、財産分与の期限が迫っている状況で、悠長に話し合いをしていると、財産分与の除斥期間が過ぎてしまうことがありますので注意が必要です。
財産分与の2年間の期限が過ぎないために行うべきプロセスを解説します。
交渉を進める
2年間の期間がもうすぐ到来しそうであれば別ですが、時間的な余裕がある場合には交渉を進めます。
まず、離婚協議中または離婚成立後に、財産分与を求める通知をするとともに、共有財産に関する資料を開示するよう求めることが一般的です。
財産分与に関する合意が成立すれば、財産分与の具体的な内容を記した合意書を作成するようにしましょう。その他の離婚条件(養育費や離婚慰謝料等)と一緒に合意する場合には、公正証書を作成することもあります。
合意できなければ調停申立を行う
調停手続きとは、家庭裁判所の裁判官と男女の調停委員2名で構成される調停委員が、中立の立場から、当事者を仲裁し、話し合いを進めていく手続きです。
調停手続きでは、当事者が入れ替わりで、調停室に入室して、調停事項に関する言い分を述べたり、調停委員からの質問に回答することで、話し合いを進めます。
調停が行われる調停期日は、1か月半から2か月に一度の頻度で行われます。
一回の調停期日が終わる際には、調停委員から当事者の一方または双方に対して、次回期日までに主張書面や資料の提出を求めます。そのため、当事者は、調停委員から出された宿題を準備し、次回調停忌日に備えます。
調停期日を3回から5回程を行った結果、調停事項に関する合意ができれば、調停が成立します。しかし、合意ができない場合には、調停は不成立となり、審判手続きに移行します。
審判手続きとは
審判手続きでは、当事者から提出された書面や証拠を基に、財産分与に関する最終的な判断が裁判官から出されます。
審判の手続きにおいては、調停手続きのような話し合いの要素は薄く、裁判官が事実の認定と法的な評価により、終局的な判断をします。ただ、審判においても、裁判官から和解の勧告を受けることはよくあります。
審判書を受けた日の翌日から2週間であれば不服申立て(即時抗告)をすることができます。この2週間の期間内に即時抗告をしなければ審判は確定します。
調査嘱託を行う
相手方の財産調査のため、裁判所の調査嘱託を利用することがあります。
財産分与は、夫婦がそれぞれの共有財産を開示し、共有財産の多い方が少ない方に財産を分配する制度です。しかし、常に相手方が共有財産の全容を任意に開示するとも限りません。相手方の共有財産が分からなければ、分かっている範囲でしか財産分与は認められません。
そのため、財産分与を考えている場合には、同居期間中から相手方の共有財産の情報を収集するように努めます。仮に、共有財産の情報を十分に収集できていない場合でも、金融機関名と支店名が分かれば、裁判所を通じて、金融機関に対して相手方の財産状況の開示を求めることができます。これを調査嘱託といいます。支店名まで特定できない場合、支店名まで特定しているものの、それを裏付ける根拠がない場合には、裁判所は調査嘱託を採用しないことがあります。
弁護士照会(23条照会)を利用する
相手方の財産を調査する方法の一つとして弁護士会照会(23条照会)があります。
弁護士会照会としては、弁護士法23条に基づき、弁護士会を通じて官公庁や金融機関等の団体に対して、財産の情報等を調査・照会する制度です。
弁護士会照会は、委任を受けた弁護士のみが利用できる手続きです。ただ、個人情報の関係で、確定判決や確定した審判等がない場合には、回答を拒否されるケースも多々あります。
財産分与の期間を過ぎても請求できることも
財産分与の2年の期間が経過したとしても、すぐに諦める必要はありません。相手方に対して財産分与やその他の請求をすることができる場合があります。
相手方が同意する場合
財産分与の2年の期間が過ぎても、相手が財産分与の請求に任意で応じるのであれば、財産分与してもらえます。
しかし、既に離婚している男女が、財産分与に本来応じる必要がないのにこれに応じる理由はありません。そのため、相手方が、期間経過後に財産分与に応じる大きなメリットがない限り、2年の除斥期間経過後に財産分与に任意に応じることはほぼありません。
隠し財産が発覚した場合
相手方が、財産分与の対象とするべき共有財産を意図的に隠すなどした場合には、不法行為に基づく損害賠償請求ができる可能性があります。
財産分与の対象財産は、婚姻期間中に築いた共有財産です。共有財産の中には、不動産、預貯金、生命保険の解約返戻金、有価証券、退職金などが含まれます。
相手方が、共有財産の開示に任意に応じる場合には問題ありません。しかし、相手方が自身の財産を守るために、財産の開示に協力しないことは多々あります。その場合には、財産分与の請求側において、相手方の共有財産の内容や金額を証明しなければなりません。
しかし、相手方が財産隠しを行ったり、詐術を用いるなどして、財産分与の対象となる財産がないものと誤信させた場合には、不法行為に基づく損害賠償が認められる余地があります。
不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年間請求しないときは、時効によって消滅します。
【参考裁判例】浦和地裁川越支部判平元・9・13
国債のうち金200万円分については夫婦の共有財産に属しており、したがって、離婚に際しては財産分与の協議対象とすべき財産であったことになる。
それにもかかわらず、原告は被告に対しそれを秘していたことから、被告は原告に対する共有持分権ないしは財産分与請求権の行使をする機会を失ってしまったことになる。
そうすると、原告の右行為は、被告に対する共有持分権侵害の不法行為ということになる。
財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となる財産は多岐にわたります。
現金
現金も共有財産となります。しかし、現金については、預貯金のように取引履歴が記録されていません。そのため、配偶者が共有財産となる現金を持っていることを証明することは簡単ではありません。
預貯金
典型的な財産が預貯金です。夫婦本人名義の預貯金だけでなく、子供や第三者名義の口座であっても、名義を借りているだけで、その実質は配偶者の資産であれば財産分与の対象となります。他方で、独身時代から持っている預貯金は特有財産として対象から外れます。
不動産
自宅不動産をはじめとした不動産も共有財産となります。相続や贈与を受けた不動産は特有財産として財産分与の対象から除外されます。
不動産を財産分与の対象とするとしても、いくらで計上するのか、つまり、不動産の評価額が問題となることが多く、不動産の査定書や鑑定書を提出して、自身に有利な評価額を主張することが一般的です。
生命保険の解約返戻金
生命保険や学資保険に加入している場合、その解約返戻金も財産分与の対象となります。実際に解約する必要はありませんが、別居日時点で解約した場合に支払われる解約返戻金が対象となります。
株式その他金融資産
株式や投資信託などの金融資産も財産分与の対象となります。別居日時点の銘柄や数量が対象となりますが、その評価時点は別居日ではなく離婚時となります。
退職金
退職金も財産分与の対象となります。
しかし、実際に退職をする必要はありません。別居日時点で退職したことを仮定して、勤務先から支給される退職金額が共有財産となります。ただ、退職金額のうち、結婚する前の独身自体の期間にあたる部分は財産分与の対象から外れます。
関連記事|退職金も財産分与の対象になるのか?弁護士が詳しく解説します
借金
借金そのものは、財産分与の対象にはなりません。つまり、財産分与により、借金の半分を相手方に負担させることはできません。ただ、夫婦の共同生活のための借金や住宅ローンを、プラスの財産と相殺する限りで、債務を考慮することはできます。
年金分割
財産分与とは別の制度にはなりますが、離婚に際して年金分割を求めることもできます。ただ、年金分割の対象は、婚姻期間中の厚生年金保険料の納付記録に限ります。国民年金部分は対象外です。実際に支給される年金を半分にするものではなく、保険料の納付記録を分割するものです。
財産分与の問題は弁護士に相談しよう

離婚時に財産分与の請求しなかった場合には、2年が経つまでに調停等の手続に着手しなければなりません。調停の準備には専門的な部分も多く、予想以上の手間と時間を要することもあります。
申立ての準備に時間を費やしてしまい、いつの間にか2年の期限を徒過してしまうリスクもあります。1人で抱え込まず、まずは弁護士に相談することが重要です。
弁護士に依頼するメリット
- 期限内に確実に財産分与の調停申立てができる
- 財産分与の手続を一任できる
- 離婚全般について相談できる
- 自身に有利な条件を教えてもらえる
初回相談30分を無料で実施しています。
面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
お気軽にご相談ください。
対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。