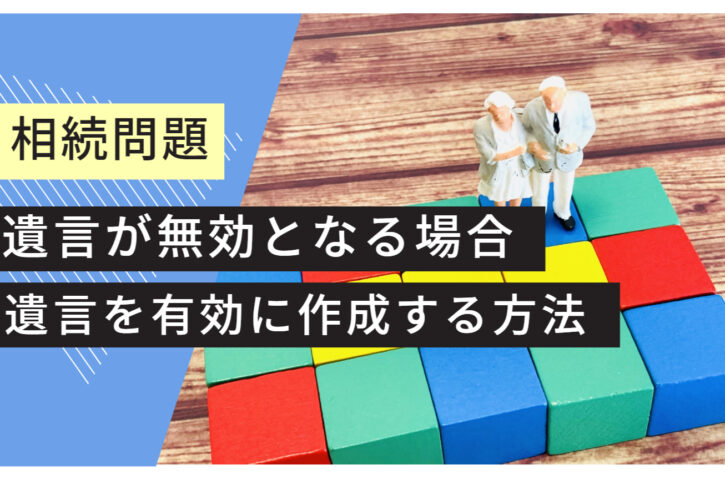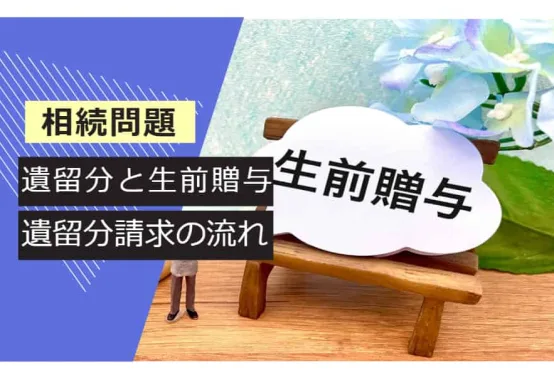せっかく遺言書を作成しても、無効になってしまっては意味がありません。
遺言者の意思を実現させるためにも、遺言が無効となる事態は回避しなければなりません。
遺言書には、守らなければならないルール・要式があります。自筆証書遺言であれば、全文を手書きが作成する必要があります。署名や年月日の記載も必要です。これらの要式に間違いがあれば遺言は無効となります。また、要式を守っていても、認知症等で意思能力が低下している状況で遺言書を作成すると、遺言の効力は否定されます。
自筆証書遺言の要式違反であれば、ある程度客観的な判断できますので、遺言の無効確認は難しいとまではいえません。ただ、遺言書の筆跡が遺言者ではない場合には、筆跡鑑定を行う必要があるため、その判断は簡単ではありません。
他方で、遺言能力がないことを理由とする場合、年齢、遺言の内容、認知症等の判断能力の程度、遺言を作成する経緯などを総合的に判断しなければなりません。そのため、遺言能力を理由とした遺言無効は難しいことが多く、特に、公正証書遺言であれば、さらに困難となるケースも多いでしょう。
遺言が無効になれば、相続人全員が遺産分割協議を行う必要があり、相続人に大きな負担を生じさせます。場合によっては、遺産分割の調停や審判手続きまで発展することもあります。
このような事態にならないためにも、早い時期から遺言書の作成を行い、無効とならないように弁護士にチェックをしてもらうことが大切です。
遺言が無効になるとどうなるのか?
遺言が無効になれば、遺産分割協議をしなければなりません。これにより相続人間の対立が生じ、様々な負担が相続人に発生します。
① 遺産分割協議が必要になる
遺言書が無効になると、その遺言書の内容通りに遺産を取得することができません。
遺言の無効により、遺言書がないのと同じ状態になるので、遺言書を作成した意味がなくなってしまいます。
つまり、相続人による遺産分割協議をしなければ、遺産を取得することができません。
また、相続人ではない人は遺産を取得することができなくなります。
② 相続人間の対立が激しくなる
さらに、遺言書に疑義がある場合には、遺言書が「有効」と主張する相続人と「無効」と主張する相続人との間で、遺言書の有効性を巡ってトラブルになってしまうケースが多数です。
その上、遺言が無効か否かは、簡単に判断することができません。
裁判になるケースも多いため、長期間にわたって係争状態となってしまいます。
このような事態を避けるため、遺言書が無効になるのはどういったパターンがあるのか、把握しておきましょう。


遺言書が無効になる場合とは
遺言は、①民法で定められている要式に違反すると無効となります。また、法律の要式に違反していない場合であっても、②遺言者に遺言をするだけの能力(遺言能力)がない場合にも遺言は無効となります。
本来、遺言者は、自由に自身の財産を誰に渡すのかを自由に決めることができます。しかし、遺言書のルールが守られていない遺言書まで有効にしてしまうと、遺言者の真意とは異なる遺産分けが行われてしまうリスクがあります。そこで、民法で定められた遺言書だけが有効な遺言書となります。
また、15歳以上であれば遺言を作成することは認められています。しかし、自分の財産を誰にどの程度遺すのかを判断できるだけの十分な判断能力がなければ、遺言書は遺言者の真意によって作成されたものとはいえません。そのため、遺言能力がない状況で作成された遺言書も無効として扱われます。
以下では、遺言書が無効になる場合や無効になると生じる事態を詳しく説明していきます。

遺言書の要式(ルール)違反で無効となる場合
要式違反で遺言が無効になる多くのケースは自筆証書遺言の場合です。
自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自筆で書く必要がある遺言書です。自筆証書遺言の作成方法(要式)は民法で詳細に規定されています。この要式を守らずに作成すると遺言が無効になる可能性があります。
自筆でない部分がある
自筆証書遺言は、遺言者が全文を自署で書かねばなりません。
パソコンを使ってはいけませんし、他人に代筆させてもなりません。
ただし、財産目録の部分だけはパソコン作成や預貯金通帳のコピー添付なども認められています。
ところが自筆証書遺言でも、誰に何をどの程度相続させるのかといった、全文を自筆せず、パソコンなどで作成してしまう方がいます。財産目録を除いた本文は全て自筆であることが必要です。
その場合、遺言書が無効になってしまうので、パソコンなどを利用しないよう注意しましょう。
署名がない又は偽造されている
遺言書を完成させるには遺言者の「署名押印」が必要です。
ただし自署で遺言書を作成すると達成感があり、ついつい署名押印をしないまま保管してしまう方がいます。
また、署名捺印があったとしても、遺言者本人の自署ではなく偽造されたものである場合にも無効となります。遺言者本人の自署であるか否かを確認するために、筆跡鑑定を利用されることもあります。
署名のない遺言書は全体が無効になってしまうので、くれぐれも署名を抜かしてしまわないように注意しましょう。
捺印がない
署名がなされていても、捺印を忘れてしまうと遺言は無効となります。
印鑑は実印である必要はなく認印でも有効です。また、捺印は、拇印や指印でも良いとされていますが、できれば印鑑を用いて捺印するべきです。
日付がない
遺言書には日付が必要です。
複数の遺言書がある場合には「日付の新しい方」が優先されるというルールもあります。
ところが、遺言書に日付を入れないまま保管してしまう方もおられます。
日付がない遺言書は無効になってしまうので、遺言書を自筆する場合でも必ず日付を入れましょう。また、「令和6年1月吉日」といった記載では作成日の特定ができないため、無効となります。
なお、日付も自筆する必要があります。スタンプ印を使ったり日付をパソコンで入力したりしないように注意してください。
加除訂正方法が間違っている
遺言書を自筆で書くとき、間違ってしまうケースも珍しくありません。
遺言書を間違ったときの訂正方法は法律によって定められています。
遺言者が修正ペンなどで適当に修正すると、無効になってしまうので注意が必要です。たとえば遺言書の一部をカットしたい場合には、カットする部分に二重線を引いてその二重線の近くに訂正印を押します。
そのうえで、遺言書の末尾や訂正した箇所の近くに「11行目の第3条全体を削除」などと訂正内容を書き、署名しなければなりません。
捨印による修正は、間違った修正方法となります。間違った修正方法により、遺言全体が無効となる可能性があります。
加除訂正方法がわからない場合には、弁護士にチェックを依頼したり遺言書全文を書き直したりすると良いでしょう。
遺言の要式違反の注意点
遺言の要式違反の関係でよくある疑問とその回答を紹介します。
封印をする必要があるのか?
遺言書が封筒に入れたとしても、法律的に封印する必要はありません。仮に封印がなくても遺言が無効になることはありません。
ただ、封印された遺言書の開封は、家庭裁判所の検認手続きで行う必要があるため、遺言書の発見時には注意が必要です。
勝手に開封すると無効になるのか?
遺言書が封筒に封印されている場合、これを検認手続きを経ずに勝手に開封したとしても、直ちに遺言が無効になるわけではありません。
確かに、自筆証書遺言が封印されている場合、家庭裁判所の検認手続きを通じて開封する必要があります。勝手に開封すると、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。
そうだからといって、遺言が無効となるわけではないです。また、遺言を隠したり、偽造変造等をしているわけではないため、相続欠格として相続権を失うわけではありません。
法務局に預ければ遺言が有効となるのか?
自筆証書遺言を作成すると、法務局で預かってもらえます。
法務局に預ける際には担当者に遺言書の内容を見てもらえるので、「遺言書は有効と確認された」と思い込んでしまう方が少なくありません。
しかし遺言書を法務局に預けたとしても、遺言書が無効になる可能性はあります。法務局の担当者は遺言書の有効性を判断しているわけではないためです。
法務局に預けるとしても、遺言書の有効性については遺言者が責任を持たねばなりません。要式不備に不安があるなら、公正証書遺言を作成すると良いでしょう。
遺言能力がないために遺言書が無効となる場合
遺言書の作成時、遺言者に遺言を作成するだけの判断能力がない場合、その遺言書は無効となります。
遺言能力とは、「遺言内容を理解し、遺言の結果を弁識し得るに足る意思能力」をいいます。民法では、その基準を満15歳としています(民法961条)。
精神上の障害や疾病の有無や程度から判断する
遺言者が作成時に遺言を作成する能力があったかを医学的に説明できるかがポイントとなります。
医学的に遺言能力があるかないかは、介護記録、医療記録、介護認定記録等の資料から判断していきます。また、要介護認定を受けている場合には、その診断書や認定調査票などの資料から遺言能力の有無を判断することもあります。
遺言の内容や難しさ
遺言書の内容が複雑困難なものであれば、遺言は無効と判断される可能性があります。
遺言書の内容が、1人の相続人に全て相続させるといったシンプルな内容であれば、高齢の遺言者でも作成することは可能です。
しかし、細かい取得割合を記載したり、細かな予備的な遺言を記載するなど、およそ高齢の遺言者が理解できない複雑な遺言内容であれば、本人の意思が反映されていないとして無効になる可能性があります。
遺言の内容の複雑さと遺言者の年齢・判断能力の程度に応じて検討されます。
遺言内容の合理性や動機
遺言の内容が不自然である場合にも遺言の効力が否定される事情となります。
例えば、遺産を受ける相続人との人間関係が希薄であるのに、その相続人に全ての遺産を渡すような遺言の内容は不合理といえるかもしれません。
かつての遺言者の思いや意思と明らかに反するような内容の遺言書についても、遺言の効力を否定する事情のひとつになります。

公正証書遺言でも無効になるケース
公正証書遺言は公証人が職務として作成してくれる遺言書です。公証人が公文書として作成するので、自筆証書遺言のように要式不備で無効になる可能性はほぼありません。
意思能力が低下してから遺言書が作成された場合
ただし公正証書遺言でも、意思能力が低減している場合には遺言は無効になる可能性があります。
「遺言能力」が遺言の作成に必要
遺言書を作成するには遺言者に遺言能力が必要です。
つまり、遺言者が、遺言の内容とこれによって生じる結果を判断できる能力を有していることが必要となります。詳細は上述のとおりです。ただ、公正証書遺言の場合には、公証人によるチェックが行われるため、無効となるケースはあまりありません。
公証人による遺言能力のチェック
公正証書遺言を作成する場合、公証人による意思確認を行います。公証人によっては、長谷川スケールといった認知機能テストを実施することもあります。
公証人が、遺言者の意思能力が低減していると判断する場合には、公正証書遺言の作成が中止されることがあります。
そのため、公正証書遺言が作成できているということは、遺言者に遺言能力があったことを推認させます。
公正証書遺言が無効となることも
しかし、遺言者の意思能力の有無を十分にチェックされることなく、公正証書遺言が作成されてしまうケースがあります。
過去の事案で、遺言者に成年後見人が就いているのに、これを明かさずに公正証書遺言が作成されたため、公正証書遺言であっても無効とされたケースがありました。
そのため、有効な遺言書を作成するには、遺言者の意思能力がはっきりしているうちに対処する必要があります。
遺言書の要式違反がある場合には無効となる
公正証書遺言でも、必要とされる手続きを踏まずに作成されている場合には無効となります。
公正証書遺言が有効に成立するためには、「口授」が必要となります。口授とは、遺言者自身が公証人に遺言の内容を直接口頭で伝えることを言います。遺言者が病気のために遺言の内容を伝えることができず、単に肯定又は否定の挙動を示しただけの場合には、「口授」があったとはいえません。また、遺言者が公証人の手を握り返したにすぎないような場合にも言語をもって陳述したとはいえないため、「口授」したとはいえません。
このように遺言者による「口授」が適切に行われずに公正証書遺言が作成された場合には、その遺言は無効になります。
関連記事|遺言書を書くべき人とは?遺言のメリットを弁護士が解説します
遺言が無効となる事例を紹介
遺言能力がないことを理由に自筆証書遺言が無効になった事例(東京地判平成26年1月30日)
| 事例 | |
| 作成当時年齢 | 86歳(男性) |
| 遺言内容 | 全て相続人1人(A)にに相続させる |
| 疾病 | 認知症あり |
| 判断内容 | |
| ・遺言の内容は、財産の全てを特定の相続人に相続させるシンプルな内容 ・遺言書作成当時86歳で高齢 ・診断書に「日常生活,財産管理等の認知能力に著しい低下を認める。」と記載 ・鑑定書に「現在居住している場所は答えられず」「現在重度のアルツハイマー型認知症に罹患、時や場所、人の見当識障害を認め、認知機能は著しく低下。社会生活上、状況に即した適切な判断をする能力は低下。自己の財産を管理・処分するには常に援助が必要。」と記載 ・何らかの形で遺言書作成に際し遺言内容にAの意図が反映されたというべき。 | |
遺言能力がないことを理由に公正証書遺言が無効となった事例(東京地判平成28年3月4日)
| 事例 | |
| 作成当時年齢 | 94歳 |
| 遺言内容 | 過去の遺言を全て撤回し,全ての不動産及び会社の株式全部をAに、金融資産をA、B、Cに3分の1ずつ相続させた上で、遺留分減殺はAに相続させる金融資産からすること、遺言執行者にAに指定する内容 |
| 疾病 | 認知症の記載はない |
| 判断内容 | |
| ・遺言者はBに会社経営を引き継がせることを強く望みつつ、相続人間の平等を保つよう配慮していた。 ・本件遺言は他家に嫁いだAに相続させるものであり、遺言者が明確に示した意向と根本的に異なる内容。 ・遺言書の作成手続きは、A及びその夫の関与の下に進められており、遺言書作成前日にはAが遺言者宅玄関鍵を交換し、遺言者との接触をさせないようにしていた。 ・遺言書作成当時94歳の高齢・遺言書作成から12日後の入院直後はせん妄状態が継続し、治まった後も簡単な意思表明すら口頭でも筆談でもできない状態に陥っていた | |
口授がないことを理由に公正証書遺言が無効になった事例(東京高判平成30年7月18日)
| 事例 | |
| 作成当時年齢 | 88歳 |
| 遺言内容 | 全財産をAに相続させる |
| 疾病 | 認知症認定なし |
| 判断内容 | |
| ・遺言書作成日であるや前日17日時点でも意識障害があり、カルテ上JCS3あるいはJCS10とされ、自分の名前や生年月日が言えない状態であったこと ・遺言者は公証人に対して肯定する動作や発言をしただけで具体的な遺言内容を自ら述べていない。 ・遺言の直近時期に遺言の内容が遺言者から直接確認された客観的な証拠もなく、遺言者の希望する具体的な遺言内容が記載された文書が作成された事実も証明されない。 | |
遺言書が無効にならないための対処方法
遺言書が無効にならないためにはどのような点に注意すれば良いのでしょうか?以下では遺言書が無効にならないための対処方法を弁護士が法的な観点からお伝えします。
遺言書の要式を正しく知る
まずは遺言書に要求される要式を正しく知ることが大切です。
特に自分一人で自筆証書遺言を作成する場合、正しい作成方法を知らないと遺言書は無効になってしまいやすい傾向があります。
遺言書を作成する前に、自筆証書遺言の作成方法を調べて間違わないように正しい方法で作成しましょう。
公正証書遺言を利用する
自己判断で自筆証書遺言を作成すると、どうしても間違いが起こりやすくなります。
死後に発見されないリスクもありますし、発見した相続人が隠したり破棄したりする可能性もあります。
さらに、自筆証書遺言の場合には、裁判所の検認手続も必要となります。
このような自筆証書遺言のリスクを低減するには、公正証書遺言を作成するようおすすめします。
公正証書遺言であれば、公証人が職務として作成するので、要式不備で無効になる問題は考えられません。また公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるので、紛失や破棄などのおそれもありません。
相続人は公正証書遺言の検索サービスを利用できるので、発見されないリスクも低減できるでしょう。
心配なら遺言執行者をつけておくと、より確実に遺言内容を実現できます。
遺言書を無効にしたくないなら、公正証書遺言を作成するようおすすめします。
遺言者が元気なうちに作成する
遺言者の認知症が進行してから遺言書が作成されると、相続人間で遺言者の意思能力が争われてトラブルになる可能性が高まります。
その結果、遺言書が無効になってしまうケースも少なくありません。
遺言書を無効にせずに確実に遺志を実現したいなら、遺言者が元気なうちに作成しておくべきです。
先延ばしにしているとせっかく作成した遺言書がトラブルの種になってしまう可能性もあるので注意しましょう。
弁護士のチェックを受ける
遺言書を作成するときには、弁護士によるチェックを受けるようおすすめします。
弁護士が内容をチェックすると、遺言書に不備がないと確認されるので要式不備によって無効になる可能性は通常なくなるでしょう。
弁護士を遺言執行者にしておけば、死後に弁護士が責任もって遺言内容を実現するので、希望する遺産分割の方法などが現実に執行されやすくなります。
相続人に預金払戻しなどの手間もかけずにすみますし、相続人間における相続トラブルも避けやすくなるでしょう。
遺言書を無効にしたくない場合や遺言書によるトラブルを避けたい場合などには、弁護士に遺言書の作成サポートを依頼するのがおすすめです。
遺言無効を争う方法・手続き
遺言の効力を争う場合、調停手続き又は訴訟手続きを行います。
調停手続きによる争い方
遺言無効を争う場合、まず家庭裁判所に対して遺言無効確認の調停申立を行います。
遺言無効の問題は、いきなり訴訟提起するのではなく、まずは話合いのプロセスである調停手続きを先行させなければなりません(調停前置)。ただし、対立関係が強く話合いによる解決がおよそ期待できない場合には、調停手続きを経ずに訴訟手続きから始めることもあります。
調停手続きは、家庭裁判所の調停委員が当事者を仲裁して紛争を話合いにより解決させていく手続きです。話合いにより解決できる場合には、調停が成立します。
他方で、話し合いを通じても解決できない場合、調停は不成立となり調停手続きは終了します。
訴訟手続きによる争い方
訴訟提起をして、遺言の有効・無効を争うことがあり、一般的な争い方です。
訴訟手続きでは、原告と被告が、争点となっている事項について、主張と反論を繰り返し、審理を進めていきます。具体的には、遺言者の遺言能力の有無や要式違反について、具体的な主張と立証を繰り返します。
ある程度審理が尽くされれば、裁判官から和解の勧告が行われます。ただ、遺言が無効となれば、遺産分割協議を行う必要があるなど、相続手続全般に大きな影響を生じさせます。そのため、遺言無効の事案では、通常の事案と比べて話合いによる解決は難しいことが多いでしょう。
和解による解決が難しい場合には、証人尋問や当事者尋問を実施した上で判決手続きに移ります。
遺言無効確認訴訟の管轄
被告(相続人や受遺者)の住所地または被相続人の相続開始時(死亡時)の住所地を管轄する地方裁判所
遺留分侵害額請求もしておくこと
遺言無効が問題となるケースでは、遺言の有効性だけでなく遺留分の問題も生じます。
遺言無効が問題となる多くのケースでは、特定の相続人に遺産の多くが集中する遺言内容となっているため、その他の相続人の遺留分を侵害していることがあります。
遺留分侵害額請求には、消滅時効があります。遺留分の侵害の事実を知ってから1年以内に遺留分請求をする必要があります。
遺言無効を主張しながら、遺言が有効であることを前提とする遺留分請求をすることは矛盾しているようにも思います。しかし、遺留分の消滅時効の問題もあるため、主位的には遺言無効を主張しつつ、遺留分侵害請求もしておくことが無難です。
遺言書を作成するなら弁護士へ相談を

遺言書を作成するとき、自己判断で自筆証書遺言を作成しても無効になってしまうケースが多々あります。
せっかく作成した遺言書を無効にしないためにも、弁護士に遺言書作成のサポートを依頼しましょう。
難波みなみ法律事務所では遺言書作成や相続トラブルの解決に力を入れています。遺言書を作成されたい方、遺言書の有効無効をめぐってトラブルになってしまった場合などにはお気軽に弁護士までご相談ください。
当事務所では、初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。