もしも自分の所有する不動産が、身に覚えのない第三者に占拠されてしまったら、一体どうすれば良いのでしょうか?
「まさか自分が…」と思っていても、決して他人事ではありません。賃貸物件について、借主が使用していると思っていると、実は借主ではない第三者が借主に代わって建物を権原なく占有していることがあります。
この記事では、実際に不法占拠が発生した場合に、所有者が取るべき具体的な対処法を、所有者が取るべき手順に沿ってわかりやすく解説します。また、対応する上での注意点や、専門家への相談についても触れていきますので、ぜひ参考にしてください。
土地や建物、本当に「不法占拠」?まずは状況を確認しよう
ご自身の所有する土地や建物に、見知らぬ第三者が勝手に住み着いている状況に直面した場合、大きな驚きと不安を感じるのは当然のことです。しかし、動揺したまま感情的に対処することは、かえって問題を複雑にしたり、さらなるトラブルを引き起こしたりする可能性も少なくありません。不法占拠への対応は、最初の段階で冷静に、そして慎重に状況を把握することが極めて重要となります。
その後の法的な手続きを適切に進めるための大前提となるのが、現在の占有状態が、法的な権利に基づかない真の「不法占拠」にあたるのかを正確に見極めることです。単に見知らぬ人がいるというだけでなく、その人物が本当に何の権利も持たない状態なのかを確認しなければなりません。次の項目では、不法占拠の法的な定義について掘り下げるとともに、現在占有している人物が、実は賃借権などの何らかの権利を有していないかを確認するための具体的な方法について詳しく解説していきます。
不法占拠の定義とは?
不法占拠とは、法律上の占有権原を持たないにもかかわらず、土地や建物を事実上支配し、利用している状態を指します。ここで言う「正当な権原」とは、賃貸借契約や使用貸借契約、地上権など、その不動産を使用・収益することが法的に認められた根拠のことです。すなわち、所有者の同意や有効な契約に基づかずに、無断で他人の不動産に立ち入って占有している状態を指します。
この不法占拠にあたるか否かを判断する上で、最も重要な基準となるのが、占有している人物に正当な権原があるか、ないかという点です。
たとえば、過去に賃貸借契約を結んでいたとしても、契約期間が終了したり、家賃滞納などで賃貸借契約が解除されたりした後も退去せずに居座る場合は、もはや正当な権原がないため不法占拠となり得ます。また、全く面識のない第三者が所有者の知らない間に空き家に勝手に住み着くケースなども、法的な権原がなければ原則として不法占拠に該当します。
不法占拠者に権利がないかを確認する方法
不法占拠と判断する前に、まずは現在その不動産を占有している人物が、法的に使用を認められる何らかの権利(賃借権、使用貸借権、地上権など)を有していないか確認することが重要です。たとえ書面での契約がなくても、口頭での合意によってこれらの権利が有効に成立するケースもあります。安易に不法占拠だと決めつけないよう注意が必要です。
例えば、借主が第三者に無断で転貸している場合、その第三者は所有者との関係では占有権原を有さず不法占拠となります。
他方で、借主本人ではない第三者が賃借物件を使用していても、その第三者が借主の家族である場合、法人である借主の代表者や従業員である場合、その第三者は単なる占有補助者となるため、不法占拠にはなりません。
このように建物を使用している人がたとえ知らない人であっても、安直に不法占拠と決めつけるのではなく、借主との関係性を確認する作業を経ることが必要となります。


絶対にやってはいけない!自力救済が招くさらなるトラブル
たとえご自身の所有する不動産が不法占拠されている状況であっても、所有者が自らの実力で相手を強制的に退去させる行為は「自力救済」と呼ばれ、日本の法律では原則として禁止されています。法的な手続きを経ずに、実力をもって権利を回復することは認められていません。
もし自力救済を行った場合、思わぬトラブルを招く危険性が高まります。以下では、不法占拠において、やってはいけない事項を紹介します。
勝手に鍵を交換する、荷物を運び出すのは犯罪行為
たとえご自身の不動産が不法占拠されている場合でも、所有者が法的な手続きを経ずに、自らの実力で不法占拠者を排除することは「自力救済の禁止」という原則に反し、日本の法律では許されていません。もし、所有者が勝手に鍵を交換したり、不法占拠者の荷物を運び出したり、処分したりした場合、自力救済として違法行為と見なされる可能性があります。
具体的には、以下のような行為は犯罪行為とされる可能性もあります。
- 鍵の無断交換:不法占拠者の住居への立ち入りを妨害するものとして、住居侵入罪にあたる可能性
- 不法占拠者の私物の運び出しや処分:窃盗罪や器物損壊罪に該当する可能性
このような自力救済行為を行った結果、所有者が逆に不法占拠者から損害賠償を請求される民事上のリスクも発生します。過去の裁判例でも、家賃滞納者などに対する自力救済行為に対して、所有者や管理会社に対して損害賠償の支払いが命じられたケースが複数存在します。不法占拠者を退去させたい一心での行動が、所有者を加害者の立場にしてしまう危険性を十分に理解しておく必要があります。自力救済は絶対に避けて、適切な法的手段を講じることが重要です。
脅迫や暴力による退去要求のリスク
不法占拠者に対し、感情的に「出ていかないとどうなるか分かっているのか」といった脅迫的な言動を用いることは、刑法上の脅迫罪に該当する可能性があります。「殺すぞ」「痛い目にあわせてやる」などの発言は、生命や身体への害悪の告知と見なされかねません。
また、相手の身体に触れたり、物を投げつけたりする行為は暴行罪にあたり、万が一相手に怪我をさせてしまえば傷害罪が成立し得ます。これらの行為を行った場合、所有者が被害者であるにもかかわらず、刑事罰を受けるリスクが生じます。さらに、感情的な対立が強くなると、相手からの反撃を受け、所有者自身が身体的な危害を加えられる危険性も否定できません。
加えて、こうした脅迫や暴力の様子が相手によって録音・録画されていた場合、その後の法的手続きにおいて所有者側が著しく不利な立場になるだけでなく、逆に不法占拠者から損害賠償を請求される可能性も十分に考えられます。
不法占拠者を退去させるための4つの法的ステップ

不法占拠者との話し合い(任意交渉)で解決できなかった場合、自力救済は法的に認められていないため、裁判所を介した法的な手続きを行うことが、不動産の明け渡しを実現するための唯一の合法的な手段です。
不法占拠者に不動産からの退去を強制するまでには、通常、以下の4つのステップを踏みます。
- 内容証明郵便による明渡し請求
- 占有移転禁止の仮処分
- 建物明け渡し請求訴訟の提起
- 強制執行による立ち退き
訴訟の提起やその後の強制執行といった手続きには専門的な知識が必要で、時間や費用もかかります。そのため、弁護士と連携しながら進めるのが一般的です。各ステップの詳細については、以降で詳しく解説します。
ステップ1:内容証明郵便で「明け渡し請求」を行う
不法占拠者に対し、まずは所有者の明確な意思として、不動産の明け渡しを求める意思表示を行います。この意思表示をするための手段として、内容証明郵便の送付が挙げられます。
内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書が誰から誰あてに差し出されたかということを日本郵便が証明する制度であり、後の裁判になった際には、所有者が不法占拠者に対して明け渡しを請求したことの強力な証拠となります。これは法的措置へ移行する前の最終警告としての意味合いも持ちます。
内容証明郵便には、以下の項目を記載します。
- 明け渡しを請求する物件の特定情報(所在地、物件名など)
- 不法占拠者に対して明け渡しを求める根拠
- 不法占拠者に対する明け渡しを求める明確な意思表示
- 具体的な明け渡しの期限(通常は通知到着後1ヶ月程度)
- 期限内に退去しない場合には、法的措置(訴訟など)に移行する旨の警告
相手がこの郵便を受け取ったという事実も郵便局によって記録されるため、「請求を受けていない」という言い逃れを防ぐことができます。
この段階で弁護士に依頼し、弁護士名義で内容証明郵便を送付することも非常に有効です。弁護士が介入したことが相手に伝わることで、事態の重要性を認識させ、心理的なプレッシャーを与えやすくなります。これにより、裁判に至る前に相手方が任意での退去に応じる可能性が高まることもあります。
ステップ2:「占有移転禁止の仮処分」を申し立てる
建物明け渡し請求訴訟を提起する際、「占有移転禁止の仮処分」の申し立ては重要です。
占有移転禁止の仮処分は必ず行うプロセスではありません。ただ、将来的に、占有者が転々と変わるおそれがある場合には、占有移転禁止の仮処分を得ておくことも検討します。
占有移転禁止の仮処分とは、訴訟が進行している間、不法占拠者が建物の占有を勝手に第三者に移してしまうことを防ぐための保全手続きです。もし訴訟の途中(口頭弁論終結前)で、占有者が別の人に変わってしまうと、所有者が勝訴判決を得ても、その判決は訴訟の相手方(当初の占有者)にしか効力が及ばず、新しい占有者に対しては改めて訴訟を起こす必要が生じる可能性があります。一方、占有移転禁止の仮処分を得ておくことで、口頭弁論終結前に第三者が訴訟の相手方から占有を承継したとしても、強制執行をすることができます(当事者恒定効)。
ステップ3:「建物明け渡し請求訴訟」を提起する
内容証明郵便による明け渡し請求をしてもなお、不法占拠者が任意に退去しない場合、最終的には裁判所に不動産の明け渡しを求める「建物明け渡し請求訴訟」を提起することになります。これは、不法占拠者に対し、法的な根拠に基づいて不動産から退去するよう命じる判決を得るための手続きです。
訴訟は、訴状を裁判所に提出することから始まります。その後、指定された期日に裁判が開かれ(口頭弁論)、双方の主張や証拠の提出が行われます。必要に応じて当事者尋問なども実施され、最終的には裁判官が双方の主張や証拠に基づいて判断を下し、判決が言い渡されます。この訴訟の最大の目的は、「建物を明け渡せ」という法的な命令を含む判決を得ることです。
訴訟で勝訴するためには、所有権があること、そして占有者に正当な権原がないことを証明する強力な証拠が必要です。具体的には、不動産の所有者であることを示す不動産登記事項証明書、不法占拠者との間に賃貸借契約などの権原が存在しないことの証明、そして内容証明郵便の控えやこれまでの交渉経緯を示す記録などが重要な証拠となります。
建物明け渡し請求訴訟にかかる期間は、事案の複雑さや裁判所の状況によって異なりますが、一般的には半年から1年以上を要する場合が多くあります。また、訴訟には裁判所に納める印紙代のほか、弁護士に依頼する場合には弁護士費用が発生します。これらの手続きには専門的な知識が不可欠であるため、弁護士への依頼は必須と言えるでしょう。
ステップ4:「強制執行」で不動産の明け渡しを実現する
建物明け渡し請求訴訟で所有者が勝訴判決を得たにもかかわらず、不法占拠者が任意に退去しない場合、最終的に公権力によって不動産の明け渡しを強制的に実現するのが「強制執行」という手続きです。
強制執行を申し立てるには、訴訟で得た勝訴判決の正本(これは債務名義と呼ばれます)や、その判決が相手に送達されたことを証明する送達証明書など、定められた書類を揃える必要があります。これらの書類とともに、対象不動産の所在地を管轄する地方裁判所の執行官に対して申し立てを行います。
申立てが受理されると、申立てから2週間ほどを目処に、執行官が現地で不法占拠者に対し「催告」を行います。これは、不動産から退去すべき期限を正式に告知する手続きです。もし、この期限までに占有者が退去しない場合、「断行」と呼ばれる強制執行が実施されます。断行では、執行官の指揮のもと、執行補助者である搬出作業員によって不法占拠者の家財道具が強制的に運び出され、占有者が不動産から排除されます。
強制執行には費用がかかります。裁判所に納める予納金として6万円程度が必要となるほか、執行業者に支払う作業員の人件費、荷物の運搬・一時保管費用などがかかります。物件の広さや残置動産の量や大きさにより費用は変動します。これらの費用は債務者である不法占拠者に請求できますが、相手に資力がない場合は回収が困難となるケースも少なくありません。
警察は対応してくれる?「民事不介入」の原則と例外ケース
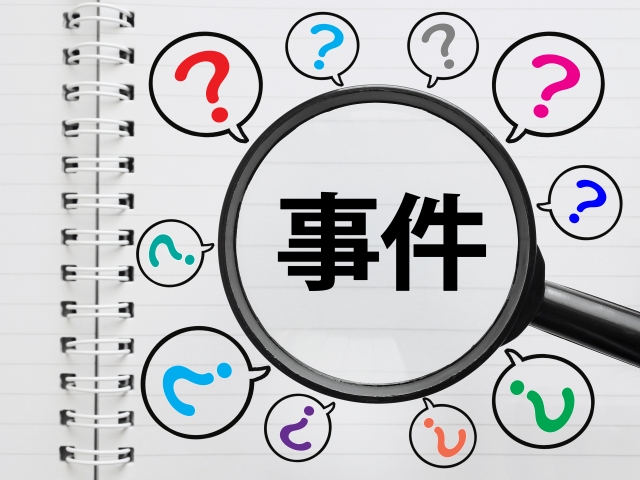
ご自身が所有する不動産が不法占拠されている状況に直面したとき、多くの所有者の方がまず頼るのが警察かもしれません。
以下ではどのような場合に警察への相談が可能となるのか、原則と例外について次項で詳しく解説します。
原則として警察は民事トラブルに介入しない
ご自身の所有する不動産に勝手に他人が住み着いている状況は、所有者にとって非常に深刻な問題です。この状況を解決したいと考えたとき、まず警察に相談することを思いつく方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、日本の警察には「民事不介入の原則」があります。これは、個人間の権利や契約に関する争い、つまり民事事件には、公権力である警察は原則として介入しないという基本的な考え方です。
不法占拠は、不動産の所有権や占有権といった個人間の財産権をめぐる争いと見なされるため、基本的に民事事件に分類されます。そのため、単に不法占拠の被害を警察に訴えても、原則として民事不介入を理由に警察は積極的に動いてくれません。警察に通報しても、「当事者間で解決してください」「弁護士に相談してください」といった対応を促されることが多く、警察が強制的に占有者を退去させてくれることは期待できないのが実情です。
刑事事件として相談できるケースとは
民事不介入の原則により、不法占拠そのものへの介入は難しい警察ですが、不法占拠者の行為が刑法に触れる場合は、刑事事件として相談できる可能性があります。
刑事事件として相談できる可能性のある罪名には、以下のようなものがあります。
- 建造物侵入罪(刑法130条)
- 不動産侵奪罪(刑法235条の2)
- 器物損壊罪
- 脅迫罪
具体的には、正当な理由がないにもかかわらず他人の建物に侵入する行為は「建造物侵入罪」に該当し得ます(刑法130条)。
また、他人の不動産を権原なく占有し、所有者の支配を排除し、自身の支配下に置く行為は「不動産侵奪罪」にあたる可能性があります(刑法235条の2)。
さらに、不法占有者が無断で建物の鍵を変更したり破壊する場合には、器物損壊罪に該当する可能性があります。
所有者が退去を求めた際に不法占拠者から脅された場合は「脅迫罪」などの犯罪が発生しているケースも考えられます。
警察に相談する際は、被害状況の写真や会話の録音など、具体的な証拠を揃えて提示することが重要です。証拠があることで、警察も刑事事件として対応を検討しやすくなります。
長期間の放置は危険!不動産を奪われる「取得時効」とは
不法占拠への対応を怠り、長期間にわたって放置してしまうことには、非常に深刻なリスクが伴います。その最たるものが、ご自身の不動産に対する所有権そのものを失う可能性がある「取得時効」という制度です。
以下の項目では、この取得時効が具体的にどのような条件で成立するのか、そして所有者として取得時効の成立をどのように防ぐべきかについて、さらに詳しく解説していきます。
取得時効が成立してしまう2つの条件
取得時効が成立するには、民法に定められた要件を満たす必要があります。その要件の一つに「一定期間」の占有継続がありますが、この期間は占有を開始した時点における占有者の状況によって、「10年間」と「20年間」の2種類に分かれます。
より短い10年という期間で取得時効が成立するのは、占有を開始した時点で、その不動産を自分のものだと信じており、かつそう信じることに過失がなかった場合、すなわち「善意無過失」であった場合です。このように善意無過失の状態で、他人の不動産であっても所有の意思をもって平穏かつ公然に10年間占有を継続すると、取得時効が完成します。
一方、占有を開始した時点で、不動産が自己の所有物でないことを知っていた場合(悪意)や、過失があった場合など、善意無過失ではなかった場合は、20年間の占有が必要です。この場合も、所有の意思をもって平穏かつ公然と20年間占有を続けることで、取得時効が成立します。
ただ、10年または20年の期間、不動産を占有していれば当然に時効取得が成立するわけではありません。その占有は自主占有であることが必要です。自主占有とは、所有の意思に基づく占有をいいます。そのため、賃貸借や使用貸借により占有を開始した場合には、所有の意思が認められないため、自主占有が否定されるのが原則です。
所有者として取得時効を防ぐための対策
不動産が不法占拠された状態で長期間放置されていると、取得時効が成立してしまい、所有権を失うリスクがあります。これを防ぐためには、時効の進行を止めるための法的な対策を速やかに講じる必要があります。これは、「時効の完成猶予」や「時効の更新」と呼ばれる効果のある行為を行うことで実現できます。
対策の一つは、不法占拠者に対し、内容証明郵便で不動産の明け渡しを「催告」することです。これにより、催告から6ヶ月間、時効の完成を猶予させることができます。
さらに強力な手段としては、建物明け渡し請求訴訟を裁判所に提起することが挙げられます。訴訟を提起すると、裁判が終了するまでの間、時効の完成が猶予されます。そして、訴訟で所有者が勝訴し、その判決が確定すれば、時効は更新され、それまでの時効期間はリセットされます。
取得時効を防ぐための主な対策:
- 内容証明郵便による明渡しの催告
- 建物明け渡し請求訴訟の提起
不法占拠の問題を弁護士に依頼する場合
不法占拠問題を解決するには、高度な法的な専門知識が不可欠です。所有者自身が対応しようとすると、かえってリスクを高めてしまう可能性があります。これまでの解説でも触れたように、内容証明の送付や複雑な裁判手続き、最終的な強制執行など、専門的な対応が求められます。こうした不動産トラブルに直面した際には、弁護士へ相談することが最も安全かつ確実な解決策と言えるでしょう。以下では、弁護士に依頼する具体的なメリット、そして問題解決に強い弁護士の選び方について、詳しく解説します。
弁護士に相談するメリットとタイミング
不法占拠問題の解決には、高度な法的知識と複雑な手続きが伴います。弁護士に依頼することで、所有者は主に3つの大きなメリットを得られます。第一に、内容証明の作成・送付、訴訟提起、そして最終的な強制執行といった一連の法的手続きをすべて一任できます。これにより、専門的な知識がないために生じる不安や、手続きに費やす多大な時間と労力を軽減できます。
第二に、不法占拠者との直接交渉や、感情的な対立からくる精神的な負担を避けることができます。弁護士が代理人として冷静に対応することで、不要なトラブルを防ぎ、精神的な安定を保つことが可能になります。
第三に、個別の状況を正確に分析し、最も迅速かつ効果的な解決策を提案してもらえます。
不法占拠問題の解決に向けた法的手続きは、専門家でなければ判断が難しい場面が多くあります。弁護士に任せることで、法的に最も確実な方法で問題解決を進めることが期待できます。
弁護士に相談すべき具体的なタイミングとしては、不法占拠の事実が発覚した直後、あるいはご自身で退去交渉を試みたものの相手が応じず、対応に窮している時点が挙げられます。問題が判明したらできるだけ早く専門家に相談することで、対応が遅れることによる不法占拠の長期化や、「取得時効」が成立してしまうといったリスクを回避するための適切なアドバイスを受け、早期に手を打つことができます。
不動産問題に強い弁護士の選び方
不法占拠問題の解決を弁護士に依頼する場合、誰に頼むかで結果や進捗が大きく変わる可能性があります。事務所のウェブサイトで解決事例を確認したり、初回相談時に具体的に尋ねたりして、経験と専門知識がある弁護士を選びましょう。
次に、弁護士との相性も重要なポイントです。初回相談などを利用し、専門用語を避け、依頼者にも分かりやすく説明してくれるか、親身になって話を聞いてくれるかなどを確認しましょう。信頼して自身の財産に関わる重要な問題を任せられる弁護士かを見極めることが大切です。
また、料金体系が明確に提示されているかも確認すべき点です。相談料、着手金、成功報酬など、どのような場合にどの程度の費用がかかるのか、契約前に十分な説明がある事務所を選ぶようにしましょう。
将来のトラブルを防ぐ!空き家を不法占拠させないための予防策

これまでは、万が一、空き家が不法占拠されてしまった場合の対処法や法的手続きについて詳しく解説しました。ご紹介した通り、一度不法占拠が発生すると、その解決には多大な労力、時間、そして費用が必要となります。こうした事態を避けるためには、何よりも不法占拠を未然に防ぐための予防策を講じることが重要です。
以下では、不法占拠を防ぐための具体的な予防策をさらに掘り下げてご紹介します。
定期的な訪問と清掃で管理状況を示す
空き家を不法占拠から守るための最も効果的な予防策の一つは、物件が「管理されている状態」にあることを物理的に示すことです。人の出入りがなく、手入れされていない空き家は、不法占拠者にとって狙われやすいターゲットになりがちです。
所有者や代理人が定期的に物件を訪問し、手入れをすることで、「この物件は放棄されていない」という明確なメッセージを発信できます。
また、簡単な清掃や手入れを行うことも大変有効です。建物内部の換気、庭の草むしり、落ち葉の清掃などを行うだけでも、建物の状態維持につながり、放置されている物件という印象を与えにくくなります。
管理委託サービスや警備システムの導入
遠隔地に空き家があり、所有者自身での定期的な管理が難しい場合は、不動産管理会社や空き家管理サービスの利用が有効な選択肢となります。こうしたサービスでは、月に1回程度の定期巡回や清掃、郵便物の整理といった基本的な管理業務を代行してもらえます。これらのサービスを活用することで、物件が第三者によって継続的に「管理されている」状態であることを外部に示し、不法占拠を企てる者にとってターゲットになりにくい環境を作ることができます。
より積極的な侵入対策としては、警備システムの導入も有効です。監視カメラや人感センサー付きライトは、侵入を試みる者への物理的な威嚇効果が期待できます。また、警備会社のホームセキュリティサービスを導入すれば、異常発生時に即座に所有者や警備会社へ通報されるため、早期の対応が可能となります。
売却や賃貸など空き家の活用を検討する
空き家を単に放置し続けることは、経済的・防犯的に様々なリスクを伴います。固定資産税などの税金や管理コストがかかるだけでなく、管理不備により「特定空き家」に指定されると、固定資産税が最大6倍に増額されたり、50万円以下の過料が科されたりするリスクもあります。さらに、手入れされていない物件は不審者にとって狙われやすく、不法占拠の標的になりやすい危険性も高まります。
こうしたリスクを根本的に回避するためには、不動産を適切に活用することが有効な予防策となります。
最も確実な選択肢の一つが「売却」です。売却すれば、管理の負担や将来のリスクから解放され、まとまった現金を得られます。また、「賃貸」という方法もあります。定期的な家賃収入が得られるだけでなく、入居者がいることで建物の状態が保たれ、不法占拠のリスクも大幅に低減できます。
ご自身の空き家の状態や立地条件に合わせた最適な活用方法を検討することが、将来のトラブルを防ぐための重要な一歩です。
不法占拠の問題は難波みなみ法律事務所へ

今回は不法占拠の問題を詳しく解説してきました。不法占拠の形態は様々ありますが、自力執行は回避しなければなりません。自身に所有権があることを理由に、不法占拠者に対して何をしても許されると勘違いしている人は少なくありません。
時間と費用を要しますが、法律に基づく適正な手続きをしっかり踏んだ上で明渡請求を進めるのが必要です。ただ、明渡請求の各手続きには高度な法的知識と経験を求められることもあります。また、不法占有者との直接の対峙には、大きな精神的な負担も伴います。そのような場合には、法律の専門家である弁護士に相談することが望ましいです。
初回相談30分を無料で実施しています。
面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
お気軽にご相談ください。
対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。




























































































