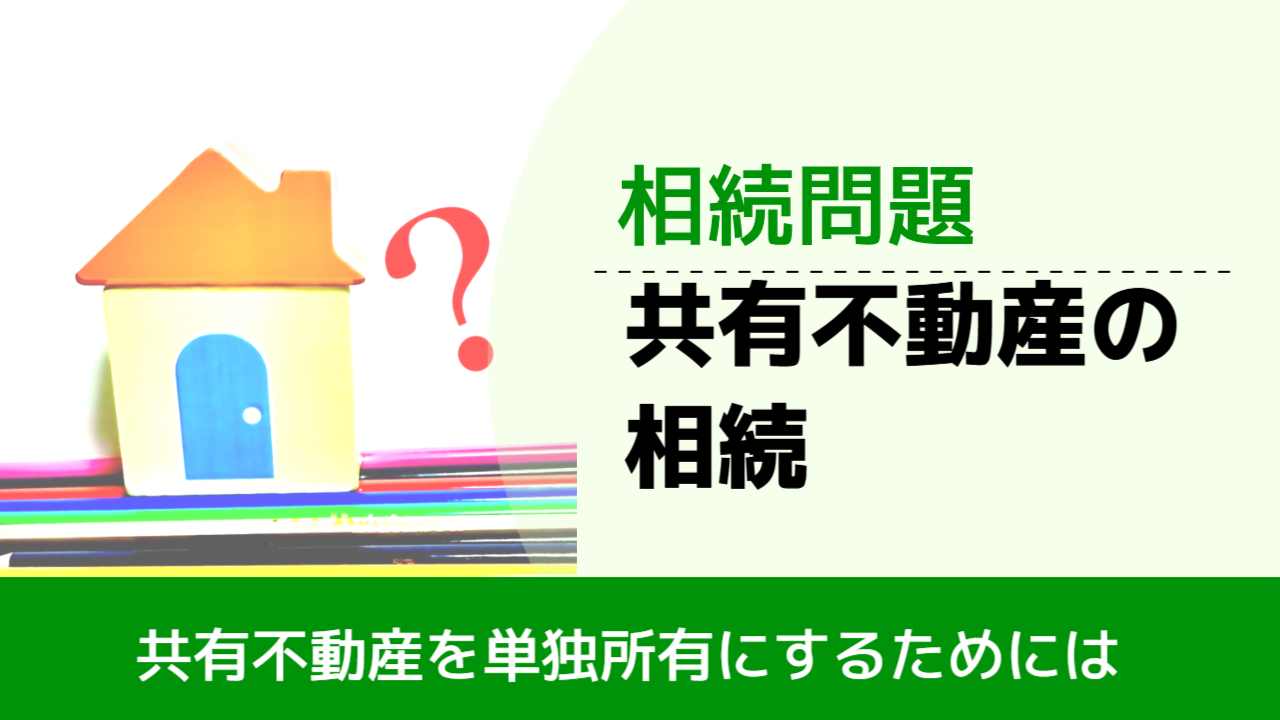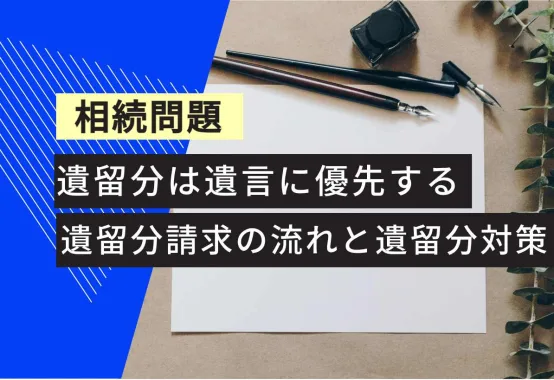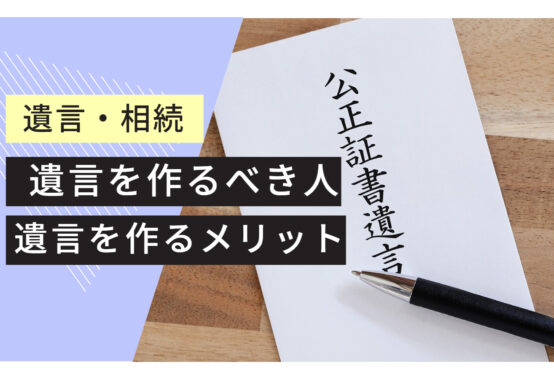共有名義の不動産をお持ちの方で、もし共有者の1人が死亡した場合、相続はどうなるのか、不安に思われる方もいるのではないでしょうか。共有名義の不動産は、単独名義の不動産と比べて手続きが複雑になることがあります。
この記事では、共有名義の家で共有名義者のうち誰か一人が亡くなった場合に、どのような手続きが必要になるのか、注意すべき点は何かをわかりやすく解説します。相続の基本的な知識から、具体的な手続きの流れ、相続税の計算、相続トラブルの回避策まで、初心者の方にも理解できるよう丁寧に説明していきますので、ぜひ参考にしてください。
共有名義の不動産、片方が亡くなるとその持ち分はどうなる?
共有名義の不動産において、共有者のうち一人が亡くなった場合、その方の持ち分が残された共有名義人へ自動的に移ることはありません。
以下では、共有者の1人が死亡した場合に具体的にどのような手続きが必要になるのかを詳しく解説します。
自動的に残された共有名義人が相続するわけではない
共有名義の不動産について、「夫婦で半分ずつ持っている家だから、片方が亡くなれば残された方がすべてを引き継ぐ」と考えている方は少なくありません。しかし、これは誤解です。実際には、亡くなった方の不動産の持ち分は、「遺産」として扱われます。
したがって、残された共有者が亡くなった方の持ち分を自動的に相続することはできません。民法で定められた相続のルールに基づき、故人の持ち分は、配偶者、子ども、親など、その故人の法定相続人全員が引き継ぐ権利を持つ対象となります。遺言書がない限り、この持ち分を誰がどれだけの割合で相続するかは、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)を経て決定されるのが原則です。たとえ夫婦間であっても、他の相続人の権利を無視して残された配偶者が単独で取得することは原則として認められないため、注意が必要です。
故人の持ち分は「法定相続人」が受け継ぐ
故人の不動産の共有持ち分は、民法で定められた「法定相続人」が相続する権利を有します。法定相続人には優先順位が定められており、常に相続人となる配偶者を除き、法定相続人には以下の順位が適用されます。
第一順位は故人の子です。故人の子がすでに亡くなっている場合は、その孫が代襲相続します。
第二順位は故人の親などの直系尊属です。これは第一順位の人がいない場合に適用されます。
第三順位は故人の兄弟姉妹です。これは第一順位および第二順位の人がいない場合に適用されます。
自身より上位の順位の人がいる場合、下位の順位の人が相続人になることはありません。
法定相続人が誰になるかによって、法律で定められた法定相続分も異なります。主な法定相続分の組み合わせは次の通りです。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | その他の相続人の相続分 |
| 配偶者と子 | 2分の1 | 子が残りの2分の1を均等に相続 |
| 配偶者と親 | 3分の2 | 親が残りの3分の1を相続 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹が残りの4分の1を相続 |
このように、故人の持ち分は、残された共有名義人だけでなく、故人の他の親族(例えば前妻の子や故人の兄弟姉妹など)も、新たな共有者となる可能性がある点に注意が必要です。これにより、共有名義人が増え、相続関係が複雑になることも考えられます。
【具体例】夫婦の共有名義で夫が亡くなった場合の相続人
夫婦で共有名義の家を所有している場合、もし夫が亡くなったら、その持ち分は誰が相続する権利を持つのでしょうか。ここでは、夫の家族構成に応じて、法定相続人が誰になり、夫の持ち分をどれくらいの割合で相続するのかを、具体例を挙げて解説します。
| 夫の家族構成(被相続人から見た関係) | 法定相続人 | 相続割合(夫の持ち分に対して) |
| 子供がいる場合 | 妻、子供 | 妻:2分の1、子供:2分の1 |
| 子供がおらず、両親が存命の場合 | 妻、夫の両親 | 妻:3分の2、夫の両親:3分の1 |
| 子供も両親もおらず、兄弟姉妹がいる場合 | 妻、夫の兄弟姉妹 | 妻:4分の3、夫の兄弟姉妹:4分の1 |
パターン1:子供がいる場合
このケースでは、配偶者である妻と子供が相続人となります。夫が所有していた持ち分は、妻が2分の1、子供が残りの2分の1を相続します。もし子供が複数いる場合は、子供たちの間でこの2分の1の持ち分を均等に分け合うことになります。
パターン2:子供がおらず、夫の両親が存命の場合
子供がおらず、夫の両親(直系尊属)がいる場合は、妻と夫の両親が法定相続人になります。夫の持ち分は、妻が3分の2、夫の両親が3分の1を相続することになります。
パターン3:子供も両親もおらず、夫の兄弟姉妹がいる場合
夫に子供も両親もおらず、兄弟姉妹がいる場合は、妻と夫の兄弟姉妹が相続人となります。この場合の夫の持ち分は、妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1を相続する形です。


共有名義不動産の相続手続き|5つのステップで解説
共有名義の不動産に関する相続は、複数の関係者が関わるため、単独名義の場合と比べて手続きが複雑になりがちです。しかし、適切な手順を踏んで進めることで、不要なトラブルを避け、スムーズに手続きを完了させることが可能です。
以下では、共有名義の不動産に関する相続手続きの全体像を把握できるよう、具体的な5つのステップに分けて詳しく解説します。
【STEP1】遺言書があるか確認する
相続手続きの最初のステップは、故人が遺言書を残していたかどうかの確認です。遺言書がある場合、その内容は法定相続のルールよりも優先され、故人の遺産の承継方法が決定されます。遺言書の有無は、その後の手続きの流れや相続人同士の話し合いの内容を大きく左右します。
遺言書には、主に故人自身が手書きする「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」があります。それぞれの保管場所や、発見された際の「検認」という手続きの要否は以下の通りです。
| 遺言書の種類 | 主な保管場所 | 検認の要否 | 補足 |
| 自筆証書遺言(自宅保管) | 自宅(金庫、仏壇など) | 必要 | 家庭裁判所での検認が必要 |
| 自筆証書遺言(法務局保管) | 法務局 | 不要 | |
| 公正証書遺言 | 公証役場 | 不要 |
遺言書が見つかった際には、いくつか注意すべき点があります。特に、法務局で保管されていない自筆証書遺言は、勝手に開封してはなりません。偽造や変造を防ぐため、速やかに家庭裁判所に提出し、「検認」という手続きを受ける必要があります。検認は、遺言書の現状を明確にする手続きであり、遺言の有効性を判断するものではありません。一方、公正証書遺言や法務局に保管されていた自筆証書遺言は検認が不要で、次のステップへスムーズに進めます。
【STEP2】相続人と相続財産をはっきりさせる
遺言書がない場合、故人の財産を誰が引き継ぐのかを明確にするため、次のステップでは「法定相続人」を確定し、すべての「相続財産」を調査します。まず、法定相続人を特定するためには、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)を取得する必要があります。これにより、思わぬ相続人がいないかを確認できます。
次に、共有名義の不動産に限らず、故人が遺したすべての財産を調査し、リストアップします。預貯金、株式、投資信託、生命保険といったプラスの財産はもちろん、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も漏れなく把握することが大切です。調査した相続人と財産については、それぞれ「相続関係説明図」と「財産目録」にまとめることをおすすめします。
【STEP3】相続人全員で話し合う(遺産分割協議)
故人に遺言書がない場合、法定相続人全員で「遺産分割協議」を行い、遺産の分割方法について話し合います。誰がどの遺産をどれくらいの割合で相続するかを決定しますが、相続人全員の合意が不可欠です。一人でも合意しないと成立しないため、全員の同意が求められます。
相続人で遺産分割の合意ができれば、その合意内容は「遺産分割協議書」にまとめます。遺産分割協議書は、以後の不動産の名義変更(相続登記)や相続税申告において不可欠な書類となります。
共有名義の不動産については、配偶者が単独で相続する、あるいは売却して現金で分割するといった選択肢が考えられます。将来的なトラブルを避けるため、相続人全員が納得できる方法を見つけることが大切です。
【STEP4】不動産の名義を変更する(相続登記)
遺産分割協議がまとまり、不動産の相続人が決定したら、次に行うのが、法務局での名義変更手続き、いわゆる「相続登記」です。これは、不動産の所有権を故人から相続人へ正式に移行させるための重要な手続きです。特に、2024年4月1日からは相続登記が義務化され、不動産を取得したことを知った日、または遺産分割協議が成立した日から3年以内に申請する必要があります。この義務を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があり、早めの対応が求められます。
【STEP5】相続税の申告と納税を行う
相続財産が確定し、遺産分割協議が完了したら、最後の重要なステップとして、相続税の申告と納税が必要です。相続税は、故人の遺産総額が「基礎控除額」を超える場合に発生します。基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算され、相続財産がこの額を超えない場合は、原則として相続税の申告は不要です。
相続税の申告と納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限を過ぎると延滞税などが課される可能性があるため、早めの対応が重要です。申告書の提出先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署です。
| 項目 | 詳細 |
| 基礎控除額 | 3,000万円+(600万円×法定相続人の数) |
| 申告・納税期限 | 被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内 |
| 申告書の提出先 | 亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署 |
共有名義の家を「単独名義」にするには?
共有名義の不動産は、複数の所有者がいることで、将来的な売却や管理の意思決定が複雑になりがちです。特に相続が発生すると、新たな共有者が加わり、権利関係がさらに複雑化するリスクがあります。
共有不動産の問題を避けるには、相続のタイミングで、特定の相続人一人の「単独名義」にまとめることが有効な選択肢です。
以下では、単独名義にするための方法について詳しく解説します。
他の相続人に自分の財産を渡して調整する(代償分割)
共有名義の不動産を特定の相続人一人の単独名義にする有効な方法の一つに、「代償分割」があります。これは、不動産を現物で取得する相続人が、他の相続人に対し、自身の相続分に見合う現金などの財産(代償金)を支払うことで調整する方法です。例えば、夫が亡くなり、妻が自宅に住み続けたいと希望する場合、妻が夫の不動産持分をすべて相続し、その代わりに子などの他の相続人へ持分相当額の現金を支払うケースなどが典型です。ただ、代償分割にも注意点があるため、十分に留意しておきましょう。
注意点
- 不動産を取得する側に、他の相続人へ支払うための十分な現金(代償金)が必要となります。
- 代償金の額を巡るトラブルを避けるため、不動産の評価額を相続人全員が納得できる形で決めることが重要です。時価(実勢価格)を基準にするのが一般的です。
- 贈与とみなされるリスクを避けるため、遺産分割協議書に代償分割の旨を明確に記載しておく必要があります。
亡くなった方の共有持ち分を買い取る
亡くなった方の持ち分を相続した他の相続人から、共有名義人である残された人がその持ち分を買い取ることで、不動産を単独名義にできます。共有名義を解消することは、将来的な売却や管理における意思決定の複雑さを避けることにも繋がります。
買い取りの具体的な手順は、以下の通りです。
- 相続人全員で合意を形成する
- 不動産の評価額を算定する
- 合意した価格で売買契約を締結し、代金を支払う
- 所有権移転登記を行う
注意すべき点としては、買い取りのための資金準備が必要となること、そして持ち分を売却した他の相続人には売却益に対して譲渡所得税が課税される可能性があることです。さらに、適正な市場価格からかけ離れた金額で取引すると、贈与税が課されるリスクがあるため、注意が必要です。共有者間で合意が成立しない場合には、共有物分割の調停や裁判といったプロセスに移行させていくしかありません。
共有物分割を行う
共有不動産の共有者の1人が亡くなった場合、亡くなった人の共有持分について遺産分割をした上で、共有持分の買取り交渉を行うことで共有関係を解消するのが原則です。共有持分の買取交渉が難航する場合には、共有物分割の調停や訴訟のプロセスを通じて、共有関係の解消を目指します。
しかし、相続財産である共有持分について、遺産分割されることやく10年を経過した場合には、遺産分割の手続を先行することなく共有物分割を進めることができるようになりました(民法258条の2)。
民法258条の2
- 共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定による分割をすることができない。
- 共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から10年を経過したときは、前項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。
- 相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第1項の規定による請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から2箇月以内に当該裁判所にしなければならない。
所在等不明共有者の持分の取得および譲渡
共有者の所在が不明である場合、その他の共有者は、裁判所に対する請求により、所在等不明の共有者の共有持分を取得できるようになりました(262条の2第1項前段)。複数の共有者が持分取得の請求をした場合には、請求をした各共有者の持分の割合で按分して取得することになります。ただ、所在等不明の共有者の持分が相続財産である場合には、相続開始から10年経過していなければ、持分取得の請求をすることができません。
持分取得が認められると、所在不明の共有者は、持分取得をした共有者に対して、持分の時価相当額の支払いを求めることができます。
相続で揉めないために今からできる3つの対策
共有名義の不動産は、単独名義と比べて法定相続人が複数いる場合に意見の相違が生じやすく、トラブルに発展するリスクがあります。
以下では、後々のトラブルを避けるために有効な以下の3つの対策を紹介し、それぞれの方法について詳しく解説していきます。
夫婦でお互いに「遺言書」を書いておく
共有名義の不動産において相続が発生した場合、遺言書がなければ、法定相続人全員による遺産分割協議が必須となります。この協議がまとまらないと、残された配偶者が希望通りに不動産の持ち分を相続できず、結果として自宅を単独で引き継げなくなるリスクがあります。
そこで、遺言書を作成し「配偶者に自分の持ち分を相続させる」と指定すれば、他の相続人との協議を経ることなく、不動産の名義を配偶者にスムーズに集約できます。これにより、住み慣れた家に安心して住み続けられるという大きなメリットが得られます。将来の安心を確保するためには、夫婦がお互いに、相手に持ち分を相続させる旨の遺言書を作成しておく「双方向の遺言」が非常に有効な対策となるでしょう。
生前に家の名義を整理しておく(生前贈与)
将来の相続トラブルを未然に防ぐため、ご自身が元気な間に、共有持ち分を配偶者や特定の子供に贈与し、名義を一本化する「生前贈与」という方法があります。これにより、遺産分割協議が不要となり、相続手続きをスムーズに進められる可能性があります。
ただし、生前贈与には原則として贈与税がかかり、その税額が高額になる場合もあるため、十分な注意が必要です。
贈与税の負担を軽減するための特例として、「夫婦間の居住用不動産の贈与の特例」、通称「おしどり贈与」と呼ばれる制度があります。この特例は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産またはその購入資金を贈与する際に、最大2,000万円まで贈与税が非課税となるものです。
また、「相続時精算課税制度」を利用することも選択肢の一つです。この制度は、贈与時に一定額まで贈与税が非課税となる一方、贈与者の相続が発生した際には、その贈与財産を相続財産と合算して相続税を計算するものです。
ただし、これらの特例を利用した場合でも、贈与税以外に不動産取得税や登録免許税といった費用が発生します。
共有名義の相続でよくある質問
共有名義の不動産相続は、多くの疑問や不安を伴うものです。 以下では、共有名義の不動産相続に関してよく寄せられる具体的な疑問点に対し、Q&A形式でわかりやすくお答えします。
住宅ローンが残っている場合はどうなりますか?
多くの住宅ローンでは、契約時に団体信用生命保険(団信)への加入が必須とされています。団信は、住宅ローンの契約者に万が一の事態(死亡や高度障害状態など)が発生した際に、生命保険会社が金融機関へ保険金を支払い、その時点で住宅ローンの残債が完済される仕組みです。これにより、残されたご家族がローンの返済に困ることなく、住み慣れた家に住み続けられるという大きな安心が得られます。
ただし、夫婦それぞれが住宅ローンを組むペアローンの場合は注意が必要です。亡くなった方のローンは団信によって完済されますが、残された方が契約しているローンについては、引き続き返済義務が残ります。このため、ご自身のローンの返済は継続して行う必要があります。
相続手続きをしないまま放置するとどうなりますか?
共有名義の不動産で相続が発生し、相続登記をはじめとする手続きを放置すると、多くの不利益が生じる可能性があります。まず、所有者が故人の名義のままだと、その不動産を売却したり、担保に入れて融資を受けたりすることが一切できなくなります。
さらに、手続きをしないまま時間が経過すると、相続人が次々と亡くなり、新たな相続人が増えていきます。このように権利を持つ人がネズミ算式に増加し、最終的には相続人が大人数になるようなケースも発生します。そうなると、相続人全員の合意形成が極めて困難になり、遺産分割協議がいつまでもまとまらない事態に陥りかねません。
また、2024年4月1日からは相続登記が法律で義務化されています。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行わない場合、正当な理由がない限り、10万円以下の過料が科される可能性があります。
加えて、相続人の一人に借金の滞納などがあった場合、その人の持分が債権者によって差し押さえられるリスクがあります。最悪の場合、持分が競売にかけられ、見ず知らずの第三者が新たな共有者となる事態も想定されます。このような状況を避けるためにも、相続手続きは速やかに進めることが肝要です。
相続人の中に連絡が取れない人がいる場合は?
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しないため、もし一人でも連絡が取れない相続人がいると、手続きを進めることができません。このような状況に直面した場合でも、段階的に対処する方法があります。
まず、連絡が取れない相続人の現住所を調査するために、「戸籍の附票」を取得することを試みましょう。戸籍の附票とは、戸籍が作られてから現在までの住所の履歴が記録されている書類です。
ご自身での調査が難しい場合は、弁護士などの専門家へ相談することも有効です。弁護士は職務上の権限に基づき、連絡が取れない相続人の住所を調査できるため、解決の糸口が見つかる可能性があります。
これらの方法でも連絡が取れない場合、最終手段として家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる手続きがあります。不在者財産管理人は、連絡の取れない相続人の代わりに遺産分割協議に参加し、その財産を管理する役割を担います。また、遺産分割審判において公示送達という特殊な送達方法を用いて手続を進められる余地もあります。
共有名義不動産の相続は難波みなみ法律事務所へ相談を

共有名義の不動産において最も重要な点は、共有名義者のうち片方が亡くなったとしても、その持ち分が残された共有者に自動的に移転するわけではないということです。故人の持ち分は『相続財産』として扱われ、配偶者や子などの法定相続人が受け継ぎます。そのため、遺言書がない限り、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの持ち分を相続するのかを明確に合意する必要があります。
複雑な相続手続きを円滑に進め、将来的なトラブルを未然に防ぐためには、早い段階で専門家である弁護士へ相談することが最善の策です。
当事務所では初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。お気軽にご相談ください。
対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。