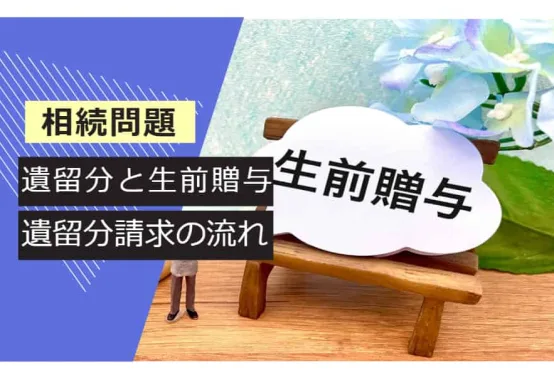叔父や叔母が亡くなった際に、甥や姪が相続するケースは意外と多く見られます。ただし、親や子などの直系の相続とは異なり、どのように相続人が決まるのか、相続分の割合はどうなるのかなど、事前の知識がないと戸惑うこともあるでしょう。
特に相続順位が上位になる人がいない場合や、叔父・叔母の兄弟姉妹にあたる人物がすでに亡くなっている場合に、甥や姪が代襲相続人となる可能性があります。こうした状況では、相続税の加算や、遺留分が存在しない点など、独特のルールを踏まえて手続きを進めなければなりません。
本記事では、甥や姪が叔父・叔母の相続人になるための条件や相続分、手続きの流れ、さらに生前の準備方法などを分かりやすく解説します。正しい情報を押さえることで、相続トラブルの回避やスムーズな手続きにつながるでしょう。
甥・姪が叔父・叔母の相続人になるための条件
まずは、甥や姪がどのような条件で叔父・叔母の相続人となるのかを理解しましょう。
相続には相続順位という仕組みがあり、被相続人である叔父・叔母に配偶者がいる場合は常に相続人となります。また、子がいない、またはすでに亡くなっている、さらに被相続人の両親や祖父母が死亡している場合に初めて兄弟姉妹が相続の順位を得ることになります。その上で、甥や姪が相続人となるのは、叔父・叔母の兄弟姉妹も先に亡くなっているなどの条件が重なった時です。
叔父や叔母の相続人となるケースを具体的に解説していきます。
叔父・叔母の兄弟姉妹が相続人となる場合
叔父・叔母に子がおらず、両親や祖父母もすでに亡くなっているとき、相続人は叔父・叔母の兄弟姉妹になります。
法定相続人が誰になるのかは、民法で具体的に定められています。配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。一方で、子供・両親・兄弟姉妹も相続人となる可能性がありますが、その順位は、【子供→両親(直系尊属)→兄弟姉妹】となります。そのため、叔父や叔母に、子供がおらず、両親も既に他界している場合に、はじめて兄弟姉妹が相続人となります。
子供がいても先に他界しているものの、子供に子供、つまり、孫がいる場合には、孫が代襲相続人となるため、兄弟姉妹が相続人にはなりません。ただし、先順位の相続人が相続放棄をすると、先順位の相続人が存命であっても、兄弟姉妹が相続人となることがあります。
叔父・叔母の兄弟姉妹の代襲相続が発生している場合
叔父・叔母の兄弟姉妹がすでに亡くなっている、もしくは相続欠格や相続廃除により相続権を失っている場合に、甥や姪が代襲相続人として相続人となります。代襲相続では、本来の相続人の地位を子が継承する形を取り、叔父・叔母の兄弟姉妹が相続できない理由があれば、その子にあたる甥や姪が相続人として権利を引き継ぎます。ただし、兄弟姉妹の場合、代襲相続は一代までに限られるので、甥や姪の子どもに引き継がれません、つまり、再代襲は認められません。
相続放棄をしている場合には代襲相続は発生しない
相続放棄を行うと、相続権そのものを放棄したことになり、はじめから相続人ではなかったことになるため、その子に相続権が移るということはありません。つまり相続放棄をすると、代襲相続は発生しません。叔父・叔母の兄弟姉妹が相続放棄を選択した場合、甥や姪が相続人となることはなくなります。


甥と姪が相続人となる時の相続分
甥や姪が相続人となることが決まった場合、実際の相続割合はどのように決まるのでしょうか。
相続分は、配偶者の有無に加えて相続人の人数によって決まります。もし叔父・叔母に配偶者がいれば常に相続人に含まれ、甥や姪の法定相続分は4分の1の相続分を人数に応じて分け合う形になります。また、配偶者が存在しない場合は兄弟姉妹、または兄弟姉妹の子にあたる甥や姪の間で均等に分け合うことになります。
叔父・叔母の配偶者がいる場合
叔父・叔母に夫や妻がいるケースでは、まず配偶者は4分の3の法定相続分を持っています。
法定相続では配偶者の相続分が大きく確保されるため、甥や姪の取り分は配偶者の相続分を控除した残り4分の1を人数で按分することになります。
例えば、姉A、弟B、亡くなった妹の子供2人(甥Cと姪D)の場合、きょうだいの1人当たりの法定相続分は12分の1となり、甥と姪はこの法定相続分を半々で分け合うため、CとDの法定相続分は24分の1となります。
叔父・叔母の配偶者がいない場合
独身または配偶者がすでに亡くなっているなど、叔父・叔母に配偶者がいない場合は、叔父・叔母の兄弟姉妹やその代襲相続人である甥や姪が相続人となり、人数に応じて相続分を分け合います。
例えば、先ほど同様のケースで、姉A、弟B、亡くなった妹の子供2人(甥Cと姪D)の場合、きょうだい1人あたりの法定相続分は3分の1となるため、Cと Dの法定相続分は、それぞれ6分の1となります。
甥・姪が叔父・叔母を相続する時のポイント
叔父・叔母の相続に甥や姪が関与するときには押さえておくべきポイントがあります。
兄弟姉妹やその子どもである甥や姪には遺留分が認められていない点が特徴的です。そのため、遺言書で別の人へ多くの財産を譲ると指定されていたとしても、遺留分侵害額請求をすることが困難になります。その他に、必要となる戸籍謄本もかなりのボリュームになります。
叔父と叔母の相続手続きの注意点を解説します。
甥・姪は遺留分を持たない
子供、配偶者、両親には遺留分がありますが、兄弟姉妹やその代襲相続人である甥や姪には遺留分がありません。
遺留分とは、遺言によっても奪うことのできない最低限守られる相続の権利をいいます。この遺留分は、兄弟姉妹に法律上与えられていません。そのため、兄弟姉妹の代襲相続人である甥や姪も同様に遺留分の権利を持ちません。
遺留分を持たないことの帰結として、叔父・叔母が甥や姪に遺産を一切承継させないような不公平な遺言書を作成していたとしても、甥や姪は遺留分侵害額請求をして、遺産の一部を受け取ることができなくなります。
そのため、甥や姪が相続人となる場合には、遺言書が存在するかどうかの確認が非常に重要です。
相続税が2割加算される
被相続人の配偶者、子供及び両親以外の人が相続人になる場合、相続税が2割加算されて課税されます。
具体的には、叔父・叔母の相続で甥や姪が遺産を相続すると、相続税は2割加算されます。そのため、甥や姪の相続税負担は大きくなる可能性があります。ただし、遺産額が相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えない場合には、相続税の課税を受けません。
甥・姪の子どもの再代襲しない
兄弟姉妹からの代襲相続は一代に限られるため、相続開始以前に甥や姪自身が亡くなっている場合でも、その子どもには再代襲は認められません。つまり、二重三重に相続権が引き継がれることはない仕組みになっています。相続人調査の過程で、このルールを誤って解釈しないよう注意が必要です。
相続放棄すべきかどうかを検討する
借金などの負債が多い場合や複雑な事情により、甥・姪として相続を受けるメリットが少ないこともあります。相続はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐことを意味するため、相続放棄の検討を早期に行うことが大切です。
相続の開始、つまり、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に相続放棄の手続きをしなければならないため、期限には十分注意しましょう。
遺産分割協議に参加する
複数の相続人がいる場合には、誰がいくらの財産を相続するかを協議し、遺産分割協議書にまとめる必要があります。
自分は「何もいらない」と思っていても、遺産分割協議に参加しなければなりません。遺産分割協議への参加を控えたい場合には、相続放棄や相続分の譲渡を検討します。
また、遺産分割協議に参加する場合でも、他の相続人との話し合いには相応の負担が生じることも珍しくありません。そのため、相続人間の話し合いを円滑に進めるためにも、専門家である弁護士などのサポートを受けることが望ましいケースも多いです。
叔父・叔母の相続手続きの流れ
相続人が確定した後、どのような手順で相続手続きを進めるのか、全体的な流れを把握しておくとスムーズに進行できます。
相続手続きは期限のある制度もあり、特に相続放棄は、相続開始を知った時点から3か月以内など早い段階で手続きが必要となります。まずは誰が相続人になるのかを正しく確定し、その後、相続財産の内容や遺言書の有無を確認する作業が基本の流れです。もし相続人間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所への調停や審判の手続きが求められます。
戸籍謄本を取り寄せて相続人の調査をする
相続人を確定する際には被相続人である叔父・叔母の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せる必要があります。法定相続人となる兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本も取り寄せる必要があります。
その上で、相続人となる兄弟姉妹やその代襲相続人である甥や姪が何人いるかを確認し、相続人を正確に把握するようにします。相続関係を明確にするために、相続関係図を作成するようにします。この作業を怠ると、相続人の一部が漏れ、後々トラブルに発展する可能性があります。
遺産の調査をする
相続財産には不動産、預貯金、株式、投資信託など様々なものが含まれます。負債が残っている可能性もあるため、カードローンや住宅ローンなど見落としのないように全体像を把握しなければいけません。債務の有無を正確に把握するために信用情報機関に被相続人の信用情報を確認することもあります。
資産と負債を整理した遺産目録を作成することで、遺産分割協議を円滑に進めることが期待できます。
遺言書の有無を確認
遺言書が存在するかどうかは非常に重要なポイントです。
公正証書遺言の有無や自筆証書遺言が自宅の金庫に保管されている場合など、あらゆる可能性を考慮して入念に確認しましょう。公正証書遺言であれば公証役場、自筆証書遺言であれば自宅や法務局で保管されている可能性があります。
遺言が作成されている場合には、遺言の内容に沿って遺産を受け取りますので、相続人間の遺産分割協議が必要なくなります。
相続人間で遺産分割協議をする
相続人が複数いる場合は、相続人間で遺産分割協議をしなければなりません。
遺言がなければ、相続人間で、誰がどの遺産をどの程度取得するのかという話し合いをしなければなりません。遺産分割協議がスムーズに進むように事前に遺産目録を整理し、誰がどのように相続するのかを具体的に検討しましょう。相続人間で合意に至れば、具体的な分割内容を記載した遺産分割協議書を必ず作成します。
遺産分割協議書には、各相続人が実印を押印した上で、印鑑登録証明書を添付するようにします。
遺産分割調停を申し立てる
もし相続人同士の話し合いがまとまらず、平行線を辿るような場合には、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることを検討するべきです。
調停では調停委員が当事者を仲裁して、公平な立場で相続問題の解決に向けて話し合いを重ねていきます。調停でも解決しない場合には遺産分割審判に移行して、裁判所の終局的な判断によって相続問題の解決を図ります。
叔父・叔母が甥・姪に財産を渡す方法
叔父・叔母が甥や姪に財産を渡したいと考える場合、法定相続以外にもいくつかの方法が考えられます。
叔父や叔母に子供や両親がいる場合には、何らの対応もしなければ、甥や姪に財産を渡すことはできません。遺言書や生前贈与、養子縁組などの手段を用いることで、叔父や叔母の思いを実現させることができます。
遺言書を作成する
遺言書を活用すれば、甥や姪が相続人にならないケースでも遺産を承継させることができます。甥や姪に相続させたい場合には、自筆証書遺言よりも公正証書遺言を作成しておくと安心です。自筆証書遺言の場合は形式要件を満たさないと無効になる可能性もあるからです。
ただ、遺言の内容によっては他の相続人の遺留分を侵害する場合もありますから、遺留分対策にも気を配りながら遺言を作成するようにしましょう。
生前贈与をする
叔父・叔母が生前に甥や姪に対して財産を贈与する方法もあります。
ただし、生前贈与では、基礎控除額を超える資産を贈与すると、高額な贈与税が課税されるため、非課税枠を活用するなど上手に計画を立てる必要があります。
また、生前贈与された財産は将来的に特別受益として遺産分割時の調整が行われる場合もあるので、専門家に相談するのが望ましいでしょう。さらに、生前贈与の金額によっては、生前贈与であっても遺留分侵害額の対象になる可能性もあります。
死因贈与をする
死因贈与は、契約者の死亡時に効力が生じる贈与契約です。遺言書に近い性質を持ちますが、口頭での約束だけではトラブルに発展するリスクがあります。法律上の紛争を避けるためには書面化を行い、贈与をする条件や財産の範囲をはっきりさせておくことが大切です。
養子縁組をする
叔父・叔母が甥や姪を養子として迎えることで、子供として第一順位の法定相続人にすることができます。この場合には、遺言書を作成しなくても遺産を相続することができます。
ただし、親子としての交流がほとんどなく、財産をもらう目的だけで養子縁組をするような場合には、縁組意思が否定され、養子縁組が無効となる可能性があります。
叔父・叔母の相続問題は難波みなみ法律事務所に

叔父や叔父・叔母が亡くなった際の手続や注意点を詳しく解説してきました。最後にポイントを簡潔にまとめると、叔父・叔父・叔母の相続では法定相続人や代襲相続の確認から始め、甥・姪が相続する際には遺留分や2割加算、相続放棄の手続などをしっかり押さえておくことが大切になります。
- 叔父・叔母には子供や配偶者がいない場合、兄弟姉妹が相続人になり、そこもいなければ甥・姪が代襲相続人となる。
- 甥・姪には遺留分はないため、遺言で他人に全財産を譲られても争うことは難しい。
- 相続税では甥・姪が相続する場合、2割加算される。
- 相続放棄の検討や遺産分割協議への参加など、期限と手続きを踏まえて動く必要がある。
- 戸籍謄本の調査や財産調査は複雑になりがちなので、専門家への相談も有効。
もし叔父・叔父・叔母の相続問題で悩んでいるなら、まずは早めに必要な戸籍を取り寄せて状況を整理し、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。放っておくと期限切れで放棄ができなくなる、あるいはトラブルが深刻化するといったリスクもあるため、早めの行動が大切です。
初回相談30分を無料で実施しています。
面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。