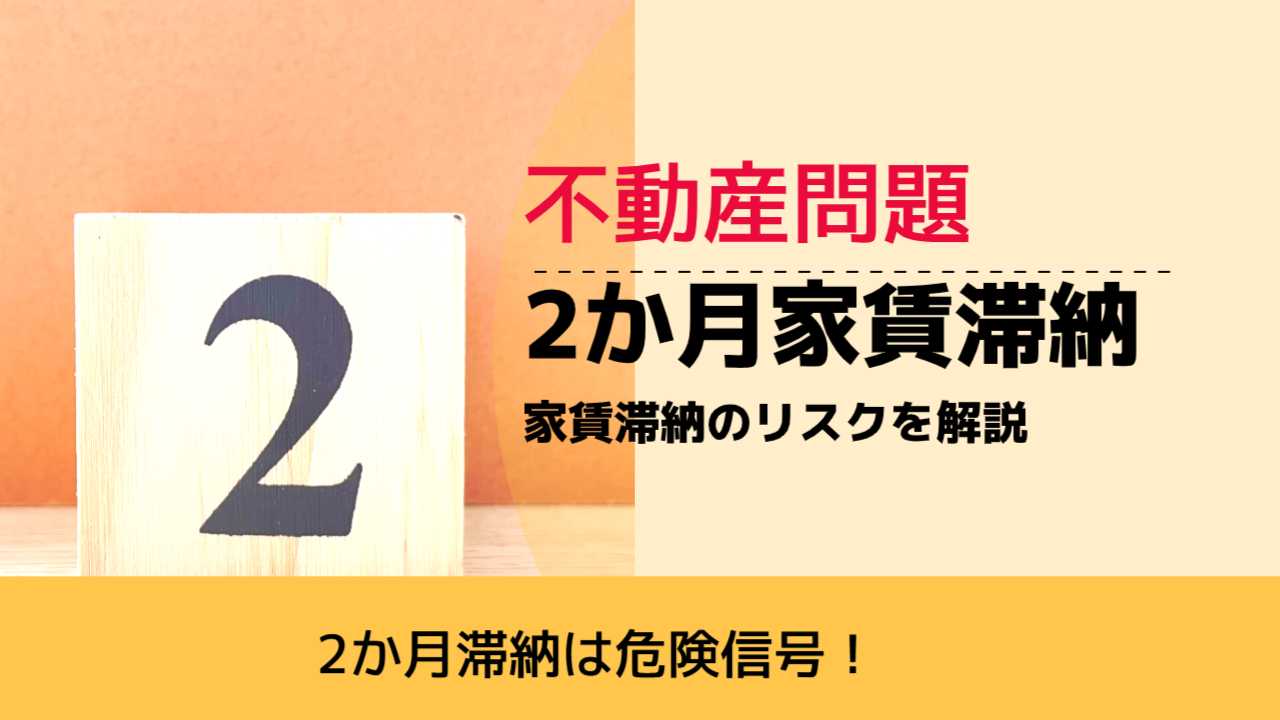賃貸経営において、家賃滞納は大きな悩みの種です。特に家賃滞納2ヶ月は、単なるうっかりミスでは済まされない、深刻な状況であると認識する必要があります。
この記事では、家賃滞納が発生した場合のオーナー向けの対処法を解説します。2ヶ月の滞納は、法的措置も視野に入れる必要が出てくる危険信号です。
滞納家賃の督促から強制退去の手続き、そして入居者への対応について、具体的なステップを解説していきます。万が一の事態に備え、冷静かつ迅速に対処するための知識を身につけましょう。
家賃滞納2ヶ月では解除できない
賃貸借契約の解除には、貸主と借主の間に「信頼関係の破壊」が認められることが必要です。つまり、賃貸借契約が、売買契約のように単発的な契約ではなく一定期間にわたって使用される継続的契約であるため、当事者間の信頼関係が契約の基礎となっています。そのため、当事者間の信頼関係が修復できない程に破壊されてはじめて、賃貸借契約を解消できると考えられています。
これは、単に家賃の支払いが遅れたからといって、当然に契約解除ができるわけではないことを意味しています。
一般的に、家賃滞納が3ヶ月以上に及んだ場合に「信頼関係の破壊」が認められやすいとされており、過去の判例においてもこの期間が一つの目安として扱われてきました。そのため、家賃滞納が2ヶ月の段階では、信頼関係の破綻は認められにくく、貸主が一方的に契約解除を通告しても、解除が有効と判断される可能性はそれ程高くないのが実情です。
しかし、この「3ヶ月」という目安は絶対的なものではありません。裁判所が「信頼関係の破壊」を判断する際には、滞納期間の長さだけでなく、個々の具体的な状況が総合的に考慮されます。主な考慮事項は以下の通りです。
- 家賃を支払えなくなった事情
- 借主の支払い意思の有無
- これまでの滞納履歴
- 借主の対応姿勢
一方で、たとえ、2か月分の賃料滞納であっても、これまで再三にわたり賃料の滞納を繰り返したり、賃借人の不誠実な態度がある場合には、信頼関係の破壊があるとして契約の解除が認められる可能性があります。
ただ、結論として、家賃滞納が2ヶ月の段階では、法的に賃貸借契約を解除することは容易ではありません。貸主としては、この期間を冷静に事態を把握し、借主への連絡や督促など、次のステップへ進むための準備期間と捉えることが重要となります。
東京地方裁判所令和元年12月19日の判決では、賃借人が賃料等の支払を2か月分以上怠ったときは、賃貸人は、催告の上、賃貸借契約を解除することができる旨の特約がある中で、賃借人が2か月分の賃料を滞納したケースでは、解除を有効としています(ただ、賃借人が十分な反論ができていない特殊事情が見受けられます。)。
東京地方裁判所平成14年11月28日では、形式的には3か月分の賃料の滞納が生じているものの、滞納賃料の支払いを督促したことがなかったこと、解除通知到達後に未払い賃料5か月分相当額を一括して支払っていることなどから、信頼関係の破壊が否定されました。


家賃滞納2ヶ月が「重要な節目」とされる理由
家賃滞納2ヶ月は、単なる支払いの遅れではなく、貸主にとっては警戒すべき事態です。その後の契約解除や建物明け渡し請求訴訟において、貸主と借主の間に「信頼関係の破綻」が認められるかどうかの判断に大きく影響を及ぼします。以下では、家賃滞納2ヶ月が重要とされる具体的な理由を詳しく見ていきましょう。
滞納の長期化・常態化するリスクが高まる
家賃滞納が2ヶ月に及ぶと、単なるうっかり忘れや一時的な資金難によるものではなく、入居者の支払い意識が低下し、滞納が常態化するリスクが一段と高まります。1ヶ月の滞納であれば、まだ軽い気持ちで解決を図ろうとするかもしれませんが、2ヶ月連続すると、入居者にとって一度に支払うべき金額が大きくなり、経済的・心理的な負担が重くのしかかります。その結果、返済を断念してしまうケースも少なくありません。
滞納が3ヶ月目以降に達すると、貸主の家賃収入の損失はさらに拡大し、雪だるま式に増えていきます。回収がより一層困難になるだけでなく、貸主の精神的な負担も増大するでしょう。家賃滞納を放置することは、金銭的な被害だけでなく、最悪の場合、物件全体の価値低下や、他の入居者への悪影響を招く可能性もあります。そのため、滞納が2ヶ月に達した段階で、いかに迅速かつ適切な対応を取るかが極めて重要になります。早期の行動が、被害を最小限に抑える鍵となるでしょう。
法的手続きにおいて「信頼関係の破綻」と判断されやすくなる
一般的に、家賃滞納が3ヶ月以上に及ぶと、裁判所は「信頼関係の破綻」を認めやすい傾向にあります。しかし、2ヶ月の滞納であっても、先ほど解説したように、以下のような状況によっては信頼関係の破壊が認められるケースもあります。
- 滞納に至った事情
- 貸主からの催告に対する入居者の対応姿勢
このため、家賃滞納が2ヶ月に及んだ段階は、将来の契約解除や建物明け渡し請求訴訟を見据える上で、非常に重要な分岐点となります。この時点で適切な対応を取り、入居者の態度や対応状況を記録に残すことは、万が一の法的手続きに備え、貸主として有利な状況を構築するために有効です。
連帯保証人や保証会社との関係にも影響
家賃滞納が2ヶ月に及ぶと、連帯保証人や保証会社との関係にも大きな影響が生じます。連帯保証人がいる場合、2ヶ月分の滞納となると、いよいよ連帯保証人への本格的な請求が現実味を帯びてきます。
一方、家賃保証会社を利用している場合、滞納が2ヶ月に及ぶと、保証会社への代位弁済請求を検討する重要な時期となります。多くの保証会社では、滞納家賃を貸主に代わって支払う「代位弁済」の請求期限を設けているため、保証会社からの代位弁済を考えている場合には、早めに事故報告することが必要です。
いずれについても、2ケ月滞納の段階で連帯保証人や保証会社と速やかに連携し、状況を共有することが、円満な解決や将来的なトラブル回避につながります。そのため、家賃滞納2ヶ月は非常に重要な節目と言えるでしょう。
家賃滞納2ヶ月が発生!貸主がまず取るべき初期対応

家賃滞納が2ヶ月に及ぶと、滞納が長期化したり常態化したりするリスクが高まり、貸主にとってより深刻な問題となります。この段階で重要なのは、感情的にならず、冷静かつ段階的に対応を進めることです。賃料を確実に回収し、信頼関係の破綻を防ぐためにも、初期の適切な対応は不可欠と言えます。
的確な初期対応が、その後のスムーズな問題解決につながります。次項では、それぞれの具体的な手順について詳しく解説します。
電話や現地訪問による支払い状況の確認と催促
家賃滞納が判明した場合、最初に行うべきは電話による入居者への連絡です。この段階では、単なる「支払いの忘れ」である可能性も考慮し、高圧的な態度を避け、事務的に状況を尋ねる姿勢が重要です。
電話で連絡が取れない場合や、入居者からの誠意ある対応が見られない場合は、現地訪問による催促も選択肢の一つとなります。ただし、訪問時間には十分な配慮が必要です。早朝や深夜の訪問、または大声で呼びかけるなど、近隣住民に迷惑をかけたり、入居者との関係を不必要に悪化させたりする行為は避けるべきです。
書面で滞納家賃の支払いを求める
電話や訪問による連絡で支払いが確認できない場合、次の段階として書面での通知を行います。2ケ月分の滞納に至っている場合には、電話や訪問を省略して、いきなり書面を送付して支払を強く催告することも珍しくありません。
口頭でのやり取りとは異なり、書面は正式な記録として残るため、後の法的手続きにおいて重要な証拠となります。書面でのやり取りは、入居者に対し支払いの重要性を強く認識させ、事態の深刻さを伝える効果も期待できます。
送付する書面には、以下の事項を明確に記載しましょう。
- 滞納している家賃の期間と総額
- 具体的な支払期限
- 振込先口座情報
- 期限内に支払いが確認できない場合の連帯保証人への連絡や法的措置の検討に関する旨
連帯保証人への連絡
入居者本人への電話や書面による催促にもかかわらず、支払いに応じない、あるいは連絡が取れない場合、次の重要なステップとして連帯保証人への連絡を検討する必要があります。連帯保証人は、賃貸借契約において入居者と同等の支払い義務を負っており、入居者が家賃を支払わない場合に、その支払いを代わりに行う責任を負っています。このため、連帯保証人に連絡することで、滞納家賃の回収可能性が高まります。
連帯保証人へ連絡する際は、感情的にならず、客観的な事実のみを正確に伝えることが重要です。場合によっては連帯保証人から入居者本人に支払いを促してもらうことで、事態の解決につながるケースも少なくありません。
すべてのやり取りを記録に残す重要性
家賃滞納への初期対応においては、入居者や連帯保証人とのすべてのやり取りを記録に残すことが極めて重要です。これは、後の法的手続き、特に建物明け渡し請求訴訟へと発展した場合に、貸主側が誠実かつ適切に督促を重ねてきたことを証明するための客観的な証拠となります。
また、口頭でのやり取りでは「言った・言わない」といった水掛け論に陥りやすく、無用なトラブルに発展する可能性があります。これを未然に防ぎ、スムーズな問題解決を図るためにも、書面や記録として残すことが有効です。
具体的に記録すべき項目としては、以下の点を網羅するようにしましょう。
| 項目 | 記録内容 |
| 日時 | いつ連絡を取ったか |
| 対応者 | 誰が対応したか(管理会社の場合) |
| 相手方 | 入居者本人か、連帯保証人か |
| 連絡手段 | 電話、訪問、メール、SMS、書面など |
| やり取りの内容 | どのような会話があったか、具体的な支払い約束の有無、入居者側の反応など |
これらの記録は、督促状のコピーを保管することはもちろん、電話での会話を録音することも有効です。メールやSMSのやり取りは、削除せずに保存し、時系列でまとめた対応履歴メモを作成することも有効な手段となります。具体的な記録が多ければ多いほど、後のトラブル回避や法的手続きを有利に進める上で役立つはずです。
初期対応で解決しない場合|強制退去までの法的手続き3ステップ
家賃滞納が2ヶ月を超え、初期対応を尽くしてもなお支払いが見込めない場合、貸主は法的な手段を用いた強制退去の手続きを進める必要が生じます。
強制退去までの手続きは、大きく分けて以下の3つのステップで進行します。
- 契約解除の通知
- 建物明け渡し請求訴訟
- 強制執行
強制執行が終結するまでには多くの時間と費用を要するため、適切な判断と進行のためには、不動産問題に強い弁護士などの専門家へ相談することも検討すべきでしょう。
ステップ1:内容証明郵便による「契約解除の最終通告」
家賃滞納に対する初期対応で解決に至らない場合、次の法的手続きの第一歩として内容証明郵便を送付します。内容証明郵便とは、いつ、誰が、どのような内容の文書を差し出したかを郵便局が公的に証明するサービスです。解除通知の内容証明郵便は、貸主が契約解除の意思表示を行ったことの確実な証拠となります。
内容証明郵便には、以下の項目を明確に記載する必要があります。
- 滞納している家賃の総額と具体的な内訳
- 支払いを行うべき明確な期限
- 期限内に支払いがない場合、賃貸借契約を解除するという明確な意思表示
この通知を送ることは、入居者に対し、貸主が法的手続きも辞さないという強い意思を伝え、支払いや退去を促す最終勧告としての役割を果たします。特に、この内容証明郵便は、後に建物明け渡し請求訴訟へ移行した場合、「催告した上で解除通知を行った」という極めて重要な証拠として機能します。
ステップ2:「建物明け渡し請求訴訟」を提起する
内容証明郵便を送付しても支払いがなく、または入居者と連絡が取れない場合、次の段階として、「建物明け渡し請求訴訟」を裁判所に提起します。この訴訟の主な目的は、賃貸借契約の解除が正当であることを確認し、建物の明け渡しと未払い家賃の支払いを命じる判決を得ることにあります。これにより、法的に強制執行へと進むための土台が作られます。
訴訟を提起するためには、適切な内容の訴状等の必要書類が必要です。訴訟提起をする場合の必要書類、訴訟手続きの期間の目安、費用について整理しました。
| 項目 | 内容・備考 |
| 必要書類 | 訴状、賃貸借契約書の写し、これまでの督促に関する証拠(内容証明郵便など)、不動産登記簿謄本 |
| 期間の目安 | 数ヶ月から1年程度(事案によって異なります) |
| 費用 | 印紙代、郵券代などの実費に加え、弁護士に依頼する場合は別途弁護士費用が発生します |
訴訟の進行中、裁判官から和解が勧められるケースも少なくありません。和解に応じることで、長期化する裁判手続きを避け、早期に解決を図ることも可能です。裁判上の和解が困難である場合には、尋問手続を経て判決の言い渡しを受けることになります。
しかし、相手方が判決の内容に不服があれば控訴することができます。そのため、控訴される場合には、判決が確定しないため、強制執行の時期はさらに先延ばしになります。
ステップ3:勝訴判決後の「強制執行」の申し立て
建物明け渡し請求訴訟で勝訴判決を得たにもかかわらず、入居者が自主的に退去に応じない場合、最終手段として強制執行を申し立てます。これは、裁判所の執行官に手続きを依頼し、強制的に建物を明け渡させるための法的な措置です。
強制執行は、主に以下の2つの段階で進行します。
- 催告: 執行官が物件を訪問し、入居者に対して断行日を通告します。この期限は、通常、催告から4週間後に設定されることが多いです。
- 断行: 催告で定められた期限までに自主的な退去が確認できない場合、実施されます。断行では、執行官の立ち会いのもと、室内の家財道具が強制的に搬出され、建物の明け渡しが行われます。
この強制執行手続きには、執行官への予納金など、さまざまな費用が必要です。主な費用は以下の通りです。
これらの費用は、貸主にとって金銭的、時間的に大きな負担となるため、強制執行はあくまで最終的な手段として位置づけられます。
| 費用の種類 | 目安 | 備考 |
| 不動産執行の予納金 | 6万円前後 | 状況により変動 |
| 動産執行の予納金 | 3万円前後 | 状況により変動 |
| 運び出した荷物の搬出費用 | 原則貸主が立て替え(30万円~60万円程) | 広さや荷物の量によって変動 |
| 運び出した荷物の保管費用 | 原則貸主が一時立て替え | 保管替えをした時の保管費用 |
家賃滞納の対応で貸主が絶対にやってはいけないこと

家賃滞納が発生すると、貸主は焦りや怒りを覚え、すぐにでも問題を解決したいと考えるかもしれませんが、焦りは禁物です。
以下では、具体的な禁止行為について、詳しく解説します。
鍵の無断交換や室内への立ち入り
家賃滞納が発生しても、貸主が一方的に入居者の部屋の鍵を無断で交換したり、許可なく室内に立ち入ったりする行為は、「自力救済の禁止」に違反します。これは、権利者が法的な手続きを経ずに実力行使をして、自身の権利を実現することを禁じるものであり、たとえ家賃の滞納があっても認められません。
このような行為には、以下のようなリスクが伴います。
- 住居侵入罪や器物損壊罪といった刑事罰の対象となる可能性があります。
- 入居者からプライバシー等の権利侵害などを理由とした不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償請求をされるリスクがあります。
これらの行為は、貸主の立場を著しく不利にし、問題解決をさらに複雑化させるため、絶対に避けるべきです。
入居者の私物を勝手に処分する行為
家賃滞納が続いている場合であっても、貸主が借主の私物を勝手に処分することは、「自力救済の禁止」によって固く禁じられています。
賃貸借契約を解除した後であっても、借主の所有権は保護されるため、無断で私物を処分する行為は法的な問題を引き起こす可能性があります。
入居者の私物の処分は、不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償請求や、器物損壊罪などの刑事罰につながる可能性があります。
借主の私物を法的に適正に撤去・処分するには、「建物明け渡し請求訴訟」を提起し、勝訴判決を得た上で、「強制執行」という法的手続きを踏む必要があります。これらの正規の手続きを経ることが、新たなトラブルを避け、円滑な問題解決のために不可欠です。
脅迫的な言動や過度な取り立て
家賃滞納が発生したからといって、貸主が感情的になり、入居者を脅したり、不当な取り立てを行ったりすることは、重大な法的リスクを伴う違法行為にあたります。例えば、「家賃を払わないと会社に言うぞ」「鍵を変えるぞ」といった発言や大声で怒鳴る行為は、刑法上の脅迫罪や強要罪に問われる可能性があります。
また、深夜早朝の訪問や電話、勤務先への連絡、さらには滞納の事実を玄関ドアや共用部に張り紙する行為は、入居者のプライバシー等の私法上の権利を侵害し、民法第709条の不法行為に基づく損害賠償請求を受ける可能性もあります。
これらの違法な取り立ては、貸主自身が刑事罰を科されたり、多額の損害賠償を請求されたりするリスクがあるだけでなく、その後の建物明け渡し請求訴訟など、法的手続きにおいて貸主の立場を著しく不利にするため、絶対に避けるべき行為です。冷静かつ法に則った対応を心がけましょう。
今後の経営のために!家賃滞納を未然に防ぐための予防策
家賃滞納が発生した後の督促や法的手続きは重要ではあるものの、安定した賃貸経営を継続するには、そもそも滞納を未然に防ぐ「予防策」を講じるのが最も効果的です。
以下の項目では、今後の健全な賃貸経営のために、家賃滞納を未然に防ぐ具体的な予防策を詳しくご紹介します。
入居審査の基準を見直す
安定した賃貸経営を維持していく上で、家賃滞納を未然に防ぐ最も重要な対策の一つが、入居審査の基準を見直すことです。問題が発生してから対処するよりも、入居の段階でリスクを排除する予防的な視点を持つことが極めて重要になります。
申込者の収入額に加えて、雇用形態の安定性(企業規模や雇用形態)や勤続年数も重要な判断材料となります。これらの要素を総合的に評価することで、入居後の滞納リスクを大幅に低減し、安定した賃貸経営の基盤を築くことが可能になります。
家賃保証会社の利用を必須にする
家賃保証会社は、入居者が家賃を滞納した場合に、貸主に代わって家賃を立て替えて支払うサービスです。これにより、貸主は安定した家賃収入を確保できるという大きなメリットを享受できます。
保証会社は各会社の審査基準に基づき、入居希望者の収入や信用情報、過去の滞納履歴などを確認します。信販系の保証会社は、金融機関の信用情報も参照するため、入居後の滞納リスクを未然に防ぐ効果が期待できます。
支払い方法を口座振替やクレジットカードに限定する
家賃滞納を未然に防ぐには、支払い方法を銀行振込や現金手渡しから、自動引き落としが可能な方法に限定することが有効です。こうした自動決済システムを導入することで、入居者による「うっかり払い忘れ」といった人的ミスを防ぎ、貸主の未回収リスクを低減できます。
口座振替やクレジットカード決済は、これらの導入に手数料や手間が発生する場合もありますが、家賃滞納による損失、督促にかかる手間や時間、さらには法的手続きにかかるコストを考慮すると、非常に有効な予防策です。安定した賃貸経営のためにも、積極的に検討すべきでしょう。
家賃滞納トラブルはどこに相談すべき?専門家の活用法
家賃滞納トラブルの解決には法的な知識が不可欠であり、ご自身での対応はリスクを伴います。そのため、専門家への相談が解決への近道です。
以下の項目では、賃貸物件の管理状況に応じた専門家の活用法について、詳しく解説します。
弁護士への相談を検討
賃貸物件を自主管理しているオーナーにとって、家賃滞納トラブルは特に大きな負担となる問題です。賃貸住宅管理に関する専門知識や、複雑な法的手続きの経験が不足している場合、自己判断で対応を進めることにはリスクがあります。家賃滞納に伴う信頼関係の破壊の判断、およびそれに続く法的手続きは高度な専門性を要します。時間的、精神的な負担も大きいため、弁護士への相談を強く推奨します。
弁護士に依頼することで、以下の一連の法的手続きをワンストップで任せることが可能です。
- 入居者との交渉の代理
- 内容証明郵便の作成・送付
- 建物明け渡し請求訴訟の代理
- 最終的な強制執行の申し立て
初期の催促で解決せず、法的手続きを視野に入れ始めた段階で弁護士に相談することが、早期解決や結果的に時間と費用の節約につながるでしょう。
初回相談を無料で受け付けている法律事務所も多いため、まずは気軽に相談してみることを推奨します
管理会社に任せる方法
多くの管理会社では、管理委託契約の範囲内で、日常的な家賃の督促業務を代行しています。これには、入居者への電話連絡や請求書の送付などが含まれることが一般的です。
しかし、特に、内容証明郵便の送付や、建物明け渡し請求訴訟といった法的な手続きに移行する際に、管理会社が貸主の代理人となることは非弁行為に該当するため、管理会社が対応できる範囲は限定的といえ、弁護士への相談や委任を積極的に検討することになります。
家賃滞納は難波みなみ法律事務所へ

家賃滞納が2ヶ月に及ぶと、単なる支払いの遅れにとどまらず、法的手続きを視野に入れる重要な節目に差し掛かったといえます。この段階での適切な対応は、その後のトラブルの長期化を防ぎ、法的な解決への道を開く上で極めて重要です。
本記事で解説したように、家賃滞納が発生した場合、法に則った段階的な手続きを冷静に進めることが不可欠です。これらのステップを正確に踏むことで、貸主は自身の正当な権利を守り、損失の拡大を防ぐことができます。
もし家賃滞納が発生し、2ヶ月に及ぶなど深刻化する兆候が見られた場合は、問題が手遅れになる前に、不動産問題に強い弁護士などの専門家へ相談することを強く推奨します。