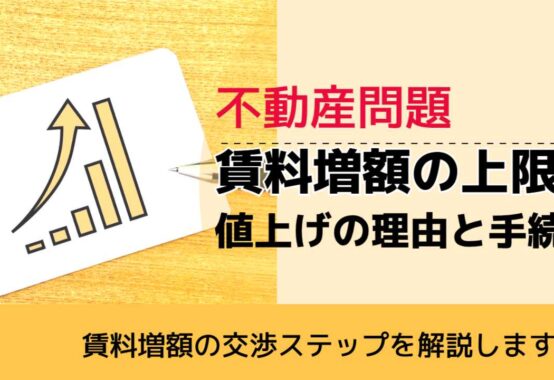不動産の購入や賃貸を検討する際、物件の「心理的瑕疵」という言葉を耳にするかもしれません。これは、過去にその物件で起きた事件や事故などが、住む人の心理的な抵抗感を生じさせる可能性のあるものを指します。
しかし、具体的にどのようなケースが心理的瑕疵にあたるのか、また、売主や貸主、その仲介業者にはどこまでの告知義務があるのでしょうか。今回は、心理的瑕疵の期間や範囲、国土交通省のガイドラインなどを参考に、告知義務についてわかりやすく解説します。安心して不動産取引を行うために、ぜひ参考にしてください。
まず知っておきたい「心理的瑕疵」の基本
不動産取引における「心理的瑕疵(しんりてきかし)」とは、どのようなものを指すのかを解説していきます。
心理的瑕疵とは?過去の出来事が原因となる「住みにくさ」
瑕疵とは、目的物が通常有するべき品質や性能を有していないことを指します。
瑕疵の中でも心理的な瑕疵とは、宅地建物で過去に起きた出来事等により、通常、一般人が嫌悪を感じるものを指します。このような心理的な瑕疵がある宅地建物を俗に事故物件などと呼称されることがあります。
心理的瑕疵に当たるかは、個別のケースに応じて判断するしかありませんが、取引目的事件性の有無、その重大性、発生場所、事案発生からの経過年数、近隣住民の周知の程度等を踏まえて判断されます。
心理的な瑕疵の代表は、自殺、他殺、焼死等の人の死に関係する事実が存在するケースですが、人の死に限らず、性風俗店や反社会的な組織のアジトとして利用されていたような場合にも心理的瑕疵に該当する場合があります。
心理的瑕疵は、外見や構造からは判断できない「目に見えない瑕疵」です。そのため、不動産取引においては、売主や不動産会社が買主や借主に対して正確な情報を伝える告知が非常に重要となります。この告知が適切に行われることが、トラブルを防ぎ、安心して取引を進めるための重要なポイントと言えます。
不動産取引で注意すべき4つの瑕疵
不動産取引における「瑕疵」は、心理的瑕疵のほか以下の3つに分類されます。それぞれの特徴を知っておくことで、より安心して物件を選べるでしょう。
- 物理的瑕疵:物件そのものに物理的な欠陥がある状態を指します。建物の雨漏り、シロアリ被害、給排水管の故障、建物の傾き、基礎のひび割れ、土地の土壌汚染や地盤沈下など、安全性や快適性に直接関わるものです。
- 法律的瑕疵:建築基準法や都市計画法などの法律上の制約により、不動産の利用が制限される状態を指します。
- 環境的瑕疵:物件自体に問題がなくても、周辺環境が原因で住み心地に影響を与えるものです。近くの騒音・振動・異臭、墓地、ゴミ処理場、反社会的勢力の事務所といった嫌悪施設などが含まれます。
これらの瑕疵は、買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性があります。安心して取引を進めるためには、適切な情報開示が重要となります。


告知義務の根拠となる法律と国のガイドライン
国土交通省は、人の死に関係する不動産取引に際しての宅建業者の判断基準を示すため、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました。このガイドラインは、特に人の死に関する告知の要否について、より具体的な判断基準を示す重要な役割を果たしています。以下では、このガイドラインの内容を中心に、告知義務の具体的な範囲や期間について詳しく見ていきましょう。
宅地建物取引業法と契約不適合責任の関係
不動産業者は、宅地建物取引業法35条で定められた重要事項について、積極的に調査した上で正しく説明する義務を負っています。しかし、心理的瑕疵は、宅建業法35条で規定された重要事項には当たりません。
ただ、宅建業者である不動産業者が取引の過程で認識した事実があり、それが売買契約を締結するか否かを買主が判断するにあたって重要な事実である場合には、宅建業法47条1号に基づき、故意に事実を告げず、不実のことを告げてはならないとされています。
よって、宅建業者は、宅建業法47条1号にあたる事実がある場合には、それを正確に告知する義務を負います。告知義務に違反する場合には、告知義務違反を理由とした損害賠償請求を受ける可能性があります。そのため、宅建業者が取引の過程で心理的瑕疵に関する情報を得た場合には、心理的瑕疵に関する調査をした上で、心理的瑕疵の内容や程度に応じて、心理的瑕疵に関する告知・説明する義務を負うことになります。
また、契約の内容に適合しない心理的な瑕疵がある場合には、物件の売主や賃貸人は契約の解除や損害賠償請求を受ける可能性があります。
「人の死の告知に関するガイドライン」の概要
これまで心理的瑕疵の中でも人の死に関する告知をするべきか否かの判断基準は曖昧であったため、これが要因となって不動産取引の円滑な進行を妨げるケースも少なくありませんでした。
このような状況を踏まえて、国土交通省は令和3年10月に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました。
ガイドラインでは、告知するべき人の死とは何か、逆に告知しなくても良い人の死とは何かを明記しています。ただし、このガイドラインは居住用不動産が対象となっており、事業用不動産については対象としていない点で注意が必要です。
今後は、不動産仲介業者は、将来の不動産トラブルを防ぐため、ガイドラインを一般的な基準として参照しながら適切な対応を取ることが求められます。
【どこまで?】告知義務が発生する事案の範囲
心理的瑕疵、特に物件内で発生した「人の死」に関する告知義務は、全てのケースで一律に求められるわけではありません。どのような場合に告知が必要となるのか、その具体的な範囲をガイドラインを参照しながら解説していきます。
人の死に関するケース
人の死に関する告知義務については、ガイドラインの内容を踏まえながら告知義務の有無を判断していきます。
告知が不要なケース
人の死に関係する事情があっても常に告知義務を負うわけではありません。以下のケースは告知義務を負わないとガイドラインにて規定されています。
| ①賃貸借取引及び売買取引の対象不動産において自然死又は日常生活の中での不慮の死が発生した場合 ②賃貸借取引の対象不動産(及び日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分)において①以外の死が発生又は特殊清掃等が行われることとなった①の死が発覚して、その後おおむね3年が経過した場合 ③賃貸借取引及び売買取引の対象不動産の隣接住戸又は借主若しくは買主が日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分において①以外の死が発生した場合又は①の死が発生して特殊清掃等が行われた場合 |
①については、老衰、病死などの自然死を想定しています。自然死が居住用不動産において生じることは珍しいことではありません。そのため、自然死については、不動産の買主や借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いとして、原則として告知義務の対象から除外されています。また、階段からの転落、入浴中の溺死、誤嚥による窒息死などの不慮の事故による死亡についても、そのような死が生じることは当然に予想されるため、原則、自然死と同様に告知義務の対象から外れています。
また、②について、①以外の死が発生している場合や特集清掃が必要となる①の死が発生している場合には、①以外の死が発生又は特殊清掃等が行われることとなった①の死が発覚してからおおむね3年間が経過すれば原則として、告知義務を負わないとされています。
次に、③について、取引対象そのものではないものの、隣接する住戸や日常生活で通常使用しない共用部分において、①以外の死が発生した場合又は①の死が発生して特殊清掃等が行われた場合にも原則として告知を必要としないとされています。
告知が必要なケース
①から③に該当しない人の死については、相手方の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、告知が必要となります。
また、仮に、先ほど告知を要しないケースとして紹介した②や③に該当するとしても、事件性、周知性、社会への影響等が特に高いケースであれば、告知を必要とするとされています。
さらに、相手方から事案の有無について問われた場合や社会的影響の大きさから相手方が知っておくべき事情がある場合には、不動産業者は調査を通じて告知をする必要があります。
風俗店として利用されているケース
対象物件が風俗店として利用されてきた場合、その物件を使用することで耐え難い程の心理的負担を負うといえるため、心理的瑕疵に該当する可能性があります。
そのため、不動産業者としては、風俗店として利用されてきた過去を知っている場合には、告知義務を負うものと考えます。
ただ、風俗店として利用されたことがあれば常に心理的瑕疵にあたるというわけではなく、風俗営業の種類や営業の期間、周知の有無などに応じた個別の判断になるものと考えます。
火災の発生
建物内で過去に発生した火災についても、心理的瑕疵に該当する場合があります。
火災により建物の物理的な価値が減退していれば、物理的な瑕疵に該当します。一方で、過去の火災が建物の物理的な価値に影響を及ぼさない場合であっても、消防車が出動する火災で、火災の痕跡が残存している場合には、過去の火災は心理的な瑕疵に該当する可能性があります。
そのため、不動産業者は、過去の火災を知っていたり、知ることができる事情があれば、告知義務を負うものと考えます。
反社会的な組織のアジトであったこと
対象物件が暴力団事務所や犯罪行為を繰り返していた宗教団体のアジトとして利用していた場合には、心理的瑕疵となります。そのため、不動産業者が対象物件が反社会的勢力のアジトとして利用されていたことを知っている、あるいは、知ることができる場合には、告知義務を負うものと考えます。
もし告知義務違反があったらどうなる?
不動産取引において、売主(または貸主)が心理的瑕疵に関する重要な事実の告知を怠った場合、それは単なる不手際として済まされるものではなく、深刻な法的なリスクや金銭的な負担を負う可能性があります。また、不動産業者が告知義務に違反した場合にも同様に損害賠償などの負担を負う可能性があります。
以下では、売主が心理的瑕疵の告知義務を果たさなかった場合に、具体的にどのような責任を問われるのか、その法的根拠や実際の裁判例を交えながら、詳しく解説します。
契約解除や損害賠償請求に発展する可能性(契約不適合責任)
売主や貸主が心理的瑕疵に関する重要な事実の告知を怠った場合、買主や借主は、契約不適合責任に基づき様々な請求をすることができます。買主・借主が取り得る主な法的手段は以下の通りです。
- 契約解除の請求
- 代金減額請求
- 損害賠償
まず、買主・借主は、心理的瑕疵があることで契約の目的が達成できないとして、売買契約や賃貸借契約の解除を請求できる可能性があります。
また、契約解除だけでなく、金銭的な請求も考えられます。心理的瑕疵のある物件は、一般的に市場価値が低下します。そのため、買主は、心理的瑕疵があることを前提とした価格と実際に支払った価格との差額、すなわち資産価値の低下分を損害として請求する可能性があります。
さらに、心理的な抵抗や精神的苦痛に対する慰謝料が請求されるケースも存在します。
これらの請求は、まずは当事者間での話し合い(協議)が行われますが、合意に至らない場合は、調停や最終的には訴訟といった法的な手続きに発展するリスクも伴います。
説明義務違反による損害賠償請求
売主、貸主などの物件の所有者だけでなく不動産の仲介業者が心理的瑕疵を説明しなかった場合には、説明義務違反を理由とした損害賠償請求を受けるリスクがあります。
損害賠償の具体的な内容として、適切な説明がされたことを前提とする適正価格との差額分が損害となります。
ただ、説明義務違反は、過失責任ですので、心理的瑕疵の存在を認識していない場合に加えて、心理的瑕疵の存在を疑う事情がない場合には、説明義務違反に基づく責任は生じません。
【裁判例】告知義務違反が認められた事例
心理的瑕疵に関する告知義務違反が争点となった裁判例は数多く存在します。これらの事例を見ると、裁判所がどのような基準で告知義務違反を判断しているのか具体的に理解できます。ここでは、告知義務違反が認められた事例と、認められなかった事例を一つずつ見ていきましょう
飛び降り自殺(東京地裁平成20年4月28日判決)
2年前に居住者が飛び降り自殺する死亡事故があった建物を不動産業者が、これを告知せずに売却した事案です。
裁判所は、飛び降り自殺があったことは、買主や借主の主観的な忌避感を生じさせるおそれがある事実であることから、これを認識していた不動産業者は販売の相手方に対し、当該情報を提供する義務があると判断した上で、死亡事故から未だ2年を経過したにすぎないため、告知義務を消滅させるには至らないとしています。
そして、説明義務違反と相当因果関係の認められる損害額は、2500万円と認定しています。
自殺(東京地裁平成21年6月26日判決)
建物内で自殺があったケースですが、自殺の態様が睡眠薬の服用によるもので、病院への搬送後、約2週間程度生存していたものであって、建物内で直接死亡したものではないこと、自殺から1年11か月が経過していることを理由に瑕疵としては軽微であると判断しました。
その上で、自殺の事実は限られた者だけが知っている事実で、いわば秘密に近い事実であったことを踏まえて、調査義務違反や説明義務違反があったとすることはできないとしました。
また、担保責任(契約不適合責任)については、瑕疵が極めて軽微であることから、売買代金の1パーセントに相当する220万円の損害賠償が認められました。
自殺(大阪高裁平成26年9月18日判決)
賃貸物件の建物内で自殺をしていたケースです。
建物内で1年数か月前に居住者が自殺したとの事実があることは、当該建物を賃借してそこに居住することを実際上困難ならしめる可能性が高いものであるから、賃貸借契約を締結するに当たって、自殺に関する事実を告知すべき義務があったというべきであると判断しました。
その上で、説明義務違反の損害について、自殺の事実を告知していれば、賃貸借契約を締結することはなかったことから、賃貸保証料、礼金、賃料等に加えて、治療費や慰謝料30万円が説明義務違反と相当因果関係がある損害であると認定しました。
性風俗店(福岡高裁平成23年3月8日判決)
対象物件が性風俗店に利用されていた事案です。
裁判所は、対象物件が前入居者によって相当長期間にわたり性風俗特殊営業に使用されていたことが売買代金を下落させる(財産的価値を減少させる)瑕疵にあたると判断しました。
暴力団事務所(東京地裁平成25年8月21日判決)
対象物件の近隣に暴力団関係の興行事務所があったケースです。
裁判所は、本件土地の近隣に暴力団事務所ではなく、暴力団が関係する興行事務所があるということを告知することは容易に行えるにも関わらず、告知することはなかったので説明義務違反となると判断しました。
その上で、説明義務違反と相当因果関係のある原告の損害として、売買代金額2億円を基準に減価率1割を乗じた2000万円をもって相当と認めると判断しました。
不動産取引のトラブルを防ぐためのポイント
心理的瑕疵に関係するトラブルは、外形的に確認しにくいため、心理的瑕疵を認識していても、取引の成立を優先させるために、ついつい心理的瑕疵に関する情報を隠してしまいがちです。
しかし、取引後に、買主や借主に心理的瑕疵の存在が発覚すると、大きなトラブルを招いてしまいます。
そこで、不動産取引のトラブルを防ぐためのポイントを解説していきます。
売主・仲介業者が行うべき正確な告知方法
心理的瑕疵に関するトラブルを防ぐためには、売主や仲介業者が買主に対して正確かつ誠実な告知を行うことが不可欠です。
まず、宅建業者が売主、貸主または仲介業者となる場合、宅地建物取引士をして、重要事項説明書を交付して重要事項を説明しなければなりません。相手方が宅建業者である場合を除き、書面交付と口頭の説明が必要となります。
告知が必要となる心理的瑕疵がある場合には、重要事項説明書に記載する必要があります。ただ、心理的瑕疵の記載をする場合には、故人やその遺族等の名誉や生活の平穏に十分に配慮する必要があります。
また、売主や貸主が不動産業者ではなく、不動産業者に仲介を依頼しない場合、買主や借主に対して、宅建業法上の重要事項の説明は求められません。しかし、告知が必要となる心理的瑕疵がある場合には、売主や貸主にも信義則上の説明義務を負うことから、心理的瑕疵の内容を契約書等の書面に記載した上で口頭による説明をしておくことが必要です。
調査の方法
人の死については、ガイドラインによれば、不動産業者が媒介を行う場合には、売主・貸主に対して、告知書(物件状況等報告書)その他の書面(以下「告知書等」といいます。)に過去に生じた事案を記載するように求めることで、媒介活動における調査義務を果たしたものとするとされています。
それ以上に、売主、貸主、管理業者以外に周辺住民への聞き込みやインターネットサイトの調査などの自発的な調査をする義務までは原則として負わないとされています。
心理的瑕疵の問題は難波みなみ法律事務所へ

本記事では、まず心理的瑕疵の基本的な定義や、不動産取引で注意すべき4つの瑕疵について解説しました。続いて、告知義務の根拠となる宅地建物取引業法や民法の契約不適合責任、さらには判断基準を明確にするため国土交通省が策定した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」の重要性について触れました。
売主や仲介業者にとっては、正確な告知を行うことが将来的なトラブルや法的なリスクを回避するために不可欠です。心理的瑕疵や告知義務について少しでも疑問や不安を感じた場合は、決して自己判断せず、弁護士や信頼できる不動産会社といった専門家に必ず相談することをお勧めします。
専門家である弁護士の助言を得ることで、自身の状況に応じた適切な対応方法を知ることができ、予期せぬトラブルに巻き込まれるリスクを大幅に減らすことができます。