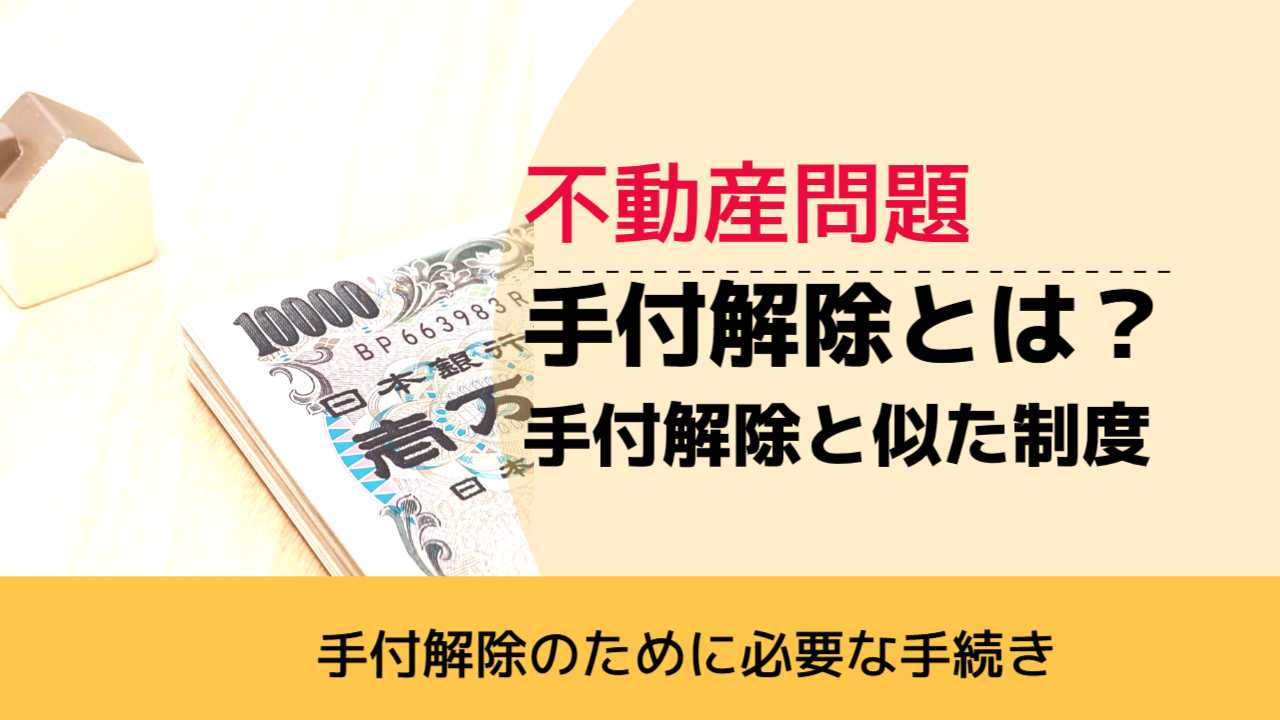不動産の売買契約後、万が一の事態で売買契約を解除しなければならない状況になった場合、「手付解除」することで売買契約を解消することができるかもしれません。しかし、手付解除が認められるためには、法律上の要件を満たす必要があります。
今回は、不動産売買における「手付解除」について、その意味や条件、注意点を初心者にも分かりやすく解説します。
手付解除とは?不動産契約をやむを得ずキャンセルする際のルール
不動産の契約するための手付解除とは何か、手付解除のための基本的なルールを解説します。
そもそも「手付金」ってどんなお金?3つの性質を解説
不動産売買契約において、買主が売主に対して支払う金銭が「手付金」です。これは単なる前払い金というだけでなく、契約の成立を証明する役割に加え、いくつかの重要な性質を併せ持っています。
手付金には主に「証約手付」「解約手付」「違約手付」の3種類があり、それぞれの役割が異なるため、これらを理解しておくことが大切です。
「証約手付」は、売買契約が確かに成立したことの証拠として交付されるものです。一方、「解約手付」は、買主が支払った手付金を放棄するか、売主が受け取った手付金の倍額を買主に支払うことによって、当事者が契約を解除する権利を留保するものです。本記事のテーマである手付解除は、この解約手付の性質に基づいています。また、「違約手付」は、契約違反があった場合のペナルティとして違約金に充当される性質を持ちます。ことができます。
当事者間で特別な取り決めがない限り、手付金は「解約手付」の性質を持つものと推定されています。
手付金の相場はどれくらい?上限についても知っておこう
不動産売買における手付金の金額は、売買代金の10%程度が一般的な相場です。これは、契約の拘束力を保ちつつ、買主の負担も考慮した現実的な金額として設定されることが多くあります。手付金があまりに少額だと、買主が安易に契約解除を選択しやすくなるため、この程度の割合が適切とされています。
ただし、売主が宅地建物取引業者(不動産会社)の場合、宅地建物取引業法により手付金の上限が定められています。具体的には、売買代金の20%(10分の2)を超える額の手付金を受け取ることは禁じられています(宅建業法39条1項)。これは、一般消費者である買主を保護するための重要なルールです。
一方、売主・買主ともに個人間の売買においては、法律上の手付金の上限は特に設けられていません。しかし、実務上は不動産会社が介在する場合と同様に、売買代金の5%から10%の範囲で設定されることが一般的です。これは、双方にとって公平かつ合理的な取引を行うための慣習と言えます。
宅建業法39条(手付の額の制限等)
1 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。
2 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであつても、買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
3 前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。
参照|e-gov法令検索


手付解除の具体的な方法|買主と売主で対応が異なる
不動産売買契約において手付解除を行う際、契約を解除したい当事者が買主か売主かによって、その具体的な方法は異なります。以下では、手付解除をするための具体的な方法を解説します。
【買主の場合】支払った手付金を放棄する
買主が不動産売買契約の解除を希望する際には、契約締結時に売主に支払った手付金を放棄することで売買契約を解除できます。この方法は「手付放棄」と呼ばれ、買主からの一方的な意思表示によって認められるのが特徴です。売主の承諾は不要であり、利口に着手する前であれば買主自身の判断で契約を解除することが可能です。
手付金を放棄すれば、買主はそれ以上の損害賠償等を請求されることなく、契約を解除できます。民法では、手付解除が行われた場合、手付放棄により損害が補填されているため、原則として損害賠償の請求はできないとされています。これにより、買主は予期せぬ大きな金銭的負担を回避できる点がメリットです。
このような買主側の都合による理由であっても、手付放棄によって契約解除は可能です。手付放棄は、買主に一定の解除権を認めつつ、契約の安定性を保つための重要な仕組みです。
民法557条【手付】
1 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
2 第545条第4項の規定は、前項の場合には、適用しない。
【売主の場合】受け取った手付金の2倍の額を支払う
売主の都合により不動産売買契約を解除する場合、買主より受け取った手付金の倍額を買主に対して支払うことで、契約を解除できます。この仕組みは「手付倍返し」と呼ばれています。なぜ2倍の金額を支払う必要があるのかというと、その内訳は、買主から預かった手付金の返還分と、売主が契約を解除することへのペナルティとして手付金と同額の解除金に分けられます。
例えば、買主が売主へ手付金として200万円を支払っていた場合、売主が契約を解除するためには、買主に対し合計400万円を支払う必要があります。これは、受け取った手付金200万円を返還し、さらに200万円を解除金として支払うという計算になります。
この手付倍返しの制度は、売主が「より高値で買い取ってくれる別の買主が現れた」といった理由で安易に契約解除することを防ぐ目的があります。なお、手付倍返しによる解除は、単に口頭で申し入れるだけでなく、現実の金銭を提供する必要がある点も重要なポイントです。
手付解除はいつまで可能?重要な「期限」について
不動産売買契約における手付解除は、いつでも無条件に解除できるわけではありません。所定の期限を過ぎてしまうと、手付解除は認められず、よりペナルティの重い「違約解除」となる可能性もあるため、正確に把握しておくことが極めて重要です。以下の項目では、手付解除の期限に関する具体的なルールについて詳しく解説していきます。
原則は「相手方が契約の履行に着手するまで」
不動産売買契約において、手付解除が可能な期限は、民法で原則として「相手方が契約の履行に着手するまで」と定められています。
ここでいう「履行の着手」とは、売買契約の目的を達成するために、客観的に外部から認識できる具体的な行動を開始した時点を指します。これは単なる準備行為ではなく、契約内容を実現するための具体的な行為や、その行為を行うために不可欠な前提行為が該当します。
手付解除ができるかどうかの判断基準は、「自分自身が履行に着手したかどうか」ではなく、「相手方が履行に着手したかどうか」である点が重要です。たとえ自分が契約の履行に向けた準備や一部の行動を開始していたとしても、相手方が履行に着手していなければ、手付解除権は有効に存続します。
「履行の着手」とは?具体例でわかりやすく解説
先ほど解説したとおり、契約の相手方が履行に着手すると、それ以後は手付解除することは制限されます。たとえば、以下の場合には履行に着手したと判断される可能性があります。
- 売買代金を現実に提供した
- 移転登記に必要な書類を司法書士に提供した
- 残代金の借入れをした
- 農地売買許可申請書を知事宛てに提出した
- 引越し業者との契約
一方、売主側では、以下のような行為が履行の着手と見なされます。
- 物件に住む賃借人との賃貸借契約を解除し、賃借権を消滅させる合意をする
- 売買対象土地の境界確定作業を行う
- 売買対象土地の分筆作業を行う
- 所有権移転登記に必要な書類を司法書士に交付する
- 買主の希望に応じて建築工事に着手した
契約書で定める「手付解除期日」が優先される
民法上の「履行の着手」による手付解除の期限は、その判断が曖昧になりがちで、トラブルの原因となることがあります。そのため、不動産取引の実務では、売買契約書に具体的な「手付解除期日」を特約として定めるのが一般的です。
契約書に「手付解除期日」が明確に記載されている場合、民法上の原則である「相手方が履行に着手するまで」という規定よりも、契約書で定めた期日が優先されます。たとえ相手方がまだ履行に着手していなかったとしても、契約書で定められた解除期日を1日でも過ぎてしまうと、手付解除は原則として行えなくなります。
宅建業者が売主である場合
宅建業法39条3項では、買主に不利な特約は無効となると定めています。
売主が宅建業者である場合には、買主に不利となる特約は無効となります。先ほど解説した手付解除期日についても、履行に着手する前であっても手付解除できないとする特約は無効となります。また、手付の授受があっても手付解除できないとする特約も無効となります。
【実践】手付解除を行う際の具体的な手続きの流れ
不動産売買契約において、手付解除は法的に認められた契約解消手段です。万が一、契約解除が必要になった場合に備え、具体的な手続きの流れを事前に理解しておくことは非常に重要です。
以下の項目では、手付解除をスムーズかつ確実に完了させるために必要な手続きを、段階的に解説します。これからご紹介する3つのステップに沿って対応することで、不要な紛争を避け、安心して手続きを進めることができます。
手付解除の内容証明を送付する
手付解除は「相手方が契約の履行に着手するまで」という期限があります。または、手付解除の期限が定められていることもあります。この期限を過ぎると手付解除は認められず、違約金発生のリスクが高まります。そのため、解除を決めたら速やかに意思を伝えることが非常に重要です。
口頭での連絡では客観的な証拠としては残りません。後々の「言った、言わない」といったトラブルを回避するために、手付解除の通知として「配達証明付き内容証明郵便」を利用します。内容証明郵便は、郵便局が「いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送付したか」を公的に証明してくれるサービスです。これにより、手付解除の意思表示が確実に行われたという揺るぎない証拠として残すことができ、相手方との契約トラブルを未然に防ぐことにつながります。
書面の作成に不安を感じる場合は、弁護士へ相談し、作成を依頼することも選択肢の一つです。弁護士に依頼することで、法的に不備のない形で確実に通知を行えるでしょう。
手付倍返しをする
手付解除の意思表示と正式な通知を終えたら、最後にお金の授受を完了します。買主が契約を解除する際は、すでに支払った手付金を放棄することになるため、原則として売主への追加の金銭のやり取りは発生しません。買主は手付金を放棄することで、売買契約を解除することができます。
一方、売主が契約を解除する際には、買主に対し、受け取った手付金の2倍の金額を支払う必要があります。これは、手付金の返還分に加え、解除に伴う金銭的な補償を合わせたものです。手付倍返しの方法は現金で支払うことも可能ですが、その場合は必ず領収書を取り交わすことが重要です。
手付解除と混同しやすいケースと注意点
これまで、不動産売買契約における手付解除の仕組みについて詳しく解説しました。しかし、不動産売買契約の解除方法は手付解除だけではなく、他にも手付解除と混同されやすい解除方法が存在します。
特に注意が必要なのは、ローン特約による解除、手付解除の期限を過ぎた場合の違約解除です。以下では、手付解除と混同しやすいこれらのケースについて、その違いと契約解除を検討する際の具体的な注意点を分かりやすく解説します。
「ローン特約」での解除なら手付金は返還される
不動産売買契約において、「手付解除」と「ローン特約(融資特約)」による契約解除は混同されがちです。ローン特約とは、買主が住宅ローンを利用して物件を購入する際、金融機関のローン審査に通らなかった場合に、買主がペナルティなしで契約を解除できる特約を指します。そのため、ローン特約による解除の場合には、手付金の返還を受けることができます。
ローン特約を適用する際のいくつかの注意点があります。例えば、買主は、誠実にローンの申し込み手続きを行う必要があります。故意に審査に落ちるような行為や、契約で定められた対象外の金融機関へ申し込んだ場合は、特約が適用されない可能性があります。
| 解除の種類 | 金銭的な負担(買主側からの解除の場合) | 備考 |
| 手付解除 | 手付金を放棄 | 期限内かつ相手方が履行に着手するまで |
| 違約解除 | 売買代金の10%~20%程度の違約金 | 期限後、債務不履行とみなされる場合 |
「違約解除」の場合には違約金が発生する可能性も
不動産売買契約における手付解除には、民法上の「相手方が契約の履行に着手するまで」という原則や、契約書に明記された「手付解除期日」といった明確な期限が設けられています。これらの期限を過ぎてしまうと、手付金の放棄や倍返しによる契約解除は、原則として認められません。
他方で、当事者の債務不履行を理由に契約を解除する場合には、相手方に対してあらかじめ約定された違約金を請求することができます。
違約金の相場は、売買代金の10%から20%程度が一般的です。例えば、3,000万円の物件であれば300万円から600万円程度にもなり得ます。これは、一般的な手付金の相場が売買代金の5%から10%であることと比較しても、非常に高額な負担となるケースが多いでしょう。
手付解除の問題は難波みなみ法律事務所へ

不動産売買契約における「手付解除」について、その意味や手続き、注意点を詳しく解説してきました。手付解除は、買主が支払った手付金を放棄するか、売主が受け取った手付金の2倍の金額を提供することで、売買契約を一方的に解除できる制度です。不動産取引において手付金は「解約手付」の性質を持つことが一般的であり、万が一の事態に備える上で重要な役割を果たします。
もし、手付解除に関して不安な点や不明な点が生じた際には、安易な自己判断は避け、不動産仲介会社の担当者や弁護士などの法律専門家へ速やかに相談することが重要です。
特に、手付解除期日が迫っている場合は、一日も早く専門家のサポートを求めることで、最善の解決策を見つけることができるでしょう。正しい知識と専門家のアドバイスを得ることで、安心して不動産取引を進めることにつながります。
初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。