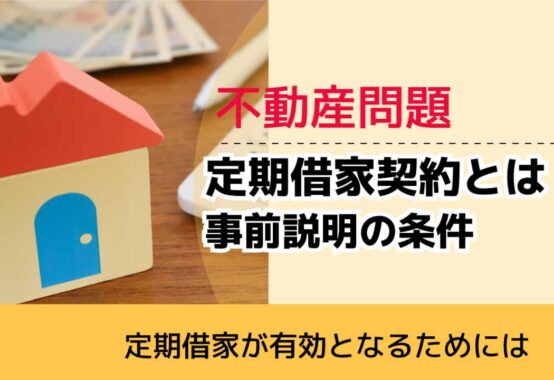生命保険は、万が一の事態に備えるための大切なものですが、相続においては、その受取人の指定が重要な意味を持ちます。保険金は、相続財産とみなされる場合と、そうでない場合があり、税金の計算にも影響を与えるためです。
この記事では、生命保険金と相続税の関係について、基本的な仕組みから非課税枠、相続対策までをわかりやすく解説します。「うちの場合はどうなるの?」といった疑問を解消し、スムーズな相続の実現に役立てていただけるように、ぜひ最後までお読みください。
まず知っておきたい!生命保険金は相続財産とは別の扱い
故人(被相続人)が遺した財産、例えば預貯金や不動産などは、「相続財産」にあたります。これらの相続財産は、亡くなった方の配偶者や子供といった相続人全員が、どのように分けるかを話し合う「遺産分割協議」の対象となるのが基本的なルールです。しかし、生命保険金に関しては、この相続財産とは異なる特別な扱いが適用されます。
以下では、相続財産と生命保険金の違いを詳しく解説します。
生命保険金は「受取人固有の財産」が原則
生命保険金が「受取人固有の財産」とされるのは、被相続人が亡くなった際、保険契約に基づき受取人に指定された人が保険会社に対し直接保険金請求権を行使できるためです。そのため、受取人はこの契約によって固有の権利として保険金を取得します。
最高裁判所の判例(平成16年10月29日決定)においても、「保険金受取人が自らの固有の権利として取得するのであって、保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく、これらの者の相続財産に属するものではない」と明確に示されています。
そのため、生命保険金は民法上の「相続財産」には含まれず、受取人固有の財産とされています。その結果、故人(被相続人)が遺した預貯金や不動産といった財産とは切り離して扱われるため、原則として遺産分割協議の対象外となります。受取人は、遺産分割協議を待つことなく、保険会社に直接保険金を請求し、受け取ることができます。
| 区分 | 根拠・性質 | 遺産分割協議への影響 |
| 相続財産 | 被相続人の財産を承継取得 | 対象となる |
| 受取人固有の財産 | 保険契約に基づき受取人が固有の権利として取得 | 原則として対象外となる |
遺産分割協議の対象外になるという大きなメリット
生命保険金が遺産分割協議の対象外であることは、受取人にとって多くの具体的なメリットをもたらします。故人の死後、受取人は遺産分割協議を待つことなく、保険会社に保険金を請求し、速やかに現金を受け取ることが可能です。これにより、葬儀費用や当面の生活費など、急な出費が必要な場面で活用できるという、実用的な利点があります。
一方、故人の銀行預金は、相続開始後速やかに口座が凍結され、遺産分割協議が終了するまで原則として引き出しが難しくなるのが一般的です。
このように、生命保険金は遺産分割協議の対象外であるため、必要なときにすぐに利用できるのが大きなメリットと言えるでしょう。
また、被相続人が「この人にお金を遺したい」という明確な意思を持っていた場合、受取人を指定しておくことで、遺言書がなくてもその意思を確実に実現できます。指定された受取人は、被相続人の意思通りに保険金を受け取ることが可能です。保険金は原則として遺産分割の対象にならないため、相続財産の分け方をめぐる相続人間での意見の対立や、いわゆる「争続」と呼ばれるトラブルを回避しやすくなるという点も重要なメリットです。


生命保険金にかかる税金は3種類!契約形態で変わる課税関係
生命保険金にも相続税などの税金が課税される場合があります。ただ、生命保険の死亡保険金を受け取った際、必ずしも相続税だけが課せられるわけではありません。保険の契約形態によって、相続税、所得税、贈与税のいずれかが適用されます。
それぞれの税金がどのような場合に適用されるのか、以下の項目で詳しく解説します。
| 契約形態 | 契約者(保険料負担者) | 被保険者 | 受取人 | 適用される税金 |
| 契約者と被保険者が同じ | A | A | B | 相続税 |
| 契約者と受取人が同じ | A | B | A | 所得税 |
| 契約者・被保険者・受取人がすべて違う | A | B | C | 贈与税 |
【相続税】契約者と被保険者が同じ場合
生命保険金に相続税が課される最も典型的な契約形態は、「契約者(保険料を支払う人)と被保険者(保険の対象となる人)が同一」であるケースです。この場合、被保険者の死亡により指定された受取人が保険金を受け取ると、その保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
ただ、常に相続税の課税対象となるわけではありません。この契約形態で受け取る死亡保険金には、税制上の大きなメリットがあるのが特徴です。それは「生命保険の非課税枠」を利用できる点です。この非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数」で計算され、受け取った保険金からこの非課税枠を差し引いた金額が相続税の課税対象額として決定されます。
【所得税】契約者と受取人が同じ場合
生命保険において、契約者(保険料を支払う人)と受取人(保険金を受け取る人)が同一人物である場合、死亡保険金には相続税ではなく所得税(および住民税)が課税されます。これは、保険料を支払ってきた契約者自身が、その保険契約から生じる利益を受け取るとみなされ、「一時所得」として扱われるためです。
例えば、妻が保険料を支払い、被保険者である夫が亡くなり、妻自身が保険金を受け取るケースがこれに該当します。この場合、妻が支払った保険料に対し、得られた利益と判断されるため、所得税が課されます。
【贈与税】契約者・被保険者・受取人がすべて違う場合
生命保険金に贈与税が課税されるのは、以下の三者がすべて異なる人物である場合です。
- 契約者(保険料負担者)
- 被保険者(保険の対象となる人)
- 保険金受取人
この場合、保険金は保険料を負担した方から保険金を受け取る方への「贈与」とみなされ、贈与税が課税されます。
具体例として、夫が契約者として保険料を支払い、妻を被保険者とし、子を保険金受取人に指定しているケースが挙げられます。この状況で妻が亡くなった場合、保険料を負担していた夫から保険金を受け取った子に対し、実質的に財産が移転したと判断されます。そのため、夫から子への贈与があったものとみなされ、子に贈与税が課されます。
【重要】生命保険の相続税には「非課税枠」がある
生命保険の非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数」という計算式で算出され、相続人が受け取る死亡保険金に適用されます。非課税枠を利用するための具体的な条件や、より詳しい計算方法については、この後で詳細に解説していきます。
非課税限度額の計算方法「500万円×法定相続人の数」
生命保険金が相続税の課税対象となる場合でも、非課税枠を利用することで、税負担を軽減できます。この非課税限度額は、「500万円 × 法定相続人の数」という計算式で算出されます。
ここでいう「法定相続人」とは、民法で定められた相続人を指します。具体的には、配偶者は常に法定相続人となり、これに加えて以下の順位で相続人が決まります。
- 子(子が死亡している場合は孫も含む)
- 直系尊属(父母や祖父母など)
- 兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥姪も含む)
非課税枠を利用するための条件とは?
生命保険金の非課税枠を適用するためには、以下の3つの重要な条件を満たす必要があります。
- 保険金の受取人が法定相続人であること
- 被相続人(亡くなった方)が保険料を負担していた保険契約であること
- 相続を放棄した人は非課税枠の適用対象外となること
一つ目の条件は、保険金の受取人が法定相続人であることです。内縁の妻や友人など、法定相続人以外の方が受取人に指定されている場合、この非課税枠は適用されません。
二つ目の条件は、被相続人(亡くなった方)が保険料を負担していた保険契約であることです。具体的には、保険契約者と被保険者が同一人物であり、被相続人自身が保険料を支払っていた契約である場合に、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となり、非課税枠の適用対象となります。
三つ目の条件は、相続を放棄した人は非課税枠の適用対象外になるという点です。相続放棄をした場合、その人は法定相続人ではなかったものとみなされます。そのため、仮に生命保険金の受取人に指定されていたとしても、この非課税枠を利用することはできません。
注意!生命保険金が相続トラブルの原因になる例外的なケース
生命保険金は原則として受取人固有の財産とされ、遺産分割の対象外となる大きな利点があります。しかし、この原則が常に適用されるわけではありません。受け取った生命保険金が民法上の「特別受益」とみなされ、遺産分割の際に考慮されたり、他の相続人の「遺留分」を侵害してしまうといった事態に発展する恐れがあります。次の項目からは、これらの例外的なケースについて、具体的な事例を交えながら詳しく解説いたします。
受取額が不公平だと「特別受益」とみなされる可能性
民法上の「特別受益」とは、一部の相続人が被相続人から生前贈与や遺贈などによって受けた特別な利益を指します。これは、相続人間の公平性を保つため、これらの利益を相続財産に含めて計算し直し、遺産分割を行う制度です。
生命保険金は原則として受取人固有の財産であり、通常は特別受益に該当しません。しかし、保険金額が遺産総額に対して極めて大きいなど、相続人間で到底認められないほどの著しい不公平が生じる場合、生命保険金も特別受益に準じて「持ち戻しの対象」とするというものです。
具体的な判例として、東京高裁平成17年10月27日決定では遺産総額の約99%、名古屋高裁平成18年3月27日決定では約61%を占める保険金が特別受益とみなされました。生命保険金額が遺産総額の5割以上を超える場合に、特別受益と判断される可能性があるとされています。
もし生命保険金が特別受益とみなされた場合、その保険金額は「みなし相続財産」として遺産分割の計算に含められます。これを「特別受益の持ち戻し」と呼び、その結果、他の相続人の取り分に影響が生じることになります。
| 判決裁判所・日付 | 遺産総額に対する保険金の割合 | 判断結果 |
| 東京高等裁判所 平成17年10月27日 | 約99% | 特別受益と判断 |
| 大阪家裁堺支部 平成18年3月22日 | 約6% | 特別受益を否定 |
| 名古屋高等裁判所 平成18年3月27日 | 約61% | 特別受益と判断 |
| 広島高等裁判所 令和4年2月25日 | 約272%(2.72倍) | 特別受益を否定→夫から妻への保険金で生活保障が目的 |
遺留分侵害額請求の対象になることも
生命保険金は原則として受取人固有の財産であり、法定相続人に保障された最低限の遺産取得分である「遺留分」を算定する際の基礎財産には含まれません。したがって、通常であれば、生命保険金を受け取った相続人に対し、他の相続人が遺留分侵害額請求を行うことはできないとされています。
しかし、先ほども解説したように、例外的なケースとして、保険金の額が遺産総額に対して極めて大きく、相続人間の公平性が著しく損なわれると裁判所が判断した場合、生命保険金も「特別受益」に準ずるものとして遺留分の算定に含められる可能性があります。
このような例外的なケースに該当すると判断された場合、他の相続人から遺留分侵害額請求をされるリスクが生じます。その結果、保険金を受け取った相続人は、金銭を支払って遺留分侵害額を補填しなければならなくなるため、注意が必要です。
遺言書の作成を検討する
先ほど解説したように、保険金の金額が大きすぎると、特別受益として持ち戻しの対象となります。また、相続人の一部が遺留分額に満たない遺産しか得られていない場合には、遺留分請求の問題も引き起こします。
そこで、相続対策として生命保険を活用する場合には、セットで遺言書の作成を検討しましょう。遺言書を作成しておけば、遺産分割協議をせずに遺言書の内容のとおり遺産が承継されます。ただ、遺言書の内容が特定の相続人を優遇するような偏った内容で、その他の相続人の遺留分を侵害してしまうと、遺言よりも遺留分が優先されるため、遺留分の問題を招いてしまいます。
そのため、遺言書を作成する場合でも、生命保険金を受け取る相続人と他の相続人の公平さを損なわれないよう、他の相続人の遺留分に一定の配慮をする遺言書を作成することが求められます。
生命保険の問題は難波みなみ法律事務所へ

本記事では、生命保険金が相続においてどのような役割を果たすのか、その基本的な仕組みと税務上の取り扱いについて解説しました。特に、生命保険金が原則として「受取人固有の財産」であり、遺産分割協議の対象外となること、そしてその契約形態によって「相続税」「所得税」「贈与税」のいずれかが課される点が重要なポイントです。
ただ、生命保険金が遺産総額と比べてかなり大きい金額になると、相続人間の対立を深めてしまい、遺産分割や遺留分侵害額請求の問題を招きます。そのため、保険金額の設定や遺言書の作成をする際には、将来の争族問題を回避するため、相続問題を得意とする弁護士に相談することを検討しましょう。
初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。