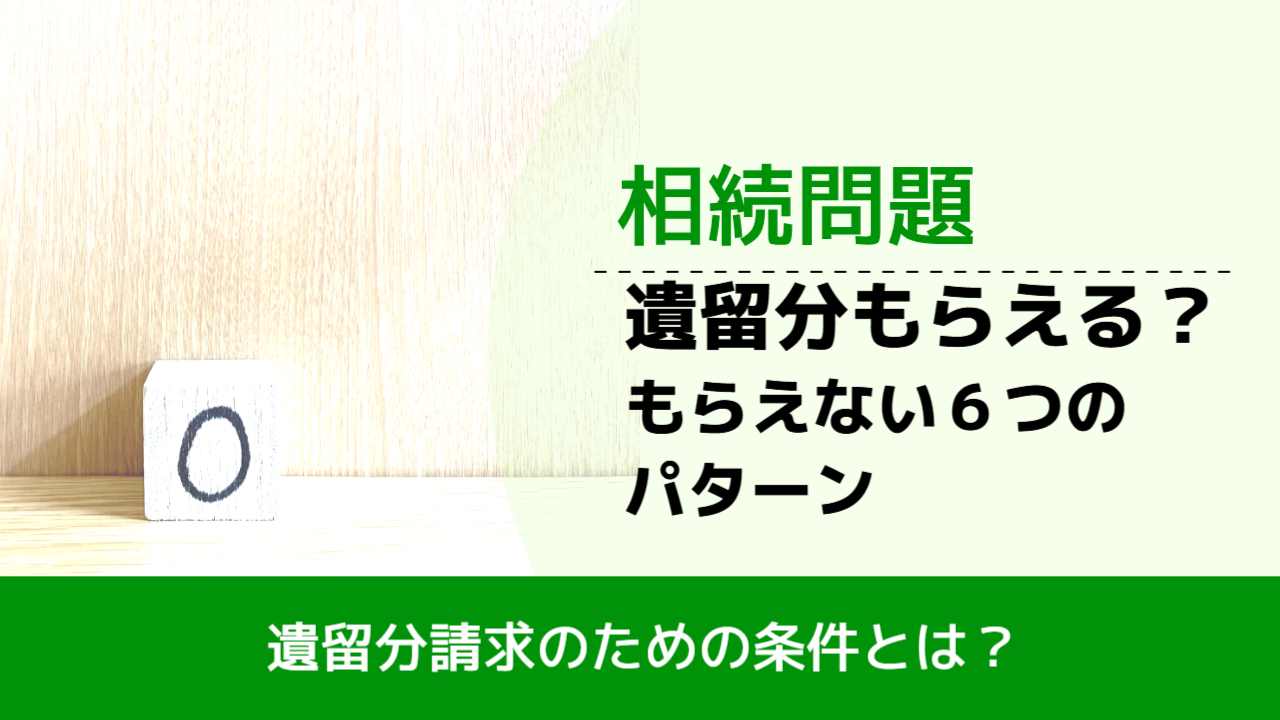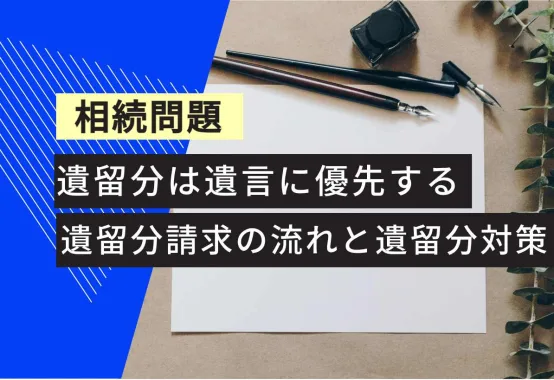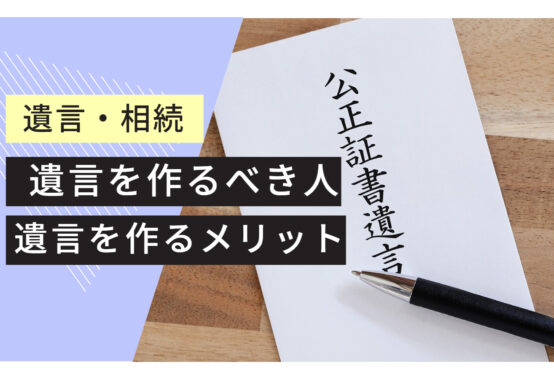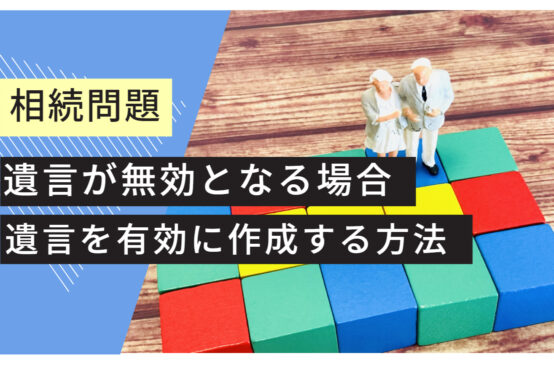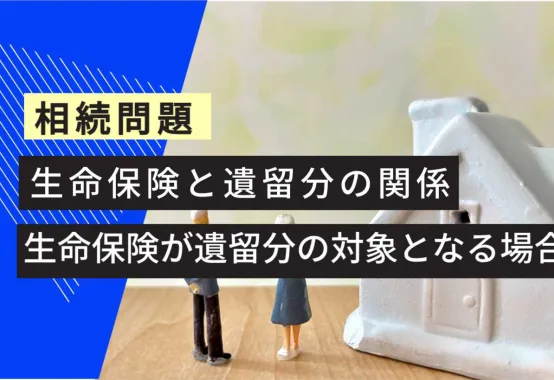相続が発生したものの、遺留分をもらえないかもしれない。そうした状況に直面し、不安を感じている方もいるのではないでしょうか。遺留分は、法律で保障された相続人の権利ですが、一定の条件のもとで、その権利が制限されることもあります。
この記事では、遺留分が認められないケースや、その原因について詳しく解説します。また、もしもの時に、ご自身でできる対処法についてもご紹介します。「相続」は複雑な問題ですが、ぜひこの記事を参考に、解決への第一歩を踏み出してみてください。
「遺留分がもらえない…」と諦める前に確認したいこと
不公平な遺言書や多額の生前贈与を理由に、ご自身の遺留分が侵害されていると感じ、焦りや不安を抱えている方もいるかもしれません。まずは、遺留分に関する基本的な知識を正確に確認することが、状況を打開するための第一歩となります。
そもそも遺留分とは?相続人に最低限保障される遺産の取り分
遺留分とは、亡くなった方の兄弟姉妹以外の法定相続人に対し、民法によって最低限保障される遺産の取り分を指します。これは、たとえ遺言書に異なる内容が記されていたとしても、それを覆すことができる強力な権利です。
混同しやすい概念に「法定相続分」がありますが、これは遺言書がない場合に法律で定められた遺産の取り分の目安となる割合ですが、遺言書があればその内容によって変更が可能です。これに対し、遺留分は遺言によっても侵害されない、相続人が受け取るべき最低限の権利として保護されています。
遺留分として保障される具体的な割合は、相続人の構成によって以下のように定められています。
| 相続人の構成 | 遺留分の割合 |
| 原則(配偶者、子など) | 法定相続分の2分の1 |
| 直系尊属のみの場合 | 法定相続分の3分の1 |
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。例えば、配偶者と子が相続人である場合、子の法定相続分は2分の1ですが、その遺留分は法定相続分(2分の1)のさらに2分の1にあたるため、遺産全体の4分の1となります。
【重要】遺留分を請求できる相続人とできない相続人
遺留分は、法定相続人であれば誰もが請求できる権利ではありません。遺留分を請求できるのは、原則として「被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人」に認められています。具体的には、次の3種類の相続人が遺留分権利者となります。
- 配偶者
- 子(または孫などの代襲相続人)
- 直系尊属(父母や祖父母など)
これらの相続人は、遺言書などによって遺産を全く受け取れなかった場合でも、法律で保障された最低限の遺産を取り戻す権利を持ちます。配偶者と子は常に遺留分権利者であり、直系尊属は故人に子や孫がいない場合に限り、遺留分権利者となります。
一方、後述するように法定相続人であっても、兄弟姉妹やその代襲相続人である甥・姪には、遺留分を請求する権利は認められていません。
ご自身の立場が、上記の遺留分権利者に該当するかどうか、この機会に確認されることをお勧めします。


法定相続人なのに遺留分を請求できない6つのケース
法定相続人だからといって、必ず遺留分が保障されるわけではありません。
以下では、遺留分を請求できなくなる代表的な6つのケースを具体的に解説していきます。ご自身の状況と照らし合わせながら、ぜひ確認を進めてみてください。
ケース1:被相続人の兄弟姉妹・甥・姪である
遺留分を請求できないケースとして、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹、およびその代襲相続人である甥・姪が挙げられます。民法の規定により、これらの相続人には遺留分を請求する権利が認められていません。
兄弟姉妹は、他に相続人がいない場合に「法定相続人」となることは可能です。しかし、法定相続人であることと、遺留分を請求できる「遺留分権利者」であることには、重要な違いがあります。遺留分は、家族の生活維持を目的としているため、被相続人との関係性が他の相続人よりも遠いとされる兄弟姉妹には認められていません。したがって、たとえ「全財産を特定の人物に遺贈する」といった内容の遺言書があったとしても、兄弟姉妹や甥・姪が、その遺言に対して遺留分を不服として請求することはできません。
ケース2:相続欠格や相続廃除に該当する
法定相続人であっても、特定の重大な非行があった場合や、被相続人から廃除された場合には、遺留分を請求する権利を失います。これは「相続欠格」と「相続廃除」と呼ばれる制度によるものです。
相続欠格とは、被相続人の殺害や遺言書の偽造・隠蔽など、民法第891条に定められた相続秩序を著しく乱す行為があった際に、特別な手続きを経ることなく、法律により当然に相続権を失う制度です。相続欠格に該当すると、相続人としての権利そのものが剥奪されるため、遺留分を請求する権利も失われます。
次に、相続廃除について説明します。相続廃除とは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい非行があった場合に、被相続人の意思に基づいて家庭裁判所に申し立てを行い、特定の相続人の相続権を剥奪する制度です。相続廃除の対象となるのは、遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、直系尊属など)です。家庭裁判所が廃除を認めた場合、その相続人は相続財産を受け取る権利だけでなく、遺留分も失うことになります。
| 項目 | 相続欠格 | 相続廃除 |
| 内容 | 法律により当然に相続権を失う | 家庭裁判所の審判で相続権を剥奪する |
| 要件 | 被相続人の殺人、遺言書偽造・隠蔽など(民法891条) | 被相続人への虐待、重大な侮辱、著しい非行など(民法892条) |
| 手続き | 不要(行為があれば当然発生) | 家庭裁判所への申立てが必要 |
| 対象 | すべての相続人 | 遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、直系尊属) |
| 効果 | 相続権・遺留分請求権を失う | 相続権・遺留分請求権を失う |
ケース3:相続放棄の手続きを済ませている
家庭裁判所で相続放棄の手続きを済ませている場合も、遺留分を請求する権利は失われます。相続放棄とは、被相続人のプラスの財産(預貯金や不動産など)も、マイナスの財産(借金など)も一切引き継がないという意思表示を、家庭裁判所に対して行う手続きです。
この手続きが受理されると、その人は法律上「はじめから相続人ではなかった」とみなされます。相続人としての地位をすべて失うため、当然のことながら、プラスの財産だけでなく、遺留分を請求する権利も失われます。
一度、家庭裁判所で相続放棄が受理されると、原則としてその撤回はできません。例えば、「後から多額の財産が見つかった」「遺留分を請求したくなった」といった理由で、一度行った相続放棄を取り消すことは、基本的に認められていません。
ケース4:遺留分の権利を自ら放棄している
法定相続人であっても、自身の意思で遺留分の権利を放棄した場合、その権利を請求することはできません。遺留分の放棄には、相続開始前に行う場合と、相続開始後に行う場合の2種類があります。
まず、被相続人が亡くなる前、すなわち相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必須です。家庭裁判所は、遺留分の放棄が遺留分権利者自身の自由な意思に基づくものか、また、遺留分の放棄に合理的な理由や必要性があるかなどを総合的に判断し、許可の有無を決定します。
一方、被相続人が亡くなった後の遺留分放棄に関しては、家庭裁判所への特別な手続きは不要です。この場合、遺留分侵害額請求権を行使しないことにより、遺留分を放棄したものとされます。
生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄した場合、その決定を原則として覆すことはできません。そのため、過去にそのような手続きを行った覚えがないか、一度確認してみることをお勧めします。
ケース5:遺留分侵害額請求の時効が過ぎている
遺留分を請求する権利である遺留分侵害額請求権には、法律で定められた時効が存在します。この期間を過ぎると、本来遺留分を受け取る権利があったとしても、その主張は認められなくなりますので注意が必要です。
遺留分侵害額請求権には、主に以下の2種類の時効期間が設けられています。
- 短期消滅時効:遺留分権利者が「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与や遺贈があったこと」を知った時から1年間(民法第1042条前段)。
- 除斥期間:相続開始の時から10年間。
これらの期間のいずれか一方でも過ぎると、遺留分の請求ができなくなります。特に短期消滅時効は、遺言書の内容など、遺留分侵害の事実を知った時点から起算されるため、早めの確認が重要です。
もしご自身の遺留分が侵害されている可能性に気づいた際は、時効の成立を防ぐためにも、速やかに行動を起こすことが重要です。時効を止めるには、相手方に対して遺留分を請求する意思表示を行う必要があります。内容証明郵便などを利用し、法的な証拠を残しつつ意思表示を行うのが一般的です。迷った場合は、早めに弁護士へ相談し、適切な対処法を検討することをおすすめします。
ケース6:遺留分を超える生前贈与などをすでに受けている
被相続人から生前に贈与(特別受益)を受けていた場合、遺留分を請求できないことがあります。特別受益とは、特定の相続人に対し、経済的な利益を目的として行われた贈与を指します。
遺留分侵害額を計算する際には、この特別受益の額が、本来請求できるはずの自身の遺留分額から控除される仕組みです。具体的には、まず遺留分の基礎となる財産額から遺留分額を算定し、そこからすでに受け取った特別受益の額が差し引かれます。
| 遺留分侵害額=遺留分額−遺留分権利者が受けた遺贈や贈与(特別受益)の額−遺留分権利者が取得した遺産の額+遺留分権利者が承継する相続債務の額 |
例えば、被相続人から住宅購入資金として高額な生前贈与を受けていた場合、その金額が自身の遺留分額を上回ると、新たに遺留分を請求することはできません。過去に特別受益を受けていないか、確認しておくことをお勧めします。
遺留分を取り戻すための手続き「遺留分侵害額請求」の流れ
ご自身の遺留分が侵害された場合、その権利を取り戻すための具体的な手続きが「遺留分侵害額請求」です。以下では、遺留分侵害額請求の具体的な手続きのステップを詳しく解説します。
STEP1:内容証明郵便で請求の意思表示をする
ご自身の遺留分を取り戻すための手続きである「遺留分侵害額請求」を行う最初のステップは、相手方へ明確な意思表示をすることです。この際、口頭や普通郵便ではなく、内容証明郵便を利用します。
その理由の一つは、請求の意思表示をしたという客観的な証拠を残すためです。これにより、後々の交渉や裁判になった場合でも、いつ、どのような内容の請求をしたかを明確に証明できます。
もう一つは、遺留分侵害額請求権の時効を更新させることです。遺留分侵害額請求の時効は1年ですが、時効完成までに遺留分請求を行使することで、この時効は更新されます。そのため、内容証明を利用することで遺留分請求をしたことを明確にして時効の更新を確実にさせるのです。
STEP2:当事者間で話し合い(交渉)を行う
内容証明郵便を送付し、遺留分侵害額請求の意思表示を行った後は、相手方との直接的な話し合い(交渉)の段階へと移行します。この交渉では、請求する遺留分侵害額の算定根拠を明確に提示し、具体的な支払金額、支払方法、支払期限などについて詳細な協議を進めます。
話し合いの結果、合意に至った場合は、将来のトラブルを防ぐためにも、その合意内容を書面(合意書や和解書)として残すことが非常に重要です。さらに、可能であれば「強制執行認諾文言付き公正証書」として作成することで、万が一相手方が合意内容を履行しない場合に、裁判を経ずに強制執行を行うことが可能となり、より強力な証拠となります。
当事者間での交渉がまとまらない場合は、次のステップとして家庭裁判所に「遺留分侵害額の調停」を申し立てることになります。弁護士に依頼すれば、交渉段階からサポートを受けられ、感情的な対立を避けながらスムーズな解決を目指すことも可能です。
STEP3:家庭裁判所で調停を申し立てる
当事者間の話し合い(交渉)で解決できない場合は、次の段階として家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。調停とは、調停委員が双方の間に入り、客観的な立場から解決案の提示や助言を行いながら、話し合いによる円満な解決を目指す手続きです。この調停の場では、お互いの主張を整理し、合意形成を図ることが期待されます。
もし調停でも合意に至らず、解決が困難であると判断された場合は、最終的に地方裁判所で「遺留分侵害額請求訴訟」を提起し、裁判官による法的な判断を求めることになります。訴訟では、提出された証拠に基づき裁判官が判決を下し、侵害された遺留分額が確定されます。
調停や訴訟の手続きには、多くの法的な専門知識と複雑な書類作成が伴うため、個人で進めるには大きな負担となります。そのため、これらの手続きは通常、弁護士に依頼して進めるのが一般的です。弁護士は、あなたの状況に応じた適切なアドバイスを提供し、複雑な手続きを代行してくれるため、安心して解決を進めることができるでしょう。
| 手続きの種類 | 担当機関 | 目的 | 進め方 |
| 遺留分侵害額の請求調停 | 家庭裁判所 | 話し合いによる円満な解決 | 調停委員が双方の間に入り、客観的な立場で助言や解決案を提示 |
| 遺留分侵害額請求訴訟 | 地方裁判所(請求額によっては簡易裁判所) | 裁判官による法的な判断 | 提出された証拠に基づき、裁判官が判決を下し遺留分額を確定 |
複雑な相続問題は弁護士に相談するべき3つの理由
遺留分をはじめとする相続問題は、民法などの専門的な法律知識が求められるだけでなく、親族間の感情的な対立が絡むため、当事者のみで解決に導くのは困難です。
このような複雑な状況下で、問題を円滑かつ有利に解決するためには、法律の専門家である弁護士に相談することが非常に有効な手段となります。以下では、弁護士に依頼することで得られる具体的なメリットを詳しく解説します。
あなたの状況で請求できる権利を正確に判断してくれる
遺留分の具体的な金額を算出する作業は複雑です。不動産や株式のように評価が難しい財産の評価に加え、過去の生前贈与や特別受益などもすべて考慮し、正確な遺留分侵害額を算定します。この計算には専門知識が不可欠であり、弁護士はこれらの要素を総合的に分析して、請求可能な金額を明確にします。
また、遺留分侵害額請求には、時効(除斥期間)が設けられています。具体的には「相続の開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ってから1年」、または「相続開始の時から10年」です。これらの期限が到来していないかを確認し、いつまでにどのような行動を取るべきかについても、弁護士から的確なアドバイスを得られる点は大きなメリットです。
遺留分以外にも、被相続人への貢献が認められる「寄与分」など、状況に応じて主張できる可能性のある権利がないか、多角的な視点から検討します。
相手方との交渉や面倒な手続きをすべて任せられる
相続問題、特に遺留分に関する交渉や裁判の手続きは、親族間での感情的な対立が生じやすく、当事者同士で話し合いを進めることは精神的な負担が大きいものです。弁護士に依頼すれば、あなたの代理人として相手方との交渉にあたります。これにより、直接的なやり取りを避けることができ、感情的になりがちな状況でも、法的な観点から冷静に話し合いを進めることが可能です。結果として、精神的な負担を大幅に軽減できるでしょう。
また、遺留分侵害額請求には、相続財産の正確な調査や評価、そして複雑な計算が伴います。弁護士は、預貯金の取引履歴を含む財産調査を行い、遺産の正確な評価や資産の特定を進めます。専門知識を要するこれらの作業を任せることで、請求額の算定ミスを防ぎ、あなたの正当な権利を主張できるようになります。
さらに、内容証明郵便の作成・送付から、家庭裁判所での調停、さらには訴訟に至るまで、複雑で時間のかかる法的手続きをすべて代行してもらえます。書類の不備なく、スムーズに手続きを進めることができるため、安心して解決を待つことが可能です。弁護士が間に入ることで、納得のいく解決へ早期に導かれることが期待できるでしょう。
感情的な対立を避け、スムーズな解決が期待できる
相続問題は、金銭的な側面だけでなく、長年にわたる家族間の人間関係や過去の不満が絡み合うため、当事者同士の話し合いでは感情的な対立に発展しやすい傾向があります。
このような状況で弁護士が代理人として交渉の窓口になることは、あなたにとって大きなメリットをもたらします。具体的な利点は以下の通りです。
- 他の相続人と直接顔を合わせる必要がなくなるため、精神的な負担を大幅に軽減できます。
- 弁護士が感情論に流されることなく、法的な根拠に基づいて冷静に交渉を進めるため、感情的な衝突を避け、客観的な話し合いを進められます。
- 紛争の泥沼化や長期化を防ぎ、円満かつ迅速な解決へと導かれることが期待できます。
遺留分の問題は難波みなみ法律事務所へ

この記事では、遺留分を請求できないケースとして、兄弟姉妹が相続人である場合、相続欠格・廃除、相続放棄、遺留分権利の放棄、時効の経過、あるいはすでに遺留分を超える生前贈与を受けている場合があることを解説しました。
相続は、個々の状況によって適用される法律や手続きが大きく異なり、非常に複雑な問題です。ご自身の判断だけで「遺留分はもらえない」と結論付けてしまうと、本来受け取れるはずの正当な権利を失うリスクがあります。法的な知識がないまま自己判断を進めることは、不利益を被る可能性が高まります。また、遺留分侵害額請求には時効があるため、対応が遅れると権利行使の機会を逃すことにもつながりかねません。
もし、ご自身の遺留分について少しでも疑問や不安を感じているのであれば、まずは弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。弁護士は、あなたの状況を詳細にヒアリングし、法的な観点から請求できる権利の有無や、具体的な遺留分侵害額を正確に判断してくれます。感情的な対立を避け、円満かつスムーズな解決を目指す上で、専門家のサポートは最も確実な第一歩となるでしょう。
初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。