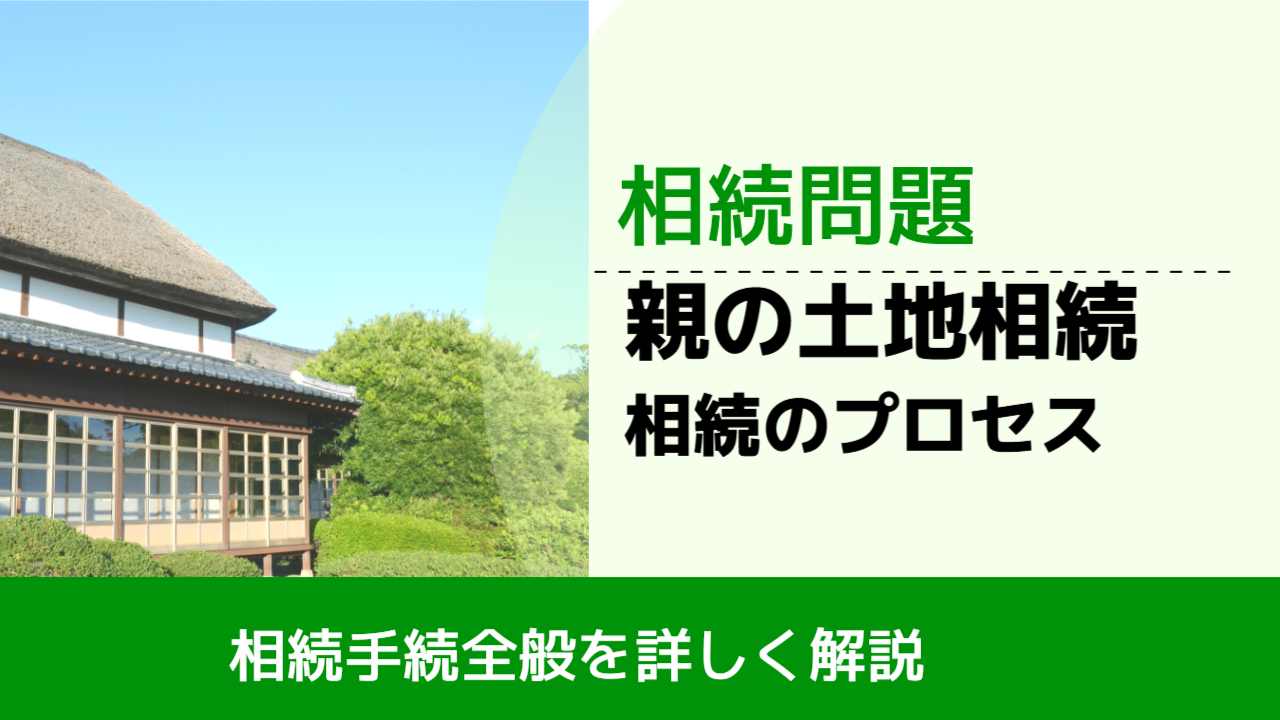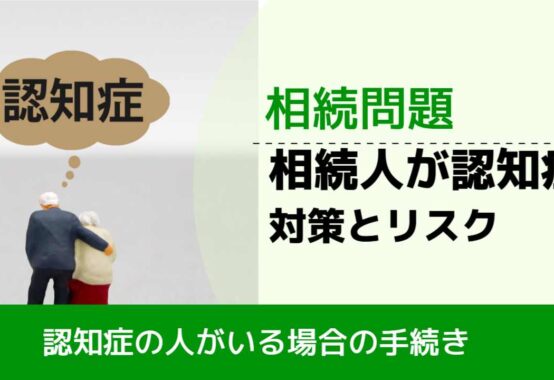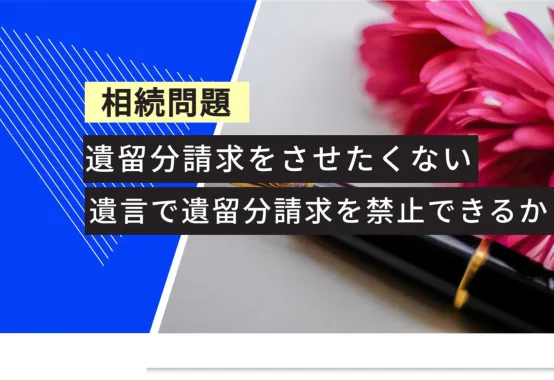相続は、人生においてそう何度も経験するものではありません。特に親から土地を相続する場合、何から手をつければ良いのか、戸惑う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、土地の相続について、一連の手続きの流れをわかりやすく解説します。 相続の手続き、名義変更、税金のこと、親族間のトラブルを回避するための対策まで、 親の土地の相続に関するあなたの疑問を解消できるよう解説していきます。
親の土地相続でまず知っておきたい手続きの全体像
親が亡くなり、土地を相続することになった際、多くの方は経験が少なく、「何から手をつければ良いのか」と戸惑うことが多いでしょう。
以下の項目では、相続開始から手続き完了までの具体的な6つのステップを、順を追って詳しく解説します。
ステップ1:遺言書の有無を確認する
| 遺言書の種類 | 主な保管場所 | 家庭裁判所での検認の要否 |
| 自筆証書遺言(個人保管) | 自宅の金庫・書斎、親族宅 | 必要 |
| 自筆証書遺言(法務局保管) | 法務局 | 不要 |
| 公正証書遺言 | 公証役場 | 不要 |
親の土地を相続する際、最初に行うべきは遺言書の有無の確認です。遺言書が存在すれば、その内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるため、相続手続きにおける最も重要な第一歩となります。また、遺言書があれば、相続人間の遺産分割協議をすることなく、遺言執行により相続手続を進めることができます。
遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。自筆証書遺言は、自宅の金庫や書斎、または親族の自宅などに保管されている可能性があります。また、2020年7月に開始された「自筆証書遺言保管制度」を利用している場合は、法務局で保管されている可能性もあります。一方、公正証書遺言は全国の公証役場で作成されるため、公証役場を通じて遺言書の有無を確認することができます。
もし遺言書を発見したら、特に自筆証書遺言(法務局保管制度を利用していないもの)の場合は注意が必要です。家庭裁判所での「検認」という手続きが必要となります。これを怠り、勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられる可能性もあります。遺言書が見つからない場合は、法定相続人が遺産分割協議を行うことになります。その際は、次のステップである相続人の確定に進みましょう。
ステップ2:誰が相続人になるのかを確定する
遺言書がない場合は、民法で定められた「法定相続人」を正確に確定する必要があります。配偶者は常に相続人となりますが、法定相続人には以下の順位があります。
- 第1順位:子(子がすでに亡くなっている場合は孫などの直系卑属が代襲相続人となります)
- 第2順位:父母(父母がすでに亡くなっている場合は祖父母などの直系尊属が相続人となります)
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は甥や姪が代償相続人となります)
相続人を正確に確定するには、被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)」を収集することが不可欠です。これは、前妻との間に子がいる場合、認知した子がいる場合、養子がいる場合など、現時点では把握していない相続人が存在する可能性を確認するためです。これらの戸籍謄本は、被相続人の本籍地がある市区町村役場で取得できます。遠方の場合でも、郵送で請求することも可能です。
ステップ3:相続する財産をすべて調査する
相続財産の調査は、その後の遺産分割協議や相続税の申告・納税の基礎となる、きわめて重要なステップです。ここでは、故人がどのような財産を所有していたのかを正確に把握し、リストアップすることが求められます。調査の対象となるのは、土地や建物、預貯金、有価証券といったプラスの財産だけではありません。借入金やローン、未払いの税金など、マイナスの財産もすべて洗い出す必要があります。
具体的な調査方法として、以下の点が挙げられます。
- 不動産: 市区町村役場で「固定資産税評価証明書」や「名寄帳(なよせちょう)」を取得し、所有している不動産を確認します。
- 預貯金: 心当たりのある金融機関に対して「残高証明書」の発行を依頼し、死亡日時点の残高を確認することが可能です。
- 有価証券など: 株式や投資信託などの有価証券、生命保険、ゴルフ会員権なども見落とさないよう、手がかりとなる書類(通帳や手紙など)がないか丁寧に確認しましょう。
これらの調査で判明したすべての財産は、「遺産目録」として一覧にまとめます。この遺産目録は、相続人全員での遺産分割協議を進める際や、相続税の申告を行う際に必要不可欠な資料となるため、正確に作成することが重要です。
ステップ4:相続人全員で遺産の分け方を話し合う(遺産分割協議)
遺言書がない場合、法定相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行うことになります。この協議は、相続人全員の参加と合意がなければ法的に成立せず、その後の相続手続きの基礎をなす非常に重要なプロセスです。土地の主な分割方法は、以下の四つが挙げられます。
| 分割方法 | 内容 |
| 現物分割 | 土地を物理的に複数に分け、各相続人が単独で取得する方法です。 |
| 代償分割 | 一人の相続人が土地を相続し、その代わりに他の相続人へ金銭などを支払う方法です。 |
| 換価分割 | 土地を売却し、得られた現金を相続人で分け合う方法です。 |
| 共有分割 | 複数の相続人が共同で土地を所有する方法です。将来的なトラブルを避けるためには、慎重な検討が求められます。 |
協議で合意した内容は、「遺産分割協議書」として書面にまとめます。この書類には、亡くなった方の最後の住所、死亡日、氏名、そして相続人全員が分割方法について合意した旨、具体的な分割財産などを明確に記載します。後の相続登記や預貯金の解約手続きで必要となるため、相続人全員が署名し、実印を押印すること、印鑑証明書の添付が必須となります。もし話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることで、法的な解決を図ることも可能です。
ステップ5:土地の名義を相続人に変更する(相続登記)
遺産分割協議が成立し、各相続人が取得する土地が確定したら、その内容に従って土地の所有者名義を相続人に変更する「相続登記」を行います。この手続きは、亡くなった方(被相続人)から相続人へ不動産の権利を移転させる手続きです。
相続登記は、2024年4月1日より義務化されました。これは、所有者不明土地問題の解消を目的としており、不動産の所有権を得た相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をする義務を負うことになりました。正当な理由なくこの義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ステップ6:相続税の申告と納付を行う
相続手続きの最終段階では、相続財産が一定額を超える場合に、相続税の申告と納付が必要です。この手続きには厳格な期限が定められています。
相続税の申告と納付は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
提出先を誤らないよう注意が必要です。ご自身の住所地ではなく、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する税務署へ申告書を提出します。もしこの期限内に申告や納付が完了しなかった場合、延滞税や加算税といったペナルティが課されるリスクがあります。追加で税金を支払う事態を避けるためにも、計画的に準備を進めることが重要です。
| 項目 | 詳細 |
| 申告・納付期限 | 被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内 |
| 申告書の提出先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する税務署 |
| 納付方法 | 原則として現金による一括納付 |


2024年4月から義務化!不動産の相続登記の具体的な進め方
相続した不動産の登記を3年以内に行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。このように、手続きを怠ると罰則の対象となるため、相続登記は非常に重要です。以下では、義務化された相続登記について、具体的な手続きの流れ、必要な書類、そしてかかる費用を詳しく解説していきます。
土地の名義変更手続きの3つのステップ
相続した土地の相続登記を自分で行う際には、主に以下の3つのステップで手続きを進めます。書類の準備から申請、そして完了まで、各段階で必要な作業を確認していきましょう。
まずは、相続登記に必要となる書類を漏れなく集めていきます。必要書類の種類は後述のとおりです。
必要書類が揃えば、法務局に相続登記の申請をします。相続登記の申請は、不動産が存在する住所地を管轄する法務局宛にする必要がありますので、事前に管轄の法務局を調査しておきましょう。
相続登記を終えると、法務局から登記完了証及び登記識別情報通知書が交付されるため、これらを受け取ることで相続登記の手続は完了します。
【一覧】相続登記に必要な書類と取得場所
相続登記(土地の名義変更)に必要な書類は、遺言書の有無や遺産分割協議の状況によって異なります。ご自身のケースに合わせて書類を準備することが大切です。ここでは、相続登記に必要な書類をまとめてご紹介します。
書類の取得には時間がかかる場合もあるため、早めに準備を進めることが、スムーズな手続きの鍵となります。
| 書類名 | 取得場所 | 備考 |
| 登記申請書 | 申請人が作成(法務局ホームページで雛形有) | |
| 被相続人の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 被相続人の出生から死亡まで、連続したすべての記録が必要です。 |
| 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 | 最後の住所地の市区町村役場、本籍地の市区町村役場 | 被相続人の最後の住所が記載されていることを確認します。 |
| 相続人の住民票 | 住所地の市区町村役場 | 不動産を相続する方の現在の住所が記載されている住民票です。 |
| 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の都(市)税事務所または市区町村役場 | 登記申請をする年度のものが求められます。 |
| 登記事項証明書 | 管轄の法務局(管轄外の法務局でも取得可能) | 不動産の最新情報を確認するために必要です。なお、インターネットの登記情報提供サービスでも内容を確認できます。 |
| 遺産分割協議書または遺言書 | 遺産分割協議書は相続人全員で作成 | 遺産分割協議書は相続人全員の署名と実印の押印が必要です。 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 住所地の市区町村役場 | 遺産分割協議書に押印された実印の証明として必要です。ただし、遺言書がある場合には印鑑証明書は不要です。 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | |
| 相続関係説明図 | 取得者が作成する | 戸籍謄本の原本を還付を求める場合には作成する必要 |
名義変更手続きにかかる費用の内訳
土地の名義変更(相続登記)には、主に以下の3種類の費用が発生します。
- 登録免許税(国に納める税金)
- 書類の取得費用(手続きに必要な各種証明書など)
- 専門家へ支払う報酬(司法書士などへの依頼費用)
これらの費用は、相続する不動産の価額や、専門家への依頼範囲によって変動します。
気になる相続税の基本|節税のポイントは?
親から不動産やその他の財産を受け継ぐ際、気になることの一つに「相続税」が挙げられます。
以下の項目では、相続税の課税対象となるかどうかの具体的な判断基準や、税負担を軽減するための特例・控除について詳しく解説します。
相続税の申告が必要になるのはどんな場合?基礎控除額の計算方法
相続税は、全てのケースに適用されるわけではありません。相続税の申告や納税が必要となるのは、相続財産の総額が「基礎控除額」を超える場合のみです。まずは、ご自身のケースで相続税の申告・納税が必要かどうかを判断するために、この基礎控除額がいくらになるのかを確認しましょう。
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算出されます。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
例えば、相続人が配偶者と子2人の合計3人である場合、基礎控除額は4,800万円となります。
| 法定相続人の数 | 計算式 | 基礎控除額 |
| 3人 | 3,000万円 + (600万円 × 3人) | 4,800万円 |
つまり、遺産の総額がこの4,800万円を超えなければ、相続税の申告や納税は原則として不要です。しかし、遺産総額が基礎控除額を上回る場合は、相続税の申告と納税が必要となるため、速やかに準備を進める必要があります。
相続税額を大きく左右する「土地の評価額」とは
相続税は、被相続人が残した財産の総額に対して課される税金ですが、その中でも土地の評価額は最終的な税額を大きく左右する重要な要素となります。土地は一般的に高額な財産となるケースが多いため、その評価方法によって相続税額が大きく変動する可能性があります。
土地の評価方法には、主に「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があります。これらの評価方法は、以下のように適用地域と計算方法が異なります。
| 評価方法 | 適用地域 | 計算方法の概要 |
| 路線価方式 | 市街地の宅地など | 1平方メートル当たりの路線価 × 土地の面積 |
| 倍率方式 | 路線価が定められていない地域 | 固定資産税評価額 × 国税局長が定める一定の倍率 |
市街地にある宅地は路線価方式で評価されます。一方、路線価が定められていない地域、例えば郊外や農村部の土地などでは、倍率方式が用いられます。この方式では、対象となる土地の固定資産税評価額に、国税局長が定める一定の倍率を掛けることで評価額が算出されます。
これらの路線価や評価倍率は、国税庁のウェブサイトで公開されている「路線価図・評価倍率表」で確認できます。また、個別の事情がある土地では、評価額が減額される特例が適用される場合があります。
知っておきたい相続税の負担を軽くする特例・控除
相続税には、様々な特例や控除制度が設けられています。これらの制度を適切に活用することで、相続税の負担を軽減させることができます。
中でも特に効果が大きいのが、「小規模宅地等の特例」です。この特例を適用すると、被相続人が居住用や事業用として使用していた土地の評価額を最大80%減額できます。
また、配偶者が相続する場合には、「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」という制度があります。これは、配偶者が実際に取得した遺産額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、相続税がかからない仕組みです。この特例の適用を受けるためにも、相続税の申告が必要となります。
相続税には、上記で紹介した特例以外にも、状況に応じて利用できる様々な控除制度が存在します。
家族でもめないために。土地相続でよくあるトラブルとその回避策
親の土地相続は、しばしば家族間のトラブルに発展することがあります。これは、土地が預貯金のように明確に分割しにくい性質を持つためです。以下では、土地にまつわる相続問題を未然に防ぐための回避策や、相続人同士が円満に話し合いを進めるための具体的なコツを解説いたします。
土地の相続で起こりがちな家族間の対立
親の土地相続は、家族関係に大きな影響を与えがちな複雑な問題をはらんでいます。特に金銭では割り切れない複雑な感情が絡むことが多く、以下のようなトラブルに発展するケースが少なくありません。
- 親の介護に関係する寄与分の主張
- 土地の評価額や分割方法に関する認識の相違
- 価値の高い不動産の取得を巡る争い
- 同居相続人の居住継続と費用負担の問題
親の介護を献身的に行ってきた相続人が「寄与分」を主張し、法定相続分以上の権利を求めることで、他の兄弟と対立する場合があります。
次に、相続人の間で土地の評価額に対する認識が異なり、公平な分割が難しくなることもあります。土地を「売却して現金で分けたい」と考える相続人と、「先祖代々の土地としてそのまま所有し続けたい」と考える相続人の間で意見が割れるケースも頻繁に見られます。
さらに、複数の土地がある場合、都心部のような価値の高い不動産の取得を巡って兄弟間で争いが生じることもあります。
このような状況は、遺産分割協議を長期化させ、家族間の関係を悪化させる原因となります。
感情的な対立を避けるための話し合いのコツ
親の土地相続において感情的な対立を避けるためには、事前の準備と、相続人全員が冷静に話し合うための工夫が不可欠です。具体的な準備としては、まず相続人全員が故人の財産に関する正確な情報を共有することが極めて重要です。これらの準備により、相続人間の情報格差による不信感を取り除き、公平な話し合いの土台を築けます。
話し合いの場では、相手の意見を頭ごなしに否定せず、まずは最後まで耳を傾ける「傾聴」の姿勢を心がけることが大切です。これにより、相続人間の円滑なコミュニケーションを促します。互いの立場や感情を尊重し、理解し合う努力が求められます。
共有名義で相続するメリットと将来的なリスク
相続した土地を複数の相続人で「共有名義」とすることは、一時的な解決策として選ばれることがあります。短期的なメリットとして、法定相続分通りに分割するため、相続人の方々の公平感が保たれやすく、遺産分割協議を比較的円滑に進められる点が挙げられます。しかし、この共有名義には、将来的なトラブルの火種となりかねない多くのリスクが潜んでいます。例えば、土地の売却や活用(家を建てる、賃貸に出すなど)を行う際に、共有者全員の同意が必要となります。たった一人でも反対する共有者がいれば、これらの行為は実現できず、大切な財産が「塩漬け不動産」となってしまう危険性があります。
さらに、共有名義の不動産は、世代を重ねるごとに権利関係が複雑化する傾向にあります。共有者が亡くなると、その持分はさらにその子や孫へと相続されるため、共有者の数は「ネズミ算式」に増えていきます。数十年後には、面識のない遠い親戚と土地を共有することになり、合意形成が極めて困難になるケースも少なくありません。
このような将来的なリスクを避けるためにも、共有名義はあくまで一時的な解決策に過ぎないことを認識し、できる限り「代償分割」や「換価分割」を検討することが重要です。
親の土地相続に関するよくある質問
以下では、多くの方が抱く質問をQ&A形式でご紹介します。それぞれの質問に対する回答を読むことで、ご自身の状況に合った具体的な解決策を見つけ、今後の対応を考える上での参考となると思います。
相続したくない土地がある場合はどうすればいい?
相続したくない土地がある場合、主に「相続放棄」「相続土地国庫帰属制度の利用」「相続後の売却・寄付」という3つの選択肢が考えられます。どの選択肢もそれぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身の状況を考慮し、慎重に検討することが重要です。
まず「相続放棄」は、亡くなった方が残した土地や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて、全ての遺産を一切相続しない方法です。この手続きは、ご自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で行う必要があります。この期間を過ぎると、原則として相続放棄は認められなくなるため、注意が必要です。
次に、2023年4月27日から施行された「相続土地国庫帰属制度」は、不要な土地を国に引き取ってもらう新たな制度です。ただし、この制度を利用するには、建物がない更地であることや、担保権などが設定されていないことなど、満たすべき要件が多岐にわたります。また、法務局での審査手数料や、10年分の土地管理費用に相当する負担金が必要となる点も考慮に入れるべきでしょう。
さらに、一度土地を相続した後に、第三者への売却や自治体への寄付を検討する方法もあります。しかし、買い手が見つかりにくい地方の土地や、自治体側が寄付を受け入れないケースも少なくありません。
| 選択肢 | 概要 | 主な条件・注意点 |
| 相続放棄 | 全ての財産(プラス・マイナス)を相続しない。 | 相続人であることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てが必要。 |
| 相続土地国庫帰属制度 | 不要な土地を国に引き取ってもらう。 | 建物がない更地であること、担保権がないことなど、厳しい要件がある。審査手数料と10年分の管理費用相当額の負担金が必要。 |
| 相続後の売却・寄付 | 相続した土地を第三者へ売却するか、自治体へ寄付する。 | 買い手が見つかりにくい場合や、自治体が寄付を受け入れない場合がある。 |
相続手続きは自分でできますか?
親の土地相続を含む一連の相続手続きは、ご自身で行うことが可能です。実際に、相続人調査や相続財産調査、遺産分割協議から遺産分割協議書の作成、そして不動産の名義変更(相続登記)に至るまで、全ての手続きをご自身で進める方もいらっしゃいます。しかし、手続きには多大な時間と労力、そして専門的な知識が求められる場面があることを理解しておく必要があるでしょう。
ご自身で手続きを進めやすいのは、相続人が配偶者と子供のみなど少数で、相続財産が預貯金と自宅のみといったシンプルなケースです。また、相続人同士の関係が良好で、協力体制が整っている場合もスムーズに進めやすい傾向にあります。
一方で、専門家に依頼した方が良いケースも存在します。以下のような状況では、専門家による客観的なサポートが不可欠です。
- 相続人の数が多い、あるいは行方不明者がいる
- 不動産が複数ある、非上場株式が含まれるなど財産の種類が複雑である
- 相続人同士で遺産の分け方について意見が対立している
ご自身で手続きを行う最大のメリットは、費用の節約です。しかし、戸籍謄本の収集や書類作成の複雑さによるミスのリスク、膨大な時間的・精神的な負担はデメリットと言えるでしょう。
| 項目 | ご自身で行う場合 | 専門家に依頼する場合 |
| メリット | 費用を節約できる(最低3,000円程度) | 正確かつ迅速な手続きが期待できる |
| デメリット | 戸籍謄本の収集や書類作成の複雑さ、ミスのリスク、時間的・精神的負担 | 費用がかかる(10万円以上が目安) |
親の土地相続の問題は難波みなみ法律事務所へ

親の土地相続における一連の手続きについて、全体像から具体的な進め方、税金の基本、そして家族間のトラブル回避策までを幅広く解説しました。
相続は一生のうちに何度も経験するものではなく、複雑な手続きや専門用語の多さに不安を感じる方も少なくありません。特に、家族間で意見が対立しやすい遺産分割協議では、感情的なもつれから関係性が悪化してしまうケースも存在します。しかし、一人で抱え込む必要はありません。
相続の専門家である弁護士の知見を借りることで、手続きの負担を軽減し、正確かつスムーズに相続を完了させることが可能です。
当事務所では初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。お気軽にご相談ください。
対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。