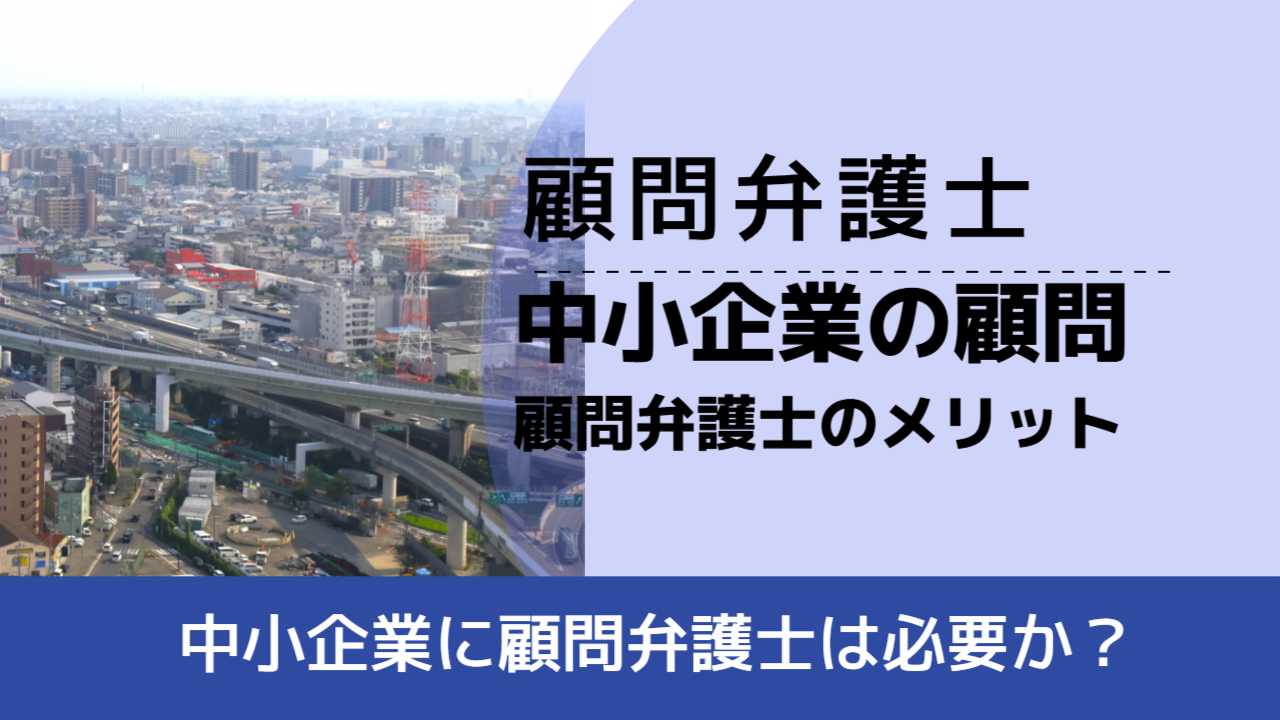中小企業の経営者にとって、法務リスクへの対策は重要な課題です。事業を継続していく上で、契約書の作成・確認、従業員との労務問題、取引先との紛争など、様々な法律問題に直面する可能性があります。
いざという時に慌てないためにも、顧問弁護士の存在は心強い味方となるでしょう。もっとも、「顧問料はどれくらいかかるのか」「本当に必要なのか」と疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
この記事では、顧問弁護士を中小企業がつけるメリットや費用相場、そして顧問弁護士の選び方について詳しく解説していきます。
なぜ今、中小企業にこそ顧問弁護士が必要なのか?
「顧問弁護士は大企業だけのもので、自社は法的なトラブルとは無縁だ」と考える中小企業の経営者は少なくありません。しかし、現代のビジネス環境は急速に変化しており、中小企業を取り巻く法的リスクは増大しています。
以下では、顧問弁護士が具体的にどのような役割を果たし、なぜトラブルが起きてからでは遅いのかを詳しく解説します。
経営者にのしかかる法的リスクの増大
近年、企業が遵守すべき法規制は、複雑化・厳格化の一途を辿っています。特に、以下の法改正がその代表的な例として挙げられます。
- 2020年4月1日から中小企業にも時間外労働の上限規制が適用された「働き方改革関連法」
- 2022年4月に中小企業にも義務化された「パワハラ防止法」
また、民法改正に伴って、残業代の消滅時効は2年から3年に伸長され、いずれは5年にまで伸長されることになっています。残業代は本来支払うべき賃金ではありますが、この点についても中小企業の負担を増加させる法改正の一つといえます。
これらの法改正は企業の労務管理に大きな影響を与え、対応が不十分な場合には法的トラブルに発展しかねません。
さらに、取引先との契約トラブルや顧客からのクレームに加え、SNSの普及によって従業員の不適切な投稿が企業の信用を著しく損なう「レピュテーションリスク」といった新たな課題も浮上しています。
これら多岐にわたる法的リスクは、専門の法務部門を持たない多くの中小企業において、経営者が直接対応せざるを得ない状況を生み出しています。
トラブル発生後では手遅れになるケースも
企業経営において、法的トラブルはいつ発生するか予測できません。いざ問題が起きた際、その初動対応を誤ってしまうと、後々取り返しのつかない致命的な結果を招くことがあります。例えば、取引先との紛争で不利な内容の念書を作成してしまったり、従業員に対する不適切な解雇通知を出してしまったりするケースです。不適切な内容の文書は後に高額な賠償責任や裁判での不利につながる可能性を秘めています。また、不当な解雇と判断されれば、パックペイ、解決金などの経済的な負担に加えて、社内外に大きな悪影響をもたらします。
問題が深刻化し、複雑に絡み合ってから慌てて弁護士を探し始めても、状況を正確に把握し、最適な解決策を迅速に提示できる弁護士をすぐに見つけるのは容易ではありません。対応が遅れることで、訴訟で不利になったり、長年の取引先からの信用を失ったり、最悪の場合、資金繰りが悪化して事業の存続自体が危ぶまれる回復不可能な損害につながるリスクが高まります。
このような事態を避けるためにも、平時から専門家である顧問弁護士と関係を築いておくことの重要性をご理解いただけるかと思います。

顧問弁護士を導入する5つのメリット|事業を守る「予防法務」とは
顧問弁護士は、企業の日常的な経営状況を継続的に把握しているため、潜在的なリスクを早期に発見し、効果的な予防策を講じることが可能な、まさに事業を守るパートナーといえます。
以下では、顧問弁護士を導入することで得られる「予防法務」の具体的なメリットを、以下の5つの観点から詳しく解説します。
- 法的トラブルの未然防止
- 取引における契約書対応
- 複雑化する労務問題への適切な対処
- 経営判断を下す際の法的な相談役としての活用
- 企業のコンプライアンス体制と社会的信用の強化
法的トラブルを未然に防ぎ、訴訟リスクを大幅に軽減
企業経営における法的リスク対策は、病気になってから治療するのではなく、日頃から健康診断を受ける「予防法務」の考え方が極めて重要です。顧問弁護士は、企業の事業内容や経営方針を理解し、日常業務に潜む潜在的な法的リスクを事前に洗い出すことで、トラブル発生を未然に防ぎます。例えば、契約書の細かな不備や、気づかないうちに生じている労務管理上の問題点などを早期に発見し、修正することが可能です。
万が一、問題が訴訟に発展した場合、多大な弁護士費用や解決までの時間、そして企業の信用低下といった大きなコストが発生します。顧問弁護士との継続的な契約は、こうした大きな損害を未然に防ぐものです。いつでも気軽に相談できる体制があることで、疑問点が生じた際に速やかに弁護士に確認でき、問題が小さいうちに解決を図れます。これにより、紛争が深刻化するのを防ぎ、結果として経営者は本業に安心して集中できるのです。
取引で不利にならないための契約書チェック・作成
日々の事業活動において、契約書は極めて重要な意味を持ちます。特に、テンプレートの利用や取引先から提示された契約書には、自社にとって不利な条項が潜んでいるケースが少なくありません。例えば、想定を超える過大な損害賠償の予定や、相手方だけが一方的に契約を解除できる条項、あるいは曖昧な秘密保持条項などが挙げられます。これらの不利な条項を見過ごしてしまうと、万が一トラブルが発生した際に、想定外の賠償責任を負うなど、企業に甚大な損害をもたらすリスクがあります。
顧問弁護士は、企業の事業内容や取引の実態を理解した上で、提示された契約書を法的な観点から細部まで精査する「リーガルチェック」を行います。これにより、潜在的なリスクや自社に不利な条項を特定し、修正案の提示や必要な条項の追加を行うことで、リスクを効果的にヘッジします。
これらによって、将来の法的トラブルを未然に防ぎ、企業の安定した事業運営に大きく貢献するでしょう。
労務問題への迅速かつ適切な対応
中小企業にとって、未払い残業代、問題社員への対応、解雇問題、ハラスメントといった労務問題は、企業経営を揺るがしかねない重大なリスクとなります。これらの問題に、経営者が主観的な判断や誤った知識で対応を進めてしまうと、事態がさらに悪化し、訴訟に発展するリスクが高まります。例えば、不適切な解雇が不当解雇と判断され、後から多額の賃金支払いを命じられるケースや、未払い残業代を巡り多額の支払いが認定されるケースは決して珍しくありません。
顧問弁護士は、このような労務問題が発生した際、労働法規に基づいた迅速かつ適切な法的アドバイスをします。これにより、問題の初期段階で的確な対応が可能となり、不要な紛争の拡大を防ぐことができます。トラブルが訴訟に発展する前に、弁護士が代理人として従業員との交渉にあたることで、より穏便な解決を図りやすくなります。
経営判断に迷ったときの法的な相談役
新規事業の立ち上げ、あるいは業務提携といった重要な経営判断を下す際には、常に法的なリスクが伴います。適切なリスク評価を怠った結果、例えば新規事業への投資が大きな損失につながるケースも存在します。専門知識がない状態でこれらのリスクを正確に評価し、適切な手続きを進めることは容易ではありません。顧問弁護士は、このような場面において、経営者が抱える法的懸念を解消する羅針盤となる存在です。
企業のコンプライアンス体制と社会的信用の強化
顧問弁護士の大きな役割の一つとして、実効的なコンプライアンス体制の構築が挙げられます。弁護士は、以下の活動を通じて、企業のガバナンス体制強化を支援し、法的リスクを未然に防ぐ基盤を構築します。
- 就業規則、ハラスメント規程、個人情報保護規程といった社内規程の整備・運用指導
- 従業員向けのコンプライアンス研修や講演の実施
従業員向けの研修を通じて、内部からのリスク発生を予防し、健全な企業文化を醸成することも可能です。
顧問弁護士がいるという事実は、取引先や金融機関、顧客に対し「コンプライアンス体制が整った信頼できる会社」という印象を与え、社会的信用の獲得につながります。不祥事を未然に防ぐことは、企業のブランドイメージや評判が損なわれる「レピュテーションリスク」を回避し、長期的な成長を支える重要な要素となります。


【事例で比較】顧問弁護士が解決する中小企業の法的トラブル
顧問弁護士の導入を検討する上で、「実際にどのような場面で役立つのか」という具体的なイメージを持つことは重要です。そこで以下では、中小企業が直面しやすい法的トラブルに焦点を当て、顧問弁護士が介入した場合とそうでない場合とで、どのような結果の違いが生まれるのかを具体的な事例を通して解説します。
労務問題|問題社員への適切な対応で訴訟発展を阻止
コンビニを運営する中小企業で、店長や他のアルバイト社員に対して非協調的な態度を繰り返したり、遅刻を繰り返すといった「問題社員」を抱えていました。
経営者は感情的になって、問題社員の即座の解雇を検討していました。しかし、不適切な解雇は不当解雇として多額の賠償請求につながるリスクがあります。たとえ、問題社員といえども、厳格な解雇の要件を満たさなければ不当解雇となり、今回の事案でも解雇の条件は満たしていない状況でした。
そこで、顧問先に対して、感情的な判断ではなく法的に正しい手順を踏むことの重要性をアドバイスしました。具体的には、社員への暴言や遅刻といった問題行為があれば、逐一、注意指導や戒告等の懲戒処分を行います。並行して、暴言等の問題行為を録音するなどして記録を保全するように徹底します。指導等を通じても改善されないために、退職勧奨を行います。
退職勧奨の進め方についても具体的な助言をすることで、訴訟リスクを最小限に抑えるサポートが行われました。例えば、退職勧奨時のロールプレイをしたり、勧奨時の注意事項をアドバイスします。
結果として、不当解雇による訴訟トラブルに発展することなく、円満な合意退職が実現しました。経営者は労務問題に煩わされることなく、本来の事業活動に集中できる環境を維持できました。この事例は、顧問弁護士が企業の労務リスクを回避し、事業の安定に貢献した具体例です。
債権回収|迅速な交渉で売掛金を回収し資金繰りを改善
中小企業が頭を悩ませる問題の一つに、取引先の支払い遅延や未払いがあります。
自社の担当者が何度も催促しても明確な返答がなく、時間だけが過ぎていくといった状況は少なくありません。現に、取引先の経営状況が悪化したため、顧問先の売掛金が滞納されている事案は多くあります。
このような事案では、弁護士名義で内容証明郵便を送付することで、心理的プレッシャーを与えることができ、支払いに応じるケースが多く見られます。それでも反応がない場合には、取引先の財産(預貯金、不動産、取引先の債権等)を調査した上で、仮差押えをすることで、確実に債権回収を図れるようにします。並行して、以下のような法的手続きを迅速に進めていきます。
- 通常訴訟の提起
- 支払督促の申立て
- 少額訴訟
これらの法的手続きを的確に進めることで確実に債権回収を図ります。
不動産経営|賃料不払いや迷惑行為に対応
不動産経営において、賃料不払いや迷惑行為といった入居者とのトラブルは日常的に生じるといっても言い過ぎではありません。顧問弁護士は、このような問題に対し、法的な側面から迅速かつ的確に対応し、オーナーの負担を軽減します。
例えば、家賃を滞納している入居者に対しては、顧問弁護士が内容証明郵便を送付し、支払いを督促します。内容証明郵便を送付することで、相手方への心理的圧迫効果も期待でき、問題の早期解決を促します。督促に応じない場合は、以下の法的手続きを迅速に進めます。
- 交渉
- 契約解除
- 明け渡し請求訴訟
- 強制執行
強制執行には、予納金や執行補助者費用などの実費が発生することもありますが、弁護士に依頼することで煩雑な手続きから解放されます。
また、騒音やゴミ出しルール違反といった迷惑行為に対しても、顧問弁護士が法的な根拠に基づいた警告文書を作成・送付します。口頭注意で解決しない場合は、契約の解除も含めた法的手続きを顧問弁護士に一任することが可能です。
さらに、賃貸借契約書の作成やレビューを依頼することは、「予防法務」の観点から将来のトラブルを未然に防ぐ上で非常に重要です。契約書に禁止事項、解除条件等に関する条項を盛り込むことで、いざという時の対応がスムーズになります。顧問弁護士がいれば、問題が深刻化する前の初期段階から対応できるため、不動産オーナーの時間的・精神的な負担を大幅に軽減することに繋がるでしょう。
気になる顧問弁護士の費用相場は?料金プランの目安
顧問弁護士の導入を検討する際、多くの方が不安に感じる点として「費用は高額ではないか」「実際の相場が分からない」といった点が挙げられるのではないでしょうか。
以下では中小企業向けの顧問弁護士費用について、具体的な相場や料金プランの目安を詳しく解説します。
顧問料の一般的な月額相場
中小企業における顧問弁護士の月額顧問料は、一般的に3万円から10万円程度が相場です。中でも、月額5万円前後のプランが最も一般的だと考えられています。顧問料に幅があるのは、以下の様々な要因によって変動するためです。
- 企業の従業員数や事業規模
- 予測される相談の頻度
- 依頼する業務の複雑さ
提示した相場は一般的な目安であり、具体的な料金は法律事務所によって異なります。そのため、実際に顧問弁護士の導入を検討する際は、自社のニーズに合った費用対効果の高いプランを比較検討することが重要です。
料金プランで受けられるサービス範囲の違い
顧問弁護士の料金プランは、提供されるサービス内容によって大きく異なります。主に月間の相談時間、契約書レビューや作成の通数、内容証明郵便の送付の数、そして対応可能な業務範囲によって変動するのが一般的です。
また、訴訟、債権回収といった顧問契約の範囲外となる個別案件が発生した場合、顧問契約を結んでいることで、通常の弁護士費用(着手金や報酬金)が割引されることがあります。この割引率は顧問料プランによって異なるため、契約前に確認することをおすすめします。
トラブル発生時のスポット依頼とのコスト比較
法的な問題が発生した際、弁護士への依頼方法には「顧問契約」と「スポット依頼」の二通りがあります。スポット依頼は、トラブルが発生した後にその都度弁護士を探し、依頼する方法であり、案件ごとに着手金や成功報酬といった費用が発生します。特に緊急性の高い案件では、弁護士を探すための時間的コストも発生し、焦りから十分な比較検討ができないまま、高額な弁護士費用を支払うケースも少なくありません。
一方、顧問契約は月額固定の費用で日常的な法律相談が可能であり、万が一、訴訟などの個別案件が発生した際には、通常よりも割引料金で依頼できるのが一般的です。これにより、突発的な高額出費のリスクを平準化し、予算管理がしやすくなります。
これら弁護士費用にとどまらず、トラブル対応にかかる経営者や従業員の時間・労力といった「見えないコスト」も無視できません。また、顧問弁護士による予防法務は、これらのコストを大幅に削減することもでき、全体的なコストパフォーマンスに優れている点が顧問弁護士の大きなメリットです。

失敗しない!中小企業のための顧問弁護士選び5つのポイント
顧問弁護士は、単に法的なアドバイスを提供する外部の専門家としてだけでなく、貴社の事業成長を共に目指す重要なビジネスパートナーとしての役割も担います。
自社に最適な顧問弁護士を見つけるには、費用だけでなく、多角的な視点から慎重に検討することが不可欠です。以下では、以下の5つのポイントを参考に、本当に信頼できる顧問弁護士を選ぶための判断基準を提示します。
自社のビジネスや業界への理解度
顧問弁護士を選ぶ際、自社のビジネスモデルや業界への理解があるかどうかは重要です。法律論だけでなく、業界特有の商慣習や規制、競争環境を熟知している弁護士であれば、企業の実情に合った具体的なアドバイスが期待できます。
法律事務所のウェブサイトで、顧問先の業種実績や関連案件の解決事例を確認することは、その専門性を見極める上で有効な手段となります。
中小企業支援の実績
弁護士には、離婚や相続といった個人の法律問題を得意とする者もいれば、企業法務を専門とする者もいます。
貴社が顧問弁護士に求めるのは、日々の事業活動における法的課題の解決や予防ですので、企業法務に特化し、豊富な経験を持つ弁護士を選ぶことが重要です。
コミュニケーションの取りやすさとレスポンスの速さ
顧問弁護士を選ぶ上で、コミュニケーションの取りやすさとレスポンスの速さは、企業の経営判断やトラブル対応の成否を左右する重要な要素となります。緊急性の高い問題が発生した際、すぐに相談でき、迅速な対応を期待できる弁護士であることは、ビジネスを円滑に進める上で不可欠です。
また、弁護士が法律の専門用語を多用せず、経営者が理解しやすい平易な言葉で説明してくれるかどうかも、円滑な意思疎通の鍵を握ります。些細なことでも気軽に相談できる雰囲気や人柄であるかを見極めることは、長期的なパートナーシップを築く上で不可欠です。
料金体系の明確さと費用対効果
顧問弁護士を選ぶ上で、料金体系が明確であるかは非常に重要です。具体的には、以下の点を確認しましょう。
- 月額の顧問料に含まれるサービス範囲(例:月間の相談時間の上限、契約書レビューの通数など)が具体的に規定されているか。
- 顧問契約の範囲外となる個別案件(例:訴訟対応)について、別途費用が発生するのか、その金額や算出方法が事前に明示されているか。
顧問契約の料金プランを比較する際には、単に月額料金の安さだけで判断するのではなく、自社の相談頻度や事業フェーズに見合ったサービスが受けられるかという「費用対効果」の観点から検討することが肝要です。
契約後に「こんなはずではなかった」という事態を避けるには、見積書や契約書の内容に不明瞭な点があれば、契約前に納得いくまで質問し、全てをクリアにしておくことが肝心です。
経営者に寄り添い、共に成長できる相性
顧問弁護士は、単に法律的な問題に対処する専門家という側面だけでなく、貴社の経営戦略を共に考え、成長を支える重要なビジネスパートナーとしての役割も担います。そのため、単に法律論に終始するだけでなく、経営者のビジョンや日々の悩みに深く共感し、精神的な支えとなり得る人柄であるかどうかも重要です。
些細なことでも気軽に相談できる「話しやすさ」は、潜在的なトラブルの早期発見や迅速な解決に不可欠です。初回相談や面談の際には、コミュニケーションの相性を確認することが非常に大切です。具体的には、以下の点に注目しましょう。
- 高圧的な態度ではないか
- 話を真摯に聞いてくれるか
- 分かりやすい言葉で説明してくれるか
こうした確認を通じて、貴社の未来を共に考え、成長していける信頼関係を築くことができるでしょう。
中小企業の顧問は難波みなみ法律事務所へ
本記事では、中小企業を取り巻く法的リスクが増大する現代において、顧問弁護士がどれほど重要であるかを詳しく解説しました。
当事務所では、中小企業診断士の代表弁護士と元裁判官のベテラン弁護士が在籍しており、経験豊富な弁護士により、予防法務だけでなく経営的な側面から貴社を全面的にサポートすることができます。
また、月額9500円のスマートプランをご用意しており、費用負担を抑えながら顧問サービスを受けることができます。
当事務所では初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。お気軽にご相談ください。
対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。